ポールウォーカーにとっては嬉しい研究報告「5,001~7,500歩の歩行は、脳内のタウ蓄積を抑えることで、アルツハイマー病を予防する」と、マインドキャプションの最新研究報告、下畑先生の最新医学情報が、今月お届けする関連学術ニュースです。
1.2025年11月の活動状況
・杉浦 伸郎さんの投稿
 今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。
今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます
#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます
・中村 理さんの投稿
 佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。
佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。
・田村 芙美子さんの投稿
 前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。
前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動
【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動
・遠藤 恵子さんの投稿
 🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶
🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶
・スマイルチームさんの投稿
 20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106
20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106
・田村 芙美子さんの投稿
 今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。
今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。
・中村 理さんの投稿
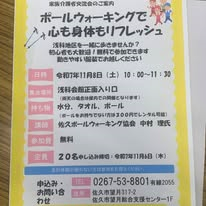 佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️
佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️
・校條 諭さんの投稿
 地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。
地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク
【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク
・田村 芙美子さんの投稿
 この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。
この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。
・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿
 2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走
2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね
それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね
・長谷川 弘道さんの投稿
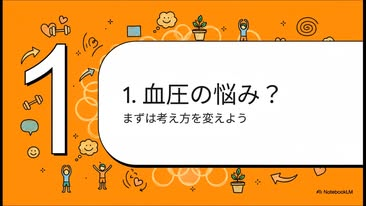 先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM
先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM
・柳澤 光宏さんの投稿
 2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。
2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。
・森川 まことさんの投稿
 本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました
本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました
・校條 諭さんの投稿
 朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。
朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
・柳澤 光宏さんの投稿
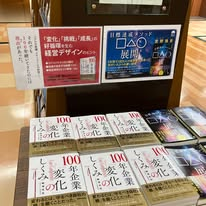 書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ
書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ
・株式会社シナノ(sinano)さんの投稿
 本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!
本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!
・田村 芙美子さんの投稿
 大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。
大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。
・校條諭さんの投稿
 鎌倉広町緑地でポール歩き
鎌倉広町緑地でポール歩き
田村芙美子さんが企画してくださった広町緑地ツアー、快晴に恵まれて充実したとっても楽しいウォーキングでした。
田村さんは、2年前くらいまでやっていた杉ポ=杉並ポール歩きの会の講師としてお世話になっていました。日本ポールウォーキング協会マスターコーチプロとして、湘南や都内で忙しい日々を送っておられます。
広町緑地は10年前(2015年)に開園した鎌倉の新名所です。地元以外ではまだあまり知られてないように思います。公園としては新しいですが、もともと48ヘクタールもある里山でした。そこに宅地開発の計画がもちあがったのですが、ねばりづよい反対運動により、市が買い取ることになり、公園として整備されました。
私は、およそ50年前に、この緑地のすぐ近くのアパートに住んでいたのですが、目の前にこんもりした山があるのは知っていたものの、中に入ったことはありませんでした。
田村さんのはからいで、今もあるアパートの前まで行ってみました。ここから鎌倉市内の梶原山にあった野村総研本社・鎌倉研究本部に通っていました。当初バイク(ダックスホンダ)で、のちにシビックで。
緑地内は、コースにもよりますが、楽なコースでも多少アップダウンがあります。そのおかげか、翌日の今日はいつもより軽快に歩けました。田村さんに心から感謝です。
・江原 健次さんの投稿
 【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。
【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。
・水間 孝之さんの投稿
 MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌
MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌
・田村 芙美子さんの投稿
 第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。
第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。
・佐藤珠美さんの投稿
 11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊
11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ
【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ
・スマイルチームさんの投稿
 20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘
20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘
2.PW関連学術ニュース
2-1)前臨床アルツハイマー病における修正可能な危険因子としての身体活動
岐阜大学の下畑先生、大坂大学の宮坂先生が、この論文を紹介されています。
・よく歩く人ほどタウの蓄積が抑えられ,認知機能が守られる―5,000歩から始めるアルツハイマー病予防
**以下は、岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月7日のFB投稿です**
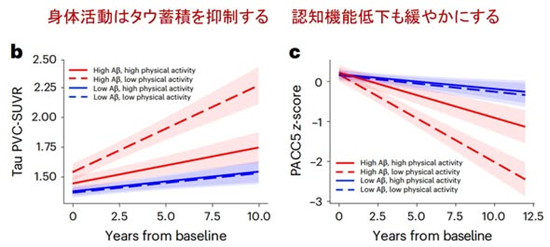
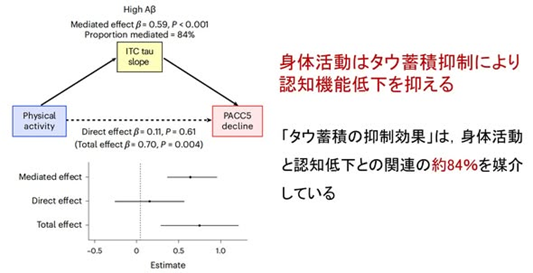 アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.
アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.
著者らはHarvard Aging Brain Studyに参加した296名の認知機能正常の高齢者を対象に,歩数計によって測定した1日の平均歩数と,アミロイドβおよびタウのPET画像を最大14年間(!)追跡しました.対象者の平均年齢は72歳で,追跡期間の中央値は約9年でした.
さて結果ですが,身体活動量が多い人ほど認知機能(PACC5)および日常生活機能(CDR-Sum of Boxes)の低下が遅く,特に脳内アミロイドβ高値群では,この効果がより顕著でした.具体的には,まず図1bですが,アミロイドβ高値群では,身体活動量が多いほど下側頭皮質におけるタウ蓄積の増加がより緩やかになるという交互作用効果が認められました(身体活動 × Aβ:β=−0.13,P<0.001).さらに,アミロイドβの有無に関わらず,身体活動そのものにもタウ蓄積を抑制する独立した効果がみられました(身体活動:β=−0.07,P=0.04).すなわち,「Aβ陽性であるほど運動が効きやすい」ことに加えて,「そもそも運動はタウ蓄積を抑える方向に働く」という2つの効果が存在することになります.
さらに図1cでは,アミロイドβ高値群(赤)で,身体活動が多いほど(赤実線),認知機能低下(PACC5スコア)の進行が緩やかになることが示されています(β=0.10,P<0.001).この効果はアミロイドβ低値群ではみられず,アミロイド病理が存在する段階において,身体活動が保護的に働くことが分かります.横軸をご覧いただくと,運動の効果は10年経っても認めますので非常に驚きます.
そしてもう一つ驚くのは,身体活動はアミロイドβの蓄積そのものには影響を与えず,タウ病理の進行を抑制するということです.これを明確に示しているのが媒介解析を示した図2です.身体活動量が多いほど下側頭皮質でのタウ蓄積が遅く,その結果として認知機能低下が緩やかになることが示されています.この「タウ蓄積の抑制効果」は,身体活動と認知低下との関連の約84%を媒介していました.つまり,「よく歩く人ほどタウの蓄積が抑えられ,結果として認知機能が守られる」ことが定量的に裏づけられたわけです.やはり認知機能低下に直接重要なのはタウなのだなあと思います.
さらに歩数との関係を調べると,1日5,000〜7,500歩の中等度の活動で効果が最大となり,それ以上歩いても効果は頭打ちになることが示されました.この「5,000〜7,500歩」という目標は,高齢者でも達成可能であり,アルツハイマー病予防における行動指針として実践的な意味を持つと考えられます.著者らは,この結果を踏まえ,前臨床期アルツハイマー病の進行を抑制する介入として「身体活動の増加」を提案しています.お散歩は,安上がりで,かつ強力な認知症予防と言えます.
Yau WYW, et al. Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease. Nature Medicine. 2025; https://doi.org/10.1038/s41591-025-03955-6.
**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年11月4日のFB投稿です**
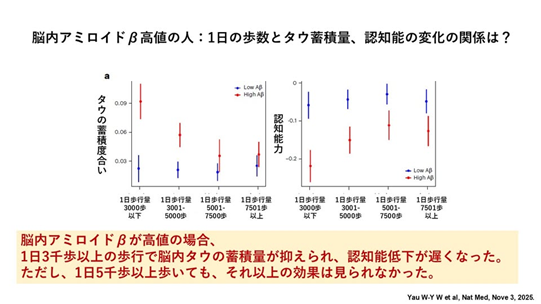 かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。
かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。
https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid0AvyhytkWARXJrxrEs4xC4E5FxtM3Q227Hjzx9V8wRD1DtwHTExTpF3KcCPjA1BgUl
https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid02jfp9LTRnHtYxekBXgYoopCyNZu5DkHak1SQGiGxqCP6iNwvSRRpaFwM9VFP2wFXql
またFB上で、アルツハイマー病のリスクを下げると思われる「脳洗い体操」の実際についてもお示ししています。
https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid0oF6VNLpBmVPfT2gfqdubXG1jMvQ3zsDo6hbK22dy9AzgavTVKrYLqStriKTHMUKFl
これまでの報告では、運動不足により脳内にアミロイドβが蓄積する傾向があり、これがアルツハイマー病のリスクを高める、とされてきました。
ところが、最新号のNature Medicineでは、アメリカの研究グループが、アミロイドβよりはタウというタンパク質の蓄積のほうが問題であり、1日3千歩以上の歩行によりタウの蓄積とそれに伴う認知機能低下をかなり防げる、という報告をしています(https://www.nature.com/articles/s41591-025-03955-6)。296人について最長14年間観察した結果です。脳内のアミロイドβやタウの量はPETで測定しています。
この研究では、歩数計で測定した歩数を用いてアミロイドβのベースラインが高かった人について調査をしていて、身体活動を積極的に行うと(=毎日一定歩数以上歩くと)認知機能の低下が遅くなることを示しています。ただし、注目すべきはアミロイドβの量ではなく、タウのほうだということです。すなわち、身体活動を増やすと、下側頭葉におけるタウの蓄積が遅くなり、これに伴い認知機能低下が遅くなることがわかりました。特に、タウ蓄積の遅延と認知機能低下の関連は、1日3,000~5,000歩の歩行ではっきりと見られ、その効果は中等度の身体活動レベル(1日5,001~7,500歩)でプラトーに達するとのことです。
この程度の運動量ならば、多くの高齢者ではなんとか可能ですね。まずはやってみましょう。
原論文
掲載誌:Nature Medicine 、Article Open access
公開日:Published: 03 November 2025
表題:Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease
(和訳:前臨床アルツハイマー病における修正可能な危険因子としての身体活動)
著者:Wai-Ying Wendy Yau, Dylan R. Kirn, Jennifer S. Rabin, Michael J. Properzi, Aaron P. Schultz, Zahra Shirzadi, Kailee Palmgren, Paola Matos, Courtney Maa, Jeremy J. Pruzin, Stephanie A. Schultz, Rachel F. Buckley, Dorene M. Rentz, Keith A. Johnson, Reisa A. Sperling & Jasmeer P. Chhatwal
要旨
身体活動不足はアルツハイマー病(AD)の修正可能な危険因子として認識されているが、ヒトにおけるAD病態の進行との関係は依然として不明であり、予防試験への有効な応用が限られている。認知機能に障害のない高齢者において、歩数計で測定した歩数を用いて、ベースラインのアミロイドが高かった人において、身体活動の増加と認知機能および機能低下の遅延との間に関連性があることを実証した。重要な点は、この有益な関連性はベースラインまたは縦断的なアミロイド負荷量の低さとは関連していなかったことである。むしろ、身体活動の増加はアミロイド関連の下側頭葉タウ蓄積の遅延と関連しており、これが認知機能低下の遅延との関連性を有意に媒介していた。用量反応解析によりさらに曲線関係が明らかになり、タウ蓄積の遅延と認知機能低下との関連性は中等度の身体活動レベル(1日5,001~7,500歩)でプラトーに達することが明らかになった。これは、高齢の運動不足者にとってより達成可能な目標となる可能性がある。総合的に、私たちの研究結果は、将来の予防試験において前臨床 AD の軌跡を修正するための介入として身体活動不足をターゲットにすることを支持するものであり、さらに、アミロイド値が高く座りがちな個人を優先的に登録することで、早期 AD におけるタウ蓄積と認知機能および機能低下に対する身体活動の保護効果を実証する可能性が最大化される可能性があることを示唆しています。
図 1: ベースラインの身体活動と縦断的 Aβ、タウ、認知機能との関連。
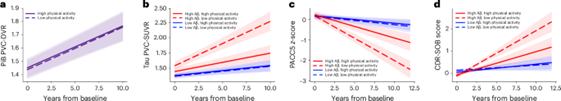 a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。
a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。
図 2: タウの蓄積は、前臨床 AD における身体活動と認知機能/機能低下との関連を媒介しました。
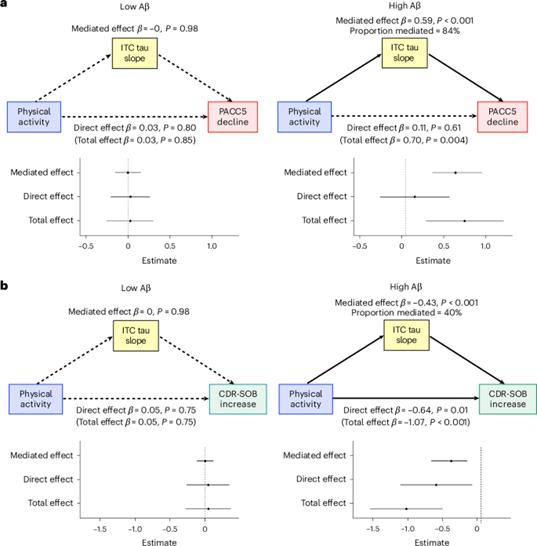 a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。
a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。
図3: 前臨床ADにおける身体活動レベルとタウおよび認知機能の変化。
 a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。
a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。
2-2)マインドキャプション:人間の脳活動から精神的内容の説明文を進化させる
次に紹介する論文の著者は、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の堀川友慈氏です。
掲載誌:Science Advances Vol 11, Issue 45
掲載日:5 Nov 2025
表題:Mind captioning: Evolving descriptive text of mental content from human brain activity
(和訳:マインドキャプション:人間の脳活動から精神的内容の説明文を進化させる)
著者:Tomoyasu Horikawa(堀川 友慈)
DOI: 10.1126/sciadv.adw1464
要旨
神経科学における中心的な課題は、脳活動をデコードし、複数の要素とそれらの相互作用からなる心的内容を明らかにすることです。人間の脳活動から言語関連情報をデコードする技術は進歩しているものの、構造化された視覚的意味論に関連する複雑な心的内容を包括的に記述することは依然として困難です。本研究では、深層言語モデルによって計算された意味特徴を用いて、脳表現を反映した記述テキストを生成する手法を提示します。動画によって誘発される脳活動を対応する字幕の意味特徴に変換する線形デコードモデルを構築し、単語の置換と補間によって候補記述の特徴を脳でデコードされた特徴と整合させることで、候補記述を最適化しました。このプロセスにより、標準的な言語ネットワークに依存せずに、視聴された内容を正確に捉えた、構造化された記述が得られました。この手法は、想起された内容を言語化するようにも一般化され、心的表現とテキスト間の解釈インターフェースとして機能し、同時に、失語症などの言語表現に困難を抱える人々にとって代替的なコミュニケーション経路となる可能性のある、非言語的思考に基づく脳-テキストコミュニケーションの可能性を実証しました。
図1マインドキャプション
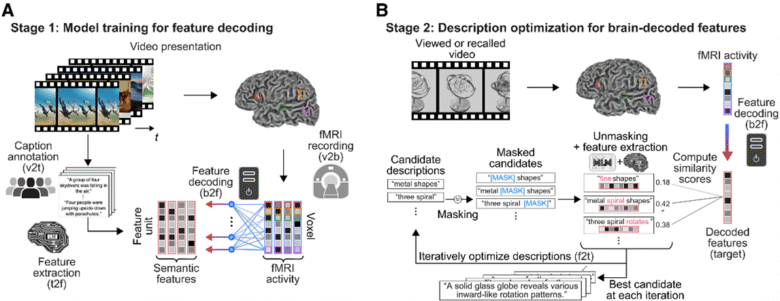 私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
表1情報モダリティとその変換の概要。
図 1では、各変換プロセスを示すために、変換 ID [例: v2t (ビデオからテキスト)、b2f (脳から特徴) など] が一貫して使用されています。

関連情報
① NATURE NEWSで、取り上げられています。
掲載日:05 November 2025
表題:‘Mind-captioning’ AI decodes brain activity to turn thoughts into text
A non-invasive imaging technique can translate scenes in your head into sentences. It could help to reveal how the brain interprets the world.
「マインドキャプション」AIが脳活動を解読し思考をテキストに変換
非侵襲的な画像化技術は、頭の中の光景を文章に変換することができます。脳がどのように世界を解釈するかを解明するのに役立つ可能性があります。
著者: Max Kozlov
 機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL
機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL
**以下、同記事の初めの部分訳**
脳活動の記録から人の心を読むというのは未来的に聞こえるかもしれませんが、現実に一歩近づきました。「マインドキャプション」と呼ばれる技術は、脳活動の読み取りから、人が心の中で見ているものや描いているものを、驚くほど正確に描写した文章を生成します。
本日Science Advances に掲載された論文で説明されているこの技術は、思考が言葉に表現される前に脳がどのように世界を表象するかについての手がかりも提供する。また、脳卒中などによる言語障害を持つ人々のコミュニケーション能力向上にも役立つ可能性がある。
このモデルは、人が何を見ているかを「非常に詳細に」予測できると、カリフォルニア大学バークレー校の計算神経科学者アレックス・ヒュース氏は言う。「これは難しい。これほど詳細に予測できるのは驚きだ」
② 著者である堀川友慈氏の研究紹介記事が、NTT技術ジャーナル2022年10月号の「明日のトップランナー」に掲載されています(https://journal.ntt.co.jp/article/19918)。
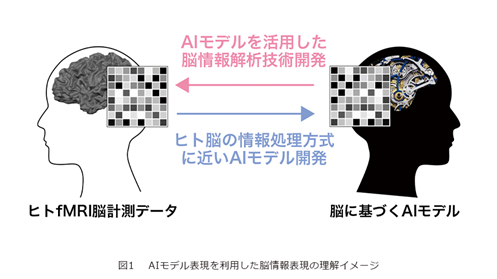
2-3)岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報
・岐阜大学脳内抄読会 第99回「歩行中のUターン速度はパーキンソン病発症の予測因子となる」
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月30日のFB投稿です**
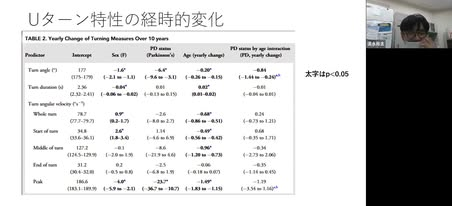 今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.
今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.
Elshehabi M, et al. Turning Slowly Predicts Future Diagnosis of Parkinson’s Disease: A Decade‐Long Longitudinal Analysis. Annals of Neurology. 2025;00:1–10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.78034
・評価しにくい「疲労」を3つの起源と5つの概念によって理解する
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月30日のFB投稿です**
 疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.
疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.
重要な図は,疲労を3つの起源と5つの概念によって体系化した“疲労の概念図”です.円の内側には,疲労の主な起源として以下の3つを挙げています.①神経原性(neurogenic):中枢・末梢神経の機能異常によるもので,中枢性ではMS,PD,AD,脳卒中後疲労などがあり,視床前頭回路や線条体ネットワーク異常が関与します.末梢性ではALSやCIDPなどが含まれます.②筋原性(myogenic):筋疾患や重症筋無力症などに伴うもの.③全身性(systemic):炎症性疾患(RA,Sjögren症候群など)や新型コロナ後遺症,筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)などが該当します.
円の中央から外側には,疲労をより精緻に理解するための五つの概念軸が配置されています.①時間的側面:その時々の変化か慢性的傾向かを区別する.②原因性:疾患の直接機序によるか,疼痛・抑うつ・薬物などの二次的要因によるか.③心理・行動的要素:性格傾向や動機づけ,行動パターンとの関連を考慮する.④領域:認知疲労か,筋活動に関わる運動疲労か.⑤客観性:主観的な「疲れやすさ」と客観的な持続力低下の差異を区別する.これら5つの軸が三つのクラスターを横断して交わり,複雑に絡み合う様子が図の中心にネットワークとして示されています.
このモデルが強調するのは,疲労が単一の原因から生じるのではなく,遺伝的素因,免疫・炎症,神経ネットワーク変化,行動パターンの相互作用によって形成されるという点です.著者らは,このような「多層的ネットワーク症候」として疲労を捉えることで,疾患を超えた理解と共通の評価基準が可能になると述べています.
疲労評価には多数の質問票が存在するものの,文化・言語差や対象疾患の違いにより結果の比較が難しいとされています.代表的尺度としてFatigue Severity Scale(FSS)やFatigue Scale for Motor and Cognitive Functions(FSMC)が挙げられ,MSやSLEなどで広く用いられています.
疲労の機序については,免疫・神経・代謝・行動の相互作用による多層的ネットワーク障害として説明されています.慢性炎症によりIL-1,IL-6,TNFなどのサイトカインが上昇します.この炎症が長期化すると,皮質―線条体―視床ループや報酬系の機能低下を介して中枢性疲労が形成されます.さらに,ミクログリア活性化,トリプトファン‐キヌレニン経路異常,ミトコンドリア機能障害が炎症と神経変性を結びつけ,休息で回復しない疲労を持続させます.これらの生物学的変化は,心理的・行動的要因と重なりあって疲労を悪化させるため,疲労は単なる「感覚」ではなく,全身と脳をつなぐ神経免疫代謝ネットワークの破綻として理解すべきとされています.
治療においては個別化アプローチの重要性が指摘されており,MSやPDでは運動療法や認知行動療法(CBT)が有効ですが,新型コロナ後遺症やME/CFSでは過度な運動により症状が悪化するため慎重な調整(エネルギーマネジメント)が必要とされています.また,非侵襲的脳刺激(tDCSやrTMS)が一部の神経疾患で有望な結果を示しており,今後の研究が期待されます.さらに,マインドフルネス瞑想など,自己調整能力を高める介入の重要性も指摘されており,疲労に対する多面的アプローチの必要性が強調されています.
Penner I-K, et al. Fatigue: a common but poorly understood symptom in neurological and non-neurological diseases. Nature Reviews Neurology. 2025; https://www.nature.com/articles/s41582-025-01153-z
・「ゼロカロリー」の代償?人工甘味料摂取と認知機能低下の関連
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月1日のFB投稿です**
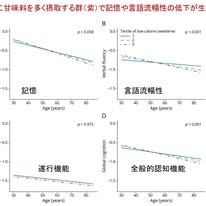 人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.
人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.
研究対象は35歳以上の公務員12,772名です(平均年齢51.9歳,女性55%).2008年から2019年までの約8年間にわたり3回の評価が行われ,食事内容は114項目の質問票で調査されました.解析ではアスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,エリスリトール,ソルビトール,キシリトール,タガトースの7種類の低・無カロリー甘味料の摂取量を算出し,摂取量に基づいて三分位に分類しました.認知機能は記憶,言語流暢性,遂行機能など6つのテストのzスコアで評価されました.
その結果,人工甘味料を多く摂取する群で認知機能の低下が速く進むことが示されました.図に示されたように,摂取量が最も多い群(紫の点線)では,最も少ない群(青緑の実線)と比べて,記憶の低下率が32%高く,言語流暢性では173%,全般的な認知機能では62%高い低下率を示しました.これは通常の加齢による変化に比べて1.3〜1.6年分の「余分な脳の老化」に相当します.一方,遂行機能を反映するTrail-Making Testでは有意な差は認めませんでした.個々の甘味料別では,アスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,エリスリトール,ソルビトール,キシリトールが記憶と言語流暢性の低下と関連し,天然由来のタガトースだけが影響を示しませんでした.
年齢層別の解析では,60歳未満の参加者で有意な関連がみられ,中年期からの人工甘味料摂取が特にリスクとなることが明らかになりました.また糖尿病の有無による検討では,糖尿病をもつ参加者でアスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,キシリトールの摂取と記憶・全体認知の低下が強く関連しました.非糖尿病者では,エリスリトールやソルビトールの摂取が有意に関連していました.
著者らは,これらの結果を説明する可能性として,人工甘味料の代謝産物による神経毒性や神経炎症,腸内細菌叢の変化による血液脳関門の障害,さらにシナプス機能障害などを挙げています.動物実験ではアスパルテーム摂取が海馬での細胞死や神経炎症を引き起こすことが報告されているそうで,人でも同様のことが起こり得る可能性もあります.健康のために砂糖を避けて人工甘味料を多用する行動が,かえって脳の老化を早めてしまう可能性があるようです.ただし本研究は観察研究であり,人工甘味料摂取と認知低下の間に因果関係を直接示すものではありません.食事内容は自己申告に基づくため誤差があり,摂取量の経時的変化も反映されていません.また,脱落による選択バイアスや,糖尿病や生活習慣などの残余交絡の影響も否定できません.したがって,結果は関連を示唆するものですが,慎重な解釈が必要です.
Gonçalves NG, et al. Association Between Consumption of Low- and No-Calorie Artificial Sweeteners and Cognitive Decline: An 8-Year Prospective Study.Neurology. 2025;105:e214023.doi.org/10.1212/WNL.0000000000214023
・脳神経内科医が直面する臨床倫理の最前線―終末期・遺伝・治療選択をめぐって―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月9日のFB投稿です**
 昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.
昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.
まず杉浦真先生(安城更生病院)は「神経疾患における治療の差し控え・中止」について議論されました.神経疾患は経過の予測が難しく,かつコミュニケーション障害・認知機能障害により「治療の自己決定」においてしばしば難しい判断を迫られることを示した上で,本人の自己決定をただ尊重して即時に実行するのではなく,一旦立ち止まり,その希望の背景に隠れている「この苦痛から解放されたい」「助けてほしい」というサインを見逃さず,全人的苦痛への緩和ケアを行うことの重要性を指摘されました.そして治療の効果と患者の利益は必ずしもイコールではないことを意識しつつ協働意思決定を行う大切さを強調されました.
笹月桃子先生(早稲田大学)は,遺伝子治療・新型出生前診断・着床前胚遺伝子検査・臓器提供の議論が進むなか,「子どもは自ら選択することができない存在である」という現実に立ち返る必要があることを強調されました.いのちをめぐる判断が,新たな優生的な価値観へと傾かないよう,中立性と対話を持続させる姿勢の大切さを語られました.また日本小児科学会の先進的な取り組みについてもご紹介くださり,大変勉強になりました.
徳永純先生(狭山神経内科病院)は,アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体療法において,ARIAリスクとAPOE遺伝子型の関係,遺伝子検査が保険適用外である現状,さらに治療の費用対効果と患者個人の利益をどう調和させるかという課題について議論されました.平均値に基づく議論では,重篤な副作用の重みが埋もれてしまうことがあるため,患者の状況を悪化させない選択を基準とする「パレート効率性」の視点が重要であることを学びました.また患者の個別性を尊重する医療,最も不利な立場に立たされている患者の利得を最大化する医療についてご提示くださいました.
続いて,山田晋一郎先生(名古屋大学)は,着床前胚遺伝子検査(PGT-M)の適応が拡大しつつある現状において,家系内での情報共有の難しさ,保因者診断がもたらす心理的負担,そして「重篤性」をどのように定義するのかという根源的な問題をご提示くださいました.疾患担当医・生殖医療専門医・臨床遺伝専門医が連携し,中立性を保ちつつ対話を継続する姿勢を学びました.
最後に,私は機能性神経障害(FND)における臨床倫理的問題について議論しました.FNDは陽性徴候に基づいて診断可能であり,かつ認知行動療法やリハビリテーションによって改善が期待できる「診断可能かつ治療可能な疾患」として再定義されつつあります.しかし現場では依然として,人格を否定されるようなスティグマ,不必要な検査や処置が行われてしまう医原性の害,症状を「心の問題」と単純化することで患者の体験が軽視される危険,そして歴史的に形成されたジェンダー偏見が根強く残ります.これらに向き合うためには,自律尊重,善行,無危害,正義という臨床倫理の四原則にもとづき,患者さんと理解を共有しながら,診断・説明・治療を丁寧に進める姿勢が欠かせないことを述べました.この内容は『臨床神経学』1月号に掲載予定です.またスライドは以下からご覧いただけます.
https://www.docswell.com/…/800…/KG2PW4-2025-11-09-070636
今回のシンポジウムを通して,神経疾患の医療に関する臨床倫理的問題を多くの医療者が学ぶ場や議論する場が必要であると強く思いました.また医療者が社会的な問題に目を背けず,議論する重要性を改めて感じました. 座長をご担当くださり,非常に示唆に富むコメントをくださった荻野美恵子先生,そしてご参加いただいた皆様に,心より御礼申し上げます.
・病原性が低いと思われていたヒトペギウイルスは自己免疫性脳炎やパーキンソン病と関連する!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月11日のFB投稿です**
 ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.
ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.
まず,ジョンズホプキンス大学のTagaらは,既往歴のない21歳男性が頭痛と発熱に続いて認知・行動異常を呈し,最終的にオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群を呈しました.脳脊髄液検査,自己免疫性脳炎の各種抗体,腫瘍検索では原因を特定できませんでした.このためmNGSを行ったところ,HPgV配列が検出され,続いて標的RT-PCRでもその存在を確認しました.頭部MRIでは橋,延髄,中脳および脊髄にT2高信号病変が認められ,いわゆる脳幹・脊髄を中心とする脳脊髄炎の像を呈しました(図1).延髄(A),橋および歯状核(B),中脳(C)の高信号域, DWI(D)およびADC(E)での脳梁における細胞障害性病変を示唆する信号異常,頸髄にわたる長大な病変(F, G),頭部から馬尾まで及ぶ広範な髄膜増強効果(H-J)を認めます.治療として免疫グロブリン大量静注療法を行ったところ,オプソクローヌス・ミオクローヌスは速やかに消失し,1年後には後遺症なく回復しました.著者らは,HPgVが直接神経細胞を障害したというよりも,免疫反応を介して中枢神経障害を引き起こした可能性を考えています.
一方,ノースウェスタン大学のHansonらは,HPgVがパーキンソン病(PD)の病態に関与する可能性を議論しています.10例のPD患者脳組織のうち5例からHPgV遺伝子が検出され,一方,対照14例では全例陰性でした.興味深いことに,免疫染色ではオリゴデンドロサイト内にHPgV由来タンパクが認められ,中枢神経内感染が示唆されました(図2).さらにHPgV陽性のPD患者では,神経原線維変化のBraakステージがより進行しており,グルタミン酸放出に関与するComplexin-2が増加していました.
また,血液レベルでは,HPgV陽性PD患者でIGF-1の上昇とpS65-Ubの低下が認められました.IGF-1の上昇は,進行する神経変性に対する代償的な神経保護反応と考えられます.一方,pS65-Ubの低下は,障害を受けたミトコンドリアを選択的に除去する仕組み(ミトファジー)が十分に働いていない状態を示唆します.さらに免疫シグナル解析では,HPgVは炎症を単純に促進あるいは抑制するのではなく,免疫応答全体の振れ幅を小さくする方向に働くことが示唆されました.このため,PD患者同士を比較すると,IL-4もMMP-9も相対的に低下してみえる点が今回の重要な所見です(図3).加えて注目されるのは,この免疫応答の変化が,パーキンソン病の代表的な遺伝的リスクであるLRRK2変異の有無によって異なる方向性を示すことです.LRRK2は免疫応答の「反応の強さ」を調整する遺伝子であり,その変異があると免疫系は刺激に対して過敏になります.そのため,免疫の振れ幅を小さくしようとするHPgVの作用が,変異の有無によって異なる方向に現れると考えられます.非常に複雑です.いずれにせよ,「ウイルス感染」と「遺伝的素因」が相互に作用して神経変性の進行に影響しうる可能性が示された点に,本研究の新規性と臨床的意義があります.
1)Taga A, et al. Bridging the Gap: Opsoclonus-Myoclonus Syndrome — Human Pegivirus Encephalomyelitis Diagnosed Through Metagenomic Next-Generation Sequencing. Neurology. 2025;105(6):e214091. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214091
2)Hanson BA, et al. Human pegivirus alters brain and blood immune and transcriptomic profiles of patients with Parkinson’s disease. JCI Insight. 2025;10(13):e189988. doi.org/10.1172/jci.insight.189988
・お読みいただきたい「見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録」
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月12日のFB投稿です**
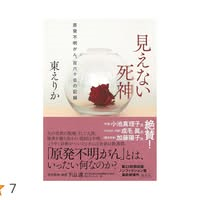 話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.
話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.
まず,若い医療者にぜひ読んでいただきたいと思いました.本書は,医療者にとって重要な資質のひとつである「エンパシー(共感)」を身につけるうえで,きわめて示唆に富んでいるからです.エンパシーとは,相手の内側に入り,その立場に立って考える知的な力です.生まれつきの感受性とは異なり,「もし自分がその人の立場なら,どう感じ,何を選ぶか」を意識的に思考する営みです.東さんは,当事者である患者と家族だけでなく,初回入院を担当した医師,セカンドオピニオン先の医師,多職種の医療者や介護者など,多面的な聞き取りを丹念に重ねています.診断がつかない不確かさの中で揺れる患者と家族の思い,そのとき側にいた医療者・介護者の戸惑いや願いが率直に描かれています.脳神経内科でも,希少で診断に難渋する疾患にしばしば遭遇します.そのとき患者と家族がどのような心情にあるのかを理解するうえで,本書は実践的な教材となる一冊だと感じました.
また,本書は一般の方にも強くお勧めします.末期がんの過ごし方が多様化した現在,在宅療養がどのように支えられているかなど,終末期医療の実際を知ることができます.「より善い生のあり方」を考えるための多くの示唆が得られると思います.
なかでも私に深く残ったのは,配偶者を亡くした人々の言葉でした.「半身を奪われたよう」「心の真ん中に穴が空いた」「この世にひとりでいることがつらい」.そして東さん自身の「私は異世界に来てしまったのだなと感じた」という一文には胸を衝かれました.自分は漠然と家内より先に死にたいと考えていましたが,残された側がこのような思いを抱えるのだと想像すると,胸が締めつけられる思いがしました.そして,自分がいつ大きな病に襲われても悔いのないように,日々を丁寧に生きたいと改めて思いました.
東さん,本当に素晴らしい本をお書きくださり,ありがとうございました.
・多系統萎縮症はプリオン様(prion-like)疾患である!!―自己複製するαシヌクレイン線維の構造が初めて可視化される
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月13日のFB投稿です**
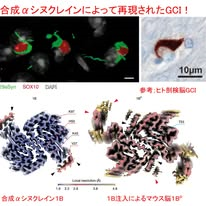 多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.
多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.
著者らはまず,合成線維1Bを正常マウスの線条体に注入し,数か月後に蛍光免疫染色にて観察しました.この結果,前交連や終条床核に多数のαシヌクレイン陽性封入体が形成されていました.これらの部位はヒトMSAでもGCIが早期から出現する白質経路として知られています.また封入体はオリゴデンドログリア細胞の核周囲に分布し,炎のかたちのような形態を呈しており(図上段左),ヒトのGCIの形態(図上段右)と類似していました.また,神経細胞の細胞質封入体(NCI)や核内封入体(NII)も観察され,初期には神経細胞に始まり,時間の経過とともにオリゴデンドログリアへと病理が波及する様子が示されました.
つぎに蛍光顕微鏡でαシヌクレイン陽性封入体を特定し,その領域を電子顕微鏡で観察することで,封入体の内部に束状の線維構造が存在することを確認しました.さらに,αシヌクレイン抗体による免疫金染色で金粒子が線維に一致して検出され,これらの線維がαシヌクレイン由来であることが直接的に証明されました.
続いてクライオ電子顕微鏡を用いて,1B線維の立体構造を明らかにしました.1B線維は2本のプロトフィラメントが互いに巻きつき,「2₁ねじれ対称」と呼ばれる規則的ならせん構造をとっていることが明らかになりました(図下段左).これは線維を軸に沿って180度回転し,同時に一定の距離だけ進むと同じ構造が繰り返される対称性を意味します.このような幾何学的規則性が,αシヌクレイン線維が同じ形を保ったまま自己複製するための基盤になっていると考えられます.さらに1B線維注入によりできたマウス脳内封入体(1BP;1B product)をクライオ電顕で解析したところ,両者の立体構造はほぼ完全に一致していました(図下段右).すなわち,αシヌクレイン線維が生体内で自己の立体構造を保持したまま複製する,プリオン様伝播を明確に示したものと言えます.
ちなみにThioflavin T(ThT)は,アミロイド線維やプリオンタンパク質のβシート構造に特異的に結合して蛍光を発する色素で,プリオン研究では古くから「線維形成の検出指標」として使われてきました.しかし1B線維は「ThT陰性」で,MSA患者由来のαシヌクレイン線維も「ThT陰性」でした.これはThTが結合するN末端側およびC末端側の「ThT結合ポケット(N-pocketとC-pocket)」が閉じた構造になっているためであり,その閉鎖がMSA線維の高い安定性とプリオン様自己複製能を生み出していると考えられました.著者らはこの閉鎖構造を「MSA構造核(MSA kernel)」と名付け,MSAの病理を引き起こすために必要十分な立体構造の中枢部分と述べています.
さらに,ヒトA53T変異αシヌクレイン発現マウスに1B線維を注入すると,16週間で致死的な神経変性を呈し,GCIやグリア核内封入体(GNI)が多数出現しました.このマウス脳ホモジネートを別の正常マウスに再注入しても同様の病理が再現され,1B線維が感染性をもつ構造株として振る舞うことが確認されました.つまり変異αシヌクレインは,野生型よりもプリオン様構造変化を受けやすく,自己複製や伝播を促進する「高感受性宿主」として働くということです.
本研究は,人工的に合成されたαシヌクレイン線維が生体内で自己複製し,ヒトMSA様の封入体病理を形成することを世界で初めて実証したものです.これにより,MSAがタンパク質単独で複製できる,つまりプリオン様機構によって進展するという仮説が,明確な根拠を得たと言えます.ただし,感染性や種間伝播など古典的なプリオン病の要件をすべて満たすわけではなく,現時点では「プリオン様(prion-like)疾患」と呼ぶのが正確です.今後,MSA構造核の安定化を阻害する治療戦略や,ポケット閉鎖を標的とした創薬が期待されます.
Burger D, et al. Synthetic α-synuclein fibrils replicate in mice causing MSA-like pathology. Nature. 2025. doi.org/10.1038/s41586-025-09698-1.
・片頭痛は頭痛前からすでに始まっている ―今後の片頭痛治療では予兆の時系列を知る必要がある―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月14日のFB投稿です**
 片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.
片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.
この研究では,成人片頭痛患者20名を対象に,60分間の半構造化インタビューを行い,患者さんが自覚する予兆とその出現タイミングを詳細に評価しています.参加者は平均43.8歳で,月あたり2〜8回片頭痛発作を持つ典型的な患者群でした.
さて結果ですが,患者はなんと36種類もの予兆を報告し,1人あたり平均13症状と,非常に多彩な症状が予兆として出現することが明らかになりました.悪心,疲労・倦怠感,光過敏,頸部痛,めまいが代表的ですが,温度過敏,思考困難,集中困難,嗅覚過敏,食欲低下など,自律神経・感覚・認知の幅広い領域が関与していました.それだけ脳の多くの領域,システムが関与するということだと思われます.また多くの患者が,予兆そのものが仕事や家事,睡眠,外出など日常生活に支障をきたすと述べており,片頭痛が頭痛発作だけの病気ではないことが分かります.
この研究で最も重要な成果は,図に示された「予兆が頭痛のどれくらい前に出るか」という時間情報です.症状ごとに平均時間・中央値・最小〜最大(いずれも単位はh)が整理されています.予兆の72%は頭痛発作の1〜6時間前に出現していました.たとえば頭痛発作に近い予兆として,悪心は平均0.8時間前,光過敏は1.0時間前,めまいは2.0時間前に現れます.一方,もっと離れて,早期から出現する症状もあり,食欲低下はなんと9.1時間前,嗅覚過敏は8.5時間前,腸蠕動の変化は6.5時間前に出現します.このように症状によっては,頭痛発作との距離が大きいため,患者自身はこれらの予兆を片頭痛の症状と思わず,誘因(トリガー)と思ってしまいます.図が見にくいので表にまとめてましたが,この表でもう1箇所,チェックすべきは人数です.これは20人の参加者のうち,何人がその症状を予兆として経験したかを示しており,各予兆の頻度がうかがえます.
また予兆期における服薬も重要なポイントです.予兆期で薬を服用している患者は8割にのぼり,その多くが「頭痛を軽減できる」「発作を防げる」と回答していました.一方で,「どの症状をサインとして薬を飲むべきか判断が難しい」という声も多く,予兆期の症状把握と内服タイミングが治療の成否に関わっている可能性があります.近年,CGRP受容体拮抗薬であるubrogepantが,予兆期に内服すると頭痛そのものを防ぎうることが臨床試験で示されました.具体的には,予兆が出た時点で服用した患者の46%は24時間以内に頭痛が起こらず,安全性も良好でした.「痛くなる前に止める」新しい治療戦略として注目されています.つまり予兆期をより深く理解することは今後の治療戦略において重要になっていくと考えられます.患者さんが自分の予兆パターンを理解し,医療者がその情報をもとに治療のタイミングを適切に指導することで,片頭痛の負担を大きく減らせる可能性があります.その意味でこの研究は非常に価値が高いと言えます.
補足ですが,現在,予兆はICD-3で「頭痛の4-72時間前に出現しうる前駆症状」と定義されていますが,今回の論文で次回改訂でこの定義が変わるのかなと思いました.
Lipton RB, et al. Characterizing the patient experience during the prodrome phase of migraine: A qualitative study of symptoms and their timing. Headache. 2025;65:1355–1368. doi.org/10.1111/head.15024.
Dodick DW, et al. Ubrogepant for the treatment of migraine attacks during the prodrome: a phase 3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial in the USA. Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2307-2316. doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01683-5.
・新型コロナウイルス感染症COVID-19:最新エビデンスの紹介(11月17日)
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月17日のFB投稿です**
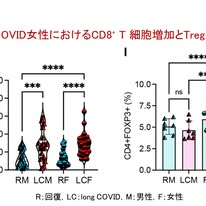 今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.
今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.
今回取り上げた3論文から見えてくるのは,Long COVIDとパンデミックの影響は依然として深刻であり,① 女性でコロナ後遺症が目立つのは免疫・ホルモン・遺伝子発現に原因があること,② 感染後の認知症状に対する治療はいまだ試行錯誤の段階であること,③ 一方でワクチン接種による重症化予防効果は現在も揺るぎないこと,という現状です.
◆ Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で,ノーベル賞で話題の制御性 T 細胞(Treg)も低下する
Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)はいずれも強い疲労やブレインフォグを呈しますが,その背景に性差があることを示した包括的な免疫学研究が報告されました.ME/CFS型Long COVID患者78名と回復者62名を比較し,免疫細胞,サイトカイン,ホルモン,遺伝子発現を詳細に解析しました.女性のLong COVID患者では,好中球と単球が増加し,ウイルス感染細胞を破壊するCD8⁺ T 細胞が急性期後も高いままであり,過剰な免疫活性化が続いている状態を示唆します.また免疫のブレーキ役である制御性 T 細胞(Treg)が減少しており,炎症のアクセルが強く踏まれているにもかかわらず,ブレーキが壊れたままという状態であり,女性で慢性的な炎症が持続しやすい特徴を示しています(図1G, I).さらにホルモンバランスの異常も加わります.女性の Long COVID ではコルチゾールに加え,テストステロンが低下しており,免疫調整機能が弱くなることで炎症がさらに悪化しやすくなります(図2A, C).一方で男性ではエストラジオールが低下しており,こちらも炎症制御に影響することが示唆されています(図2B).またI-FABP や LPS-BP も上昇していますが,いずれも腸管の損傷とバリア機能の低下を反映する指標であり,特に女性で顕著な変化として描かれています.トランスクリプトーム解析では,女性患者で神経炎症関連遺伝子の活性化が目立ち,認知機能低下との関係が示されています.病態の複雑さと性差の重要性を示す,非常に示唆的な研究であり,今後は女性特異的な治療戦略,とくにホルモン補充療法も含めた介入の検討が必要になるかもしれません.
Shahbaz S, et al. Cell Reports Medicine, 2025; 6: 101234. https://www.cell.com/cell…/fulltext/S2666-3791(25)00522-1
◆ Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし
Long COVIDの認知症状は臨床で大きな問題となっていますが,治療はまだ確立していません.米国22施設による大規模ランダム化比較試験では,①オンライン認知トレーニング(BrainHQ),②構造化認知リハビリ(PASC-CoRE)+BrainHQ,③経頭蓋直流電気刺激(tDCS)+BrainHQ,に加えて,教育的ビデオ視聴を行う能動的対照群やtDCSシャム群を含む5群を比較しました.図3で示すようにLong COVIDの認知障害に対して現時点で考えうる主要な介入をほぼ網羅した,非常に野心的なデザインであることが分かります.しかし結果は主要評価項目であるmodified ECog-2では,いずれの介入も対照群と有意差なし,さらに神経心理検査や疲労・気分・睡眠・QOLといった副次評価項目でも群間差なしという厳しいものでした.興味深いのは,介入の種類にかかわらず,すべての群で時間とともに認知症状がわずかに改善していた点です.これは特定の治療効果というよりも,自然経過として徐々に良くなる患者が一定数存在することを示唆しています.ただし改善の大きさは平均すると小さく,群間の統計学的差は認められませんでした.いずれにせよ現時点では,「決定打となる治療はまだない」というのが結論であり,新たなアプローチや,より長期間・集中的な介入の検討が必要と考えられます.
Knopman DS, et al. JAMA Neurology, 2025; 82: e1–e10. https://jamanetwork.com/…/jamaneuro…/fullarticle/2841155
◆ 2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす
ワクチン接種率が低下するなかで,「本当にまだ効果があるのか?」という疑問に答える重要な研究です.米国退役軍人省の電子カルテデータを用いて,インフルエンザワクチンのみ接種群131,839名と,COVID-19ワクチン+インフルエンザ同日接種群164,132名を比較した,約29万人を対象とする大規模解析が報告されました.6か月間の追跡の結果,COVID-19ワクチン接種は,COVID-19関連救急受診を29.3%減少,COVID-19関連入院を39.2%減少,COVID-19関連死亡を64.0%減少させました(図4).これらの効果は,高齢者,基礎疾患の有無,免疫不全の有無など,あらゆるサブグループで一貫していました.ワクチン接種は「感染そのものを完全に防ぐ」効果は以前よりも弱くなっているかもしれませんが,「重症化を防ぐ」というワクチンの本質的な価値は依然として非常に大きいことが改めて確認されたと言えます.
Cai M, et al. N Engl J Med, 2025; 393: 1612–1623. doi.org/10.1056/NEJMoa2510226
関連情報
前回の「下畑先生のCOVID-19:最新エビデンス」は、2025年7月のニュースに掲載しています。
・三浦謹之助先生に関する研究論文を発表いたしました!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月19日のFB投稿です**
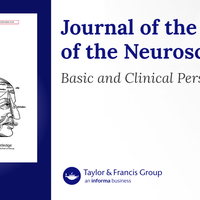 日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.
日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.
「なぜ三浦謹之助先生に関心を持たれたのですか?」というご質問をしばしばいただきます.きっかけは,もともとシャルコー先生に強い関心を抱いていたことに加え,コロナ禍,そしてワクチン接種後に増加した機能性神経障害(かつてのヒステリー)の患者さんを診療する中で,ヒステリー研究の祖でもあるシャルコー先生について学び直すなかで,三浦謹之助先生の存在がどんどん大きくなったためです.
今回の学会発表と論文執筆を通じて,多くの学びを得ることができました.海外のシャルコー研究者との交流も生まれましたし,日本の神経学がどのような道筋を辿って現在に至ったのか,そのルーツを改めて知る貴重な機会となりました.若い先生方にもこうした歴史を伝えていけるよう,今後も機会を見つけて医学史の勉強を続けていきたいと思います.
論文は下記リンクよりご覧いただけます(ただし無料でのダウンロードは50名までとのことです).もしダウンロードできなかった場合にはPDFをお送りしますので,どうぞお気軽にご連絡ください.
https://www.tandfonline.com/eprint/KJUMWCHK7AYTTQ8JTYCK/full?target=10.1080/0964704X.2025.2581565
Shimohata T, Iwata M. Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A master-disciple legacy in modern Japanese neurology. J Hist Neurosci. 2025 Nov 18:1-11. doi.org/10.1080/0964704X.2025.2581565.
・画期的「脳クリアランス治療時代」の到来か!!脳出血後の脳内デブリ(ゴミ)を集束超音波で掃除して予後を改善する
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月20日のFB投稿です**
 6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.
6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.
今回紹介するスタンフォード大学の研究グループによる論文は,その「脳クリアランス」の概念を臨床応用に向け大きく前進させるものです.低強度の集束超音波(FUS)を用いて脳内に蓄積した有害なデブリを非侵襲的に頸部リンパ節へと運び除去し,脳出血モデル動物で神経炎症や神経細胞死を減らし,行動の改善と生存率向上にまでつながることを示しました.基礎研究ではありますが,明確に臨床応用を視野に入れた学際的な研究と言えます.
研究の中心となるのは,著者らが開発した「Ultrasonic Debris Clearance(UDC)」という250 kHzの低強度集束超音波プロトコールです.頭蓋骨を通して照射しても安全なレベルの低出力でありながら,脳脊髄液や脳実質に散らばる赤血球や細胞片といった微小なデブリを“動かして排出する”という新しいアプローチを可能にしました.著者らは,くも膜下出血(SAH)と脳内出血(ICH)のマウスモデルでUDCを適用し,どちらのモデルでも顕著なデブリ除去効果を確認しています.
図1では,このUDCの核心となる現象が非常にわかりやすく示されています.とくに重要なのは(d)と(e)のパネルで,(d)ではSAHモデルにおいて,UDC照射によってくも膜下腔の脳脊髄液中に散らばった赤血球が劇的に減少し,同時に深頸部リンパ節に赤血球が多く集積していることが示されます.つまり,「超音波を当てる → デブリが動く → リンパ節へ流れる」ということです.(e)では脳出血モデルにおいて,脳実質に残存する赤血球がUDCによって大幅に減少し,深頸部リンパ節への集積が確認されます.深部の血腫デブリでさえ動かせるという点で,非常に強いインパクトを持つ結果です.
さらに著者らは,UDCによるデブリ除去が神経炎症の軽減につながることも明らかにしました.ミクログリアやアストロサイトの炎症マーカー(IBA1,GFAP)の発現はUDC群で抑えられ,Fluoro-Jade Cで染まる変性神経細胞も減少しています(図2).加えて,UDCを施された動物モデルでは,corner turn testや前肢握力といった運動機能が改善し,脳浮腫の軽減,さらには生存率改善まで確認されています.
では,なぜ超音波でこのような効果が得られるのでしょうか.物理的な力ではないようです.著者らは,超音波の微細な振動がミクログリアに作用し,その性質を“炎症を起こしやすい状態”から“通常の落ち着いた状態”へ切り替えている可能性を示しています!!私たちの細胞には,圧力や揺れといった物理的な刺激を感じ取る仕組みが備わっているそうで,その代表例としてPiezo(ピエゾ)やTRP(トリップ)と呼ばれる分子が知られています.これらは「振動や圧力を感知するセンサー」のような働きをする分子で,超音波がこのセンサーを刺激することでミクログリアの状態が整い,その結果としてデブリ除去や炎症軽減が進むのではないかという考え方です.実際に,これらのセンサーを阻害するとUDCの効果は消失しており,超音波の作用がこうした分子経路を介していることが強く示唆されています.また,AQP4の血管周囲への極性回復など,グリンファティック機能の改善を示す所見も得られています.
UDCは薬物治療のような全身副作用が少なく,外科的血腫除去のような侵襲性もありません.本研究で用いられた周波数や出力はすでに臨床機器で再現可能です.もし今後の臨床試験で有効性が示されれば,脳出血の急性期治療のみならず,グリンファティック機能障害が関与する認知症など神経変性疾患などへの応用が期待されます.かなり画期的な治療になるような予感がします.
Azadian MM, et al.Clearance of intracranial debris by ultrasound reduces inflammation and improves outcomes in hemorrhagic stroke models. Nat Biotechnol. 2025 Nov 10. doi.org/10.1038/s41587-025-02866-8.
・アルツハイマー病は「脳血管病」の性質をもつ:血液脳関門破綻,低灌流,血小板から見える新しい姿
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月22日のFB投稿です**
 2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).
2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).
Ventura-Antunes L, et al. Arteriolar degeneration and stiffness in cerebral amyloid angiopathy are linked to Aβ deposition and lysyl oxidase. Alzheimers Dement. 2025 Jun;21(6):e70254. doi.org/10.1002/alz.70254.
この論文を読んで思ったことの1番目は,アルツハイマー病(AD)では想像以上に,血管性認知症の要素があるかもしれないということ,2番目はこのような状態の血管にAβ抗体(レカネマブ・ドナネマブ)を使用して病理学的に何が生ずるか非常に気になるということです.最近,報告された3つの論文はこれらの疑問に対し,非常に重要な示唆を与えるものです.
◆1.ADでは血液脳関門の破綻が認知機能低下を加速する
血液脳関門(BBB)の脆弱性が認知機能にどのような影響を与えるかを,脳脊髄液中のsPDGFRβを指標として検討したものです.sPDGFRβはBBBの要である周皮細胞(ペリサイト)が障害を受けた際に上昇するマーカーであり,BBBの破綻を鋭敏に反映します.認知症のない高齢者83名を5年間追跡し,BBB障害とADバイオマーカー,そして認知機能の変化を詳細に調べました.興味深いことに,sPDGFRβが高い人は,観察開始時には注意機能や実行機能が比較的保たれていたものの,経時的には認知機能の低下がより急速に進行しました.特にアミロイド陽性者やAPOE ε4保有者ではその傾向が顕著であり(図2),BBBの脆弱性がAD病理と相互作用して認知症への進展を加速する可能性が強く示唆されました.
Edwards L, et al. Interactive effects of blood–brain barrier breakdown and Alzheimer’s disease biomarkers on cognitive trajectories. Alzheimer’s & Dementia. 2025. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/…/alz…
◆2.死後脳が示す「低灌流 → 血管反応 → BBB破綻」という連鎖
AD患者の剖検脳を用いて血管病理の進行を詳細に解析したものです.白質の慢性的な低灌流を示すMAG(Myelin-Associated Glycoprotein):PLP1(Proteolipid Protein 1)比は,ADの比較的初期であるBraak III–IVの段階からすでに低下しており,脳が長期にわたって虚血にさらされていたことを示しています(PLP1は強い虚血でも保たれるのに対し,MAGは軽度の虚血でも低下します;図3).さらに,脳が虚血にさらされているにも関わらず血管収縮因子であるエンドセリン-1が分泌されて一層,虚血が進んだり,血管新生因子VEGF-Aが過剰分泌されて異常で質の悪い血管が形成されていることが明らかになりました.ペリサイトマーカーであるPDGFRβは初期ADから発現低下しており,BBBを維持する力が弱まっていることを示しています.BBB破綻の指標であるフィブリノーゲンの漏出は後期ADで顕著になっており,早期の低灌流と血管反応の異常,ペリサイト障害が積み重なり,最終的にBBB破綻へと至る段階的な血管病態が推測されます.以上より,ADでは早期から神経変性のみならず,脳血管の異常が進行していることが分かります.
Asby DJ, et al. Post-mortem evidence of pathogenic angiogenesis and abnormal vascular function in early Alzheimer’s disease. Brain. 2025 Oct 22:awaf394. doi.org/10.1093/brain/awaf394.
◆3. 中年期の血小板凝集能がすでにAβ・タウ蓄積と結びついている
平均56歳の一般住民382人を対象に血小板凝集能を評価し,アミロイドPET,タウPET,MRI所見と照合しています.その結果,血小板の凝集反応が低い三分位(T1)に属する参加者では,凝集能が高いほど脳内アミロイド沈着およびタウ蓄積がいずれも大きいことが明らかになりました(図4).一方,中間の三分位(T2)では,アミロイド蓄積とは関連が認められたものの,タウ蓄積との関連は認められませんでした.MRI解析でも,血小板凝集能が高いほど,ADに特徴的な皮質萎縮パターンがより強いという関連が示されました.これらの結果は,中年期における血小板の反応特性(凝集の強さ・速さ・閾値・飽和度)が,すでに神経変性の極めて早期の変化と結びついている可能性を示唆します.血小板はアミロイドβの主要な供給源の一つであり,血管内皮障害や炎症反応の誘導にも関与することが知られています.したがって,本研究の所見は,アルツハイマー病の背景に血小板を含む血管系の慢性炎症や凝固異常が潜在的に存在するという「血管病態仮説」を強く支持するものといえます.
Ramos-Cejudo J, et al. Association of Platelet Aggregation With Markers of Alzheimer Disease Pathology in Middle-Aged Participants of the Framingham Heart Study. Neurology. 2025 Nov 25;105(10):e214314. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214314.
◆抗アミロイドβ抗体療法はAD患者の脳血管にどのような影響をもつのか?
これら3つの研究を総合すると,ADの脳ではすでに血管代償機構が限界に近い状態にあり,慢性的な低灌流,血管収縮反応の過剰化,異常な血管新生,そしてペリサイト障害といった複数の血管病態が重層的に進行していることが明らかになります.このような状況下で抗アミロイドβ抗体療法を行う際には,アミロイド除去が脳血管にもたらす影響を慎重に考慮する必要があります.もちろん,血管構造と血流が比較的保たれている初期の患者では,抗アミロイドβ抗体の効果が血管系への負荷を上回る可能性があり,治療価値そのものを否定するものではありません.しかし,上記の血管病態が顕著な患者においては,BBBの脆弱性がすでに存在するため,急速なアミロイド除去によって血管壁にさらなるストレスがかかり,ARIA-EやARIA-Hといった副作用が生じやすくなることは十分に理解できます.加えて,血小板凝集亢進を示す患者では,もともとの炎症・凝固亢進を背景に,抗体治療によるアミロイドクリアランスの過程で局所炎症反応が増幅され,血管損傷のリスクがさらに高まる可能性があります.さらに慢性的な低灌流状態にある脳では血管の代償能力が低いため,アミロイド除去に伴う急性の血管ストレスに耐えられず,脳血管由来の認知機能低下へとつながる懸念も否定できません.
以上を踏まえると,抗アミロイドβ抗体療法は,血管病変の強い患者では十分な効果を発揮しにくいだけでなく,場合によっては認知機能悪化につながる可能性すらあると考えられます.治療対象の選別においては,神経病理だけでなく脳血管の状態を評価し,血管の脆弱性を正しく見極めることが今後ますます重要になると思われます.
・新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症@第44回日本認知症学会学術集会
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月23日のFB投稿です**
 第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.
第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.
セッションは,中嶋秀人先生(日本大学)による総論から始まり,森泰子先生(岐阜大学)の水痘・帯状疱疹ウイルス,横山和正先生(東静脳神経センター)の単純ヘルペスウイルス,私からのSARS-CoV-2(新型コロナウイルス),そして黒田隆之先生(東京科学大学)のEBウイルスと,各演者よりウイルス感染症と認知症の関連について多角的な議論が展開されました.改めて,認知症予防を考えるうえで極めて重要な視点であると実感いたしました.要点は以下のとおりです.
◆神経向性ウイルス感染が認知症や神経変性疾患の危険因子となることを示す疫学研究が,近年複数報告されている.
◆神経炎症のメカニズムとして,NFκBやcGAS–STINGシグナルなどの関与が明らかになりつつある.
◆アルツハイマー病の病因タンパクであるアミロイドβやタウは,ウイルス感染に対する宿主防御反応として作用している可能性が指摘されている.
◆病態に関連する機序として,病因タンパクの凝集(おそらくこれはウイルスに対する防御反応),神経炎症,血液脳関門破綻,他ウイルスの再活性化など複数の経路が考えられる.
◆帯状疱疹ウイルスに対するワクチン接種が認知症予防に有効であるという質の高いエビデンスが2つ報告された.また,新型コロナワクチンについても,罹患後症状を予防するとのメタ解析が示されている.
◆認知症予防の観点から,感染予防およびワクチン接種について市民への啓発を進めていくことが今後一層重要となる.
最後に,本シンポジウムを大いに盛り上げてくださった演者の先生方に改めて深く御礼申し上げます.また,会場で熱心にご参加いただき,活発なご質問とご意見をお寄せくださった多くの先生方に心より感謝申し上げます.
・急速に悪化する原因不明の重症脳炎をメタゲノム次世代シーケンスで診断し治療する!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月24日のFB投稿です**
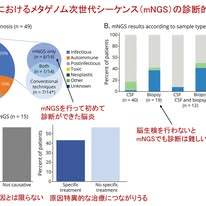 脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.
脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.
メタゲノムとはある環境(例:患者検体,腸内,土壌,海水など)に存在するすべての微生物の遺伝子情報をまとめてひとつのゲノム集合体として扱う概念です.そしてmNGSとは患者検体などに含まれるすべての遺伝子断片を網羅的に読み取り,未知・既知を問わず微生物(ウイルス,細菌,真菌,寄生虫)を一括で同定できる手法を指します.今回,パリのサルペトリエール病院から,重症脳炎の原因検索におけるmNGSの有用性を検証した研究が報告されています.次世代の脳炎医療を学ぶことができます.
対象患者は,2016年から2023年までで,血液検査や脳脊髄液検査,MRIなどの初期検査では原因が全く特定できないまま集中治療室に入室した重症脳炎患者です.特に免疫不全状態の患者が多く含まれ,全体の約45%を占めていました.最終診断がついた49例のうち40例が「脳炎」と確定し,この40例の中では14例(35%)が感染性脳炎でした.全49例を母数にすると感染性脳炎は約29%(14/49)であり,研究の対象全体の中で一定の割合を占めています(図1A).重要な点は感染性脳炎14例のうち6例はmNGSがなければ診断に至らなかったことです.
詳しく見ると,49例のうち,脳脊髄液mNGSが40例で,脳生検mNGSが19例で行われ,12例では両者が施行されました.結果としては脳脊髄液では40例中7例(17.5%)で何らかの病原体が検出されましたが,そのうち実際に脳炎の原因と判断されたのはわずか1例(2.5%)にとどまりました.一方,脳生検では19例中7例(36.8%)で何らかの病原体が検出され,その7例すべてが脳炎の原因病原体と評価されました(図1B).具体的には,風疹ウイルス,麻疹ウイルス,デングウイルス,Nocardia,HHV-6,アストロウイルス,オーソブニヤウイルスが検出されました.これらはいずれも免疫不全患者に起こりやすい稀な病原体です.聞いたことさえないアストロウイルスやオーソブニヤウイルスが含まれ,原因を同定できないのも無理はないと思いました.
さらに図1Cでは,mNGSの「陽性」の内訳が示されています.49例中15例でmNGS陽性でしたが,本当に脳炎の原因だった(causative)と判断されたのは7例(46.7%)のみでした.そして重要なのは,この7例はすべて脳生検で検出されており,全員が免疫不全患者だったという点です.一方,残りの陽性8例は「非原因性」で,偶然検出されただけのpegivirus,rhinovirus,HHV7,HHV8,EBVなどでした.mNGS陽性だからといって,すべてが脳炎の原因ではないことが如実に示されています.ただしpegivirus 2例は最近の報告をみると本当に「非原因性」かは疑わしい(グレイゾーン)のような気もします.
そしてうち4/7例(57.1%)ではmNGSの結果に基づき,以下のような原因に合った治療が開始されました(図1Cの右のグラフは数字が間違っている?).
① 風疹ウイルス→ニタゾキサニド(注;in vitro での抗ウイルス活性があるらしい)
② Nocardia + HHV-6→抗菌薬(セフロキシム, テイコプラニンなど)(注;NocardiaにはST合剤を使うはずだが…)
③ アストロウイルス→免疫回復治療(免疫再構築)(注;特異的抗ウイルス薬が存在しないため,免疫抑制剤中止+IVIGなど)
④ JCウイルス(PML)→ペムブロリズマブ(注;PD-1阻害剤は症例報告レベルで有効例あり)
議論となるのは脳生検の是非かと思います.まず脳生検のマイナス面ですが,生検に伴う合併症は19例中6例にありましたが,いずれも無症候性の軽微な画像所見で,臨床的な悪化を引き起こすものではありませんでした.つぎにプラス面はなんといっても治療に繋がった症例がいるということです.原因不明のまま治療が遅れれば致死的となる病原体も多く,その場合,脳生検+mNGSが唯一の突破口となり得ます.脳生検は「最後の手段」というイメージが強いですが,免疫不全を背景に急速に悪化する原因不明の脳炎においては,むしろ「必要な手段」として検討すべき場面があることが分かりました.mNGSはまだどこでもできる検査ではありませんが,将来的にこのような医療が行われるようになることが分かり大変勉強になりました.
Benghanem S, et al. Diagnostic yield of next-generation sequencing in CSF or brain biopsy for severe encephalitis requiring intensive care. Neurol Clin Pract. 2025 Dec;15(6):e200558. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200558.
・自律神経障害を欠く多系統萎縮症は確実に存在し,従来は見逃されていた可能性が高い!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月26日のFB投稿です**
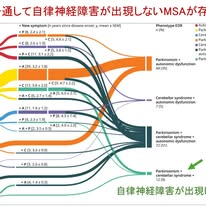 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.
多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.
本研究の一番の注目点は,患者の発症時の症候がパーキンソニズム(P),小脳性運動失調(C),自律神経障害(A)のいずれであったかを丁寧に分類し,どのような順番で症候が追加されていくかを追跡した点にあります.下記に示すサンキー図(Sankey diagram;工程間の流量を表現する図表)では,P・C・Aの3要素がどのように分岐し,最終的にどの症候の組み合わせに到達するのかが視覚的に示されています.
まず興味深いのは,初発時に自律神経障害を欠いていた症例が全体の58%(41+12+5%)にものぼったことです.従来の診断基準ではMSAと診断されていなかった可能性が高い患者が,実は多数存在していたことを意味します.さらに追跡の結果,最終診察時に至るまで自律神経障害が一度も出現しなかった患者が12例(9%)存在し,この群は平均8.1年と比較的長い罹病期間を示しました(明るい緑色の線).具体的には,
Aなし群の罹病期間:8.1 ± 2.1 年
Aあり群の罹病期間:6.3 ± 2.6 年
と,Aが出ない群の方が生存期間が有意に長いことが示されています(p=0.035).また自律神経障害を欠いていた症例は,起立性低血圧を悪化させ得るレボドパ治療によって説明できるものではありませんでした(A欠如群の83%がレボドパを使用していました).
一方,小脳症候で発症した患者は,早期から自律神経障害やパーキンソニズムへ枝分かれし,疾患の多系統化がもっとも早い群でした.これは従来の報告とも一致し,小脳発症MSAの疾患進行の速さを裏づけています.
また最終的には51%の患者がP+C+Aの3症候すべてを呈し,MSAが真の意味で「多系統」の疾患であることも再確認されました.
この研究は,MSAの診断と病態理解に大きな影響を与えます.とくに,自律神経症状がないからMSAではないと判断されていた患者が実際にはMSAであった可能性を示し,新しいMDS基準が臨床現場で非常に重要であることを改めて示唆しています.また非自律神経型MSA(=運動症のみのMSA)が進行の遅いサブタイプである可能性も示され,治療介入研究において,運動症状のみで経過する症例を除外してしまうことのリスクが強調されています.以下,論文のまとめです.
① 非自律神経型MSAは確実に存在する.従来は見逃されていた可能性が高い.
② MDS基準の運動症状のみでの診断は妥当である.
③ 非自律神経型MSAは進行が緩徐で予後が比較的良い.
④ 逆に小脳発症MSAは進行が速い.
⑤ 自然歴研究や治療介入試験では,進行度が遅く治療効果を検出しやすい非自律神経型MSA患者の存在を考慮する必要がある.
Wilkens I,Bebermeier S,Heine J,et al.Multiple System Atrophy Without Dysautonomia:An Autopsy-Confirmed Study.Neurology.2025;105:e214316.doi.org/10.1212/WNL.0000000000214316
・Happy birthday, Prof. Charcot! —シャルコー先生の遺した現代の脳神経内科医に必要な言葉とは?—
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月29日のFB投稿です**
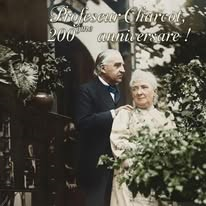 本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.
本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.
第1の柱は,解剖学と臨床を結びつけた方法論です.シャルコーはサルペトリエール病院に集まる多くの患者を「生きた病理博物館」と呼び,詳細な診察記録を重ね,死後の剖検所見と比較することで,臨床症候と神経病理を精密に結びつけました.パーキンソン病における動作緩慢やALSにおける上下位運動ニューロン徴候など,今日の教科書に記される基本概念の多くはここから生まれています.この「臨床と病理を行き来する」姿勢は,いま私たちが行っているトランスレーショナルリサーチの原点といえます.
第2の柱は,他分野からの知的刺激を積極的に取り込むという考え方です.シャルコーは写真技術を医学教育に活かし,美術学校の画家や彫刻家を招いて臨床所見の視覚化を進めました.歩行解析,電気生理学,新しい計測技術など,当時としては革新的な手法を次々に導入し,サルペトリエールを総合的な神経科学研究の中心へと押し上げました.彼が語った「医学は自律して存在するのではなく,他から着想を借り続けなければ停滞する」という考えは,現代の学祭的な連携や技術統合の在り方と見事に響き合います.
第3の柱は,遺伝素因に対する洞察です.メンデル遺伝学が確立される以前にもかかわらず,シャルコーは神経疾患の背景に「家族的な脆弱性」が存在すると考え,一つの遺伝素因がさまざまな症状として現れる可能性を示しました.彼が思い描いた「一つの遺伝的基盤から多様な表現型が生じる」という考え方は,21世紀の遺伝学やエピジェネティクス研究において重要なものになっています.
論文の最後でGoetz教授は,シャルコーの遺した数多くの言葉の中から,現代の脳神経内科医に必要な一節を紹介しています.1887年,彼は学生たちに向けてこう語りました.「When a patient calls on you, he is under no obligation to have a simple disease just to please you.(患者は,あなたのために簡単な病気で来てくれる義務などない.)」という言葉です.この一文には,複雑で理解しがたい症例と向き合う脳神経内科医にとって重く響きます.当然ですが,患者さんは医師のために簡単な病気を選んで来るわけではありません.だからこそ医師は慢心を捨て,地道な観察と探求を続け,今日の限界を認めつつも,明日の診断や治療がより良いものになるよう不断に学び続けなければならないのだと思います.200年を経てもなお,彼の言葉と精神は私たち脳神経内科医を照らし続けています.
Goetz CG. Si je ne me trompe pas: Charcot’s neurological legacy in the 21st century. Lancet Neurol. 2025 Dec;24(12):1000-1001. doi.org/10.1016/S1474-4422(25)00399-0.
・難病診療における医療倫理の難しさ@第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月29日のFB投稿です**
 第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。
第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。
まず岩木三保先生より、Jonsenの4分割表、臨床倫理の4原則、さらに「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等についてご講演いただき、適切な診療を実践するうえでの重要ポイントをご解説いただきました。その後は会場全体を巻き込んだ事例検討が行われました。
提示された事例は、在宅介護中で人工呼吸器を装着して生活しているALS患者さんが慢性腎不全を併発し、人工透析導入の是非を検討せざるを得ないという、現実に存在したケースでした。看護師の高田久美子さんから事例提示があり、会場の参加者同士が小グループを作り、各自の立場から議論し、最終的に意見を共有しました。
議論を通して、多職種の医療者がこのような臨床倫理的アプローチを実際に経験することの重要性を改めて実感しました。上述のガイドラインにも示されているとおり、患者さんの希望が必ずしもそのまま最終決定になるわけではありません。患者さん・ご家族が適切な意思決定に至れるよう、どの程度の情報を、どのように、どのタイミングで提供するのが望ましいのか――医療者側が深く考え続ける必要があると感じました。
この学会の大きな特色は、難病医療に関わる多職種が連携し、よりよい医療体制の構築を目指している点にあります。今回も大変有意義で刺激的な学術集会となりました。とくに今回は、本学会に加えて日本難病看護学会、神経難病リハビリテーション研究会の3学会による共同開催(難病支援学術コンソーシアム)であり、多様な職種の先生方と交流する貴重な機会となりました。このような素晴らしい学術集会を企画・運営いただいた漆谷真先生をはじめ大会長の先生方、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)
 8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪
8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪ 9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!
9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!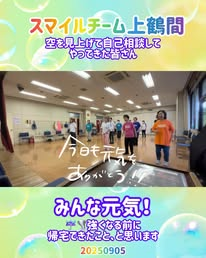 20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️
20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️ meet.google.com
meet.google.com 本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義
本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義 #インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6
#インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6 佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww 本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️
本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️ 2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名
2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名 鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。
鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。 9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊
9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊 【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園
【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園 天気も気まま
天気も気まま 佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^
佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^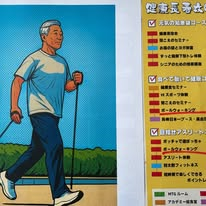 昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。
昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。 9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題
9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題 シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト
シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト 神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。
神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。 台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️
台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️ いつもの秋がやって来ました。@大巧寺
いつもの秋がやって来ました。@大巧寺 第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。
第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。 第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️
第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️ 9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。
9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。 ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。
ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。 ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️
ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️ あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。
あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。 通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践
通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践 介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?
介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?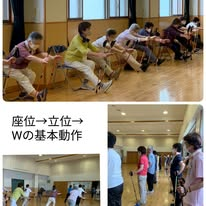 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加
#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加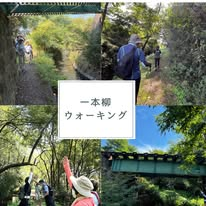 9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊
9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊 日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣
日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣 都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京
都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京 秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ
秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ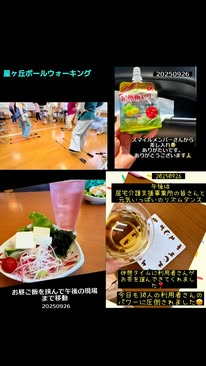 スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926
スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926 9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵
9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵 秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊
秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊 9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。
9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。 【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩
【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩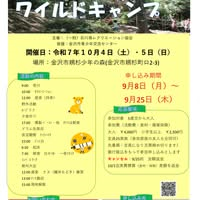 あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会
あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会 写真1件
写真1件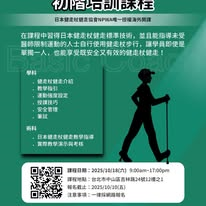 由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~
由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~ 【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地)
【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地) 私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。
私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。 第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内
第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内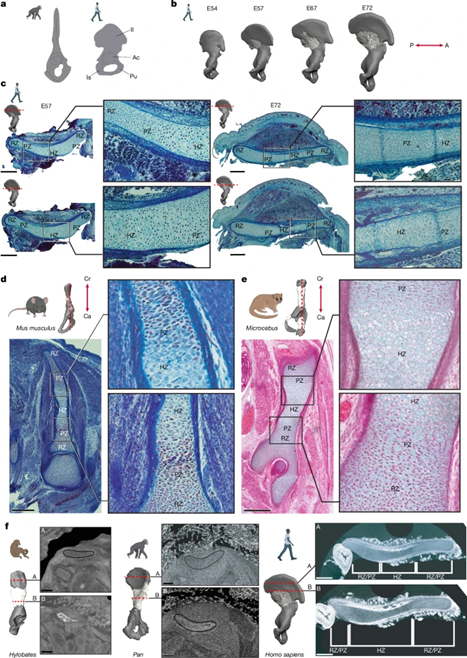 a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。
a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。 腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー
腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー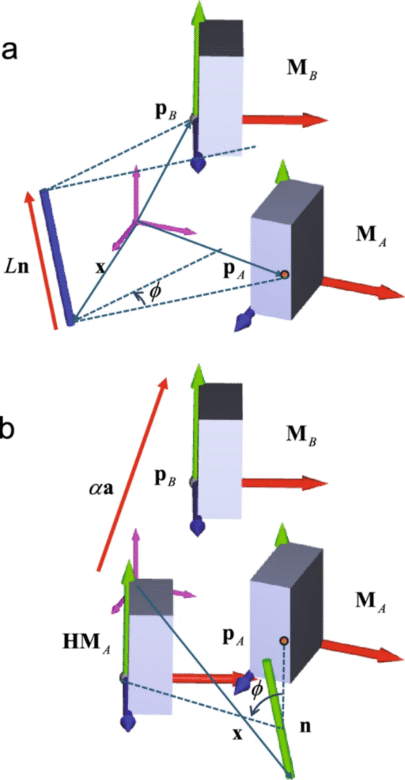 螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋
螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋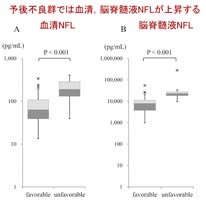 GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.
GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.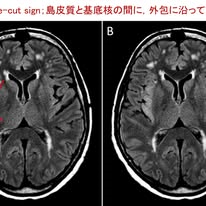 ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています.
ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています. 緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.
緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.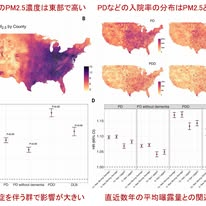 Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.
Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.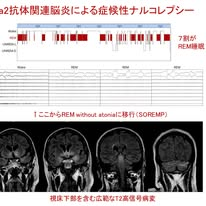 Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.
Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.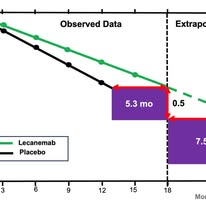 アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.
アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.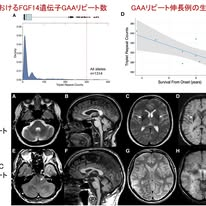 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.
多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.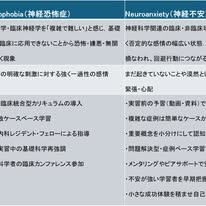 「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.
「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.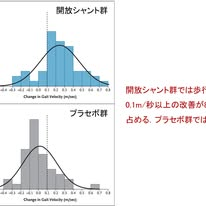 特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.
特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.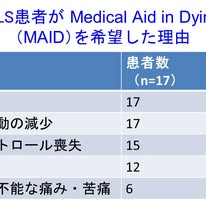 Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.
Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.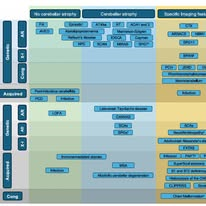 近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.
近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.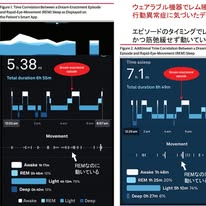 近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.
近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.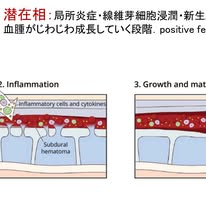 慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています.
慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています. オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.
オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.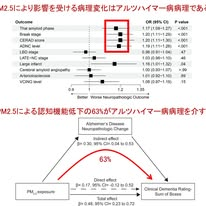 先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました.
先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました. 6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。
6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。 佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。
佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。 【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います!
【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います! 6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/
6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/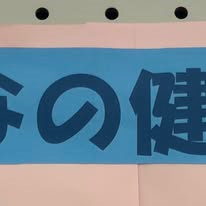 昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座
昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座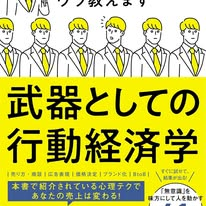 できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。
できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。 6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな?
6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな? Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング
Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング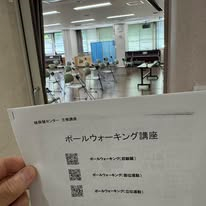 本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり
本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり 第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️
第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️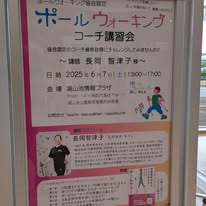 初上陸
初上陸 6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね)
6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね) #これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7
#これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7 佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️
佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️ 6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦
6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦 さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥
さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥 昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操
昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操 6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略
6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略 6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。
6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。 #船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。
#船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。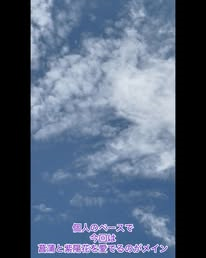

 緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。
緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。 6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。
6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。 いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。
いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。 6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。
6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。 猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり
猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり ㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇
㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇 6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。
6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。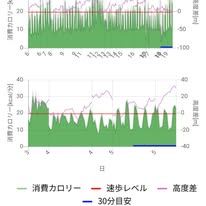 【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き
【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き #ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ
#ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ 【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体
【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体 先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。
先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。 6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。
6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。 海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl
海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl 「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています!
「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています! 【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座
【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座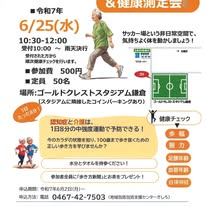 梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。
梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。 6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。
6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。 6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。
6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。 2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ
【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ 6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや
6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや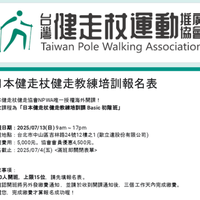 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表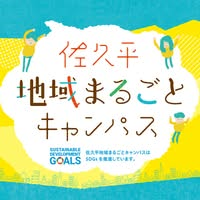 佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス!
佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス! 〇目 的
〇目 的 図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪
図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪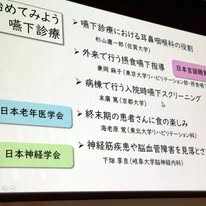 第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.
第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.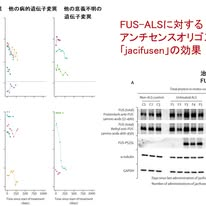 難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.
難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.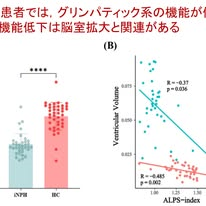 特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.
特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.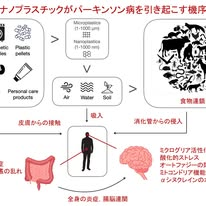 Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024).
Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024). 驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.
驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.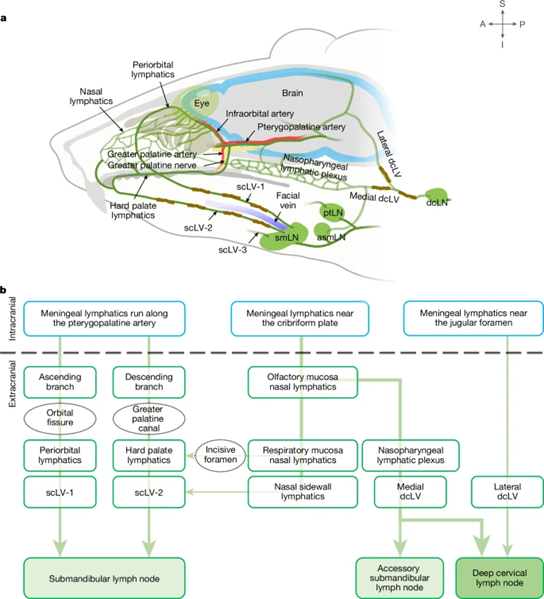 a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。
a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。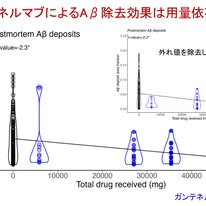 Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.
Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.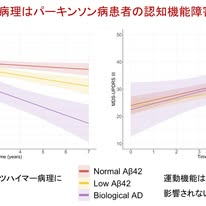 パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.
パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.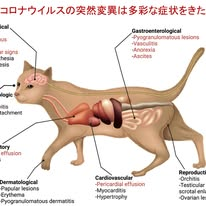 臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).
臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).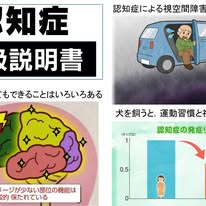 認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした.
認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした. 12/1 池上本門寺① 本蒲田1丁目から池上本門寺まで大田区の楽校の皆さんと数年振りにPWを楽しみました。昔の教え子さんたちは校長先生になられたりご立派に成長されたのに私はただ歳を重ねただけ。 本門寺で富士山を仰いで解散後ナマ友・FBFの事務局長さんに境内を案内して頂きました。鎌倉とも縁の深い日蓮宗のお寺は江戸時代の立派な珍しい墓地がたくさんあります。歴史上の方々始め有名人のお墓を巡らせて頂き、境内が広すぎて足が棒。
12/1 池上本門寺① 本蒲田1丁目から池上本門寺まで大田区の楽校の皆さんと数年振りにPWを楽しみました。昔の教え子さんたちは校長先生になられたりご立派に成長されたのに私はただ歳を重ねただけ。 本門寺で富士山を仰いで解散後ナマ友・FBFの事務局長さんに境内を案内して頂きました。鎌倉とも縁の深い日蓮宗のお寺は江戸時代の立派な珍しい墓地がたくさんあります。歴史上の方々始め有名人のお墓を巡らせて頂き、境内が広すぎて足が棒。 蒲田PW行進曲 今日は蒲田でPWイベント。 長く続けていたお陰で 懐かしい方々に再会できました。池上本門寺ご案内下さったYさんありがとうございました。北鎌倉を歩きませんか。
蒲田PW行進曲 今日は蒲田でPWイベント。 長く続けていたお陰で 懐かしい方々に再会できました。池上本門寺ご案内下さったYさんありがとうございました。北鎌倉を歩きませんか。 12/2 鎌倉ミステリーNo.10-① 鎌倉🍁のメッカ獅子舞から鎌倉アルプスの大平山~覚園寺を歩きました。イチョウの💛絨毯を踏みしめながら、始まったばかりの紅葉の🍁燃える色を見上げながらニコニコ元気に完歩。8日の②は後半のコースを変えます。 ご参加ありがとうございましたm(_ _)m
12/2 鎌倉ミステリーNo.10-① 鎌倉🍁のメッカ獅子舞から鎌倉アルプスの大平山~覚園寺を歩きました。イチョウの💛絨毯を踏みしめながら、始まったばかりの紅葉の🍁燃える色を見上げながらニコニコ元気に完歩。8日の②は後半のコースを変えます。 ご参加ありがとうございましたm(_ _)m 2024.11.29〜12.2 活動記録 ☺︎スマイルエクササイズ 13名 和室で出来るコンディショニングも とりいれました ☺︎上鶴間PW教室 14名 3回コース無事修理 半数の方がポール購入 自主サークル化決定 ☺︎上溝公民館自主企画事業打合せ 5回コースでのリズムエクササイズ 体験と発表 女性学級で1講座やらせて頂き好評 につき、自主企画事業として行う事 になりました ☺︎スマイル光が丘 20名 ラストに言葉遊びチェア体操で沢山 笑いました ☺︎公民館利用団体施設予約 5団体分
2024.11.29〜12.2 活動記録 ☺︎スマイルエクササイズ 13名 和室で出来るコンディショニングも とりいれました ☺︎上鶴間PW教室 14名 3回コース無事修理 半数の方がポール購入 自主サークル化決定 ☺︎上溝公民館自主企画事業打合せ 5回コースでのリズムエクササイズ 体験と発表 女性学級で1講座やらせて頂き好評 につき、自主企画事業として行う事 になりました ☺︎スマイル光が丘 20名 ラストに言葉遊びチェア体操で沢山 笑いました ☺︎公民館利用団体施設予約 5団体分 【楽しい街歩き】 船橋にこんな所があったの! そんな驚きの声が聞かれます #火曜日美姿勢コース #路地に佇む社寺を訪ねる街歩き 天気良し 案内の解説良し 聞くマナー良し 歩くマナー良し 皆がHAPPYで 良かったな〜💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #船橋寺町巡り #日本一小さい東照宮 #因果地蔵尊 #飯盛り大仏 #お女郎地蔵 #桜桃忌 #太宰治
【楽しい街歩き】 船橋にこんな所があったの! そんな驚きの声が聞かれます #火曜日美姿勢コース #路地に佇む社寺を訪ねる街歩き 天気良し 案内の解説良し 聞くマナー良し 歩くマナー良し 皆がHAPPYで 良かったな〜💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #船橋寺町巡り #日本一小さい東照宮 #因果地蔵尊 #飯盛り大仏 #お女郎地蔵 #桜桃忌 #太宰治 12/3 広町緑地公園で黄葉ポールウォーキング 昨日の天園の写真と紛らわしい こちらは泥濘がありませんが坂道階段は頻繁にあります。12/22は公園主催の紅葉散策(自由参加)イベントがあります。全体が色づくのはまだまだ先なんですね。 富士山も目の前に!
12/3 広町緑地公園で黄葉ポールウォーキング 昨日の天園の写真と紛らわしい こちらは泥濘がありませんが坂道階段は頻繁にあります。12/22は公園主催の紅葉散策(自由参加)イベントがあります。全体が色づくのはまだまだ先なんですね。 富士山も目の前に! 12/4 北鎌倉 爽やかで暖かな小春日和 テラススタジオでNewプログラム 鎌倉まで色づく秋を楽しみながらのんびり歩いて帰りました 円覚寺~東慶寺~途中 鉢の木でランチ~~~
12/4 北鎌倉 爽やかで暖かな小春日和 テラススタジオでNewプログラム 鎌倉まで色づく秋を楽しみながらのんびり歩いて帰りました 円覚寺~東慶寺~途中 鉢の木でランチ~~~ 2024【日式健走 Advance Coach 進階教練培訓課】 課程圓滿結束!🎉 為期2天的進階教練培訓課程在滿滿的收穫中劃下句點!👏💪 在專業講師的悉心指導下, 學員們不僅深入學習了健走杖運動的進階技巧, 更強化了教學能力與團隊帶領能力, 為推廣健康運動邁出了關鍵一步!🌟🚶♂️🚶♀️ 這是一場充滿挑戰與成長的旅程, 學員們在理論與實作中不斷突破自我, 展現了對健走運動的熱忱與專注🔥。 每一步都走得穩健,每一次學習都收穫滿滿!📚✨ 感謝所有參與的學員與教練們, 因為你們的投入與努力, 讓這次課程充滿活力與意義💖! 接下來, 讓我們一起期待未來更多的健走推廣計畫, #共同邁向更健康更精彩的生活!🌏💪 #日式健走AdvanceCoach進階教練培訓課
2024【日式健走 Advance Coach 進階教練培訓課】 課程圓滿結束!🎉 為期2天的進階教練培訓課程在滿滿的收穫中劃下句點!👏💪 在專業講師的悉心指導下, 學員們不僅深入學習了健走杖運動的進階技巧, 更強化了教學能力與團隊帶領能力, 為推廣健康運動邁出了關鍵一步!🌟🚶♂️🚶♀️ 這是一場充滿挑戰與成長的旅程, 學員們在理論與實作中不斷突破自我, 展現了對健走運動的熱忱與專注🔥。 每一步都走得穩健,每一次學習都收穫滿滿!📚✨ 感謝所有參與的學員與教練們, 因為你們的投入與努力, 讓這次課程充滿活力與意義💖! 接下來, 讓我們一起期待未來更多的健走推廣計畫, #共同邁向更健康更精彩的生活!🌏💪 #日式健走AdvanceCoach進階教練培訓課 #スマイルチーム#四季彩の杜#薬師池 #ポールウォーキング#紅葉#お弁当 #プラントベースのお弁当 ポールウォーキング12月は大人の遠足ポカポカ陽氣で氣もち良く楽しい遠足でした〜😘
#スマイルチーム#四季彩の杜#薬師池 #ポールウォーキング#紅葉#お弁当 #プラントベースのお弁当 ポールウォーキング12月は大人の遠足ポカポカ陽氣で氣もち良く楽しい遠足でした〜😘 12/6 渋谷PW教室3学期最終日 計測・ポールゲーム・お一人ずつモデルウォークでシメマシタ。全員の歩幅が、広がったのは素晴らしいです。 渋谷の街は少し寂しげ、クリスマス🎄🎅🎁✨の華やかさはショップのウィンドウのみ。夜になるとイルミネーションが綺麗なんでしょうね。あの幻想的な青の洞窟🟦とか。
12/6 渋谷PW教室3学期最終日 計測・ポールゲーム・お一人ずつモデルウォークでシメマシタ。全員の歩幅が、広がったのは素晴らしいです。 渋谷の街は少し寂しげ、クリスマス🎄🎅🎁✨の華やかさはショップのウィンドウのみ。夜になるとイルミネーションが綺麗なんでしょうね。あの幻想的な青の洞窟🟦とか。 2024.12.7 活動記録 活き活き中屋敷ライフ ポールウォーキング 10名 中屋敷中央公園集合 準備体操をして、境川沿いにウォーキング🐾本郷公園まで周りの景色を楽しみながら、今日の先導は89歳のゴローさん、しっかりしたウォーキングで交差点や横断歩道での確認、誘導までを行って下さいました。 公園ではみんなでおしゃべりタイム、自治会長から色々な情報もいただきました。帰路は親生会会長が先導、ゴローさんはしんがりで皆様を見守りながらのウォーキング。 帰路では珍しい青パパイヤの木にパパイヤもなっているし可愛らしいお花も咲いているのを見る事ができました。 中央公園にもどり整理体操と次回の連絡等、締めはゴローさんの『みなさん良いお年をね』で解散。 お天氣良く、氣温もウォーキングにちょうど良く、大変氣もちの良いウォーキングが出来ました😄 #ポールウォーキング #スマイルチーム #活き活き中屋敷ライフ
2024.12.7 活動記録 活き活き中屋敷ライフ ポールウォーキング 10名 中屋敷中央公園集合 準備体操をして、境川沿いにウォーキング🐾本郷公園まで周りの景色を楽しみながら、今日の先導は89歳のゴローさん、しっかりしたウォーキングで交差点や横断歩道での確認、誘導までを行って下さいました。 公園ではみんなでおしゃべりタイム、自治会長から色々な情報もいただきました。帰路は親生会会長が先導、ゴローさんはしんがりで皆様を見守りながらのウォーキング。 帰路では珍しい青パパイヤの木にパパイヤもなっているし可愛らしいお花も咲いているのを見る事ができました。 中央公園にもどり整理体操と次回の連絡等、締めはゴローさんの『みなさん良いお年をね』で解散。 お天氣良く、氣温もウォーキングにちょうど良く、大変氣もちの良いウォーキングが出来ました😄 #ポールウォーキング #スマイルチーム #活き活き中屋敷ライフ 【急がば回れ】 基本振り返りからの インターバルへ 2024/12 /7 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜日海老川ロード #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #インターバルウォーキング #トレーニング3原理5原則
【急がば回れ】 基本振り返りからの インターバルへ 2024/12 /7 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜日海老川ロード #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #インターバルウォーキング #トレーニング3原理5原則 感動~
感動~ 12月7日にスキルアップ研修会福岡会場を開催しました。 福岡の藤崎MCプロをメイン講師に、アットホームな感じのセミナーでした。 長崎の平山MCプロも参加して下さり、充実した内容になりました。 参加者同士の情報交換もでき、有意義なセミナーとなりました。
12月7日にスキルアップ研修会福岡会場を開催しました。 福岡の藤崎MCプロをメイン講師に、アットホームな感じのセミナーでした。 長崎の平山MCプロも参加して下さり、充実した内容になりました。 参加者同士の情報交換もでき、有意義なセミナーとなりました。 鎌倉ミステリーウォーキングvol.10 今回はアクティブ獅子舞谷コース。 12月2日(18名)と8日(25名) 2回の開催で鎌倉の紅葉🍁を楽しみながらたくさんの方に参加していただきました。 泥濘や丸太の橋を恐々と渡ったり… 銀杏の葉で黄色に染まった道を登りながら見上げると紅葉のグラデーション🍁とても綺麗でした。 そして楽しかったです。 ありがとうございました😊
鎌倉ミステリーウォーキングvol.10 今回はアクティブ獅子舞谷コース。 12月2日(18名)と8日(25名) 2回の開催で鎌倉の紅葉🍁を楽しみながらたくさんの方に参加していただきました。 泥濘や丸太の橋を恐々と渡ったり… 銀杏の葉で黄色に染まった道を登りながら見上げると紅葉のグラデーション🍁とても綺麗でした。 そして楽しかったです。 ありがとうございました😊 12/12 お昼前、一瞬でしたが小町通を歩いていたら 霙(みぞれ)のような粒が降りました。寒い筈ですね。 高齢者センターもクリスマスの飾りつけがされています。そしてどのPWサークルも忘年会の話で盛り上がっていますが、コロナや帯状疱疹にも気を付けなければ。
12/12 お昼前、一瞬でしたが小町通を歩いていたら 霙(みぞれ)のような粒が降りました。寒い筈ですね。 高齢者センターもクリスマスの飾りつけがされています。そしてどのPWサークルも忘年会の話で盛り上がっていますが、コロナや帯状疱疹にも気を付けなければ。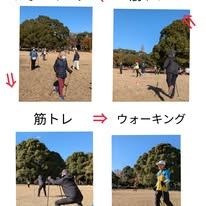 【寒さは何処に〜】 2024/12/12 ウォーキングとウォーキング の間に 色んな筋トレが次から次へと 入ります これが楽しい〜♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 #サーキットトレーニング #脂肪燃焼 #持久力UP #筋力UP
【寒さは何処に〜】 2024/12/12 ウォーキングとウォーキング の間に 色んな筋トレが次から次へと 入ります これが楽しい〜♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 #サーキットトレーニング #脂肪燃焼 #持久力UP #筋力UP 2024.12.13 活動記録 青空ポールウォーキング 9名 昨年包括支援センターでの事業で教室を行い、その後自主化し今年の1月から活動開始しました 私がコーチで一緒に行う日と、集まった仲間で自主練をする日の月2回の活動です 今日は私とアシスタントのMちゃんを除くと平均年齢80歳超えのハイシニアチームでした😆 楽しいが1番 集まって体操しておしゃべりして歩いて、お天気は少しどんよりでしたが 良く笑って皆さん明るい笑顔で帰っていかれました 楽しいと続けたくなるよね〜♡ #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #スマイルチーム #みかん狩り #地域包括支援センター
2024.12.13 活動記録 青空ポールウォーキング 9名 昨年包括支援センターでの事業で教室を行い、その後自主化し今年の1月から活動開始しました 私がコーチで一緒に行う日と、集まった仲間で自主練をする日の月2回の活動です 今日は私とアシスタントのMちゃんを除くと平均年齢80歳超えのハイシニアチームでした😆 楽しいが1番 集まって体操しておしゃべりして歩いて、お天気は少しどんよりでしたが 良く笑って皆さん明るい笑顔で帰っていかれました 楽しいと続けたくなるよね〜♡ #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #スマイルチーム #みかん狩り #地域包括支援センター 紅葉・黄葉ラストチャンス 12月の「気ままにポール歩き」は、地元コースでした。 善福寺川緑地・和田堀公園、大宮八幡宮、おおぞら公園、神田川遊歩道、塚山公園、柏の宮(かしのみや)公園 予報では昼頃でも気温12度で、おまけに風が強いということでしたが、快晴のひざしに当たりながら快適なウォーキングでした。 ウォーキングのあとは、おなじみ浜田山駅前のネパール料理店「まいた」でランチ忘年会を楽しみました。
紅葉・黄葉ラストチャンス 12月の「気ままにポール歩き」は、地元コースでした。 善福寺川緑地・和田堀公園、大宮八幡宮、おおぞら公園、神田川遊歩道、塚山公園、柏の宮(かしのみや)公園 予報では昼頃でも気温12度で、おまけに風が強いということでしたが、快晴のひざしに当たりながら快適なウォーキングでした。 ウォーキングのあとは、おなじみ浜田山駅前のネパール料理店「まいた」でランチ忘年会を楽しみました。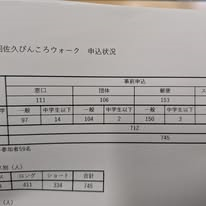 先週「ぴんころウォーク」の実行委員会が開かれ、9月実施の最終的な報告があった。参加人数745名(市内309名、市外201名、県外から235名)。多くの方に参加いただきました。ありがとうございました。「健康」×「観光」が融合したよい大会になってきたと思います。特にプルーン食べ放題が大きなフックになっています。 しかし大幅に人数が増えたことで課題も浮き彫りに。アンケートでは駐車場の問題、農道など細い道や草の問題、開会式のマイクが後ろまで聞こえていなかったなど。概ね好評でまた来たいという内容が大多数だが、実行委員長としてこれらの問題をできるだけ解決し、次回さらによい大会にしたいと思います。あとは収支の問題も大きい。これまでは元気づくり支援金を活用し収支がトントンの事業だったが、次回以降は支援金なしでしっかり黒字にしないといけない。とはいえ700名以上集まる「ぴんころウォーク」なので、まずはそこに魅力を感じてくれる地元企業から協賛を募っていきたい。これを見た経営者の皆さん宜しくお願い致します。応援してください(^.^)
先週「ぴんころウォーク」の実行委員会が開かれ、9月実施の最終的な報告があった。参加人数745名(市内309名、市外201名、県外から235名)。多くの方に参加いただきました。ありがとうございました。「健康」×「観光」が融合したよい大会になってきたと思います。特にプルーン食べ放題が大きなフックになっています。 しかし大幅に人数が増えたことで課題も浮き彫りに。アンケートでは駐車場の問題、農道など細い道や草の問題、開会式のマイクが後ろまで聞こえていなかったなど。概ね好評でまた来たいという内容が大多数だが、実行委員長としてこれらの問題をできるだけ解決し、次回さらによい大会にしたいと思います。あとは収支の問題も大きい。これまでは元気づくり支援金を活用し収支がトントンの事業だったが、次回以降は支援金なしでしっかり黒字にしないといけない。とはいえ700名以上集まる「ぴんころウォーク」なので、まずはそこに魅力を感じてくれる地元企業から協賛を募っていきたい。これを見た経営者の皆さん宜しくお願い致します。応援してください(^.^) #シニアポールウォーキング 2024/12/16 社会性は満点のメンバーです #転倒 #認知症予防 その二つに絞って 講堂内をフル活用 最期に一言スピーチ テーマは 「今年の自分を褒めてあげましょう」 皆さん、ニコニコしながら話します メンバーは今年も 充実した生活だったようです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #法典公民館
#シニアポールウォーキング 2024/12/16 社会性は満点のメンバーです #転倒 #認知症予防 その二つに絞って 講堂内をフル活用 最期に一言スピーチ テーマは 「今年の自分を褒めてあげましょう」 皆さん、ニコニコしながら話します メンバーは今年も 充実した生活だったようです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #法典公民館 12/16 本日は渋谷。 友達とブツの受け渡し+お茶 そして、渋谷区役所で年に1度の渋谷介護事業の横繋がりの MTGがありました。社協、包括支援、健康はつらつ事業、元気すこやか事業その他充実したフレイル予防等プログラムの各担当など合同のミィーティングで大変有意義な意見交換会でした。大田区もポール事業では1歩大きく進展していますが、文系・運動系両方をここまで進めているのは都内で唯一の充実活動だと思います。渋谷区民は幸せです☘️ これからzoomです。(スマホばかり使ってPCを放置していたので動かなくなってしまいました😢 仕方なくスマホで参加)
12/16 本日は渋谷。 友達とブツの受け渡し+お茶 そして、渋谷区役所で年に1度の渋谷介護事業の横繋がりの MTGがありました。社協、包括支援、健康はつらつ事業、元気すこやか事業その他充実したフレイル予防等プログラムの各担当など合同のミィーティングで大変有意義な意見交換会でした。大田区もポール事業では1歩大きく進展していますが、文系・運動系両方をここまで進めているのは都内で唯一の充実活動だと思います。渋谷区民は幸せです☘️ これからzoomです。(スマホばかり使ってPCを放置していたので動かなくなってしまいました😢 仕方なくスマホで参加) 2024年、年忘れウォーキング。
2024年、年忘れウォーキング。 12/17 青い空 風もなく暖かい冬の朝 広町緑地で輪になってストレッチ・筋トレを済ませ、今日は忘年会✨🍹🎶 at homeな腰越サークルはもう何年目になりますか。継続のコツは「楽しい」こと。お花見🌸会や忘年会も交流を深めます。20名のメンバーのうちスマホを使わないお一人(電話連絡)以外はLINEで繋がりました。
12/17 青い空 風もなく暖かい冬の朝 広町緑地で輪になってストレッチ・筋トレを済ませ、今日は忘年会✨🍹🎶 at homeな腰越サークルはもう何年目になりますか。継続のコツは「楽しい」こと。お花見🌸会や忘年会も交流を深めます。20名のメンバーのうちスマホを使わないお一人(電話連絡)以外はLINEで繋がりました。 昨日の様子です #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング 2024/12/17 #行田公園イベント広場で #サーキットトレーニング 程よい高さの石垣で #腕立て伏せ #ボート漕ぎで腹筋 バラエティに富んだ筋トレが 出来ます 全天候型舗装になったので ウォーキングも思い切り 歩けるようになりました〜 目線は前に 中々良い調子です がっちりトレーニング 程々トレーニング 皆、自分の良い加減でね ♫
昨日の様子です #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング 2024/12/17 #行田公園イベント広場で #サーキットトレーニング 程よい高さの石垣で #腕立て伏せ #ボート漕ぎで腹筋 バラエティに富んだ筋トレが 出来ます 全天候型舗装になったので ウォーキングも思い切り 歩けるようになりました〜 目線は前に 中々良い調子です がっちりトレーニング 程々トレーニング 皆、自分の良い加減でね ♫ ポールウォーキングを始める動機は人それぞれ。同級会で同い年の歩きを見て、年寄りくさくて驚いたというFさんの変化ご覧ください。 #ポールウォーキング #ウォーキング #笠間市 #地域交流センターともべ
ポールウォーキングを始める動機は人それぞれ。同級会で同い年の歩きを見て、年寄りくさくて驚いたというFさんの変化ご覧ください。 #ポールウォーキング #ウォーキング #笠間市 #地域交流センターともべ 【根気よく身体に覚え込ませる】 2824/12/21 しっくり落ちるのは どの表現 ポールを使って歩くウォーキング 本日も感覚を身体に染み込ませます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク
【根気よく身体に覚え込ませる】 2824/12/21 しっくり落ちるのは どの表現 ポールを使って歩くウォーキング 本日も感覚を身体に染み込ませます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク みなとみらいわくわくポールウォーキング ステッキ工房の店長さんのご紹介で変形性膝関節症の方、腰痛の方が初めて体験にいらしてくれました。 歩き始めは痛そうで心配しましたがポールに慣れてくると、 「ポールがあると楽に歩けます」 「腰痛が楽になりました」と。 ポールの効果はお2人を笑顔にしてくれました♪良かった! 今年始めたM Mわくわくポールウォーキングはシナノ ステッキ工房さんのご協力もあり多くの方に参加いただきました。 また来年、楽しく歩きましょう。 次回は1月10日(金)です😊 #みなとみらい #ステッキ工房 #わくわくポールウォーキング #楽しい仲間たち #アメリカンポーク試食会
みなとみらいわくわくポールウォーキング ステッキ工房の店長さんのご紹介で変形性膝関節症の方、腰痛の方が初めて体験にいらしてくれました。 歩き始めは痛そうで心配しましたがポールに慣れてくると、 「ポールがあると楽に歩けます」 「腰痛が楽になりました」と。 ポールの効果はお2人を笑顔にしてくれました♪良かった! 今年始めたM Mわくわくポールウォーキングはシナノ ステッキ工房さんのご協力もあり多くの方に参加いただきました。 また来年、楽しく歩きましょう。 次回は1月10日(金)です😊 #みなとみらい #ステッキ工房 #わくわくポールウォーキング #楽しい仲間たち #アメリカンポーク試食会 夕暮れ時の八丁堀~隅田川畔~小網町~人形町あたりの雰囲気を満喫 杉並ポール歩きの会(2023年休止)で講師としてお世話になってきた藤井直子さん(ポルク主宰)が企画された“ポール遠足”に参加しました。(2024/12/21) 江戸情緒の残る界隈をキョロキョロしながらノルディックウォーキング。クールダウンのあとは、人形町の名前から想像しなかった「生ハムとワインの店」で忘年会でした。 年のしめくくりのハッピーウォーキング。藤井さんと忘年会企画でお世話になった木村研一さんに感謝です。 ※当初、藤井さんのお立場を間違って書いていたので修正しました。(12/23)
夕暮れ時の八丁堀~隅田川畔~小網町~人形町あたりの雰囲気を満喫 杉並ポール歩きの会(2023年休止)で講師としてお世話になってきた藤井直子さん(ポルク主宰)が企画された“ポール遠足”に参加しました。(2024/12/21) 江戸情緒の残る界隈をキョロキョロしながらノルディックウォーキング。クールダウンのあとは、人形町の名前から想像しなかった「生ハムとワインの店」で忘年会でした。 年のしめくくりのハッピーウォーキング。藤井さんと忘年会企画でお世話になった木村研一さんに感謝です。 ※当初、藤井さんのお立場を間違って書いていたので修正しました。(12/23) 12/22 午前中は逗子で PW教室(年内歩き納め)① 午後は葉山の🥑ファームで冬支度。
12/22 午前中は逗子で PW教室(年内歩き納め)① 午後は葉山の🥑ファームで冬支度。 【2024健走杖輕旅行 宜蘭冬山站】活動圓滿結束! 🌿🚶♂️🚶♀️ 在宜蘭的冬山美景中, 一場健康活力的健走杖輕旅行順利完成!🌞💪 夥伴們在清新空氣與自然美景的陪伴下, 一邊健走,一邊享受身心舒暢的美好時光。🍃🏞️ 感謝所有參與的朋友們熱情投入, 讓活動增添了滿滿的活力與歡笑聲!😄👏 還有協會教練們的專業帶領, 讓大家體驗到了健走杖運動的多重益處,既健康又有趣!✨🎯 期待下次的健走旅程,與大家再次相見, 共同走出健康新里程!🚶♀️🚶♂️🌟 #雷公農園 #健走杖輕旅行宜蘭冬山站 #台灣健走杖運動推廣協會
【2024健走杖輕旅行 宜蘭冬山站】活動圓滿結束! 🌿🚶♂️🚶♀️ 在宜蘭的冬山美景中, 一場健康活力的健走杖輕旅行順利完成!🌞💪 夥伴們在清新空氣與自然美景的陪伴下, 一邊健走,一邊享受身心舒暢的美好時光。🍃🏞️ 感謝所有參與的朋友們熱情投入, 讓活動增添了滿滿的活力與歡笑聲!😄👏 還有協會教練們的專業帶領, 讓大家體驗到了健走杖運動的多重益處,既健康又有趣!✨🎯 期待下次的健走旅程,與大家再次相見, 共同走出健康新里程!🚶♀️🚶♂️🌟 #雷公農園 #健走杖輕旅行宜蘭冬山站 #台灣健走杖運動推廣協會 佐久ポールウォーキング協会より 〜eveの日〜❗️ 佐久大学看護学部/1年生のPW実習報告会がありました。 毎年1年生がポールウォーキングをし参加者とふれあい佐久地域と皆さんの健康的な生き方の調査?が目的です。 コロナ時に始まり4年目で、その時体験した4年生も参加し新旧入り混じった和やかな報告会でした。 生徒の皆さん〜 同席したコーチの皆んな〜 お疲れ様でした。 〜Have a fun eve〜❣️
佐久ポールウォーキング協会より 〜eveの日〜❗️ 佐久大学看護学部/1年生のPW実習報告会がありました。 毎年1年生がポールウォーキングをし参加者とふれあい佐久地域と皆さんの健康的な生き方の調査?が目的です。 コロナ時に始まり4年目で、その時体験した4年生も参加し新旧入り混じった和やかな報告会でした。 生徒の皆さん〜 同席したコーチの皆んな〜 お疲れ様でした。 〜Have a fun eve〜❣️ #2024年歩き納め #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 暖かで軽やかに2024年を締めくくり 皆で集まるから元気になっちゃうね〜 そんなこんなの1年間 小さな元気の積み重ねが嬉しいね みんな今年も ありがとう〜
#2024年歩き納め #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 暖かで軽やかに2024年を締めくくり 皆で集まるから元気になっちゃうね〜 そんなこんなの1年間 小さな元気の積み重ねが嬉しいね みんな今年も ありがとう〜 志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会(埼玉県 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所グランドテラス)
志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会(埼玉県 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所グランドテラス) 家の中や家の周りで、つまずいたり滑ったりして転びそうになったことはありませんか。年を重ねるにつれて転びやすくなり、骨折などのけがをしやすくなります。特に65歳以上の高齢者は要注意です。骨折がきっかけで寝たきりになってしまうことも。転倒事故が起こりやすい家の中や周囲の危険な箇所をチェックしながら、事故を防ぐための注意点を紹介します。
家の中や家の周りで、つまずいたり滑ったりして転びそうになったことはありませんか。年を重ねるにつれて転びやすくなり、骨折などのけがをしやすくなります。特に65歳以上の高齢者は要注意です。骨折がきっかけで寝たきりになってしまうことも。転倒事故が起こりやすい家の中や周囲の危険な箇所をチェックしながら、事故を防ぐための注意点を紹介します。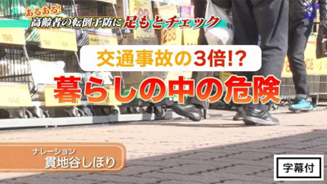 年齢と共に増える、暮らしの中の危険。簡単にできる「足もとチェック」で転倒事故を防ぎましょう。【字幕付】ナレーション:貫地谷しほり
年齢と共に増える、暮らしの中の危険。簡単にできる「足もとチェック」で転倒事故を防ぎましょう。【字幕付】ナレーション:貫地谷しほり 加齢に伴い身体機能が徐々に低下し、筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰え、とっさの反射的防御動作が、素早く力強く行えなくなります。また、自分自身の予測・期待する動作と現実の動作との間に齟齬が生まれて転倒を引き起こすことがあります。
加齢に伴い身体機能が徐々に低下し、筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰え、とっさの反射的防御動作が、素早く力強く行えなくなります。また、自分自身の予測・期待する動作と現実の動作との間に齟齬が生まれて転倒を引き起こすことがあります。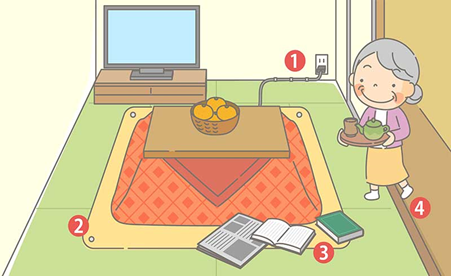 1. コードの配線は歩く動線を避ける。壁をはわせるか、部屋の奥にまとめる
1. コードの配線は歩く動線を避ける。壁をはわせるか、部屋の奥にまとめる 1. 手すりをつける
1. 手すりをつける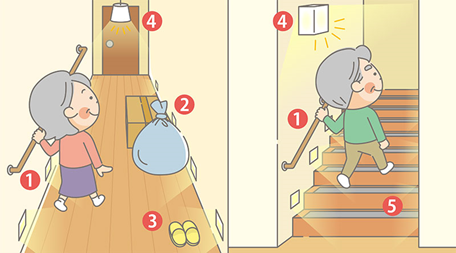 1. 手すりをつける
1. 手すりをつける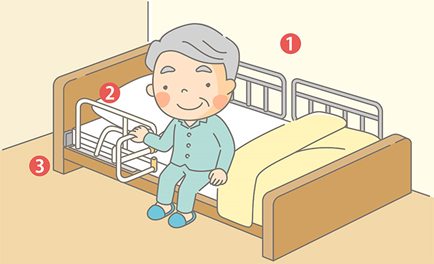 1. ベッドを壁に面するように配置し片方からの転落リスクをなくす
1. ベッドを壁に面するように配置し片方からの転落リスクをなくす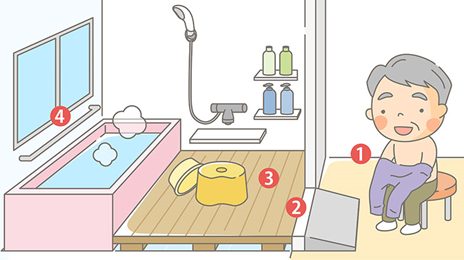 1. 椅子に座って着替える
1. 椅子に座って着替える • 床の水濡れで転倒(雨やケースからの水たれ)
• 床の水濡れで転倒(雨やケースからの水たれ)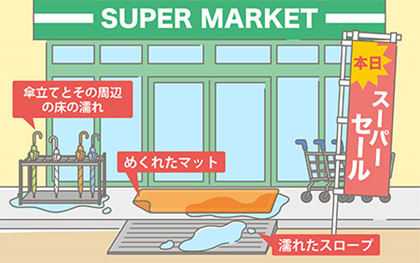 • 床の水濡れで転倒(雨など)
• 床の水濡れで転倒(雨など)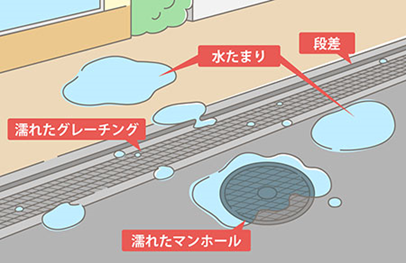 • 濡れた道路(雨など)で転倒
• 濡れた道路(雨など)で転倒 • 車止めにつまずく
• 車止めにつまずく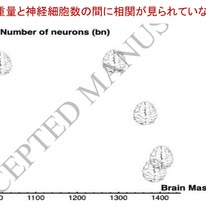 ヒトの脳のニューロン(神経細胞)数は「860億」と広く知られています(図3).しかしこの数値が科学的にどれほど正確なのか疑問を投げかける興味深いエッセイがBrain誌に発表されました.このエッセイの著者はオックスフォード大学の数学者Alain Goriely教授です.Goriely教授は,科学におけるデータの扱い方に厳密さを求める立場から,この「860億」という数字の根拠を詳細に検討しています.
ヒトの脳のニューロン(神経細胞)数は「860億」と広く知られています(図3).しかしこの数値が科学的にどれほど正確なのか疑問を投げかける興味深いエッセイがBrain誌に発表されました.このエッセイの著者はオックスフォード大学の数学者Alain Goriely教授です.Goriely教授は,科学におけるデータの扱い方に厳密さを求める立場から,この「860億」という数字の根拠を詳細に検討しています.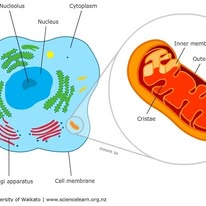 ミトコンドリアはパーキンソン病,脳卒中,認知症や老化など様々な病態において重要な役割を果たしています.動画はコロンビア大学のMartin Picard先生(@MitoPsychoBio)がSNSに投稿した,1つの細胞内のミトコンドリアを示したものです(オリジナルは@chillinwithpfn1).何百もの曲がりくねった細胞内小器官がエネルギーと情報を感知し,処理し,信号を送っています.初めてミトコンドリアの真の姿を示した動画を見たときには感動しましたし,教科書とのあまりの違いに驚きました.科学にはこういうことがまだまだたくさんあるのだろうと思います.
ミトコンドリアはパーキンソン病,脳卒中,認知症や老化など様々な病態において重要な役割を果たしています.動画はコロンビア大学のMartin Picard先生(@MitoPsychoBio)がSNSに投稿した,1つの細胞内のミトコンドリアを示したものです(オリジナルは@chillinwithpfn1).何百もの曲がりくねった細胞内小器官がエネルギーと情報を感知し,処理し,信号を送っています.初めてミトコンドリアの真の姿を示した動画を見たときには感動しましたし,教科書とのあまりの違いに驚きました.科学にはこういうことがまだまだたくさんあるのだろうと思います.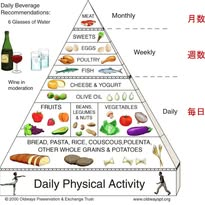 アメリカのハーバード大学を中心とする研究チームによる大規模なコホート研究が,JAMA Network Open誌に掲載されています.この研究では,認知症予防に有効らしいとされてきた地中海式食事(野菜や果物,全粒雑穀類,豆類,オリーブオイル,適量のワイン等;図1)のなかでオリーブオイルに着目し,米国成人において認知症予防に有効かを検討しています.具体的にはオリーブオイル摂取量が,認知症関連の死亡リスクを減少させるかを調べています.またマーガリンやマヨネーズ,バター,植物油といった他の脂質をオリーブオイルに置き換えることで,死亡リスクに変化が生じるかも評価しています.
アメリカのハーバード大学を中心とする研究チームによる大規模なコホート研究が,JAMA Network Open誌に掲載されています.この研究では,認知症予防に有効らしいとされてきた地中海式食事(野菜や果物,全粒雑穀類,豆類,オリーブオイル,適量のワイン等;図1)のなかでオリーブオイルに着目し,米国成人において認知症予防に有効かを検討しています.具体的にはオリーブオイル摂取量が,認知症関連の死亡リスクを減少させるかを調べています.またマーガリンやマヨネーズ,バター,植物油といった他の脂質をオリーブオイルに置き換えることで,死亡リスクに変化が生じるかも評価しています.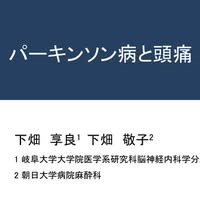 第52回頭痛学会総会(大会長 永田栄一郎先生)において,シンポジウム「片頭痛と神経疾患」のなかで,「パーキンソン病と頭痛」という講演をさせていただきました.8年前の頭痛学会で,同じテーマでシンポジストを担当し,歯が立たなかった内容ですが,今回,再挑戦の機会をいただきました.①片頭痛患者さんがパーキンソン病を発症すると片頭痛が改善する理由,②ドパミン作動薬が一部のパーキンソン病患者の片頭痛を改善する理由.③片頭痛がパーキンソン病の危険因子である理由,について考察しました.スライドは以下よりご覧いただけます.座長の立花久大先生,松浦徹先生,どうもありがとうございました.
第52回頭痛学会総会(大会長 永田栄一郎先生)において,シンポジウム「片頭痛と神経疾患」のなかで,「パーキンソン病と頭痛」という講演をさせていただきました.8年前の頭痛学会で,同じテーマでシンポジストを担当し,歯が立たなかった内容ですが,今回,再挑戦の機会をいただきました.①片頭痛患者さんがパーキンソン病を発症すると片頭痛が改善する理由,②ドパミン作動薬が一部のパーキンソン病患者の片頭痛を改善する理由.③片頭痛がパーキンソン病の危険因子である理由,について考察しました.スライドは以下よりご覧いただけます.座長の立花久大先生,松浦徹先生,どうもありがとうございました. 取材をいただき,新型コロナ感染症による神経後遺症について,最新の知見を分かりやすく記事にしていただきました.ワクチン接種についてはいろいろな考え方があって良いと思いますが,まず判明している科学的な事実を知って頂くことが大切だと思います.
取材をいただき,新型コロナ感染症による神経後遺症について,最新の知見を分かりやすく記事にしていただきました.ワクチン接種についてはいろいろな考え方があって良いと思いますが,まず判明している科学的な事実を知って頂くことが大切だと思います.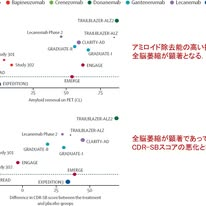 アルツハイマー病では,脳の萎縮(=体積の減少)が病態の進行を示す重要な指標とされてきました.しかし,アミロイドβを除去するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブなど)の臨床試験では,治療群において脳体積が対照群よりも速く減少するという「矛盾した」結果が報告されています.過去のブログでも紹介しました(https://tinyurl.com/2bzfv7wq).
アルツハイマー病では,脳の萎縮(=体積の減少)が病態の進行を示す重要な指標とされてきました.しかし,アミロイドβを除去するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブなど)の臨床試験では,治療群において脳体積が対照群よりも速く減少するという「矛盾した」結果が報告されています.過去のブログでも紹介しました(https://tinyurl.com/2bzfv7wq).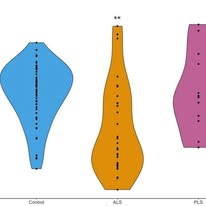 筋萎縮性側索硬化症(ALS)と原発性側索硬化症(PLS)におけるglymphatic systemの機能を縦断的に評価した研究が,カナダ・カルガリー大学等からBrain誌に報告されました.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)と原発性側索硬化症(PLS)におけるglymphatic systemの機能を縦断的に評価した研究が,カナダ・カルガリー大学等からBrain誌に報告されました.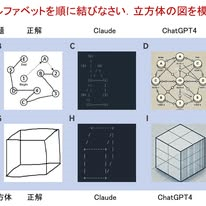 世界五大医学誌の一つBMJ誌は,毎年,クリスマスの時期になるとイグノーベル賞を凌駕するような面白論文の特集号を公開します.今年の原著論文は4つで,変形性手関節症患者の手指機能に対する電気加熱ミトンの効果を調べた論文や,タクシー運転手と救急車運転手におけるアルツハイマー病による死亡率を分析した論文などが報告されていますが,個人的に面白かったのは,今年急速に広まった大規模言語モデルであるChatGPT(OpenAI開発),Claude(Anthropic開発),そしてGemini(Alphabet開発)の「認知機能」を人間と同じようにテストした研究です.エルサレムにあるハダサ医療センターの脳神経内科チームが中心に行ったものです.
世界五大医学誌の一つBMJ誌は,毎年,クリスマスの時期になるとイグノーベル賞を凌駕するような面白論文の特集号を公開します.今年の原著論文は4つで,変形性手関節症患者の手指機能に対する電気加熱ミトンの効果を調べた論文や,タクシー運転手と救急車運転手におけるアルツハイマー病による死亡率を分析した論文などが報告されていますが,個人的に面白かったのは,今年急速に広まった大規模言語モデルであるChatGPT(OpenAI開発),Claude(Anthropic開発),そしてGemini(Alphabet開発)の「認知機能」を人間と同じようにテストした研究です.エルサレムにあるハダサ医療センターの脳神経内科チームが中心に行ったものです. 【イベント広場が全天候型舗装】 2024/10/1 奇麗になったイベント広場 早速歩きました 枯れ葉🍂 黄花コスモス いい季節 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #笑顔全開 #動画撮影 #呼吸筋活性化ウォーキング #健康効果アップウォーキング
【イベント広場が全天候型舗装】 2024/10/1 奇麗になったイベント広場 早速歩きました 枯れ葉🍂 黄花コスモス いい季節 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #笑顔全開 #動画撮影 #呼吸筋活性化ウォーキング #健康効果アップウォーキング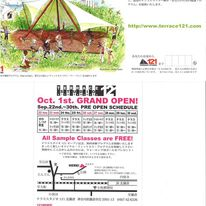 北鎌倉テラススタジオ ㊗15年 今日はまた夏の暑さが戻ってきましたが テラスは風が心地よく みんなで床にごろんと転がってコアトレ等々楽しみました。鳩の鳴き声に梟みたいね、とワイワイガヤガヤ。 町内の皆さんのジモト話が楽しいです。当初からの仲間がいなくなりちょっと寂しさを感じる今日この頃。 杉浦コーチは15年変わらぬおやじギャグです。
北鎌倉テラススタジオ ㊗15年 今日はまた夏の暑さが戻ってきましたが テラスは風が心地よく みんなで床にごろんと転がってコアトレ等々楽しみました。鳩の鳴き声に梟みたいね、とワイワイガヤガヤ。 町内の皆さんのジモト話が楽しいです。当初からの仲間がいなくなりちょっと寂しさを感じる今日この頃。 杉浦コーチは15年変わらぬおやじギャグです。 10/2.3の2日間、一関市、奥州市、平泉町、金ヶ崎町の保健師さんを対象にした講義&実技を担当させていただきました! 健康づくりのプロが対象ですから、プレッシャーもありましたが、顔見知りの保健師さんが多く、とても和やかに展開できたのがありがたかったです。 日々の保健指導に繋がれば嬉しく思います😌
10/2.3の2日間、一関市、奥州市、平泉町、金ヶ崎町の保健師さんを対象にした講義&実技を担当させていただきました! 健康づくりのプロが対象ですから、プレッシャーもありましたが、顔見知りの保健師さんが多く、とても和やかに展開できたのがありがたかったです。 日々の保健指導に繋がれば嬉しく思います😌 「大穴総合スポーツクラブ健康教室」 〜ポールウォーキング講習会〜 2024/10/3 普段から良く運動されている方々からお呼ばれして行ってきました。 「ポールは年をとってから使うだけ じゃ無かった。ただ歩くのと全然違う〜」 「ポールって凄いんですね」 「大穴近隣公園」はスロープも有り 変化に富んだメニューで歩きました。 運動し慣れている人もびっくりの 運動効果! ポールに対する思い込みを払しょく! 今後は積極的に取り組んで頂けそうです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #大穴総合スポーツクラブ
「大穴総合スポーツクラブ健康教室」 〜ポールウォーキング講習会〜 2024/10/3 普段から良く運動されている方々からお呼ばれして行ってきました。 「ポールは年をとってから使うだけ じゃ無かった。ただ歩くのと全然違う〜」 「ポールって凄いんですね」 「大穴近隣公園」はスロープも有り 変化に富んだメニューで歩きました。 運動し慣れている人もびっくりの 運動効果! ポールに対する思い込みを払しょく! 今後は積極的に取り組んで頂けそうです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #大穴総合スポーツクラブ 今朝は渋谷区の介護予防事業の一環 PW教室 秋の新学期開講でした。 夕べの豪雨で道路はまだ濡れて歩き難かったですが、こんな時2本のポールがあれば滑らず安心して歩けます。 新しいメンバーさんは体力測定の片足立ちで60秒を越しても微動だにせずストップと声をかけるまで悠々と続けるかたがあれば 3秒キープも難しい方まで。 体力の違う方々の一斉指導の良さは上手は下手の手本下手は上手の手本。
今朝は渋谷区の介護予防事業の一環 PW教室 秋の新学期開講でした。 夕べの豪雨で道路はまだ濡れて歩き難かったですが、こんな時2本のポールがあれば滑らず安心して歩けます。 新しいメンバーさんは体力測定の片足立ちで60秒を越しても微動だにせずストップと声をかけるまで悠々と続けるかたがあれば 3秒キープも難しい方まで。 体力の違う方々の一斉指導の良さは上手は下手の手本下手は上手の手本。 郡山でもポールウォーキング広まっています💕 地域の観光案内ににポールウォーキングで歩きます。 ナイスアイデア👍 私も11月11日、郡山を歩きます🚶
郡山でもポールウォーキング広まっています💕 地域の観光案内ににポールウォーキングで歩きます。 ナイスアイデア👍 私も11月11日、郡山を歩きます🚶 みなとみらいわくわくPWの朝、急に風が吹いたと思ったら嵐のような横なぐりの雨にビックリ🫢 それでも大丈夫!絶対晴れる!と信じて雨が止んだ合間に出かける。 そして誰も休むことなく全員集合🤗初PW体験者も4名。 突然の雨の場合はビルに退避出来るところを選んで臨海パーク方面へ。 なーんと暑いくらいに晴れて☀️汗びっしょり!みんなで歩くと楽しい充実した時間。 次回は11月15日(金) 12月20日(金) #みなとみらい地区を歩こう #わくわくポールウォーキング #ステッキ工房
みなとみらいわくわくPWの朝、急に風が吹いたと思ったら嵐のような横なぐりの雨にビックリ🫢 それでも大丈夫!絶対晴れる!と信じて雨が止んだ合間に出かける。 そして誰も休むことなく全員集合🤗初PW体験者も4名。 突然の雨の場合はビルに退避出来るところを選んで臨海パーク方面へ。 なーんと暑いくらいに晴れて☀️汗びっしょり!みんなで歩くと楽しい充実した時間。 次回は11月15日(金) 12月20日(金) #みなとみらい地区を歩こう #わくわくポールウォーキング #ステッキ工房 佐久ポールウォーキング協会より PW三昧の1日(歩きました)ww 午前は教育委員会主催/PW教室で臼田/五稜郭(龍岡城)〜蕃松院〜新海3社神社〜上宮寺〜五稜郭約4kmの田舎原風景散策。タワワに実る柿が旨そうでした。 午後は56回ぞっこんさく市(いち)開催中/駒場公園に戻り出展ブースでPW体験会へ❗️ブース内ではウォーキング用ポールの販売も。 早朝からの雨も止み昨年に増して入り客の多さに驚いた初日でした。 明日は当協会駒場例会9時〜10時半も開催です さく市は最終日で〜15:30までですのでお越しください〜^_^
佐久ポールウォーキング協会より PW三昧の1日(歩きました)ww 午前は教育委員会主催/PW教室で臼田/五稜郭(龍岡城)〜蕃松院〜新海3社神社〜上宮寺〜五稜郭約4kmの田舎原風景散策。タワワに実る柿が旨そうでした。 午後は56回ぞっこんさく市(いち)開催中/駒場公園に戻り出展ブースでPW体験会へ❗️ブース内ではウォーキング用ポールの販売も。 早朝からの雨も止み昨年に増して入り客の多さに驚いた初日でした。 明日は当協会駒場例会9時〜10時半も開催です さく市は最終日で〜15:30までですのでお越しください〜^_^ 一昨日 講習会を開催して下さった 「大穴総合スポーツクラブ」の役員さんから写真が送られてきました 歴史と経験が深い団体様から呼んで頂き大変光栄に思います 役員さんの謙虚さと誠実さ 見習いたいと思います 大穴総合スポーツクラブ健康教室の皆様は明るく元気! 又 一緒に歩きたいです #大穴総合スポーツクラブ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #大穴近隣公園
一昨日 講習会を開催して下さった 「大穴総合スポーツクラブ」の役員さんから写真が送られてきました 歴史と経験が深い団体様から呼んで頂き大変光栄に思います 役員さんの謙虚さと誠実さ 見習いたいと思います 大穴総合スポーツクラブ健康教室の皆様は明るく元気! 又 一緒に歩きたいです #大穴総合スポーツクラブ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #大穴近隣公園 佐久ポールウォーキング協会より PW駒場例会〜ww イベントで賑やかの中60名越えの集まりでした。遠く諏訪市からPWを広げたく学びに参加頂けたご夫婦や、佐久大学生1年と4年生/15名も実習で駆け付けてくれました。 来週は女神湖PW散策です〜ww 午後はイベント〜ぞっこん!さく市〜ブースに戻ってPWの案内と体験会開催でした。 2日間ご来場の会員や皆さん〜お疲れ〜でした❗️
佐久ポールウォーキング協会より PW駒場例会〜ww イベントで賑やかの中60名越えの集まりでした。遠く諏訪市からPWを広げたく学びに参加頂けたご夫婦や、佐久大学生1年と4年生/15名も実習で駆け付けてくれました。 来週は女神湖PW散策です〜ww 午後はイベント〜ぞっこん!さく市〜ブースに戻ってPWの案内と体験会開催でした。 2日間ご来場の会員や皆さん〜お疲れ〜でした❗️ 第4回ポールdeウォーク活動交流集会in会津若松! 記念講演は杉浦さん‼️ 流石の楽しく、充実した納得の講演でした‼️ お疲れ様でした‼️
第4回ポールdeウォーク活動交流集会in会津若松! 記念講演は杉浦さん‼️ 流石の楽しく、充実した納得の講演でした‼️ お疲れ様でした‼️ 今日は、福島県会津若松市へ!「ポールdeウォークの魅力を語る」で登壇させてもらいました! さらには、久々のリアル杉浦さんの講義。おやじギャグを炸裂させながらも、健康づくりにとっても大切なことを心に刺さる言葉でシンプルに伝えているスゴさ!やっぱり痺れました!! ポールウォーキング協会&シナノの水間さんとも久々にお会いし情報交換でき、有意義な時間を過ごすことができました! さぁ明日は、鶴ヶ城をみんなで歩きます♪
今日は、福島県会津若松市へ!「ポールdeウォークの魅力を語る」で登壇させてもらいました! さらには、久々のリアル杉浦さんの講義。おやじギャグを炸裂させながらも、健康づくりにとっても大切なことを心に刺さる言葉でシンプルに伝えているスゴさ!やっぱり痺れました!! ポールウォーキング協会&シナノの水間さんとも久々にお会いし情報交換でき、有意義な時間を過ごすことができました! さぁ明日は、鶴ヶ城をみんなで歩きます♪ 今日は、鶴ヶ城ポールdeウォーク! 杉浦さんのウォームアップからスタート!会津の鈴木さんが説明しながら歩いてくれました!ポールとノルディックの両方を体験。 心地良い汗をかきながら、いろんな人とコミュニケーションも取れ、会津の歴史も学べた贅沢な1日となりました♪
今日は、鶴ヶ城ポールdeウォーク! 杉浦さんのウォームアップからスタート!会津の鈴木さんが説明しながら歩いてくれました!ポールとノルディックの両方を体験。 心地良い汗をかきながら、いろんな人とコミュニケーションも取れ、会津の歴史も学べた贅沢な1日となりました♪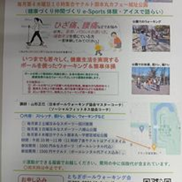 ポールウォーキング体験・定例会参加者募集 毎月第2土曜日10時集合みなスポーツ~田川散策 毎月第3日曜日10時集合みなスポーツ~八幡山 毎月第4木曜日10時集合ヤクルト御本丸カフェ~城址公園 《健康づくり仲間づくりe-Sports体験・アイスで語らい》
ポールウォーキング体験・定例会参加者募集 毎月第2土曜日10時集合みなスポーツ~田川散策 毎月第3日曜日10時集合みなスポーツ~八幡山 毎月第4木曜日10時集合ヤクルト御本丸カフェ~城址公園 《健康づくり仲間づくりe-Sports体験・アイスで語らい》 ここのところポールウォーキング三昧の週末を過ごしています。土曜日はぞっこん!さく市というイベントでポールウォーキング体験を担当していたところ、「最近学校で運動不足だからやってみたい!」という小学生が😄 ちょっとだけポイントを教えたら、歩く、歩く、早いし、しっかり地面を踏めてるし、上手い❗️待って〜〜💦 実は最近、小学生の歩き方が気になり始めていたところ。こんなに楽しく全身でポールを使ってもらえると、子どもとポールウォーキングで何かできないかなー、なんて想像がふくらみます。
ここのところポールウォーキング三昧の週末を過ごしています。土曜日はぞっこん!さく市というイベントでポールウォーキング体験を担当していたところ、「最近学校で運動不足だからやってみたい!」という小学生が😄 ちょっとだけポイントを教えたら、歩く、歩く、早いし、しっかり地面を踏めてるし、上手い❗️待って〜〜💦 実は最近、小学生の歩き方が気になり始めていたところ。こんなに楽しく全身でポールを使ってもらえると、子どもとポールウォーキングで何かできないかなー、なんて想像がふくらみます。 ポールウォーク三昧の癒しのひと時❗️ ヴィラデストワイナリー/玉村さんちでティタイム〜ww ワインや雑貨の買い物も〜❗️
ポールウォーク三昧の癒しのひと時❗️ ヴィラデストワイナリー/玉村さんちでティタイム〜ww ワインや雑貨の買い物も〜❗️ 📢 2024年10月6日 【日式健走Basic Coach 培訓課程】圓滿結束!🎉 🇯🇵 日本健走杖協會NPWA唯一授權海外開課 🏆 🎉感謝大家的熱情參與, 也恭喜這次17位學員成功完成課程!🎓👏 這次培訓課程是NPWA唯一授權海外開設的健走課程,意義非凡! 課程內容涵蓋了日式健走杖的基本技巧、姿勢調整、步伐訓練等多方面知識, 讓每一位學員不僅學會了健走杖運動的精髓, 也進一步提升了個人的健走技能。💪🚶♂️🚶♀️ 🌟 期待未來更多挑戰, 接下來,協會即將開啟的進階課程 AC教練培訓課程, 將為BC教練們提供更深入的專業訓練, 敬請期待,讓我們一起向更高的目標邁進!🚀💯 讓我們一起 #共同推廣這項健康有益的運動 💖
📢 2024年10月6日 【日式健走Basic Coach 培訓課程】圓滿結束!🎉 🇯🇵 日本健走杖協會NPWA唯一授權海外開課 🏆 🎉感謝大家的熱情參與, 也恭喜這次17位學員成功完成課程!🎓👏 這次培訓課程是NPWA唯一授權海外開設的健走課程,意義非凡! 課程內容涵蓋了日式健走杖的基本技巧、姿勢調整、步伐訓練等多方面知識, 讓每一位學員不僅學會了健走杖運動的精髓, 也進一步提升了個人的健走技能。💪🚶♂️🚶♀️ 🌟 期待未來更多挑戰, 接下來,協會即將開啟的進階課程 AC教練培訓課程, 將為BC教練們提供更深入的專業訓練, 敬請期待,讓我們一起向更高的目標邁進!🚀💯 讓我們一起 #共同推廣這項健康有益的運動 💖 2024年【日式健走Basic Coach 培訓課程】
2024年【日式健走Basic Coach 培訓課程】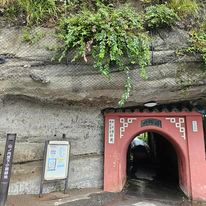 一昨日は夏日だったのに風向きが変わり昨日から急に寒くなりました。風邪などひかないように。 今日の Dojoサークルは何故か朝から♫ハワイアン♬♪体幹チェック兼ねて腰をひねり片足交互のSTEP そして各関節を滑らかに yī èr sān sì & パタカラスクワット 衆院解散。石破・野田氏は1957年生まれ! 私よりずっと若いんですね。私も相当の年寄りだと自覚www
一昨日は夏日だったのに風向きが変わり昨日から急に寒くなりました。風邪などひかないように。 今日の Dojoサークルは何故か朝から♫ハワイアン♬♪体幹チェック兼ねて腰をひねり片足交互のSTEP そして各関節を滑らかに yī èr sān sì & パタカラスクワット 衆院解散。石破・野田氏は1957年生まれ! 私よりずっと若いんですね。私も相当の年寄りだと自覚www 雨が上がり秋らしくなり、寒いくらい。が、あすはまた夏日に?今日の貯筋クラスは新しい方を迎え久々に倉庫に預けてある貯筋棒を取り出してきました。以前からのメンバーさんたちが、気持ちいい~気持ちいい~と大感動の声。初めて使ったかのような感激ぶりに笑ってしまいました。仲間の背中をコロコロ転がして芋虫のように一列になっていました(^O^)🐛 スマホ忘れその様子が撮れず残念でした。そして朝タンの話。
雨が上がり秋らしくなり、寒いくらい。が、あすはまた夏日に?今日の貯筋クラスは新しい方を迎え久々に倉庫に預けてある貯筋棒を取り出してきました。以前からのメンバーさんたちが、気持ちいい~気持ちいい~と大感動の声。初めて使ったかのような感激ぶりに笑ってしまいました。仲間の背中をコロコロ転がして芋虫のように一列になっていました(^O^)🐛 スマホ忘れその様子が撮れず残念でした。そして朝タンの話。 【あの手この手で】 2024/10/10 前方着地メソッドと 後方押し出し型メソッド 分れて肩甲骨を寄せる練習 それだけで 〇〇が減って 〇〇が増えた〜 あの手もこの手も 効いたみたいです (*^^*)
【あの手この手で】 2024/10/10 前方着地メソッドと 後方押し出し型メソッド 分れて肩甲骨を寄せる練習 それだけで 〇〇が減って 〇〇が増えた〜 あの手もこの手も 効いたみたいです (*^^*)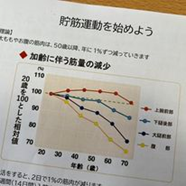 今日は、一関地域保健推進委員研修会で、「貯筋運動」を指導してきました! 美智子上皇后さまの大腿骨骨折の話をさせていただき、退院後に普段通りの生活に戻るためには、筋肉貯金が大切であることを伝えました。 美智子さまが早く良くなるよう祈りつつ、ケガや病気のリスクを下げ、早期復活を可能にする日々の筋トレの重要さが伝わったのなら幸いです。
今日は、一関地域保健推進委員研修会で、「貯筋運動」を指導してきました! 美智子上皇后さまの大腿骨骨折の話をさせていただき、退院後に普段通りの生活に戻るためには、筋肉貯金が大切であることを伝えました。 美智子さまが早く良くなるよう祈りつつ、ケガや病気のリスクを下げ、早期復活を可能にする日々の筋トレの重要さが伝わったのなら幸いです。 西武国分寺線は単線だって、はじめて知りました。 10月の気まポ(気ままにポール歩き)は快晴の小平市が舞台でした。 西武国分寺線の鷹の台駅に集合、小平市中央公園でウォーミングアップ、玉川上水沿いの木々の間を行きました。 途中、個人宅を開放している森田オープンガーデンに立ち寄り、休業中の「こもれびの足湯」を横目に見て、西武拝島線東大和市駅近くの東京都薬用植物園に到着、ゆったりくつろぎました。 メンバーのひとりは、来週末100km歩きのイベントに参加されるそうです。 今回欠席の一人は長崎でゴルフ、別の一人は孫の運動会。 今回のコースは、以前新里るりさんの会に参加してとても快適だったので、真似させてもらいました。 一部田村和史さん撮影の写真を拝借しています。
西武国分寺線は単線だって、はじめて知りました。 10月の気まポ(気ままにポール歩き)は快晴の小平市が舞台でした。 西武国分寺線の鷹の台駅に集合、小平市中央公園でウォーミングアップ、玉川上水沿いの木々の間を行きました。 途中、個人宅を開放している森田オープンガーデンに立ち寄り、休業中の「こもれびの足湯」を横目に見て、西武拝島線東大和市駅近くの東京都薬用植物園に到着、ゆったりくつろぎました。 メンバーのひとりは、来週末100km歩きのイベントに参加されるそうです。 今回欠席の一人は長崎でゴルフ、別の一人は孫の運動会。 今回のコースは、以前新里るりさんの会に参加してとても快適だったので、真似させてもらいました。 一部田村和史さん撮影の写真を拝借しています。 佐久ポールウォーキング協会より 当協会のマスコット犬🐶〜 癒しのセラピー犬の藤井七葉(ナナハ/フミヤ)の活躍が新聞記事に掲載されました。 4〜5kmの散策にも文句❓も言わず、参加者を癒しながらの4足歩行です〜ww 明日の女神湖PW散策にも参加予定です。 いつもご苦労様です‼️
佐久ポールウォーキング協会より 当協会のマスコット犬🐶〜 癒しのセラピー犬の藤井七葉(ナナハ/フミヤ)の活躍が新聞記事に掲載されました。 4〜5kmの散策にも文句❓も言わず、参加者を癒しながらの4足歩行です〜ww 明日の女神湖PW散策にも参加予定です。 いつもご苦労様です‼️ 【心はひとつ 地域で皆HAPPY♥】 2024/10/12 塚田地区スポーツ推進協議会 の依頼で 「#初めてのポールウォーキング」 指導を #県立行田公園 にて行ないました 今年で2回目です #塚田地区スポーツ推進協議会 #船橋ウォーキングソサイエティ 近隣の人達の健康を願う企画が 良い形で継続しています #姿勢を良くしたい #歩幅を大きくしたい #正しいウォーキング法を知りたい #ウエストを細くしたい #足首が痛いからポールが良さそう #歩行力を上げたい 参加動機は様々です。 其々の期待にポールウォーキングは 応えられそうです 参加者・主催者チーム・ 船橋ウォーキングソサイエティチー厶 健康を願う気持ちがひとつになり HAPPY♥な日になりました 感謝の一日です
【心はひとつ 地域で皆HAPPY♥】 2024/10/12 塚田地区スポーツ推進協議会 の依頼で 「#初めてのポールウォーキング」 指導を #県立行田公園 にて行ないました 今年で2回目です #塚田地区スポーツ推進協議会 #船橋ウォーキングソサイエティ 近隣の人達の健康を願う企画が 良い形で継続しています #姿勢を良くしたい #歩幅を大きくしたい #正しいウォーキング法を知りたい #ウエストを細くしたい #足首が痛いからポールが良さそう #歩行力を上げたい 参加動機は様々です。 其々の期待にポールウォーキングは 応えられそうです 参加者・主催者チーム・ 船橋ウォーキングソサイエティチー厶 健康を願う気持ちがひとつになり HAPPY♥な日になりました 感謝の一日です 佐久ポールウォーキング協会より 秋🍂恒例の〜女神湖PW散策〜でした。 快晴で少し肌寒く紅葉はもう少しの湖畔でしたが、中央分水嶺の林道コースと湖畔周遊コースに別れてのポールウォークを楽しんだ皆さんでした。 今回も佐久市内だけでなく、遠くは関東勢(遠藤夫妻 瀧MCproと母上)や 周辺地域からの一般の参加者が来て頂いている事にPWの繋がりを感じています。 締めは〜きのこ鍋定食〜を囲んでのランチでした。 ・・とUPしている当方ですが私用で本日欠席でしたが、頼り甲斐ある協会コーチのみんなが楽しんで開催してくれました。 みんな〜お疲れ様でした。
佐久ポールウォーキング協会より 秋🍂恒例の〜女神湖PW散策〜でした。 快晴で少し肌寒く紅葉はもう少しの湖畔でしたが、中央分水嶺の林道コースと湖畔周遊コースに別れてのポールウォークを楽しんだ皆さんでした。 今回も佐久市内だけでなく、遠くは関東勢(遠藤夫妻 瀧MCproと母上)や 周辺地域からの一般の参加者が来て頂いている事にPWの繋がりを感じています。 締めは〜きのこ鍋定食〜を囲んでのランチでした。 ・・とUPしている当方ですが私用で本日欠席でしたが、頼り甲斐ある協会コーチのみんなが楽しんで開催してくれました。 みんな〜お疲れ様でした。 【美・姿勢ウォーキング】 2024/9/15 秋はしっかり歩きだよ〜 上半身を起こして肘引きね スマートベルトを使って 身体へ意識付けも いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #パワーウォーキング #日本ウォーキング協会 #健康ウォーキング指導士 #JWA公認指導員
【美・姿勢ウォーキング】 2024/9/15 秋はしっかり歩きだよ〜 上半身を起こして肘引きね スマートベルトを使って 身体へ意識付けも いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #パワーウォーキング #日本ウォーキング協会 #健康ウォーキング指導士 #JWA公認指導員 今日は十三夜 午前の広町里山グループは久々に 谷戸を囲む尾根道を草花を楽しみながら2時間近く歩きました。先回まで暑さを避け室内だったので 森の風を感じながら自然を満喫できました。ポールのお陰でどの道も皆さん安心して歩けました。
今日は十三夜 午前の広町里山グループは久々に 谷戸を囲む尾根道を草花を楽しみながら2時間近く歩きました。先回まで暑さを避け室内だったので 森の風を感じながら自然を満喫できました。ポールのお陰でどの道も皆さん安心して歩けました。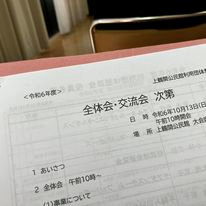 2024.10.13〜17 活動記録 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会全体交流会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎相模原スポーツフェスティバル(欠席) ☺︎上溝包括支援センター主催ポールウォーキング教室① ☺︎シニアサポート活動上半期利用者チェック ☺︎健康体操サークル ☺︎スマイルチーム上溝 ☺︎公民館利用抽選申し込み 4団体
2024.10.13〜17 活動記録 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会全体交流会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎相模原スポーツフェスティバル(欠席) ☺︎上溝包括支援センター主催ポールウォーキング教室① ☺︎シニアサポート活動上半期利用者チェック ☺︎健康体操サークル ☺︎スマイルチーム上溝 ☺︎公民館利用抽選申し込み 4団体 マスターコーチ2日間セミナー10月18日、19日シナノ本社で開催しました。 5名の受講者、4名の講師陣、安藤名誉会長のご指摘をいただきながら良い緊張感の中明るい2日間でした‼️ 今回は名誉会長、講師陣とも異論無く全員合格です‼️ 受講者の熱意と努力の賜物です。マスターコーチプロ目指して2回のインターンセミナー精進お願いします‼️
マスターコーチ2日間セミナー10月18日、19日シナノ本社で開催しました。 5名の受講者、4名の講師陣、安藤名誉会長のご指摘をいただきながら良い緊張感の中明るい2日間でした‼️ 今回は名誉会長、講師陣とも異論無く全員合格です‼️ 受講者の熱意と努力の賜物です。マスターコーチプロ目指して2回のインターンセミナー精進お願いします‼️ 10月18、19日にMC2日間セミナーが(株)シナノで開催され、5名の受講生全員が合格されました👏 今年の受講生は非常に勉強熱心な方ばかりで、マニュアルを熟読し暗記されている方もいらっしゃいました。 PWに対する熱意とスキルに、安藤名誉会長、講師陣とも感心いたしました。 今後、5名の受講生は2回のインターン研修を終了し、晴れてMCProの仲間入りとなります。
10月18、19日にMC2日間セミナーが(株)シナノで開催され、5名の受講生全員が合格されました👏 今年の受講生は非常に勉強熱心な方ばかりで、マニュアルを熟読し暗記されている方もいらっしゃいました。 PWに対する熱意とスキルに、安藤名誉会長、講師陣とも感心いたしました。 今後、5名の受講生は2回のインターン研修を終了し、晴れてMCProの仲間入りとなります。 【上半身を働かせたら 歩きは変わる】 2024/10/19 土曜日コースもポイント練習 前方着地型も後方押し出し型も 無理のない上半身運動の コツは肩甲骨を寄せるよ♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #JWA健康ウォーキング指導士 #全身の9割の筋肉を使う運動 #肩甲骨 #スポーツの秋 #海老川をポールで歩く
【上半身を働かせたら 歩きは変わる】 2024/10/19 土曜日コースもポイント練習 前方着地型も後方押し出し型も 無理のない上半身運動の コツは肩甲骨を寄せるよ♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #JWA健康ウォーキング指導士 #全身の9割の筋肉を使う運動 #肩甲骨 #スポーツの秋 #海老川をポールで歩く また派遣のお仕事を頼まれて2か月間働くことになりました。 東京都のシニア雇用事業 今日は事前研修で新宿へ。 シニア雇用を取り巻く環境から 即戦力としてシニアがどう働くか。。。 あらためて学び、気が引き締まりました😊 心身共に健康であること 気力を充実させる 思考転換 positiveに! そんな簡単な事から専門用語まで。汗 何人かのシニア男性の健康法が面白かったです😅 久しぶりの新宿駅西口 小田急デパート🏬の建てかえは知ってたけど、実際目にすると‼️ こんなに工事中なのぉ⁉️ 全く田舎モンの私ですw 研修のあとは 都庁の食堂で眺めを楽しみひと休み😊 2時すぎで食堂は終わっていて、持参したお弁当を食べてる人が多かったです。 モンベルを偵察して帰宅😆
また派遣のお仕事を頼まれて2か月間働くことになりました。 東京都のシニア雇用事業 今日は事前研修で新宿へ。 シニア雇用を取り巻く環境から 即戦力としてシニアがどう働くか。。。 あらためて学び、気が引き締まりました😊 心身共に健康であること 気力を充実させる 思考転換 positiveに! そんな簡単な事から専門用語まで。汗 何人かのシニア男性の健康法が面白かったです😅 久しぶりの新宿駅西口 小田急デパート🏬の建てかえは知ってたけど、実際目にすると‼️ こんなに工事中なのぉ⁉️ 全く田舎モンの私ですw 研修のあとは 都庁の食堂で眺めを楽しみひと休み😊 2時すぎで食堂は終わっていて、持参したお弁当を食べてる人が多かったです。 モンベルを偵察して帰宅😆 本日、弥栄市民センター主催、いやさか祭りステージにて、プチ健康体操教室を行ってきました! 子どもからお年寄りまで、みんなで参加していただき、とっても楽しかったです♪ 青空の下での体操は、最高でした😊
本日、弥栄市民センター主催、いやさか祭りステージにて、プチ健康体操教室を行ってきました! 子どもからお年寄りまで、みんなで参加していただき、とっても楽しかったです♪ 青空の下での体操は、最高でした😊 イベントの秋🍂 昨日は、我が街長久手のジブリパークこと愛・地球博記念公園にて、鈴木智香子代表のohanaフィットネスさんのトレーナーの1人として、ある企業様の社内健康イベントに参加いたしまして、子供向けの運動プログラム(遊びットネス)および、ポールウォーキングを担当させていただきました❗️ こちらの会社では、これまでの社内研修会を打破すべく、社員家族にも参加できるような企画ということで、今回ohanaさんの企画が採用となりました。 社員の皆さんとそのご家族、総勢80名ほどに皆さんが、自律神経コンディショニングやピラティス、そして子供達は運動遊びプログラム『遊びットネス』、家族参加でのポールウォーキングに、それぞれ選択して参加いただきました😊 終了後、担当者の方から、大変有意義で楽しい企画でしたとの感想もいただきました❣️ 参加された皆さんに楽しんでいただけたことが何よりですね❗️ また、その午後は滋賀県に向かいまして、日本ウォーキング学会に参加してまいりました。 一番最後の写真は、琵琶湖でございます😲琵琶湖を近場で見たのは人生初かと思います❗️ 今回の学会参加は、慶應大学の山内賢教授のポスター発表の 1人として参加しました。 数名の先生方の講演も拝聴しましたが、「歩行寿命」という言葉を使われていらしゃったのが印象に残りました。 そして、今日日曜日は愛知県は津島市でウォーキングイベントに参加。 このイベントは毎年恒例のイベントで、今回で19回目。私も半分くらいは参加してますかね。。。 毎回、準備体操、整理体操を担当させていただいています。 今回は、ご高齢の方で膝腰の具合が悪く長距離歩くのは少し大変、という方を対象として、椅子体操を1時間ほど実施。 一人でも多くの市民の皆んに参加していただきたいという主催者のお気持ちがこうした形となりましたね❣️ 老若男女、600名の皆さん参加です‼️ ウォーキングから戻ってきますと、ボランティアの皆さんがカレーを作ってお迎えです❣️ 体を動かし、多くの皆さんと交流を楽しむ❗️ 運動、食事、社会交流が健康の3本柱といわれるようになっていますね。 この三要素が全て揃ったこの津島ウォークイベントは素敵ですね❣️ #ohanaフィットネス #遊びットネス #ポールウォーキング #健康経営 #日本ウォーキング学会 #慶應義塾大学体育研究所 #津島市
イベントの秋🍂 昨日は、我が街長久手のジブリパークこと愛・地球博記念公園にて、鈴木智香子代表のohanaフィットネスさんのトレーナーの1人として、ある企業様の社内健康イベントに参加いたしまして、子供向けの運動プログラム(遊びットネス)および、ポールウォーキングを担当させていただきました❗️ こちらの会社では、これまでの社内研修会を打破すべく、社員家族にも参加できるような企画ということで、今回ohanaさんの企画が採用となりました。 社員の皆さんとそのご家族、総勢80名ほどに皆さんが、自律神経コンディショニングやピラティス、そして子供達は運動遊びプログラム『遊びットネス』、家族参加でのポールウォーキングに、それぞれ選択して参加いただきました😊 終了後、担当者の方から、大変有意義で楽しい企画でしたとの感想もいただきました❣️ 参加された皆さんに楽しんでいただけたことが何よりですね❗️ また、その午後は滋賀県に向かいまして、日本ウォーキング学会に参加してまいりました。 一番最後の写真は、琵琶湖でございます😲琵琶湖を近場で見たのは人生初かと思います❗️ 今回の学会参加は、慶應大学の山内賢教授のポスター発表の 1人として参加しました。 数名の先生方の講演も拝聴しましたが、「歩行寿命」という言葉を使われていらしゃったのが印象に残りました。 そして、今日日曜日は愛知県は津島市でウォーキングイベントに参加。 このイベントは毎年恒例のイベントで、今回で19回目。私も半分くらいは参加してますかね。。。 毎回、準備体操、整理体操を担当させていただいています。 今回は、ご高齢の方で膝腰の具合が悪く長距離歩くのは少し大変、という方を対象として、椅子体操を1時間ほど実施。 一人でも多くの市民の皆んに参加していただきたいという主催者のお気持ちがこうした形となりましたね❣️ 老若男女、600名の皆さん参加です‼️ ウォーキングから戻ってきますと、ボランティアの皆さんがカレーを作ってお迎えです❣️ 体を動かし、多くの皆さんと交流を楽しむ❗️ 運動、食事、社会交流が健康の3本柱といわれるようになっていますね。 この三要素が全て揃ったこの津島ウォークイベントは素敵ですね❣️ #ohanaフィットネス #遊びットネス #ポールウォーキング #健康経営 #日本ウォーキング学会 #慶應義塾大学体育研究所 #津島市 佐久平ハーフマラソン無事完走!今年はバスケ仲間と偶然一緒に走りました。記録も昨年から3分短縮(^^) 仲間の力は大きいなぁと実感。足が動かなくなっても、なんとかついて行こうと思えるし、なにより気持ちが切れそうで“歩きたい”と思っても、仲間がいれば頑張れてしまう!それを今回体感しました(^^)雑談しながら走るのも気分転換にいいしね! 運営スタッフやボランティアの皆さん本当にありがとうございました! さて明日の身体が心配だ(TT)
佐久平ハーフマラソン無事完走!今年はバスケ仲間と偶然一緒に走りました。記録も昨年から3分短縮(^^) 仲間の力は大きいなぁと実感。足が動かなくなっても、なんとかついて行こうと思えるし、なにより気持ちが切れそうで“歩きたい”と思っても、仲間がいれば頑張れてしまう!それを今回体感しました(^^)雑談しながら走るのも気分転換にいいしね! 運営スタッフやボランティアの皆さん本当にありがとうございました! さて明日の身体が心配だ(TT) あびこポールウォーキング倶楽部 あけぼの山公園。 コスモスを摘み、モルックで遊び、楽しく歩きました。
あびこポールウォーキング倶楽部 あけぼの山公園。 コスモスを摘み、モルックで遊び、楽しく歩きました。 📢 【2024健走杖健康活力輕旅行】 新北林口民視站 活動圓滿結束!🎉 今天我們的健走杖夥伴們, 在新北林口民視站度過了一個充實且充滿活力的早晨!🌞 🚶♂️🚶♀️ 大家一早邊健走邊欣賞林口的美麗風景, 接著參觀了民視大樓, 了解電視台背後的故事, 更深入了解了我們身邊健康生活的重要性。📺🌳 活動中特別安排娘家保健品介紹,讓大家認識如何選安心用心的保健產品,親身體驗到了它們對於我們健康的好處!💊 同時,阿瘦皮鞋也提供了專業的足部健康檢測, 讓我們更加關注雙腳的健康!👣👟 此外,很多夥伴們在完成健走後, 還利用joiisport app打卡記錄, 並且蒐集到了專屬的獎章🎖️! 這真是一個既健康又充滿科技感的健走體驗啊!📱🏅 感謝所有參與的朋友們,期待我們下一次的輕旅行!讓我們繼續走出健康,邁向更美好的生活!💪✨ #2024健走杖健康活力輕旅行 腳丫聚樂部 娘家保健生技 A.S.O 阿瘦皮鞋
📢 【2024健走杖健康活力輕旅行】 新北林口民視站 活動圓滿結束!🎉 今天我們的健走杖夥伴們, 在新北林口民視站度過了一個充實且充滿活力的早晨!🌞 🚶♂️🚶♀️ 大家一早邊健走邊欣賞林口的美麗風景, 接著參觀了民視大樓, 了解電視台背後的故事, 更深入了解了我們身邊健康生活的重要性。📺🌳 活動中特別安排娘家保健品介紹,讓大家認識如何選安心用心的保健產品,親身體驗到了它們對於我們健康的好處!💊 同時,阿瘦皮鞋也提供了專業的足部健康檢測, 讓我們更加關注雙腳的健康!👣👟 此外,很多夥伴們在完成健走後, 還利用joiisport app打卡記錄, 並且蒐集到了專屬的獎章🎖️! 這真是一個既健康又充滿科技感的健走體驗啊!📱🏅 感謝所有參與的朋友們,期待我們下一次的輕旅行!讓我們繼續走出健康,邁向更美好的生活!💪✨ #2024健走杖健康活力輕旅行 腳丫聚樂部 娘家保健生技 A.S.O 阿瘦皮鞋 【UR横浜南永田 ポールウォーキングサークル立ち上げ事業】 千葉、埼玉そして横浜では初のURを任されました。 高齢者が多くなったUR団地の皆さんが自宅にこもらず自力で団地の階段を上がれるよう健脚になってもらいたい! だからポールウォーキング! 桜が満開の4月に打ち合わせをして6月からスタート 月に2回× 4ヶ月= 全8回 10/20 ラストとなり無事にサークルが立ち上がりました。 URの方、そしてこの地区の保健活動推進委員、地域包括支援、社会福祉協議会の方々もこの事業を応援してくださり毎回参加。YouTubeでも紹介されることになりました。 保健活動推進委員の方が中心にPWサークルを引っ張ってくださいます。ネックとなっていたポールも用意され更に助成金でポール購入も考えて下さいます。 皆さんで楽しく和気藹々とそして階段だってなんのその。健脚になっていただきましょう。 この活動が次に繋がることを切に願います。 #ポールウォーキング #ポールウォーキング協会 #URサークル立ち上げ事業
【UR横浜南永田 ポールウォーキングサークル立ち上げ事業】 千葉、埼玉そして横浜では初のURを任されました。 高齢者が多くなったUR団地の皆さんが自宅にこもらず自力で団地の階段を上がれるよう健脚になってもらいたい! だからポールウォーキング! 桜が満開の4月に打ち合わせをして6月からスタート 月に2回× 4ヶ月= 全8回 10/20 ラストとなり無事にサークルが立ち上がりました。 URの方、そしてこの地区の保健活動推進委員、地域包括支援、社会福祉協議会の方々もこの事業を応援してくださり毎回参加。YouTubeでも紹介されることになりました。 保健活動推進委員の方が中心にPWサークルを引っ張ってくださいます。ネックとなっていたポールも用意され更に助成金でポール購入も考えて下さいます。 皆さんで楽しく和気藹々とそして階段だってなんのその。健脚になっていただきましょう。 この活動が次に繋がることを切に願います。 #ポールウォーキング #ポールウォーキング協会 #URサークル立ち上げ事業 猛暑の夏は活動休止。久しぶりの三浦ネットPWグループでした。神奈川健康生き甲斐つくりの会員だった頃3年前に地域のメンバーで結成。 月一市内をコースを変えて歩いています。今日は女子3人で先にランチをしてから時計台広場に男性陣と合流。まず寿福寺へ。山門前で美しい参道を見ながら念入りウォーミングアップ。北条政子や実朝の墓地横の山道を登って 源氏山公園へ。鎌倉5名水の一つ銭洗弁財天宇賀福神社の銭洗水で小銭を洗って 皆さんは福祉センター定例会へ。私は佐助隧道を抜けて帰宅🏠👣
猛暑の夏は活動休止。久しぶりの三浦ネットPWグループでした。神奈川健康生き甲斐つくりの会員だった頃3年前に地域のメンバーで結成。 月一市内をコースを変えて歩いています。今日は女子3人で先にランチをしてから時計台広場に男性陣と合流。まず寿福寺へ。山門前で美しい参道を見ながら念入りウォーミングアップ。北条政子や実朝の墓地横の山道を登って 源氏山公園へ。鎌倉5名水の一つ銭洗弁財天宇賀福神社の銭洗水で小銭を洗って 皆さんは福祉センター定例会へ。私は佐助隧道を抜けて帰宅🏠👣 昨日の日刊工業新聞に掲載いただきました。いろんなご縁で取材をしていただくことになりました。ありがたいことです! 昨日から地元の中学生が社会体験で4人実習にきています。次女と同じクラスの子もいるようで、地元の大きな中学なのであちこちに実習にいっておりセブンでも見かけましたね。次女は母校の小学校へ体験実習したようです(心ではシナノに来ないかなぁと思っていましたが・・・)。1年生に教えたようですが、小さい子どもを教えたり仕切ったりしている次女の姿が全く想像できず(^.^)現場を覗きたい!! 昨日は読売新聞の取材を受けたり、母校の学校評議員会だったりでバタバタ。生徒会3役から今年の方針を聞きましたが、しっかりしていて頼もしい! さて今日は交通会館のテナント会へ。
昨日の日刊工業新聞に掲載いただきました。いろんなご縁で取材をしていただくことになりました。ありがたいことです! 昨日から地元の中学生が社会体験で4人実習にきています。次女と同じクラスの子もいるようで、地元の大きな中学なのであちこちに実習にいっておりセブンでも見かけましたね。次女は母校の小学校へ体験実習したようです(心ではシナノに来ないかなぁと思っていましたが・・・)。1年生に教えたようですが、小さい子どもを教えたり仕切ったりしている次女の姿が全く想像できず(^.^)現場を覗きたい!! 昨日は読売新聞の取材を受けたり、母校の学校評議員会だったりでバタバタ。生徒会3役から今年の方針を聞きましたが、しっかりしていて頼もしい! さて今日は交通会館のテナント会へ。 【秋だもの】 しっかり歩くのはいつ? 今でしょ! 2024/10/24 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #インターバルウォーキング #持久力アップ #心肺機能アップ #気分スキッリ #身体の声を聞きながらマイペース #行田公園
【秋だもの】 しっかり歩くのはいつ? 今でしょ! 2024/10/24 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #インターバルウォーキング #持久力アップ #心肺機能アップ #気分スキッリ #身体の声を聞きながらマイペース #行田公園 午後から社協なごやかセンターでPW教室。26日(土)はなごやかフェスタだそうですが、鎌倉ミステリーとぶつかりましたのでお手伝い等失礼いたします。既に開催中のギャラリー展を覗いて来ました。 鳥の絵にタッチするとその鳥の鳴き声が聞こえる電子ペン✏は優れものです。 🐦 🦜 🐥 🐦⬛ ポールウォーキング教室は中強度歩き、7秒スクワット、筋トレ各種で暑い上に(汗)を流し、運動量バッチリ!朝タン20も浸透して来ました。健康寿命延伸クラスです。
午後から社協なごやかセンターでPW教室。26日(土)はなごやかフェスタだそうですが、鎌倉ミステリーとぶつかりましたのでお手伝い等失礼いたします。既に開催中のギャラリー展を覗いて来ました。 鳥の絵にタッチするとその鳥の鳴き声が聞こえる電子ペン✏は優れものです。 🐦 🦜 🐥 🐦⬛ ポールウォーキング教室は中強度歩き、7秒スクワット、筋トレ各種で暑い上に(汗)を流し、運動量バッチリ!朝タン20も浸透して来ました。健康寿命延伸クラスです。 記念すべき創立30周年記念イベントで2講座(足裏筋膜を整えよう/ポールウォーキング)講師を担当させていただきました。 パワフルで自由すぎるアクティブシニア、後期高齢者の皆さんと賑やかに講座をおこなう事ができました! このような大学に通われている方や イベントに参加される方は基本おゲンキ!! ゲンキすぎるw 皆さん、イキイキしておられますね! 良い経験になりました! ありがとうございました!
記念すべき創立30周年記念イベントで2講座(足裏筋膜を整えよう/ポールウォーキング)講師を担当させていただきました。 パワフルで自由すぎるアクティブシニア、後期高齢者の皆さんと賑やかに講座をおこなう事ができました! このような大学に通われている方や イベントに参加される方は基本おゲンキ!! ゲンキすぎるw 皆さん、イキイキしておられますね! 良い経験になりました! ありがとうございました! 夏休み明けの「鎌倉ミステリーno.9」東京~神奈川の合同大所帯25名で歩きました。懐かしいもと杉ポの校條さんも遥々御一緒にポールでハイキング。私は日頃歩きなれた道ですが初めてのかたにはすこし凸凹道がハードでしたか。楽しかった~との感想を頂きほっとしました。 ハイキングコース下の北条高時腹切りやぐら~東勝寺跡(北条高時等870余人が自害)~宝戒寺橋~紅葉山やぐら~宝戒寺は 生き延びた高時の息子時行の鎌倉奪還劇にちなむ場所。アニメ「逃げ上手の若君」は個人的に私のブームです。
夏休み明けの「鎌倉ミステリーno.9」東京~神奈川の合同大所帯25名で歩きました。懐かしいもと杉ポの校條さんも遥々御一緒にポールでハイキング。私は日頃歩きなれた道ですが初めてのかたにはすこし凸凹道がハードでしたか。楽しかった~との感想を頂きほっとしました。 ハイキングコース下の北条高時腹切りやぐら~東勝寺跡(北条高時等870余人が自害)~宝戒寺橋~紅葉山やぐら~宝戒寺は 生き延びた高時の息子時行の鎌倉奪還劇にちなむ場所。アニメ「逃げ上手の若君」は個人的に私のブームです。 佐久ポールウォーキング協会より 本日のポールウォークは 佐久市内中部横断自動車道・長野区間/臼田ICを降りた地域の「北川区」秋の公民館活動に呼ばれてのPW体験会でした。 この地域はIC開通と共に従来未開発地域に工業団地や統合小学校が出来たり・・とこれからの賑わいが大予想される田園エリアで、15名程の興味津々の参加者とPW闊歩でした。
佐久ポールウォーキング協会より 本日のポールウォークは 佐久市内中部横断自動車道・長野区間/臼田ICを降りた地域の「北川区」秋の公民館活動に呼ばれてのPW体験会でした。 この地域はIC開通と共に従来未開発地域に工業団地や統合小学校が出来たり・・とこれからの賑わいが大予想される田園エリアで、15名程の興味津々の参加者とPW闊歩でした。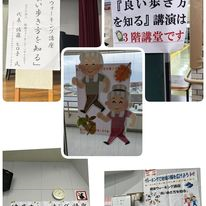 習志野台地域ケア会議主催 ウォーキング講座 【良い歩き方を知る】 2024/10/26 ネット検索されて船橋ウォーキング・ソサイエティがケア会の主旨に合っているとの事でお呼びがかかりました 「地域ケア会議 」の熱意凄い! 講座を盛り立ててくれる 沢山のイラストが貼られました 地域住民を元気にしたい気持が グングン伝わってきます それに応え講堂内の参加者も やる気に満ち溢れていました。 40代〜80代迄の30名超えの参加 実技と理論 「量より質のウォーキング」 対話も弾む楽しい体験会 になりました 今日も出会いに感謝です #船橋ウォーキングソサイエティ #良い歩き方を知る #健康ウォーキング指導士 #パワーウォーキング指導士 #地域ケア会議 #習志野台公民館 #良い歩き方6つのポイント #中之条研究 #一日8000歩速歩20分
習志野台地域ケア会議主催 ウォーキング講座 【良い歩き方を知る】 2024/10/26 ネット検索されて船橋ウォーキング・ソサイエティがケア会の主旨に合っているとの事でお呼びがかかりました 「地域ケア会議 」の熱意凄い! 講座を盛り立ててくれる 沢山のイラストが貼られました 地域住民を元気にしたい気持が グングン伝わってきます それに応え講堂内の参加者も やる気に満ち溢れていました。 40代〜80代迄の30名超えの参加 実技と理論 「量より質のウォーキング」 対話も弾む楽しい体験会 になりました 今日も出会いに感謝です #船橋ウォーキングソサイエティ #良い歩き方を知る #健康ウォーキング指導士 #パワーウォーキング指導士 #地域ケア会議 #習志野台公民館 #良い歩き方6つのポイント #中之条研究 #一日8000歩速歩20分 朝から横須賀線下りは5分遅れ。今日は逗子のPW教室で20数名集合。猛暑と雨で延び延びになり漸く皆さんと顔を合わせた定例会。PWの3つのポイントを復習し肩の力を抜いて街の散歩道をゆったり歩きました。ここは紅葉が始まっていい雰囲気です。次回は小網代へ遠足です。
朝から横須賀線下りは5分遅れ。今日は逗子のPW教室で20数名集合。猛暑と雨で延び延びになり漸く皆さんと顔を合わせた定例会。PWの3つのポイントを復習し肩の力を抜いて街の散歩道をゆったり歩きました。ここは紅葉が始まっていい雰囲気です。次回は小網代へ遠足です。 2024.10.21〜29 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名 ☺︎上溝ポールウォーキング教室 15名 ☺︎ポールエクササイズ資料作成 ☺︎健康体操サークル 13名 ☺︎ベトナムアンサンブルチャリティーコンサート観劇 10名 ☺︎上鶴間包括担当者とミーティング ☺︎星が丘ポールウォーキング 4名 ☺︎EEOAオンラインセミナー①受講 アンケート提出 ☺︎スマイルフレンズ 18名 ☺︎ルネポールウォーキング 3名 ☺︎上溝ポールウォーキング教室 15名
2024.10.21〜29 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名 ☺︎上溝ポールウォーキング教室 15名 ☺︎ポールエクササイズ資料作成 ☺︎健康体操サークル 13名 ☺︎ベトナムアンサンブルチャリティーコンサート観劇 10名 ☺︎上鶴間包括担当者とミーティング ☺︎星が丘ポールウォーキング 4名 ☺︎EEOAオンラインセミナー①受講 アンケート提出 ☺︎スマイルフレンズ 18名 ☺︎ルネポールウォーキング 3名 ☺︎上溝ポールウォーキング教室 15名 今朝は小雨も混じり寒かったですね。市場公会堂でDojoレッスン。下半身強化のスクワットか変顔の筋トレ(選択式)。変顔は顎の筋肉を鍛える・・らしい。ベルトを使ってトレーニングのあとマットでは 新型「闇バイト詐偽対策のポーズ」練習www 赤ちゃんのように小さくなります。 笑いメニューの指導は勿論3本杉コーチです。 午後はフリーでしたので のんびり歩いて帰りました。
今朝は小雨も混じり寒かったですね。市場公会堂でDojoレッスン。下半身強化のスクワットか変顔の筋トレ(選択式)。変顔は顎の筋肉を鍛える・・らしい。ベルトを使ってトレーニングのあとマットでは 新型「闇バイト詐偽対策のポーズ」練習www 赤ちゃんのように小さくなります。 笑いメニューの指導は勿論3本杉コーチです。 午後はフリーでしたので のんびり歩いて帰りました。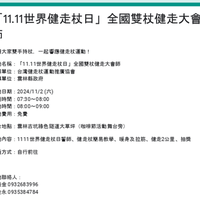 「11.11世界健走杖日」全國雙杖健走大會師
「11.11世界健走杖日」全國雙杖健走大會師 郡山市制施行100周年記念事業の一環として、がんばっぺチャリンコがイベントを企画しました。 旧久留米藩士が郡山に入植した明治11年11月11日に因んで11月11日(月)に開催いたします。因みに来年は久留米・郡山姉妹都市提携50周年でもあります♪ 更に11月11日は「ポールウォーキングの日」でもあります。 開拓者の「夢をあきらめないというフロンティアスピリット」に溢れている開成山公園。 11月11日の記念すべき日に、久留米藩士が刀から持ちかえた鍬を更にポールに持ちかえて、秋のウォーキングを楽しみませんか。🍂
郡山市制施行100周年記念事業の一環として、がんばっぺチャリンコがイベントを企画しました。 旧久留米藩士が郡山に入植した明治11年11月11日に因んで11月11日(月)に開催いたします。因みに来年は久留米・郡山姉妹都市提携50周年でもあります♪ 更に11月11日は「ポールウォーキングの日」でもあります。 開拓者の「夢をあきらめないというフロンティアスピリット」に溢れている開成山公園。 11月11日の記念すべき日に、久留米藩士が刀から持ちかえた鍬を更にポールに持ちかえて、秋のウォーキングを楽しみませんか。🍂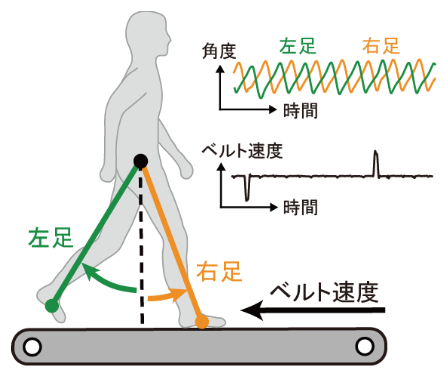 図1. 歩行計測実験
図1. 歩行計測実験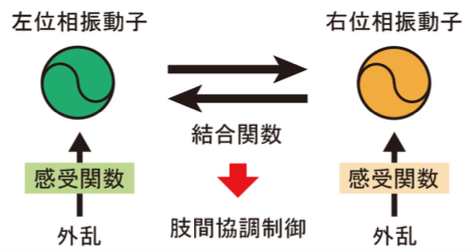 図2. 位相振動子を用いた肢間協調制御のモデル化
図2. 位相振動子を用いた肢間協調制御のモデル化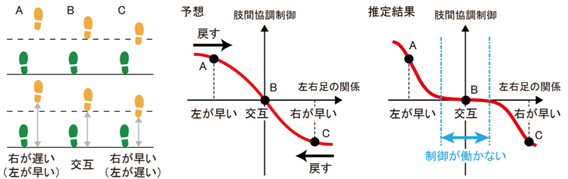 図3. 肢間協調の制御様式(予想と推定結果)
図3. 肢間協調の制御様式(予想と推定結果)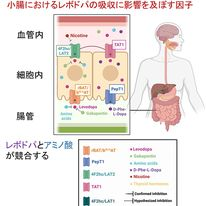 パーキンソン病治療の中心的な薬剤レボドパの吸収には個人差が大きく,さまざまな要因が関与することが知られています.私もレモン水は吸収に良いとか,高タンパク食は良くないとか患者さんにアドバイスしてきましたが,十分にメカニズムは理解していませんでした.今回,J Parkinsons Dis誌に分かりやすい総説がありましたので,ご紹介したいと思います.
パーキンソン病治療の中心的な薬剤レボドパの吸収には個人差が大きく,さまざまな要因が関与することが知られています.私もレモン水は吸収に良いとか,高タンパク食は良くないとか患者さんにアドバイスしてきましたが,十分にメカニズムは理解していませんでした.今回,J Parkinsons Dis誌に分かりやすい総説がありましたので,ご紹介したいと思います.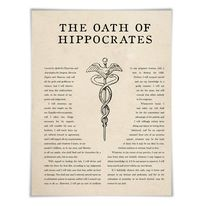 古代ギリシャの医師ヒポクラテスが残した「ヒポクラテスの誓い」は,医師が患者を治療する際の倫理的なガイドラインとして今なお広く尊重されています.その中でも最も重要な教えの一つが「まず,害を与えない(Primum non nocere)」です.もちろん医師は患者さんに害を及ぼさないよう最善を尽くしています.しかし無意識のうちに「医原性の害(iatrogenic harm)」をもたらしていることがあります.その代表例が機能性神経障害(FND),歴史的にヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症などと呼ばれてきた疾患への対応です.コロナ禍以降,複数の病院を受診したものの診断がつかず,回り回って来院したFND患者さんを少なからず診療しました.そのような患者さんは適切な対応がなされなかったため症状が悪化したり,精神的に傷ついたりしていました.このためFNDへの取り組みの必要性を感じ,先輩や仲間の先生方のお力をお借りして「機能性神経障害診療ハンドブック(https://amzn.to/4empy4i)」を作ったわけです.
古代ギリシャの医師ヒポクラテスが残した「ヒポクラテスの誓い」は,医師が患者を治療する際の倫理的なガイドラインとして今なお広く尊重されています.その中でも最も重要な教えの一つが「まず,害を与えない(Primum non nocere)」です.もちろん医師は患者さんに害を及ぼさないよう最善を尽くしています.しかし無意識のうちに「医原性の害(iatrogenic harm)」をもたらしていることがあります.その代表例が機能性神経障害(FND),歴史的にヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症などと呼ばれてきた疾患への対応です.コロナ禍以降,複数の病院を受診したものの診断がつかず,回り回って来院したFND患者さんを少なからず診療しました.そのような患者さんは適切な対応がなされなかったため症状が悪化したり,精神的に傷ついたりしていました.このためFNDへの取り組みの必要性を感じ,先輩や仲間の先生方のお力をお借りして「機能性神経障害診療ハンドブック(https://amzn.to/4empy4i)」を作ったわけです.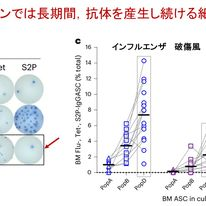 今回のキーワードは,long COVIDによる日本の経済的損失は2024年のGDPの1.6%に相当する,神経認知症状は小児期と青年期でもlong COVIDの主要症状であり,とくに小学生で記憶力や集中力の障害が多い,long COVID患者は「内部の震えや振動」を呈する,COVIDワクチンの効果が長持ちしないのは長寿命抗体産生細胞ができないためである,スパイク蛋白はフィブリンと結合して炎症性の血栓を形成し神経症状をきたす,long COVIDやワクチン後の副反応が女性に多い理由は性ホルモンで説明できる,健康な若年成人への感染で認知機能は低下するものの自覚的には気づかない,入院を経験した患者では感染1年後も脳損傷マーカーが高値を示す,です.
今回のキーワードは,long COVIDによる日本の経済的損失は2024年のGDPの1.6%に相当する,神経認知症状は小児期と青年期でもlong COVIDの主要症状であり,とくに小学生で記憶力や集中力の障害が多い,long COVID患者は「内部の震えや振動」を呈する,COVIDワクチンの効果が長持ちしないのは長寿命抗体産生細胞ができないためである,スパイク蛋白はフィブリンと結合して炎症性の血栓を形成し神経症状をきたす,long COVIDやワクチン後の副反応が女性に多い理由は性ホルモンで説明できる,健康な若年成人への感染で認知機能は低下するものの自覚的には気づかない,入院を経験した患者では感染1年後も脳損傷マーカーが高値を示す,です.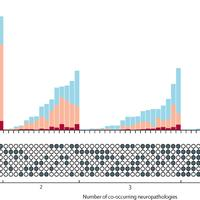
 Lancet委員会が報告した認知症の修正可能な14の因子の中に「頭部外傷」が含まれています.今回,Brain誌にオーストラリアから,慢性外傷性脳損傷(TBI)における認知機能障害のメカニズムを明らかにする目的で,血漿バイオマーカーを検討した研究が報告されました.
Lancet委員会が報告した認知症の修正可能な14の因子の中に「頭部外傷」が含まれています.今回,Brain誌にオーストラリアから,慢性外傷性脳損傷(TBI)における認知機能障害のメカニズムを明らかにする目的で,血漿バイオマーカーを検討した研究が報告されました.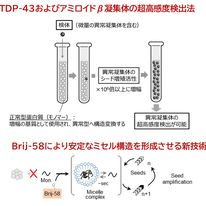 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科の本田諒准教授,大学院医学系研究科の下畑享良教授,岐阜薬科大学の位田雅俊教授らのグループは,神経変性疾患の発症に関わるTDP-43 およびアミロイドβ凝集体の超高感度検出技術を開発しました.この技術は,新たに発見された「Brij-58」という特異な性質をもつ界面活性剤を使用することによって,従来のシード増幅アッセイ法(SAA 法)の検出感度を飛躍的に向上させたものです.この技術により,最小 5 フェムトグラムという超微量の凝集体の検出が実現し,実際の患者の脳組織に蓄積した病的凝集体を検出することも可能となりました.本技術は,将来的には「ALS などの神経変性疾患の早期診断や早期治療介入」に貢献することが期待されます.本成果は,日本時間 2024 年 10 月 8 日に Translational Neurodegeneration誌のオンライン版で発表されました.
岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科の本田諒准教授,大学院医学系研究科の下畑享良教授,岐阜薬科大学の位田雅俊教授らのグループは,神経変性疾患の発症に関わるTDP-43 およびアミロイドβ凝集体の超高感度検出技術を開発しました.この技術は,新たに発見された「Brij-58」という特異な性質をもつ界面活性剤を使用することによって,従来のシード増幅アッセイ法(SAA 法)の検出感度を飛躍的に向上させたものです.この技術により,最小 5 フェムトグラムという超微量の凝集体の検出が実現し,実際の患者の脳組織に蓄積した病的凝集体を検出することも可能となりました.本技術は,将来的には「ALS などの神経変性疾患の早期診断や早期治療介入」に貢献することが期待されます.本成果は,日本時間 2024 年 10 月 8 日に Translational Neurodegeneration誌のオンライン版で発表されました.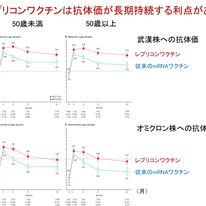 レプリコンワクチン接種者の入店拒否などの騒動が報道されていますが,「レプリコンワクチンって本当はどうなの?」という質問を何人かに聞かれました.最近,臨床試験の結果も出ているので,まとめておきたいと思います.まず,このワクチンはスパイクタンパクの遺伝子に加えて,RNAレプリカーゼという酵素の遺伝子も組み込んだmRNAワクチンです.従来のコロナワクチンでは,インフルエンザワクチンなどと比較して「長寿命抗体産生細胞」ができにくいため(Nature Med 2024;doi.org/10.1038/s41591-024-03278-y),抗体価が短期間で低下するという重大な欠点があります.ワクチンの効果切れ状態は,高齢者では生命予後に関わりますし,若い人でもlong COVIDや認知機能低下のリスクがありますので,抗体価が長く持続するワクチンの開発が急務です.
レプリコンワクチン接種者の入店拒否などの騒動が報道されていますが,「レプリコンワクチンって本当はどうなの?」という質問を何人かに聞かれました.最近,臨床試験の結果も出ているので,まとめておきたいと思います.まず,このワクチンはスパイクタンパクの遺伝子に加えて,RNAレプリカーゼという酵素の遺伝子も組み込んだmRNAワクチンです.従来のコロナワクチンでは,インフルエンザワクチンなどと比較して「長寿命抗体産生細胞」ができにくいため(Nature Med 2024;doi.org/10.1038/s41591-024-03278-y),抗体価が短期間で低下するという重大な欠点があります.ワクチンの効果切れ状態は,高齢者では生命予後に関わりますし,若い人でもlong COVIDや認知機能低下のリスクがありますので,抗体価が長く持続するワクチンの開発が急務です.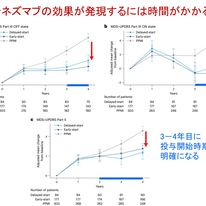 アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体は,細胞外に蓄積するタンパクを標的にするのに対し,αシヌクレインやタウ抗体は細胞内で作用する必要があり,抗体療法が有効である可能性は低いと考えられてきました.しかし近年,タウ抗体が細胞内でタウの分解を促進することが分かってきており,αシヌクレイン抗体も同様に有効性を発揮する可能性があります.候補となっているαシヌクレイン抗体は3種類あり,プラシネズマブは凝集したαシヌクレインを主に標的とし,BIIB054はフリーフォーム,MEDI1341は両方の形態に作用すると言われています.
アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体は,細胞外に蓄積するタンパクを標的にするのに対し,αシヌクレインやタウ抗体は細胞内で作用する必要があり,抗体療法が有効である可能性は低いと考えられてきました.しかし近年,タウ抗体が細胞内でタウの分解を促進することが分かってきており,αシヌクレイン抗体も同様に有効性を発揮する可能性があります.候補となっているαシヌクレイン抗体は3種類あり,プラシネズマブは凝集したαシヌクレインを主に標的とし,BIIB054はフリーフォーム,MEDI1341は両方の形態に作用すると言われています. 昨日は、愛知県は大口町にお邪魔しまして、午前、午後で1講座ずつの講師を務めてまいりました。 大口町保健センターさんが主催しました「健康推進員研修会」でした。 各講座、20〜30名の皆さんに参加いただきました。 こちらの講座は昨年の12月にも開催しており、昨日は半年ぶりの再会となりました。 町民の皆さんで、健康推進員として、各地域で住民の皆さんを対象として各種の健康づくり事業活動を展開されている皆さんです。 この大口町は3万人ほどの町で、やはり高齢化が進んでいる町ですが、横のつながりが高い地域で、こうした住民の皆さんによるボランティア活動は積極的に行われています。 私はこの大口町さんとはぼちぼち20年近いおつきあいになります。 その中で、生活習慣病予防をはじめ、特定保健指導、ポールウォーキング講座などを担当させていただき、昨年度からは3年間に及ぶ健康づくり推進員の任命を受けたり、本年度は委託事業もやらせていただく予定です。 こうして、住民の皆さんの健康づくりの一端を担わせていただけることに大きなやりがいを感じております。 大切なことは、こちらからの一方通行的な情報提供にとどまることなく、住民の皆さんがインプットされた後に、アウトプットする時に支援させていただくこと! コロナの影響を長らく受けた自治体の事業ですが、ようやく本年度からほぼ正常に戻った感じがします。 まだ反応が鈍い印象を受けますが、1人でも多くの住民の皆さんが「参加したい!」と思っていただける講座を展開し、フィットネスの輪を広げていくことに燃えています❗️😊
昨日は、愛知県は大口町にお邪魔しまして、午前、午後で1講座ずつの講師を務めてまいりました。 大口町保健センターさんが主催しました「健康推進員研修会」でした。 各講座、20〜30名の皆さんに参加いただきました。 こちらの講座は昨年の12月にも開催しており、昨日は半年ぶりの再会となりました。 町民の皆さんで、健康推進員として、各地域で住民の皆さんを対象として各種の健康づくり事業活動を展開されている皆さんです。 この大口町は3万人ほどの町で、やはり高齢化が進んでいる町ですが、横のつながりが高い地域で、こうした住民の皆さんによるボランティア活動は積極的に行われています。 私はこの大口町さんとはぼちぼち20年近いおつきあいになります。 その中で、生活習慣病予防をはじめ、特定保健指導、ポールウォーキング講座などを担当させていただき、昨年度からは3年間に及ぶ健康づくり推進員の任命を受けたり、本年度は委託事業もやらせていただく予定です。 こうして、住民の皆さんの健康づくりの一端を担わせていただけることに大きなやりがいを感じております。 大切なことは、こちらからの一方通行的な情報提供にとどまることなく、住民の皆さんがインプットされた後に、アウトプットする時に支援させていただくこと! コロナの影響を長らく受けた自治体の事業ですが、ようやく本年度からほぼ正常に戻った感じがします。 まだ反応が鈍い印象を受けますが、1人でも多くの住民の皆さんが「参加したい!」と思っていただける講座を展開し、フィットネスの輪を広げていくことに燃えています❗️😊 おはようございます 東京渋谷です 珍しく誰もいないので8月のハチ公 を撮っていると 国籍不明の女性が肩をたたき ワン、ワンと話しかけてきました U^q^U WAN? ん? ハチ公と一緒に写真を撮りましょうか、と言ってくれたようです take oneね 振り返るといつの間にか記念写真を撮るための行列ができていましたwww これから介護予防PW教室です 先週は定員15名全員出席でしたが、今日はどうでしょう 施設の階段をお借りして階段・坂道昇降練習の予定です
おはようございます 東京渋谷です 珍しく誰もいないので8月のハチ公 を撮っていると 国籍不明の女性が肩をたたき ワン、ワンと話しかけてきました U^q^U WAN? ん? ハチ公と一緒に写真を撮りましょうか、と言ってくれたようです take oneね 振り返るといつの間にか記念写真を撮るための行列ができていましたwww これから介護予防PW教室です 先週は定員15名全員出席でしたが、今日はどうでしょう 施設の階段をお借りして階段・坂道昇降練習の予定です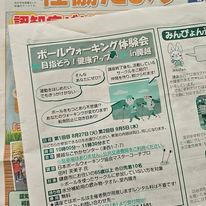 🪷かまくら ポールウォーキング体験会 8/27or 9/5 手にした2本のポール(杖・ストック)を身体の前におきながら歩きます 4本脚になり安定します ・最近足(膝)腰の調子がよくなくて気になる方 ・転ぶのが不安で外歩きを躊躇っていらっしゃる方 ・もっとよい姿勢で歩幅広く(お棺の中まで)自力で歩けるようになりたい方 ・人生の楽しみを叶えるにはまずは自立して歩けること これがはじめの一歩 そんな歩きに応えてくれるポールウォーキングの体験会です 鎌倉市民65才以上の方! 体験して続けたいと思われたら、市内サークルをご紹介します お申し込みは包括支援センター聖テレジア(写真下部)
🪷かまくら ポールウォーキング体験会 8/27or 9/5 手にした2本のポール(杖・ストック)を身体の前におきながら歩きます 4本脚になり安定します ・最近足(膝)腰の調子がよくなくて気になる方 ・転ぶのが不安で外歩きを躊躇っていらっしゃる方 ・もっとよい姿勢で歩幅広く(お棺の中まで)自力で歩けるようになりたい方 ・人生の楽しみを叶えるにはまずは自立して歩けること これがはじめの一歩 そんな歩きに応えてくれるポールウォーキングの体験会です 鎌倉市民65才以上の方! 体験して続けたいと思われたら、市内サークルをご紹介します お申し込みは包括支援センター聖テレジア(写真下部)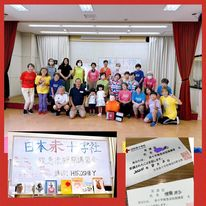 今年もスマイルチームで救急法講習会開催しました 毎年8月4日前後の日程で行っています #松田直樹を忘れない #あっぱくん #スマイルチーム #日本赤十字社
今年もスマイルチームで救急法講習会開催しました 毎年8月4日前後の日程で行っています #松田直樹を忘れない #あっぱくん #スマイルチーム #日本赤十字社 秋ですね。 今日はスマホ不携帯で渋谷教室。来週はお盆休みなので初7秒スクワットを宿題に。ポールではなくボールでも遊びました。 横浜新道が異常に渋滞🚗🚗🚗⚡したのは何かあったのでしょうか。こんな時地震が来たら怖い!と思いました。まだまだ暑いですが大巧寺は秋の気配です。
秋ですね。 今日はスマホ不携帯で渋谷教室。来週はお盆休みなので初7秒スクワットを宿題に。ポールではなくボールでも遊びました。 横浜新道が異常に渋滞🚗🚗🚗⚡したのは何かあったのでしょうか。こんな時地震が来たら怖い!と思いました。まだまだ暑いですが大巧寺は秋の気配です。 何十年ぶりかのボウリング 8月の気まポ(気ままにポール歩き)は、外歩きを避けてボウリング“体験会”としました。 みんな、何十年か前にはやったことがあるけど・・・という状態で、投げ始めは9人のうち5人がガーターを出しましたが、だんだん慣れてきて、ストライクもポツポツ出るようになり、おおいに盛り上がりました。 体の動かし方や筋肉の使い方がいつもと違うので、もしかしたら少々筋肉痛が出るかも・・・。 会場はJR中央線荻窪駅のすぐそばの「荻窪ボウル」。土日も含め、午前は1ゲーム550円と手頃です。貸靴代400円。 2ゲーム楽しんで、近所の台湾料理店でカンパイしました。 (メンバー撮影の写真もお借りしました。)
何十年ぶりかのボウリング 8月の気まポ(気ままにポール歩き)は、外歩きを避けてボウリング“体験会”としました。 みんな、何十年か前にはやったことがあるけど・・・という状態で、投げ始めは9人のうち5人がガーターを出しましたが、だんだん慣れてきて、ストライクもポツポツ出るようになり、おおいに盛り上がりました。 体の動かし方や筋肉の使い方がいつもと違うので、もしかしたら少々筋肉痛が出るかも・・・。 会場はJR中央線荻窪駅のすぐそばの「荻窪ボウル」。土日も含め、午前は1ゲーム550円と手頃です。貸靴代400円。 2ゲーム楽しんで、近所の台湾料理店でカンパイしました。 (メンバー撮影の写真もお借りしました。) 夏夜微風,揪團健走快閃活動✌️ 來到動物園,來給動物看🤣🤣 聽導覽介紹非洲象(長鼻象),大人小孩都覺得新奇有趣,好熱鬧! 祝動物園110週年快樂😁
夏夜微風,揪團健走快閃活動✌️ 來到動物園,來給動物看🤣🤣 聽導覽介紹非洲象(長鼻象),大人小孩都覺得新奇有趣,好熱鬧! 祝動物園110週年快樂😁 佐久ポールウォーキング協会より 台風一過/お盆休暇も最終日〜 〜PW散策/里山/虚空蔵山巡り〜‼️ 木々の木陰を選んでのいつものショートコース/3.5kmを48名の参加者無事完歩〜❗️ 佐久市広報10月号用取材でカメラマンも入りの緊張?した散策でした〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 台風一過/お盆休暇も最終日〜 〜PW散策/里山/虚空蔵山巡り〜‼️ 木々の木陰を選んでのいつものショートコース/3.5kmを48名の参加者無事完歩〜❗️ 佐久市広報10月号用取材でカメラマンも入りの緊張?した散策でした〜ww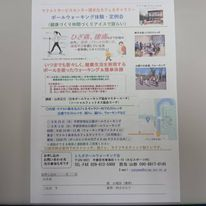 ・ヤクルト御本丸体験定例会
・ヤクルト御本丸体験定例会 午前中は材木座の長勝寺へ 午後から腰越なごやかセンターでポールウォーキング貯筋クラス 暑さに負けない元気なシニアの皆さんと7秒スクワットのあとはポールゲームでリラックス🎶 大きな声で良く笑いました。これが元気パワーのもとかも。
午前中は材木座の長勝寺へ 午後から腰越なごやかセンターでポールウォーキング貯筋クラス 暑さに負けない元気なシニアの皆さんと7秒スクワットのあとはポールゲームでリラックス🎶 大きな声で良く笑いました。これが元気パワーのもとかも。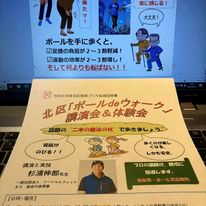 東京都北区での ポールdeウォークセッション。 毎回、シニアの皆さんの「フレイルなんて言わせないわよ!」的意気込みを感じ手応えバッチリです。 隙間時間にかつての勤務地サンシャインシティ界隈を散策。随分様子が変わりましたね。相変わらず多くの若者で賑わっていて一安心しました。
東京都北区での ポールdeウォークセッション。 毎回、シニアの皆さんの「フレイルなんて言わせないわよ!」的意気込みを感じ手応えバッチリです。 隙間時間にかつての勤務地サンシャインシティ界隈を散策。随分様子が変わりましたね。相変わらず多くの若者で賑わっていて一安心しました。 昨日、無事3回連続講座「いつでも、どこでも、誰でも、すぐにできる運動指導法」を終えることができました。 ご参加いただきました皆さん、ありがとうございました。 6月から毎月1回開催してまいりました。 これまでは、保健センターや生涯学習センター、子育て支援センターなどの自治体さんや、学校関係団体、福祉関連団体、一般企業などからお声をかけていただいて講師を務めてまいりましたが、今回は私としましては、初の主催講座でした。 募集から集金、当日の運営も全て自力ですよね。 今回はたとえ1人でも参加いただければ開催する思いで準備をしてきました。 今回は4名の皆さんのご参加いただきました。これまで関わらせていただきました自治体関係の皆さんや、トレーナー仲間や、その方からのご紹介いただいたりしてご参加いただいた皆さんでした。 自分1人の力ではできないことも、仲間の力があれば切り開けていけることを実感いたしました。 大事なことはこれを続けていくことです。 色々と改善するところもあります。 参加者の皆さんからのご意見も踏まえまして、後期に向けてまた企画してまいります。 開催の折には、ぜひみなさまご参加ください。 #運動指導法講座 #いつでもどこでも誰でもすぐにできる #保健師 #管理栄養士 #高齢者運動指導
昨日、無事3回連続講座「いつでも、どこでも、誰でも、すぐにできる運動指導法」を終えることができました。 ご参加いただきました皆さん、ありがとうございました。 6月から毎月1回開催してまいりました。 これまでは、保健センターや生涯学習センター、子育て支援センターなどの自治体さんや、学校関係団体、福祉関連団体、一般企業などからお声をかけていただいて講師を務めてまいりましたが、今回は私としましては、初の主催講座でした。 募集から集金、当日の運営も全て自力ですよね。 今回はたとえ1人でも参加いただければ開催する思いで準備をしてきました。 今回は4名の皆さんのご参加いただきました。これまで関わらせていただきました自治体関係の皆さんや、トレーナー仲間や、その方からのご紹介いただいたりしてご参加いただいた皆さんでした。 自分1人の力ではできないことも、仲間の力があれば切り開けていけることを実感いたしました。 大事なことはこれを続けていくことです。 色々と改善するところもあります。 参加者の皆さんからのご意見も踏まえまして、後期に向けてまた企画してまいります。 開催の折には、ぜひみなさまご参加ください。 #運動指導法講座 #いつでもどこでも誰でもすぐにできる #保健師 #管理栄養士 #高齢者運動指導 ~PW体験会その①~ 包括支援センターテレジア1、2 主催でポールウォーキング体験会の一回目を開催。早朝 滝のような雨音にあらあら今日は中止にするかな、とまたウトウト。次に目が覚めたときはなんとすっかり雨は上がり青空に。横の繋がりの濃い4サークル+北鎌倉紹介で お手伝いに各メンバーさんも駆けつけてくれ、さらに包括から4人もいらして会場設置やチラシも全て用意してくださいました。最初は澄まし顔だったみなさんは、顎の筋肉使いましょ!と声をだしてカウントを始めると、ぐっと活気が出て来ました。ポールの長さ合わせからストレッチ・筋トレ、インターバルウォーキングまで1時間半は楽しくあっという間。病気予防の歩き方 中之条研究の話まで。 健康の先にある楽しみ・幸せ💕のために運動を習慣化しましょう!に皆さん合点! 次回は9/5です。市民、初心者限定。
~PW体験会その①~ 包括支援センターテレジア1、2 主催でポールウォーキング体験会の一回目を開催。早朝 滝のような雨音にあらあら今日は中止にするかな、とまたウトウト。次に目が覚めたときはなんとすっかり雨は上がり青空に。横の繋がりの濃い4サークル+北鎌倉紹介で お手伝いに各メンバーさんも駆けつけてくれ、さらに包括から4人もいらして会場設置やチラシも全て用意してくださいました。最初は澄まし顔だったみなさんは、顎の筋肉使いましょ!と声をだしてカウントを始めると、ぐっと活気が出て来ました。ポールの長さ合わせからストレッチ・筋トレ、インターバルウォーキングまで1時間半は楽しくあっという間。病気予防の歩き方 中之条研究の話まで。 健康の先にある楽しみ・幸せ💕のために運動を習慣化しましょう!に皆さん合点! 次回は9/5です。市民、初心者限定。 一昨日のPWの体験会の記事を見つけました! 前を見る!が浸透していなかった写真にショック😱 最初から完璧は求めません!楽しさが一番ですね。
一昨日のPWの体験会の記事を見つけました! 前を見る!が浸透していなかった写真にショック😱 最初から完璧は求めません!楽しさが一番ですね。 2024健走杖輕旅行 【2024健走杖健康活力輕旅行】即將開始🔥 第一站 ✅9/7(六) 13:30-16:00 地點:烏來內洞森林遊樂區🌲 站長:林柏樺站長 打卡活動:https://reurl.cc/ReOGRn 歡迎各地喜愛健走的好朋友們, 共同來參與活動~ 持續追蹤粉專跟line@公告, 今年結合健康科技的joiisport app, 加入📱打卡記錄、蒐集獎章🎖️等增加活動趣味性, 凡走過必留下痕跡! 📍「2024健走杖.健康活力輕旅行」報名表:https://reurl.cc/zDr9XQ #2024健走杖健康活力輕旅行 _________________________________ 🔥【2024健走杖健康活力輕旅行】預告🔥 目前每站健走時間 ✅9/7(六) 13:30-16:00 地點:烏來內洞 森林遊樂區。 站長:林柏樺站長。 ✅9/14(六) 1 or 2 D 地點:宜蘭頭城農場 。 站長:余秋月。 ✅10/13(日) 上午 地點:嘉義公園+樹木園健走,下午可以交流分享。 站長:龔鈴智。 ✅10/18(五) 地點:新北林口民視健走+參訪。 站長:林香蘭。 ✅10/27(日) 上午 地點:未定。 站長:陳秀玲。 ✅11/19(二) 上午 地點:新竹18尖山+下午 17公里海岸 。 站長:郭玟伶。 ✅11/29(五) 下午 地點:南化玉山樂活輕旅行。 住宿:台南市(晚間有有頌缽療癒) 11/30(六) 上午 府城月老桃花滿滿輕旅行。 站長:李端木(宗翰)。 ✅12/7(六) 上午 地點:桃園平鎮站輕旅行 站長:蘇雍賀。 ✅12/8(日) 上午 地點:台中潭雅神綠園道 站長:許秀貞站長。 ✅12/7(六) 上午 地點:彰化天空步道/八卦山/扇形車庫健走杖輕旅行 站長:鄭美金站長。 陸續更新中~ ✨持續追蹤粉專跟line@公告✨
2024健走杖輕旅行 【2024健走杖健康活力輕旅行】即將開始🔥 第一站 ✅9/7(六) 13:30-16:00 地點:烏來內洞森林遊樂區🌲 站長:林柏樺站長 打卡活動:https://reurl.cc/ReOGRn 歡迎各地喜愛健走的好朋友們, 共同來參與活動~ 持續追蹤粉專跟line@公告, 今年結合健康科技的joiisport app, 加入📱打卡記錄、蒐集獎章🎖️等增加活動趣味性, 凡走過必留下痕跡! 📍「2024健走杖.健康活力輕旅行」報名表:https://reurl.cc/zDr9XQ #2024健走杖健康活力輕旅行 _________________________________ 🔥【2024健走杖健康活力輕旅行】預告🔥 目前每站健走時間 ✅9/7(六) 13:30-16:00 地點:烏來內洞 森林遊樂區。 站長:林柏樺站長。 ✅9/14(六) 1 or 2 D 地點:宜蘭頭城農場 。 站長:余秋月。 ✅10/13(日) 上午 地點:嘉義公園+樹木園健走,下午可以交流分享。 站長:龔鈴智。 ✅10/18(五) 地點:新北林口民視健走+參訪。 站長:林香蘭。 ✅10/27(日) 上午 地點:未定。 站長:陳秀玲。 ✅11/19(二) 上午 地點:新竹18尖山+下午 17公里海岸 。 站長:郭玟伶。 ✅11/29(五) 下午 地點:南化玉山樂活輕旅行。 住宿:台南市(晚間有有頌缽療癒) 11/30(六) 上午 府城月老桃花滿滿輕旅行。 站長:李端木(宗翰)。 ✅12/7(六) 上午 地點:桃園平鎮站輕旅行 站長:蘇雍賀。 ✅12/8(日) 上午 地點:台中潭雅神綠園道 站長:許秀貞站長。 ✅12/7(六) 上午 地點:彰化天空步道/八卦山/扇形車庫健走杖輕旅行 站長:鄭美金站長。 陸續更新中~ ✨持續追蹤粉專跟line@公告✨ 津田公民館 健康づくり講座 初めてでも楽しめるポールウォーキング|東京都小平市公式ホームページ
津田公民館 健康づくり講座 初めてでも楽しめるポールウォーキング|東京都小平市公式ホームページ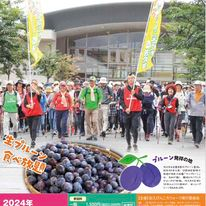 佐久ポールウォーキング協会より 〜佐久ぴんころ ウォーク〜 コロナでの中止後満を時して開催〜 9/21(土)9kmと5kmのコースを用意し、協会コーチ等もお迎えしていますので〜❗️ 「プルーン生食食べ放題」 「ジャガイモのふるまい」 「甘酒ふるまい」 「無料健康相談」〜等 内容濃い佐久の 〜食べて歩いて健康長寿〜を楽しみに〜‼️
佐久ポールウォーキング協会より 〜佐久ぴんころ ウォーク〜 コロナでの中止後満を時して開催〜 9/21(土)9kmと5kmのコースを用意し、協会コーチ等もお迎えしていますので〜❗️ 「プルーン生食食べ放題」 「ジャガイモのふるまい」 「甘酒ふるまい」 「無料健康相談」〜等 内容濃い佐久の 〜食べて歩いて健康長寿〜を楽しみに〜‼️ 資格取得セミナー
資格取得セミナー 2024 第3回中山道 馬籠宿夜明け前ウォーキングを11月10日に開催します。 今年も参加賞はTシャツだ。どっど〜ん❗️と太っ腹だね。
2024 第3回中山道 馬籠宿夜明け前ウォーキングを11月10日に開催します。 今年も参加賞はTシャツだ。どっど〜ん❗️と太っ腹だね。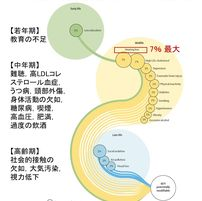 Lancet認知症委員会は定期的にエビデンスに基づいた認知症予防についての情報を報告していますが,前回の2020年の報告に最近の4年間の系統的レビューやメタ解析論文を追加して改訂がなされました(認知症に対する聴力障害とうつ病のリスクに関するメタ解析が完了されています).以下,2024年報告の要点です.
Lancet認知症委員会は定期的にエビデンスに基づいた認知症予防についての情報を報告していますが,前回の2020年の報告に最近の4年間の系統的レビューやメタ解析論文を追加して改訂がなされました(認知症に対する聴力障害とうつ病のリスクに関するメタ解析が完了されています).以下,2024年報告の要点です. 感染症がアルツハイマー病などの認知症の発症と関連することが注目されていますが,そのメカニズムは不明です.最新号のNature Aging誌に以下を示した研究が報告されています.
感染症がアルツハイマー病などの認知症の発症と関連することが注目されていますが,そのメカニズムは不明です.最新号のNature Aging誌に以下を示した研究が報告されています.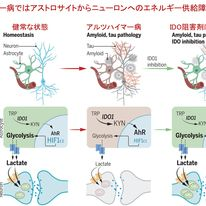 アルツハイマー病(AD)において脳内に蓄積するアミロイドβがなぜ最終的に認知症を来すのかいくつかの仮説はあるもののよく分かっていませんでした.非常に興味深い研究がスタンフォード大学からScience誌に報告されました.この研究では,記憶を司る海馬におけるグルコース代謝に注目しました.具体的には,インドールアミン-2,3-ジオキシゲナーゼ1(IDO1)という酵素に着目しています.IDO1はトリプトファン(TRP)をキヌレニン(KYN)に変換する際の律速酵素です.このKYNはアリールハイドロカーボン受容体(AhR)との相互作用を通じて,炎症や腫瘍において免疫抑制を引き起こす代謝物だそうですが,同時に「アストロサイトにおける糖代謝を抑制する作用」があります.アストロサイトは通常,解糖系により,ニューロンにエネルギーを供給するための乳酸を生成し,ニューロンのシナプス活動を支えていますが,KYNがこれを抑制してしまうことを示しています.
アルツハイマー病(AD)において脳内に蓄積するアミロイドβがなぜ最終的に認知症を来すのかいくつかの仮説はあるもののよく分かっていませんでした.非常に興味深い研究がスタンフォード大学からScience誌に報告されました.この研究では,記憶を司る海馬におけるグルコース代謝に注目しました.具体的には,インドールアミン-2,3-ジオキシゲナーゼ1(IDO1)という酵素に着目しています.IDO1はトリプトファン(TRP)をキヌレニン(KYN)に変換する際の律速酵素です.このKYNはアリールハイドロカーボン受容体(AhR)との相互作用を通じて,炎症や腫瘍において免疫抑制を引き起こす代謝物だそうですが,同時に「アストロサイトにおける糖代謝を抑制する作用」があります.アストロサイトは通常,解糖系により,ニューロンにエネルギーを供給するための乳酸を生成し,ニューロンのシナプス活動を支えていますが,KYNがこれを抑制してしまうことを示しています.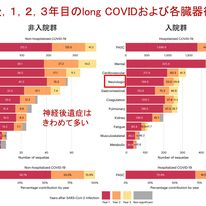 今回のキーワードは,3年間の追跡調査で死亡率と後遺症発症リスクは低下したが,入院した重症患者では依然高値である,感染後1年間のPASC発生率は経過的に減少しているが,オミクロン期のワクチン接種者においても依然として高い,long COVIDを発症しやすく,回復しにくい9つの要因,long COVIDでは持続感染により,腸管や脊髄におけるT細胞の活性化が生じている,long COVIDに伴う認知機能低下と関連する要因は,急性期重症,6ヵ月時の認知機能障害,高血圧である,COVID-19は若年成人の難聴および突発性感音難聴のリスク因子である,です.
今回のキーワードは,3年間の追跡調査で死亡率と後遺症発症リスクは低下したが,入院した重症患者では依然高値である,感染後1年間のPASC発生率は経過的に減少しているが,オミクロン期のワクチン接種者においても依然として高い,long COVIDを発症しやすく,回復しにくい9つの要因,long COVIDでは持続感染により,腸管や脊髄におけるT細胞の活性化が生じている,long COVIDに伴う認知機能低下と関連する要因は,急性期重症,6ヵ月時の認知機能障害,高血圧である,COVID-19は若年成人の難聴および突発性感音難聴のリスク因子である,です.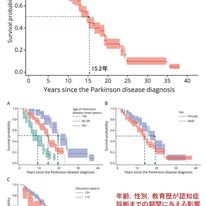 パーキンソン病(PD)患者では最大80%で認知症が発症すると言われてきました.よく引用されるノルウェーの報告では8年間で78%,オーストラリアの報告では20年間で83%の発症率でした.しかしこれらは20年以上前に発表されたもので,かつ症例数も224人および136人と少ない報告でした.今回,Neurology誌に米国からPD患者の認知症リスクを検討した研究が報告されました.大規模前向き観察研究のPPMI(多施設共同国際研究)と,ペンシルバニア大学(Penn)のPD研究コホートのデータを用いています.
パーキンソン病(PD)患者では最大80%で認知症が発症すると言われてきました.よく引用されるノルウェーの報告では8年間で78%,オーストラリアの報告では20年間で83%の発症率でした.しかしこれらは20年以上前に発表されたもので,かつ症例数も224人および136人と少ない報告でした.今回,Neurology誌に米国からPD患者の認知症リスクを検討した研究が報告されました.大規模前向き観察研究のPPMI(多施設共同国際研究)と,ペンシルバニア大学(Penn)のPD研究コホートのデータを用いています.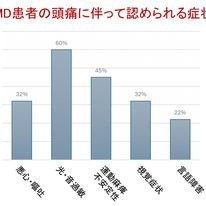 近年,欧米において機能性神経障害(functional neurological disorder; FND)の疾患概念が確立し,適切な診断および治療について盛んに検討が行われています.本邦でも,徐々にその理解が進んでいるものの十分とは言えず,その啓発は今後の重要な課題と言えます.FNDのひとつ,機能性運動異常症(functional movement disorder; FMD)に関して興味深い論文が2報ありましたのでご紹介します.
近年,欧米において機能性神経障害(functional neurological disorder; FND)の疾患概念が確立し,適切な診断および治療について盛んに検討が行われています.本邦でも,徐々にその理解が進んでいるものの十分とは言えず,その啓発は今後の重要な課題と言えます.FNDのひとつ,機能性運動異常症(functional movement disorder; FMD)に関して興味深い論文が2報ありましたのでご紹介します.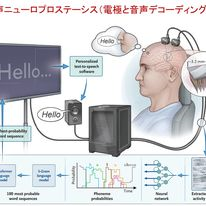 最新のNew Eng J Med誌にALSにおけるBCI技術に関する印象的な論文が3つ掲載されています.この治療は今後きわめて重要で,本邦でも脳外科,工学との連携を進め,極力早期に実現すべきと強く思いました.
最新のNew Eng J Med誌にALSにおけるBCI技術に関する印象的な論文が3つ掲載されています.この治療は今後きわめて重要で,本邦でも脳外科,工学との連携を進め,極力早期に実現すべきと強く思いました.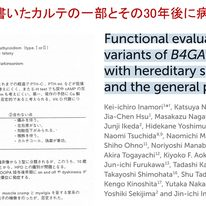 3年ほど前に,小脳失調症の研究でご一緒させていただいている信州大学中村勝哉先生から,信州大学で診療している患者さんの学会発表の共同演者になってほしいというお話をいただきました.症例は家族性痙性対麻痺SPG26の原因遺伝子であるB4GALNT1に新規ミスセンス変異があることが判明した44歳女性です.なぜ私が共同演者になるのか思い当たることがありませんでしたが,お話を伺うと,20歳時に信州大学に入院歴があり,そのカルテを調べたところ,なんと私の書いた入院サマリーが出てきて,これまでの経過を理解するのに役に立ったということでした.患者さんが17歳のときに,脳神経内科医1年目の私が新潟の市中病院で主治医となり,その後,長野県に転居されたということです.
3年ほど前に,小脳失調症の研究でご一緒させていただいている信州大学中村勝哉先生から,信州大学で診療している患者さんの学会発表の共同演者になってほしいというお話をいただきました.症例は家族性痙性対麻痺SPG26の原因遺伝子であるB4GALNT1に新規ミスセンス変異があることが判明した44歳女性です.なぜ私が共同演者になるのか思い当たることがありませんでしたが,お話を伺うと,20歳時に信州大学に入院歴があり,そのカルテを調べたところ,なんと私の書いた入院サマリーが出てきて,これまでの経過を理解するのに役に立ったということでした.患者さんが17歳のときに,脳神経内科医1年目の私が新潟の市中病院で主治医となり,その後,長野県に転居されたということです. 標題の鼎談をさせていただいたBrain Nerve誌8月号が発刊されました.今月号の特集は「Common diseaseは神経学の主戦場である revisited」です.2013年9月号に「Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望」という特集が組まれました.脳神経内科というと「難解で,治らない病気を診ている特殊な集団」というイメージを持たれている人もいるかもしれませんが,実は脳卒中,認知症,てんかん,頭痛,めまいといった,いわゆるcommon diseaseを最も多く診ている,あるいは診ることを期待されている診療科でもあります.この特集号ではこれらの多数の患者さんを実際にどの診療科が引き受けているのか,診療が不十分な原因は何か,脳神経内科が解決すべき課題は何かなどを議論しています.日本神経学会では西山和利代表理事が中心となり,common diseaseの診療レベルの向上を目指し,特別教育研修会(脳卒中・てんかん・頭痛・認知症コース)などの取り組みを行っていますが,前回の特集号から10年が経過してどのような状況になっているかを編集委員の3名が議論いたしました.
標題の鼎談をさせていただいたBrain Nerve誌8月号が発刊されました.今月号の特集は「Common diseaseは神経学の主戦場である revisited」です.2013年9月号に「Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望」という特集が組まれました.脳神経内科というと「難解で,治らない病気を診ている特殊な集団」というイメージを持たれている人もいるかもしれませんが,実は脳卒中,認知症,てんかん,頭痛,めまいといった,いわゆるcommon diseaseを最も多く診ている,あるいは診ることを期待されている診療科でもあります.この特集号ではこれらの多数の患者さんを実際にどの診療科が引き受けているのか,診療が不十分な原因は何か,脳神経内科が解決すべき課題は何かなどを議論しています.日本神経学会では西山和利代表理事が中心となり,common diseaseの診療レベルの向上を目指し,特別教育研修会(脳卒中・てんかん・頭痛・認知症コース)などの取り組みを行っていますが,前回の特集号から10年が経過してどのような状況になっているかを編集委員の3名が議論いたしました.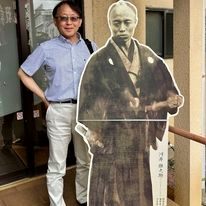 夏休みを自宅のある新潟で過ごしました.長岡市にある河井継之助記念館と山本五十六記念館を訪ねました.河井継之助(1827-1868)は幕末の越後長岡藩の家老で,戊辰戦争では長岡藩を率いました.山本五十六(1884-1943)は太平洋戦争時の連合艦隊司令長官で,真珠湾攻撃をはじめとする多くの作戦を指揮しました.長岡市が生んだふたりの共通点は,最後まで戦争に反対しながらも,戦争の旗頭に立たざるを得なかったことかと思います.
夏休みを自宅のある新潟で過ごしました.長岡市にある河井継之助記念館と山本五十六記念館を訪ねました.河井継之助(1827-1868)は幕末の越後長岡藩の家老で,戊辰戦争では長岡藩を率いました.山本五十六(1884-1943)は太平洋戦争時の連合艦隊司令長官で,真珠湾攻撃をはじめとする多くの作戦を指揮しました.長岡市が生んだふたりの共通点は,最後まで戦争に反対しながらも,戦争の旗頭に立たざるを得なかったことかと思います.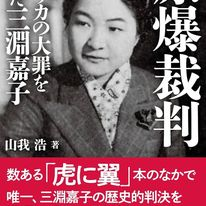 久しぶりにNHK朝ドラを見ています.『虎に翼』です.今週,主人公の寅子が「原爆裁判」に関わる場面が描かれていますが,しばらく前に書店で標題の本(https://amzn.to/4fWyzT4)を見つけました.寅子のモデルである三淵嘉子さんは第1回の口頭弁論から結審に至るまでの8年間,審理を担当しました.本の最後に判決文全文がありますが,そのなかで「原爆投下は国際法違反」と明言,さらに「政治の貧困を嘆かずにはおられない」と日本政府を批判し,被爆者への支援策を強く促しました.いまだロシアがウクライナへの侵攻で核兵器の使用をちらつかせる状況ですので,核兵器の使用が国際法に違反すると明確に述べた判決が持つ意義は現代においても大きいと思います.
久しぶりにNHK朝ドラを見ています.『虎に翼』です.今週,主人公の寅子が「原爆裁判」に関わる場面が描かれていますが,しばらく前に書店で標題の本(https://amzn.to/4fWyzT4)を見つけました.寅子のモデルである三淵嘉子さんは第1回の口頭弁論から結審に至るまでの8年間,審理を担当しました.本の最後に判決文全文がありますが,そのなかで「原爆投下は国際法違反」と明言,さらに「政治の貧困を嘆かずにはおられない」と日本政府を批判し,被爆者への支援策を強く促しました.いまだロシアがウクライナへの侵攻で核兵器の使用をちらつかせる状況ですので,核兵器の使用が国際法に違反すると明確に述べた判決が持つ意義は現代においても大きいと思います. 研究をする理由 ―若い研究者,医師,そして医学生にぜひ見ていただきたい動画―
研究をする理由 ―若い研究者,医師,そして医学生にぜひ見ていただきたい動画― 屋根より高い鯉のぼり🎏 ゴールデンウィーク 2日目は青空を仰ぎ、そよ風に吹かれながらの逗子PWサークル。新緑が眩しいほどキラキラ光っています。ゴールの椿公園前のお宅は今年も白・紫の藤が豪華に美しく爽やかな5月を五感で味わいました。
屋根より高い鯉のぼり🎏 ゴールデンウィーク 2日目は青空を仰ぎ、そよ風に吹かれながらの逗子PWサークル。新緑が眩しいほどキラキラ光っています。ゴールの椿公園前のお宅は今年も白・紫の藤が豪華に美しく爽やかな5月を五感で味わいました。 朝の北鎌倉 筋トレ教室 昨日の暑さは何処へやら 肌寒く雨の1日です 高齢者グループは1人ずつスクワットの動画を撮って鑑賞会(!?) 後ろに便座椅子を用意したら皆さん目線は前、お尻をひいて素晴らしい出来映えでした。 お土産に町内会で先日配布のベニバナ3鉢ずつ頂きました。 帰り道は敢えて階段コースを通って「歩くと筋トレ」。そのまま円覚寺に行きました。
朝の北鎌倉 筋トレ教室 昨日の暑さは何処へやら 肌寒く雨の1日です 高齢者グループは1人ずつスクワットの動画を撮って鑑賞会(!?) 後ろに便座椅子を用意したら皆さん目線は前、お尻をひいて素晴らしい出来映えでした。 お土産に町内会で先日配布のベニバナ3鉢ずつ頂きました。 帰り道は敢えて階段コースを通って「歩くと筋トレ」。そのまま円覚寺に行きました。 佐久ポールウォーキング協会より 5月PW駒場例会〜お疲れ様でした。 連休の最中の定例会に60名もの参加者で体験コース、健脚3コースに別れ公園内や牧場〜真っ黄色の菜の花畑の散策やらとPW闊歩でした。 公園一周が毎日の日課❓の92歳のP-ウォークに出会えたり弓道大会中でいつもより賑やかな駒場公園❗️ 次回5/19は〜東御市・八重原/明神池散策を地元の依田コーチの案内で開催です。ご参加よろしく願います🤲
佐久ポールウォーキング協会より 5月PW駒場例会〜お疲れ様でした。 連休の最中の定例会に60名もの参加者で体験コース、健脚3コースに別れ公園内や牧場〜真っ黄色の菜の花畑の散策やらとPW闊歩でした。 公園一周が毎日の日課❓の92歳のP-ウォークに出会えたり弓道大会中でいつもより賑やかな駒場公園❗️ 次回5/19は〜東御市・八重原/明神池散策を地元の依田コーチの案内で開催です。ご参加よろしく願います🤲 【暑熱順化】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜コースは海老川ロード 今からしっかり歩き 汗をかいて 熱中症予防対策をしましょう〜 動画撮影を早めて #フォームチェック
【暑熱順化】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜コースは海老川ロード 今からしっかり歩き 汗をかいて 熱中症予防対策をしましょう〜 動画撮影を早めて #フォームチェック 【嬉しいコメントを頂きました】 ‘24.5/1日(水)〜5/31日(金) 船橋駅前フエイエス 5F 船橋ウォーキング・ソサイエティの 活動をパネル展示しております 会員さんからのコメントが入りました 原文のまま紹介させて頂きます 〘せっかくなので、拝見しての感想を書かせていただきます。 うろ覚えのところもあるので、ご容赦いただくとして、初めての方がご覧になる折、「遠足あり」も魅力に映るだろうと思いましたが(書いてありましたよね?)、ただ集まって歩くだけではなく、スタッフの皆様のきめ細かなプランニングとご指導があることも大きな魅力であり、それを打ち出されるのも良いと思いました。 また、歩くだけではなく、ストレッチや筋トレもあり、定期的に実施している体力測定や動画撮影によるチェックの機会の提供もあることで、パフォーマンスの維持とさらなる向上に努められる点も大きな魅力だと思います。 また、毎回の活動の記録をWebで振り返れることも、かなり丁寧なフォローであり、私はありがたいと思っています。世の中には、毎回、やっておしまいで、蓄積のない活動も多いのではないでしょうか。 暑熱順化などの情報提供もありがたく、 心と身体の健やかさを目指す、総合的な活動だなあと思っているところです。 スタッフの皆様が自分達で書くのも手前味噌感があるようなら、「会員の声」として使えるところをお使いいただいたらよく、そのことで、より多くの方が、FWSの魅力を知る一助となると良いなと思った次第です。改めてスタッフの皆様、いつもありがとうございます〙 コメントが率直に嬉しいです
【嬉しいコメントを頂きました】 ‘24.5/1日(水)〜5/31日(金) 船橋駅前フエイエス 5F 船橋ウォーキング・ソサイエティの 活動をパネル展示しております 会員さんからのコメントが入りました 原文のまま紹介させて頂きます 〘せっかくなので、拝見しての感想を書かせていただきます。 うろ覚えのところもあるので、ご容赦いただくとして、初めての方がご覧になる折、「遠足あり」も魅力に映るだろうと思いましたが(書いてありましたよね?)、ただ集まって歩くだけではなく、スタッフの皆様のきめ細かなプランニングとご指導があることも大きな魅力であり、それを打ち出されるのも良いと思いました。 また、歩くだけではなく、ストレッチや筋トレもあり、定期的に実施している体力測定や動画撮影によるチェックの機会の提供もあることで、パフォーマンスの維持とさらなる向上に努められる点も大きな魅力だと思います。 また、毎回の活動の記録をWebで振り返れることも、かなり丁寧なフォローであり、私はありがたいと思っています。世の中には、毎回、やっておしまいで、蓄積のない活動も多いのではないでしょうか。 暑熱順化などの情報提供もありがたく、 心と身体の健やかさを目指す、総合的な活動だなあと思っているところです。 スタッフの皆様が自分達で書くのも手前味噌感があるようなら、「会員の声」として使えるところをお使いいただいたらよく、そのことで、より多くの方が、FWSの魅力を知る一助となると良いなと思った次第です。改めてスタッフの皆様、いつもありがとうございます〙 コメントが率直に嬉しいです 2024.5.3〜4 活動記録 ☺︎青空ポールウォーキング 9名 ☺︎活き活き中屋敷デュアルエクササイズ 14名 ☺︎相模原市文化協会祭ポンポン準備 ☺︎相模原市文化協会祭練習用音源作成
2024.5.3〜4 活動記録 ☺︎青空ポールウォーキング 9名 ☺︎活き活き中屋敷デュアルエクササイズ 14名 ☺︎相模原市文化協会祭ポンポン準備 ☺︎相模原市文化協会祭練習用音源作成 すっかり忘れていたけど、WBSで取り上げられたんだった😊
すっかり忘れていたけど、WBSで取り上げられたんだった😊 雨☔ 雨🌂 雨☔ のため広町緑地の楽しみにしていた大桐の花ツアーは中止。行政センターで座学とPWストレッチ・筋トレと俄スマホLINE教室※に変更になってしまいました。 来年こそは👊✨ 写真は雨に濡れた庭の花達 ※ グループLINEの場合 コメントをいれなくても誰の既読かわかる方法について
雨☔ 雨🌂 雨☔ のため広町緑地の楽しみにしていた大桐の花ツアーは中止。行政センターで座学とPWストレッチ・筋トレと俄スマホLINE教室※に変更になってしまいました。 来年こそは👊✨ 写真は雨に濡れた庭の花達 ※ グループLINEの場合 コメントをいれなくても誰の既読かわかる方法について 今年度より、岩手医科大学の非常勤講師に就任しました!今日は、初の授業。教師を目指した時期もあるので、感慨深いです。 1年生を担当しましたが、わ、若い! 普段、中高年の指導が多いので、逆に緊張。 ひとまず初回の講義、無事終えて、ホッ✨
今年度より、岩手医科大学の非常勤講師に就任しました!今日は、初の授業。教師を目指した時期もあるので、感慨深いです。 1年生を担当しましたが、わ、若い! 普段、中高年の指導が多いので、逆に緊張。 ひとまず初回の講義、無事終えて、ホッ✨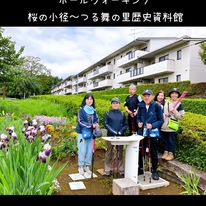 20240509。 ポールウォーキング。 桜の小径〜つる舞の里歴史資料館。 雨上がり、行ける人だけで決行‼️
20240509。 ポールウォーキング。 桜の小径〜つる舞の里歴史資料館。 雨上がり、行ける人だけで決行‼️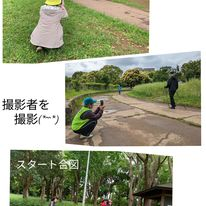 【天気予報を信じて】 2024/5/9 ジェットコースターみたいな天気です 朝は寒い雨 天気回復を願って集合! 「来て良かった〜」と 嬉しい声が聞けました〜♬ 動画撮影&この夏の熱中症対策 (暑熱馴化パネル説明) チームワークバッチリで進行! (動画撮影はいつも喜ばれます) (*^^*) \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜行田公園 #歩容はどうかなと動画撮影 #暑熱馴化で熱中症予防です
【天気予報を信じて】 2024/5/9 ジェットコースターみたいな天気です 朝は寒い雨 天気回復を願って集合! 「来て良かった〜」と 嬉しい声が聞けました〜♬ 動画撮影&この夏の熱中症対策 (暑熱馴化パネル説明) チームワークバッチリで進行! (動画撮影はいつも喜ばれます) (*^^*) \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜行田公園 #歩容はどうかなと動画撮影 #暑熱馴化で熱中症予防です 🐎 🎠 ? 渋谷PW教室が終わってニトリで母の施設のための買い物をして駅に向かう途中で 遭遇! 競馬会のイベントだったようです🎪 お花を貰ったり 馬にのせて貰ったり にわか 渋谷遊園地でした♪
🐎 🎠 ? 渋谷PW教室が終わってニトリで母の施設のための買い物をして駅に向かう途中で 遭遇! 競馬会のイベントだったようです🎪 お花を貰ったり 馬にのせて貰ったり にわか 渋谷遊園地でした♪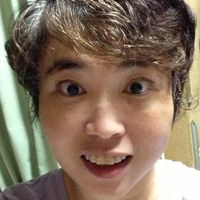 【チョコザップのピラティス】 ピラティスマシン導入と聞いて、 再入会キャンペーンでチョコザップ復帰!今日ピラティスしてきましたよ😊 正直、リフォーマー(ピラティスマシン)を使った事ないと最初はかなり戸惑うと思うけど、慣れれば簡単! 経験者にはとてもお得!(自分はリフォーマー経験者) マシントレーニングより効率良いですよ。 ピラティスは元々リハビリの為にできた運動法。自分には合ってます! マシンピラティスに興味がある人はどうぞ! 5/15まで入会キャンペーン中 私の友達紹介コード「THI8862I」を入れて契約すると毎月300円OFF! RIZAP監修の24時間ジムchocoZAP ▼今すぐチェックする https://chocozap.jp https://second-effort.com/gym/chocozap-pilates/
【チョコザップのピラティス】 ピラティスマシン導入と聞いて、 再入会キャンペーンでチョコザップ復帰!今日ピラティスしてきましたよ😊 正直、リフォーマー(ピラティスマシン)を使った事ないと最初はかなり戸惑うと思うけど、慣れれば簡単! 経験者にはとてもお得!(自分はリフォーマー経験者) マシントレーニングより効率良いですよ。 ピラティスは元々リハビリの為にできた運動法。自分には合ってます! マシンピラティスに興味がある人はどうぞ! 5/15まで入会キャンペーン中 私の友達紹介コード「THI8862I」を入れて契約すると毎月300円OFF! RIZAP監修の24時間ジムchocoZAP ▼今すぐチェックする https://chocozap.jp https://second-effort.com/gym/chocozap-pilates/ 東御市のwalkイベントに参加して来ました。他所のイベント参加は数年ぶりで気ら〜くな時間を過ごさせて頂きました〜ww 「雷電」の道の駅や生家を訪れるコースで参加者約150名/7km・2時間のウォークでした。 来年も有るそうです〜❗️
東御市のwalkイベントに参加して来ました。他所のイベント参加は数年ぶりで気ら〜くな時間を過ごさせて頂きました〜ww 「雷電」の道の駅や生家を訪れるコースで参加者約150名/7km・2時間のウォークでした。 来年も有るそうです〜❗️ ポールdeウォーク推進コーディネーター養成講座札幌会場!! 13名のコーディネーターが誕生しました☺️ 北の大地で新たな展開が始まります‼️
ポールdeウォーク推進コーディネーター養成講座札幌会場!! 13名のコーディネーターが誕生しました☺️ 北の大地で新たな展開が始まります‼️ LINK国立のリレーチームです。午後からのポールdeエクササイズのメンバーもいます。午後から顔を洗って(稼業から足も洗って)チームを引っ張ってくれました。流石疲れ知らずで感心尊敬!
LINK国立のリレーチームです。午後からのポールdeエクササイズのメンバーもいます。午後から顔を洗って(稼業から足も洗って)チームを引っ張ってくれました。流石疲れ知らずで感心尊敬! Team DOing 今年も「LINKくにたち」 で楽しませていただきました。 メンバーも増えてとても活気ある楽しいチームになりました😃 みんな愉快な時遊人🥰 北海道から、新潟からも参加してくれるパワー溢れるメンバーです。 みんなで楽しいことを企画しましょう😃仲間募集中です♪ #LINKくにたち #TeamDOing #楽しい仲間たち
Team DOing 今年も「LINKくにたち」 で楽しませていただきました。 メンバーも増えてとても活気ある楽しいチームになりました😃 みんな愉快な時遊人🥰 北海道から、新潟からも参加してくれるパワー溢れるメンバーです。 みんなで楽しいことを企画しましょう😃仲間募集中です♪ #LINKくにたち #TeamDOing #楽しい仲間たち 佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会のブロック研修会〜 今年も始まりました。 2年@の任期で「健康」についての活動の中で、ポール使ったウォーキング体験をしPWを知って普及させて貰う企画です。 5月中に総勢700名(実質受講者約400名)14会場を3コーチで廻ります。各会場殆ど初めての方ばかりでコーチングのしがいのある体験会です。
佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会のブロック研修会〜 今年も始まりました。 2年@の任期で「健康」についての活動の中で、ポール使ったウォーキング体験をしPWを知って普及させて貰う企画です。 5月中に総勢700名(実質受講者約400名)14会場を3コーチで廻ります。各会場殆ど初めての方ばかりでコーチングのしがいのある体験会です。 「UR幸町ポールウォーキング体験会」 2024/5/14 渡邊東コーチ(日本ポールウォーキングマスターコーチプロ)に引き継いで初めての体験会。 伝えたい気持がビンビン 渡邊コーチの熱気が溢れる体験会になりました。
「UR幸町ポールウォーキング体験会」 2024/5/14 渡邊東コーチ(日本ポールウォーキングマスターコーチプロ)に引き継いで初めての体験会。 伝えたい気持がビンビン 渡邊コーチの熱気が溢れる体験会になりました。 河川環境楽園オアシスパークの定期講習会 今日は熱中症対策講義とエクササイズを井上指導員に任せ 80歳と84歳のお二人と共に園内を2本のポールで 楽しくウォーキングしました。 84歳の方はこれで4回目でかなり歩行姿勢が変わってきました。 ポールの力ってほんと凄いと感じました。
河川環境楽園オアシスパークの定期講習会 今日は熱中症対策講義とエクササイズを井上指導員に任せ 80歳と84歳のお二人と共に園内を2本のポールで 楽しくウォーキングしました。 84歳の方はこれで4回目でかなり歩行姿勢が変わってきました。 ポールの力ってほんと凄いと感じました。 渋谷から駒沢~自由が丘~帰鎌 渋谷教室には原宿リハビリテーション病院から見学あり。 1時間参加されて ポールの効力・驚愕・感想をいただきました。 ・何より良い姿勢keep ! ・ポールの使用で運動の意識が高まり それを自覚できる(ex.相撲スクワット) ・転倒予防、踏み出し拡大 ポールをリハビリにも生かして行きたいとのことでした。
渋谷から駒沢~自由が丘~帰鎌 渋谷教室には原宿リハビリテーション病院から見学あり。 1時間参加されて ポールの効力・驚愕・感想をいただきました。 ・何より良い姿勢keep ! ・ポールの使用で運動の意識が高まり それを自覚できる(ex.相撲スクワット) ・転倒予防、踏み出し拡大 ポールをリハビリにも生かして行きたいとのことでした。 気持ち良い天気☀️ 2回目のみなとみらいポールウォーキング教室にはステッキ工房のショップ店長さんも参加してくださいました。 ステッキ工房でポールを購入され初めて使ってみる方。 ノルディックポールを購入された方も参加してくださったので、今日はどちらのポールの使い方、歩き方も皆さんと一緒に行いました。 「なるほど!」と皆さん大満足でした。どちらも有りですね。 最後は「もしもし亀よ」を歌いながら簡単ポールdeエクササイズで笑顔で終了🤗 密度の濃い充実した時間となりました。 #みなとみらい #ステッキ工房 #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング
気持ち良い天気☀️ 2回目のみなとみらいポールウォーキング教室にはステッキ工房のショップ店長さんも参加してくださいました。 ステッキ工房でポールを購入され初めて使ってみる方。 ノルディックポールを購入された方も参加してくださったので、今日はどちらのポールの使い方、歩き方も皆さんと一緒に行いました。 「なるほど!」と皆さん大満足でした。どちらも有りですね。 最後は「もしもし亀よ」を歌いながら簡単ポールdeエクササイズで笑顔で終了🤗 密度の濃い充実した時間となりました。 #みなとみらい #ステッキ工房 #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング 【バラの香りにうっとり】 2024/5/18 まだ5月なのに真夏到来〜? 気分ルルルンでポールでウォーキング 目的地は百花繚乱「大石ガーデン」 途中のアップ・ダウンに富んだコース ポールがあるとやっぱり楽に歩けます #船橋ウォーキングソサイエティ #大人のミニ遠足 #丸山の森緑地〜#藤原市民の森〜#大石ガーデン #2本のポールを使うウォーキング #暑熱馴化
【バラの香りにうっとり】 2024/5/18 まだ5月なのに真夏到来〜? 気分ルルルンでポールでウォーキング 目的地は百花繚乱「大石ガーデン」 途中のアップ・ダウンに富んだコース ポールがあるとやっぱり楽に歩けます #船橋ウォーキングソサイエティ #大人のミニ遠足 #丸山の森緑地〜#藤原市民の森〜#大石ガーデン #2本のポールを使うウォーキング #暑熱馴化 昨日のシナノ工場祭の様子。550名の皆様にご参加頂きました!ご来場ありがとうございました(^^) 開場前から多くの方が並んでいただき、アウトレット商品前が大繁盛。予想以上だったためレジに列ができてしまい、オペレーションは来年への課題です。アルミパイプを使ったクラフト製作も家族連れのお客様に好評でした。最高の天気、笑顔で接客する社員、そして笑顔のお客様!良かったです!!
昨日のシナノ工場祭の様子。550名の皆様にご参加頂きました!ご来場ありがとうございました(^^) 開場前から多くの方が並んでいただき、アウトレット商品前が大繁盛。予想以上だったためレジに列ができてしまい、オペレーションは来年への課題です。アルミパイプを使ったクラフト製作も家族連れのお客様に好評でした。最高の天気、笑顔で接客する社員、そして笑顔のお客様!良かったです!! 2024.5.15〜18 ☺︎健康体操サークル 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 21名 ☺︎スマイルエクササイズ上鶴間 10名 ☺︎公民館抽選申し込み5団体分 ☺︎スマイルTシャツ再々注文 ☺︎スマイルチーム上溝担当CSWと打ち合わせ ☺︎スマイルチーム上溝シニアサポート活動担当包括支援センター職員と打合せ ☺︎光が丘公民館利用団体総会(欠席、委任状提出) ☺︎相模原市文化協会総会(欠席) ☺︎上鶴間包括支援センターポールウォーキングフォローアップ教室講師依頼、打合せ ☺︎上溝包括支援センターポールウォーキング&エクササイズ介護予防教室3回コース講師依頼、打合せ ☺︎上鶴間公民館パパ&キッズ体操教室講師依頼、打合せ
2024.5.15〜18 ☺︎健康体操サークル 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 21名 ☺︎スマイルエクササイズ上鶴間 10名 ☺︎公民館抽選申し込み5団体分 ☺︎スマイルTシャツ再々注文 ☺︎スマイルチーム上溝担当CSWと打ち合わせ ☺︎スマイルチーム上溝シニアサポート活動担当包括支援センター職員と打合せ ☺︎光が丘公民館利用団体総会(欠席、委任状提出) ☺︎相模原市文化協会総会(欠席) ☺︎上鶴間包括支援センターポールウォーキングフォローアップ教室講師依頼、打合せ ☺︎上溝包括支援センターポールウォーキング&エクササイズ介護予防教室3回コース講師依頼、打合せ ☺︎上鶴間公民館パパ&キッズ体操教室講師依頼、打合せ ネモフィラ、滑り込みセーフ 世界ノルディックウォーキングデーの今日(5月19日)、国営昭和記念公園でたくさんの花を見ながら、新里るりさんの会でポール歩きしました。 ネモフィラはそろそろ終わりですが、まだ楽しめました。 集合写真は、たまたま通りかかったプロカメラマンがシャッターを押してくれてラッキーでした。モデル撮影の合間だったようです。 多種の花、日本庭園、古民家、盆栽コーナーなどたくさんの顔を持つ昭和記念公園。お勧めです。
ネモフィラ、滑り込みセーフ 世界ノルディックウォーキングデーの今日(5月19日)、国営昭和記念公園でたくさんの花を見ながら、新里るりさんの会でポール歩きしました。 ネモフィラはそろそろ終わりですが、まだ楽しめました。 集合写真は、たまたま通りかかったプロカメラマンがシャッターを押してくれてラッキーでした。モデル撮影の合間だったようです。 多種の花、日本庭園、古民家、盆栽コーナーなどたくさんの顔を持つ昭和記念公園。お勧めです。 佐久ポールウォーキング協会より 本日は「ブランド米・八重原米」の産地・東御/八重原・明神池PW散策でした。 地元コーチ(依田MC pro)の案内で3池(明神池〜新池〜大工池)を巡っての約4km・田植えの始まったアップダウンコースでした。 会員の他八重原地元の方々やわざわざ埼玉からのご夫婦も参加頂き70名越えの集まりとなりました。 我孫子(千葉県)より長岡MC proも視察❓調査?兼ね駆け付け賑やか❗️かつ楽しい❗️つどいとなりました。 ランチは池の辺りに有る「まる屋さん」地産地消いっぱいの日替わりランチ❗️ 皆様ご参加ありがとうございました。
佐久ポールウォーキング協会より 本日は「ブランド米・八重原米」の産地・東御/八重原・明神池PW散策でした。 地元コーチ(依田MC pro)の案内で3池(明神池〜新池〜大工池)を巡っての約4km・田植えの始まったアップダウンコースでした。 会員の他八重原地元の方々やわざわざ埼玉からのご夫婦も参加頂き70名越えの集まりとなりました。 我孫子(千葉県)より長岡MC proも視察❓調査?兼ね駆け付け賑やか❗️かつ楽しい❗️つどいとなりました。 ランチは池の辺りに有る「まる屋さん」地産地消いっぱいの日替わりランチ❗️ 皆様ご参加ありがとうございました。 美濃白川 道の駅ウォーキング2024 5/12・5/19 開催 道の駅清流白川クオーレの里をバスで海抜862mの金幣社大白山神社へ向かう。 約1300年前に白山大神様が祀られた神社⛩️からスタート、9kmのコースを攻略しました。 途中の新田製茶さんで白川茶の試飲とお茶スイーツをいただきゴールを目指す。 ゴールでは美味しいお弁当を食べて大満足。 2本のポールと共に楽しくウォーキングしました。‼️
美濃白川 道の駅ウォーキング2024 5/12・5/19 開催 道の駅清流白川クオーレの里をバスで海抜862mの金幣社大白山神社へ向かう。 約1300年前に白山大神様が祀られた神社⛩️からスタート、9kmのコースを攻略しました。 途中の新田製茶さんで白川茶の試飲とお茶スイーツをいただきゴールを目指す。 ゴールでは美味しいお弁当を食べて大満足。 2本のポールと共に楽しくウォーキングしました。‼️ 【運動も過ぎず 甘やかさず いい塩梅に】 2024/5/20 ☔予報が出たら #シニアポールウォーキングクラス #船橋ウォーキングソサイエティ で継ぎ目のない「アルポ」を用意します。 アルポで足の先から サーキットトレーニングまで フルコース 汗をじんわりかく適度な運動 今年の夏も今から準備 暑い夏も 元氣に皆で乘り切るぞ〜
【運動も過ぎず 甘やかさず いい塩梅に】 2024/5/20 ☔予報が出たら #シニアポールウォーキングクラス #船橋ウォーキングソサイエティ で継ぎ目のない「アルポ」を用意します。 アルポで足の先から サーキットトレーニングまで フルコース 汗をじんわりかく適度な運動 今年の夏も今から準備 暑い夏も 元氣に皆で乘り切るぞ〜 【ウォーキング6つのポイント】 2024/5/21 ポイント 一つづつの度毎に 歩容が変化し 歩数に現れます 「大切だから伝えたい」 「向上したいから受け取る」 そんなよい関係が 流れた時間になりました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #歩くは重心の移動の連続 #良い姿勢から生まれる良い歩き #暑熱順化 #県立行田公園
【ウォーキング6つのポイント】 2024/5/21 ポイント 一つづつの度毎に 歩容が変化し 歩数に現れます 「大切だから伝えたい」 「向上したいから受け取る」 そんなよい関係が 流れた時間になりました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #歩くは重心の移動の連続 #良い姿勢から生まれる良い歩き #暑熱順化 #県立行田公園 広町里山緑地公園サークル。気温上昇予報に蚊🦟避けを持っていきました。 泥濘で足元が危うかったけれど、富士見台から室ヶ谷へ抜け新装開店の森のカフェで一寸休み、予約の津のカレー屋さんに走りました。 広町サークルとなごやか貯筋サークルの有志合流で和気藹々。講師(moi)が共通のポールが繋ぐ仲間です。山道をよく歩く方々ですが、歩くより筋トレ・ストレッチ、楽しむこと優先の朗らかなメンバーさんたちです。🧑🤝🧑🧑🤝🧑🧑🤝🧑
広町里山緑地公園サークル。気温上昇予報に蚊🦟避けを持っていきました。 泥濘で足元が危うかったけれど、富士見台から室ヶ谷へ抜け新装開店の森のカフェで一寸休み、予約の津のカレー屋さんに走りました。 広町サークルとなごやか貯筋サークルの有志合流で和気藹々。講師(moi)が共通のポールが繋ぐ仲間です。山道をよく歩く方々ですが、歩くより筋トレ・ストレッチ、楽しむこと優先の朗らかなメンバーさんたちです。🧑🤝🧑🧑🤝🧑🧑🤝🧑 北鎌倉テラス・健康DOJOと名前を少し変えました。いつもの体組成にプラス身長・握力・片足立バランス・片足立ち上がりなど計測。曇り空でしたが汗をしっかり滲ませて皆さん元気な笑顔。 すべてバランスが大切。 スティックブロッコリーの苗をメンバーさんに頂き収穫が楽しみです。 写真は去年のカルミア。今年はまだ見ていません。 午後から母の面会。これまで書きためた160枚の絵を見ました。
北鎌倉テラス・健康DOJOと名前を少し変えました。いつもの体組成にプラス身長・握力・片足立バランス・片足立ち上がりなど計測。曇り空でしたが汗をしっかり滲ませて皆さん元気な笑顔。 すべてバランスが大切。 スティックブロッコリーの苗をメンバーさんに頂き収穫が楽しみです。 写真は去年のカルミア。今年はまだ見ていません。 午後から母の面会。これまで書きためた160枚の絵を見ました。 【切り口を変えて】 2024/5/23 似て非なるポールを使う ウォーキング #後方押し出しメソッド 自然体で長距離も疲れ知らず ボールを投げるように 前へ 前へ #前方着地メソッド 肩甲骨を寄せるように 其々に分かれて 上半身を積極的に動かす練習 変化があるから 新鮮!楽しい〜♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使ウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング
【切り口を変えて】 2024/5/23 似て非なるポールを使う ウォーキング #後方押し出しメソッド 自然体で長距離も疲れ知らず ボールを投げるように 前へ 前へ #前方着地メソッド 肩甲骨を寄せるように 其々に分かれて 上半身を積極的に動かす練習 変化があるから 新鮮!楽しい〜♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使ウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング 五年ぶりのエルスタ東京、第66期研修生の平均年齢が息子と同じくらいで、月日の流れを感じました。 全国から集まったエネルギッシュな彼らが、近い将来に救急救命士として活躍なさる事が楽しみです。
五年ぶりのエルスタ東京、第66期研修生の平均年齢が息子と同じくらいで、月日の流れを感じました。 全国から集まったエネルギッシュな彼らが、近い将来に救急救命士として活躍なさる事が楽しみです。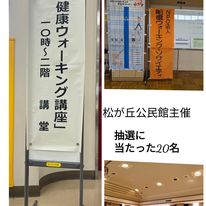 松が丘公民館主催 「健康ウォーキング講座」 2024/5/25 応募が多くて参加は抽選で選ばれたそうです。 講堂にて 「ウォーキング6つのポイント」 指導後に高根木戸近隣公園で 実践です 「歩幅計測。自分では同じ歩幅で歩いるつもりなのに計測毎に変化。感動した! 」 「楽に歩けた。疲れない♬」 「疲れた! でも楽に歩けた感じ」 「腸まで良く動きます(笑) 」 「今までウォーキングはガシガシ歩くイメージ。重心移動だとわかり感動」 感想は全てウォーキングの 長所につながります💕 打てば響く 強運の持ち主の20名の皆様の 意欲に充ち溢れた講座になりました 次回は 6月8日 (土) 効果あるウォーキングです
松が丘公民館主催 「健康ウォーキング講座」 2024/5/25 応募が多くて参加は抽選で選ばれたそうです。 講堂にて 「ウォーキング6つのポイント」 指導後に高根木戸近隣公園で 実践です 「歩幅計測。自分では同じ歩幅で歩いるつもりなのに計測毎に変化。感動した! 」 「楽に歩けた。疲れない♬」 「疲れた! でも楽に歩けた感じ」 「腸まで良く動きます(笑) 」 「今までウォーキングはガシガシ歩くイメージ。重心移動だとわかり感動」 感想は全てウォーキングの 長所につながります💕 打てば響く 強運の持ち主の20名の皆様の 意欲に充ち溢れた講座になりました 次回は 6月8日 (土) 効果あるウォーキングです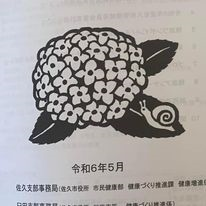 佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会ブロック研修会 〜ポールウォーキング体験会〜 全日無事終了です。 市内全地区14会場400人越えの参加者の皆さんに、2人の🔰MC proとのコーチングでPWを実践して頂きました。 どの会場も🔰90%でしたが、好評価を頂き各地区からのコーチのお呼ばれに期待です。
佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会ブロック研修会 〜ポールウォーキング体験会〜 全日無事終了です。 市内全地区14会場400人越えの参加者の皆さんに、2人の🔰MC proとのコーチングでPWを実践して頂きました。 どの会場も🔰90%でしたが、好評価を頂き各地区からのコーチのお呼ばれに期待です。 📢2024【日式健走Basic Coach 培訓課程】📢
📢2024【日式健走Basic Coach 培訓課程】📢 【スペシャル企画はヨガ】 2024/5/30 「やりたい事ある〜?」 「ヨガ」 「よし! やろうね」と 素敵なヨガ講師篠原純子先生 をお招きました 楽しい事はみんなでノリノリ みんなでやれば怖くない(笑) 《本日も笑顔全開なり》 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #2本のポールを使うウォーキング #社会参加で認知症予防
【スペシャル企画はヨガ】 2024/5/30 「やりたい事ある〜?」 「ヨガ」 「よし! やろうね」と 素敵なヨガ講師篠原純子先生 をお招きました 楽しい事はみんなでノリノリ みんなでやれば怖くない(笑) 《本日も笑顔全開なり》 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #2本のポールを使うウォーキング #社会参加で認知症予防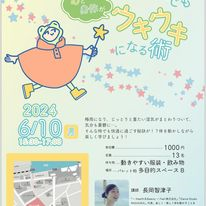 写真1件
写真1件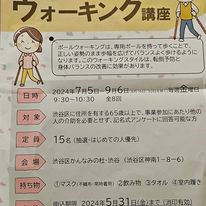 今年度第2期の募集です。 渋谷区在住の65歳以上のかたに限ります。
今年度第2期の募集です。 渋谷区在住の65歳以上のかたに限ります。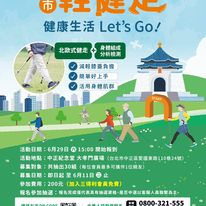 三得利健康網路商店X台灣健走杖運動推廣協會 📣 6/29(六) 在中正紀念堂,三得利城市輕健走與您不見不散~ 親愛的健走愛好者們, 我們很高興地宣布,由三得利健康網路商店與台灣健走杖運動推廣協會共同主辦的「城市輕健走 健康生活Let’s Go❗」活動即將登場!這是一個結合健康與樂趣的健走活動,讓您透過雙手持專用健走杖,產生支撐和推進的效果,可減緩關節壓力,幫助平衡預防跌倒,並活用全身肌群,讓全身筋骨動起來❗ 🗓️ 活動日期:2024年6月29日(六) 15:00起開始報到 📍 活動地點:中正紀念堂—大孝門廣場 📌 報名截止日期:即日起至6月11日(二)止 💰 參加費用:200元,加入三得利會員免費🆓 立即加入三得利會員並報名參加抽選 👉👉 https://swtt.cc/6rQsY 🌟 活動亮點: * 專業教練帶領:我們將率領專業教練與您一起輕鬆健走。 * 健走杖體驗:使用專用健走杖,減少關節壓力,提升運動效果。 * 健康檢測:現場備有專業儀器,讓您檢測體脂率、肌肉量📊。 * 快趁著氣溫舒適的6月,來與我們一起「城市輕健走 健康生活Let‘s Go❗」 📍報名只到6/11唷,名額有限,手刀報名! 👉👉 https://swtt.cc/6rQsY 期待與您在中正紀念堂相見,共同享受這場健康盛會!💪😊
三得利健康網路商店X台灣健走杖運動推廣協會 📣 6/29(六) 在中正紀念堂,三得利城市輕健走與您不見不散~ 親愛的健走愛好者們, 我們很高興地宣布,由三得利健康網路商店與台灣健走杖運動推廣協會共同主辦的「城市輕健走 健康生活Let’s Go❗」活動即將登場!這是一個結合健康與樂趣的健走活動,讓您透過雙手持專用健走杖,產生支撐和推進的效果,可減緩關節壓力,幫助平衡預防跌倒,並活用全身肌群,讓全身筋骨動起來❗ 🗓️ 活動日期:2024年6月29日(六) 15:00起開始報到 📍 活動地點:中正紀念堂—大孝門廣場 📌 報名截止日期:即日起至6月11日(二)止 💰 參加費用:200元,加入三得利會員免費🆓 立即加入三得利會員並報名參加抽選 👉👉 https://swtt.cc/6rQsY 🌟 活動亮點: * 專業教練帶領:我們將率領專業教練與您一起輕鬆健走。 * 健走杖體驗:使用專用健走杖,減少關節壓力,提升運動效果。 * 健康檢測:現場備有專業儀器,讓您檢測體脂率、肌肉量📊。 * 快趁著氣溫舒適的6月,來與我們一起「城市輕健走 健康生活Let‘s Go❗」 📍報名只到6/11唷,名額有限,手刀報名! 👉👉 https://swtt.cc/6rQsY 期待與您在中正紀念堂相見,共同享受這場健康盛會!💪😊 金澤雅人先生ら(新潟大学)とともに研究を進めてきたOGD(Oxygen-Glucose Deprivation:低酸素低糖刺激)を行った末梢血単核球による細胞療法の臨床応用を目指す「株式会社OhGooD」を今年1月25日に設立しました.そして本日,岐阜大学発ベンチャーの称号を吉田和弘学長より授与されました.会社名のOhGooDは,OGDを眺めていてひらめきました.多くの人に「Oh Good!!」と言ってもらえるような治療の確立を目指して頑張りたいと思います.
金澤雅人先生ら(新潟大学)とともに研究を進めてきたOGD(Oxygen-Glucose Deprivation:低酸素低糖刺激)を行った末梢血単核球による細胞療法の臨床応用を目指す「株式会社OhGooD」を今年1月25日に設立しました.そして本日,岐阜大学発ベンチャーの称号を吉田和弘学長より授与されました.会社名のOhGooDは,OGDを眺めていてひらめきました.多くの人に「Oh Good!!」と言ってもらえるような治療の確立を目指して頑張りたいと思います. ドイツから,縦断的に追跡された個人において,血液中の異常αシヌクレイン(α-syn conformer)がパーキンソン病(PD)と臨床診断される10年前に遡って検出できることを初めて示した研究が報告されました.発症前診断は,早期の病態修飾療法を可能にするため,重要な目標となっていました.
ドイツから,縦断的に追跡された個人において,血液中の異常αシヌクレイン(α-syn conformer)がパーキンソン病(PD)と臨床診断される10年前に遡って検出できることを初めて示した研究が報告されました.発症前診断は,早期の病態修飾療法を可能にするため,重要な目標となっていました.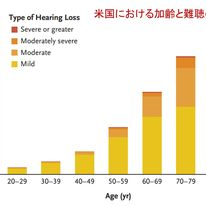 New Engl J Med誌最新号に「加齢性難聴と認知機能障害」に関する総説が掲載されています.難聴は加齢とともに徐々に増加します(図1).内耳(蝸牛)の有毛細胞が徐々に喪失することが主な原因です.また難聴のリスク因子としては加齢のほか,皮膚の色,男性,騒音暴露が知られています(皮膚の色はメラニン量のことです.メラニンは内耳の有毛細胞にも存在し,酸化ストレスに対して保護的な役割を果たします).
New Engl J Med誌最新号に「加齢性難聴と認知機能障害」に関する総説が掲載されています.難聴は加齢とともに徐々に増加します(図1).内耳(蝸牛)の有毛細胞が徐々に喪失することが主な原因です.また難聴のリスク因子としては加齢のほか,皮膚の色,男性,騒音暴露が知られています(皮膚の色はメラニン量のことです.メラニンは内耳の有毛細胞にも存在し,酸化ストレスに対して保護的な役割を果たします). 毎年恒例のアルツハイマー病(AD)治療のための薬物開発の現状(いわゆるパイプライン)に関する論文が発表されました.clinicaltrials.govを調査し,2024年1月1日時点でADの薬物開発に関するすべての臨床試験を検討しています.164件の臨床試験で,計127種類の薬剤が評価されています(図1).
毎年恒例のアルツハイマー病(AD)治療のための薬物開発の現状(いわゆるパイプライン)に関する論文が発表されました.clinicaltrials.govを調査し,2024年1月1日時点でADの薬物開発に関するすべての臨床試験を検討しています.164件の臨床試験で,計127種類の薬剤が評価されています(図1).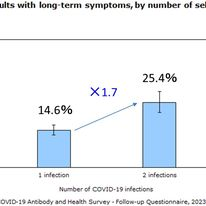 COVID-19が感染症法上の5類に移行して今日で1年だそうです.読売新聞から取材いただき,後遺症について現在までに分かっていることについて解説し,コメントをしました.
COVID-19が感染症法上の5類に移行して今日で1年だそうです.読売新聞から取材いただき,後遺症について現在までに分かっていることについて解説し,コメントをしました.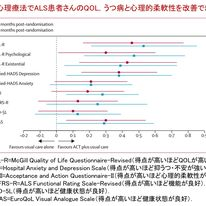 筋萎縮性側索硬化性(ALS)などの運動ニューロン病は根本療法が未確立の神経難病です.心理的サポートは有益であろうと想像できますが,小規模・短期間の研究のみで十分なエビデンスはありませんでした.Lancet誌に,英国からAcceptance and Commitment Therapy(ACT)と名付けられた,受容,マインドフルネス,認知行動療法を取り入れた心理療法が,患者さんのQOLを大幅に向上できることを示した臨床試験が報告されました.ちなみにACTは,つらい感情や思考をコントロールしたり回避したりするのではなく,受け入れることに重点を置いています.
筋萎縮性側索硬化性(ALS)などの運動ニューロン病は根本療法が未確立の神経難病です.心理的サポートは有益であろうと想像できますが,小規模・短期間の研究のみで十分なエビデンスはありませんでした.Lancet誌に,英国からAcceptance and Commitment Therapy(ACT)と名付けられた,受容,マインドフルネス,認知行動療法を取り入れた心理療法が,患者さんのQOLを大幅に向上できることを示した臨床試験が報告されました.ちなみにACTは,つらい感情や思考をコントロールしたり回避したりするのではなく,受け入れることに重点を置いています.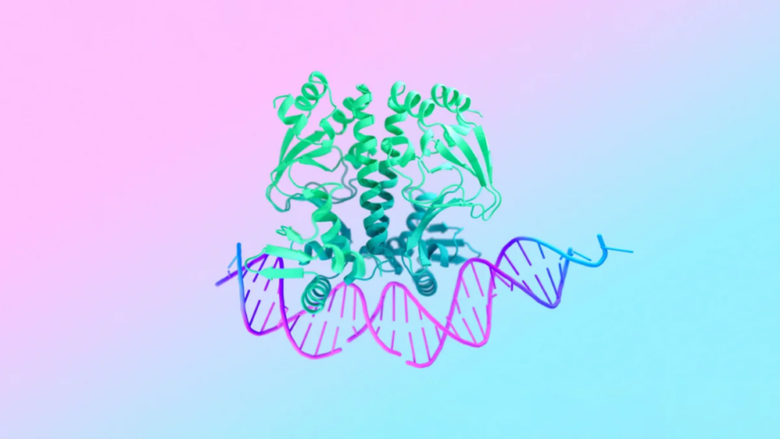 Google DeepMind と Isomorphic Labs によって開発された新しい AI モデルである AlphaFold 3 を紹介します。タンパク質、DNA、RNA、リガンドなどの構造とそれらがどのように相互作用するかを正確に予測することで、生物学の世界と創薬に対する私たちの理解を変えることができると期待しています。
Google DeepMind と Isomorphic Labs によって開発された新しい AI モデルである AlphaFold 3 を紹介します。タンパク質、DNA、RNA、リガンドなどの構造とそれらがどのように相互作用するかを正確に予測することで、生物学の世界と創薬に対する私たちの理解を変えることができると期待しています。 20240201 スマイルチーム ポールウォーキング部。 目指せ七福神‼️ #スマイルチーム #ポールウォーキング #相模原市南区 #七福神 #記録 #20240201 #ポールウォーキングらしい写真ゼロってゆー😂
20240201 スマイルチーム ポールウォーキング部。 目指せ七福神‼️ #スマイルチーム #ポールウォーキング #相模原市南区 #七福神 #記録 #20240201 #ポールウォーキングらしい写真ゼロってゆー😂 なんと!コアコンジャーナル2月号の We love C.C.に私の記事が掲載することになりました。 コアコンに出会えて本当によかったです。人も品物も。よきめぐりあいです。 今後ともよろしくお願いします🙇
なんと!コアコンジャーナル2月号の We love C.C.に私の記事が掲載することになりました。 コアコンに出会えて本当によかったです。人も品物も。よきめぐりあいです。 今後ともよろしくお願いします🙇 渋谷の春 ブルルル((😖)) 寒い朝 それでも皆さん元気にお集まりになり、スキップでは笑顔で跳ねて嬉しそう♪ 終了後は個人的質問(4人)の多い日。 /ポールが背中に触ると腎臓の辺りが痛く、先週から血尿がでるんです。内科で診察を受けお薬処方されたのですが 変化がないんです。/う~ん、私は医者ではないので診断できかねます。運動続けてもよいかも併せて再度受診をお勧めしました。
渋谷の春 ブルルル((😖)) 寒い朝 それでも皆さん元気にお集まりになり、スキップでは笑顔で跳ねて嬉しそう♪ 終了後は個人的質問(4人)の多い日。 /ポールが背中に触ると腎臓の辺りが痛く、先週から血尿がでるんです。内科で診察を受けお薬処方されたのですが 変化がないんです。/う~ん、私は医者ではないので診断できかねます。運動続けてもよいかも併せて再度受診をお勧めしました。 【福は内 鬼は外〜】 船橋ウォーキングソサイエティ 土曜定例会 2024/2/3 船橋港親水公園へ向かいます。 道中で珍しく船が陸揚げされ ペンキ塗装中です。 ここでも盛り上がり 船橋は港町なんだよね〜 ワイワイ 土曜日定例会は 若手(?)が中心で進行。 3人のスタッフが ポールdeダンスもリード。 会員もニコニコノリノリです ♬ 定例会後にスタッフ4人は 神社の豆まきに寄り道。 これ又、しっかり楽しんで来ました。 紅白餅・節分豆 たっぷりゲット(笑) HAPPYな一日でした♥
【福は内 鬼は外〜】 船橋ウォーキングソサイエティ 土曜定例会 2024/2/3 船橋港親水公園へ向かいます。 道中で珍しく船が陸揚げされ ペンキ塗装中です。 ここでも盛り上がり 船橋は港町なんだよね〜 ワイワイ 土曜日定例会は 若手(?)が中心で進行。 3人のスタッフが ポールdeダンスもリード。 会員もニコニコノリノリです ♬ 定例会後にスタッフ4人は 神社の豆まきに寄り道。 これ又、しっかり楽しんで来ました。 紅白餅・節分豆 たっぷりゲット(笑) HAPPYな一日でした♥ [健康フェスタ2024] 地域健康づくりの5グループが各ブースでパホーマンスを行ったんです。 広報に掲載された直後に問い合わせが殺到…募集100名が120数名でお断りする状態だったとか♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪ 我が紙芝居グループは「ロコモチェク」…椅子から立ち上がり足の筋力をチェクする場を担当したんです。60台〜90台、平均年齢75才の方々… 片足で立ち上がれず「ショックです」の声が多くあったのですが、 「今のご自分を知ることが出来て良かったですね」と、「ちょい曲げ体操(テーブルに手をついての軽いスクワット)」と、「簡単片足立ち(テーブルに手をついて片足5センチから)」をお勧め🩷
[健康フェスタ2024] 地域健康づくりの5グループが各ブースでパホーマンスを行ったんです。 広報に掲載された直後に問い合わせが殺到…募集100名が120数名でお断りする状態だったとか♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪ 我が紙芝居グループは「ロコモチェク」…椅子から立ち上がり足の筋力をチェクする場を担当したんです。60台〜90台、平均年齢75才の方々… 片足で立ち上がれず「ショックです」の声が多くあったのですが、 「今のご自分を知ることが出来て良かったですね」と、「ちょい曲げ体操(テーブルに手をついての軽いスクワット)」と、「簡単片足立ち(テーブルに手をついて片足5センチから)」をお勧め🩷 20240205。 フォローアップ教室でした。 本講座受講された方の半分ほどの方がフォローアップ教室に参加されました。 本日の最高齢は86さい? どの方か当ててみて🤭🤭🤭 介護予防教室なのでリハビリメインの方もいらっしゃいますが みなさんしっかり歩きが身についていて嬉しかったです。 午後から雪予報につき、 午後からのスマイル活動は朝のうちに全員に中止連絡をしました。。。 皆様も 雪や寒さにお気をつけくださいませ。 #介護予防教室 #地域包括支援センター #上溝 #ポールウォーキング
20240205。 フォローアップ教室でした。 本講座受講された方の半分ほどの方がフォローアップ教室に参加されました。 本日の最高齢は86さい? どの方か当ててみて🤭🤭🤭 介護予防教室なのでリハビリメインの方もいらっしゃいますが みなさんしっかり歩きが身についていて嬉しかったです。 午後から雪予報につき、 午後からのスマイル活動は朝のうちに全員に中止連絡をしました。。。 皆様も 雪や寒さにお気をつけくださいませ。 #介護予防教室 #地域包括支援センター #上溝 #ポールウォーキング 『Let’s enjoy Paul Walking』🌴🌴 コーチ資格を持つ方々の勉強会開催からの アロハファームにて お食事&飲み会😍😍 皆様が健康に笑顔になるためのポールウォーキング健康法👏👏👏おすすめです(^ω^)
『Let’s enjoy Paul Walking』🌴🌴 コーチ資格を持つ方々の勉強会開催からの アロハファームにて お食事&飲み会😍😍 皆様が健康に笑顔になるためのポールウォーキング健康法👏👏👏おすすめです(^ω^) 大雪明けの介護予防教室。 雪残る街中 誰も来ないかもと思いつつ 地域包括支援センターへ お一人ご参加頂いたので 保健師さんを交え 人生ゲーム大会に。 これはただの人生ゲームではなく 第二の人生を自分らしく暮らし、前向きなシニアライフを楽しんでもらおうと、自治体とメーカーがコラボしたゲーム「おかざきゴールデンシニア人生ゲーム」。 実家の愛知に戻った折、岡崎市役所で1枚頂いてきました。筋トレカードをオリジナルで追加して楽しいゲームができました。
大雪明けの介護予防教室。 雪残る街中 誰も来ないかもと思いつつ 地域包括支援センターへ お一人ご参加頂いたので 保健師さんを交え 人生ゲーム大会に。 これはただの人生ゲームではなく 第二の人生を自分らしく暮らし、前向きなシニアライフを楽しんでもらおうと、自治体とメーカーがコラボしたゲーム「おかざきゴールデンシニア人生ゲーム」。 実家の愛知に戻った折、岡崎市役所で1枚頂いてきました。筋トレカードをオリジナルで追加して楽しいゲームができました。 【活動を妨げずに共に楽しむ】 今週は降雪で定例会が2回中止。 2/8の木曜日の行田公園のみ開催になりました。 行田公園の状況確認して安心して定例会に臨む。 おやおや次から次と保育園児がサーキットを予定していた円形花壇で遊んでいます。臨機応変に場所を替え 縮こまった身体をしっかり動かしました。 青空が気持よかった〜♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #千葉県立行田公園 #サーキットトレーニング #しっかり歩き #フレイル改善予防
【活動を妨げずに共に楽しむ】 今週は降雪で定例会が2回中止。 2/8の木曜日の行田公園のみ開催になりました。 行田公園の状況確認して安心して定例会に臨む。 おやおや次から次と保育園児がサーキットを予定していた円形花壇で遊んでいます。臨機応変に場所を替え 縮こまった身体をしっかり動かしました。 青空が気持よかった〜♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #千葉県立行田公園 #サーキットトレーニング #しっかり歩き #フレイル改善予防 🎉 台灣健走杖運動推廣協會 祝大家龍年新年快樂! 🐉🌟
🎉 台灣健走杖運動推廣協會 祝大家龍年新年快樂! 🐉🌟 2024.2.6〜10 活動記録 ☺︎中屋敷地区センター チェアエクササイズ 25名参加 ☺︎健康体操サークル 16名参加 マルチエクササイズ、リズムダンス ☺︎相模原市高齢者活動支援課活動発表会(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 25名参加 リズムダンス ☺︎青空PW 9名参加 今日で3回目のポールウォーキング初心者のサークルですが、全員マイポール購入してやる氣まんまんです ☺︎上溝公民館祭り準備、連絡 ☺︎上鶴間公民館青少年部 部会 ☺︎相模原市青少年指導委員 上鶴間 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会令和6年度後援事業決定 今週月曜日からは85名の方とそれぞれの教室で、また14名の方と会議でご一緒しました。 雪で中止になった教室もありますが、明日は卓球大会があります。 スマイルシスターズフル回転🌀😵💫 頑張ってます、元氣が1番❣️ 正しいより楽しい‼️
2024.2.6〜10 活動記録 ☺︎中屋敷地区センター チェアエクササイズ 25名参加 ☺︎健康体操サークル 16名参加 マルチエクササイズ、リズムダンス ☺︎相模原市高齢者活動支援課活動発表会(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 25名参加 リズムダンス ☺︎青空PW 9名参加 今日で3回目のポールウォーキング初心者のサークルですが、全員マイポール購入してやる氣まんまんです ☺︎上溝公民館祭り準備、連絡 ☺︎上鶴間公民館青少年部 部会 ☺︎相模原市青少年指導委員 上鶴間 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会令和6年度後援事業決定 今週月曜日からは85名の方とそれぞれの教室で、また14名の方と会議でご一緒しました。 雪で中止になった教室もありますが、明日は卓球大会があります。 スマイルシスターズフル回転🌀😵💫 頑張ってます、元氣が1番❣️ 正しいより楽しい‼️ 青空のもと満開の梅 梅まつり初日の羽根木公園 少人数の仲間と歩く「気まポ(気ままにポール歩き)」、今月は、世田谷区の羽根木公園で満開の梅を楽しみました。そのあと、北沢川緑道をたどって、北沢八幡神社、森巌寺から下北沢駅まで。 梅まつり初日の羽根木公園では、ウォーキングというよりも、ゆったりと観梅の時間としました。梅大福などをほおばりながら一服。 下北沢の町に入ると雰囲気は一変。すごいにぎわいで、ポールでは歩けません。予約していた台湾料理の店でビールとおいしい料理で締めくくりました。 もうすぐバレンタインデーだからと、Tさんからサプライズで、お手製のチョコがみんなに配られました。 ※写真は田村和史さんほかのみなさんと私
青空のもと満開の梅 梅まつり初日の羽根木公園 少人数の仲間と歩く「気まポ(気ままにポール歩き)」、今月は、世田谷区の羽根木公園で満開の梅を楽しみました。そのあと、北沢川緑道をたどって、北沢八幡神社、森巌寺から下北沢駅まで。 梅まつり初日の羽根木公園では、ウォーキングというよりも、ゆったりと観梅の時間としました。梅大福などをほおばりながら一服。 下北沢の町に入ると雰囲気は一変。すごいにぎわいで、ポールでは歩けません。予約していた台湾料理の店でビールとおいしい料理で締めくくりました。 もうすぐバレンタインデーだからと、Tさんからサプライズで、お手製のチョコがみんなに配られました。 ※写真は田村和史さんほかのみなさんと私 盛り沢山の楽しい1日でした😊 午前中は、🥑アボカドファーム仲間のイベントでいちご狩り🍓 🍓食べ過ぎでお腹いっぱいのまま3回目の大岡山東急ウェリナ。 私も皆さんも慣れてきました。 中庭のガーデンウォーキングも気持ち良い。 仕事終了後は、大岡山に住むお友達と待ち合わせて嬉しいひととき☕️🎵😊 盛り沢山の充実した1日に感謝。 ありがとう💕
盛り沢山の楽しい1日でした😊 午前中は、🥑アボカドファーム仲間のイベントでいちご狩り🍓 🍓食べ過ぎでお腹いっぱいのまま3回目の大岡山東急ウェリナ。 私も皆さんも慣れてきました。 中庭のガーデンウォーキングも気持ち良い。 仕事終了後は、大岡山に住むお友達と待ち合わせて嬉しいひととき☕️🎵😊 盛り沢山の充実した1日に感謝。 ありがとう💕 DX移行のための最大経由ポイントは「アナログトランスフォーメーション」(AX)かも。シンプル、明快で、これ以上の標準化はないから。老人会講座では、これに勝るものはない!
DX移行のための最大経由ポイントは「アナログトランスフォーメーション」(AX)かも。シンプル、明快で、これ以上の標準化はないから。老人会講座では、これに勝るものはない!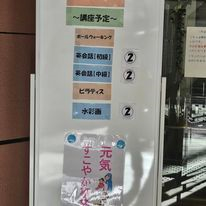 渋谷介護保険課の事業でポールウォーキングのサークルを5年余続けさせて頂いております。3カ月ごとのクラスで年に4期(4回) 定員各15名募集しています。初心者優先でキャンセル待ちを承知での申し込み。各回様々な方(年令・体調・男女)が参加して楽しんでいただいています。既に数百人の方々とご一緒しました。今日 23日の鎌倉ミステリーの案内をしたところ4~5名が参加したいと挙手🙋♀️ PWのメンバーですがポールなしで歩きたいと言う方も。ところが週間予報では当日は寒い上雨予報。雨の場合は日を改め延期しましょうか。
渋谷介護保険課の事業でポールウォーキングのサークルを5年余続けさせて頂いております。3カ月ごとのクラスで年に4期(4回) 定員各15名募集しています。初心者優先でキャンセル待ちを承知での申し込み。各回様々な方(年令・体調・男女)が参加して楽しんでいただいています。既に数百人の方々とご一緒しました。今日 23日の鎌倉ミステリーの案内をしたところ4~5名が参加したいと挙手🙋♀️ PWのメンバーですがポールなしで歩きたいと言う方も。ところが週間予報では当日は寒い上雨予報。雨の場合は日を改め延期しましょうか。 【冬の土曜日定例会は面白い】 2024/2/17 冬だから出来る事。 冬だからしっかり歩き。 たった90分の定例会は笑顔で締めくくりです。 スタッフの工夫が満載で、 それが効いています。 \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング土曜定例会 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #海老川ジョギングロード #サーキットトレーニング
【冬の土曜日定例会は面白い】 2024/2/17 冬だから出来る事。 冬だからしっかり歩き。 たった90分の定例会は笑顔で締めくくりです。 スタッフの工夫が満載で、 それが効いています。 \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング土曜定例会 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #海老川ジョギングロード #サーキットトレーニング 佐久ポールウォーキング協会より 2023年度締め括りPWイベント 「室内ポールウォーク」でした。 一年PW三昧〜ありがとうございました。 好天春❗️の陽気の中暖房の効いた体育館に集まって頂き、皆さんでひと汗ふた汗と〜ww 佐藤美穂コーチによる「3B体操」で身体の隅々までほぐし、 後半は新地コーチ主導のポールウォーキング❗️体験者8名程交えもう一度本気PWを! 〜目線〜体重移動〜肘引き〜と慣れ親しんだポールウォーカーも原点に戻ってのPWでした。 ➕のコーチテーマは「褒めるコーチング」でした。 コーチ8名〜良く出来たと思います‼️ 2024PWは4/7から始動予定ですww
佐久ポールウォーキング協会より 2023年度締め括りPWイベント 「室内ポールウォーク」でした。 一年PW三昧〜ありがとうございました。 好天春❗️の陽気の中暖房の効いた体育館に集まって頂き、皆さんでひと汗ふた汗と〜ww 佐藤美穂コーチによる「3B体操」で身体の隅々までほぐし、 後半は新地コーチ主導のポールウォーキング❗️体験者8名程交えもう一度本気PWを! 〜目線〜体重移動〜肘引き〜と慣れ親しんだポールウォーカーも原点に戻ってのPWでした。 ➕のコーチテーマは「褒めるコーチング」でした。 コーチ8名〜良く出来たと思います‼️ 2024PWは4/7から始動予定ですww 始めました😊
始めました😊 野川公園など都立3公園が集中している地域をノルディックウォーキング 杉ポ(杉並ポール歩きの会)の講師としてお世話になってきた新里るりさん主催の会に参加しました。 JR武蔵小金井駅に集合、武蔵野公園、野川公園、調布飛行場、武蔵野の森公園をポールで歩きました。 飛行場をながめながら野外でランチ。プロペラ機が次々と離着陸するのはなかなか迫力がありました。 そのあとモルックで遊びました。つい夢中に。 ※私の写っている写真は新里さんからいただきました。
野川公園など都立3公園が集中している地域をノルディックウォーキング 杉ポ(杉並ポール歩きの会)の講師としてお世話になってきた新里るりさん主催の会に参加しました。 JR武蔵小金井駅に集合、武蔵野公園、野川公園、調布飛行場、武蔵野の森公園をポールで歩きました。 飛行場をながめながら野外でランチ。プロペラ機が次々と離着陸するのはなかなか迫力がありました。 そのあとモルックで遊びました。つい夢中に。 ※私の写っている写真は新里さんからいただきました。 2月なのに20℃ 暑いよ〜💦 2024/2/20 美姿勢ウォーキング 年に1度のポールウォーキング体験日。 恒例なのでほぼ経験者ばかり 流石に飲み込みが早く ボンボン進みます ♬ 「ポールは面倒くさい」 毎年正直な感想も出ます(笑) ポールを持つとね普段のウォーキングフォームも良くなるのよ 体験者1名を迎え「楽しい」 とそのまま入会になりました。 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ポールウォーキング #パワーウォーキング #健康ウォーキング指導士 #行田公園 #身体と心が喜ぶウォーキング #ウォーキングでHAPPY
2月なのに20℃ 暑いよ〜💦 2024/2/20 美姿勢ウォーキング 年に1度のポールウォーキング体験日。 恒例なのでほぼ経験者ばかり 流石に飲み込みが早く ボンボン進みます ♬ 「ポールは面倒くさい」 毎年正直な感想も出ます(笑) ポールを持つとね普段のウォーキングフォームも良くなるのよ 体験者1名を迎え「楽しい」 とそのまま入会になりました。 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ポールウォーキング #パワーウォーキング #健康ウォーキング指導士 #行田公園 #身体と心が喜ぶウォーキング #ウォーキングでHAPPY 仲良き事は美しく哉 PW
仲良き事は美しく哉 PW お天気は一日で逆転し、今日は肌寒い雨。北鎌倉健康教室は外歩きの移動は止め、室内トレーニングと座学。今日は「筋肉」について改めて学びました。指導は杉浦コーチ。 高齢者に限らず52才~54才の若い方も増えました。7、80代のメンバーは良い刺激パワーを貰えラッキーです。
お天気は一日で逆転し、今日は肌寒い雨。北鎌倉健康教室は外歩きの移動は止め、室内トレーニングと座学。今日は「筋肉」について改めて学びました。指導は杉浦コーチ。 高齢者に限らず52才~54才の若い方も増えました。7、80代のメンバーは良い刺激パワーを貰えラッキーです。 千葉県鋸南町へ 雨のため頼朝桜を拝む事はできませんでしたが、その分しっかり講義の時間に充てることができました。前回の介護予防事業と違って、今回は生活習慣病予防事業という事で中高年層対象ですが、参加者の皆さんを前にするとフレイル予防講座にどうしてもなりがちです。こういった現象は日本全国どこに行っても共通しますが、65〜75歳の個別対応の難しいところですね。それにしても鋸南町の皆さんはイキイキとされていて、実年齢より一回り以上若く見えます!
千葉県鋸南町へ 雨のため頼朝桜を拝む事はできませんでしたが、その分しっかり講義の時間に充てることができました。前回の介護予防事業と違って、今回は生活習慣病予防事業という事で中高年層対象ですが、参加者の皆さんを前にするとフレイル予防講座にどうしてもなりがちです。こういった現象は日本全国どこに行っても共通しますが、65〜75歳の個別対応の難しいところですね。それにしても鋸南町の皆さんはイキイキとされていて、実年齢より一回り以上若く見えます! 1月開催の日本ポールウォーキング協会ベーシックコーチ資格取得セミナーで、9名のコーチが誕生しました!宮城4名、秋田3名、山形1名、岩手1名! 今年は東北でポールウォーキングが更に広がっていきそうです!広がれ、ポールウォーキングの輪!
1月開催の日本ポールウォーキング協会ベーシックコーチ資格取得セミナーで、9名のコーチが誕生しました!宮城4名、秋田3名、山形1名、岩手1名! 今年は東北でポールウォーキングが更に広がっていきそうです!広がれ、ポールウォーキングの輪!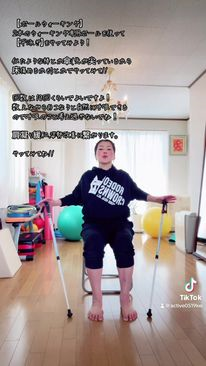 ポールウォーキング専用ポールを使って平泳ぎをやってみよう!! (ポールウォーキングを行う前の準備運動/椅子に座っておこなうバージョンso1(その1)) #ポールウォーキングマスターコーチプロ #準備運動
ポールウォーキング専用ポールを使って平泳ぎをやってみよう!! (ポールウォーキングを行う前の準備運動/椅子に座っておこなうバージョンso1(その1)) #ポールウォーキングマスターコーチプロ #準備運動 [ポールde遊ぼう!]はい!ポールで遊んでみた。簡単で簡単でない????笑うしかないwいやいや、笑うことが目的よ!
[ポールde遊ぼう!]はい!ポールで遊んでみた。簡単で簡単でない????笑うしかないwいやいや、笑うことが目的よ! 鎌倉二階堂早咲き桜 冷たい風と暖かい日射しの道を鎌倉宮から二階堂を歩きました (三浦ネットgroup)
鎌倉二階堂早咲き桜 冷たい風と暖かい日射しの道を鎌倉宮から二階堂を歩きました (三浦ネットgroup) 🌸 春暖花開🌿 健走杖體驗活動🚶♂️ 親愛的健走好友🧑🤝🧑 春天是一個充滿活力和希望的季節 也是健走杖運動的最佳時機 由 北歐運動治療師 楊子欣(欣欣老師) 帶領的健走杖體驗活動 一同感受春天🐝的氣息 享受健康的樂趣! 澄心康健-神經復健 l 動作優化 l 高齡運動
🌸 春暖花開🌿 健走杖體驗活動🚶♂️ 親愛的健走好友🧑🤝🧑 春天是一個充滿活力和希望的季節 也是健走杖運動的最佳時機 由 北歐運動治療師 楊子欣(欣欣老師) 帶領的健走杖體驗活動 一同感受春天🐝的氣息 享受健康的樂趣! 澄心康健-神經復健 l 動作優化 l 高齡運動 最長老でなにかと相談にのってもらっていた監査役が本日卒業。製造から営業まで経験され、取締役として長年父や私を支えてもらいました。本当にありがとうございました。 本日の信濃毎日新聞記事。製品一組当たりのCO2排出量を算出し、今後排出量を減らす取組みを実施していきます。
最長老でなにかと相談にのってもらっていた監査役が本日卒業。製造から営業まで経験され、取締役として長年父や私を支えてもらいました。本当にありがとうございました。 本日の信濃毎日新聞記事。製品一組当たりのCO2排出量を算出し、今後排出量を減らす取組みを実施していきます。 今日は早咲き観桜🌸🌸🌸 友達とフリーポールウォーキング 三浦海岸駅から小松ガ池公園まで見事な河津桜と菜の花の並木道!途中の地元の農家さんのキャベツや大根、芽キャベツを覗くのも楽しい 夕飯はお土産のワカメをしゃぶしゃぶに、大根おろしとポン酢で。
今日は早咲き観桜🌸🌸🌸 友達とフリーポールウォーキング 三浦海岸駅から小松ガ池公園まで見事な河津桜と菜の花の並木道!途中の地元の農家さんのキャベツや大根、芽キャベツを覗くのも楽しい 夕飯はお土産のワカメをしゃぶしゃぶに、大根おろしとポン酢で。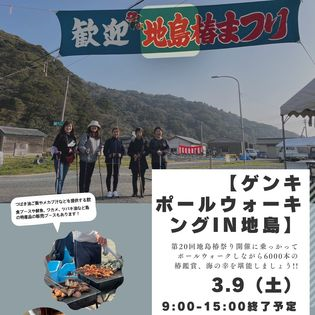 【ゲンキポールウォーキングin地島」
【ゲンキポールウォーキングin地島」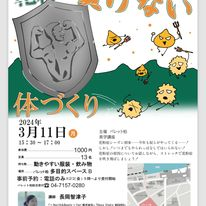
 「お知らせ」 楽しみにしていた明日23日の鎌倉歩きですが 雨降りの冷たい気温を予報していますので、残念ですが中止とし、改めて3月15日金曜日(16日予備日) に延期させて頂くことになりました。
「お知らせ」 楽しみにしていた明日23日の鎌倉歩きですが 雨降りの冷たい気温を予報していますので、残念ですが中止とし、改めて3月15日金曜日(16日予備日) に延期させて頂くことになりました。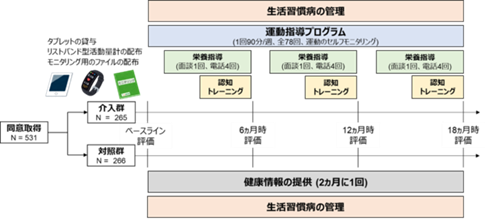 図1 J-MINT研究の概要
図1 J-MINT研究の概要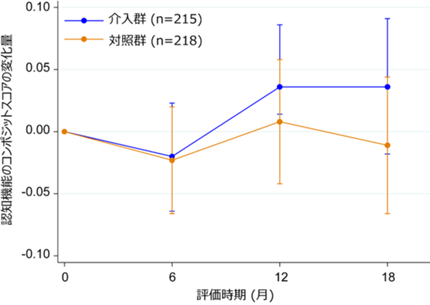 図2 全対象者 (n=433)における多因子介入プログラムの効果
図2 全対象者 (n=433)における多因子介入プログラムの効果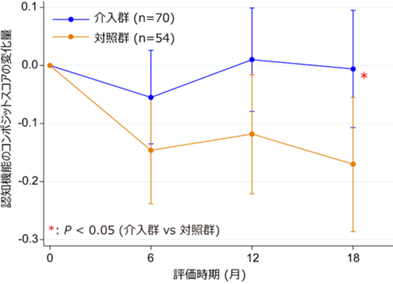 図3 アポリポ蛋白E遺伝子のE4多型の保因者 (n = 124)における多因子介入プログラムの効果
図3 アポリポ蛋白E遺伝子のE4多型の保因者 (n = 124)における多因子介入プログラムの効果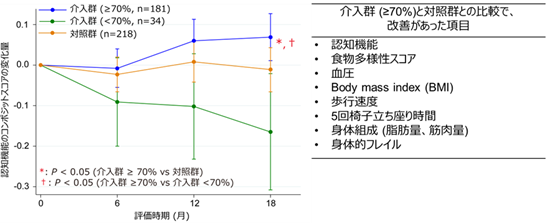 図4 運動教室への参加率による多因子介入プログラムの効果
図4 運動教室への参加率による多因子介入プログラムの効果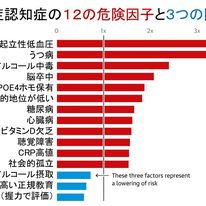 高齢発症の認知症の約40%は,12の危険因子を修正することによって予防・遅延できる可能性があると言われています(Lancet委員会報告)(ブログ解説;http://tinyurl.com/2yutulna).しかし65歳未満の若年発症認知症についてはよく分かっていません.遺伝的要因の関与が大きいものと思われがちですが,本当の原因が何であるか正確には分かっていません.
高齢発症の認知症の約40%は,12の危険因子を修正することによって予防・遅延できる可能性があると言われています(Lancet委員会報告)(ブログ解説;http://tinyurl.com/2yutulna).しかし65歳未満の若年発症認知症についてはよく分かっていません.遺伝的要因の関与が大きいものと思われがちですが,本当の原因が何であるか正確には分かっていません.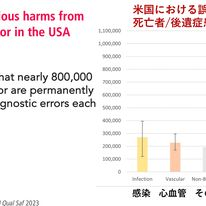 Science誌に標題のタイトルで,スクリップス研究所のEric Topol教授が寄稿しており興味深く読みました.以下,要約です.
Science誌に標題のタイトルで,スクリップス研究所のEric Topol教授が寄稿しており興味深く読みました.以下,要約です.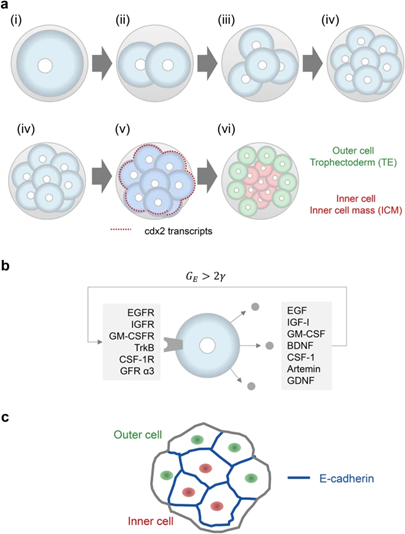 図 1. サロゲートモデルとメッセージ力場モデルの統合による胚盤胞分化誘導過程の推論
図 1. サロゲートモデルとメッセージ力場モデルの統合による胚盤胞分化誘導過程の推論 2024.1.5 青空ポールウォーキングサークル 今日より本格始動です 色々な決め事、活動日、ポール選びなどなどの後、スポーツ広場を一周しました。 スマイルチームも関わりつつ、包括支援センター事業から発生した自主サークルとしての活動を目指しています。 楽しく長く続けていきましょう😊 #ポールウォーキング #スマイルチーム #高齢者体力つくり支援士 #シナノ #キザキ #ハタチ
2024.1.5 青空ポールウォーキングサークル 今日より本格始動です 色々な決め事、活動日、ポール選びなどなどの後、スポーツ広場を一周しました。 スマイルチームも関わりつつ、包括支援センター事業から発生した自主サークルとしての活動を目指しています。 楽しく長く続けていきましょう😊 #ポールウォーキング #スマイルチーム #高齢者体力つくり支援士 #シナノ #キザキ #ハタチ ポールウォーキング&ノルディック(スローも含)ウォーキング [walking hut 121駒沢公園教室] は 鎌倉に移転いたしました。 駒沢のメンバーさんは若いPWコーチ・NWイントラさんに託しそのまま継続して頂いています。 鎌倉教室は各4~5名の自主グループでコアヌードルを使った骨盤エクササイズなどとご希望に依っては近隣ウォークの2本立て。 お問い合わせはメッセ、メールで。
ポールウォーキング&ノルディック(スローも含)ウォーキング [walking hut 121駒沢公園教室] は 鎌倉に移転いたしました。 駒沢のメンバーさんは若いPWコーチ・NWイントラさんに託しそのまま継続して頂いています。 鎌倉教室は各4~5名の自主グループでコアヌードルを使った骨盤エクササイズなどとご希望に依っては近隣ウォークの2本立て。 お問い合わせはメッセ、メールで。 珠洲市でフットケア、インストラクターをしついるみきさんの今の珠洲市をシェアさせていただきます。 昨年珠洲市にインストラクター仲間と珠洲市木の浦ビレッジに泊まり、みきさんのフットセラピーを受けて気持ちよかった事。日常を忘れて今の時間をゆっくり過ごすことができた珠洲市。早い復興を願います。
珠洲市でフットケア、インストラクターをしついるみきさんの今の珠洲市をシェアさせていただきます。 昨年珠洲市にインストラクター仲間と珠洲市木の浦ビレッジに泊まり、みきさんのフットセラピーを受けて気持ちよかった事。日常を忘れて今の時間をゆっくり過ごすことができた珠洲市。早い復興を願います。 【今年も宜しくお願い致します】 新年早々 思いもよらぬ事態が続きます。被災された皆様、心よりお見舞い申しあげます。平穏な日々が早く戻る事を強く祈ります。 穏やかな日差しに包まれて 船橋ウォーキングソサイエティは土曜日コース定例会の恒例《初詣ウォーク》からスタートしました。 小さな幸せを大切に今年も楽しく歩きたいと思います。
【今年も宜しくお願い致します】 新年早々 思いもよらぬ事態が続きます。被災された皆様、心よりお見舞い申しあげます。平穏な日々が早く戻る事を強く祈ります。 穏やかな日差しに包まれて 船橋ウォーキングソサイエティは土曜日コース定例会の恒例《初詣ウォーク》からスタートしました。 小さな幸せを大切に今年も楽しく歩きたいと思います。 年明け広町緑地サークルは広場で念入り体操をしたあと 平地しか歩けない方がいらしたので 山歩きはやめ 龍口明神社へ初詣に参りました。来週?来月は江島神社お詣りになりました。
年明け広町緑地サークルは広場で念入り体操をしたあと 平地しか歩けない方がいらしたので 山歩きはやめ 龍口明神社へ初詣に参りました。来週?来月は江島神社お詣りになりました。 午前中のサークルのあと 長い間近くに住んでいるのに行ったことがない,とおっしゃるメンバーさん達と本覚寺本えびすに。今日はちょうど1月10日。ポールで初詣。境内では使いません。
午前中のサークルのあと 長い間近くに住んでいるのに行ったことがない,とおっしゃるメンバーさん達と本覚寺本えびすに。今日はちょうど1月10日。ポールで初詣。境内では使いません。 【続編17】第六章〜第二、三、四節 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道
【続編17】第六章〜第二、三、四節 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道 【千昌夫の北国の春】 2024/1/11 #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース 冬メニュー #サーキットトレーニング。 考慮すべき点が多い木曜日定例会。 諦めずに繰り返しが大切ですね。 繰り返す事でスタッフの 指導力が上がり、 花壇円周50mを上手く使い 誘導できるようになりました。 万事スムーズです。 コロナ禍で中断し、 再開して3年目の冬。 一層楽しい定例会が期待できます。 スタッフの嬉しい嬉しい成長です。 #船橋ウォーキングソサイエティ #心も若く身体も若く #日本ポールウォーキング #全日本ノルディックウォーク #日本ノルディックウォーキング #ソーシャルフィットネス協会
【千昌夫の北国の春】 2024/1/11 #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース 冬メニュー #サーキットトレーニング。 考慮すべき点が多い木曜日定例会。 諦めずに繰り返しが大切ですね。 繰り返す事でスタッフの 指導力が上がり、 花壇円周50mを上手く使い 誘導できるようになりました。 万事スムーズです。 コロナ禍で中断し、 再開して3年目の冬。 一層楽しい定例会が期待できます。 スタッフの嬉しい嬉しい成長です。 #船橋ウォーキングソサイエティ #心も若く身体も若く #日本ポールウォーキング #全日本ノルディックウォーク #日本ノルディックウォーキング #ソーシャルフィットネス協会 本日は渋谷クラス4学期初日。 介護保険課の指導で恒例の体力測定。 筋バランスが不安定で片足立ちを継続できる方が少なかった。講習会でのポールの効果を期待します。 嬉しかったのは椅子からの立ち上がりの難しい方(要介護2)が今回ポールを知って感動しましたと声を掛けてくださったこと。
本日は渋谷クラス4学期初日。 介護保険課の指導で恒例の体力測定。 筋バランスが不安定で片足立ちを継続できる方が少なかった。講習会でのポールの効果を期待します。 嬉しかったのは椅子からの立ち上がりの難しい方(要介護2)が今回ポールを知って感動しましたと声を掛けてくださったこと。 新年初のポールウォーキングベーシックセミナーでした。 受講者は2名。 介護福祉士さんと公共施設で指導予定の方々です。 かなり実技に時間を費やしました。 毎回、私自身も学びがあります。 気を引き締めて行わなくては!と反省もありました。 いつものコース…北条実時のお墓がある金沢文庫 称名寺です。 先日までたくさんあった達磨さん達はもう無くて、少しだけあった達磨さん。 ちょっと寂しい… #ポールウォーキング #ベーシックセミナー #称名寺 #北条実時 #金沢文庫
新年初のポールウォーキングベーシックセミナーでした。 受講者は2名。 介護福祉士さんと公共施設で指導予定の方々です。 かなり実技に時間を費やしました。 毎回、私自身も学びがあります。 気を引き締めて行わなくては!と反省もありました。 いつものコース…北条実時のお墓がある金沢文庫 称名寺です。 先日までたくさんあった達磨さん達はもう無くて、少しだけあった達磨さん。 ちょっと寂しい… #ポールウォーキング #ベーシックセミナー #称名寺 #北条実時 #金沢文庫 新年初の「気ままにポール歩き」 杉並区立桃井原っぱ公園に集まって、観泉寺、切り通し公園、井草八幡神社、善福寺、都立善福寺公園などをめぐりました。途中おやつタイムを設けて一服。 体調をくずしてキャンセルとなった常連メンバーも複数出たのは残念でしたが、西荻窪の「洋食みかさ」でカンパイ、ウォーキングや健康に関係ない話題で盛り上がりました。 この会は、NPOとして開催してきた杉並ポール歩きの会(杉ポ)を休会としたあと、個人的な少人数の会として続けてきました。下見無し、指導無し、公募無し、参加費無しで、私の運動習慣につきあってもらっています。
新年初の「気ままにポール歩き」 杉並区立桃井原っぱ公園に集まって、観泉寺、切り通し公園、井草八幡神社、善福寺、都立善福寺公園などをめぐりました。途中おやつタイムを設けて一服。 体調をくずしてキャンセルとなった常連メンバーも複数出たのは残念でしたが、西荻窪の「洋食みかさ」でカンパイ、ウォーキングや健康に関係ない話題で盛り上がりました。 この会は、NPOとして開催してきた杉並ポール歩きの会(杉ポ)を休会としたあと、個人的な少人数の会として続けてきました。下見無し、指導無し、公募無し、参加費無しで、私の運動習慣につきあってもらっています。 ポールウォーキングベーシックコーチ講座…の巻 今日はポールウォーキングベーシックコーチ講座でした。 ポールウォーキングは日本のスポーツドクターが考案した2本のポールを使用したウォーキングです。 ポールを持つことで、安定したウォーキング、歩行姿勢の改善に効果があり、歩ける限りずっと続けられる全身運動です。 普段運動不足の私が1度体験して、これは素晴らしい✨と惚れ込んだウォーキングスタイル。 6名集まれば、郡山で講座ができるということで、長岡智津子先生には、はるばる千葉県我孫子市からお越しいただきました。 予定より2名も多く8名集まり郡山でのトレーナー資格講座を実現することができました。 座学&実技4時間の講習 お天気にも恵まれ、青空の下実技講習ができました。 終了後は先生を囲んで親睦会🍻 郡山名物が揃う「居酒屋 安兵衛」さんにお邪魔しました。 来月みんなでブラッシュアップしようという事に。 さっそく明日からポールを持って歩くぞ!
ポールウォーキングベーシックコーチ講座…の巻 今日はポールウォーキングベーシックコーチ講座でした。 ポールウォーキングは日本のスポーツドクターが考案した2本のポールを使用したウォーキングです。 ポールを持つことで、安定したウォーキング、歩行姿勢の改善に効果があり、歩ける限りずっと続けられる全身運動です。 普段運動不足の私が1度体験して、これは素晴らしい✨と惚れ込んだウォーキングスタイル。 6名集まれば、郡山で講座ができるということで、長岡智津子先生には、はるばる千葉県我孫子市からお越しいただきました。 予定より2名も多く8名集まり郡山でのトレーナー資格講座を実現することができました。 座学&実技4時間の講習 お天気にも恵まれ、青空の下実技講習ができました。 終了後は先生を囲んで親睦会🍻 郡山名物が揃う「居酒屋 安兵衛」さんにお邪魔しました。 来月みんなでブラッシュアップしようという事に。 さっそく明日からポールを持って歩くぞ! 年明け恒例の ポールウォークで長野/善光寺七福神巡り&善光寺詣❗️ 年始より地震災害 飛行機事故と悲しい始まりとなりましたが、今回は20名程の詣者で百福万来を祈願しました。 長野駅近の不老人さん/西光寺から善光寺門前の毘沙門天さんまで中央通り(善光寺表参道)沿いPW約3km❗️ 本堂初詣後境内傍に在る「佛足跡」で一年の無事PW(歩き)のお願いも忘れずに〜‼️ ランチは宿坊/兄近坊(このこんぼう)での精進を頂き食べ過ぎシニアの予防に一歩でも近づければと・・。
年明け恒例の ポールウォークで長野/善光寺七福神巡り&善光寺詣❗️ 年始より地震災害 飛行機事故と悲しい始まりとなりましたが、今回は20名程の詣者で百福万来を祈願しました。 長野駅近の不老人さん/西光寺から善光寺門前の毘沙門天さんまで中央通り(善光寺表参道)沿いPW約3km❗️ 本堂初詣後境内傍に在る「佛足跡」で一年の無事PW(歩き)のお願いも忘れずに〜‼️ ランチは宿坊/兄近坊(このこんぼう)での精進を頂き食べ過ぎシニアの予防に一歩でも近づければと・・。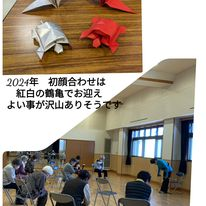 屋内だから思い切って歩ける それがいい! シニアポールウォーキング 2024/1/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ポールエクササイズ #チェアエクササイズ #昭和メロディ #コグニサイズ #転倒予防 #ソーシャルフィットネス #ストレッチ筋トレであるける身体づくり
屋内だから思い切って歩ける それがいい! シニアポールウォーキング 2024/1/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ポールエクササイズ #チェアエクササイズ #昭和メロディ #コグニサイズ #転倒予防 #ソーシャルフィットネス #ストレッチ筋トレであるける身体づくり 今季一番の冷え込み、のはずでしたがストレッチ・筋トレをしたあと山を登っているうちに身体が温かくなってきました。 新メンバー5名増えて更に賑やか(お喋りが)なグループになりました。
今季一番の冷え込み、のはずでしたがストレッチ・筋トレをしたあと山を登っているうちに身体が温かくなってきました。 新メンバー5名増えて更に賑やか(お喋りが)なグループになりました。 渋谷は新しいまちづくりが進んでいますが この飲んべえ横丁は昔のまま。 珍しいのか 外人が写真を撮っていました📸 渋谷PW教室 4期2日目の今日は、ポールの種類とゴムチップ、なんば歩きの質問に答え、大鏡に各々自分の姿を映し(うっとりし?)ながらストレッチ・筋トレ・ウォーキングを時間一杯楽しみました💦
渋谷は新しいまちづくりが進んでいますが この飲んべえ横丁は昔のまま。 珍しいのか 外人が写真を撮っていました📸 渋谷PW教室 4期2日目の今日は、ポールの種類とゴムチップ、なんば歩きの質問に答え、大鏡に各々自分の姿を映し(うっとりし?)ながらストレッチ・筋トレ・ウォーキングを時間一杯楽しみました💦 【大寒で午後は雨天予報】 口々に出る言葉は 「寒いね〜」 「雨、大丈夫〜?」 インターバルを14分2セット。 直ぐに暖かくなる人、 なかなか暖かくならない人 普通にいろんなメンバーがいます。 その後、10分間のしっかり歩きで 寒がりさんもホカホカです。 冬だからこそのメニューでね。
【大寒で午後は雨天予報】 口々に出る言葉は 「寒いね〜」 「雨、大丈夫〜?」 インターバルを14分2セット。 直ぐに暖かくなる人、 なかなか暖かくならない人 普通にいろんなメンバーがいます。 その後、10分間のしっかり歩きで 寒がりさんもホカホカです。 冬だからこそのメニューでね。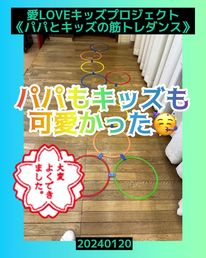 20240120 パパとキッズの筋トレダンス。 1歳2ヶ月から6歳のkidsとパパママ達。 kidsは当たり前だけどパパママも最高に可愛く素敵でした。 参加下さりありがとうございました。 ロビーでの昼食を挟み 午後からはスマイル特別練習でした。 みんなお疲れ様でした♪ #スマイルチーム #健康普及活動 #マタニティからシニアまで #相模原市 #上鶴間公民館
20240120 パパとキッズの筋トレダンス。 1歳2ヶ月から6歳のkidsとパパママ達。 kidsは当たり前だけどパパママも最高に可愛く素敵でした。 参加下さりありがとうございました。 ロビーでの昼食を挟み 午後からはスマイル特別練習でした。 みんなお疲れ様でした♪ #スマイルチーム #健康普及活動 #マタニティからシニアまで #相模原市 #上鶴間公民館 佐久ポールウォーキング協会より 1月「室内PW」〜 大雪予報が外れ〜雨☔の中集まってくれた参加者30名程。 微暖房の効いた体育館で、 大塚MC proの身体ほぐしのレクからブローライフルで心肺機能up〜 締めのポールウォーキングは🔰依田MC pro指導で体験コースとシッカリ歩きに分かれての室内PWでした。 次回は最終イベントで2/18(日)です。
佐久ポールウォーキング協会より 1月「室内PW」〜 大雪予報が外れ〜雨☔の中集まってくれた参加者30名程。 微暖房の効いた体育館で、 大塚MC proの身体ほぐしのレクからブローライフルで心肺機能up〜 締めのポールウォーキングは🔰依田MC pro指導で体験コースとシッカリ歩きに分かれての室内PWでした。 次回は最終イベントで2/18(日)です。 寒くなるとつらさが増しがちな肩こりや腰痛。肩こりや腰痛ってどうして起こる?改善する方法は?
寒くなるとつらさが増しがちな肩こりや腰痛。肩こりや腰痛ってどうして起こる?改善する方法は? 【だるまさんが転んだ!】 日曜日は総合型地域スポーツクラブ ぴいすく美川主催によるACP運動あそび教室でした。年中児から小学3年生までのちびっこたちが参加してくれました! このプログラムは子どもたちに必要な 基礎体力、体幹づくり。 今回は「はう、くぐる、またぐ」 ワニ、くま、くも になりながらだるまさんが転んだをしたり、アスレチックでは友達と協力しながら 楽しんでいました。 後半は大きなボール「キンボール」を楽しみました。 石川県では【地震】と言う言葉にビクビクしている子ども達もいます。思い切りからだを動かし、少しでも解放できたらと 運動あそびをしましょう‼️ 今日もキラキラした目の輝きをみました。 次回は3月です。 #ぴいすく美川 #acp運動プログラム #こども #石川県 #運動あそび
【だるまさんが転んだ!】 日曜日は総合型地域スポーツクラブ ぴいすく美川主催によるACP運動あそび教室でした。年中児から小学3年生までのちびっこたちが参加してくれました! このプログラムは子どもたちに必要な 基礎体力、体幹づくり。 今回は「はう、くぐる、またぐ」 ワニ、くま、くも になりながらだるまさんが転んだをしたり、アスレチックでは友達と協力しながら 楽しんでいました。 後半は大きなボール「キンボール」を楽しみました。 石川県では【地震】と言う言葉にビクビクしている子ども達もいます。思い切りからだを動かし、少しでも解放できたらと 運動あそびをしましょう‼️ 今日もキラキラした目の輝きをみました。 次回は3月です。 #ぴいすく美川 #acp運動プログラム #こども #石川県 #運動あそび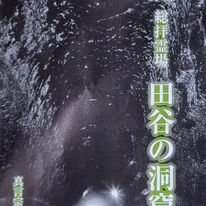 大船駅からバスで15分程のところにある「田谷の洞窟」という処に、元富士通スタジアムポールウォーキング教室のメンバーさんたちと共に行ってまいりました。 いや、正しくは「行ってきました」というより「連れて行ってもらいました」というべきですね…。 当初メンバーさんから「田谷の洞窟に行ってみませんか?」と誘われた時、「洞窟」と聞いて私は勝手に鍾乳洞的なものを想像してしまったのですが、ここはそれとはまったく違いました。 「田谷の洞窟」は「田谷山定泉寺」に所在し、正式名称を「田谷山瑜伽洞(ゆがどう)」といって、修行僧がひたすら掘り進めた宗教的な意義のある洞窟なのだそうです。 私は何の前調べもせずにただついて行っただけなのですが、18か所の壁面に刻まれた数百体の御仏や仏法説話について、メンバーさんのお一人の方が詳しく説明をしていってくれたので、本当に色々と勉強になりましたし、きちんとお詣りすることができました。 今回私は「PWコーチ」という立場ではなく、まったくの「1参加者」としてこの企画に同行させていただいたのですが、人生の先輩方から学ぶことも多く、とても貴重な体験を得ることができました。 (洞窟の中は撮影禁止だったので、洞窟に入る前と後で写真を撮りました)。
大船駅からバスで15分程のところにある「田谷の洞窟」という処に、元富士通スタジアムポールウォーキング教室のメンバーさんたちと共に行ってまいりました。 いや、正しくは「行ってきました」というより「連れて行ってもらいました」というべきですね…。 当初メンバーさんから「田谷の洞窟に行ってみませんか?」と誘われた時、「洞窟」と聞いて私は勝手に鍾乳洞的なものを想像してしまったのですが、ここはそれとはまったく違いました。 「田谷の洞窟」は「田谷山定泉寺」に所在し、正式名称を「田谷山瑜伽洞(ゆがどう)」といって、修行僧がひたすら掘り進めた宗教的な意義のある洞窟なのだそうです。 私は何の前調べもせずにただついて行っただけなのですが、18か所の壁面に刻まれた数百体の御仏や仏法説話について、メンバーさんのお一人の方が詳しく説明をしていってくれたので、本当に色々と勉強になりましたし、きちんとお詣りすることができました。 今回私は「PWコーチ」という立場ではなく、まったくの「1参加者」としてこの企画に同行させていただいたのですが、人生の先輩方から学ぶことも多く、とても貴重な体験を得ることができました。 (洞窟の中は撮影禁止だったので、洞窟に入る前と後で写真を撮りました)。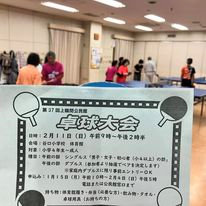 2024.1.19〜22 活動記録 ☺︎上鶴間卓球愛好会 総勢15名 久々の卓球🏓 素晴らしいコーチのお陰様でみなさん上達していました👏👏👏 ダブルストーナメント優勝者には素敵な賞品があり試合も盛り上がりました ☺︎キッズ愛LOVEプロジェクト[上鶴間公民館] ♡パパとキッズの筋トレダンス♡ 1歳2ヶ月〜6歳の女の子とパパが 7組 お兄ちゃんやママも来てくれて 幸せな2時間でした〜可愛すぎた🥰 ☺︎公民館祭り練習会 7名参加 5曲練習 立ち位置や衣装も決めました お部屋の掃除は2年生のスマイルメンバーが率先してしっかりと行ってくれました🧹 ☺︎上溝、上鶴間公民館祭り衣装等準備 ガレージ整理しながら準備しました ☺︎スマイルフレンズ 16名参加 2組に分かれてリズムダンスの動画撮影🎥 ☺︎ルネPW 4名参加 ポールのグループレッスンです 今日参加の3名は整形外科でリハビリを行なっていますのでPWもリハビリ的に行っています メンバーから晩白柚をいただきました🍊食べるのが楽しみ 皮はお風呂に入れてみます♨️ ☺︎新磯包括支援センターと電話打合せ 3月に出張介護予防教室依頼されました ☺︎相模原SDG’s推進課より チラシとノベルティが届きました チラシはフレンズのメンバーに配りました
2024.1.19〜22 活動記録 ☺︎上鶴間卓球愛好会 総勢15名 久々の卓球🏓 素晴らしいコーチのお陰様でみなさん上達していました👏👏👏 ダブルストーナメント優勝者には素敵な賞品があり試合も盛り上がりました ☺︎キッズ愛LOVEプロジェクト[上鶴間公民館] ♡パパとキッズの筋トレダンス♡ 1歳2ヶ月〜6歳の女の子とパパが 7組 お兄ちゃんやママも来てくれて 幸せな2時間でした〜可愛すぎた🥰 ☺︎公民館祭り練習会 7名参加 5曲練習 立ち位置や衣装も決めました お部屋の掃除は2年生のスマイルメンバーが率先してしっかりと行ってくれました🧹 ☺︎上溝、上鶴間公民館祭り衣装等準備 ガレージ整理しながら準備しました ☺︎スマイルフレンズ 16名参加 2組に分かれてリズムダンスの動画撮影🎥 ☺︎ルネPW 4名参加 ポールのグループレッスンです 今日参加の3名は整形外科でリハビリを行なっていますのでPWもリハビリ的に行っています メンバーから晩白柚をいただきました🍊食べるのが楽しみ 皮はお風呂に入れてみます♨️ ☺︎新磯包括支援センターと電話打合せ 3月に出張介護予防教室依頼されました ☺︎相模原SDG’s推進課より チラシとノベルティが届きました チラシはフレンズのメンバーに配りました 昨年撮ったポールウォーキング動画を整理していたら、こんな動画が。 都内の大学生がゼミの研究のためポールウォーキング体験と参加者へのヒアリングをしに佐久まで来てくれた時のものです。 コーチ達からの指導をものともせず、弾ける笑顔で歩ききる学生達。この笑顔にコーチ、参加者やられました✨ またおいでねー!と、うちでとれたトマト、やら、うちで漬けた漬物、佃煮など持たせる持たせる😆 楽しい交流でした。
昨年撮ったポールウォーキング動画を整理していたら、こんな動画が。 都内の大学生がゼミの研究のためポールウォーキング体験と参加者へのヒアリングをしに佐久まで来てくれた時のものです。 コーチ達からの指導をものともせず、弾ける笑顔で歩ききる学生達。この笑顔にコーチ、参加者やられました✨ またおいでねー!と、うちでとれたトマト、やら、うちで漬けた漬物、佃煮など持たせる持たせる😆 楽しい交流でした。 三浦PWグループの定例会は鎌倉七福神巡り・・・まずは浄智寺布袋さまに。七福神だけに限らずあちらこちら寄りながら今年のスタートとなりました。逗子からお客様も参加。
三浦PWグループの定例会は鎌倉七福神巡り・・・まずは浄智寺布袋さまに。七福神だけに限らずあちらこちら寄りながら今年のスタートとなりました。逗子からお客様も参加。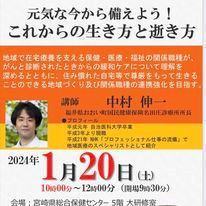 今年初の講演、中村理事長とのセットメニューは、やはり楽しかったです。 講演後の宮崎名物は、やはり美味しかったです
今年初の講演、中村理事長とのセットメニューは、やはり楽しかったです。 講演後の宮崎名物は、やはり美味しかったです 昨日、市川さんのチャリティー講座に参加しましていろいろな学びをしました。 クロージングは私も苦手意識がありますが、こちらがお願いするのではなく、お願いされて買っていただける、そんな魔法のようなお話しなのですが、市川さんの講座が進むにつれて、なるほど❗️と思った次第です。 やはり大切なのは、お客様ファースト、お客様との共感です。 こちらの一方的な商品の押し売りでは、『ぜひ』、『よろしければ』、『〜してください』の禁句を使ってしまいます。 そのためにも相手に関心を持ち、お客様がムズムズしてくるような質問をしていくことが大切。 しかし、これも日々のトレーニングなんですよね。 顔晴ります❗️
昨日、市川さんのチャリティー講座に参加しましていろいろな学びをしました。 クロージングは私も苦手意識がありますが、こちらがお願いするのではなく、お願いされて買っていただける、そんな魔法のようなお話しなのですが、市川さんの講座が進むにつれて、なるほど❗️と思った次第です。 やはり大切なのは、お客様ファースト、お客様との共感です。 こちらの一方的な商品の押し売りでは、『ぜひ』、『よろしければ』、『〜してください』の禁句を使ってしまいます。 そのためにも相手に関心を持ち、お客様がムズムズしてくるような質問をしていくことが大切。 しかし、これも日々のトレーニングなんですよね。 顔晴ります❗️ 西鎌倉界隈にメンバー増員の流行風が吹いています。 広町緑地グループに続いて今日のなごやかセンター貯筋の会も新入会員さんが一度に4名増えました。思わず「番号」って号令かけてしまいました。行政センターの貼紙を見たという方、町内会の掲示板をご覧になられた方・・・広町から移動された方、貼紙PRは力を発揮してくれます。 90の女性はヨガをしていたそうで身体が柔らか。去年まで現役ヘルパーだったという85の女性はどうみても80代には見えず若々しい。教養センター講座に参加していらした方も入会してくださいました。 嬉しくて私も引き出しをめいっぱい開けてステップエクササイズやポールダンスまでして汗だく👕💦 写真は とろろ蕎麦 (でした)
西鎌倉界隈にメンバー増員の流行風が吹いています。 広町緑地グループに続いて今日のなごやかセンター貯筋の会も新入会員さんが一度に4名増えました。思わず「番号」って号令かけてしまいました。行政センターの貼紙を見たという方、町内会の掲示板をご覧になられた方・・・広町から移動された方、貼紙PRは力を発揮してくれます。 90の女性はヨガをしていたそうで身体が柔らか。去年まで現役ヘルパーだったという85の女性はどうみても80代には見えず若々しい。教養センター講座に参加していらした方も入会してくださいました。 嬉しくて私も引き出しをめいっぱい開けてステップエクササイズやポールダンスまでして汗だく👕💦 写真は とろろ蕎麦 (でした) 【ポールdeダンス】 このシーズンはこれもいい! 2024/1/25 松尾コーチの話術とリードで 乗せ上手に 乗せられ上手なメンバー 「真っ赤な太陽」で とっても楽しそう〜♬ 今日の行田公園広場は 2つの対象的な 集団の競演です ◯園児のマラソン練習 ◯船橋歌劇団(笑い) それぞれが一生懸命なのが いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールdeダンス #県立行田公園 #ポールエクサイズ #体幹トレーニング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング
【ポールdeダンス】 このシーズンはこれもいい! 2024/1/25 松尾コーチの話術とリードで 乗せ上手に 乗せられ上手なメンバー 「真っ赤な太陽」で とっても楽しそう〜♬ 今日の行田公園広場は 2つの対象的な 集団の競演です ◯園児のマラソン練習 ◯船橋歌劇団(笑い) それぞれが一生懸命なのが いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールdeダンス #県立行田公園 #ポールエクサイズ #体幹トレーニング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング 今年になって始まった大岡山の東急ウェリナでのポールウォーキングクラス。2回目。 初回は、どの様な方がいらしてくださるのか?様子を見ながら。 今回は指導内容も変更し、それとなく2クラスに分けることにしました。 高級ホテルの様な素晴らしい施設です。中庭には利用者さまが育てているお花や野菜や。小川も流れてたくさんの鳥達も来ていました。 お庭を歩くだけでも気持ちが良い。 ポールでお散歩!が定着してくれると嬉しいですナ
今年になって始まった大岡山の東急ウェリナでのポールウォーキングクラス。2回目。 初回は、どの様な方がいらしてくださるのか?様子を見ながら。 今回は指導内容も変更し、それとなく2クラスに分けることにしました。 高級ホテルの様な素晴らしい施設です。中庭には利用者さまが育てているお花や野菜や。小川も流れてたくさんの鳥達も来ていました。 お庭を歩くだけでも気持ちが良い。 ポールでお散歩!が定着してくれると嬉しいですナ
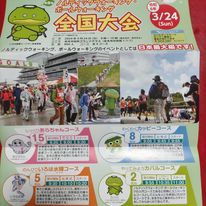 【3/24(日)志木市ノルディックウォーキング・ポールウォーキング】 初心者(2キロ)から長距離(15キロ)までの4コース。 申込み方法も4つ。 ネット、電話、FAX、市役所窓口 ※写真参照 ☀あとは快晴を願うだけ😁
【3/24(日)志木市ノルディックウォーキング・ポールウォーキング】 初心者(2キロ)から長距離(15キロ)までの4コース。 申込み方法も4つ。 ネット、電話、FAX、市役所窓口 ※写真参照 ☀あとは快晴を願うだけ😁 くにたちの今年(2024年)のイベントは5月12日(日) 東京国立市で毎年開催されている「LINKくにたち ポールdeウォーク」の今年の予定が決まりました。
くにたちの今年(2024年)のイベントは5月12日(日) 東京国立市で毎年開催されている「LINKくにたち ポールdeウォーク」の今年の予定が決まりました。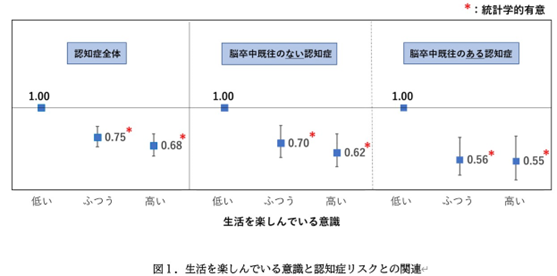 さらに、自覚的ストレスが生活を楽しんでいる意識と認知症の関係に与えている影響を調べるため、生活を楽しんでいる意識の調査と同時点における自覚的ストレスについても調べてみたところ、自覚的ストレスが「少ない」および「ふつう」のグループでは、生活を楽しんでいる意識が低い人と比較して、中程度ならびに高い人では認知症リスクが統計学的有意に低く、さらに脳卒中の既往のない認知症、既往のある認知症のいずれも同様でした。一方、自覚的ストレスが「多い」グループでは、生活を楽しんでいる意識と認知症リスクの間に統計学的有意な差はみられず、認知症のタイプ別に分けた解析の場合でも、生活を楽しんでいる意識と脳卒中の既往のない認知症との関連がみられませんでした (図2)。
さらに、自覚的ストレスが生活を楽しんでいる意識と認知症の関係に与えている影響を調べるため、生活を楽しんでいる意識の調査と同時点における自覚的ストレスについても調べてみたところ、自覚的ストレスが「少ない」および「ふつう」のグループでは、生活を楽しんでいる意識が低い人と比較して、中程度ならびに高い人では認知症リスクが統計学的有意に低く、さらに脳卒中の既往のない認知症、既往のある認知症のいずれも同様でした。一方、自覚的ストレスが「多い」グループでは、生活を楽しんでいる意識と認知症リスクの間に統計学的有意な差はみられず、認知症のタイプ別に分けた解析の場合でも、生活を楽しんでいる意識と脳卒中の既往のない認知症との関連がみられませんでした (図2)。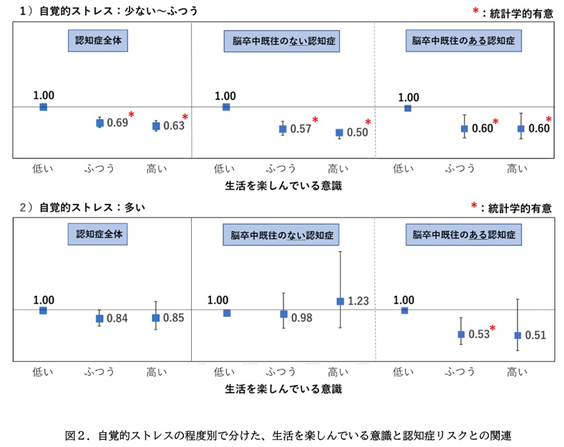 ◆今後の展開
◆今後の展開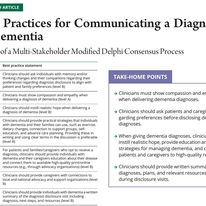 認知症の診断を伝えるための7つの新しい最善の方法(Best practice)
認知症の診断を伝えるための7つの新しい最善の方法(Best practice) COVID-19感染後認知症は20歳の加齢に相当し,感染から1年経過しても脳損傷が持続する!
COVID-19感染後認知症は20歳の加齢に相当し,感染から1年経過しても脳損傷が持続する!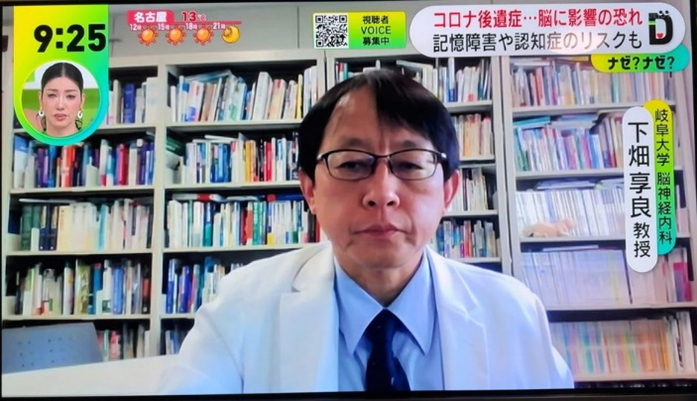 昨日の日本テレビの情報番組「DayDay.」の「FOCUSなぜなぜ」というコーナーに,VTRで出演させていただきました.新型コロナでは後遺症として,記憶障害,集中力障害をきたし,さらに認知症のリスクも上昇しうること,その機序として脳への感染などが報告されていることを紹介させていただきました.じつは「COVID-19から脳を守ることを啓発し,流行時は感染対策(手洗い,マスク),そしてワクチン接種の継続を検討する必要がある」ということをとくにお伝えしたかったのですが,「新型コロナは後遺症を起こす病気」という話題が主体でした.脳への影響についてもう少しお伝えしたかったなと思いました.今度はスタジオに行って解説するぞという野望を持ちました(笑.冗談です).もっと詳しく聴きたかったというメッセージも複数 頂きました.スタッフの方への説明資料として使用したスライド26枚のリンクはこちらになります.よろしければご覧ください.
昨日の日本テレビの情報番組「DayDay.」の「FOCUSなぜなぜ」というコーナーに,VTRで出演させていただきました.新型コロナでは後遺症として,記憶障害,集中力障害をきたし,さらに認知症のリスクも上昇しうること,その機序として脳への感染などが報告されていることを紹介させていただきました.じつは「COVID-19から脳を守ることを啓発し,流行時は感染対策(手洗い,マスク),そしてワクチン接種の継続を検討する必要がある」ということをとくにお伝えしたかったのですが,「新型コロナは後遺症を起こす病気」という話題が主体でした.脳への影響についてもう少しお伝えしたかったなと思いました.今度はスタジオに行って解説するぞという野望を持ちました(笑.冗談です).もっと詳しく聴きたかったというメッセージも複数 頂きました.スタッフの方への説明資料として使用したスライド26枚のリンクはこちらになります.よろしければご覧ください.
 午前中は渋谷PW教室 今期のステップウォーキングの実習がようやくできました 隣の消防署はなにやら慌ただしい
午前中は渋谷PW教室 今期のステップウォーキングの実習がようやくできました 隣の消防署はなにやら慌ただしい 【碧天! 海だ〜】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日定例会海老川コース 2023/12/2 あまりにも美しい碧天に 予定を変更! 急遽、港⚓🌊に向かいました〜☀ 「踵接地〜爪先離地?」 昨入会したメンバーに向け途中でミニ講習。 歩き方ばかりではなく、 何故、大切か❣ ふくらはぎを触って確認。 腑に落ちたようです。 水門を通って親水公園に到着〜 「船橋市に住んで◯十年、港も水門も初めて見た〜」 いつも嬉しい反応です。 \(^o^)/ #ミルキングアクション #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #船橋港親水公園
【碧天! 海だ〜】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日定例会海老川コース 2023/12/2 あまりにも美しい碧天に 予定を変更! 急遽、港⚓🌊に向かいました〜☀ 「踵接地〜爪先離地?」 昨入会したメンバーに向け途中でミニ講習。 歩き方ばかりではなく、 何故、大切か❣ ふくらはぎを触って確認。 腑に落ちたようです。 水門を通って親水公園に到着〜 「船橋市に住んで◯十年、港も水門も初めて見た〜」 いつも嬉しい反応です。 \(^o^)/ #ミルキングアクション #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #船橋港親水公園 2023.12.2 ☺︎中屋敷 活き活きポールウォーキング ☺︎上鶴間公民館青少年部 わんぱくチャレンジ キャンドル作り
2023.12.2 ☺︎中屋敷 活き活きポールウォーキング ☺︎上鶴間公民館青少年部 わんぱくチャレンジ キャンドル作り 佐久ポールウォーキング協会より シーズン最後の外歩き〜 駒場PW定例会でした。 集合場所の噴水池も結氷した朝 40名を越えるポールウォーカーが集まってくれました。 会場のゴミ拾いを兼ねた定例会を皆さん〜ゆっくり〜のんびり〜と歩かれて居たのが印象的でした。 皆さんお疲れ様でした。 良い歳をお迎えください‼️
佐久ポールウォーキング協会より シーズン最後の外歩き〜 駒場PW定例会でした。 集合場所の噴水池も結氷した朝 40名を越えるポールウォーカーが集まってくれました。 会場のゴミ拾いを兼ねた定例会を皆さん〜ゆっくり〜のんびり〜と歩かれて居たのが印象的でした。 皆さんお疲れ様でした。 良い歳をお迎えください‼️ 手袋の🧤ありがたみを感じた朝 御所ケ丘広町緑地PWクラスの定例会 風邪でお休みが二人 木道~うさぎ山🐰を歩きました こんな曇りの朝でしたが水墨画のように富士山がはっきり見えて感動🗻
手袋の🧤ありがたみを感じた朝 御所ケ丘広町緑地PWクラスの定例会 風邪でお休みが二人 木道~うさぎ山🐰を歩きました こんな曇りの朝でしたが水墨画のように富士山がはっきり見えて感動🗻 【いろんなのやって楽しかった〜♬】 2023/12/5 と言ってもメーンメニューは 二つだけどネ コーディネーションウォーク インターバルウォーク 寒さはどこに〜? 吹き飛んでいきました〜〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 #パワーウォーキング #コーディネーションウォーキング #インターバルウォーキング #良い歩き方は一生の宝 #行田公園 #踵接地爪先離地
【いろんなのやって楽しかった〜♬】 2023/12/5 と言ってもメーンメニューは 二つだけどネ コーディネーションウォーク インターバルウォーク 寒さはどこに〜? 吹き飛んでいきました〜〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 #パワーウォーキング #コーディネーションウォーキング #インターバルウォーキング #良い歩き方は一生の宝 #行田公園 #踵接地爪先離地 12月3日に、スキルアップ研修会(東京会場)を実施しました。 参加者35名と今年最多のコーチに参加頂きました。 冬の寒さに耐えながら、皆さん熱心に研修されました。 お疲れ様でした‼️
12月3日に、スキルアップ研修会(東京会場)を実施しました。 参加者35名と今年最多のコーチに参加頂きました。 冬の寒さに耐えながら、皆さん熱心に研修されました。 お疲れ様でした‼️ 本日は午前、午後、通しで愛知県丹羽郡大口町保健センターのお仕事で、「健康推進員研修会」の講師のお仕事でした。 午前、午後、それぞれ30名ほどの皆さんが参加されました。町民の皆さんに各地区で健康づくりの輪を広げるべく、この健康推進員の養成を保健センターが担い、外部講師として務めさせていただきました。 30〜40歳台の若い方から70歳代のシニアの皆さんと幅広い年代の皆さんでした。 各人、体組成測定をしまして、その結果を踏まえて自分の体力アップのためにどうするかというお話と実技をさせていただきました。 コロナが落ち着き、こうした場が以前同様に開催いただけるようになったことを本当にありがたいなと感じでおります。 90分ほどの講習会でした。ちょいと盛りだくさんだったかなと思いますが、一つでも実践いただくことを最後にしっかりとお伝えし、来年の7月にこのパート2の研修会が開催される予定ですので、そこでこの半年間の皆さんの行動をお聞きしたいと思います。 インプットしたら、それをどう活用するかのアウトプットの大切さをお伝えしたつもりですが、7月、皆さんの体組成の変化や、どんな行動をしたかをお聞きすれば、本日の私が伝えたかったことが本当に伝わったかどうかがわかります。 楽しみです😊
本日は午前、午後、通しで愛知県丹羽郡大口町保健センターのお仕事で、「健康推進員研修会」の講師のお仕事でした。 午前、午後、それぞれ30名ほどの皆さんが参加されました。町民の皆さんに各地区で健康づくりの輪を広げるべく、この健康推進員の養成を保健センターが担い、外部講師として務めさせていただきました。 30〜40歳台の若い方から70歳代のシニアの皆さんと幅広い年代の皆さんでした。 各人、体組成測定をしまして、その結果を踏まえて自分の体力アップのためにどうするかというお話と実技をさせていただきました。 コロナが落ち着き、こうした場が以前同様に開催いただけるようになったことを本当にありがたいなと感じでおります。 90分ほどの講習会でした。ちょいと盛りだくさんだったかなと思いますが、一つでも実践いただくことを最後にしっかりとお伝えし、来年の7月にこのパート2の研修会が開催される予定ですので、そこでこの半年間の皆さんの行動をお聞きしたいと思います。 インプットしたら、それをどう活用するかのアウトプットの大切さをお伝えしたつもりですが、7月、皆さんの体組成の変化や、どんな行動をしたかをお聞きすれば、本日の私が伝えたかったことが本当に伝わったかどうかがわかります。 楽しみです😊 【富山ポールウォーキング部】 今日は参加者5人。 最高のお天気でした! しっかり筋トレを交えたポールを使ったストレッチ。 パソコン作業ばかりで椅子に根っこがはえそうな今日この頃。身体の劣化が‥ポールを持つとすぐわかってしまいます(//∇//) 約7km程の🚶中島閘門までのウォーキング。素晴らしいお天気に恵まれ、リフレッシュできる会となりました☀️ 父母と同世代の方と一緒に歩くと、あと30年経ったら自分はどうなっていたいか‥素敵な✨光輝高齢者✨さんと過ごさせていただくことで、日々の運動、メンテナンスの大切を感じさせていただけます。
【富山ポールウォーキング部】 今日は参加者5人。 最高のお天気でした! しっかり筋トレを交えたポールを使ったストレッチ。 パソコン作業ばかりで椅子に根っこがはえそうな今日この頃。身体の劣化が‥ポールを持つとすぐわかってしまいます(//∇//) 約7km程の🚶中島閘門までのウォーキング。素晴らしいお天気に恵まれ、リフレッシュできる会となりました☀️ 父母と同世代の方と一緒に歩くと、あと30年経ったら自分はどうなっていたいか‥素敵な✨光輝高齢者✨さんと過ごさせていただくことで、日々の運動、メンテナンスの大切を感じさせていただけます。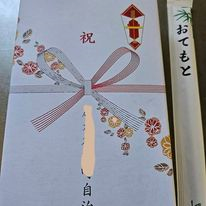 毎年地元町内自治会から高齢者宅にお赤飯が配られます。母が不在なので一人前。㊗️とあるので敬老の日? お昼に頂いて、強風のなか午後の高齢者介護予防教室で高齢者が高齢者指導して来ました。前半ポール体操、後半マット運動。年内このクラスは来週でおしまいです。今日も肝油ドロップや脱脂粉乳、DDTなど共通の話題が多く盛り上がりました。
毎年地元町内自治会から高齢者宅にお赤飯が配られます。母が不在なので一人前。㊗️とあるので敬老の日? お昼に頂いて、強風のなか午後の高齢者介護予防教室で高齢者が高齢者指導して来ました。前半ポール体操、後半マット運動。年内このクラスは来週でおしまいです。今日も肝油ドロップや脱脂粉乳、DDTなど共通の話題が多く盛り上がりました。 [レポート]12月の「気ままにポール歩き」は高井戸地域区民センターに集合、善福寺川緑地と大田黒公園を経由して荻窪駅まで歩きました。 途中、メンバーの一人Aさんのお宅に寄り、Aさんが世界各地を旅して集めてきた人形や小物などの膨大なコレクションを見せてもらいました。感嘆! 今年3月に始めたこの会、なんといちども雨に降られずでした。快晴のもと快適に歩いて、忘年会ランチを楽しみました。 ※写真の多くは田村和史さん撮影。一部校條諭。 ※この会は、少人数グループで、杉並区など近隣の人が集まって、街探訪を兼ねて歩いています。(経験者限定、指導無し、レンタルポール無し、下見無し)
[レポート]12月の「気ままにポール歩き」は高井戸地域区民センターに集合、善福寺川緑地と大田黒公園を経由して荻窪駅まで歩きました。 途中、メンバーの一人Aさんのお宅に寄り、Aさんが世界各地を旅して集めてきた人形や小物などの膨大なコレクションを見せてもらいました。感嘆! 今年3月に始めたこの会、なんといちども雨に降られずでした。快晴のもと快適に歩いて、忘年会ランチを楽しみました。 ※写真の多くは田村和史さん撮影。一部校條諭。 ※この会は、少人数グループで、杉並区など近隣の人が集まって、街探訪を兼ねて歩いています。(経験者限定、指導無し、レンタルポール無し、下見無し) 【いつものように集まるのが嬉しい】 2023/12/11 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング #歩き納め定例会 #Xmasバージョンで 今年も元氣に過ごせました〜 貴方から 私から ありがとう〜 #コグニサイズ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #転倒予防体操 #ラダー
【いつものように集まるのが嬉しい】 2023/12/11 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング #歩き納め定例会 #Xmasバージョンで 今年も元氣に過ごせました〜 貴方から 私から ありがとう〜 #コグニサイズ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #転倒予防体操 #ラダー ポールウォーキング歴1年の倉さん。いつも「歩けるうちにポールに出会えてよかった」と言ってくれます。講師としては感動ものくらいに歩きが進化しています。 他の参加者からも、かっこいい❗️の声が。 これからも一緒に歩きましょう!
ポールウォーキング歴1年の倉さん。いつも「歩けるうちにポールに出会えてよかった」と言ってくれます。講師としては感動ものくらいに歩きが進化しています。 他の参加者からも、かっこいい❗️の声が。 これからも一緒に歩きましょう! 【楽しいよね〜会食は ♬ UR幸町ポールウォーキング歩き納め】 2023/12/12 こうして交わるといいですね〜 1歩も2歩も近くなるんです。 身体を動かして 美味しい物を一緒に頂いて 元氣が出ない訳がないわね〜 (会員さんの声) 2019年から関わってきたUR幸町 来年4月から渡邉東コーチとバトンタッチ 紹介もできて良かったです。
【楽しいよね〜会食は ♬ UR幸町ポールウォーキング歩き納め】 2023/12/12 こうして交わるといいですね〜 1歩も2歩も近くなるんです。 身体を動かして 美味しい物を一緒に頂いて 元氣が出ない訳がないわね〜 (会員さんの声) 2019年から関わってきたUR幸町 来年4月から渡邉東コーチとバトンタッチ 紹介もできて良かったです。 【続編15】第五章〜第二節 「2.歩行チェック方法」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道
【続編15】第五章〜第二節 「2.歩行チェック方法」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道 2023121スマイルチーム ポール部 プチプチ遠征。 ポール部は12/25が年内最後の活動となります。 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #相模原市
2023121スマイルチーム ポール部 プチプチ遠征。 ポール部は12/25が年内最後の活動となります。 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #相模原市 【繰り返しの大事さ】 2023/12/14 数年前から始めた インターバルウォーキング 秋のメニューとして いい感じに定着しました。 \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #インターバル #ソーシャルフィットネス #ミルキングアクション #ローリング
【繰り返しの大事さ】 2023/12/14 数年前から始めた インターバルウォーキング 秋のメニューとして いい感じに定着しました。 \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #インターバル #ソーシャルフィットネス #ミルキングアクション #ローリング ホーチミンシティ郊外新都心ビンズオンにてJICAミッション推進中です。 日本式健康増進法としてのポールウォークと下駄エクササイズを、筋肉貯金検定に続いて提供。現時点での体力、バランス能力を簡易的にチェックした後、効き目のある歩きとしてのローリング歩行に誘導。下駄との親和性の高さに私もびっくりです。今回は就労層の皆さんがたくさん参加してくれました。お疲れ様!
ホーチミンシティ郊外新都心ビンズオンにてJICAミッション推進中です。 日本式健康増進法としてのポールウォークと下駄エクササイズを、筋肉貯金検定に続いて提供。現時点での体力、バランス能力を簡易的にチェックした後、効き目のある歩きとしてのローリング歩行に誘導。下駄との親和性の高さに私もびっくりです。今回は就労層の皆さんがたくさん参加してくれました。お疲れ様! 【土曜日定例会の歩き納め】 2023/12/16 12月も中旬なのに ワ〜オ 気温が20℃! 暑い 暑い 2023年歩き納めに 「追い抜きでインターバル15分」 疲れ過ぎず・軽すぎず 元氣シニアは力の入れどころが 上手いです 💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日定例会 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #海老川ロード #シニアポールウォーキング #インターバルウォーキング
【土曜日定例会の歩き納め】 2023/12/16 12月も中旬なのに ワ〜オ 気温が20℃! 暑い 暑い 2023年歩き納めに 「追い抜きでインターバル15分」 疲れ過ぎず・軽すぎず 元氣シニアは力の入れどころが 上手いです 💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日定例会 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #海老川ロード #シニアポールウォーキング #インターバルウォーキング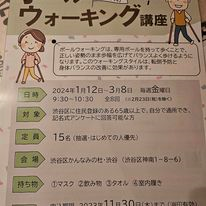 抽選 渋谷区福祉介護保険課の元気すこやか事業 ポールウォーキングクラス4学期の申し込みは先月末で締め切り、定員オーバーで抽選が行われたとのと。 また 落っこちちゃった💧というメールが前々回の受講者さんから舞い込んで来ました。お気の毒。リピーターさんには厳しいようです。懲りずに再々度挑戦してください。
抽選 渋谷区福祉介護保険課の元気すこやか事業 ポールウォーキングクラス4学期の申し込みは先月末で締め切り、定員オーバーで抽選が行われたとのと。 また 落っこちちゃった💧というメールが前々回の受講者さんから舞い込んで来ました。お気の毒。リピーターさんには厳しいようです。懲りずに再々度挑戦してください。 『パーソナルレッスンをしています。』
『パーソナルレッスンをしています。』 今年最後のポールウオーキング。 強風でしたが、晴天に恵まれ気持ちよく歩けました。 その後は、野菜レストランにて忘年会。 お疲れ様でした。 来年は寅さん記念館経由、帝釈天。 お楽しみに。。。。。 良いお年を。
今年最後のポールウオーキング。 強風でしたが、晴天に恵まれ気持ちよく歩けました。 その後は、野菜レストランにて忘年会。 お疲れ様でした。 来年は寅さん記念館経由、帝釈天。 お楽しみに。。。。。 良いお年を。 【2023健走杖接力環島 第十二站竹北站】 – #2023健走杖接力環島 #竹北站圓滿成功 #雙杖在手健康跟著走 目標號召百人參加 達標共120位😆❗️ 社區長輩很多都只是體驗過一次 或是陪家人來參加的 所以沿路都有專業的教練或指導員協助 只為提供給大家健康又完美的健走體驗 陳秀玲-竹北市民代表 陳秀玲 站長跑社區揪民眾的行動力👍👍 感謝大家的熱情參與 我們在台灣的其他縣市再一起 健康前行~ 歡迎大家熱烈報名各縣市的環島活動~ 🌟活動詳情: 📅 日期:2023年10月14日~12月23日 📍 地點:台灣各地區 享受健康、快樂的生活吧! 健康,從腳開始 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 講容-講話有內容 不倒翁學校 健走杖運動
【2023健走杖接力環島 第十二站竹北站】 – #2023健走杖接力環島 #竹北站圓滿成功 #雙杖在手健康跟著走 目標號召百人參加 達標共120位😆❗️ 社區長輩很多都只是體驗過一次 或是陪家人來參加的 所以沿路都有專業的教練或指導員協助 只為提供給大家健康又完美的健走體驗 陳秀玲-竹北市民代表 陳秀玲 站長跑社區揪民眾的行動力👍👍 感謝大家的熱情參與 我們在台灣的其他縣市再一起 健康前行~ 歡迎大家熱烈報名各縣市的環島活動~ 🌟活動詳情: 📅 日期:2023年10月14日~12月23日 📍 地點:台灣各地區 享受健康、快樂的生活吧! 健康,從腳開始 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 講容-講話有內容 不倒翁學校 健走杖運動 御所ケ丘広町緑地里山公園 腰越貯筋クラス 令和5年のストレッチ&筋トレ納めのあとは忘年会へ
御所ケ丘広町緑地里山公園 腰越貯筋クラス 令和5年のストレッチ&筋トレ納めのあとは忘年会へ 【美姿勢ウォーキング 2023年歩き納め】 2023/12/19 トナカイさん サンタさん 沢山集合しました〜 皆でやれば 怖くない〜 気分はウキウキ 少しづつ 派手派手に〜(笑) コグニサイズは 「追い抜きしりとりゲーム」 ワォ〜 頭使えば足止まる(笑) スペシャルメニューは 公園ど真ん中で 自己流ダンスからの 美男美女ラインナップ?? 火曜日歩き納め 元氣笑顔で締めくくりしました〜
【美姿勢ウォーキング 2023年歩き納め】 2023/12/19 トナカイさん サンタさん 沢山集合しました〜 皆でやれば 怖くない〜 気分はウキウキ 少しづつ 派手派手に〜(笑) コグニサイズは 「追い抜きしりとりゲーム」 ワォ〜 頭使えば足止まる(笑) スペシャルメニューは 公園ど真ん中で 自己流ダンスからの 美男美女ラインナップ?? 火曜日歩き納め 元氣笑顔で締めくくりしました〜 今日は、第2回ポールdeウォークin宮城県石巻市へ!冷たい風でしたが、青空の広がるいいお天気でした! 振り返ると、今年は仙台を始め東北各地に呼んでいただき、ポールウォーキングが急速に広がりを見せ始めた、と感じた1年でした。 「もっと多くの人に伝えたい!」と思った8年前。感慨深いなぁ‥😌
今日は、第2回ポールdeウォークin宮城県石巻市へ!冷たい風でしたが、青空の広がるいいお天気でした! 振り返ると、今年は仙台を始め東北各地に呼んでいただき、ポールウォーキングが急速に広がりを見せ始めた、と感じた1年でした。 「もっと多くの人に伝えたい!」と思った8年前。感慨深いなぁ‥😌 【幸せはなに〜?】 船橋ウォーキングソサイエティ 2023年の歩き納めは 2本のポールを使うウォーキング 木曜日コースです。 2023/12/21 ブロッコリーみたいに見える 🌳の下で 色んなお顔で勢ぞろい 各曜日リーダーが 目一杯頑張りました。 連なるスタッフも 力をいっぱい いっぱい出しました。 それにしっかり付いて来てくれた 会員さん こんなに素敵なメンバーと 今年も一年樂しく 歩けました。 これが一番の幸せです。 みんな今年もありがとう〜 来年も宜しくお願いします 船橋市ウォーキングソサイエティ いつもの言葉は 《こころも若く 身体も若く ウォーキングでHAPPY》
【幸せはなに〜?】 船橋ウォーキングソサイエティ 2023年の歩き納めは 2本のポールを使うウォーキング 木曜日コースです。 2023/12/21 ブロッコリーみたいに見える 🌳の下で 色んなお顔で勢ぞろい 各曜日リーダーが 目一杯頑張りました。 連なるスタッフも 力をいっぱい いっぱい出しました。 それにしっかり付いて来てくれた 会員さん こんなに素敵なメンバーと 今年も一年樂しく 歩けました。 これが一番の幸せです。 みんな今年もありがとう〜 来年も宜しくお願いします 船橋市ウォーキングソサイエティ いつもの言葉は 《こころも若く 身体も若く ウォーキングでHAPPY》 本日は、千葉の「きょなん健幸セミナー」水仙ロードウォーキングを担当させていただきました。 早朝、強風で目覚め、少しの不安を感じましたが… やはり。。。😓 乗船予定だった久里浜港⇔金谷港の東京湾フェリーが欠航。 自宅から千葉へ渡る手軽で最短手段なのに… そして本日はペリーの黒船に乗船できる予定だったのに…😭 幸いアクアラインは閉鎖しておらず急遽変更して車に飛び乗り出発しました🚗 アクアラインは強風の為に速度規制があったり横風でハンドルを取られそうになったり… 10:00〜の指導に間に合うかドキドキでしたが何とか無事に到着。 皆さんの笑顔でホッとしました。 しかし、強風でこちらも予定が変更となり、室内でのポールエクササイズと少しの外歩きでポールウォーキングを楽しみました♪ 鋸南町の保健福祉課の保健師さんとは長いお付き合いになります。 SFAの杉浦代表からのご縁で今もing〜です。 いつまでも健康で自分の足で歩けるように。生活習慣病予防のために。 鋸南地区のポールウォーキング企画はこれからまだまだ盛りだくさんです。
本日は、千葉の「きょなん健幸セミナー」水仙ロードウォーキングを担当させていただきました。 早朝、強風で目覚め、少しの不安を感じましたが… やはり。。。😓 乗船予定だった久里浜港⇔金谷港の東京湾フェリーが欠航。 自宅から千葉へ渡る手軽で最短手段なのに… そして本日はペリーの黒船に乗船できる予定だったのに…😭 幸いアクアラインは閉鎖しておらず急遽変更して車に飛び乗り出発しました🚗 アクアラインは強風の為に速度規制があったり横風でハンドルを取られそうになったり… 10:00〜の指導に間に合うかドキドキでしたが何とか無事に到着。 皆さんの笑顔でホッとしました。 しかし、強風でこちらも予定が変更となり、室内でのポールエクササイズと少しの外歩きでポールウォーキングを楽しみました♪ 鋸南町の保健福祉課の保健師さんとは長いお付き合いになります。 SFAの杉浦代表からのご縁で今もing〜です。 いつまでも健康で自分の足で歩けるように。生活習慣病予防のために。 鋸南地区のポールウォーキング企画はこれからまだまだ盛りだくさんです。 『雪が降ってきたよ』
『雪が降ってきたよ』 【続編16】第六章〜第一節 「1.自分ごと」になっていますか?」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道
【続編16】第六章〜第一節 「1.自分ごと」になっていますか?」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道 Merry Christmas✨🎄✨🎅 年内最後から2番目のPW教室。 地域の自治会の一斉落葉掃きと重なり掃除終了の10時になると続々集合。新しいかた2人も迎えてさらに大勢で賑やかになりました。つばき公園(🐗猪出没!)でたっぷりストレッチ+筋トレをして外へ。個人的な質問に順番にお応えしながらグループに分かれストライク公園までポールウォーキング。間欠性跛行のかた、術後リハビリ中のかた、生まれて初めてポールを手にするかた。ラストは大きな1つの輪になってポールゲームで盛り上がり、来年も「楽しくやりましょう」で締めました。 皆さんに喜んで頂けるのがじわっと嬉しいです。 良いクリスマスと新年を~!
Merry Christmas✨🎄✨🎅 年内最後から2番目のPW教室。 地域の自治会の一斉落葉掃きと重なり掃除終了の10時になると続々集合。新しいかた2人も迎えてさらに大勢で賑やかになりました。つばき公園(🐗猪出没!)でたっぷりストレッチ+筋トレをして外へ。個人的な質問に順番にお応えしながらグループに分かれストライク公園までポールウォーキング。間欠性跛行のかた、術後リハビリ中のかた、生まれて初めてポールを手にするかた。ラストは大きな1つの輪になってポールゲームで盛り上がり、来年も「楽しくやりましょう」で締めました。 皆さんに喜んで頂けるのがじわっと嬉しいです。 良いクリスマスと新年を~!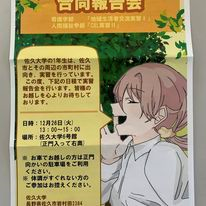 佐久ポールウォーキング協会より 佐久大学看護学部1年生のポールウォーキング実習の報告会に出席して来ました。 ポールウォーキングで 歩く事により得る〜健康利益〜❗️ ・メタボ予防・・ ・骨太・・ ・リラックス・・ ・免疫力・・他 「健康利益」 学生から新しいワードが出て来ました❗️ 来年度も実習は続く様です‼️
佐久ポールウォーキング協会より 佐久大学看護学部1年生のポールウォーキング実習の報告会に出席して来ました。 ポールウォーキングで 歩く事により得る〜健康利益〜❗️ ・メタボ予防・・ ・骨太・・ ・リラックス・・ ・免疫力・・他 「健康利益」 学生から新しいワードが出て来ました❗️ 来年度も実習は続く様です‼️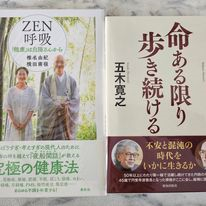 今日は北鎌倉 若いサクマネ(サークルマネージャー)さんは二人ともコロナで欠席😞私は罹患せず今年も最後まで無事 教室やイベントを終えることができたので帰りにお礼と報告を兼ねて円覚寺へ
今日は北鎌倉 若いサクマネ(サークルマネージャー)さんは二人ともコロナで欠席😞私は罹患せず今年も最後まで無事 教室やイベントを終えることができたので帰りにお礼と報告を兼ねて円覚寺へ 【冬休み児童クラブ巡回指導】 石川県レクリエーション協会からの仕事に 児童クラブ巡回指導の仕事があります。 冬休み1日目に90名の子供たちとレクリエーションを楽しみました。 走り回ったり、仲間と協力しあったり、新聞紙で発散したりと90分間めいいっぱい からだを動かしました。 これから始まる冬休み。楽しんでくださいね。 #石川県レクリエーション協会 #レクリエーション #レクリエーションインストラクター #金沢市 #児童クラブ #小学生 #みんなちがってみんないい
【冬休み児童クラブ巡回指導】 石川県レクリエーション協会からの仕事に 児童クラブ巡回指導の仕事があります。 冬休み1日目に90名の子供たちとレクリエーションを楽しみました。 走り回ったり、仲間と協力しあったり、新聞紙で発散したりと90分間めいいっぱい からだを動かしました。 これから始まる冬休み。楽しんでくださいね。 #石川県レクリエーション協会 #レクリエーション #レクリエーションインストラクター #金沢市 #児童クラブ #小学生 #みんなちがってみんないい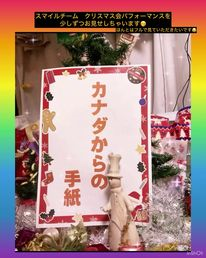 12月21日 スマイルチームクリスマス会🎄のパフォーマンスを少しづつお見せしちゃう動画です🤭
12月21日 スマイルチームクリスマス会🎄のパフォーマンスを少しづつお見せしちゃう動画です🤭 【2023健走杖接力環島 第十四站閉幕雙北站】
【2023健走杖接力環島 第十四站閉幕雙北站】 台湾の東急ハンズ2店舗にこの什器が設置されたみたいです。台湾の販売代理店頑張ってくれています。まさか自分の写真が使われようとは・・・(^.^) 新しいバスケのユニフォームが自分に届きました。昨日は早速それを着て練習。結構いいですね(^.^)気温はマイナスだけど走っていると半袖短パンでいけるものです!!
台湾の東急ハンズ2店舗にこの什器が設置されたみたいです。台湾の販売代理店頑張ってくれています。まさか自分の写真が使われようとは・・・(^.^) 新しいバスケのユニフォームが自分に届きました。昨日は早速それを着て練習。結構いいですね(^.^)気温はマイナスだけど走っていると半袖短パンでいけるものです!! シナノの工場紹介!🏭(組み立てライン編)組み立てラインの様子を動画にしてみました。いつも工場へ行くと、整然とポールや杖が並んでいるのをみて綺麗だなぁと感動します。地域の学生向けに工場見学を行なっていますが、来ていただいた中高生の皆さんも同じように思ってくれていたらいいなぁと思います。シナノ営業部なかむら #シナノ #sinano #sinanojapan
シナノの工場紹介!🏭(組み立てライン編)組み立てラインの様子を動画にしてみました。いつも工場へ行くと、整然とポールや杖が並んでいるのをみて綺麗だなぁと感動します。地域の学生向けに工場見学を行なっていますが、来ていただいた中高生の皆さんも同じように思ってくれていたらいいなぁと思います。シナノ営業部なかむら #シナノ #sinano #sinanojapan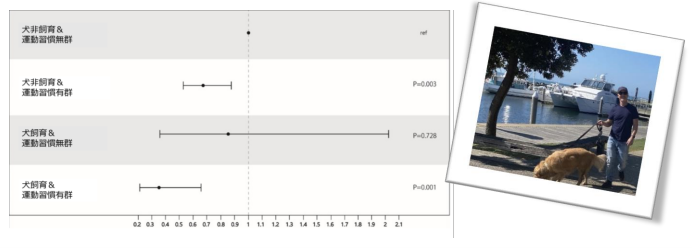 犬の飼育及び運動習慣の有無別にみた認知症発症オッズ比。
犬の飼育及び運動習慣の有無別にみた認知症発症オッズ比。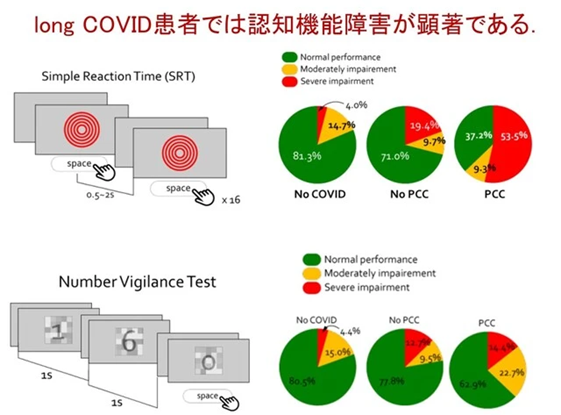
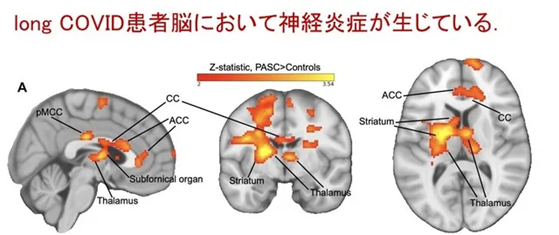
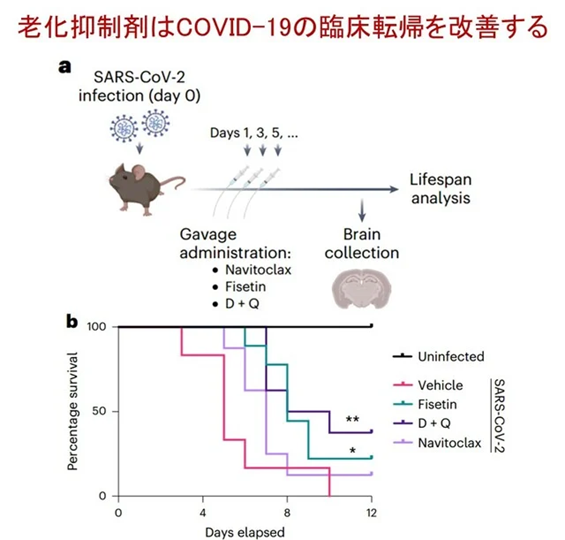
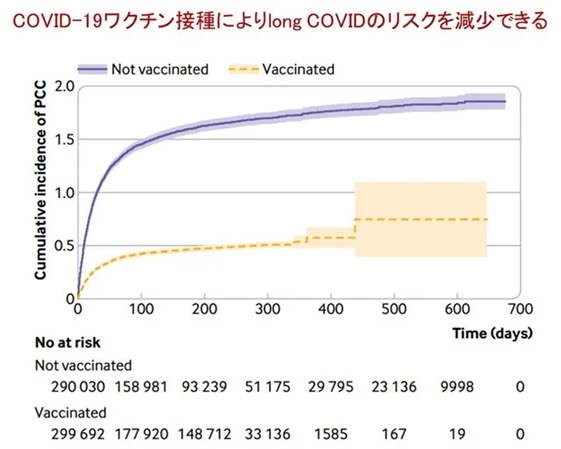
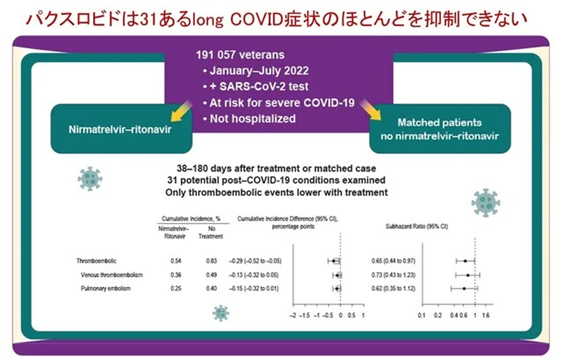
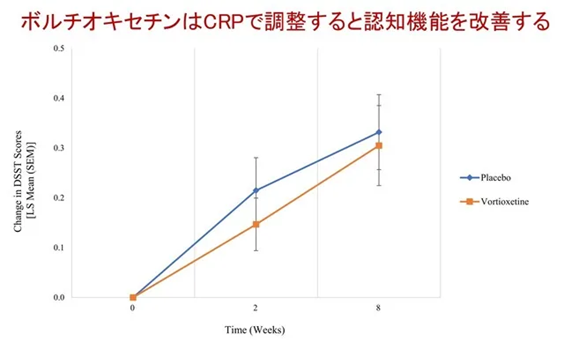
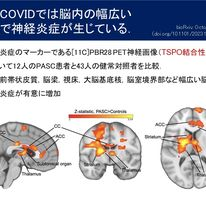 COVID-19から脳を守る必要がある@日本認知症学会,札幌市医師会講演会 「COVID-19後遺症としての認知機能障害―病態機序と治療の展望―」という講演をさせていただきました.認知症の新しい危険因子であるCOVID-19について,最新情報にアップデートしご紹介しました.Long COVIDの病態機序はだいぶ明らかになりつつあり,COVID-19は急性期の呼吸器疾患から慢性期の神経疾患としての人体への影響が危惧され始めています.つまりCOVID-19から脳を守ることを啓発する必要があります.札幌市医師会の先生方から非常にたくさんのコメントを頂き,スライドのご希望がありました.こちらからダウンロードいただけます. https://tinyurl.com/yukpgoht 以下,講演要旨です. ◆入院患者の認知機能障害を予測する2 つの血液バイオマーカーとしてフィブリノゲンとD-ダイマーが同定された. ◆Long COVIDのなりやすさを規定する臨床的・遺伝学的・免疫学的要因が判明した. ◆Long COVIDは2年間の追跡でも回復しにくい. ◆COVID-19はアルツハイマー病のリスクを2倍程度上昇させる. ◆認知症を来しやすい要因として,高齢者,重症感染,3ヶ月以上の嗅覚障害が報告されている. ◆軽症感染でも(気が付かないだけで)高次脳機能に影響が生じている可能性がある ◆オミクロン株は嗅覚障害は生じにくいものの,神経侵襲性は武漢株を含めた他の変異株と変わっていない. ◆ヒトLong COVIDで脳内の幅広い領域で神経炎症が生じている. ◆認知症を含む神経後遺症の機序として,ウイルスの持続感染が重要視されている. ◆ほぼ全身の臓器にウイルススパイク蛋白が存在しうる. ◆Long COVIDの異なる病態を結びつけるメカニズムとしてセロトニン欠乏が同定された. ◆持続感染が認知機能障害を引き起こす機序についても解明されつつある. ◆持続感染による脳への障害を考慮すると,ワクチン接種によってCOVID-19を予防することが大切である. ◆治療戦略として,抗ウイルス薬の長期間投与や,ミトコンドリア機能の回復が有効であるかが注目されている.
COVID-19から脳を守る必要がある@日本認知症学会,札幌市医師会講演会 「COVID-19後遺症としての認知機能障害―病態機序と治療の展望―」という講演をさせていただきました.認知症の新しい危険因子であるCOVID-19について,最新情報にアップデートしご紹介しました.Long COVIDの病態機序はだいぶ明らかになりつつあり,COVID-19は急性期の呼吸器疾患から慢性期の神経疾患としての人体への影響が危惧され始めています.つまりCOVID-19から脳を守ることを啓発する必要があります.札幌市医師会の先生方から非常にたくさんのコメントを頂き,スライドのご希望がありました.こちらからダウンロードいただけます. https://tinyurl.com/yukpgoht 以下,講演要旨です. ◆入院患者の認知機能障害を予測する2 つの血液バイオマーカーとしてフィブリノゲンとD-ダイマーが同定された. ◆Long COVIDのなりやすさを規定する臨床的・遺伝学的・免疫学的要因が判明した. ◆Long COVIDは2年間の追跡でも回復しにくい. ◆COVID-19はアルツハイマー病のリスクを2倍程度上昇させる. ◆認知症を来しやすい要因として,高齢者,重症感染,3ヶ月以上の嗅覚障害が報告されている. ◆軽症感染でも(気が付かないだけで)高次脳機能に影響が生じている可能性がある ◆オミクロン株は嗅覚障害は生じにくいものの,神経侵襲性は武漢株を含めた他の変異株と変わっていない. ◆ヒトLong COVIDで脳内の幅広い領域で神経炎症が生じている. ◆認知症を含む神経後遺症の機序として,ウイルスの持続感染が重要視されている. ◆ほぼ全身の臓器にウイルススパイク蛋白が存在しうる. ◆Long COVIDの異なる病態を結びつけるメカニズムとしてセロトニン欠乏が同定された. ◆持続感染が認知機能障害を引き起こす機序についても解明されつつある. ◆持続感染による脳への障害を考慮すると,ワクチン接種によってCOVID-19を予防することが大切である. ◆治療戦略として,抗ウイルス薬の長期間投与や,ミトコンドリア機能の回復が有効であるかが注目されている. ワクチン接種のススメ@第10回日経・FT感染症会議 今日の日経新聞の1面広告です.第10回日経・FT感染症会議(https://cdc.nikkei.com/)での講演内容を,モデルナがまとめてくださいました.内容は今年1年述べてきたことで,「新型コロナは新しい認知症の危険因子」「できるだけ感染を避け,唯一,long COVIDを抑制することが証明されているワクチン接種を定期的に行いましょう」というものになります. もともとアルツハイマー病などの病理変化が脳に生じているところに,新型コロナによる脳の炎症が生じると,病理変化が一気に促進されうるということです.新型コロナに限らず,インフルエンザなどのウイルス感染症は,アルツハイマー病やALSなど神経変性疾患の発症の引き金となることも今年明らかになりました(http://tinyurl.com/yokxcbom).インフルエンザワクチン接種のアルツハイマー病予防効果も示されています.認知症や神経変性疾患予防にワクチン接種をオススメします.
ワクチン接種のススメ@第10回日経・FT感染症会議 今日の日経新聞の1面広告です.第10回日経・FT感染症会議(https://cdc.nikkei.com/)での講演内容を,モデルナがまとめてくださいました.内容は今年1年述べてきたことで,「新型コロナは新しい認知症の危険因子」「できるだけ感染を避け,唯一,long COVIDを抑制することが証明されているワクチン接種を定期的に行いましょう」というものになります. もともとアルツハイマー病などの病理変化が脳に生じているところに,新型コロナによる脳の炎症が生じると,病理変化が一気に促進されうるということです.新型コロナに限らず,インフルエンザなどのウイルス感染症は,アルツハイマー病やALSなど神経変性疾患の発症の引き金となることも今年明らかになりました(http://tinyurl.com/yokxcbom).インフルエンザワクチン接種のアルツハイマー病予防効果も示されています.認知症や神経変性疾患予防にワクチン接種をオススメします.