今年もホットな情報をお届けします。
今月は、NPWA会員の活動報告、「急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する」と「グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する」の論文紹介、岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報に加え、特別企画として、CES2026での「ヘルスケア分野」「PW関連」の発表をAIに訊く、をお届けします。
1. 2026年1月の活動状況
・柳澤 光宏さんの投稿
 明けましておめでとうございます!初日の出は曇っていてダメだったので、テレビで見たゴールデン富士(笑) 仕事は昨年からの取組みを引き続き行う一年になりますが、工場の一部建て替えが控えているので、この1、2年の設備投資額は社長になってから過去1になるかと。 身体のメンテやトレーニングは引続きしっかり行い健康第一。ゴルフやスキーなどの趣味は継続で! なんといっても次女の高校受験が控えているので、本人が納得できる結果がでるといいなと。 写真の記事は元旦に発行された地元の週刊さくだいらに掲載されたものです。 本年も挑戦をモットーに走るので、宜しくお願い致します‼️
明けましておめでとうございます!初日の出は曇っていてダメだったので、テレビで見たゴールデン富士(笑) 仕事は昨年からの取組みを引き続き行う一年になりますが、工場の一部建て替えが控えているので、この1、2年の設備投資額は社長になってから過去1になるかと。 身体のメンテやトレーニングは引続きしっかり行い健康第一。ゴルフやスキーなどの趣味は継続で! なんといっても次女の高校受験が控えているので、本人が納得できる結果がでるといいなと。 写真の記事は元旦に発行された地元の週刊さくだいらに掲載されたものです。 本年も挑戦をモットーに走るので、宜しくお願い致します‼️
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 明けまして おめでとうございます 2026年1月5日 #船橋ウォーキングソサイエティ 歩き初めは #シニアポールウォーキング からです。 #寒い時期は基礎体力をつけよう 唄を歌いながら 筋トレとポールウォーキング いい汗をかきました〜〜
明けまして おめでとうございます 2026年1月5日 #船橋ウォーキングソサイエティ 歩き初めは #シニアポールウォーキング からです。 #寒い時期は基礎体力をつけよう 唄を歌いながら 筋トレとポールウォーキング いい汗をかきました〜〜
・田村 芙美子さんの投稿
 えっ!雪!?❄❄❄? これは4年前の今日の写真。遠方からの友人と雪のなか七福神巡りをした時。 今年の1/6は仕事始め。行政センターの中庭で初春チェアエクササイズをしていたら 島根で地震の速報。震度5ってかなり大きいですね。おトキちゃんのお里は大丈夫だったかしら。 11時スギの送迎バスで今日のお昼は皆さんと新年会(その1)に行きました。笑顔でお喋りのランチでお腹が膨れました。今年も元気で楽しく健康づくりしましょうか。
えっ!雪!?❄❄❄? これは4年前の今日の写真。遠方からの友人と雪のなか七福神巡りをした時。 今年の1/6は仕事始め。行政センターの中庭で初春チェアエクササイズをしていたら 島根で地震の速報。震度5ってかなり大きいですね。おトキちゃんのお里は大丈夫だったかしら。 11時スギの送迎バスで今日のお昼は皆さんと新年会(その1)に行きました。笑顔でお喋りのランチでお腹が膨れました。今年も元気で楽しく健康づくりしましょうか。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【心を合わせて ジャンケンポン】 2026/1/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜美姿勢ウォーキング 新年の挨拶からスタートして ちょっとハードな #サーキットトレーニング 本日の締めは 豪華景品付(?) 恒例のジャンケンゲームです 勝ち抜いたチーム 今年は幸先宜しいようで 他のTeamsも 今年もうま〜く回りますようにね
【心を合わせて ジャンケンポン】 2026/1/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜美姿勢ウォーキング 新年の挨拶からスタートして ちょっとハードな #サーキットトレーニング 本日の締めは 豪華景品付(?) 恒例のジャンケンゲームです 勝ち抜いたチーム 今年は幸先宜しいようで 他のTeamsも 今年もうま〜く回りますようにね
・遠藤 恵子さんの投稿
 日常の生活が戻って4日目!! 午前は外部指導【介護予防運動】 午後はサロンで【加圧トレーニング】 そして今夜は外部指導【やさしい健康運動教室】 動いて、支えて、また動く一日! さっ、介護予防運動を終えたので これからサロンワーク!! 加圧トレーニングセッションです💪✨ #加圧トレーニング #加圧 #ゲンキクリエイターケイコ #フィットネスインストラクター #エアロビクスインストラクター #フィットネストレーナー #介護予防運動指導者 #フットセラピスト #プロボディデザイナー #フェイスデザイナー #ボニャックインストラクター #セラピスト #35周年 #運動指導
日常の生活が戻って4日目!! 午前は外部指導【介護予防運動】 午後はサロンで【加圧トレーニング】 そして今夜は外部指導【やさしい健康運動教室】 動いて、支えて、また動く一日! さっ、介護予防運動を終えたので これからサロンワーク!! 加圧トレーニングセッションです💪✨ #加圧トレーニング #加圧 #ゲンキクリエイターケイコ #フィットネスインストラクター #エアロビクスインストラクター #フィットネストレーナー #介護予防運動指導者 #フットセラピスト #プロボディデザイナー #フェイスデザイナー #ボニャックインストラクター #セラピスト #35周年 #運動指導
・スマイルチームさんの投稿
 2026年初ポールウォーキング。 今年も楽しく元気に冒険へ出かけよう❣️ #健康普及活動 #ポールウォーキング #607080代メインサークル #相模原市
2026年初ポールウォーキング。 今年も楽しく元気に冒険へ出かけよう❣️ #健康普及活動 #ポールウォーキング #607080代メインサークル #相模原市
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【大きなコースを使って サーキットトレーニング】 2026/1/8 #船橋ウォーキングソサイエティ #木曜行田公園 #2本のポールを使うウォーキング 正月も明けて 療養から会員が帰って来ました 青い空と皆がお出迎えです 筋トレの唄に合わせて 慌てず力まずのびのびと 脂肪燃焼を期待しての サーキットトレーニングの実践 その後のじゃんけんゲーム チャンピオンチームには 復帰会員が入り 新年と3重の喜びです
【大きなコースを使って サーキットトレーニング】 2026/1/8 #船橋ウォーキングソサイエティ #木曜行田公園 #2本のポールを使うウォーキング 正月も明けて 療養から会員が帰って来ました 青い空と皆がお出迎えです 筋トレの唄に合わせて 慌てず力まずのびのびと 脂肪燃焼を期待しての サーキットトレーニングの実践 その後のじゃんけんゲーム チャンピオンチームには 復帰会員が入り 新年と3重の喜びです
・長谷川 弘道さんの投稿
 オンライン健康講座「いつでも、どこでも、誰でも楽しめる!ファミリーフィットネス!!」
オンライン健康講座「いつでも、どこでも、誰でも楽しめる!ファミリーフィットネス!!」
・校條 諭さんの投稿
 新春の「気まポ(気ままにポール歩き)」は快晴のもと初詣を兼ねて 本当にきれいな青空でした。行きの電車からは、遠くに富士山が見えました。(写真撮れず) JR・京王井の頭線吉祥寺駅(武蔵野市)に集合して、善福寺公園と井草八幡宮を主たる目的地としてノルディックウォーキングしました。 冬の善福寺公園もなかなかよい風情でした。ゴイサギが木の枝に何羽も止まっていたり、池の水面では、たくさんのカモが休んでいました。 公園では「おやつタイム」をとって、お菓子を交換し合ったりして、たのしいおしゃべり休憩でした。 井草八幡宮は、松の内も過ぎているので混んでませんでした。おみくじを買った人もいました。 以前、NPOとしてやっていた「杉ポ(杉並ポール歩きの会)」は、広く参加者を募集して、ポール歩き(ノルディックウォーキング・ポールウォーキング)の普及促進を目的としていました。多いときには40人くらい参加がありました。 それに対して気まポは、杉並区や近辺の杉ポ経験者の個人的なお楽しみ会です。したがって、指導無し、下見無し、参加費無しです。また、杉ポはあくまでもポールを持ったウォーキング本位でしたが、気まポは文字通り気ままに街探訪を楽しみながら歩いています。ほぼ決まった顔ぶれで、メンバーの拡大も目指しません。 ※写真の半分は田村和史君からいただきました。
新春の「気まポ(気ままにポール歩き)」は快晴のもと初詣を兼ねて 本当にきれいな青空でした。行きの電車からは、遠くに富士山が見えました。(写真撮れず) JR・京王井の頭線吉祥寺駅(武蔵野市)に集合して、善福寺公園と井草八幡宮を主たる目的地としてノルディックウォーキングしました。 冬の善福寺公園もなかなかよい風情でした。ゴイサギが木の枝に何羽も止まっていたり、池の水面では、たくさんのカモが休んでいました。 公園では「おやつタイム」をとって、お菓子を交換し合ったりして、たのしいおしゃべり休憩でした。 井草八幡宮は、松の内も過ぎているので混んでませんでした。おみくじを買った人もいました。 以前、NPOとしてやっていた「杉ポ(杉並ポール歩きの会)」は、広く参加者を募集して、ポール歩き(ノルディックウォーキング・ポールウォーキング)の普及促進を目的としていました。多いときには40人くらい参加がありました。 それに対して気まポは、杉並区や近辺の杉ポ経験者の個人的なお楽しみ会です。したがって、指導無し、下見無し、参加費無しです。また、杉ポはあくまでもポールを持ったウォーキング本位でしたが、気まポは文字通り気ままに街探訪を楽しみながら歩いています。ほぼ決まった顔ぶれで、メンバーの拡大も目指しません。 ※写真の半分は田村和史君からいただきました。
・田村 芙美子さんの投稿
 銭洗弁財天の近く、佐助ギャラリーで開催中の友人の色鉛筆2人展🖼️に行きました。女子3人組の路地歩き「静」🚶🚶♂️🚶♀️のメンバーの一人です。色鉛筆で写真かとみまがう精細な描写! 私には出来ない技です。力作の数々鑑賞のあとはお向かいの佐助カフェでもう一人の仲間とお喋り。「静」のグループ名由来は・・・ 10才と20才の歳の差の3人で 気持ちが若返るエキスを貰えます。東日本大震災をきっかけに知り合った繋がりは老婆の宝物です。
銭洗弁財天の近く、佐助ギャラリーで開催中の友人の色鉛筆2人展🖼️に行きました。女子3人組の路地歩き「静」🚶🚶♂️🚶♀️のメンバーの一人です。色鉛筆で写真かとみまがう精細な描写! 私には出来ない技です。力作の数々鑑賞のあとはお向かいの佐助カフェでもう一人の仲間とお喋り。「静」のグループ名由来は・・・ 10才と20才の歳の差の3人で 気持ちが若返るエキスを貰えます。東日本大震災をきっかけに知り合った繋がりは老婆の宝物です。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【恒例 船橋大神宮初詣】 2026/1/10 正月の賑わいを残す 船橋大神宮へ向い初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #2本のポールをつかうウォーキング 今年は街歩き案内でデビューした 会員が常盤神社と燈明台の説明を してくれました。歴史のみならず 建物の魅力にも聴き入りました。 帰路 西福寺へも寄り 古き良き船橋の魅力にふれた 初歩きとなりました。
【恒例 船橋大神宮初詣】 2026/1/10 正月の賑わいを残す 船橋大神宮へ向い初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #2本のポールをつかうウォーキング 今年は街歩き案内でデビューした 会員が常盤神社と燈明台の説明を してくれました。歴史のみならず 建物の魅力にも聴き入りました。 帰路 西福寺へも寄り 古き良き船橋の魅力にふれた 初歩きとなりました。
・新地 昌子さんの投稿
 ウォーキングポールを相棒に仲間と巡る小さな旅 名づけて"ぽる旅"なんてどうでしょう。 子供の頃から大通りより裏の路地、新しい施設より古い建物を見るのが好きでした。あっ!と思ったら立ち止まってゆっくり風景を楽しめるポールウォーキングは、そんな私にとってまさに旅の相棒です。 今年は自分が行ってみたい!見てみたい!と思う茨城の景色をポールウォーキングの仲間と歩いてみようと思います。 だから、題して「ぽる旅」😊 第一弾は「🦊笠間稲荷神社に健康祈願!」 コース概要/約4.1キロ/歩行時間80分 笠間芸術の森公園北駐車場→ 洋画家山下りんゆかりの白凛居→ 笹目惣兵衛商店→ 笠間稲荷神社→ 笠間歴史交流館井筒屋→ 笠間芸術の森公園北駐車場 今日のお土産 二つ木 胡桃入り稲荷寿司 適度にアップダウンがあり、城下町笠間を感じられました。私にとっては懐かしい通学路も入れた地元を知る人ならではのルートです。ポールウォーカーの皆様、笠間に来られたときはぜひ歩いてみてください😊
ウォーキングポールを相棒に仲間と巡る小さな旅 名づけて"ぽる旅"なんてどうでしょう。 子供の頃から大通りより裏の路地、新しい施設より古い建物を見るのが好きでした。あっ!と思ったら立ち止まってゆっくり風景を楽しめるポールウォーキングは、そんな私にとってまさに旅の相棒です。 今年は自分が行ってみたい!見てみたい!と思う茨城の景色をポールウォーキングの仲間と歩いてみようと思います。 だから、題して「ぽる旅」😊 第一弾は「🦊笠間稲荷神社に健康祈願!」 コース概要/約4.1キロ/歩行時間80分 笠間芸術の森公園北駐車場→ 洋画家山下りんゆかりの白凛居→ 笹目惣兵衛商店→ 笠間稲荷神社→ 笠間歴史交流館井筒屋→ 笠間芸術の森公園北駐車場 今日のお土産 二つ木 胡桃入り稲荷寿司 適度にアップダウンがあり、城下町笠間を感じられました。私にとっては懐かしい通学路も入れた地元を知る人ならではのルートです。ポールウォーカーの皆様、笠間に来られたときはぜひ歩いてみてください😊
・大内 克泰さんの投稿
 居酒屋からの帰り道。 街一番のスナックの集まるビルの近くに多くの人だかり。 「大内コーチ!」 10年前と同じ様に声を掛けてくれて、集まってくる「20歳の集い」を終えた見覚えのある元子ども達😆 「伊達市すこやか事業」と称して、放射能物質の除染が進められる中、外遊びを自粛せざろうえなかった期間を体力作りと肥満予防の為、約6年にわたり市内小学校全校全学年の体育授業を外部講師として委託を受け、巡回していた頃の子ども達。 1校あたり年6回で、大規模校は1学年1回だったにもかかわらず、皆んなが覚えてくれていたのが、見た目のインパクトだけではなく、実施したアクティビティが「楽しかった」と。 数人の新成人達と「飲もう」となり、移動した先にも「教え子」達が。スマホに保存していた約10年前の写真を観ながら当時の思い出話と、今これからの夢や目標を深夜まで語ってくれました。
居酒屋からの帰り道。 街一番のスナックの集まるビルの近くに多くの人だかり。 「大内コーチ!」 10年前と同じ様に声を掛けてくれて、集まってくる「20歳の集い」を終えた見覚えのある元子ども達😆 「伊達市すこやか事業」と称して、放射能物質の除染が進められる中、外遊びを自粛せざろうえなかった期間を体力作りと肥満予防の為、約6年にわたり市内小学校全校全学年の体育授業を外部講師として委託を受け、巡回していた頃の子ども達。 1校あたり年6回で、大規模校は1学年1回だったにもかかわらず、皆んなが覚えてくれていたのが、見た目のインパクトだけではなく、実施したアクティビティが「楽しかった」と。 数人の新成人達と「飲もう」となり、移動した先にも「教え子」達が。スマホに保存していた約10年前の写真を観ながら当時の思い出話と、今これからの夢や目標を深夜まで語ってくれました。
・田村 芙美子さんの投稿
 山手線停電でストップ🚃大混乱の1日 湘南ラインで渋谷に向かっていた途中、横浜~武蔵小杉手前でアナウンス。恵比寿、渋谷、新宿など山手線駅に向かうかたは東急線に乗り換えるなど検討下さい📢 えっ、スムーズに動かないの?・・・? 良く理解できないまま 武蔵小杉で降りて東急線和光行きに乗り換えました。大の苦手の武蔵小杉乗り換えでしたが20分オーバーで渋谷駅にたどり着きました。下車したものの渋谷駅で右往左往💦万が一のために1時間近く早めに出ているので遅刻の心配はありません。 夕方のニュースによると30分位電車が停まってしまったり、線路を歩いたり、大混乱だったようです。 再開したのは午後1時過ぎとのこと。ポールウォーキング教室は区民の方ばかりなので私以外は影響なし。ナンバ歩きの数名(3/15)の皆さんとの格闘で大汗流しました。 写真は@妙本寺
山手線停電でストップ🚃大混乱の1日 湘南ラインで渋谷に向かっていた途中、横浜~武蔵小杉手前でアナウンス。恵比寿、渋谷、新宿など山手線駅に向かうかたは東急線に乗り換えるなど検討下さい📢 えっ、スムーズに動かないの?・・・? 良く理解できないまま 武蔵小杉で降りて東急線和光行きに乗り換えました。大の苦手の武蔵小杉乗り換えでしたが20分オーバーで渋谷駅にたどり着きました。下車したものの渋谷駅で右往左往💦万が一のために1時間近く早めに出ているので遅刻の心配はありません。 夕方のニュースによると30分位電車が停まってしまったり、線路を歩いたり、大混乱だったようです。 再開したのは午後1時過ぎとのこと。ポールウォーキング教室は区民の方ばかりなので私以外は影響なし。ナンバ歩きの数名(3/15)の皆さんとの格闘で大汗流しました。 写真は@妙本寺
・森川 まことさんの投稿
 本日は成田山新勝寺をお参りし、成田山公園を歩きました。途中、水琴窟で聴力テスト(笑笑)を行い、解散。今年も皆んなで元気に歩けます様に。。。。。
本日は成田山新勝寺をお参りし、成田山公園を歩きました。途中、水琴窟で聴力テスト(笑笑)を行い、解散。今年も皆んなで元気に歩けます様に。。。。。
・長谷川 弘道さんの投稿
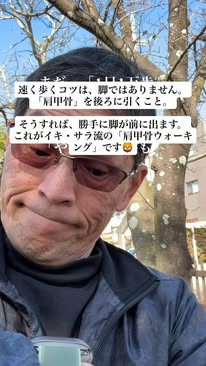 「今日はまだ5,000歩しか歩いてない…」 と落ち込んでいませんか? 長谷川弘道です。 その罪悪感、今日でサラリと捨てましょう🦁 実は「1日1万歩」という数字には、 明確な医学的根拠はないと言われています。 レポートでも紹介していますが、 2019年の米国の研究データでは、 高齢女性において「1日4,400歩」で死亡率が低下し、 「7,500歩」を超えると効果は横ばいになることが分かっています。 つまり、無理して1万歩を目指す必要はないのです。 むしろ、疲れているのにダラダラ歩くのは、 関節を痛めるだけで逆効果になりかねません。 私が40年の指導で大切にしているのは、 「量」よりも「質」です。 ✅ 歩幅をあと5cm広くしてみる ✅ 信号が点滅する前に渡り切れる速度(秒速1m)で歩く これを意識するだけで、脳への刺激も運動効果も段違いです。 「たくさん」ではなく「颯爽(さっそう)」と。 それが、粋な大人の歩き方です。 皆さんは普段、何歩くらい歩いていますか? 「歩きすぎだったかも!」という方はコメントで教えてください👇 ────────────── 長谷川弘道|イキ・サラ健幸ライフ @hasegawa_iki_sara 運動指導歴40年。 頑張らない「ライオン流」健康法を発信中。 ────────────── #ウォーキング #1日1万歩 #健康法 #長谷川弘道 #イキサラ 50代からの健康 シニアフィットネス 散歩 ウォーキングダイエット 肩甲骨 SKA運動
「今日はまだ5,000歩しか歩いてない…」 と落ち込んでいませんか? 長谷川弘道です。 その罪悪感、今日でサラリと捨てましょう🦁 実は「1日1万歩」という数字には、 明確な医学的根拠はないと言われています。 レポートでも紹介していますが、 2019年の米国の研究データでは、 高齢女性において「1日4,400歩」で死亡率が低下し、 「7,500歩」を超えると効果は横ばいになることが分かっています。 つまり、無理して1万歩を目指す必要はないのです。 むしろ、疲れているのにダラダラ歩くのは、 関節を痛めるだけで逆効果になりかねません。 私が40年の指導で大切にしているのは、 「量」よりも「質」です。 ✅ 歩幅をあと5cm広くしてみる ✅ 信号が点滅する前に渡り切れる速度(秒速1m)で歩く これを意識するだけで、脳への刺激も運動効果も段違いです。 「たくさん」ではなく「颯爽(さっそう)」と。 それが、粋な大人の歩き方です。 皆さんは普段、何歩くらい歩いていますか? 「歩きすぎだったかも!」という方はコメントで教えてください👇 ────────────── 長谷川弘道|イキ・サラ健幸ライフ @hasegawa_iki_sara 運動指導歴40年。 頑張らない「ライオン流」健康法を発信中。 ────────────── #ウォーキング #1日1万歩 #健康法 #長谷川弘道 #イキサラ 50代からの健康 シニアフィットネス 散歩 ウォーキングダイエット 肩甲骨 SKA運動
・中村 理さんの投稿
 佐久ポールウォーキング協会より 「室内ポールウォーク」でした。 冬季間のポールウォーキングは体育館での室内歩きに〜 外は雪や凍結路の環境下の時が有り、寒さ・転倒の危険性を回避してのPW〜 2時間の中で前半/PWを〜 歩くだけでなく「スクエアステップ」を取り入れての足踏みも取り入れ〜 後半は「レクリエーション/ボッチャ・ラダーゲッター・布ボール」で脳トレも取り入れ内容でした。
佐久ポールウォーキング協会より 「室内ポールウォーク」でした。 冬季間のポールウォーキングは体育館での室内歩きに〜 外は雪や凍結路の環境下の時が有り、寒さ・転倒の危険性を回避してのPW〜 2時間の中で前半/PWを〜 歩くだけでなく「スクエアステップ」を取り入れての足踏みも取り入れ〜 後半は「レクリエーション/ボッチャ・ラダーゲッター・布ボール」で脳トレも取り入れ内容でした。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【うまれる一体感】 2026/1/20 程よく仲間が見渡せる 藤棚は強風の影響もなく ベンチ、椅子 柱が サーキットトレーニングに ピッタリです 「梅の花が咲いてるよ〜」 寒波でも春を感じます #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #サーキットトレーニング
【うまれる一体感】 2026/1/20 程よく仲間が見渡せる 藤棚は強風の影響もなく ベンチ、椅子 柱が サーキットトレーニングに ピッタリです 「梅の花が咲いてるよ〜」 寒波でも春を感じます #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #サーキットトレーニング
・田村 芙美子さんの投稿
 今日はPWグループ3個目の新年会でした。パークホテルにバスで送迎は楽です。(要介護の方が3人在籍なので) 往復の湘南海岸路はお日様キラキラ、富士山も真っ白に雪化粧。一番寒いこの時期を越せば嬉しい花の季節が待っています。 右は鎌倉市腰越のマサキの実です。弾けてますね。 夕焼けも綺麗な1日でした。 12年後📆⏳👣
今日はPWグループ3個目の新年会でした。パークホテルにバスで送迎は楽です。(要介護の方が3人在籍なので) 往復の湘南海岸路はお日様キラキラ、富士山も真っ白に雪化粧。一番寒いこの時期を越せば嬉しい花の季節が待っています。 右は鎌倉市腰越のマサキの実です。弾けてますね。 夕焼けも綺麗な1日でした。 12年後📆⏳👣
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【寒波襲来】 2026/1/22 行田公園広場枯草に小さな白い 物体があたり一面に点々と… 「何〜 これ?」 「ひょうよ!!」 「ヒェ〜!寒い訳よ!」 手強い寒気団にも2本のポールを 持って歩けば立ち向かう元気 が出てきます! ステップエクササイズ どんぐりコロコロの唄に 合わせて慌てずにね〜 身体も温まるのが早いよね♥ 歩くだけではない 【ストレッチ・筋トレ】 しっかり時間をかけてる効果が 厳しい環境の中で現れますね〜 ポールって凄いね〜
【寒波襲来】 2026/1/22 行田公園広場枯草に小さな白い 物体があたり一面に点々と… 「何〜 これ?」 「ひょうよ!!」 「ヒェ〜!寒い訳よ!」 手強い寒気団にも2本のポールを 持って歩けば立ち向かう元気 が出てきます! ステップエクササイズ どんぐりコロコロの唄に 合わせて慌てずにね〜 身体も温まるのが早いよね♥ 歩くだけではない 【ストレッチ・筋トレ】 しっかり時間をかけてる効果が 厳しい環境の中で現れますね〜 ポールって凄いね〜
・田村 芙美子さんの投稿
 北風が少し収まり陽射しの暖かい朝、鎌倉駅西口集合で2月のイベントの下見会に参加しました。ノルディック&ポールウォーキングコーディネーター養成講座をはるばる鎌倉で開催とのことで地理案内役で参加。3時間余かけていらしたシナノさん、JNWAさんら男性5コーチと婆コーチ計6名の古都歩きでした。本番は来月2日間に渡り開催です。 写真は源氏山公園頼朝像の前で。
北風が少し収まり陽射しの暖かい朝、鎌倉駅西口集合で2月のイベントの下見会に参加しました。ノルディック&ポールウォーキングコーディネーター養成講座をはるばる鎌倉で開催とのことで地理案内役で参加。3時間余かけていらしたシナノさん、JNWAさんら男性5コーチと婆コーチ計6名の古都歩きでした。本番は来月2日間に渡り開催です。 写真は源氏山公園頼朝像の前で。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【余力のある内に】 2026/1/30 今年は立ち上げたNPO法人団体の活動縮小と解散をします。 主要スタッフの高齢化と後継者不在で定例会の安全運営を維持するのが困難と判断しました。 大切なのは「志の継承」で形ではないと思ってます。 年内で「シニアポールウォーキング」のみを残し活動も終了する予定です。 7カ月かけてスタッフ全員で「会員の不利益にならない活動縮小体制」の準備をしてこの1月の定例会で発表しました。 そして1年かけて解散へ進みます。 《安全・安心で楽しい定例会》 その為の決断です。 会員へは運動継続への意識づけと仲間づくりを推し進めて来ました。 それが結実するのを願ってやみません 新たなウォーキング指導員の任意団体の立ち上げ準備も同時にスタートします。 ○地域で今の自分にできる事 ○しなければならない事 今後も追い続けて行く所存です。 引き続きご指導とご鞭撻を宜しくお願いいたします。
【余力のある内に】 2026/1/30 今年は立ち上げたNPO法人団体の活動縮小と解散をします。 主要スタッフの高齢化と後継者不在で定例会の安全運営を維持するのが困難と判断しました。 大切なのは「志の継承」で形ではないと思ってます。 年内で「シニアポールウォーキング」のみを残し活動も終了する予定です。 7カ月かけてスタッフ全員で「会員の不利益にならない活動縮小体制」の準備をしてこの1月の定例会で発表しました。 そして1年かけて解散へ進みます。 《安全・安心で楽しい定例会》 その為の決断です。 会員へは運動継続への意識づけと仲間づくりを推し進めて来ました。 それが結実するのを願ってやみません 新たなウォーキング指導員の任意団体の立ち上げ準備も同時にスタートします。 ○地域で今の自分にできる事 ○しなければならない事 今後も追い続けて行く所存です。 引き続きご指導とご鞭撻を宜しくお願いいたします。
来月以降の開催
・長岡智津子さんの投稿
 写真1件
写真1件
2.PW関連学術ニュース
2-1)急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する
**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2026年1月7日のFB投稿です**
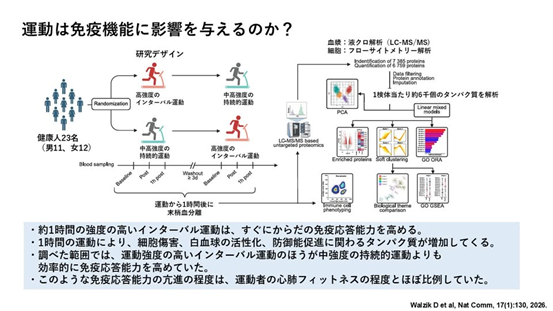 運動が健康に良いことがいろいろな研究から示されています。たとえば、運動により健康寿命が延びたり、アルツハイマー病やがんのリスクが下がったりすることなど、さまざまな運動による効能が報告されています。しかし、それが実際にどのような機序によって起きているのかについてはあまり良くわかっていません。
運動が健康に良いことがいろいろな研究から示されています。たとえば、運動により健康寿命が延びたり、アルツハイマー病やがんのリスクが下がったりすることなど、さまざまな運動による効能が報告されています。しかし、それが実際にどのような機序によって起きているのかについてはあまり良くわかっていません。
この点、ドイツの研究グループが、果たして運動がどの程度、免疫機能に影響を与えうるのかについて詳細に調べ、その結果をNature Communicationsの最新号に発表しています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-68101-9)。
具体的には、健康人23名(男11名、女12名;年齢30±4歳)に対して約1時間の高強度のインターバル練習あるいは約1時間の中強度の持続的運動をしてもらい、1時間後に末梢血を得て、末梢血白血球のフローサイトメトリー解析と血漿のプロテオーム解析(LC-MS/MSを用いた解析;1検体あたり約6千種類の蛋白質について解析)を行いました。
わかったことをまとめると次のようです。
・約1時間の強度の高いインターバル運動は、すぐにからだの免疫応答能力を高める。
・1時間の運動により、細胞傷害、白血球の活性化、防御能促進に関わるタンパク質が増加してくる。
・調べた範囲では、運動強度の高いインターバル運動のほうが中強度の持続的運動よりも効率的に免疫応答能力を高めていた。
・このような免疫応答能力の亢進の程度は、運動者の心肺フィットネスの程度とほぼ比例していた。
つまり、強度の高い運動は、約1時間程度のものでも、からだの免疫応答能力に関わる種々のタンパク質の産生を高めていて、この効果は、若い健康人で見る限り、運動強度の高いインターバル運動のほうが中強度の持続的運動よりも強かった、ということです。また、心肺能力の高い人でこのような効果が見られやすい傾向があったことから、普段からの運動で心肺の予備力を鍛えておくほうが、運動の効果が見られやすくなるようです。
ただし、この研究は若い健康人だけが対象となっていて、高齢者に対してそのままこのような結果があてはまるかは注意して考えないといけません(特に高齢者においては高強度のインターバル運動を1時間も続けることはできないので)。しかし、『運動によって免疫力が良い方向に向かう』とか『心肺能力の高い人では免疫応答能が高い傾向がある』ということは、間違いなく高齢者にも当てはまることだと思います。今後、このような研究が高齢者も対象として行われていくことになるでしょう。
関連情報
1)原論文
公開日:Published: 02 January 2026 (Open access)
表題:Acute exercise rewires the proteomic landscape of human immune cells
(和訳:急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する)
著者:David Walzik, Niklas Joisten, Alan J. Metcalfe, Sebastian Proschinger, Alexander Schenk, Charlotte Wenzel, Alessa L. Henneberg, Martin Schneider, Silvia Calderazzo, Andreas Groll, Carsten Watzl, Christiane A. Opitz, Dominic Helm & Philipp Zimmer
掲載誌:Nature Communications volume 17, Article number: 130 (2026)
要旨
運動が免疫系に良い影響を与えることは広く認められているが、運動に対する免疫細胞の分子的応答については未解明な点が多い。本研究では、末梢血単核細胞(PBMC)を6000タンパク質を超える深さまで質量分析法を用いてプロテオーム解析した。運動時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動(HIIE)と中強度持続運動(MICE)を比較することで、PBMCのプロテオーム構成における多様な変化を特定し、運動後1時間以内にエフェクター機能と免疫細胞活性化経路に関連する大きな変化を明らかにした。これらの変化は、MICEと比較してHIIE後の方が顕著であり、2つの運動条件間で免疫細胞動員パターンが同一であるにもかかわらず発生した。さらに、心肺機能のフィットネスを効果的に予測する免疫プロテオームシグネチャーを特定し、運動によって引き起こされる潜在的な適応や、運動によって媒介される免疫学的健康効果についての知見を得た。この研究は、運動が免疫系を調節する仕組みについての知識を広げる信頼できるデータリソースを提供し、健康維持に関連する要因として運動の強度を強調するWHO 2020ガイドラインを裏付ける生物学的証拠をもたらします。
図1:研究デザイン、分析計画、運動誘発性免疫細胞動員。
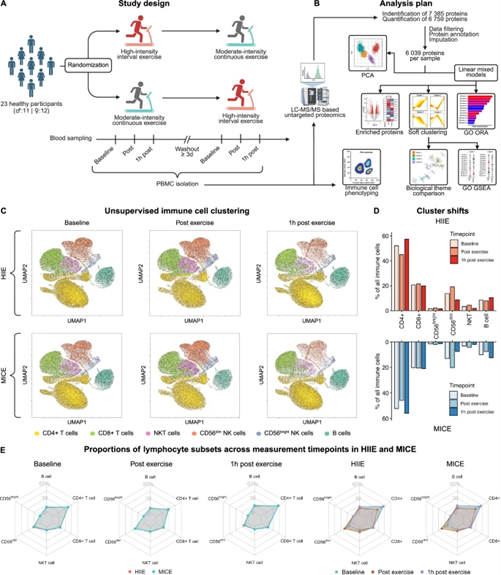 A 時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動 (HIIE) と中強度持続運動 (MICE) を含む研究デザインの概要。 B 末梢血単核細胞 (PBMC) を分析するために使用したバイオ分析およびバイオインフォマティクス手法の概要。C自己組織化マップ (SOM) を使用した教師なしクラスタリングによって識別された免疫細胞クラスターの均一多様体近似および投影 (UMAP)。免疫細胞クラスターは色分けされ、運動条件と測定時点別に表示されます。各 UMAP は 22 のサンプルからの 3000 個の生きたリンパ球に対応し、合計 66,000 件のイベントが発生します。MICE 後 1 時間を表す UMAP の場合、21 のサンプルしか利用できなかったため、63,000 件のイベントが発生します。D識別されたクラスターにおける運動誘発性シフトの比較。E HIIE および MICE に応答したリンパ球サブセットの割合。補足図 S1および補足データ S2、S3、S4も参照。BioRenderで作成。Walzik, D. (2025) https://BioRender.com/y85v219。
A 時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動 (HIIE) と中強度持続運動 (MICE) を含む研究デザインの概要。 B 末梢血単核細胞 (PBMC) を分析するために使用したバイオ分析およびバイオインフォマティクス手法の概要。C自己組織化マップ (SOM) を使用した教師なしクラスタリングによって識別された免疫細胞クラスターの均一多様体近似および投影 (UMAP)。免疫細胞クラスターは色分けされ、運動条件と測定時点別に表示されます。各 UMAP は 22 のサンプルからの 3000 個の生きたリンパ球に対応し、合計 66,000 件のイベントが発生します。MICE 後 1 時間を表す UMAP の場合、21 のサンプルしか利用できなかったため、63,000 件のイベントが発生します。D識別されたクラスターにおける運動誘発性シフトの比較。E HIIE および MICE に応答したリンパ球サブセットの割合。補足図 S1および補足データ S2、S3、S4も参照。BioRenderで作成。Walzik, D. (2025) https://BioRender.com/y85v219。
2)2026年1月10日(土)日本経済新聞記事『ゆるHIITで筋トレ』
【この記事でわかること】
・「ゆるHIIT」のトレーニング内容
・通常の筋トレや有酸素運動との違いは
・健康効果を最大化する無理ない強度とは
**以下、同記事の書き出し部分です**
新年を迎え「今年こそ運動しよう」と決意した人も多いだろう。忙しい現代人にお勧めなのが、わずか数分で筋トレと有酸素運動ができるHIITだ。強度を落とした”ゆるHIIT”ならハードルはさらに低い。
(注)「ゆるHIIT」紹介動画や、実践用のLINEチャットポット等もネットで検索できます。
2-2)グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する
**以下、大阪大学の宮坂先生の2026年1月15日のFB投稿です**
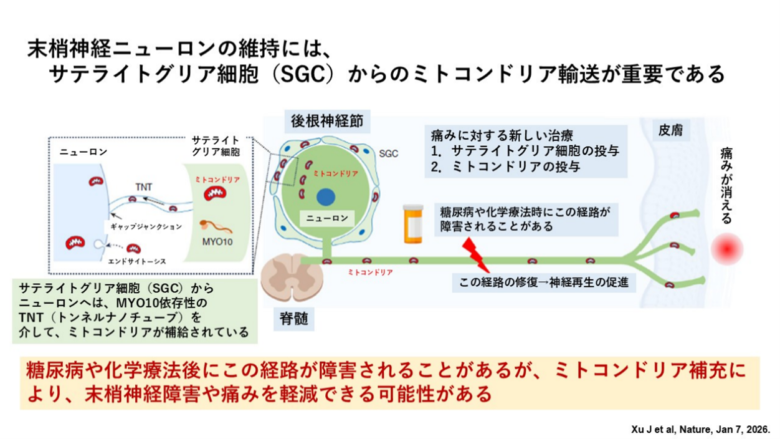 一般に、神経細胞(ニューロン)の周囲にはグリア細胞が存在していて、ニューロンに対する保護、栄養補給や代謝調節を行う、と考えられています。脳のニューロンの周りにはアストロサイト(星状膠細胞)、末梢神経系(特に神経節)のニューロンの周りにはサテライトグリア細胞が存在します。
一般に、神経細胞(ニューロン)の周囲にはグリア細胞が存在していて、ニューロンに対する保護、栄養補給や代謝調節を行う、と考えられています。脳のニューロンの周りにはアストロサイト(星状膠細胞)、末梢神経系(特に神経節)のニューロンの周りにはサテライトグリア細胞が存在します。
最近、ニューロン間や、免疫細胞とがん細胞間でミトコンドリアの移動現象が観察され、機能的に意味があることではないかとして話題になっています。また、最新号のNatureに出た論文では、グリア細胞とニューロンの間ではミトコンドリア輸送が重要であり、これが乱されると神経障害や痛みが生じる、と報告されています。アメリカの研究グループによる仕事です(https://www.nature.com/articles/s41586-025-09896-x)。
この研究では、後根神経節(脊髄のすぐ外側にある膨らみで、末梢からの触覚、痛覚、温度覚などを脊髄へ伝える感覚神経が集まっている場所)のニューロンを包むサテライトグリア細胞からニューロンに対して、トンネルナノチューブという構造を介して、ミトコンドリアが輸送されるとのことです。正常状態ではサテライトグリア細胞からニューロンへのミトコンドリア補給によって神経が保護されているのですが、糖尿病や化学療法剤投与によってこの経路が破綻することがあり,そのために神経障害と疼痛が生じることがあるとのことです(実際、糖尿病の際やパクリタキセルという抗がん剤投与後には難治性の神経障害や強い不快な痛みが生じることがあります)。これに対して、この経路を修復するためにミトコンドリアを補給すると神経障害や痛みが抑えられる可能性がある、とのことです。
これまでは、われわれのニューロンは既に出来上がってしまった細胞であり、いったん傷つくと修復が不能であるかのように考えられていました。一方、もし、ニューロンの恒常状態(ホメオスタシス)維持に周囲の細胞からのミトコンドリア供給が大事だとすると、ミトコンドリアの再補給によって痛んだニューロンを修復出来る可能性があり、これによって、神経障害や痛みに対する治療法が新たに開発される可能性があります。もしかすると、すごいことかもしれません。医学は日進月歩の世界です。
関連情報①原論文
掲載誌:Nature (2026) Open access
公開日:Published: 07 January 2026
表題:Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy
(和訳:グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する)
著者:Jing Xu, Yize Li, Charles Novak, Min Lee, Zihan Yan, Sangsu Bang, Aidan McGinnis, Sharat Chandra, Vivian Zhang, Wei He, Terry Lechler, Maria Pia Rodriguez Salazar, Cagla Eroglu, Matthew L. Becker, Dmitry Velmeshev, Richard E. Cheney & Ru-Rong Ji
要旨
脊髄後根神経節(DRG)の一次感覚ニューロンは軸索が長く、ミトコンドリアを多く必要とするため、ミトコンドリア機能不全は糖尿病や化学療法後の末梢神経障害に関係しているといわれている1 , 2。しかし、一次感覚ニューロンがミトコンドリアの供給を維持するメカニズムは依然として不明である。DRGの衛星グリア細胞(SGC)は感覚ニューロンを取り囲み、ニューロン活動と疼痛を制御している3。本研究では、SGCがSGC由来ミオシン10(MYO10)とトンネルナノチューブを形成することで、in vitro、ex vivo、in vivoでミトコンドリアをDRG感覚ニューロンに輸送できることを示す。走査型および透過型電子顕微鏡法によって、マウスとヒトのDRGのSGCと感覚ニューロンの間にトンネルナノチューブのような超微細構造が存在することが明らかになった。未処置マウスにおけるミトコンドリア輸送の阻害は、神経変性と神経障害性疼痛を引き起こす。単核RNAシークエンシングとin situハイブリダイゼーションにより、MYO10がヒトSGCで高発現していることが明らかになりました。さらに、糖尿病患者のDRG由来SGCでは、MYO10の発現が低下しており、ミトコンドリアからニューロンへの移行も見られます。ヒトSGCをマウスDRGに移植することで、MYO10依存的な末梢神経障害の予防効果が認められます。本研究は、これまで認識されていなかった末梢グリアの役割を明らかにし、糖尿病における小線維ニューロパチーに関する知見を提供し、神経障害性疼痛の管理のための新たな治療戦略を示唆しています。
図 1: 共培養における SGC からニューロンへのミトコンドリアの移動とマウス DRG の TNT 様構造。
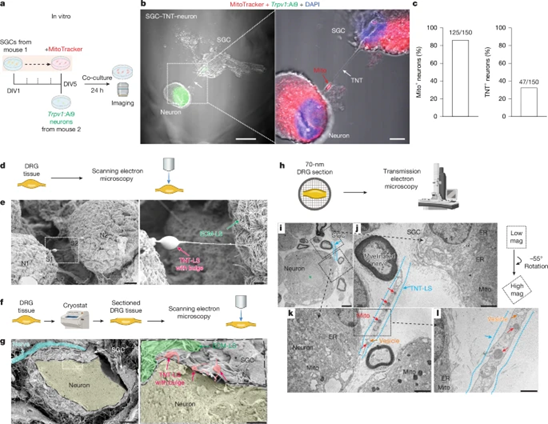 a , マウス DRG 由来の SGC-ニューロン共培養の模式図。SGC は MitoTracker 色素で標識されており、DRG ニューロンはTrpv1 :Ai9 マウス由来です。b ,左、SGC と相互作用するTrpv1 +ニューロンを示す SGC-ニューロン共培養の画像 (スケールバー、20 μm)。右、四角で囲まれた領域の拡大図。TNT (白矢印) と TNT 内のミトコンドリア (Mito、赤矢印) を示しています (スケールバー、5 μm)。c , MitoTracker 陽性 (Mito + ) および TNT 陽性ニューロンの割合。6 回の独立した実験から合計109個のニューロンが定量化のために含められました。d ,切片を作成せずに DRG 全体を観察した SEM の模式図。e , 隆起した TNT 様構造 (TNT-LS) を示す、マウス DRG 全体の高倍率 SEM 画像。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。f , 切片化したマウス DRG の SEM の模式図。g , 切片化したマウス DRG の代表的な SEM 画像。SGCからニューロンへの隆起を伴う TNT-LS を示す。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。h , マウス DRG の TEM の模式図。i , DRG ニューロンと SGC を示す代表的な低倍率 TEM 画像。n = 4 生物学的反復。緑のアスタリスクはニューロンの核を示します。スケールバー、5 μm。j – l , SGC とニューロンの間にある TNT-LS を示す代表的な高倍率 TEM 画像。黒色の「Mito」は細胞内のミトコンドリア(j – l)を示します。赤色の「Mito」はTNT-LS内のミトコンドリア(k)を示します。「Vesicle」はTNT-LS内の小胞(k、l)を示します。黒いアスタリスクはSGCの核を示します。l 、 kからの拡大図で、滑らかなTNT-LS内のミトコンドリア(赤矢印)と小胞を示しています。ER、小胞体。n = 3生物学的反復。スケールバー:2 μm(j、k); 800 nm(l)。
a , マウス DRG 由来の SGC-ニューロン共培養の模式図。SGC は MitoTracker 色素で標識されており、DRG ニューロンはTrpv1 :Ai9 マウス由来です。b ,左、SGC と相互作用するTrpv1 +ニューロンを示す SGC-ニューロン共培養の画像 (スケールバー、20 μm)。右、四角で囲まれた領域の拡大図。TNT (白矢印) と TNT 内のミトコンドリア (Mito、赤矢印) を示しています (スケールバー、5 μm)。c , MitoTracker 陽性 (Mito + ) および TNT 陽性ニューロンの割合。6 回の独立した実験から合計109個のニューロンが定量化のために含められました。d ,切片を作成せずに DRG 全体を観察した SEM の模式図。e , 隆起した TNT 様構造 (TNT-LS) を示す、マウス DRG 全体の高倍率 SEM 画像。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。f , 切片化したマウス DRG の SEM の模式図。g , 切片化したマウス DRG の代表的な SEM 画像。SGCからニューロンへの隆起を伴う TNT-LS を示す。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。h , マウス DRG の TEM の模式図。i , DRG ニューロンと SGC を示す代表的な低倍率 TEM 画像。n = 4 生物学的反復。緑のアスタリスクはニューロンの核を示します。スケールバー、5 μm。j – l , SGC とニューロンの間にある TNT-LS を示す代表的な高倍率 TEM 画像。黒色の「Mito」は細胞内のミトコンドリア(j – l)を示します。赤色の「Mito」はTNT-LS内のミトコンドリア(k)を示します。「Vesicle」はTNT-LS内の小胞(k、l)を示します。黒いアスタリスクはSGCの核を示します。l 、 kからの拡大図で、滑らかなTNT-LS内のミトコンドリア(赤矢印)と小胞を示しています。ER、小胞体。n = 3生物学的反復。スケールバー:2 μm(j、k); 800 nm(l)。
関連情報②岐阜大学医学部下畑先生も2026年1月15日のFB投稿(後掲)でこの論文を紹介されています。
2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2026年1月)
・家族性ALSはここまで治療できる:トフェルセンと「早期診断し,早期治療する」時代の到来
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月5日のFB投稿です**
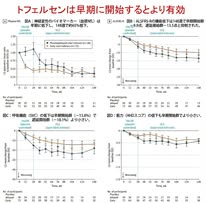 明けましておめでとうございます.
明けましておめでとうございます.
さて新年最初に取り上げる論文として,SOD1遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化症(SOD1-ALS)に対するアンチセンス核酸製剤トフェルセンの長期効果を検討した研究を選びました.その理由は最後に示しますが,本研究は米国を中心とする国際共同研究グループによって実施されたVALOR試験と,そのオープンラベル延長試験(OLE)の統合解析です.108例がトフェルセンまたは偽薬に割り付けられ,28週後に全例がトフェルセンへ移行しました.解析では,最初からトフェルセンを開始した早期開始群と,28週後に開始した遅延開始群が比較されています.したがって,図を読む際には28週までの期間とそれ以降の期間を分けて見る必要があります.
図Aでは神経変性のバイオマーカーである血漿NfLは治療開始後早期に大きく低下し,148週時点で約65%低下していました.その結果,図BではALSFRS-Rによる機能低下が148週で,早期開始群で9.9点,遅延開始群で13.5点といずれも自然経過より緩やか,かつ早期開始群で低下が抑制されていました.図Cでは呼吸機能(緩徐肺活量;SVC)の低下が早期開始群で−13.8%,遅延開始群で−18.1%と差があり,図Dでは筋力(HHDスコア)の低下も早期開始群でより小さいことが示されています.以上より,トフェルセンは約3年後の評価で有効で,かつ早期に治療開始すべきことが分かります.加えて死亡または人工呼吸器装着に至るまでの期間の検討では,進行が速い高NfL群において,早期開始群の方が,イベントフリー期間が明らかに長いことが示されています.これはトフェルセンが症状の進行だけでなく生命予後にも影響を及ぼし得ることを示唆しています.
本研究では進行抑制が主な効果ですが,一部の患者では改善も認められました.148週時点で筋力が改善した例は早期開始群の約27%に達し,生活機能や呼吸機能でも約2割で改善または安定が見られました.つまり改善の頻度は高いわけではありませんが,それでも改善しうる症例が存在する事実は重要です.なお本研究では遺伝子変異の種類ごとの詳細な効果比較は行われてはいません.また遺伝子診断に伴う倫理的問題についても議論していません.
本研究はALS治療の歴史における大きな転換点であり,「早期診断し,早期治療する」時代への移行を示しています.この論文を読みながら,1993年にSOD1遺伝子変異がALSの原因として発見されたときのことを思い出しました.私は当時,研修医1年目で,ALS研究をしていたOben(指導医)の中野亮一先生が「これでALSはついに治療できる!」と熱く語ってくださったことが,今も強く印象に残っています.あらためて当時の論文を読み直してみると,最後の段落に“Perhaps the most important implication of our finding… is that various SOD1 mutations in FALS patients are its potential therapeutic benefit.”と,治療可能性についてすでに言及されていることに気づかされます.しかし現実はそう簡単には行かなかったわけですが,30年を経て,SOD1 mRNAを分解し蛋白産生を低下させる髄注薬トフェルセンが登場し,その長期成績まで示される時代になったわけです.現代は創薬や臨床試験の知識が大きく発展し,難攻不落と言われた神経難病に対する治療薬の確立は今後,加速度的に進むのだと思います.この変化の只中にある脳神経内科という分野に,意欲ある若いドクターがより多くチャレンジしてくれることを期待したいと思います.新年最初にこの論文を取り上げた理由も,まさにそこにあります.
Miller TM, et al. Long-Term Tofersen in SOD1 Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAMA Neurology. Published online December 22, 2025. (リンクはコメント欄)
・専門分化の時代に重要な脳神経内科医の「中核的アイデンティティ」とはなにか?
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月7日のFB投稿です**
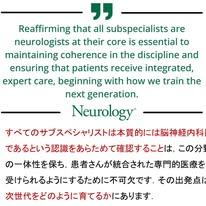 Neurology誌に,この数年私自身も気になっていた問題を正面から取り上げたOpinion論文が掲載されました.米国Weill Cornell MedicineのJoseph E. Safdieh先生らによる「The Core Identity of the Neurologist」です.この論文は,脳神経内科領域におけるサブスペシャリティ化(専門分化)の進展によって,「自分は脳神経内科医である」という感覚が薄れつつあることに警鐘を鳴らしています.つまり著者らは,てんかん専門医,頭痛専門医,脳卒中専門医,パーキンソン病専門医などといった専門分化が進むなかで,「脳神経内科医であること」よりも先に「○○専門医であること」で自らを規定するようになりつつある現状を問題視しています.これは医学の進歩の自然な帰結である一方,その結果として診療,教育,社会への発信のすべてにおいて分断が生じ,脳神経内科という分野の一体性が失われつつあると論じています.
Neurology誌に,この数年私自身も気になっていた問題を正面から取り上げたOpinion論文が掲載されました.米国Weill Cornell MedicineのJoseph E. Safdieh先生らによる「The Core Identity of the Neurologist」です.この論文は,脳神経内科領域におけるサブスペシャリティ化(専門分化)の進展によって,「自分は脳神経内科医である」という感覚が薄れつつあることに警鐘を鳴らしています.つまり著者らは,てんかん専門医,頭痛専門医,脳卒中専門医,パーキンソン病専門医などといった専門分化が進むなかで,「脳神経内科医であること」よりも先に「○○専門医であること」で自らを規定するようになりつつある現状を問題視しています.これは医学の進歩の自然な帰結である一方,その結果として診療,教育,社会への発信のすべてにおいて分断が生じ,脳神経内科という分野の一体性が失われつつあると論じています.
では著者らが考える「脳神経内科医の中核的アイデンティティ」とは何でしょうか?それは特定の疾患や手技によって定義されるものではなく,『病歴聴取,神経診察,局在診断,病態生理に基づく臨床推論という,共通の方法論によって定義されるものだ』と述べています.つまり脳神経内科は疾患の集合体ではなく,「どう考えるか」という思考様式によって統一された専門領域だと述べています.「なるほど,確かにその通りだ!」と思いました.そしてこの共通基盤が弱まると,患者さんは複数の専門外来を巡りながら断片化された医療を受けることになってしまいます.実際に,めまいや視覚症状,歩行障害といった非特異的症状の患者さんが,耳鼻咽喉科,眼科,頭痛クリニック,脳卒中科とたらい回しになり,診断が遅れるという事例が起きていることが指摘されています.
この問題に対して著者らは,「専門性を廃してgeneralistに戻れ」と言っているのではなく,専門性を維持したまま,その根底に「脳神経内科医としての思考」を再び据えるべきだと提案しています.教育の場においては,局在診断と鑑別診断をすべての脳神経内科医の共通言語としてしっかり教育し,朝のカンファレンスやベッドサイド教育では疾患知識よりも臨床推論のプロセスを可視化すること,レジデントが早期から特定の専門領域に過度に取り組まないよう多様な指導医との接点を設けることが提案されています.臨床の場では,サブスペシャリティ外の比較的単純な神経疾患にも対応できる診療の幅を保ち,診断名ではなく「ふるえ」「めまい」といった症状ベースで患者さんを受け入れる診療体制を構築することが推奨されています.さらに,職名や病院のウェブサイト,名簿などではまず「脳神経内科医」という肩書きを前面に出し,専門はその下位概念として位置づけること,社会やメディアへの発信でも「脳神経内科医」という統一した専門職像を強調することが重要だと言っています.
つまりメッセージは,サブスペシャリティは脳神経内科医としてのアイデンティティを失わせるものではなく,それを深化させるものであるべきだという点です.専門分化が進む時代だからこそ,共通の思考様式や言語を意識的に守らなければ,脳神経内科という分野そのものが分断されてしまうという著者らの警告は,日本の医療現場にとっても決して他人事ではありません.この論文はまずしっかり脳神経内科医としての基礎・土台を作ることが,分野の一体性と専門性の高度化を両立させるために不可欠であることを教えてくれているように思います.
Safdieh JE, Robbins MS. The Core Identity of the Neurologist. Neurology. 2025;105:e214265. PMID: 41066722.
・医学のあゆみ誌「全身疾患の新たな危険因子としてのマイクロ・ナノプラスチック」が発刊されます!
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月9日のFB投稿です**
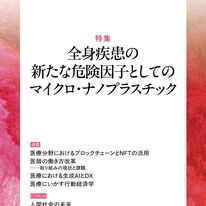 近年,マイクロ・ナノプラスチック(micro- and nanoplastics:MNPs)による環境汚染が,世界的に大きな関心を集めています.これまでプラスチック問題は,主に海洋汚染や生態系への影響として語られることが多かったわけですが,最近では「人の健康への影響」という観点からも注目されるようになってきました.
近年,マイクロ・ナノプラスチック(micro- and nanoplastics:MNPs)による環境汚染が,世界的に大きな関心を集めています.これまでプラスチック問題は,主に海洋汚染や生態系への影響として語られることが多かったわけですが,最近では「人の健康への影響」という観点からも注目されるようになってきました.
MNPsは単なる環境汚染物質にとどまらず,空気や水,食物を介して生体内に侵入し,体内に蓄積する可能性があることが分かってきています.実験研究や疫学研究からは,MNPsが炎症反応,酸化ストレス,免疫調節異常といった生体反応を惹起し得ることが示唆されています.実際に,MNPsが体内で検出された人では,心筋梗塞や脳卒中などによる死亡リスクが上昇すること,認知症患者の脳内に高濃度のMNPsが蓄積していること,さらに肺胞レベルでのMNPs曝露が慢性炎症や肺線維化を増悪させる可能性があることなどが報告されています.
こうした知見を踏まえ,医学のあゆみ誌で特集を企画させていただきました.本特集では,MNPsの免疫毒性,生体への侵入経路,細胞障害のメカニズムといった基礎的な話題から,曝露低減に向けた社会的・行政的な取り組みまでを含め,多角的な視点からMNPsに関する最新情報を紹介しています.おそらく本邦で初めて人体の影響を特集した医学誌になるのではないかと思います.環境問題としてだけでなく,私たち自身の健康に直結する課題として,MNPsを捉え直すきっかけになれば幸いです.
リンクはコメント欄にあります.
【目次】
◆はじめに(下畑享良)
◆総論─MNPsの基礎知識と問題点(芳賀優弥・他)
◆MNPsに含まれる化学物質と毒性(小川久美子・他)
◆MNPsの人体への侵入とその機序(金子昌平・酒井康行)
◆MNPsの表面性状と細胞障害性(辻野博文)
◆MNPsの心血管系への影響(曾和裕之)
◆MNPsの脳梗塞,認知症への影響(下畑享良)
◆大気中MNPsの呼吸器系への影響(和田百合花・石原康宏)
◆環境省のMNPsへの取り組み(環境省水・大気環境局環境管理課,環境省水・大気環境局海洋環境課プラスチック汚染対策室)
#医学のあゆみ #医歯薬出版
・片頭痛の原因分子CGRPの作用部位は「脳」ではなく「硬膜」である――早く治療すべき根拠も判明
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月11日のFB投稿です**
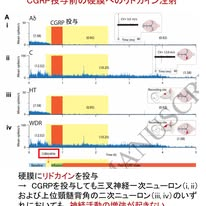 片頭痛においてカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が重要な役割を果たしていることは広く知られています.CGRPは強力な血管拡張作用を持ち,投与すると片頭痛様の頭痛を誘発することが知られています.例えばCGRPを点滴投与すると,健常者には軽度の頭痛を,片頭痛患者には典型的な片頭痛発作を高率に誘発します.このためCGRPは,片頭痛発作を引き起こす原因分子のひとつと考えられるようになりました.一方で,同じCGRPを動物に投与しても,「痛みのセンサー」として働く末梢侵害受容器(神経),すなわち硬膜を支配する三叉神経のAδ線維とC線維の興奮がほとんど観察されなかったため,「なぜCGRPが頭痛を起こすのか」という機序は長らく不明のままでした.
片頭痛においてカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が重要な役割を果たしていることは広く知られています.CGRPは強力な血管拡張作用を持ち,投与すると片頭痛様の頭痛を誘発することが知られています.例えばCGRPを点滴投与すると,健常者には軽度の頭痛を,片頭痛患者には典型的な片頭痛発作を高率に誘発します.このためCGRPは,片頭痛発作を引き起こす原因分子のひとつと考えられるようになりました.一方で,同じCGRPを動物に投与しても,「痛みのセンサー」として働く末梢侵害受容器(神経),すなわち硬膜を支配する三叉神経のAδ線維とC線維の興奮がほとんど観察されなかったため,「なぜCGRPが頭痛を起こすのか」という機序は長らく不明のままでした.
この問題に取り組んだのが,米国ハーバード大学等の研究チームです.彼らはラットを用い,CGRPを内頸動脈から選択的に投与するという新しい方法によって,硬膜に高濃度のCGRPを届ける実験系を構築しました.従来の腹腔内投与や静脈内投与では,CGRPは全身循環に希釈され,肝臓などで代謝されるため,硬膜の神経終末に十分な濃度で届かなかったと考えられます.今回の研究は,この投与経路の問題を解決することで,これまで否定的とされてきた「CGRPによる末梢侵害受容器の活性化」が実際に起こることを神経生理学的に示すことに成功しました.
研究の結果,内頸動脈からCGRPを投与すると,硬膜を支配する一次ニューロンが活性化し,さらにその入力を受ける上位頸髄背角の二次ニューロンの活動も持続的に増加することが示されました.上位頸髄背角とは,頸髄C1~C2レベルの後角に相当する部位で,三叉神経脊髄路核尾側亜核と連続する構造です.顔面や硬膜からの痛覚入力が最初に中枢で統合される場所であり,ここで感作が成立すると,痛みは末梢入力がなくても中枢で維持される状態へと移行すると考えられています.
重要なのは,CGRPの作用部位が「脳」ではなく「硬膜」であることが実験的に示された点です.図1では,硬膜に局所麻酔薬(リドカイン)をあらかじめ投与しておくと,CGRPを投与しても三叉神経一次ニューロンおよび上位頸髄背角の二次ニューロンのいずれにおいても,神経活動の増加や機械刺激に対する感作がまったく起こらないことが示されています.これは,CGRPがまず硬膜に分布する三叉神経侵害受容線維の末梢終末に作用し,そこから中枢へ向かう痛みのカスケードが開始されることを意味しています.
一方で,図2は時間の要素の重要性を示しています.Aでは,CGRP投与後30分で三叉神経節を局所麻酔で遮断すると神経活動が低下し,この段階では末梢入力が痛みの維持に必須であることが示されています.一方,B,C, Dでは,CGRP投与後1時間,2時間,3時間で同様の遮断を行っても神経活動は低下せず,痛みの駆動が末梢から中枢へと移行していることが示されています.すなわち,痛みは最初は硬膜からの入力に依存して始まりますが,時間の経過とともに中枢回路内で自己維持的に駆動される状態へと移行します.
この知見は,リメゲパントなどのCGRP受容体拮抗薬も発作急性期に使用する場合,トリプタンと同様に,「できるだけ早く治療すべきである」可能性を示唆します.つまり発作初期の末梢依存期に投与することで中枢性感作への移行を防ぎやすい一方,感作が成立した後では効果が限定的になるものと推測されます(リメゲパントの実臨床で,このようなことが言われているのでしょうか?).
いずれにせよ本研究は,片頭痛の開始点が脳内ではなく硬膜であること,そしてその後に中枢性感作へと移行するtime windowが存在することを示した点で,片頭痛の理解を一段階進めたといえます.
Melo-Carrillo A, Strassman A, Burstein R. Elucidating the nociceptive role of CGRP in migraine headache. Brain. 2026 Jan 8:awag008. PMID: 41503630.
・全身疾患としてのパーキンソン病―睡眠と便秘,そして神経炎症に着目し,発症・進行を抑える―
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月12日のFB投稿です**
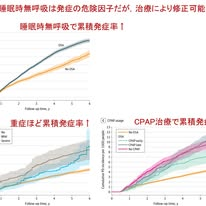 パーキンソン病(PD)では,発症よりもはるか以前から全身レベルの異常が生じていると言われています.最近発表された2つの論文は,この見方を強く支持し,PDを全身性・ネットワーク疾患として捉える重要性を浮き彫りにしています.1つは米国の大規模データを用いて睡眠時無呼吸とPD発症の関係を検討した研究であり,もう1つは発症早期PD患者において便秘と神経炎症の関連をPETで可視化した研究です.両者に共通するのは,末梢臓器の機能異常が神経炎症等を介してPDの発症,進行に関与しうるという点です.
パーキンソン病(PD)では,発症よりもはるか以前から全身レベルの異常が生じていると言われています.最近発表された2つの論文は,この見方を強く支持し,PDを全身性・ネットワーク疾患として捉える重要性を浮き彫りにしています.1つは米国の大規模データを用いて睡眠時無呼吸とPD発症の関係を検討した研究であり,もう1つは発症早期PD患者において便秘と神経炎症の関連をPETで可視化した研究です.両者に共通するのは,末梢臓器の機能異常が神経炎症等を介してPDの発症,進行に関与しうるという点です.
最初の論文は米国からの研究で,1100万人以上の退役軍人の電子カルテを用いて閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)とPD発症リスクを解析しています.その結果,OSAを有する人は有さない人に比べてPDを発症しやすく,しかもこのリスクは治療によって修正可能であることが示されました.論文の図1Aでは,OSAのある群はない群に比べて追跡2年後からPDの累積発症率が高くなり,6年後には1000人あたり約1.6人多く発症していることが示されています.図1Bでは,OSAを軽症と重症に分けて比較すると,軽症でもPDリスクは有意に上昇し,重症ではさらに早期からリスクが高まるという重症度依存性が示されています.そして図1Cでは,OSAのある人の中でもCPAPを診断後2年以内に導入した群では,導入しなかった群に比べてPDの累積発症率が明らかに低く,5年後の発症率はCPAPなし群で9.10/1000人,CPAP早期導入群で6.81/1000人であり,約2.3/1000人の絶対リスク低下とハザード比0.69という有意な低下が示されています.つまりOSAがPDの危険因子であるだけでなく,その影響は重症度に依存し,さらに治療によって修正可能であることを示しています.著者らは,OSAは間欠的低酸素,酸化ストレス,炎症反応,ミトコンドリア機能障害といった連鎖が神経炎症を介して神経変性を促進する可能性を考察しています.
もう1つの論文は英国からの研究で,発症早期PD患者27名を対象に,便秘の重症度と神経炎症の関係を,ミクログリア活性化を画像化する11C-PK11195 PETで評価しています.この結果,便秘が強い人ほど前頭葉,側頭葉,頭頂葉,後頭葉を含む広範な脳領域で神経炎症が強いことが示されました.図2では,便秘スコアと脳内炎症の相関が脳表マップとして可視化されています.図で赤い部位ほど「便秘が強い人ほどその部位の炎症が強い」ことを意味しています.とくに眼窩前頭皮質や後頭葉の一部が赤く示され,便秘の重症度とこれらの脳領域の神経炎症が強く結びついていることが示されています.さらに,便秘の重症度は血中のTh1細胞やTh17様Th1細胞の増加,および脳脊髄液リンパ球数の増加とも相関しており,腸管の異常が末梢免疫を活性化し,それが中枢神経系の神経炎症を増悪させている可能性が示唆されています.著者らは,便秘を単なる自律神経症状ではなく,炎症を介して疾患進行に関与する病態因子として捉えるべきであると論じています.私はこの論文を読んでから,PDの便秘治療を意識して強化するようにしました.
つまりPDは脳だけの病気ではなく,睡眠,呼吸,腸管,免疫といった全身のネットワークの破綻として進行する疾患であり,その中心的な媒介として神経炎症が位置づけられる可能性が高いということです.つまり,睡眠時無呼吸や排便といった症状に対して介入することの重要性を示しています.PDの発症や進行を抑えるために,無呼吸はCPAPで治療し,便秘にも今まで以上にコントロールをすることを検討するということだと思います.PD診療はより全身を診ることを意識する時代になるものと思われます.
Neilson LE, et al.Obstructive Sleep Apnea, Positive Airway Pressure, and Implications of Early Treatment in Parkinson Disease.JAMA Neurol.2025.PMID: 41284280
Camacho M, et al.Constipation Is Linked to Neuroinflammation in Early Parkinson’s Disease.Mov Disord.2025.PMID: 41231011.
・すくみ足(freezing of gait)の国際的コンセンサス声明―すり足や小刻み歩行で前に進めない状態もすくみ足である
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月13日のFB投稿です**
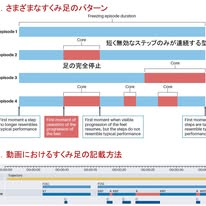 パーキンソン病や進行性核上性麻痺(PSP)におけるすくみ足(freezing of gait;FOG)は,転倒やADL低下の主要な原因でありながら,その定義が曖昧で,研究や臨床で一貫した評価が困難でした.当科でもPSPに対する抗コリン薬のすくみ足に対する効果を検証する医師主導治験を行っていますが,すくみ足の判断に迷う場面が少なからずあり,最近も回診で議論したところでした.今回,Nature Reviews Neurology誌に掲載されたコンセンサス声明は,International Consortium for Freezing of Gait(ICFOG)による国際的合意として,すくみ足の定義と評価法を整理したものです.
パーキンソン病や進行性核上性麻痺(PSP)におけるすくみ足(freezing of gait;FOG)は,転倒やADL低下の主要な原因でありながら,その定義が曖昧で,研究や臨床で一貫した評価が困難でした.当科でもPSPに対する抗コリン薬のすくみ足に対する効果を検証する医師主導治験を行っていますが,すくみ足の判断に迷う場面が少なからずあり,最近も回診で議論したところでした.今回,Nature Reviews Neurology誌に掲載されたコンセンサス声明は,International Consortium for Freezing of Gait(ICFOG)による国際的合意として,すくみ足の定義と評価法を整理したものです.
重要なポイントは,すくみ足を「有効な一歩を踏み出そうと試みているにもかかわらず,それができない発作性エピソード」と再定義した点にあります.従来の「歩こうとする意図があるにもかかわらず前進が消失する」という定義から,「意図」という主観的概念を排し,観察可能な「試み」に基づいて評価する枠組みに変更しました.また,すくみ足は完全停止に限らず,短く無効なステップや,前進がほとんど得られない歩行も含むと明確化しました.
図1は,すくみ足が単なる「足が止まる現象」ではなく,「無効な歩行が発作的に持続する期間」であることを時間軸で示しています.4つの仮想的なすくみ足エピソードが描かれており,第1エピソードは足の完全停止(core)を伴わず,短く無効なステップのみが連続する型を示しています.第2エピソードは途中に1回のcoreを含みますが,core終了後も無効な歩行が続くため,すくみ足全体は継続します.第3エピソードは1回のcoreでエピソード全体が終了する型を示しており,coreとすくみ足が一致する典型例です.第4エピソードは複数のcoreが1つのすくみ足の中に出現する型を示しており,停止と無効な歩行が交互に現れる型を表しています.つまり,すくみ足には完全に停止するcoreが含まれる場合と含まれない場合があり,coreが複数回出現することもあります.持続時間の点では,coreが終了しても無効な歩行が続く場合には,すくみ足全体は継続すると整理されました(第2エピソード).
図2は,実際の動画解析においてすくみ足がどのように区切られ,分類されるかを示した例です.横軸は時間を表し,その上にすくみ足エピソードがいつ始まり,いつ終わるかが示されています.さらに各エピソードの中で,「足が全く動かない時間(akinetic;A)」と,「足は動くが前に進まない時間(kinetic)」が区別されて表示されています.kineticの中でも,速く小刻みに震えるような動きがある場合はkinetic-trembling(KT),それ以外のすり足様の動きや小さな踏み替えはkinetic-no-trembling(KNT)と分類されます.図では2段目にいつすくみ足があるか,3段目にその特徴,4段目に足の完全停止(core)が示されています.3段目の特徴としては,1回目はKTのみが出現し,2回目はKNTとAが入れ替わりながら持続していることが示されています.また,akinetic型のすくみ足は必ずcoreとして現れますが,逆にcoreが観察されても,それが必ずしもakinetic型とは限らず,coreの前後にすり足様の無効な歩行が続くこともあります.
またfestination(突進現象)についても整理され,歩くテンポがだんだん速くなり,一歩の長さが短くなる型のfestinationはすくみ足に含める一方,バランス異常により前に倒れそうになるのを支えるために足を速く出しているだけの加速は,すくみ足とは区別すべきとされました.
さらに,患者さんのすくみ足の有無を分類する方法も整理されました.自己申告だけに頼るのではなく,薬が効いている状態と切れている状態の両方で実際に歩いてもらい,その様子を評価することで判定の確実性を高めます.その際,診察や動画で一度でもすくみ足が確認されれば「すくみ足あり(definite FOG)」と分類し,どちらの状態でも確認されなければ「すくみ足なし(definite non-FOG)」と判断してよいとされました.
本コンセンサスは,すくみ足を「止まる現象」から「発作性の無効歩行現象」へと概念転換させ,研究,臨床,治験の共通言語を提供しました.つまりすくみ足を「足が止まる現象」と捉えるのではなく,「歩こうとしているのに,有効な歩行ができなくなる状態が発作的に起こる現象」と捉え直したことを意味します.足が完全に止まらなくても,すり足や小刻み歩行で前に進めない状態もすくみ足に含まれる,という考え方への転換になります.
Gilat M,et al.An updated definition of freezing of gait. Nat Rev Neurol. 2026 Jan 9. PMID: 41513745.
・グリアからニューロンへのミトコンドリア移送という驚きの末梢神経保護の仕組み―神経障害性疼痛の機序に迫る―
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月15日のFB投稿です**
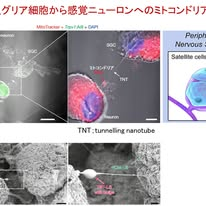 Nature誌に掲載された米国デューク大学からの論文は,後根神経節に存在する衛星グリア細胞(satellite glial cell)が,隣接する感覚ニューロンにミトコンドリアを供給するという,これまで知られていなかった神経保護機構を明らかにしました.
Nature誌に掲載された米国デューク大学からの論文は,後根神経節に存在する衛星グリア細胞(satellite glial cell)が,隣接する感覚ニューロンにミトコンドリアを供給するという,これまで知られていなかった神経保護機構を明らかにしました.
一次感覚ニューロンは非常に長い軸索を持ち,活動電位の発生や維持のために多量のエネルギーを必要とします.そのためミトコンドリアの機能は生命線とも言えますが,細胞体で作られたミトコンドリアを末梢軸索末端まで運ぶことには限界があります.本研究は,この制約を補う仕組みとして,衛星グリア細胞がミトコンドリアをニューロンへ供給している可能性を検証したものです.
著者らはマウスおよびヒトの後根神経節を用いた培養実験,生体内イメージング,電子顕微鏡解析を組み合わせ,衛星グリア細胞とニューロンの間にトンネル状の細い構造,いわゆる tunnelling nanotube が形成され,その内部をミトコンドリアが移動していることを直接示しました.図1bでは,ミトコンドリアを赤色蛍光で標識した衛星グリア細胞と,緑色蛍光で標識された感覚ニューロンを共培養すると,赤いミトコンドリアが細い管状構造を通ってニューロン側に移動していく様子が観察されています.
さらに図1eのマウス後根神経節の走査電子顕微鏡像では,衛星グリア細胞とニューロンを結ぶ極めて細い管状構造が組織内に実在することが示され,その内部に膨隆が存在することから,ミトコンドリアが輸送されていることが形態学的にも裏づけられています.
このミトコンドリア移送は神経損傷モデルにおいて増加することが示されており,著者らはこれを神経障害に対する内因性の代償的・保護的応答の一部と解釈しています.このトンネル構造の形成には MYO10 というモータータンパクが必須であり,衛星グリア細胞に特異的に高発現しています.MYO10を低下させるとトンネル構造が形成されず,ミトコンドリア移送が障害され,その結果として神経は過興奮状態となり,痛覚過敏が生じることが示されました.すなわち【神経障害 → ミトコンドリア供給低下 → 神経過興奮 → 痛み】という病態機序が想定されます.
臨床に当てはめると,糖尿病モデルや抗がん剤パクリタキセルによる末梢神経障害モデルにおいて,衛星グリア細胞とニューロンの間の距離が広がり,トンネル構造が乱れ,MYO10の発現が低下し,ミトコンドリア移送が著しく障害されていました.ヒトの糖尿病患者由来の後根神経節でも同様の変化が確認され,この仕組みの破綻が臨床的な末梢神経障害と深く関係していることが示唆されました.
さらに著者らは,健常なヒト由来衛星グリア細胞,あるいはそれらから単離したミトコンドリアをマウスの後根神経節に直接微量注入することで,糖尿病性神経障害モデルおよび化学療法誘発性神経障害モデルの疼痛行動が有意に改善することを示しました.一方,糖尿病由来の衛星グリア細胞や機能不全のミトコンドリアではこの効果が弱く,MYO10を低下させた衛星グリア細胞では治療効果が消失しました.
図2の模式図は,正常では衛星グリア細胞からニューロンへ MYO10 依存性にミトコンドリアが供給され神経が保護されているのに対し,糖尿病や化学療法ではこの経路が破綻し,その結果として神経障害と疼痛が生じること,そしてこの経路を補うことで治療が可能になることを示しています.
この研究は,末梢神経障害と神経障害性疼痛を,グリアとニューロンの間の協力関係の破綻として再定義するものです.さらに,細胞移植やミトコンドリア移植という新しい治療概念を提示しています.こういう論文を読むと本当にワクワクしますし,神経学の未来を感じます.
Xu J, et al.Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy.Nature.2025;PMID: 41501451.
・エビデンス情報が強化された『今日の治療指針2026』の発刊とオススメの使い方
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月17日のFB投稿です**
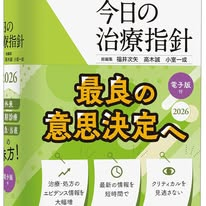 このたび『#今日の治療指針 2026(#医学書院)』が発刊され,私は神経・筋疾患領域の責任編集を担当しました.本書の内容と,日常診療でのオススメの使い方をご紹介します.
このたび『#今日の治療指針 2026(#医学書院)』が発刊され,私は神経・筋疾患領域の責任編集を担当しました.本書の内容と,日常診療でのオススメの使い方をご紹介します.
まず「神経・筋疾患領域」は,大きく4つのパートから構成されています.①最近の動向,②同種薬の特徴と使い分け(認知症治療薬,てんかん治療薬,頭痛治療・予防薬),③治療法(血漿浄化療法,IVIG,ボツリヌス治療,脳神経血管内治療,慢性疼痛のペインコントロール),④疾患各論75項目です.
本書は,日々の臨床で辞書のように必要な項目を引いて使うのが基本ですが,とくに「同種薬の特徴と使い分け」は,処方に迷ったときに非常に有用です.認知症治療薬,てんかん治療薬,頭痛治療薬が一覧表として整理されており,薬剤間の違いを容易に比較できます.また,疾患各論の各項目冒頭にある「ニュートピックス」と「治療のポイント」に目を通すだけでも,最新治療の知識を効率よくアップデートできます.さらに今回,エビデンス情報強化の一環として,主な処方薬について「推奨・エビデンス」を新たに明示しました.
私が執筆を担当した「最近の動向」では,「治療」として多発性硬化症,パーキンソン病,ALS,脳出血,CIDPなど13疾患を取り上げています.加えて「注目の臨床試験」では,片頭痛におけるPACAP抗体,認知症に対する水痘・帯状疱疹ウイルスワクチンの効果を紹介しました.キーワード2026としては「核酸医薬」を解説し,この1年間に発表された主要なガイドラインもまとめています.ぜひ日常診療にご活用ください.
最後になりますが,本書にご執筆くださった多くの先生方に,心より感謝申し上げます!!
★リンクはコメント欄に記載しました.
・NHK「あしたが変わるトリセツショー」に出演します!(1月22日(木)19:30~20:15)
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月18日のFB投稿です**
 標題の番組の「あなたの『しびれ』はどれ? 解消&予防SP」に出演させていただきます.番組では,腱反射やデルマトームを用いた診察の考え方,診断に至るまでのプロセス,「しびれ」を引き起こす代表的な病気とその対応についてお話ししました.さらに,私の「マイハンマー・コレクション」もご覧いただけます(笑).
標題の番組の「あなたの『しびれ』はどれ? 解消&予防SP」に出演させていただきます.番組では,腱反射やデルマトームを用いた診察の考え方,診断に至るまでのプロセス,「しびれ」を引き起こす代表的な病気とその対応についてお話ししました.さらに,私の「マイハンマー・コレクション」もご覧いただけます(笑).
番組のために制作された「しびれ図鑑(写真)」は,一般の方にとってはもちろん,医療者にとっても参考になる内容かもしれません.収録では,ゲストのいとうあさこさん,ダチョウ倶楽部の肥後克広さんとも楽しくやり取りさせていただきました.
私自身も今回の出演を通して,「しびれ」やデルマトームの歴史について改めて学ぶ機会を得ることができ,大変有意義な経験となりました.
ぜひご覧ください.
放送は1月22日(木)19:30~20:15です.
番組案内へのリンクはコメント欄をご覧ください.
・NHK『#あしたが変わるトリセツショー』で「しびれ」の原因と対策をご紹介しました!
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月23日のFB投稿です**
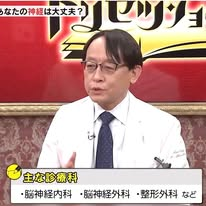 1月22日に放送された「あしたが変わるトリセツショー」に出演いたしました.今回のテーマは「あなたの『しびれ』はどれ?解消&予防SP」でしたが,ご覧いただけましたでしょうか.
1月22日に放送された「あしたが変わるトリセツショー」に出演いたしました.今回のテーマは「あなたの『しびれ』はどれ?解消&予防SP」でしたが,ご覧いただけましたでしょうか.
「しびれ」という症状は,「年のせいだから」「よくあることだから」と見過ごされがちですが,番組でもお伝えしたように,「神経のSOS」であり,その背景で神経のダメージが静かに進行している場合があります.放置せずに原因を考えることが大切です.
番組では,診察方法としびれの成り立ち,予防や対策として,注意すべきポイントや体幹を意識的に使う「ドローイン」の方法についても紹介されています.診察のなかでは私のハンマーコレクションもご覧いただきました.ちなみに斧型のハンマーはあまり見かけない形状ですが,ドイツのシャリテ病院で購入したベルリナー型というものです.
そして,ぜひご活用いただきたいのが,番組内で作成した「#しびれ図鑑」です.しびれの原因や考え方,対策が分かりやすく整理されており,ご自身の症状を理解する手がかりとして有用です.一般のかたはもちろん,医療者にとっても役に立つのではないかと思います.この「しびれ図鑑」は,番組ホームページ下部の「よくあるご質問」コーナーからダウンロードできます(リンクはコメント欄にあります).
日々の健康管理の一助として,ぜひお役立ていただければ幸いです.
・なぜがん患者さんではアルツハイマー病が少ないのか?―腫瘍由来シスタチンCとTREM2が示した新しい道筋―
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月24日のFB投稿です**
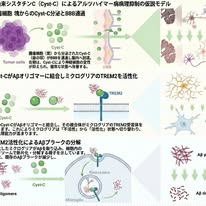 長年にわたり,がんとアルツハイマー病(AD)が同一人物に併存することは稀であるとされており,一方の疾患が他方に対して何らかの防御的効果をもつのではないかという仮説が議論されてきました.疫学的にも,がん既往がAD発症リスク低下と関連する可能性が示唆されてきましたが,その背景にある生物学的機序は不明でした.今回,中国の研究チームは,腫瘍が分泌するシスタチンCが血液脳関門(BBB)を越えてミクログリアを活性化し,アミロイドβ(Aβ)プラークを減らしうる,という機序をマウスで提示しています.
長年にわたり,がんとアルツハイマー病(AD)が同一人物に併存することは稀であるとされており,一方の疾患が他方に対して何らかの防御的効果をもつのではないかという仮説が議論されてきました.疫学的にも,がん既往がAD発症リスク低下と関連する可能性が示唆されてきましたが,その背景にある生物学的機序は不明でした.今回,中国の研究チームは,腫瘍が分泌するシスタチンCが血液脳関門(BBB)を越えてミクログリアを活性化し,アミロイドβ(Aβ)プラークを減らしうる,という機序をマウスで提示しています.
著者らはADモデルマウスに,ヒト由来の腫瘍(肺がん,前立腺がん,結腸がん)を移植してがん状態にすると,脳内のプラーク形成が抑えられ,認知機能も改善する,という現象をまず確認しました.次に,腫瘍細胞が分泌する多様なタンパク質のうち,BBBを越えて脳内に到達しうる候補を絞り込んだ結果,シスタチンC(Cyst-C)を同定しました.そして腫瘍由来Cyst-CがAβ凝集体,とくに毒性が高いとされるAβオリゴマーに結合し,ミクログリア表面受容体TREM2を介してミクログリアを活性化させ,プラークを取り込み,細胞内で分解へ導くという一連の流れが示されました.著者らは,この効果がTREM2依存性であることを検証しています.具体的には,ミクログリア特異的なTREM2欠損(Cx3cr1による細胞型特異的欠損)では効果が消失し,ヒトでADリスク上昇と関連するTREM2のR47H変異を導入した場合も,TREM2の応答性が低下するため,ミクログリア活性化が十分に起こらず,プラーク減少などの効果は同様に認められません.さらに,Cyst-CにL68Q変異を導入して機能を低下させると,Aβオリゴマーへの結合やTREM2活性化が十分に起こらず,プラーク分解促進などの効果は消失しました.
図は,この機序を3段階で視覚化しています.まず腫瘍細胞(紫)からCyst-C(緑)が分泌され,BBBを通過して脳へ到達します.次にCyst-CがAβオリゴマー(赤紫)に結合し,その複合体がミクログリア表面のTREM2(青)に関与してミクログリアを「Inactive」から「Active」へ切り替えます.最後に活性化したミクログリアがAβを取り込み,細胞内(図ではエンドソーム)で断片化して分解へ導き,結果としてAβプラークが減少する,という流れです.つまり,少なくともこのモデルでは,がんはAβの産生を抑制するのではなく,「すでに存在するプラークを分解する」ということです.
この研究の最も大きな臨床的意義は,末梢臓器のがんが,分泌因子を介して脳内免疫に影響を与えるというcancer neuroscience的な視点が,ADの治療可能性につながるかもしれないという点です.ただしTREM2経路はすでに創薬標的として注目され,活性化分子の臨床試験も進んでいる一方で,現時点では結果が一様ではありません.これは病期などを考慮したより精密な臨床試験デザインの必要性を示しているのかも知れません.
もちろん,本研究は主としてマウスモデルでの検証であり,ヒトにおいて同等の現象がどの条件で再現されるかは未確定です.疫学的検討も,がんで先に亡くなること,抗がん治療に伴う認知障害がAD診断を複雑にすることなど交絡が多く,単純には結論できません.それでもなお,「腫瘍が分泌するCyst-Cという末梢因子が,脳内でAβ凝集体とミクログリアTREM2をつなぎ,既存プラーク分解を促進する」という仮説は,AD治療を発展させるかもしれないという期待をもたらすものだと思いました.
Li X,et al.Peripheral cancer attenuates amyloid pathology in Alzheimer’s disease via cystatin-c activation of TREM2.Cell.2026年1月22日(リンクはコメント欄).
・自己免疫性小脳失調症の新規抗体TMEM132A抗体を同定しました!
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月26日のFB投稿です**
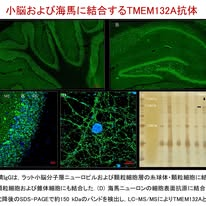 最近,抗体関連神経疾患(自己免疫性脳炎および傍腫瘍性神経症候群)1,140例を検討したオランダの後ろ向き観察研究で,運動異常症は全体の42%に認められ,最も多いものは小脳性運動失調(51%)であったと報告されています(PMID: 41270249).よって孤発性の小脳性運動失調症では抗体関連神経疾患は重要な鑑別診断の一つと考えられます.このような抗小脳抗体は少なくとも31種類同定されていますが,当科の検討ではこれら既知の抗小脳抗体が検出されないものの,免疫組織化学(ラット脳切片)では未知の抗小脳抗体の存在が示唆され,かつ免疫療法が有効な小脳性運動失調症患者が少なからず存在します.その診断の鍵のひとつとなるのが抗小脳抗体の同定です.
最近,抗体関連神経疾患(自己免疫性脳炎および傍腫瘍性神経症候群)1,140例を検討したオランダの後ろ向き観察研究で,運動異常症は全体の42%に認められ,最も多いものは小脳性運動失調(51%)であったと報告されています(PMID: 41270249).よって孤発性の小脳性運動失調症では抗体関連神経疾患は重要な鑑別診断の一つと考えられます.このような抗小脳抗体は少なくとも31種類同定されていますが,当科の検討ではこれら既知の抗小脳抗体が検出されないものの,免疫組織化学(ラット脳切片)では未知の抗小脳抗体の存在が示唆され,かつ免疫療法が有効な小脳性運動失調症患者が少なからず存在します.その診断の鍵のひとつとなるのが抗小脳抗体の同定です.
今回,当科の木村暁夫先生を中心とする研究グループは,自己免疫性小脳失調症に関連する新たな自己抗体として,TMEM132A(transmembrane protein family 132A)に対するIgG抗体を同定し,その臨床的特徴を報告しました.本研究は,生理学研究所,名古屋大学,秋田大学,山梨大学,北海道大学といった複数の施設との共同研究として行いました.当科では新たな抗小脳抗体を発見し,治療可能な症例を見出すことを重要な達成目標として取り組んできましたが,その最初の報告となります.
研究の出発点となったのは,原因不明の小脳性運動失調患者1例の血清が,ラット脳組織に対して特徴的な免疫染色パターンを示したことでした.この患者血清IgGは,小脳分子層のニューロピルや顆粒細胞層の顆粒(図1A,C),さらに海馬の顆粒細胞および錐体細胞と強く反応しました(図1B).つまり,「小脳優位だが,小脳に限局しない神経細胞表面抗原」が標的となっている可能性を強く示唆します.さらに,培養ラット海馬神経細胞を用いた解析では,生細胞の細胞表面に患者IgGが結合することが確認され(図1D),抗体が細胞内抗原ではなく,病原性を持ち得る細胞表面抗原を認識している点が重要です.図1Eの後半には,約150 kDaの蛋白バンドが患者血清によって特異的に免疫沈降されている様子が示されており,本抗体が偶発的な反応ではなく,分子レベルで同定された新規自己抗体であることを視覚的に裏付けています.
さらに,cell-based assayシステムを構築し,TMEM132A抗体の特異性を検討しました.その結果,436例の小脳性運動失調症患者のうち2例でTMEM132A-IgGが検出され,自己免疫性脳炎,多系統萎縮症,多発性硬化症,NMOSD,パーキンソン病,MOG抗体関連疾患,健常対照では一切検出されませんでした.このことから,TMEM132A-IgGは小脳性運動失調症に比較的特異的な自己抗体である可能性が示されました.
抗体陽性の2例はいずれも,進行性の小脳性運動失調を主徴とし,錐体路徴候を合併していました.脳脊髄液検査では蛋白上昇(細胞数正常)が認められ,1例ではオリゴクローナルバンド陽性でした.画像所見として注目されるのが図2です.1例では小脳萎縮が認められ,もう1例では両側下オリーブ核のT2高信号および仮性肥大を認めました.これは歯状核―赤核―下オリーブ核を結ぶMollaret三角の二次性変化(trans-synaptic degeneration)を反映する所見であり,小脳変性だけでは説明しにくい病態が存在することを示唆しています.
免疫学的には,TMEM132A-IgGのサブクラスに多様性が認められ,1例はIgG4優位,もう1例はIgG3優位でした.IgG4関連自己免疫疾患では,病気の初期には炎症を起こしやすいIgG1やIgG3が主体で,病気が長引くにつれてIgG4が増えてくることが知られています.この現象は「サブクラススイッチ」と呼ばれ,免疫反応の性質が時間とともに変化していることを意味します.本研究で,TMEM132A抗体がIgG3優位の症例とIgG4優位の症例に分かれていたことは,患者ごとに病気の時期や免疫反応の段階が異なっていた可能性を示唆しています.つまり,同じTMEM132A抗体でも,発症早期か慢性期かによって抗体の性質が変わっているのかもしれない,という解釈になります.ただし,TMEM132A-IgGが直接的に神経障害を引き起こす病原性抗体であるかどうかについては,現時点では結論づけられていません.
ちなみにTMEM132Aは,小脳を含む中枢神経系に強く発現する膜タンパク質で,小胞体・ゴルジ体から形質細胞膜表面へ移行します.細胞外には免疫グロブリン様ドメインを持ち,細胞接着因子として機能する可能性があります.機能的には,Wnt/β-cateninシグナルをはじめとする細胞内シグナル調節に関与し,細胞の増殖・分化・生存に影響を与えます.遺伝子改変マウスでは,二分脊椎や尾部欠損などの発生異常が報告されており,TMEM132Aが神経発生と維持に重要な役割を担う分子であることが示唆されています.
本研究は症例数が2例と少なく,免疫療法の有効性を前向きに検証できていないという限界はあります.しかし論文投稿後,さらに4例の追加症例を確認しています.今後,さらに多数例での検討が必要ですが,本抗体は自己免疫性小脳失調症の重要な抗体のひとつになる可能性があります.
★論文は50日間(3月11日まで),下記のリンクより無料でダウンロード可能です.
Kimura A, Takekoshi A, Miyazaki Y, Oh-Hashi K, Kamada S, Taguchi Y, Sugawara M, Watanabe T, Ueno Y, Yaguchi H, Yabe I, Fukata Y, Fukata M, Shimohata T. TMEM132A autoimmunity in patients with suspected autoimmune cerebellar ataxia. J Neuroimmunol. 2026 Jan 14;413:578867. PMID: 41564469.
論文へのリンク
https://authors.elsevier.com/c/1mTlJbfPjUciV
・IgLON5抗体関連疾患は,なんと「核」から始まる!! ― 抗体の神経細胞への結合が核内タウ異常を引き起こす
**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月28日のFB投稿です**
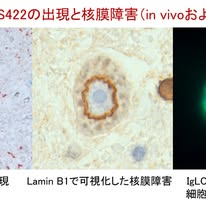 IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎と神経変性疾患の境界に位置づけられる,稀ながらきわめて重要な神経疾患です.IgLON5抗体が存在し,臨床的には球麻痺,REMおよびnon-REMパラソムニア,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)様の運動障害,自律神経障害,認知機能障害など多彩な症状を呈します.診断が遅れやすく,治療開始が遅延すると予後不良となることが知られており,さらに本症がタウオパチーでもあることから,その病態解明は神経学における重要な課題の一つです.
IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎と神経変性疾患の境界に位置づけられる,稀ながらきわめて重要な神経疾患です.IgLON5抗体が存在し,臨床的には球麻痺,REMおよびnon-REMパラソムニア,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)様の運動障害,自律神経障害,認知機能障害など多彩な症状を呈します.診断が遅れやすく,治療開始が遅延すると予後不良となることが知られており,さらに本症がタウオパチーでもあることから,その病態解明は神経学における重要な課題の一つです.
今回紹介する論文は,オーストリア・ウィーン医科大学を中心とする欧州多施設共同研究であり,IgLON5抗体関連疾患におけるタウ病理がどのように始まり,どのような順序で進行するのかを,剖検脳と培養細胞の両面から詳細に解析したものです.
著者らは,罹病期間6~180か月の剖検例14例を対象に,延髄を中心とした免疫組織化学解析を行い,PSP様症例および対照例を比較しました.本研究の特徴は,従来のAT8抗体に依存した評価にとどまらず,表に示される13種類の抗タウ抗体を用いて,タウ蛋白の翻訳後修飾を包括的かつ徹底的に解析した点にあります.これにより,タウ病理の「存在」だけでなく,「どの分子変化が,どの順序で出現するのか」という時間軸が初めて明確に描き出されました.
その結果,IgLON5抗体関連疾患において最も早期に出現するタウ異常は,従来広く用いられてきたAT8抗体で検出される細胞質タウではなく,Ser422リン酸化タウ(pTauS422)であることが明らかになりました.しかもこのpTauS422は,神経細胞の細胞質ではなく,核内に局在する!という予想外の特徴を示していました.従来,タウ病理は細胞質や神経突起に蓄積するものと考えられてきましたが,本症では神経変性の最初の舞台が「核」である可能性が示されたのです.
この点を最も分かりやすく示しているのが,Brain誌のX(旧Twitter)で紹介された図です.延髄の神経細胞では,核の輪郭が滑らかさを失い,波状に歪んだ形態を呈していました.これはLamin B1染色により可視化された核膜の陥入やcrenellation(城壁の胸壁のようなギザギザを意味する)と呼ばれる変形であり,AT8ではほとんどタウ沈着が認められない,病理学的に最も早期の段階から出現していました.
さらに,IgLON5抗体を添加したラット海馬神経細胞培養でも,同様の核膜異常が再現されており,自己抗体そのものが神経細胞核に直接的な障害を与え得ることが示されています.加えて重要なのは,神経細胞表面にIgG4,すなわちIgLON5抗体が結合している細胞に限って,その核内に最初のタウ異常であるpTauS422が出現していた点です.これは,抗体が神経細胞に結合すること自体が,核内タウ異常を引き起こす引き金となっている可能性を強く示唆します.
一方,病期が進行すると,AT8,AT180,PHF-1などで検出される細胞質タウや神経突起内タウが増加し,さらに後期には4Rタウに加えて一部3Rタウやタウのアセチル化も認められるようになります.これらの変化は,表に示す抗体を用いた解析によって一貫した時間依存的進行として示されており,本症が免疫機序を起点として進行するタウオパチーであることを分子レベルで裏付けています.
また,本研究ではCD8陽性T細胞の浸潤についても検討されていますが,本症とPSPとの間に大きな差は認められませんでした.この結果は,IgLON5抗体関連疾患の病態形成において,細胞性免疫よりも液性免疫が中心的役割を果たしている可能性を支持するものです.
本研究は,IgLON5抗体関連疾患が,自己免疫を起点として神経細胞核の障害が生じ,その後に不可逆的なタウ蓄積と神経変性へと進展する疾患であることを明確に示しました.とくに重要なのは,AT8陰性であっても核内pTauS422や核膜異常がすでに存在するという点です.これは,「AT8陰性=タウ病理なし」という従来の前提では,治療可能な初期病変を見逃してしまう可能性があることを意味します.本研究の知見は,IgLON5抗体関連疾患にとどまらず,アルツハイマー病を含む他のタウオパチーの初期病態を考えるうえでも,大きな示唆を与えるのではないかと思いました.
Reinecke R, et al. Brainstem pathology in anti-IgLON5 disease: new insights into early events and tau progression. Brain. 2026 Jan 17: awag015. PMID: 41544664.
3. 特別企画:AIに訊く
(第1回)CES2026での「ヘルスケア分野」「PW関連」発表についてAIに訊く。
**AIの回答は全てが正しいとは限りません。が、AIは大いに便利です。回答の真偽判定は、必要とあれば、読者ご自身で検証下さい**
3-1)「ヘルスケア分野」の発表についてのCopilotとの会話(2026年1月8日実施)
Q1;ラスベガスで開催されているCES2026で発表されたヘルスケア分野での注目すべき発表を教えてください。
A1;CES 2026 のヘルスケア分野では、AI・非接触センシング・女性の健康・メンタルケアといったテーマが特に大きく進化しており、医療の未来を示す革新的な発表が多数登場しています。以下に、信頼できる情報源に基づき、注目ポイントをわかりやすく整理して紹介します。
🌐 CES 2026 ヘルスケア分野の注目発表まとめ
(1)AI × バーチャルツインによる認知症・アルツハイマーケア革命
ダッソー・システムズ(Dassault Systèmes)が、 AI・バーチャルツイン・リアルタイムセンシングを融合した次世代の「ヘルスケア・オペレーティング・システム」を発表。
主なポイント
• 患者のバーチャルツインを作成し、診断・治療・研究を仮想空間で実行
• 認知症・アルツハイマー病の進行予測や個別化医療を強化
• 没入型展示「Step Inside Alzheimer’s」で体験可能
→ 医療機関中心から“患者中心”の医療へと大きくシフトする象徴的発表。
(2)非接触・非侵襲の健康モニタリング技術が進化
韓国 DolbomDream の Carearly が注目。
特徴
• ベッドに設置するだけで心拍・呼吸・動き・転倒を常時モニタリング
• 独自の Pneumatic Ballistocardiography(P-BCG) 技術で 最大98%の精度
• 皮膚接触不要で高齢者ケアや在宅医療に最適
→ 高齢化社会に向けた“見守りテクノロジー”の新基準。
(3)女性の健康(FemTech)が大きく存在感を発揮
Euronews が紹介した注目製品:
代表例
• スマート月経パッド
o 体調データをリアルタイムで取得し、周期管理や健康分析に活用
• アレルギー対策デバイス
• LED 美容マスク(肌状態に応じて光を最適化)
→ 女性の健康を可視化し、セルフケアを高度化する製品が多数登場。
(4)メンタルヘルス × テクノロジーの新潮流
Euronews が紹介した “メンタルヘルスポッド” が話題。
特徴
• ゼログラビティ姿勢でリラクゼーション
• マッサージ+自然音で深いリラックスを誘導
• ストレス軽減やメンタルケアを目的とした新しい体験型デバイス
→ メンタルヘルスを“体験型テクノロジー”で支援する新しいアプローチ。
(5)ウェアラブル & パーソナルヘルスの進化
ZDNET の現地レポートでは、以下のような新型ウェアラブルが多数紹介:
トレンド
• より精度の高いバイタル測定
• ランニング・睡眠・ストレス管理の高度化
• 生活習慣病予防を目的とした AI コーチング機能
→ “健康の自己管理”を支えるウェアラブルがさらに進化。
(6)デジタルヘルスサミットの拡大(AI・女性の健康・ウェアラブル)
CES 公式サイトによると、2026年はデジタルヘルスプログラムが大幅に拡大。
注目テーマ
• AI による精密医療
• 女性の健康
• 次世代ウェアラブル
• テレヘルスの進化
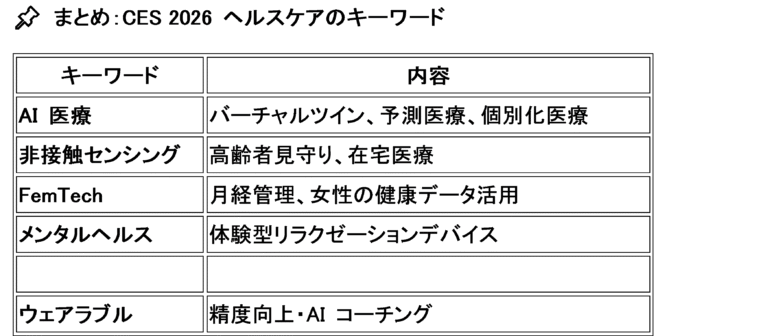 必要であれば、分野別の深掘り解説や、日本市場への影響予測もまとめます。どの分野に興味がありますか?
必要であれば、分野別の深掘り解説や、日本市場への影響予測もまとめます。どの分野に興味がありますか?
Q2;日本市場への影響予測を教えてください。
A2;日本市場への影響を考えると、CES 2026 のヘルスケア系トレンドは「日本の課題(超高齢社会・医療人材不足・女性の健康ニーズ・医療費抑制)」にかなり直結しています。ここから数年の日本のデジタルヘルスの方向性をかなり左右する内容です。
全体像:日本で起こりそうな大きな変化
• 在宅・遠隔モニタリングが一気に“当たり前の選択肢”になる
• AI を前提にした医療・介護サービス設計が加速
• FemTech(女性の健康)とメンタルケアが明確な成長市場として位置づけられる
• 「機器を売る」から「データ+サービスを継続課金で売る」ビジネスへシフト
日本のデジタルヘルス市場は、すでに 2024–2029 年で年平均成長率約 8.8% と予測されており、2029 年には約 126.5 億ドル規模になる見込みです。 CES で出てきた技術は、この成長を単に「加速」させるだけでなく、どの分野にお金と人が集まるかを方向づけるイメージに近いです。
(1)非接触・在宅モニタリング:高齢者ケアの“新標準”候補
影響が一番強いのはここです。
• 在宅介護・施設介護向けの見守りソリューション需要が急拡大
o 日本は世界一の高齢化国家で、80歳以上が人口の 1/10 超と言われる状況です。
o ベッド下に敷くだけ・センサーを置くだけで心拍・呼吸・転倒を検知するような技術は、 「人手不足を技術で埋める」現場ニーズに直撃します。
• 介護施設・病院での人員配置の見直し
o 夜勤帯の見回り回数を減らしつつ、異常はむしろ早く検知できるようになる。
o これにより「人がやる仕事」と「センサーに任せる仕事」の線引きが明確になっていく。
• 在宅医療・訪問看護との連携
o センサーからのデータがクラウドに集約され、訪問前に状態を把握して効率的な訪問計画が可能に。
o 日本で進んでいる遠隔モニタリングやデジタル療法の流れとも相性が良いです。
日本では、デジタルヘルスは「高齢社会の打開策」として位置づけられつつあり、リモートモニタリングは特に有望分野と分析されています。
(2)AI・バーチャルツイン医療:病院経営と製薬・研究側に大きなインパクト
• 病院向け:AI を活用した診断支援・治療計画のシステム導入が進む
o 日本は患者数増加と医師不足が並行して進んでおり、「医師の負担軽減+アウトカム向上」のために AI 支援は避けられない流れ。
o バーチャルツイン的な「患者デジタルモデル」による治療シミュレーションは、がん・循環器・脳神経領域などで特に関心を集めそうです。
• 製薬・医療機器メーカー:治験や製品設計プロセスのデジタル化
o シミュレーションやデジタルツインを活用した試験は、コスト削減・開発期間短縮に直結。
• 規制との距離はまだあるが、“方向性”としては既に折り込み済み
o 日本では Software as a Medical Device(SaMD)など、ソフトウェア医療機器の活用が今まさに拡大段階。
o CES 発の AI ソリューションは、そのまま入ってくるというより、 「日本ローカルの規制や医療慣行に合わせた再設計」が必要になります。
(3)FemTech:日本の「見えていなかった巨大市場」を掘り起こす
• 市場としてのポテンシャルはかなり大きい
o 日本の FemTech 市場は、2026–2033 年にかけて中長期で成長が見込まれており、 AI を活用したパーソナライズ健康管理が重要テーマになると分析されています。
• 具体的な変化の方向性
o スマート月経パッド、周期・PMS 管理アプリ、妊活・更年期サポートなどの連携が進む。
o 「月経=体調データ」として扱う文化が浸透すると、産業側もデータ連携を前提にしたサービス設計を進めざるを得ない。
• 日本特有のポイント
o 職場での健康経営・女性活躍の文脈(生理・更年期のオープンな取り扱い)が FemTech 導入を後押しする可能性が高い。
o 一方で、デリケート情報であるため、プライバシー・データ管理に対する不信感をどう解くかが鍵。
(4)メンタルヘルステック:企業・学校・自宅向けに静かに浸透
• ストレス社会の日本と親和性が高い領域
o 日本ではメンタルヘルス不調が大きな社会問題になっており、デジタルヘルスの重点領域の一つです。
• どこから広がりそうか
o 企業の福利厚生:リラクゼーションポッド、バイタル連動ストレスモニタリング、セルフケアアプリなど。
o 学校・大学:集中力向上やストレス軽減を目的としたデバイス・アプリ。
o 高齢者:孤立感・不安感を減らすためのインタラクティブなメンタルケアデバイス。
• ポイント
o 医療行為ではなく「ウェルネス」寄りの領域から浸透しやすい。
o ただし、メンタルヘルスは効果検証や安全性の担保が重要で、 真面目にやる企業ほど医療機関との連携やエビデンスづくりが必要になる段階に入ります。
(5)ビジネスモデルとプレイヤー構図の変化
• ハード単体販売から「サブスク+データサービス」へ
o センサーやウェアラブルは単体よりも、「月額でアプリ・解析・リモート相談がセット」の形が主流になりやすい。
• 日本企業にとってのチャンス
o 高齢者・介護・地域包括ケアなど、日本特有の文脈に最適化した 「ローカル仕様のソフトウェア・サービス」で差別化しやすい。
• 海外スタートアップとの関係
o そのまま日本に持ち込むというより「共同開発・ローカライズ」が現実的。
o 日本側は規制対応・医療機関ネットワーク・販売チャネルを提供し、 海外側はコア技術を提供する形が増えそうです。
(6)日本市場で“本当に起こりそうなこと”をざっくり予測
・2026–2028年ごろ
o 介護施設・病院での非接触見守りシステム導入が加速
o FemTech・メンタルヘルス系 B2C サービスがアプリストア・家電量販店を通じて拡大
o 一部の先進病院が AI 診断支援・バーチャルツイン的ソリューションを試験導入
・2028–2030年ごろ
o 在宅モニタリング+遠隔診療が高齢者向け標準オプションの一つに
o FemTech が「ヘルスケアの一分野」として当たり前に語られる
o 保険会社・自治体がデジタルヘルスデータを活用した予防施策を本格展開
もしあなたが日本でこの領域に関わっている(or 関わろうとしている)なら、
• 高齢者向け在宅モニタリング
• 女性の健康データ活用(FemTech)
• メンタルウェルネス × デジタル
このあたりは、ここ数年で「必ず波が来る」ゾーンです。 興味があるのは、医療機関寄り・介護寄り・B2C アプリ寄り・企業向け福利厚生など、どのあたりですか? そこに絞って、もう少し具体的なビジネスやキャリアの話にも落とし込めます。
3-2)「PW関連」発表についてのCopilotとの会話(2026年1月10日実施)
Q1;一昨日に続けて、CES2026について訊きたい。高齢者の健康増進や歩行のリハビリに取り入れられているポールウォーキングを実践する際に役立ちそうな内容の発表と、ポールウォーキングを指導する際に役立ちそうな内容の発表があれば教えてください。
A1;以下は CES 2026 の公式発表・現地レポート(検索結果)に基づき、 ①ポールウォーキングを実践する高齢者に役立つ発表 と ②ポールウォーキングを指導する専門家に役立つ発表 を “実際に CES2026 で報じられた技術” に限定して整理した内容です。
⭐結論(要点)
CES 2026 では「歩行アシスト」「歩行解析」「高齢者のモビリティ支援」に関する発表が非常に多く、ポールウォーキングの実践・指導の両方に応用できる技術が複数登場しました。特に、歩行を補助するウェアラブルロボット(WIM S、Dephy Sidekick、Sumbu Exo-S3)や、AI による歩行データ解析技術は、ポールウォーキングの効果測定や安全性向上に直結します。
🧓① ポールウォーキングを実践する高齢者に役立つ CES2026 技術
(1)歩行アシストウェアラブル(WIM S / WIM KIDS)
• WIRobotics の歩行アシストロボット「WIM S」 が CES2026 で実機デモを実施
• 足腰の弱い高齢者の歩行を補助し、歩幅・安定性を改善
• ポールウォーキングの「姿勢を保つ」「歩幅を広げる」効果と相性が良い
→ ポールウォーキングの“補助具”として活用可能。
(2)Dephy「Sidekick」:歩行を軽くするロボティックアシスト
• PCMag が紹介した Dephy Sidekick は、 歩くたびにかかとを持ち上げてくれる“歩行アシスト外骨格”
• 高齢者の疲労軽減、歩行距離の延伸に効果
• ポールウォーキングの「長く歩く」「坂道を歩く」際に負担を軽減
→ 下肢筋力が弱い高齢者の歩行継続をサポート。
(3)Sumbu Exo-S3:日常生活向けの軽量エクソスケルトン
• Sumbu の Exo-S3 シリーズ は「日常生活で使える軽量 AI エクソスケルトン」
• 不整地(砂利道・坂道)でも歩行を安定化
• ポールウォーキングの屋外活動に最適
→ 転倒リスクの高い高齢者の安全性向上に寄与。
🧑🏫② ポールウォーキングを指導する際に役立つ CES2026 技術
(1)AI × 歩行解析(Exoskeleton 各社のデータ機能)
CES2026 の歩行アシストロボットは、 歩行データ(歩幅・速度・左右差・荷重)をリアルタイムで取得できる機能 を搭載しているものが多い。
例:
• WIM S:歩行パターンの補助とデータ取得
• Dephy Sidekick:歩行の力学データを取得可能
→ ポールウォーキングのフォーム指導に科学的根拠を追加できる。
(2)Xtand:AI によるリハビリ・スポーツ向け動作解析
• Xtand の AI エクソスケルトンは リハビリ・スポーツ向けの動作解析 を強調
• 関節負荷・姿勢・動作効率を可視化
→ ポールウォーキングの「正しい姿勢」「腕振り」「荷重移動」をデータで指導可能。
(3)Assistive Technology(Mobility Management レポート)
Mobility Management の CES2026 レポートでは、 高齢者のモビリティ支援技術が多数紹介
内容例:
• 歩行補助デバイス
• バランス支援
• リハビリ向けウェアラブル
• 高齢者の安全歩行を支援する IoT
→ ポールウォーキング教室での安全管理・リスク評価に応用可能。
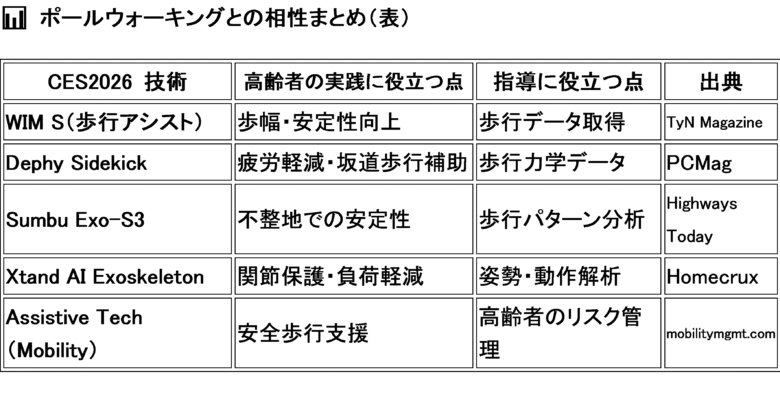 🔍 まとめ
🔍 まとめ
CES2026 の歩行アシスト・エクソスケルトン技術は、 ポールウォーキングの「実践」と「指導」の両方に直接応用できる内容が非常に多い ことがわかりました。
特に:
• 歩行を補助するロボット(WIM S / Sidekick)
• AI による歩行解析(Xtand など)
• 高齢者モビリティ支援技術(Assistive Tech)
これらは、ポールウォーキングの効果を高め、 安全性・継続性・指導の質を向上させる強力なツールになります。
必要であれば、 「ポールウォーキング教室で実際にどう活用できるか」 「高齢者の歩行能力別にどの技術が適しているか」 など、さらに具体的な提案もできます。
関連情報
「ロボティクスに ChatGPT の時代が到来しつつある」とは、NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) が昨年のCES2025で語った言葉ですが、CES2026
は正に『フィジカルAI』時代の到来を告げるものとなっています。ロボット工学分野における「ゲームチェンジャー」と呼ばれるプラットフォーム『NVIDIA Cosmos™ 』のニュースは、「2025年1月のニュース」で取り上げています。
(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)
 ohana ポールウォーキング in モリコロパーク
ohana ポールウォーキング in モリコロパーク 真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡
真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡ ポールウォーキング
ポールウォーキング 午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。
午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。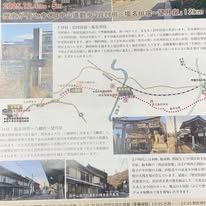 一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww
一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww 屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。
屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。 【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩
【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩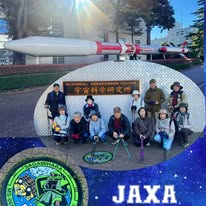 2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①
2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議① 佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。
佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。 神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)
神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ) 今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川
今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川 どっ鯉ポールウォーキング
どっ鯉ポールウォーキング 新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會 【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。
【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。 【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。
【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。 紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。
紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。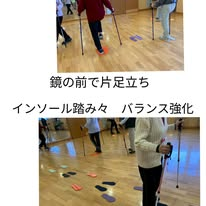 【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜
【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜 鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。
鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。 台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會 【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。
【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。 きのこ頭の愉快な集まり
きのこ頭の愉快な集まり 大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。
大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。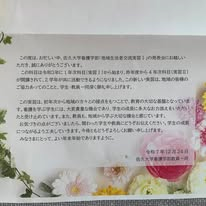 佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。
佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。 クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌
クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌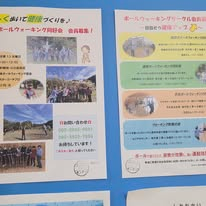 鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。
鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。 【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。
【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。 志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木
志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木 2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年
2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年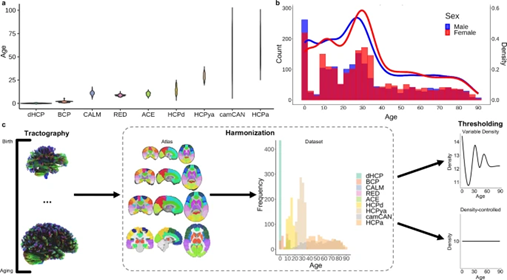 a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。
a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。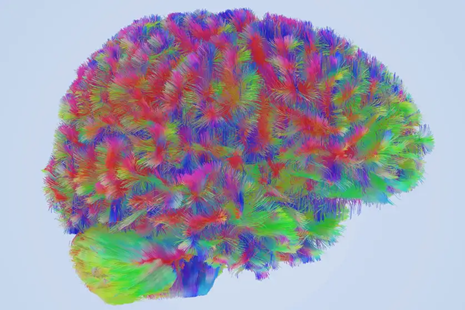 私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する
私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する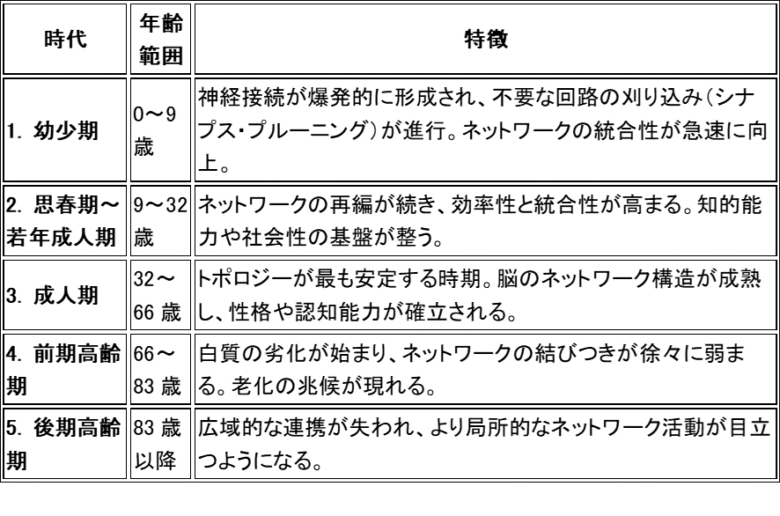 この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?
この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?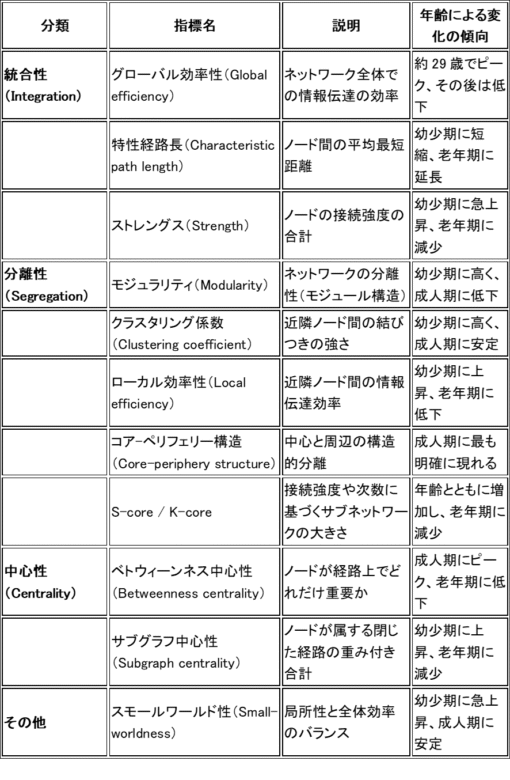 これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。
これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。 われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。
われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。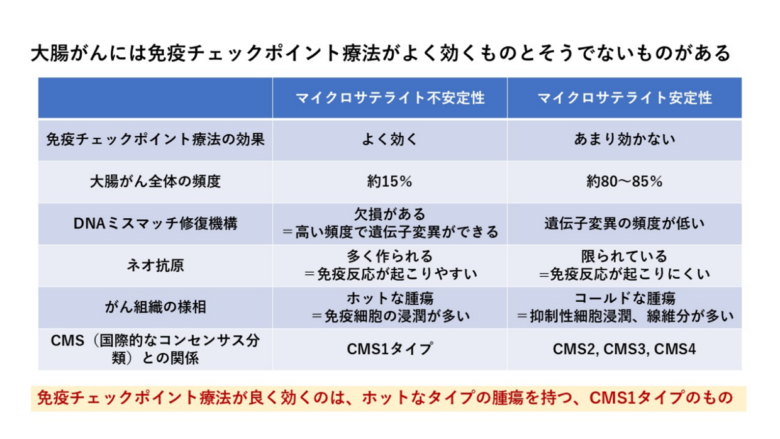 マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。
マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。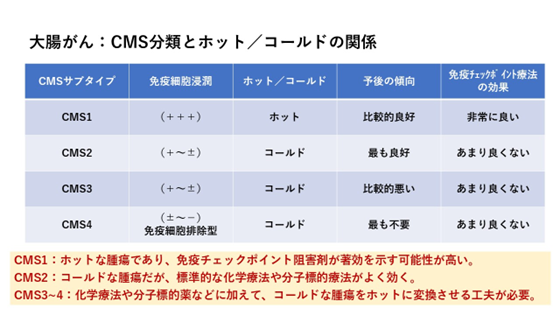 前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。
前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。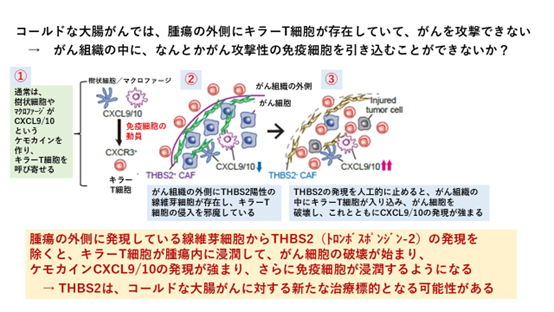 すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。
すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。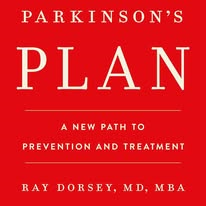 2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.
2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.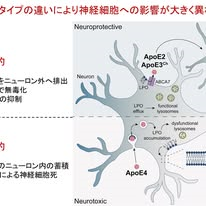 アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.
アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.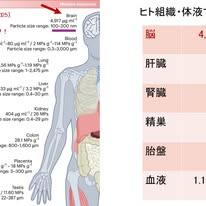 昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.
昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.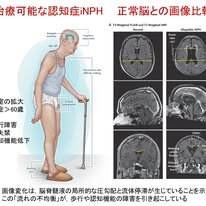 特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.
特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.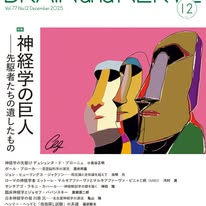 Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.
Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.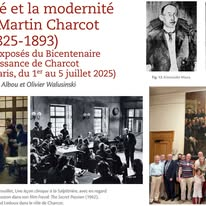 フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては
フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては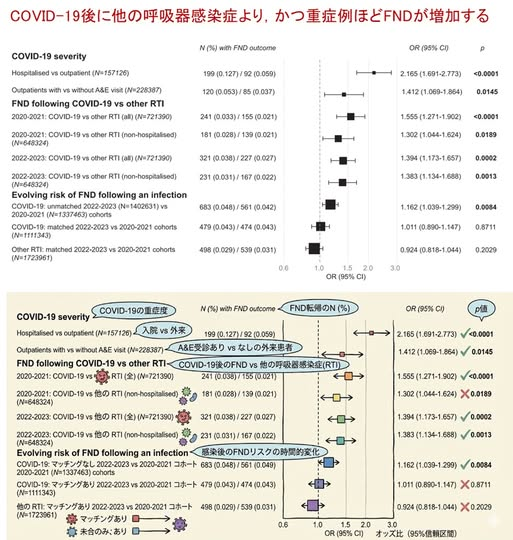
 アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.
アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.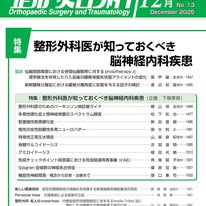 腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.
腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.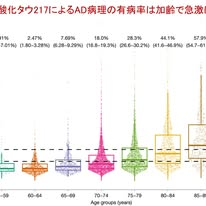 アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.
アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます. 機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.
機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.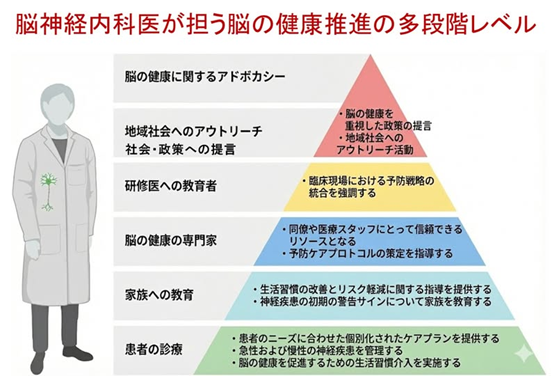
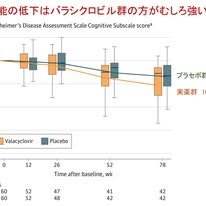 近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.
近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.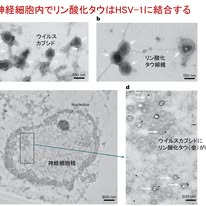 近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.
近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです. 1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.
1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています. 今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。
今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます
#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます 佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。
佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。 前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。
前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。 【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動
【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動 🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶
🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶 20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106
20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106 今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。
今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。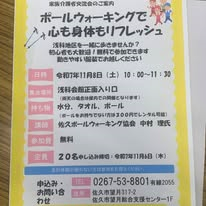 佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️
佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️ 地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。
地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。 【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク
【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。
この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。 2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走
2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走 それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね
それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね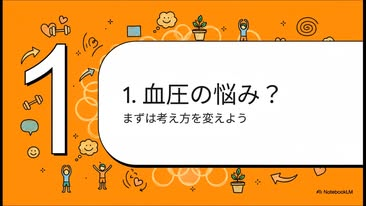 先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM
先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM 2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。
2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。 本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました
本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました 朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。
朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。 【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング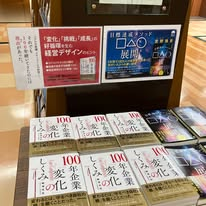 書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ
書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ 本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!
本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください! 大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。
大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。 鎌倉広町緑地でポール歩き
鎌倉広町緑地でポール歩き 【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。
【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。 MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌
MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌 第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。
第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。 11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊
11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊 【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ
【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ 20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘
20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘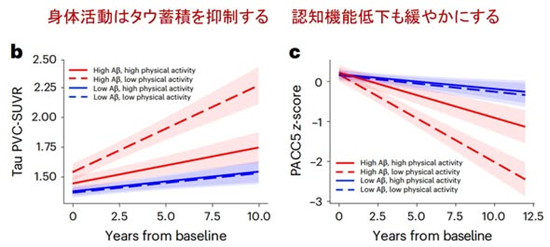
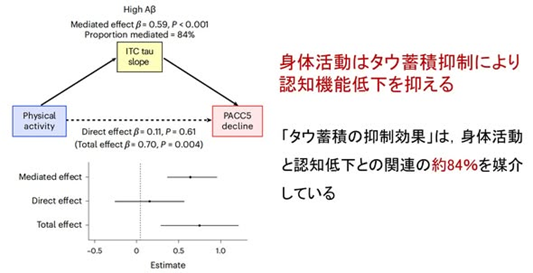 アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.
アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.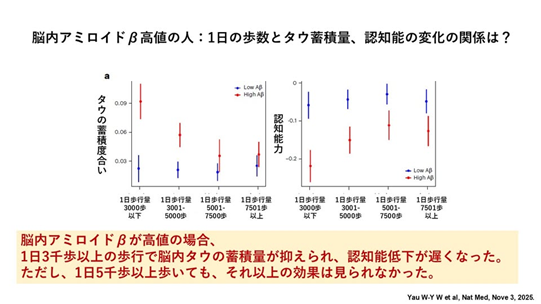 かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。
かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。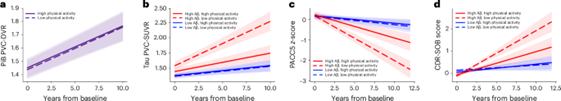 a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。
a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。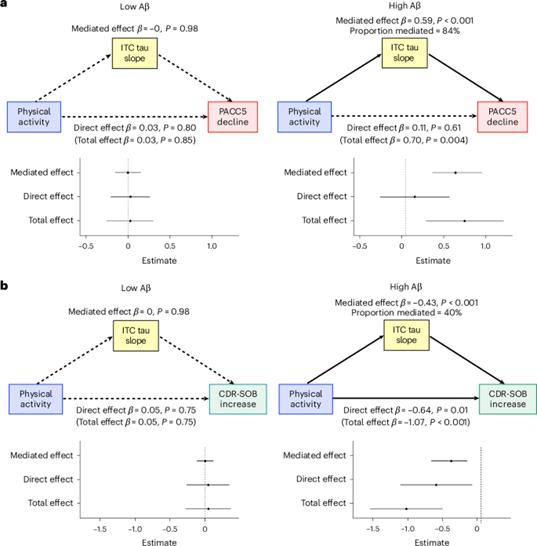 a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。
a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。 a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。
a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。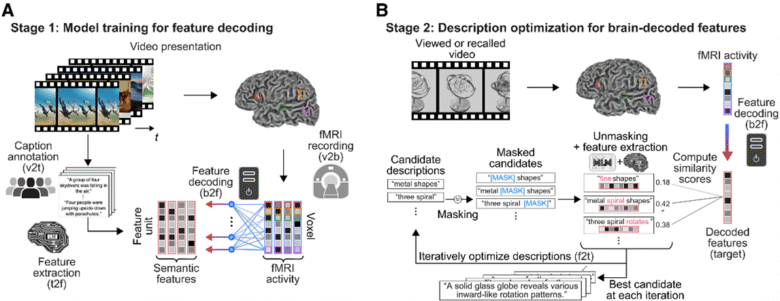 私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
 機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL
機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL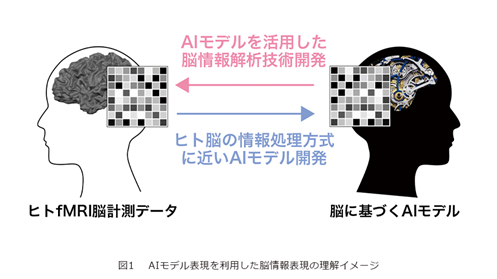
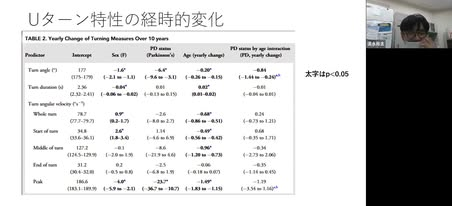 今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.
今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です. 疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.
疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.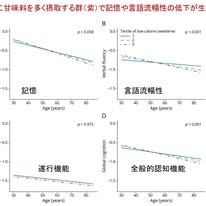 人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.
人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです. 昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.
昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました. ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.
ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.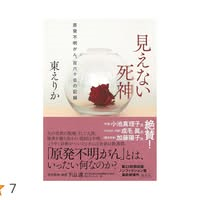 話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.
話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.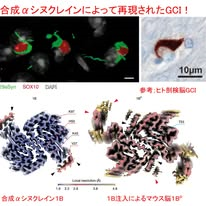 多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.
多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます. 片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.
片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.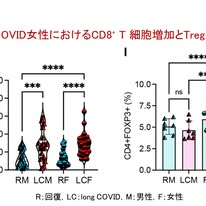 今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.
今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.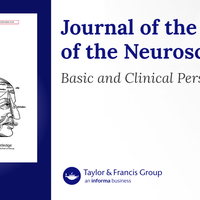 日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.
日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました. 6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.
6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした. 2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).
2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1). 第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.
第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.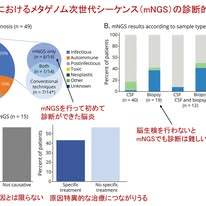 脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.
脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.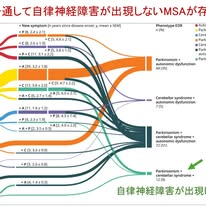 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.
多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.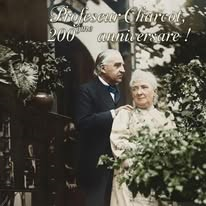 本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.
本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています. 第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。
第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。 【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩
【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩 秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨
秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨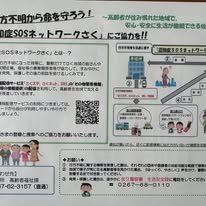 認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。
認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。 ㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。
㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。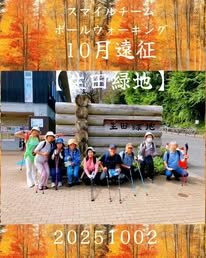 スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館
スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館 今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍
今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍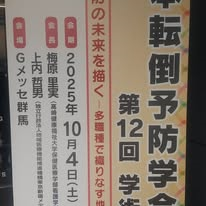 日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️
日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️ 【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会
【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会 佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww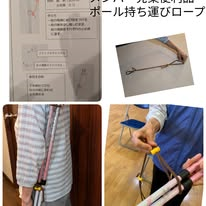 【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ
【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ 清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました
清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット
しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット 2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名
2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名 📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣
📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣 八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く
八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く 今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。
今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。 桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫
桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫ 【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動
【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動 午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡
午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡 佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww 三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。
三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。 10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。
10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。 2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける!
2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける! 一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気!
一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気! 【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング
【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング 秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル
秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル 今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。
今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。 本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝
本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝 2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部
2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部 第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC
第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC 10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊
10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊 月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。
月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。 地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。
地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。 昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭
昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭 今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス
今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス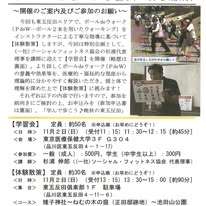 11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。
11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。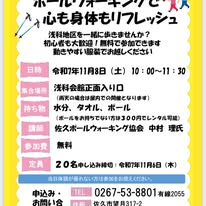 佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。
佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。 🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨
🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨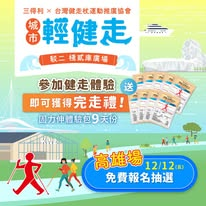 wellness.suntory.com.tw
wellness.suntory.com.tw Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。
Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。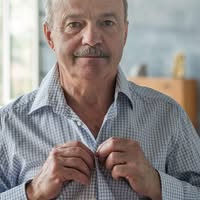 これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。
これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。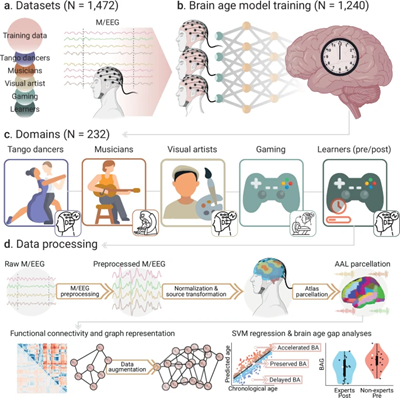 a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。
a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。 タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty
タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty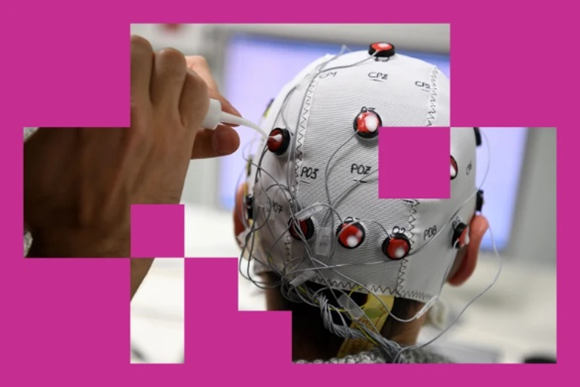 研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty
研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty 英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ
英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ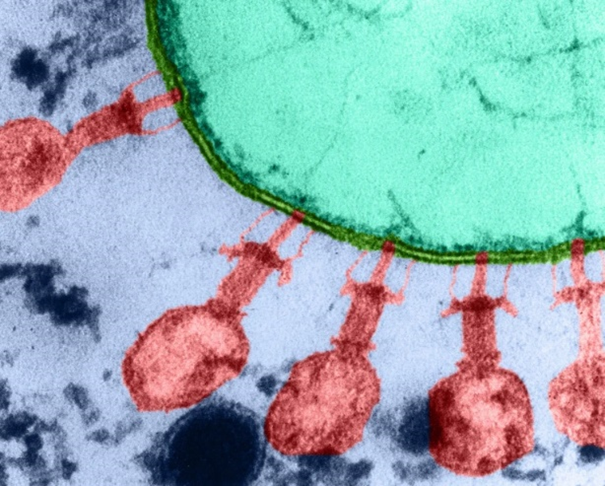 T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。
T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。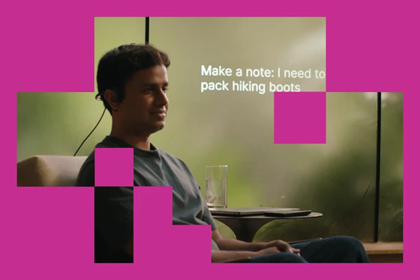 アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ
アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ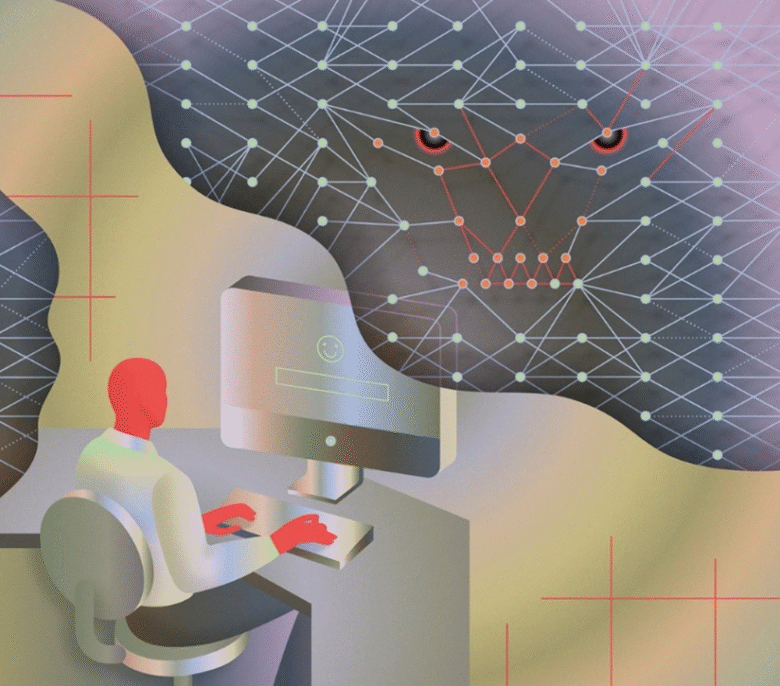 イラスト: アナ・コヴァ
イラスト: アナ・コヴァ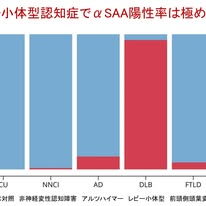 脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.
脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.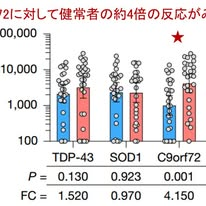 筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.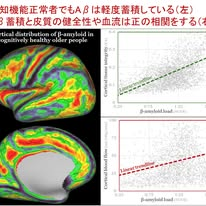 先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.
先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.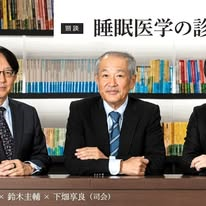 特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました.
特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました. ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.
ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.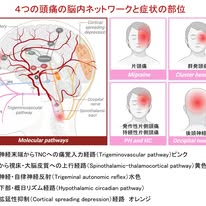 頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.
頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.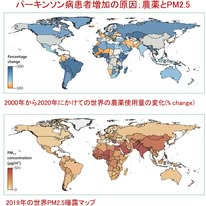 パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.
パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.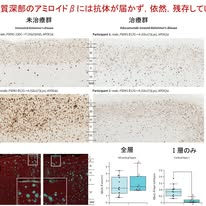 アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.
アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.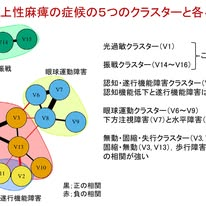 進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.
進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.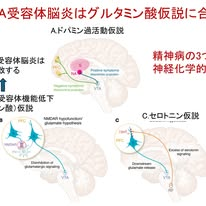 Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.
Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.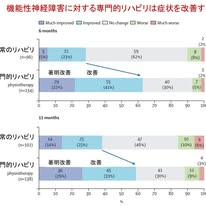 先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.
先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.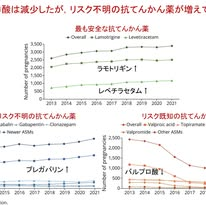 抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました.
抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました. 8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪
8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪ 9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!
9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!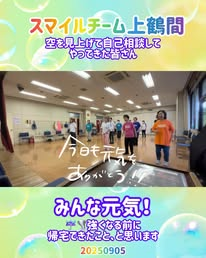 20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️
20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️ meet.google.com
meet.google.com 本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義
本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義 #インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6
#インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6 佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww 本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️
本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️ 2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名
2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名 鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。
鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。 9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊
9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊 【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園
【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園 天気も気まま
天気も気まま 佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^
佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^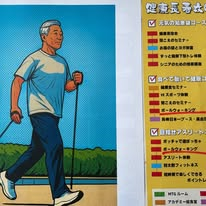 昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。
昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。 9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題
9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題 シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト
シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト 神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。
神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。 台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️
台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️ いつもの秋がやって来ました。@大巧寺
いつもの秋がやって来ました。@大巧寺 第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。
第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。 第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️
第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️ 9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。
9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。 ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。
ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。 ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️
ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️ あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。
あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。 通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践
通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践 介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?
介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?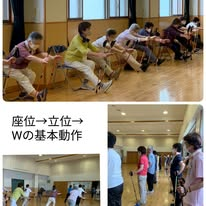 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加
#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加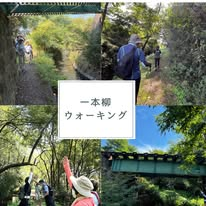 9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊
9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊 日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣
日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣 都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京
都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京 秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ
秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ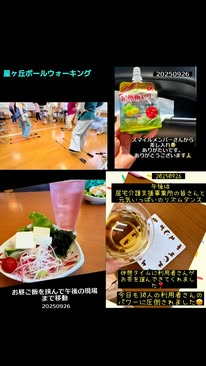 スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926
スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926 9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵
9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵 秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊
秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊 9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。
9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。 【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩
【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩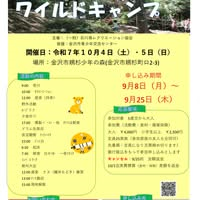 あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会
あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会 写真1件
写真1件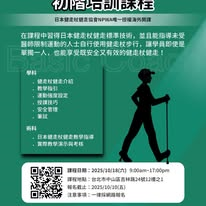 由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~
由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~ 【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地)
【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地) 私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。
私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。 第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内
第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内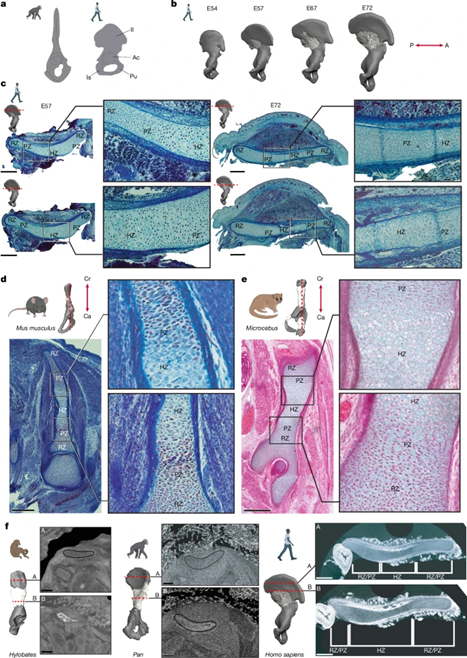 a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。
a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。 腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー
腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー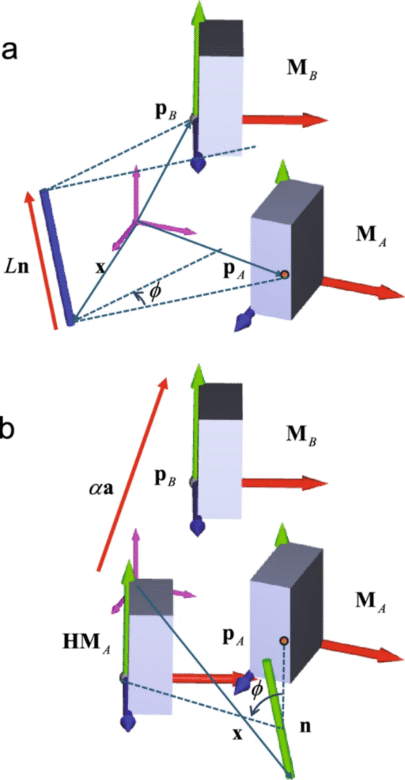 螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋
螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋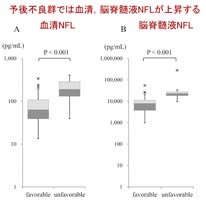 GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.
GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.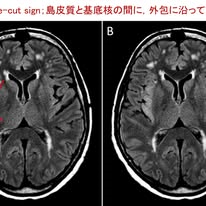 ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています.
ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています. 緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.
緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.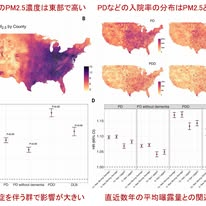 Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.
Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.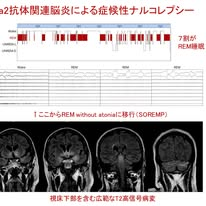 Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.
Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.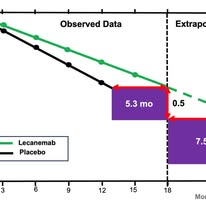 アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.
アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.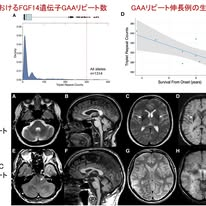 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.
多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.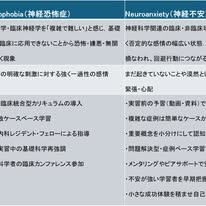 「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.
「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.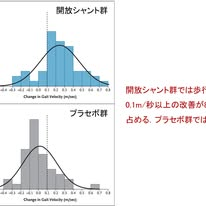 特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.
特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.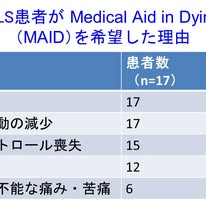 Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.
Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.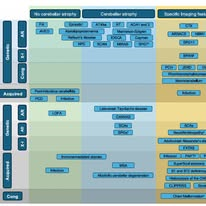 近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.
近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.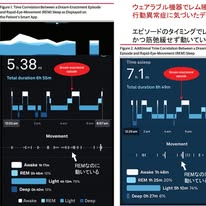 近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.
近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.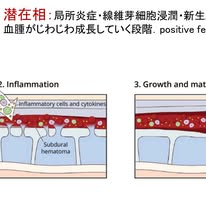 慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています.
慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています. オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.
オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.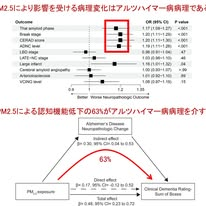 先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました.
先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました. 8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!
8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!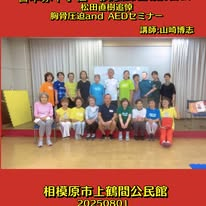 スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801
スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801 佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww 8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。
8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。 鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!
鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool! 8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。
8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。 スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩
スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩 真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。
真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。 🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!
🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來! 昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。
昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。 佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️
佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️ 8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。
8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。 8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!
8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話! 介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸
介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸 8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。
8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。 本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県
本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県 8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊
8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊 8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。
8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。 昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!
昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!! 8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!
8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話! 8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。
8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。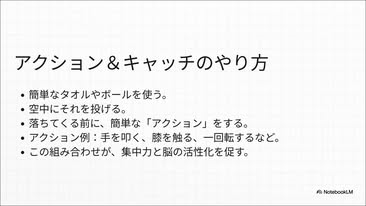 皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。
皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。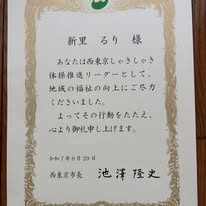 体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。
体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。 写真1件
写真1件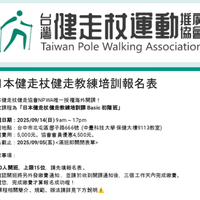 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表 📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!
📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活! 2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部
2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部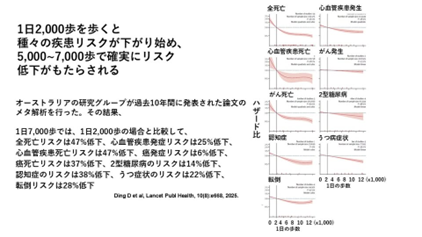 論文
論文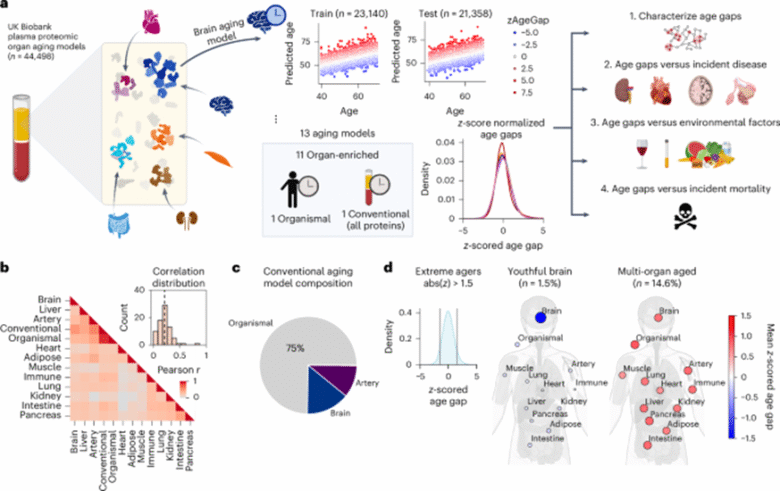 最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。
最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。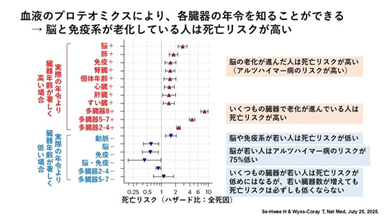 さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。
さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。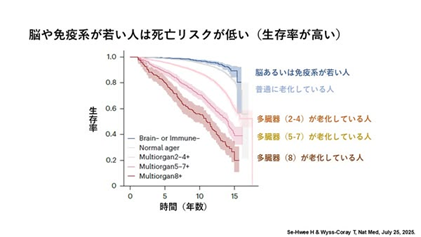 以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。
以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。 先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。
先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。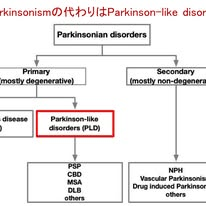 「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.
「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.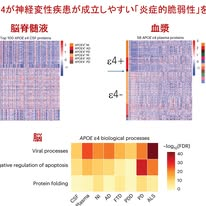 APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.
APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.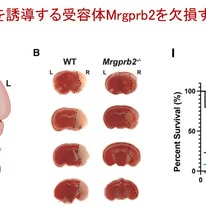 私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.
私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.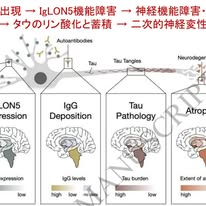 希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.
希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.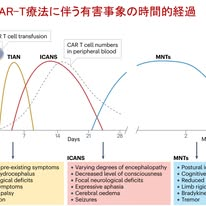 日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.
日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.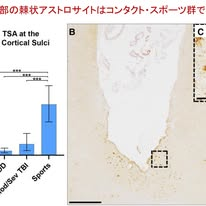 「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.
「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.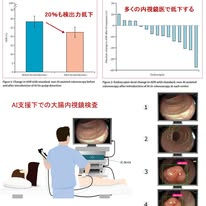 近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.
近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.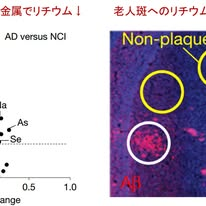 アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.
アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.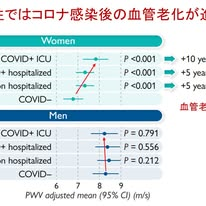 COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.
COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました. 昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.
昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです. アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).
アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります). 標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.
標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.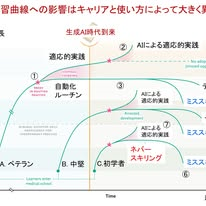 ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.
ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました. 7/1 いよいよ文月です。午後の強烈な雷雨のあとは、涼しくなったように感じました。今朝の火曜サークルは外歩きを変更して室内でポールストレッチ、筋トレのあとは、ステップエクササイズに励みました。少しずつ高さを上げて太股をしっかり上げて1-2、1-2! 徐々に回数も増やし夏休み中の自宅で出来る中強度運動に。 酷暑のため9月まで休暇に皆さん異議なし! 我が家は笹に襲われ中🎋 七夕飾りの枝 たくさんあります。
7/1 いよいよ文月です。午後の強烈な雷雨のあとは、涼しくなったように感じました。今朝の火曜サークルは外歩きを変更して室内でポールストレッチ、筋トレのあとは、ステップエクササイズに励みました。少しずつ高さを上げて太股をしっかり上げて1-2、1-2! 徐々に回数も増やし夏休み中の自宅で出来る中強度運動に。 酷暑のため9月まで休暇に皆さん異議なし! 我が家は笹に襲われ中🎋 七夕飾りの枝 たくさんあります。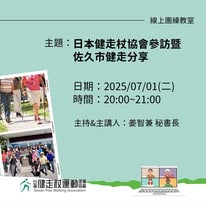 台灣健走杖運動推廣協會邀請指導員、教練們一起線上交流~ 【線上團練教室】 主持人及主講人:姜智兼 主題:日本健走杖協會參訪暨佐久市健走分享 教練分享: ⏰日期:2025/07/01(二) ⏰時間:20:00~21:00 🟩線上團練連結: https://meet.google.com/vuq-mujc-zyk (7:55pm開放入場) 非常歡迎教練們在發展健走杖推廣或教學上有任何想要更了解或交流的主題,請填寫表單,讓交流會安排更符合大家的需要。 https://forms.gle/FQoEDw2muJbjU2W28
台灣健走杖運動推廣協會邀請指導員、教練們一起線上交流~ 【線上團練教室】 主持人及主講人:姜智兼 主題:日本健走杖協會參訪暨佐久市健走分享 教練分享: ⏰日期:2025/07/01(二) ⏰時間:20:00~21:00 🟩線上團練連結: https://meet.google.com/vuq-mujc-zyk (7:55pm開放入場) 非常歡迎教練們在發展健走杖推廣或教學上有任何想要更了解或交流的主題,請填寫表單,讓交流會安排更符合大家的需要。 https://forms.gle/FQoEDw2muJbjU2W28 【暑さ薄れるウォーキング法】 2025/7/1 『#呼吸筋ストレッチ』と 『#呼吸筋活性化ウォーク』 この時期に意識を呼吸に移すと 体幹も心も整います #船橋ウォーキングソサイエティ #県立行田公園 #美姿勢ウォーキング
【暑さ薄れるウォーキング法】 2025/7/1 『#呼吸筋ストレッチ』と 『#呼吸筋活性化ウォーク』 この時期に意識を呼吸に移すと 体幹も心も整います #船橋ウォーキングソサイエティ #県立行田公園 #美姿勢ウォーキング 介護予防運動教室からの(╭☞•́⍛•̀)╭☞からの~ 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニングセッション!! ひまわり🌻いい感じに成長中🫶
介護予防運動教室からの(╭☞•́⍛•̀)╭☞からの~ 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニングセッション!! ひまわり🌻いい感じに成長中🫶 7/2 北鎌倉赤の洞門。 今日は介護予防教室を親子サークル(ネイルサロンも併設)の皆さんとスペース共有して 多世代交流会状態で 賑やかに楽しくエアーポールエクササイズ・チェア🪑筋トレ・脳トレゲームなど楽しめました。
7/2 北鎌倉赤の洞門。 今日は介護予防教室を親子サークル(ネイルサロンも併設)の皆さんとスペース共有して 多世代交流会状態で 賑やかに楽しくエアーポールエクササイズ・チェア🪑筋トレ・脳トレゲームなど楽しめました。 新幹線佐久平駅下りホームの看板を新しくしました。創業100年の看板を5年間も変えずに張っておりまして・・・。既に創業106年目、伝えたいことはいろいろありましたが、一点突破、思い切ってポールウォーキングに振り切りました。 ポールウォーキングをはじめよう!”健康と美” いかがでしょうか(^.^)?
新幹線佐久平駅下りホームの看板を新しくしました。創業100年の看板を5年間も変えずに張っておりまして・・・。既に創業106年目、伝えたいことはいろいろありましたが、一点突破、思い切ってポールウォーキングに振り切りました。 ポールウォーキングをはじめよう!”健康と美” いかがでしょうか(^.^)? 毎年この時期に担当させてもらっているヨガ教室ですが、今年が一番暑かった‥。どんなに暑くても参加率が高く、逆に元気をもらいました😌
毎年この時期に担当させてもらっているヨガ教室ですが、今年が一番暑かった‥。どんなに暑くても参加率が高く、逆に元気をもらいました😌 7/4 今日は渋谷区介護予防 PW教室2025年度2期初日。15名定員ですがお二人を除いて私より若いかたばかり。(私が高齢過ぎる?!)今日は計測日。教室休み明けの渋谷駅前のハチ公広場はハチ公の銅像を残して後ろの和風庭園などすっかりなくなっていました。34年度には新「ハチ公広場」となるそうです。
7/4 今日は渋谷区介護予防 PW教室2025年度2期初日。15名定員ですがお二人を除いて私より若いかたばかり。(私が高齢過ぎる?!)今日は計測日。教室休み明けの渋谷駅前のハチ公広場はハチ公の銅像を残して後ろの和風庭園などすっかりなくなっていました。34年度には新「ハチ公広場」となるそうです。 スキルアップ研修会IN佐久開催しました‼️ 安藤名誉会長にも参加いただきました。 坪井MCPRO,新地MCPROの正確な指導と参加者の真面目な受講姿勢に良好ですのお言葉いただきました‼️ 暑い中、皆さんお疲れ様でした‼️
スキルアップ研修会IN佐久開催しました‼️ 安藤名誉会長にも参加いただきました。 坪井MCPRO,新地MCPROの正確な指導と参加者の真面目な受講姿勢に良好ですのお言葉いただきました‼️ 暑い中、皆さんお疲れ様でした‼️ 佐久ポールウォーキング協会より 本日7月駒場PW例会でした。 佐久も朝から熱中症予防情報が出ている中、集まってくれた60名の参加者で公園〜牧場の木陰を選んでのポールウォーキングでした。 午後はNPWAコーチスキルアップセミナー(佐久会場)で 佐久の地元勿論、埼玉や千葉から#のコーチも集まってのお勉強会でした。 名誉会長/安藤先生も終始同席されPW考案者の立場より的確・明快な返答や指導を頂きました❗️
佐久ポールウォーキング協会より 本日7月駒場PW例会でした。 佐久も朝から熱中症予防情報が出ている中、集まってくれた60名の参加者で公園〜牧場の木陰を選んでのポールウォーキングでした。 午後はNPWAコーチスキルアップセミナー(佐久会場)で 佐久の地元勿論、埼玉や千葉から#のコーチも集まってのお勉強会でした。 名誉会長/安藤先生も終始同席されPW考案者の立場より的確・明快な返答や指導を頂きました❗️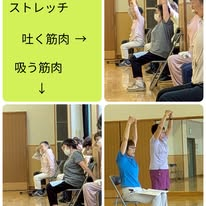 令和7年7月7日 シニアポールウォーキング 「この夏も元気に乗り切る」 そんな気迫みなぎる定例会 になりました #呼吸活性化ウォーキング #インターバルウォーク #ラダーとマットでコグニサイズ エアコンの効いた室内は 身体もしっかり動きます #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング
令和7年7月7日 シニアポールウォーキング 「この夏も元気に乗り切る」 そんな気迫みなぎる定例会 になりました #呼吸活性化ウォーキング #インターバルウォーク #ラダーとマットでコグニサイズ エアコンの効いた室内は 身体もしっかり動きます #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 7/8 今日の三浦ネットPWの活動は中止といたします。 ・・・・・・☀️・・・・・ 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されています。 本日は厳しい暑さが予想されます。 運動は原則中止し、外出はできるだけ控え、こまめに水分補給を行い、エアコン等を活用し、熱中症予防対策の徹底をお願いします。 また、炎天下の車内は大変危険です。わずかな時間であっても子どもを残したまま車から離れないようお願いします。 (市民健康課)
7/8 今日の三浦ネットPWの活動は中止といたします。 ・・・・・・☀️・・・・・ 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されています。 本日は厳しい暑さが予想されます。 運動は原則中止し、外出はできるだけ控え、こまめに水分補給を行い、エアコン等を活用し、熱中症予防対策の徹底をお願いします。 また、炎天下の車内は大変危険です。わずかな時間であっても子どもを残したまま車から離れないようお願いします。 (市民健康課) 写真1件
写真1件 柳澤 光宏さんの動画
柳澤 光宏さんの動画 今日から志木市の健康ポイント事業の計測会🦶多くの方がご参加されます! フットフレイル対策に加えて、オーラルフレイル対策がスタートします👄
今日から志木市の健康ポイント事業の計測会🦶多くの方がご参加されます! フットフレイル対策に加えて、オーラルフレイル対策がスタートします👄 ポケゴミスマイルの日。 #スマイルチーム #ポケゴミスマイル #ポールウォーキングしながらごみ拾い #日本財団海と日本プロジェクト #blueship #ブルーサンタ #記録 #20250710
ポケゴミスマイルの日。 #スマイルチーム #ポケゴミスマイル #ポールウォーキングしながらごみ拾い #日本財団海と日本プロジェクト #blueship #ブルーサンタ #記録 #20250710 7/10 猛暑日対策 「涼める場所あります」←市内に何ヵ所かありますね。今日のPW教室の会場のなごやかセンターには電動運動器具も沢山あり自由に利用できます。今日は欠席者が多くいつもの部屋が広々した感じ。他サークルのラダーをお借りしました。
7/10 猛暑日対策 「涼める場所あります」←市内に何ヵ所かありますね。今日のPW教室の会場のなごやかセンターには電動運動器具も沢山あり自由に利用できます。今日は欠席者が多くいつもの部屋が広々した感じ。他サークルのラダーをお借りしました。 2025.7.7〜11 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 19名 チェア体操 ☺︎令和7年度シニアサポートスタッフ養成研修(相模原市 高齢・障害者支援課) ☺︎親子ふれあい体操 15組 (10ヶ月〜32ヶ月.双子1組) ☺︎青少年指導委員ブロック研修 欠席 ☺︎上鶴間公民館青少年部部会 ☺︎8月日赤救急法短期講習会チラシ作成、申込受付開始 ☺︎ポケごみスマイルチーム 10名 ポールウォーキングdeゴミ拾い #BLUESANTA ☺︎ブルーシップ活動報告レポート提出 (SNSにてアップ) ☺︎相模原市文化協会会議 (9/14の文化協会祭について) ☺︎青空ポールウォーキング 11名 ☺︎スマイルチーム文化協会祭打合せ ☺︎文化協会祭ゲストチーム・ダブルダッチ Millennitm Collection 打合せ
2025.7.7〜11 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 19名 チェア体操 ☺︎令和7年度シニアサポートスタッフ養成研修(相模原市 高齢・障害者支援課) ☺︎親子ふれあい体操 15組 (10ヶ月〜32ヶ月.双子1組) ☺︎青少年指導委員ブロック研修 欠席 ☺︎上鶴間公民館青少年部部会 ☺︎8月日赤救急法短期講習会チラシ作成、申込受付開始 ☺︎ポケごみスマイルチーム 10名 ポールウォーキングdeゴミ拾い #BLUESANTA ☺︎ブルーシップ活動報告レポート提出 (SNSにてアップ) ☺︎相模原市文化協会会議 (9/14の文化協会祭について) ☺︎青空ポールウォーキング 11名 ☺︎スマイルチーム文化協会祭打合せ ☺︎文化協会祭ゲストチーム・ダブルダッチ Millennitm Collection 打合せ 【やるのは今でしょ! 私の番がきたのね】 町内では段々とご年配の方々が旅立ち、或は施設入居やデイサービスへ 在宅でも身体も思うようでは無さそう… 若い家族は赤ちゃんのお世話! 共働きと忙しいのがわかります ごみステーションのカラスよけネットもボロボロ 道路の草も時としてぼうぼうに! 町はちょっとの事を手出ししただけで気持良くすごせる! できる人ができる事をしなくては 【今が私の番】 2025/7/11
【やるのは今でしょ! 私の番がきたのね】 町内では段々とご年配の方々が旅立ち、或は施設入居やデイサービスへ 在宅でも身体も思うようでは無さそう… 若い家族は赤ちゃんのお世話! 共働きと忙しいのがわかります ごみステーションのカラスよけネットもボロボロ 道路の草も時としてぼうぼうに! 町はちょっとの事を手出ししただけで気持良くすごせる! できる人ができる事をしなくては 【今が私の番】 2025/7/11 2本のポールで西荻街歩き 夏場の気ままにポール歩き(気まポ)は、猛暑を考慮して「夕暮れウォーク」にしています。はじめはナイトウォークと呼んでいたのですが、7時頃まで明るいので呼び名を変更しました。 先日の雨のあと気温が下がって、当初の予想よりもずっと快適なウォーキングとなりました。合計12000歩。5km強のつもりだったけど、6kmくらいになったと思われます。 JR西荻窪駅南口に集合、まず仲通街を南下して駅方面にもどって、駅の北側の骨董屋などが並ぶ通りを経て、東京女子大、善福寺公園へ。池のまわりは人気少なく、暗くもなってきていたので、1人では怖そうだなんて言いながら。 帰りは、「はだしのオアシス公園」や「トトロの樹」と呼ぶ大ケヤキのある公園を通って駅近くのレストラン「バルタザール」へ。1階が有機野菜の八百屋で、その2階。3階は書店まで同じ経営です。 バルタザールでは、話題の映画「国宝」の話などで盛り上がりました。見た人3人から、ぜひとお勧め。月内に見るつもりです。 今回、会の常連北村さんが西荻に詳しいので、立ち寄りスポットや打ち上げの店の紹介などでお世話になりました。
2本のポールで西荻街歩き 夏場の気ままにポール歩き(気まポ)は、猛暑を考慮して「夕暮れウォーク」にしています。はじめはナイトウォークと呼んでいたのですが、7時頃まで明るいので呼び名を変更しました。 先日の雨のあと気温が下がって、当初の予想よりもずっと快適なウォーキングとなりました。合計12000歩。5km強のつもりだったけど、6kmくらいになったと思われます。 JR西荻窪駅南口に集合、まず仲通街を南下して駅方面にもどって、駅の北側の骨董屋などが並ぶ通りを経て、東京女子大、善福寺公園へ。池のまわりは人気少なく、暗くもなってきていたので、1人では怖そうだなんて言いながら。 帰りは、「はだしのオアシス公園」や「トトロの樹」と呼ぶ大ケヤキのある公園を通って駅近くのレストラン「バルタザール」へ。1階が有機野菜の八百屋で、その2階。3階は書店まで同じ経営です。 バルタザールでは、話題の映画「国宝」の話などで盛り上がりました。見た人3人から、ぜひとお勧め。月内に見るつもりです。 今回、会の常連北村さんが西荻に詳しいので、立ち寄りスポットや打ち上げの店の紹介などでお世話になりました。 雨天に悩まされた 1期の火曜日定例会でした 2025/7/15 本日も不安定な天気です 「しっかり運動したい」 声に応えて屋内ならではのメニュー #サーキットトレーニング #片足立ちバランスウォーキング #継足ウォーク #バックウォーキング #呼吸筋活性化ウォーキング #ペットボトルで体幹ウォーク #脳トレ 足の先から頭の中まで 動かしてみました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
雨天に悩まされた 1期の火曜日定例会でした 2025/7/15 本日も不安定な天気です 「しっかり運動したい」 声に応えて屋内ならではのメニュー #サーキットトレーニング #片足立ちバランスウォーキング #継足ウォーク #バックウォーキング #呼吸筋活性化ウォーキング #ペットボトルで体幹ウォーク #脳トレ 足の先から頭の中まで 動かしてみました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング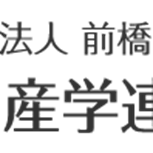 「ポールウォーキング 1日体験会」開催のお知らせ | 研究・産学連携推進本部
「ポールウォーキング 1日体験会」開催のお知らせ | 研究・産学連携推進本部 佐久ポールウォーキング協会より 梅雨明け〜 本日パラダPW散策でした。30℃越えの中、 参議院選挙投票を済ませた?60名越えの参加頂きました。 南パラダ/アスレチックコース〜セラピーロードと暑さを逃れての?癒しのPW〜❗️ マイナスイオンいっぱい〜 パラダ様より温泉券とキッズランド1日パス券の提供も有り皆さん堪能出来た散策となりました。
佐久ポールウォーキング協会より 梅雨明け〜 本日パラダPW散策でした。30℃越えの中、 参議院選挙投票を済ませた?60名越えの参加頂きました。 南パラダ/アスレチックコース〜セラピーロードと暑さを逃れての?癒しのPW〜❗️ マイナスイオンいっぱい〜 パラダ様より温泉券とキッズランド1日パス券の提供も有り皆さん堪能出来た散策となりました。 7/23 北鎌倉介護予防クラス 昨日楽動教室にも参加されたメンバーは連日出席!熱いのに偉いです。仲間と顔を合わせお喋りするのが楽しみかな。会場まで往復歩いて、認知症予防に有効ですね。チェア🪑オーラルエクササイズは嚥下予防です。70代2名のほかは80代の方々ですが皆さん回を重ねるごとに明るく笑顔で元気を増してタフです。毎週計測を続けていますが、暑い☀️連休明けにもかかわらず全員筋肉量アップしていて感心しました。
7/23 北鎌倉介護予防クラス 昨日楽動教室にも参加されたメンバーは連日出席!熱いのに偉いです。仲間と顔を合わせお喋りするのが楽しみかな。会場まで往復歩いて、認知症予防に有効ですね。チェア🪑オーラルエクササイズは嚥下予防です。70代2名のほかは80代の方々ですが皆さん回を重ねるごとに明るく笑顔で元気を増してタフです。毎週計測を続けていますが、暑い☀️連休明けにもかかわらず全員筋肉量アップしていて感心しました。 【令和7年度 佐久市1日有償仕事体験事業】参加学生を募集します!
【令和7年度 佐久市1日有償仕事体験事業】参加学生を募集します! 7/24 東京に比べると鎌倉は2~3℃低いようです。それでも暑いです。挨拶は皆共通「暑いね✨☀️✨」 腰越貯筋サークルでは包括さんの月イチ体測日。皆さん筋肉量upで素晴らしい🙌けれど握力が全体的に低いのはなぜでしょう。今日は1メンバーさんの発案 <行司スクワット>と7秒スクワットで汗を流しました。ローリング歩行はもうしっかりマスターです。次回はお盆休みなのでかき氷で暑気払いをしました。皆お元気で!
7/24 東京に比べると鎌倉は2~3℃低いようです。それでも暑いです。挨拶は皆共通「暑いね✨☀️✨」 腰越貯筋サークルでは包括さんの月イチ体測日。皆さん筋肉量upで素晴らしい🙌けれど握力が全体的に低いのはなぜでしょう。今日は1メンバーさんの発案 <行司スクワット>と7秒スクワットで汗を流しました。ローリング歩行はもうしっかりマスターです。次回はお盆休みなのでかき氷で暑気払いをしました。皆お元気で! 本日も覚悟の暑さです! 思い切ってお家を飛び出したメンバーでひとしきりの運動です #船橋ウォーキングソサイエティ 1期最後の定例会は #2本のポールを使うウォーキング ポールは今日は自宅でお留守番 クーラーの中で頭の中から爪先まで しっかり運動です! 2025/8/24 チェアエクササイズは #ふなばしシルバーリハビリ体操 その場でできる #サーキットトレーニング 狭い場所でも歩ける #バラエティウォーキング 認知症予防に #脳トレエクササイズ お口の体操は #夏休みの過ごし方 8月は夏休みです☀ 9月に元気に会うことを誓って 暑さと上手に付き合いながら お家トレーニングに励みましょう 💪🏝️🔥✨
本日も覚悟の暑さです! 思い切ってお家を飛び出したメンバーでひとしきりの運動です #船橋ウォーキングソサイエティ 1期最後の定例会は #2本のポールを使うウォーキング ポールは今日は自宅でお留守番 クーラーの中で頭の中から爪先まで しっかり運動です! 2025/8/24 チェアエクササイズは #ふなばしシルバーリハビリ体操 その場でできる #サーキットトレーニング 狭い場所でも歩ける #バラエティウォーキング 認知症予防に #脳トレエクササイズ お口の体操は #夏休みの過ごし方 8月は夏休みです☀ 9月に元気に会うことを誓って 暑さと上手に付き合いながら お家トレーニングに励みましょう 💪🏝️🔥✨ 7/25 連日熱中症警戒アラーム💥 消防署ではいつもの梯子の点検が行われていました。渋谷教室の会場 かんなみの杜はこのお隣です。包括支援センターや老人施設と同居なので共用部分はマスク着用😷です。室内はキンキンに冷えて寒いくらい。少し温度を上げて、今日はウォーキングの足の運び方!かかと接地(着地)↔ 後ろ足の踏み込み練習をびっしり練習しましたら全員歩幅が広くなり姿勢もきれいになって大喜び🎵😍🎵 ポールがあればみんな大股🚶♂️🚶♀️🚶 鎌倉から通ってる、っていうと皆びっくりですが湘南ライン1本で55分で楽勝です。車と違って眠れるし、何より楽しい🎶
7/25 連日熱中症警戒アラーム💥 消防署ではいつもの梯子の点検が行われていました。渋谷教室の会場 かんなみの杜はこのお隣です。包括支援センターや老人施設と同居なので共用部分はマスク着用😷です。室内はキンキンに冷えて寒いくらい。少し温度を上げて、今日はウォーキングの足の運び方!かかと接地(着地)↔ 後ろ足の踏み込み練習をびっしり練習しましたら全員歩幅が広くなり姿勢もきれいになって大喜び🎵😍🎵 ポールがあればみんな大股🚶♂️🚶♀️🚶 鎌倉から通ってる、っていうと皆びっくりですが湘南ライン1本で55分で楽勝です。車と違って眠れるし、何より楽しい🎶 20250725. スマイル星ヶ丘。 ポールウォーキング。リハビリポールウォーキング。ウォーキングポールでエクササイズ。 熱中症警戒アラート🥵発令中につき、外歩きはせずに室内でじっくりたっぷりエクササイズしました。 #ポールウォーキング #リハビリポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #
20250725. スマイル星ヶ丘。 ポールウォーキング。リハビリポールウォーキング。ウォーキングポールでエクササイズ。 熱中症警戒アラート🥵発令中につき、外歩きはせずに室内でじっくりたっぷりエクササイズしました。 #ポールウォーキング #リハビリポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ # #2025健走杖輕旅行
#2025健走杖輕旅行 福祉✖️スマイルチーム。 居宅介護支援事業所様からのご依頼を受け リズムダンス等,元気いっぱい体を動かす目的の活動がスタートしました。 ダウン症、自閉症,知的障害,発達障害、既往症、、、 若い世代の皆さん約30名とスタッフさんとで 約1時間半。 歌って踊って喋って、、、汗だく💦 そしてみなさんからたくさんの刺激をもらいました❣️ 次回も楽しみです😊 #福祉 #スマイルチーム #要介護1〜5 #居宅介護支援事業所 #相模原市 #sagamihara #20250725
福祉✖️スマイルチーム。 居宅介護支援事業所様からのご依頼を受け リズムダンス等,元気いっぱい体を動かす目的の活動がスタートしました。 ダウン症、自閉症,知的障害,発達障害、既往症、、、 若い世代の皆さん約30名とスタッフさんとで 約1時間半。 歌って踊って喋って、、、汗だく💦 そしてみなさんからたくさんの刺激をもらいました❣️ 次回も楽しみです😊 #福祉 #スマイルチーム #要介護1〜5 #居宅介護支援事業所 #相模原市 #sagamihara #20250725 7/27 時が経つのは本当に速い! もう7月最後の日曜日です。夕べ 7、8月の逗子PWは猛暑のため中止にすると連絡がありました。開始時間を繰り上げる予定でしたが連日の熱中症警戒アラームへの対処です。事故の心配なくなりひと安心です。時間が出来たので出掛けたいのですが こう暑くては・・・家でみちのくを味わいます。
7/27 時が経つのは本当に速い! もう7月最後の日曜日です。夕べ 7、8月の逗子PWは猛暑のため中止にすると連絡がありました。開始時間を繰り上げる予定でしたが連日の熱中症警戒アラームへの対処です。事故の心配なくなりひと安心です。時間が出来たので出掛けたいのですが こう暑くては・・・家でみちのくを味わいます。 7/31 おはようございます。今朝も心地よい風が吹いています。昨日は激動!?の1日でした。夏空の下、体操の後の月イチお楽しみ会を餌にうきうき🎵北鎌倉へ。カムチャッカの地震の影響で太平洋側へ押し寄せてくる津波注意報(→警報に変わったのを知らず)のサイレンを耳にしながら気にもせず、いつもと変わらずコアトレなど済ますと、お待ちかね!『食』の会をすっかり楽しんで帰宅路へ / <ここが境界> / 海岸方面を走る電車もバスもストップしていたのです(投稿済) 「健康のため」と自ら言い聞かせ炎天下を切通を抜けてPWで帰宅しました。前に進めば家🏚️に帰れる!と言い聞かせ、熱中症が怖くて最近は歩いてないなぁ~!と思いながら。 海の街に住むということ、今回は津波が来たときの対策を真剣に考える機会になりました。 必要なのはタフな心と身体。 今朝の団欒時の「あなたの刺激は何?」→ 「 ! 」
7/31 おはようございます。今朝も心地よい風が吹いています。昨日は激動!?の1日でした。夏空の下、体操の後の月イチお楽しみ会を餌にうきうき🎵北鎌倉へ。カムチャッカの地震の影響で太平洋側へ押し寄せてくる津波注意報(→警報に変わったのを知らず)のサイレンを耳にしながら気にもせず、いつもと変わらずコアトレなど済ますと、お待ちかね!『食』の会をすっかり楽しんで帰宅路へ / <ここが境界> / 海岸方面を走る電車もバスもストップしていたのです(投稿済) 「健康のため」と自ら言い聞かせ炎天下を切通を抜けてPWで帰宅しました。前に進めば家🏚️に帰れる!と言い聞かせ、熱中症が怖くて最近は歩いてないなぁ~!と思いながら。 海の街に住むということ、今回は津波が来たときの対策を真剣に考える機会になりました。 必要なのはタフな心と身体。 今朝の団欒時の「あなたの刺激は何?」→ 「 ! 」 今年も開催します。生プルーン食べ放題の佐久ぴんころウォーク(^^)皆さんのご参加お待ちしています!
今年も開催します。生プルーン食べ放題の佐久ぴんころウォーク(^^)皆さんのご参加お待ちしています!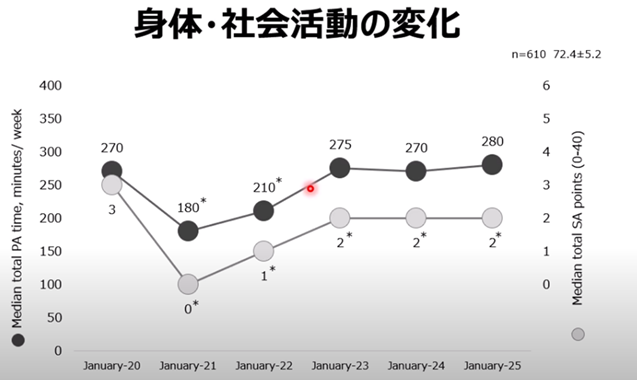 ・コロナ禍1年目で両活動は大きく制限され、
・コロナ禍1年目で両活動は大きく制限され、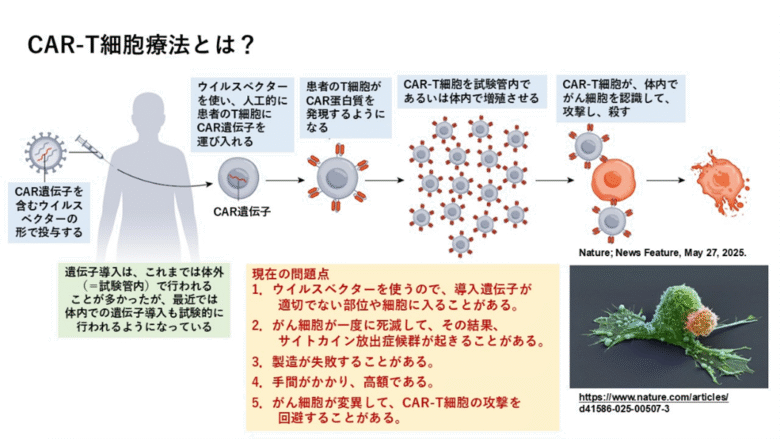 CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。ただし、患者自身のT細胞を集めて、がんを攻撃するように体外で遺伝子改変を施して同じ患者の体内に戻すという、非常に高度な個別化医療であるために、治療の実施には厳格な施設要件があり、日本では60ぐらいの施設でしか使えません。しかし、アメリカではすでにかなり広く使われるようになっていて、多くの医療機関や製薬会社が参画して、現時点でも1兆円以上の市場規模があるようです。
CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。ただし、患者自身のT細胞を集めて、がんを攻撃するように体外で遺伝子改変を施して同じ患者の体内に戻すという、非常に高度な個別化医療であるために、治療の実施には厳格な施設要件があり、日本では60ぐらいの施設でしか使えません。しかし、アメリカではすでにかなり広く使われるようになっていて、多くの医療機関や製薬会社が参画して、現時点でも1兆円以上の市場規模があるようです。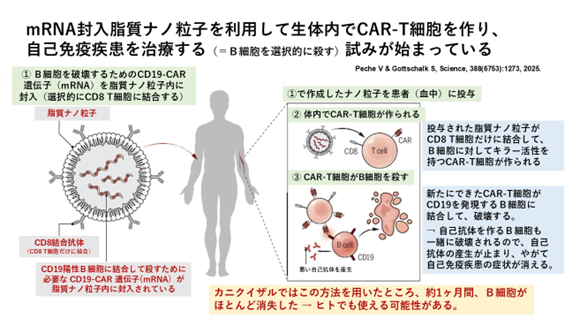 CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。
CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。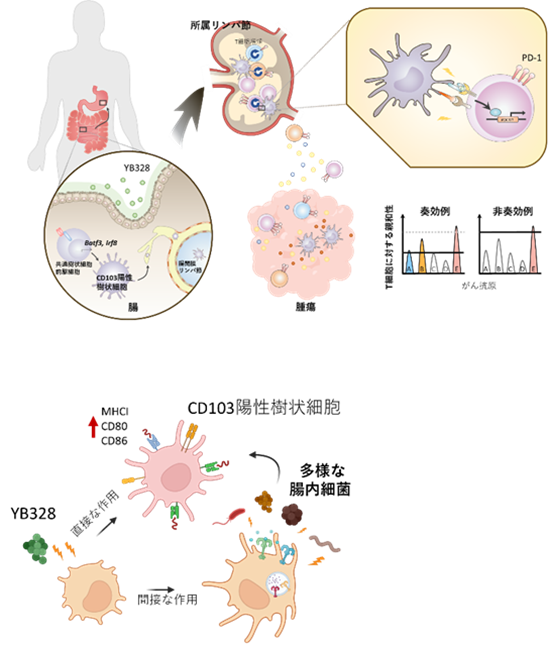
 パリでの学会(https://charcot2025.fr/)に参加する前に,週末を利用してアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れました.リベラルアーツ研究会で「夜と霧(https://amzn.to/46lteC8)」を取り上げた際に関連資料を読み漁ったため,知識としては理解していたつもりでしたが,実際にその場に立つと,まったく異なる感情がこみ上げてきました.毒ガス・チクロンBが投げ込まれたガス室,そして通路一面に貼られた被収容者の顔写真を前にしたとき,胸が押しつぶされるような苦しさを覚えました.戦争は人間をここまで残虐にするのかという思いが改めて浮かびました.
パリでの学会(https://charcot2025.fr/)に参加する前に,週末を利用してアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れました.リベラルアーツ研究会で「夜と霧(https://amzn.to/46lteC8)」を取り上げた際に関連資料を読み漁ったため,知識としては理解していたつもりでしたが,実際にその場に立つと,まったく異なる感情がこみ上げてきました.毒ガス・チクロンBが投げ込まれたガス室,そして通路一面に貼られた被収容者の顔写真を前にしたとき,胸が押しつぶされるような苦しさを覚えました.戦争は人間をここまで残虐にするのかという思いが改めて浮かびました. ジャン・マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot;1825–1893年)は,フランスの神経病学者であり,その名は多くの疾患や症候に残されています.彼の業績は医学にとどまらず,芸術や文学など広範な文化領域にまで影響を与えました.本年は,シャルコー生誕200年の節目に当たるため,第29回国際神経科学史学会(ISHN)は「シャルコー生誕200年記念式典」を兼ねて,パリのサルペトリエール病院内にあるICM Institute for Brain and Spinal Cordにて開催されています.
ジャン・マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot;1825–1893年)は,フランスの神経病学者であり,その名は多くの疾患や症候に残されています.彼の業績は医学にとどまらず,芸術や文学など広範な文化領域にまで影響を与えました.本年は,シャルコー生誕200年の節目に当たるため,第29回国際神経科学史学会(ISHN)は「シャルコー生誕200年記念式典」を兼ねて,パリのサルペトリエール病院内にあるICM Institute for Brain and Spinal Cordにて開催されています.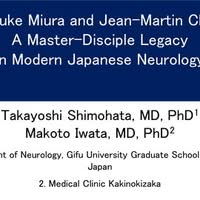 お蔭さまで,無事に講演を終了しました.終了後,多くの先生が集まって来られて,Congraturations!と言っていただき大変驚きました.これまで経験のないことで感激しました.三浦謹之助先生とシャルコー先生の師弟関係に心を動かされた先生が多かったのかなと思いました.
お蔭さまで,無事に講演を終了しました.終了後,多くの先生が集まって来られて,Congraturations!と言っていただき大変驚きました.これまで経験のないことで感激しました.三浦謹之助先生とシャルコー先生の師弟関係に心を動かされた先生が多かったのかなと思いました.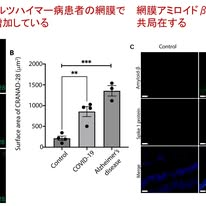 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染がアルツハイマー病発症のリスクを増加させるという複数の研究が報告されていますが,最新のScience Advances誌に報告された研究は,網膜においてアルツハイマー病様のアミロイドβ(Aβ)病理がCOVID-19によって誘導されることを示したもので注目されます.米国イェール大学眼科などの共同研究です.
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染がアルツハイマー病発症のリスクを増加させるという複数の研究が報告されていますが,最新のScience Advances誌に報告された研究は,網膜においてアルツハイマー病様のアミロイドβ(Aβ)病理がCOVID-19によって誘導されることを示したもので注目されます.米国イェール大学眼科などの共同研究です.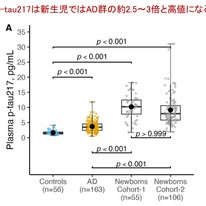 非常に驚いた報告です.スウェーデンを初めとするなど多数の研究機関が参加した国際共同研究です.チームは,「タウ蛋白のリン酸化が脳の発達と神経変性の両方に重要な役割を果たす」という仮説のもと,新生児を含む健常者とアルツハイマー病(AD)患者における血漿リン酸化タウ217(p-tau217)濃度を比較しました.
非常に驚いた報告です.スウェーデンを初めとするなど多数の研究機関が参加した国際共同研究です.チームは,「タウ蛋白のリン酸化が脳の発達と神経変性の両方に重要な役割を果たす」という仮説のもと,新生児を含む健常者とアルツハイマー病(AD)患者における血漿リン酸化タウ217(p-tau217)濃度を比較しました.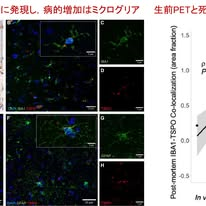 進行性核上性麻痺(PSP)は,中脳や大脳皮質にタウが蓄積し,運動障害や認知機能障害を引き起こすタウオパチーの代表的疾患です.これまで,神経炎症とタウの脳内伝播が病態進行に関与すると考えられてきましたが,その直接的証拠は限られていました.今回紹介する2つの研究は,TSPO PET画像と死後脳との対応づけ,およびタウのシナプス伝播機構の可視化というアプローチで,PSPの病態理解を大きく進めるものです.
進行性核上性麻痺(PSP)は,中脳や大脳皮質にタウが蓄積し,運動障害や認知機能障害を引き起こすタウオパチーの代表的疾患です.これまで,神経炎症とタウの脳内伝播が病態進行に関与すると考えられてきましたが,その直接的証拠は限られていました.今回紹介する2つの研究は,TSPO PET画像と死後脳との対応づけ,およびタウのシナプス伝播機構の可視化というアプローチで,PSPの病態理解を大きく進めるものです.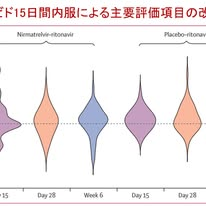 今回のキーワードは,long COVIDに対する抗ウイルス薬の単独使用では短期間での症状改善は見込めない,パーキンソン病患者ではCOVID-19罹患により長期的予後が悪化する,COVID-19後に現れる新たな片頭痛様頭痛―2年後も続く後遺症としての頭痛,Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群では共通する病態として「酸化ストレス」があり女性に顕著である,パンデミックにより感染しなくても脳の老化は進むが認知機能の低下は感染によってさらに深刻になる,です.
今回のキーワードは,long COVIDに対する抗ウイルス薬の単独使用では短期間での症状改善は見込めない,パーキンソン病患者ではCOVID-19罹患により長期的予後が悪化する,COVID-19後に現れる新たな片頭痛様頭痛―2年後も続く後遺症としての頭痛,Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群では共通する病態として「酸化ストレス」があり女性に顕著である,パンデミックにより感染しなくても脳の老化は進むが認知機能の低下は感染によってさらに深刻になる,です.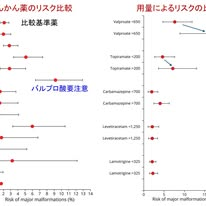 抗てんかん薬(Antiseizure Medication;ASM)は,妊娠中の使用に際して胎児への影響を十分に考慮する必要があります.2025年に発表された北米抗てんかん薬妊娠レジストリ(North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry)のデータから,妊娠初期に使用された薬剤ごとの主要な先天奇形のリスクが報告されました.図左に示されているように,主要奇形のリスクは以下の通りです:
抗てんかん薬(Antiseizure Medication;ASM)は,妊娠中の使用に際して胎児への影響を十分に考慮する必要があります.2025年に発表された北米抗てんかん薬妊娠レジストリ(North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry)のデータから,妊娠初期に使用された薬剤ごとの主要な先天奇形のリスクが報告されました.図左に示されているように,主要奇形のリスクは以下の通りです: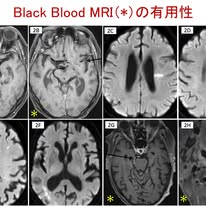 がん免疫療法に用いられる免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitor: ICI)は,進行がんの予後を大きく改善させる一方で,免疫関連有害事象(irAE)を引き起こすことが知られています.その中に中枢神経系に影響を及ぼす神経学的有害事象(nirAE)がありますが,とくに「免疫関連中枢神経血管炎(nirVasculitis)」は診断が難しく,重篤な転帰を取ることもあります.このnirVasculitisに関する最大規模のsystematic reviewが発表されています.自験例6例を含む計20症例が検討されています.
がん免疫療法に用いられる免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitor: ICI)は,進行がんの予後を大きく改善させる一方で,免疫関連有害事象(irAE)を引き起こすことが知られています.その中に中枢神経系に影響を及ぼす神経学的有害事象(nirAE)がありますが,とくに「免疫関連中枢神経血管炎(nirVasculitis)」は診断が難しく,重篤な転帰を取ることもあります.このnirVasculitisに関する最大規模のsystematic reviewが発表されています.自験例6例を含む計20症例が検討されています. 6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。
6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。 佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。
佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。 【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います!
【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います! 6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/
6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/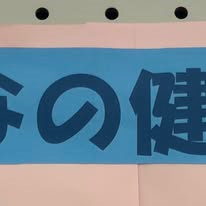 昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座
昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座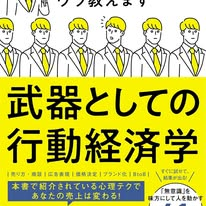 できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。
できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。 6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな?
6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな? Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング
Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング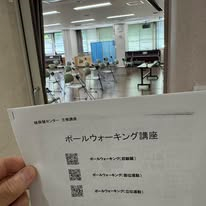 本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり
本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり 第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️
第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️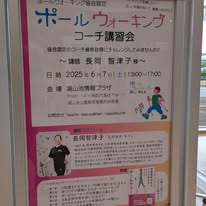 初上陸
初上陸 6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね)
6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね) #これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7
#これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7 佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️
佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️ 6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦
6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦 さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥
さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥 昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操
昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操 6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略
6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略 6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。
6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。 #船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。
#船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。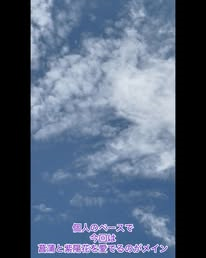

 緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。
緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。 6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。
6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。 いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。
いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。 6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。
6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。 猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり
猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり ㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇
㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇 6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。
6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。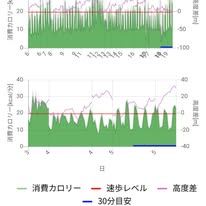 【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き
【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き #ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ
#ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ 【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体
【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体 先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。
先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。 6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。
6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。 海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl
海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl 「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています!
「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています! 【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座
【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座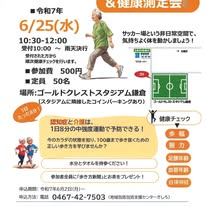 梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。
梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。 6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。
6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。 6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。
6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。 2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ
【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ 6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや
6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや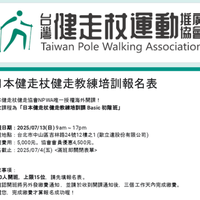 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表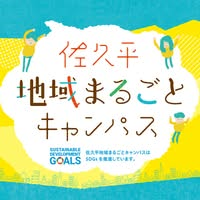 佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス!
佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス! 〇目 的
〇目 的 図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪
図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪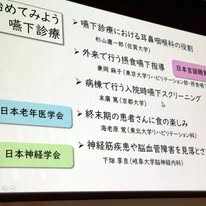 第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.
第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.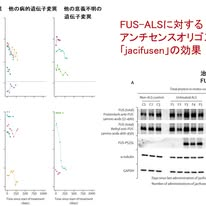 難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.
難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.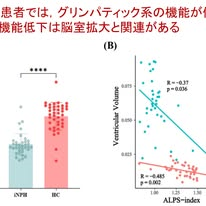 特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.
特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.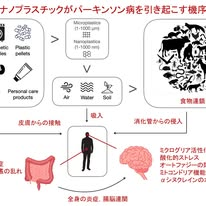 Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024).
Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024). 驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.
驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.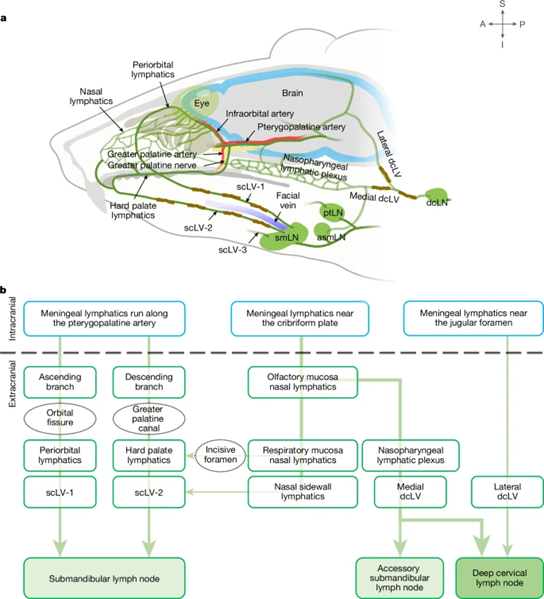 a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。
a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。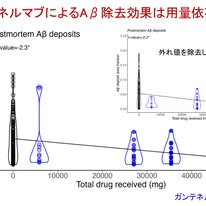 Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.
Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.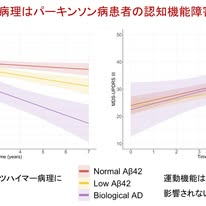 パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.
パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.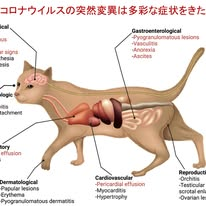 臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).
臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).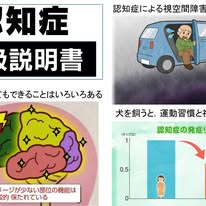 認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした.
認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした. 船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化
船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化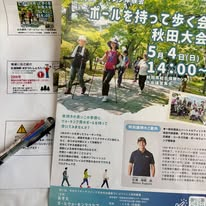 ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜
ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜 5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦
5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦 秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。
秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。 5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入!
5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入! スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun
スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun 5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。
5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。 岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね!
岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね! 先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸
先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸 5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。
5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。 2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス
2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス 佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️#
佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️# 読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介
読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜
#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜 JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH
JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH 📸【介護予防運動教室レポート】
本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ
🔹足指グーパー運動
🔹カーフレイズ&つま先上げ
🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨
これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ
📸【介護予防運動教室レポート】
本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ
🔹足指グーパー運動
🔹カーフレイズ&つま先上げ
🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨
これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun
スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun 市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513
市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513 5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ)
5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ) ✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導
✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導 5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。
5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。 【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす
【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす 本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨
本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨ 【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。
【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。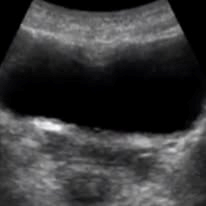 【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。
【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。 5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。
5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。 🌈アクティブシニアクラス🌈
介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。
・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)
・無理なく筋力をつけるトレーニング
・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡
#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス
🌈アクティブシニアクラス🌈
介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。
・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)
・無理なく筋力をつけるトレーニング
・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡
#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス #船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。
#船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。 シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^)
シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^) 本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。
本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。 5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。
5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。 〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな
〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな 18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。
18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。 新手使用健走杖|入門篇指南 🌿
新手使用健走杖|入門篇指南 🌿 みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね
みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね 5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。
5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。 からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道
からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道 屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。
屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。 5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。
5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。 很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學
很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學 2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会
2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会 佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️
佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️ 見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。
見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。 ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム
ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム 5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。
5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。 写真1件
写真1件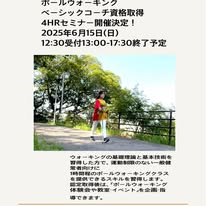 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程
【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程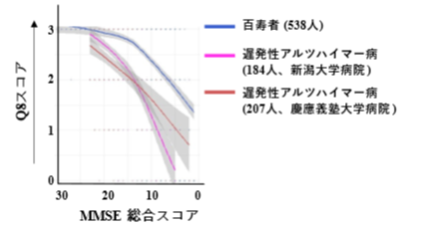 アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目
アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目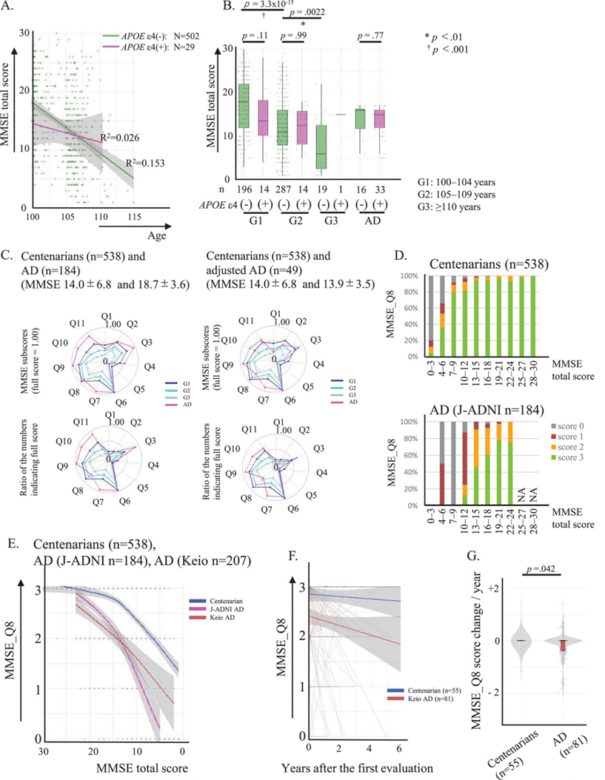 百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。
百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。 新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。
新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。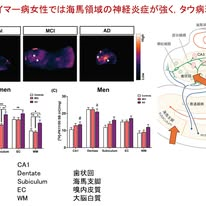 アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています.
アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています.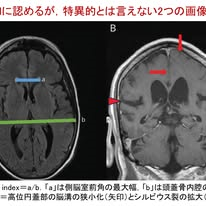 ★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします.
★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします.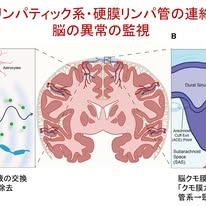 私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています.
私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています.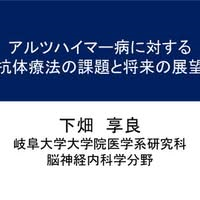 近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください.
近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください.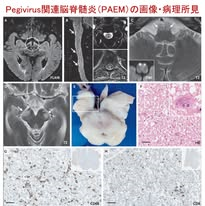 最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります.
最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります.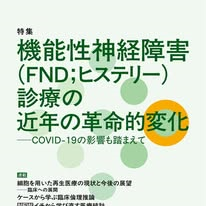 「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます.
「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます.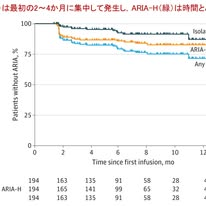 アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています.
アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています.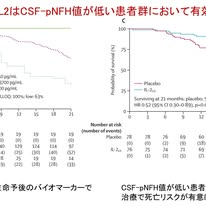 筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです.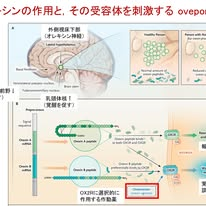 第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました.
第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました.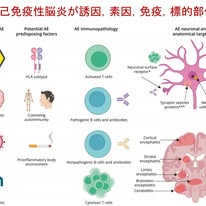 自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます.
自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます.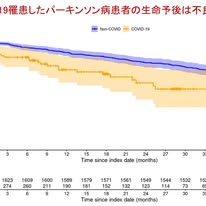 個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります.
個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります. 4/1 令和7年度初回定例会 予定では腰越の丹後が谷公園で恒例のお花見ポールウォーキングの会でしたが、冷たい雨と凍りそうな寒さで、初めて室内🌸🌸花見会となりました。20名のメンバーさんのうち15名出席。ポールで身体を暖めてからおやつに手を伸ばし、注文のお弁当が届くとお喋りの花🌸を咲かせながら賑やかにいただきました。10年目を迎えたこのサークルは広町里山と江の島を拠点にしてきましたが、皆さん歳を重ねて、たまには平らなところも歩きたいと言う希望が出ました。 義経・弁慶の満福寺辺りから始めましょうか。継続は力。
4/1 令和7年度初回定例会 予定では腰越の丹後が谷公園で恒例のお花見ポールウォーキングの会でしたが、冷たい雨と凍りそうな寒さで、初めて室内🌸🌸花見会となりました。20名のメンバーさんのうち15名出席。ポールで身体を暖めてからおやつに手を伸ばし、注文のお弁当が届くとお喋りの花🌸を咲かせながら賑やかにいただきました。10年目を迎えたこのサークルは広町里山と江の島を拠点にしてきましたが、皆さん歳を重ねて、たまには平らなところも歩きたいと言う希望が出ました。 義経・弁慶の満福寺辺りから始めましょうか。継続は力。 4/4 渋谷区健康すくすく事業ポールウォーキング教室2025新学期。 FBアップに3度失敗し(原因不明)これは力尽き4度目なので大幅に省略します。また明日にでも・・・ ※FB不調の原因は更新の為でした
4/4 渋谷区健康すくすく事業ポールウォーキング教室2025新学期。 FBアップに3度失敗し(原因不明)これは力尽き4度目なので大幅に省略します。また明日にでも・・・ ※FB不調の原因は更新の為でした 今日は良い天気の中東林包括支援センターのノルディック&ポールウォーク5日間教室の最終日 汗ばむようなお天気の中、桜も咲き乱れ、花桃も咲いていてgoodな最終日でした、皆さんとっても物覚えが早く、私が煽られてヒーヒー、来週から自主サークルグループも立ち上がり、皆で楽しくこれからも歩いていただけそうです。100歳まで楽しく歩き続けましょう。(歩かないと歩けなくなる)を合言葉に
今日は良い天気の中東林包括支援センターのノルディック&ポールウォーク5日間教室の最終日 汗ばむようなお天気の中、桜も咲き乱れ、花桃も咲いていてgoodな最終日でした、皆さんとっても物覚えが早く、私が煽られてヒーヒー、来週から自主サークルグループも立ち上がり、皆で楽しくこれからも歩いていただけそうです。100歳まで楽しく歩き続けましょう。(歩かないと歩けなくなる)を合言葉に 佐久ポールウォーキング協会より 2025年度PW歩き始め〜 3月の冬眠を経て集まった60名越えのポールウォーカー〜 〜待ってたよ❗️今年もよろしく〜の声をアチラコチラで聴き感激のスタートでした。 次回は来週桜満開?の〜さくラさく小径公園〜を闊歩です。
佐久ポールウォーキング協会より 2025年度PW歩き始め〜 3月の冬眠を経て集まった60名越えのポールウォーカー〜 〜待ってたよ❗️今年もよろしく〜の声をアチラコチラで聴き感激のスタートでした。 次回は来週桜満開?の〜さくラさく小径公園〜を闊歩です。 昨日は、月に一回の津島市天王川公園の早朝ポールウォーキングデーでした❗️ 15名の皆さんにご参加いただきました😊 私の左にいらっしゃるのはこの津島市の日比市長。そのお隣は奥様のみどりさんです。 毎月第一土曜日の朝の7:30から、2本の専用ストックを使ってのウォーキングをみなさんで楽しんでいます❣️ 満開の桜の下、15名の皆さんとご機嫌な時間を過ごしました‼️ 初めての方でも、気軽に参加できるポールウォーキングです☺️ 来月はイレギュラーになりまして2週目の土曜日、5/10になります😊 ちょっとタイミングが遅いかもですが、藤の花が見れるかもです😅 新年度のスタート‼️ 新たなことにチャレンジしてみませんか‼️
昨日は、月に一回の津島市天王川公園の早朝ポールウォーキングデーでした❗️ 15名の皆さんにご参加いただきました😊 私の左にいらっしゃるのはこの津島市の日比市長。そのお隣は奥様のみどりさんです。 毎月第一土曜日の朝の7:30から、2本の専用ストックを使ってのウォーキングをみなさんで楽しんでいます❣️ 満開の桜の下、15名の皆さんとご機嫌な時間を過ごしました‼️ 初めての方でも、気軽に参加できるポールウォーキングです☺️ 来月はイレギュラーになりまして2週目の土曜日、5/10になります😊 ちょっとタイミングが遅いかもですが、藤の花が見れるかもです😅 新年度のスタート‼️ 新たなことにチャレンジしてみませんか‼️ 2025/4/5 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025/4/5 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ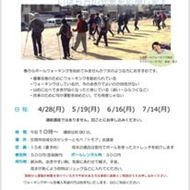 2022年から始めた茨城県笠間市でのポールウォーキング講座、今年もやりまーす。嬉しいことに段々仲間が増えてきましたよ。故郷いばらきの元気を応援します。
2022年から始めた茨城県笠間市でのポールウォーキング講座、今年もやりまーす。嬉しいことに段々仲間が増えてきましたよ。故郷いばらきの元気を応援します。 2025.4.7 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025.4.7 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 4/8 花祭り 三浦ネットポールウォーキング定例会。空は晴れ穏やかなお花見日和の心地よい1日でした。大巧寺からスタートし光明寺まで幾つかお寺を訪ね、行く先々で花祭りに出会いました。ウォーミングアップは妙本寺の広い参道下で。今日はポールがあるので難なく歩けました。そして桜の種類の多さに圧倒されました。
4/8 花祭り 三浦ネットポールウォーキング定例会。空は晴れ穏やかなお花見日和の心地よい1日でした。大巧寺からスタートし光明寺まで幾つかお寺を訪ね、行く先々で花祭りに出会いました。ウォーミングアップは妙本寺の広い参道下で。今日はポールがあるので難なく歩けました。そして桜の種類の多さに圧倒されました。 4/9 北鎌倉も快晴。@北鎌倉テラススタジオ121。青空に山桜が映えています。ウグイスの美しい声を聴きながら久々のテラスでストレッチング。テラスから見上げる六国見山の頂上は一面淡いさくら色。檜花粉以外良い季節になりましたね。マットに寝転びながら撮りました。
4/9 北鎌倉も快晴。@北鎌倉テラススタジオ121。青空に山桜が映えています。ウグイスの美しい声を聴きながら久々のテラスでストレッチング。テラスから見上げる六国見山の頂上は一面淡いさくら色。檜花粉以外良い季節になりましたね。マットに寝転びながら撮りました。 筋トレより花見 桜色がきれいな爽やかな青空が続いています。こんな時はアウトドアで五感を澄ますのも良いですね。花を咲かせるには、良い土壌(健康体)でなければ育ちにくいですよね。風にあたったり日光を浴びたりする効果は想像以上です。 新年度からスタートした介護予防教室の皆さんもお連れしますのでお楽しみに!
筋トレより花見 桜色がきれいな爽やかな青空が続いています。こんな時はアウトドアで五感を澄ますのも良いですね。花を咲かせるには、良い土壌(健康体)でなければ育ちにくいですよね。風にあたったり日光を浴びたりする効果は想像以上です。 新年度からスタートした介護予防教室の皆さんもお連れしますのでお楽しみに! 佐久市のシナノ、リハビリ対応ポール「しっかり2本杖」を発売|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
佐久市のシナノ、リハビリ対応ポール「しっかり2本杖」を発売|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト 介護予防運動教室終えて 午後からはサロンワークの水曜日!! 加圧トレーニングセッション!! あたたかい!! 気温21.3℃
介護予防運動教室終えて 午後からはサロンワークの水曜日!! 加圧トレーニングセッション!! あたたかい!! 気温21.3℃ コーチとして参加している佐久PW協会の新年度が始まりました。第一回の定例会に約60名の参加者が。待ってたよ〜、なんて声かけられて、毎回こっちが元気をもらってます。 去年から筋トレ担当にされたおかげで、班分けして私がつくとみんな筋トレさせられるんじゃないかとビクビクしてます😆今年もやりますよー。優しくね💕
コーチとして参加している佐久PW協会の新年度が始まりました。第一回の定例会に約60名の参加者が。待ってたよ〜、なんて声かけられて、毎回こっちが元気をもらってます。 去年から筋トレ担当にされたおかげで、班分けして私がつくとみんな筋トレさせられるんじゃないかとビクビクしてます😆今年もやりますよー。優しくね💕 4/10 上皇ご夫妻の結婚記念日は4月10日と話ながら今日の貯筋クラススタート。ウォーミングアップのあとはSTEPエクササイズに取り組みました。補助脚を増やして高くすると腿を90度位あげることになります。ポールの使用は自由。順番に色々な高さに挑戦して下肢強化。バランス能力向上。往復の鎌倉山は桜🌸ストリートで花吹雪のなかを走りました🚙
4/10 上皇ご夫妻の結婚記念日は4月10日と話ながら今日の貯筋クラススタート。ウォーミングアップのあとはSTEPエクササイズに取り組みました。補助脚を増やして高くすると腿を90度位あげることになります。ポールの使用は自由。順番に色々な高さに挑戦して下肢強化。バランス能力向上。往復の鎌倉山は桜🌸ストリートで花吹雪のなかを走りました🚙 【花見三昧】 4/6〜10 ほぼ毎日花見 嬉しい春です
【花見三昧】 4/6〜10 ほぼ毎日花見 嬉しい春です 『ストレッチポールと出会えてよかった!!』
『ストレッチポールと出会えてよかった!!』 4/11 毎週金曜日午前中は東京渋谷まで出前教室です。雨予報でしたが曇り空のまま夕方まで濡れずにすみました。渋谷PWはこのクラス初のウォーミングアップを1つ1つ説明しながら筋トレまで。そしてポールウォーキング、右手左足~イチニイチニ。肘も引けて皆さん綺麗に歩けました。来週は自己紹介もしなくちゃね。午後は三軒茶屋までまた野暮用でした。
4/11 毎週金曜日午前中は東京渋谷まで出前教室です。雨予報でしたが曇り空のまま夕方まで濡れずにすみました。渋谷PWはこのクラス初のウォーミングアップを1つ1つ説明しながら筋トレまで。そしてポールウォーキング、右手左足~イチニイチニ。肘も引けて皆さん綺麗に歩けました。来週は自己紹介もしなくちゃね。午後は三軒茶屋までまた野暮用でした。 春ビタミン色/水仙〜 カタクリ〜 枝垂れ桜〜と春を見にブラブラPW〜❗️ ソメイヨシノはもう少し先に〜ww 菜園始めの玉葱の春植え作業〜 冬越し玉葱は育っています〜 この調子でじゃがいも種植えも来週には〜 このご時世空いてる土が無いくらい菜園中野菜だらけに〜 帰宅後やっと土弄りで 瓢箪型の「陶函」作陶〜 小学孫のクラス体験学習「陶芸」の教材試作作り〜 と忙しい1日でした❗️ 明日も🌸花見PW散策でお出掛けです。
春ビタミン色/水仙〜 カタクリ〜 枝垂れ桜〜と春を見にブラブラPW〜❗️ ソメイヨシノはもう少し先に〜ww 菜園始めの玉葱の春植え作業〜 冬越し玉葱は育っています〜 この調子でじゃがいも種植えも来週には〜 このご時世空いてる土が無いくらい菜園中野菜だらけに〜 帰宅後やっと土弄りで 瓢箪型の「陶函」作陶〜 小学孫のクラス体験学習「陶芸」の教材試作作り〜 と忙しい1日でした❗️ 明日も🌸花見PW散策でお出掛けです。 www.tokyo-park.or.jp
www.tokyo-park.or.jp 本日は、杉ポ卒業生のきまポ(きままにポール歩きの会)に参加🌸 三鷹駅から小金井公園とその周辺を8㎞。 たくさんの桜🌸を楽しみました。
本日は、杉ポ卒業生のきまポ(きままにポール歩きの会)に参加🌸 三鷹駅から小金井公園とその周辺を8㎞。 たくさんの桜🌸を楽しみました。 長谷川 弘道さんの動画
長谷川 弘道さんの動画 2025.4.7〜13 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 健康チェア体操 21名 ☺︎健康体操サークル 13名 ☺︎スマイルポールウォーキング 12名 ☺︎青空ポールウォーキング 7名 ☺︎青少年部部会 ☺︎上鶴間公民館利用団体総会 ☺︎上溝新サークル活動ライン打合せ ☺︎e.J.LEAGUE2025横浜F・マリノス クラブ代表決定戦
2025.4.7〜13 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 健康チェア体操 21名 ☺︎健康体操サークル 13名 ☺︎スマイルポールウォーキング 12名 ☺︎青空ポールウォーキング 7名 ☺︎青少年部部会 ☺︎上鶴間公民館利用団体総会 ☺︎上溝新サークル活動ライン打合せ ☺︎e.J.LEAGUE2025横浜F・マリノス クラブ代表決定戦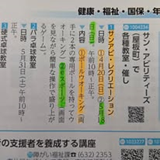 サン・アビリテーズにてポールウォーキング教室行います。 4月20日(日)10:00~12:00 定員:20名 申し込み方法:サン・アビリテーズ 028-656-1458 13日現在5名ですのでお友達お誘いでご参加ください。
サン・アビリテーズにてポールウォーキング教室行います。 4月20日(日)10:00~12:00 定員:20名 申し込み方法:サン・アビリテーズ 028-656-1458 13日現在5名ですのでお友達お誘いでご参加ください。 佐久ポールウォーキング協会より 雨の🌸花見散策で、 小雨(は決行)でしたが花冷えの中雨も感じない参加等、寒い寒いと言いながらの約1時間のPW散策でした^_^ 皆さん〜お疲れ様でした〜 桜🌸は写メの通り、レンギョウや水仙のイエローが鮮やかな「さくラさく小径」〜 信濃毎日新聞社の記者さんも参加し、皆さんを取材して居ました。 今日収穫の飴は〜ハート❤️〜の梅味でした〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 雨の🌸花見散策で、 小雨(は決行)でしたが花冷えの中雨も感じない参加等、寒い寒いと言いながらの約1時間のPW散策でした^_^ 皆さん〜お疲れ様でした〜 桜🌸は写メの通り、レンギョウや水仙のイエローが鮮やかな「さくラさく小径」〜 信濃毎日新聞社の記者さんも参加し、皆さんを取材して居ました。 今日収穫の飴は〜ハート❤️〜の梅味でした〜ww 4/15 雨天のためPW活動は室内に変更。ところが教室を始めると窓の外は青空に☀ そこで、ウォーミングアップのあと 先日も雨のため室内お弁当花見になって行けなかった桜を観に御所が丘丹後ガ谷公園迄歩きました。かなり強い花散らしの雨風でしたので花びらは道路をピンクに染めるほど落ちていましたが風情があって皆満喫。公園の桜の木のしたでポールじゃんけんなどで遊びました。ドウダンツツジが見事でした。
4/15 雨天のためPW活動は室内に変更。ところが教室を始めると窓の外は青空に☀ そこで、ウォーミングアップのあと 先日も雨のため室内お弁当花見になって行けなかった桜を観に御所が丘丹後ガ谷公園迄歩きました。かなり強い花散らしの雨風でしたので花びらは道路をピンクに染めるほど落ちていましたが風情があって皆満喫。公園の桜の木のしたでポールじゃんけんなどで遊びました。ドウダンツツジが見事でした。 鎌倉SUGATA4月より 毎月第1、第3水曜日 10時から11時30分 ノルディックスローウォーキング となります 前回は雨天の影響で中止🥲 本日☀️初レッスン 初体験者の方も参加 レディースDAYとなりました! 今年の桜はまだ楽しめる👍 葉桜が目立つ様になってきましたが、 とても気持ちの良いウォーキングとなりました! 次回は5月7日です 皆様のご参加お待ちしております♪ #ノルディックウォーキング #ノルディックスローウォーキング #フィンランド #SUGATA #鎌倉
鎌倉SUGATA4月より 毎月第1、第3水曜日 10時から11時30分 ノルディックスローウォーキング となります 前回は雨天の影響で中止🥲 本日☀️初レッスン 初体験者の方も参加 レディースDAYとなりました! 今年の桜はまだ楽しめる👍 葉桜が目立つ様になってきましたが、 とても気持ちの良いウォーキングとなりました! 次回は5月7日です 皆様のご参加お待ちしております♪ #ノルディックウォーキング #ノルディックスローウォーキング #フィンランド #SUGATA #鎌倉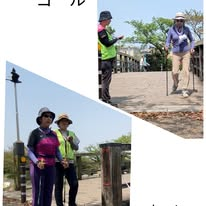 #船橋ウォーキングソサイエティ #握力計測 #1km計測 #土曜日海老川コース 毎年毎に計測して 体力の変化を知ったら 手立てが大切ね 計測の合間に #お口の筋肉はパタカでトレーニング #骨盤底筋トレーニング 2025/4/19
#船橋ウォーキングソサイエティ #握力計測 #1km計測 #土曜日海老川コース 毎年毎に計測して 体力の変化を知ったら 手立てが大切ね 計測の合間に #お口の筋肉はパタカでトレーニング #骨盤底筋トレーニング 2025/4/19 本日は、手賀沼遊歩道開通した為歩いてみました。 湖畔を歩くのは気持ちがいいです。 八重桜、菜の花、ネモフィラなどが咲き誇り、コブハクチョウもゆったりとくつろいでいました。 来月は水元公園です。
本日は、手賀沼遊歩道開通した為歩いてみました。 湖畔を歩くのは気持ちがいいです。 八重桜、菜の花、ネモフィラなどが咲き誇り、コブハクチョウもゆったりとくつろいでいました。 来月は水元公園です。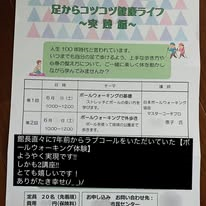 ありがたき幸せ♡ 7年越し♡ 【ポールウォーキング体験会】を某市民センターの市民講座で2講座開催させていただきます!! 館長にラブコールをいただいて7年目にしてようやく開催です!(この間、館長の移動がありなかなか実現に至らず) 他のセンターのご依頼は1講座、室内のみ、外歩きは行うことができなかったのですが今回は2講座の外歩きができます! ちなみにですね! ・1講座目は室内でポールウォーキング体験、ポールの長さの合わせ方から準備運動、歩き方、ポール筋トレなどをおこないます。 ・2講座目は室内で外歩き前にボールを使ってセルフフットケアー足はからだを支える土を体感していただいてから⇒ウォーキングコース(15分程度)をポールで歩きます!(雨天/室内) 今回の講座がご参加された皆様にとって、少しでもお役に立つことができれば幸いです🫶 発見 気づき 自信 楽しさ 喜び etc. 私にとってとても楽しみな講座です! 館長に感謝です🙏✨️✨️✨️✨️ #ポールウォーキング体験会 #フットセラピスト #セルフフットケア #足はからだを支える土台 #ポールウォーキング #歩行動作 #歩行能力 #歩けるからだ #姿勢改善 #バランス力 #転倒予防 #歩幅 #全身運動 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #市民講座 #出張講座 ※ポールウォーキングの写真は参考までに
ありがたき幸せ♡ 7年越し♡ 【ポールウォーキング体験会】を某市民センターの市民講座で2講座開催させていただきます!! 館長にラブコールをいただいて7年目にしてようやく開催です!(この間、館長の移動がありなかなか実現に至らず) 他のセンターのご依頼は1講座、室内のみ、外歩きは行うことができなかったのですが今回は2講座の外歩きができます! ちなみにですね! ・1講座目は室内でポールウォーキング体験、ポールの長さの合わせ方から準備運動、歩き方、ポール筋トレなどをおこないます。 ・2講座目は室内で外歩き前にボールを使ってセルフフットケアー足はからだを支える土を体感していただいてから⇒ウォーキングコース(15分程度)をポールで歩きます!(雨天/室内) 今回の講座がご参加された皆様にとって、少しでもお役に立つことができれば幸いです🫶 発見 気づき 自信 楽しさ 喜び etc. 私にとってとても楽しみな講座です! 館長に感謝です🙏✨️✨️✨️✨️ #ポールウォーキング体験会 #フットセラピスト #セルフフットケア #足はからだを支える土台 #ポールウォーキング #歩行動作 #歩行能力 #歩けるからだ #姿勢改善 #バランス力 #転倒予防 #歩幅 #全身運動 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #市民講座 #出張講座 ※ポールウォーキングの写真は参考までに #ポールウォーキング #桜の散歩道
#ポールウォーキング #桜の散歩道 チューリップ🌷チューリップ🌷チューリップであふれたここは横浜公園🌷 金曜日みなとみらいのポールウォーキング教室に参加してきました。 指導頂くのは酒井尚美さんと原庸子さんの2名の先生。 きちんとフォーム きちんとストレッチ きついわぁ💦😆 しっかりコース 学び満載でした😃 海のそばは気持ちいいですね💕💕 毎月 第1金曜日は酒井さんのみなとみらいを歩く会10時桜木町駅集合 第3金曜日は酒井、原美女お二人のビシビシ厳しく楽しい会 10時関内横浜スタジアム集合 参加費1,000円 皆さまご参加下さい💕
チューリップ🌷チューリップ🌷チューリップであふれたここは横浜公園🌷 金曜日みなとみらいのポールウォーキング教室に参加してきました。 指導頂くのは酒井尚美さんと原庸子さんの2名の先生。 きちんとフォーム きちんとストレッチ きついわぁ💦😆 しっかりコース 学び満載でした😃 海のそばは気持ちいいですね💕💕 毎月 第1金曜日は酒井さんのみなとみらいを歩く会10時桜木町駅集合 第3金曜日は酒井、原美女お二人のビシビシ厳しく楽しい会 10時関内横浜スタジアム集合 参加費1,000円 皆さまご参加下さい💕 🎉【日式健走 Basic Coach】培訓課程圓滿結束啦!👏🎌 4/19(六)我們在滿滿熱情與專業中, 完成了這場由 日本健走杖協會 NPWA 唯一授權的海外培訓課程✨ 📚 課程內容豐富實用, 每位學員都全力投入,不只學習到專業知識, 也體會到日式健走的獨特魅力 💪 👣 一步一腳印,大家都邁出了屬於自己的專業之路, 未來也將成為推廣健康生活的推手!👏 💡如果你也對日式健走有興趣, 想參與更多活動, 記得持續關注我們的最新消息唷!📣 【日式健走 Advance Coach 培訓課程】 ➡️https://forms.gle/5po6HgLUfUD4ZS4C6 ❗此課程限定取得「日本健走杖健走Basic Coach」認證資格者參加❗
🎉【日式健走 Basic Coach】培訓課程圓滿結束啦!👏🎌 4/19(六)我們在滿滿熱情與專業中, 完成了這場由 日本健走杖協會 NPWA 唯一授權的海外培訓課程✨ 📚 課程內容豐富實用, 每位學員都全力投入,不只學習到專業知識, 也體會到日式健走的獨特魅力 💪 👣 一步一腳印,大家都邁出了屬於自己的專業之路, 未來也將成為推廣健康生活的推手!👏 💡如果你也對日式健走有興趣, 想參與更多活動, 記得持續關注我們的最新消息唷!📣 【日式健走 Advance Coach 培訓課程】 ➡️https://forms.gle/5po6HgLUfUD4ZS4C6 ❗此課程限定取得「日本健走杖健走Basic Coach」認證資格者參加❗ 4月20日に今年度初となるスキルアップ研修会東京会場を開催しました。 参加者29名と多くのコーチが集まって下さいました。 今年度のテーマはマニュアルに沿った指導法と用語の統一ということで、BCマニュアルの補足説明を重点的に行いました。 皆さん熱心で非常に充実したスキルアップ研修会となりました。 次回開催は7月6日(日)長野県佐久市 となります。 多くのコーチの参加をおまちしております。
4月20日に今年度初となるスキルアップ研修会東京会場を開催しました。 参加者29名と多くのコーチが集まって下さいました。 今年度のテーマはマニュアルに沿った指導法と用語の統一ということで、BCマニュアルの補足説明を重点的に行いました。 皆さん熱心で非常に充実したスキルアップ研修会となりました。 次回開催は7月6日(日)長野県佐久市 となります。 多くのコーチの参加をおまちしております。 . . 【第39回宮古島トライアスロン大会】 2025.4.20 無事に2回目完走しました! 去年より1時間早くGOAL 🏁 自分自身の目標達成😭 スイムはバトルを避けて 1番左から🏊♀️ 潮の流れはほとんどなく ほどよい距離感で泳げてスイムアップ バイクは向かい風も強くなかったので 淡々と漕いでゆく 前半つま先と脛が痺れ始め… シューズのワイヤーを全開にしたら改善✨ 100km過ぎてからなぜか脚がよく動き出す んー、もっと早くからギアを入れたい🥲 ランも淡々と 自分のペースを崩さず 最後まで走る 辛すぎないペースを意識 序盤、寒さを感じヤバイなと… バナナ、餅、レモン🍋食べてたら落ち着く 25km過ぎ? 恵みの雨が降ってきた!気持ちー✨ 去年の11月から トライアスロンのプロに 練習メニューを組んでいただいたこと 結果に繋がったと思う 練習の量、質のあるメニュー 未熟の私にとって学ぶことばかり 真謝坂をあっという間に感じたのも コーチの練習のおかげ “ 絶対に欲張らない ” 常に胸におき、レースに挑む 練習してきたことは裏切らない 結果がついてきたので本当に嬉しい マキさんには感謝の気持ちでいっぱいです🙏 @nishiuchimaki 一緒に練習してきた、あや姉✨ 今年もありがとう😊😊 トライアスリートの大先輩方とも 一緒に練習させていただいたりアドバイスを沢山いただきました🙏 カラダメンテナンスも大変お世話になりました🙇♀️🙇♀️ @hiyori_sports_miyako @shinkyu_shin 設営•運営の皆様、ボランティアの皆様、 レスキュー関係者の方々、 沿道の応援して下さった皆様 たくさんの方々の力で大会を無事に完走することが出来ました🙇♀️ ありがとうございました!!! @miyakojima_triathlon また来年😆😆 #宮古島トライアスロン #トライ女子 #完走 #ちゅら風 #超える目標は自分自身 #神様は見ている #練習は嘘つかない #鬼コーチは女神 #また来年 #ゴミ拾いまでがトライアスロン
. . 【第39回宮古島トライアスロン大会】 2025.4.20 無事に2回目完走しました! 去年より1時間早くGOAL 🏁 自分自身の目標達成😭 スイムはバトルを避けて 1番左から🏊♀️ 潮の流れはほとんどなく ほどよい距離感で泳げてスイムアップ バイクは向かい風も強くなかったので 淡々と漕いでゆく 前半つま先と脛が痺れ始め… シューズのワイヤーを全開にしたら改善✨ 100km過ぎてからなぜか脚がよく動き出す んー、もっと早くからギアを入れたい🥲 ランも淡々と 自分のペースを崩さず 最後まで走る 辛すぎないペースを意識 序盤、寒さを感じヤバイなと… バナナ、餅、レモン🍋食べてたら落ち着く 25km過ぎ? 恵みの雨が降ってきた!気持ちー✨ 去年の11月から トライアスロンのプロに 練習メニューを組んでいただいたこと 結果に繋がったと思う 練習の量、質のあるメニュー 未熟の私にとって学ぶことばかり 真謝坂をあっという間に感じたのも コーチの練習のおかげ “ 絶対に欲張らない ” 常に胸におき、レースに挑む 練習してきたことは裏切らない 結果がついてきたので本当に嬉しい マキさんには感謝の気持ちでいっぱいです🙏 @nishiuchimaki 一緒に練習してきた、あや姉✨ 今年もありがとう😊😊 トライアスリートの大先輩方とも 一緒に練習させていただいたりアドバイスを沢山いただきました🙏 カラダメンテナンスも大変お世話になりました🙇♀️🙇♀️ @hiyori_sports_miyako @shinkyu_shin 設営•運営の皆様、ボランティアの皆様、 レスキュー関係者の方々、 沿道の応援して下さった皆様 たくさんの方々の力で大会を無事に完走することが出来ました🙇♀️ ありがとうございました!!! @miyakojima_triathlon また来年😆😆 #宮古島トライアスロン #トライ女子 #完走 #ちゅら風 #超える目標は自分自身 #神様は見ている #練習は嘘つかない #鬼コーチは女神 #また来年 #ゴミ拾いまでがトライアスロン 20日宇都宮市サン・アビリティーズでのポールウォーキング教室グラウンド周りを歩きました。
20日宇都宮市サン・アビリティーズでのポールウォーキング教室グラウンド周りを歩きました。 4/24 教会の裏山に山藤!腰越なごやかセンターの貯筋クラスは貯筋棒を使って筋トレ。来月11日で41年続いたLESANGES西鎌倉店が閉店すると知って有志10人で運動後行ってきました。常連さんが間際に電話で席を確保できLUCKY💕
4/24 教会の裏山に山藤!腰越なごやかセンターの貯筋クラスは貯筋棒を使って筋トレ。来月11日で41年続いたLESANGES西鎌倉店が閉店すると知って有志10人で運動後行ってきました。常連さんが間際に電話で席を確保できLUCKY💕 船橋ウォーキングソサイエティ 2本のポールを使うウォーキング 木曜日定例会 うっすら汗をかき1kmと握力の計測が終了 定例会後は第15回定期総会を開催 スタートがあれば けじめのゴールがある。 3年後にむかい 一層の努力を重ねる スタッフの想いが一致! よい話し合いが出来ました。
船橋ウォーキングソサイエティ 2本のポールを使うウォーキング 木曜日定例会 うっすら汗をかき1kmと握力の計測が終了 定例会後は第15回定期総会を開催 スタートがあれば けじめのゴールがある。 3年後にむかい 一層の努力を重ねる スタッフの想いが一致! よい話し合いが出来ました。 4/26 (訳あって深夜便) 茨城県小町の里ポールウォーキングで花山歩き。土浦に向かう常磐線が荒川沖でストップ!その先で人身事故とのアナウンス。復旧の見通し悪く 土浦待合せの友達が急遽荒川沖駅に🚙で駆けつけてくれ、30分遅刻で集合場所「小町の里」に行くことができました。ここはパラグライダーのスクールがあり、頭の上は鳶と見間違えるほどたくさんのパラグライダーが優雅に飛んでいます。1月以来の訪問ですがハイキングコースは初めて。スタート前に近くの農家の採れ採れ蕗をGET。花の写真は明日UPに。
4/26 (訳あって深夜便) 茨城県小町の里ポールウォーキングで花山歩き。土浦に向かう常磐線が荒川沖でストップ!その先で人身事故とのアナウンス。復旧の見通し悪く 土浦待合せの友達が急遽荒川沖駅に🚙で駆けつけてくれ、30分遅刻で集合場所「小町の里」に行くことができました。ここはパラグライダーのスクールがあり、頭の上は鳶と見間違えるほどたくさんのパラグライダーが優雅に飛んでいます。1月以来の訪問ですがハイキングコースは初めて。スタート前に近くの農家の採れ採れ蕗をGET。花の写真は明日UPに。 4/27昨日アップできなかった写真集(これでも抜粋) コメ欄にいつものように一言ずつ入れました 顔はそのまま・・
4/27昨日アップできなかった写真集(これでも抜粋) コメ欄にいつものように一言ずつ入れました 顔はそのまま・・ 2025.4.21〜27 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操19名 ☺︎青少年指導委員総会(欠席) ☺︎チームTシャツ配布 ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス19名 ☺︎相模原市文化協会役員会議 ☺︎スマイル星が丘ポールウォーキング6名 ☺︎上溝シニアサポートCSWメール ☺︎青少年指導委員横山公園ウォーク(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 新年度活動に関する書類まとめ ☺︎ティンカーベル練習参加
2025.4.21〜27 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操19名 ☺︎青少年指導委員総会(欠席) ☺︎チームTシャツ配布 ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス19名 ☺︎相模原市文化協会役員会議 ☺︎スマイル星が丘ポールウォーキング6名 ☺︎上溝シニアサポートCSWメール ☺︎青少年指導委員横山公園ウォーク(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 新年度活動に関する書類まとめ ☺︎ティンカーベル練習参加 4/27 逗子椿公園も藤の季節になりました。毎年見事な白・紫の、藤に心躍ります🎶 今日も爽やかな五月晴れでしたが少々気温が上がり 歩き続けるのを断念した方が一人。新米ACさんがウォーミングアップひとつ挑戦されました。今後を期待します。夏に向かって休憩する公園には影が必要です。COOLDOWNの代わりにリンパ体操をして今日はおしまい。駅前の春祭りをホームから観覧🎶
4/27 逗子椿公園も藤の季節になりました。毎年見事な白・紫の、藤に心躍ります🎶 今日も爽やかな五月晴れでしたが少々気温が上がり 歩き続けるのを断念した方が一人。新米ACさんがウォーミングアップひとつ挑戦されました。今後を期待します。夏に向かって休憩する公園には影が必要です。COOLDOWNの代わりにリンパ体操をして今日はおしまい。駅前の春祭りをホームから観覧🎶 桜はあきらめていたのに、八重桜が待っていてくれた〜🌸幸せ🩷 笠間は春の大イベント陶炎祭(ひまつり)が29日から開催されます。すでにテントが並んだ会場をちょっと覗きながら、ポールを使って体を整えたりウォーキングの約2時間でした。 来月はふるさと案内ガイドさんの説明付きで、笠間稲荷を散策します。
桜はあきらめていたのに、八重桜が待っていてくれた〜🌸幸せ🩷 笠間は春の大イベント陶炎祭(ひまつり)が29日から開催されます。すでにテントが並んだ会場をちょっと覗きながら、ポールを使って体を整えたりウォーキングの約2時間でした。 来月はふるさと案内ガイドさんの説明付きで、笠間稲荷を散策します。 笠間トモアのポールウォーキング講座 2025年の上期スタートしました🎉 今日の参加者13名。男性4名・女性9名。年齢は50歳から84歳。今日初めて参加された方が3名。その感想は、、、 「見るのと、やるのとでは、本当に大違いでした!メンバー全員の雰囲気も良く、楽しんで参加できました。」 嬉しい言葉です😊先頭を歩いた鈴木コーチが「ポールウォーキングは楽しくおしゃべりしながら歩いていいんですよ」と声をかけてくれたおかげで、いつにも増して賑やかな講座でした😊こういう声かけ大好きです👍 今日は肘の引き方をお話ししたら、それはお茶に通じますね🍵との声が。それが 面白くてまたみんなでひと盛り上がりしました😆5月が楽しみです。
笠間トモアのポールウォーキング講座 2025年の上期スタートしました🎉 今日の参加者13名。男性4名・女性9名。年齢は50歳から84歳。今日初めて参加された方が3名。その感想は、、、 「見るのと、やるのとでは、本当に大違いでした!メンバー全員の雰囲気も良く、楽しんで参加できました。」 嬉しい言葉です😊先頭を歩いた鈴木コーチが「ポールウォーキングは楽しくおしゃべりしながら歩いていいんですよ」と声をかけてくれたおかげで、いつにも増して賑やかな講座でした😊こういう声かけ大好きです👍 今日は肘の引き方をお話ししたら、それはお茶に通じますね🍵との声が。それが 面白くてまたみんなでひと盛り上がりしました😆5月が楽しみです。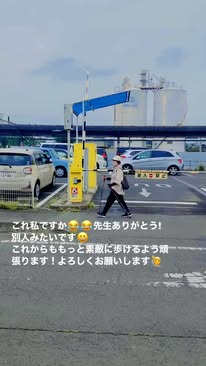 生徒さんの上達ぶりがすごくて、自慢したくなりました😆
生徒さんの上達ぶりがすごくて、自慢したくなりました😆 世の中大型連休の始まり〜ww 年金暮らしシニアには・・・ この不順天気で今朝の浅間山は冠雪に〜 この花分かる方は〜? 林檎🍎の花でした。 まじまじ見ると意外とチャーミングな色合いでかわいい花ですね。 今日はシードルさんのリンゴ園/小諸に伐採木材を頂きに〜❗️ 付近に有る高圧線鉄塔が珍しく真下より・・!
世の中大型連休の始まり〜ww 年金暮らしシニアには・・・ この不順天気で今朝の浅間山は冠雪に〜 この花分かる方は〜? 林檎🍎の花でした。 まじまじ見ると意外とチャーミングな色合いでかわいい花ですね。 今日はシードルさんのリンゴ園/小諸に伐採木材を頂きに〜❗️ 付近に有る高圧線鉄塔が珍しく真下より・・! 4/29 昭和100年、平成37年、令和7年、2025年の今日はお天気も良く爽やかな日射しだったので久々のフラセンに行ってきました。ここは鎌倉市大船の桃源郷。春の花・初夏の花が咲き狂って!いました。バラ園 ぼたん苑 芍薬苑 ミツバツツジの群れ 広場のネモフィラの大河 植物園のなかも蜜蜂の展示会、色鉛筆画展、エビネ展等々見回れない位。
4/29 昭和100年、平成37年、令和7年、2025年の今日はお天気も良く爽やかな日射しだったので久々のフラセンに行ってきました。ここは鎌倉市大船の桃源郷。春の花・初夏の花が咲き狂って!いました。バラ園 ぼたん苑 芍薬苑 ミツバツツジの群れ 広場のネモフィラの大河 植物園のなかも蜜蜂の展示会、色鉛筆画展、エビネ展等々見回れない位。 4/30 今日も朝からピカピカの青空。 飛行機雲がくっきり空に4本の白線を描いていました。鴬の歌をBGMに体操終了後はテラスでお茶会開催。本場のエチオピアの挽きたてコーヒーを味わいながら、手作りのヴィーガンプリンやオレンジピールのケーキを頂きました。私のお気に入りは優しい味の蕗!で一人で残さず頂きました。帰りはおむすび庵へ。
4/30 今日も朝からピカピカの青空。 飛行機雲がくっきり空に4本の白線を描いていました。鴬の歌をBGMに体操終了後はテラスでお茶会開催。本場のエチオピアの挽きたてコーヒーを味わいながら、手作りのヴィーガンプリンやオレンジピールのケーキを頂きました。私のお気に入りは優しい味の蕗!で一人で残さず頂きました。帰りはおむすび庵へ。 私は月曜日の9時から 5月12.26日に担当します。 ストレッチとリズム体操で一日を スタートして行きましょう❣️ よろしくお願いします。
私は月曜日の9時から 5月12.26日に担当します。 ストレッチとリズム体操で一日を スタートして行きましょう❣️ よろしくお願いします。 写真1件
写真1件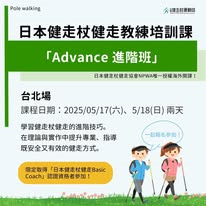 【日式健走 Advance Coach 培訓課程】 日式健走進階教練培訓課程來了~ 兩日的課程,帶你深入學習健走杖運動的進階技巧,在理論與實作中不斷突破增進能力~ 想要規劃與教導一般民眾學習日式健走的你,趕緊來參加進階班! ❗此課程限定取得「日本健走杖健走Basic Coach」認證資格者參加❗ 課程日期:2025/5/17(六)、5/18(日) 9am~17pm 課程地點:大同運動中心 ‧滿10人開班,上限20位‧ 詳細課程辦法及規範請見報名表 ➡️https://forms.gle/5po6HgLUfUD4ZS4C6 期待課程中與你相見,共同學習❤️
【日式健走 Advance Coach 培訓課程】 日式健走進階教練培訓課程來了~ 兩日的課程,帶你深入學習健走杖運動的進階技巧,在理論與實作中不斷突破增進能力~ 想要規劃與教導一般民眾學習日式健走的你,趕緊來參加進階班! ❗此課程限定取得「日本健走杖健走Basic Coach」認證資格者參加❗ 課程日期:2025/5/17(六)、5/18(日) 9am~17pm 課程地點:大同運動中心 ‧滿10人開班,上限20位‧ 詳細課程辦法及規範請見報名表 ➡️https://forms.gle/5po6HgLUfUD4ZS4C6 期待課程中與你相見,共同學習❤️ 今年もやります!5月17日(土)工場祭。 毎年5月に行っており、昨年は500名ちょっとのお客様にご来場いただきました。 ・ここでしか買えないアウトレット品 ・こどもも楽しめるアルミパイプを使ったクラフト体験 ・工場見学 ・佐久長聖高校 ダンス部と吹奏楽部 ・浅間中学校 吹奏楽部(今年初参加) などなど 昨年大人気のブースで行列ができてしまった部分のオペレーションを見直し、快適に楽しんでいただけるように工夫しています。 皆さんお待ちしております(^^)/
今年もやります!5月17日(土)工場祭。 毎年5月に行っており、昨年は500名ちょっとのお客様にご来場いただきました。 ・ここでしか買えないアウトレット品 ・こどもも楽しめるアルミパイプを使ったクラフト体験 ・工場見学 ・佐久長聖高校 ダンス部と吹奏楽部 ・浅間中学校 吹奏楽部(今年初参加) などなど 昨年大人気のブースで行列ができてしまった部分のオペレーションを見直し、快適に楽しんでいただけるように工夫しています。 皆さんお待ちしております(^^)/ 『ハッピーフェス対ポールウオーキング参加者募集!』
『ハッピーフェス対ポールウオーキング参加者募集!』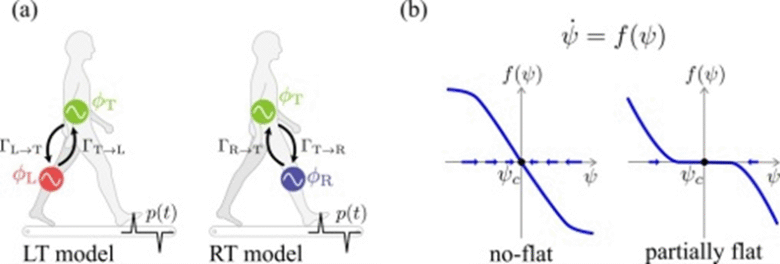 図 1。(a) 本研究で提案する 2 つの位相振動子結合モデル。歩行中、脚と体幹は単一のリズムを持つものとし、それぞれに 1 つの振動子が割り当てられている。2 つの位相振動子は、外部摂動や確率的変動の影響を受ける。 (b)相対位相ψの自発的ダイナミクスを支配する関数f ( ψ ) の形状とその制御機構との対応関係。ψがψ = ψ cに固定されていると仮定する。f ( ψ ) が左側に示すようにψ c付近で平坦でない場合、 ψのわずかなシフトでも敏感に補正される。一方、f ( ψ ) が右側に示すようにψ = ψ c付近で平坦な区間を持つ場合、 ψがある値にシフトするまでは積極的に制御は行われない。
図 1。(a) 本研究で提案する 2 つの位相振動子結合モデル。歩行中、脚と体幹は単一のリズムを持つものとし、それぞれに 1 つの振動子が割り当てられている。2 つの位相振動子は、外部摂動や確率的変動の影響を受ける。 (b)相対位相ψの自発的ダイナミクスを支配する関数f ( ψ ) の形状とその制御機構との対応関係。ψがψ = ψ cに固定されていると仮定する。f ( ψ ) が左側に示すようにψ c付近で平坦でない場合、 ψのわずかなシフトでも敏感に補正される。一方、f ( ψ ) が右側に示すようにψ = ψ c付近で平坦な区間を持つ場合、 ψがある値にシフトするまでは積極的に制御は行われない。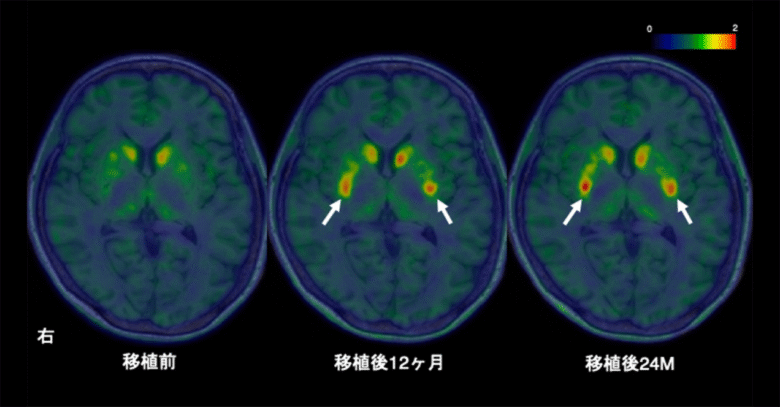 3. 波及効果、今後の予定
3. 波及効果、今後の予定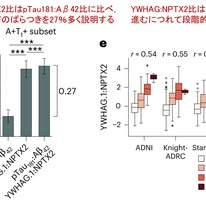 アルツハイマー病(AD)は,アミロイドβやタウタンパクの蓄積を特徴とする神経変性疾患ですが,認知機能の低下の進行速度には個人差が非常に大きいことが知られています.また脳内にアミロイドβやタウが蓄積していても,認知機能が保たれている人と,急速に悪化してしまう人が存在するのはなぜか・・・この問いは,これまでのバイオマーカー研究では十分に説明されてきませんでした.
アルツハイマー病(AD)は,アミロイドβやタウタンパクの蓄積を特徴とする神経変性疾患ですが,認知機能の低下の進行速度には個人差が非常に大きいことが知られています.また脳内にアミロイドβやタウが蓄積していても,認知機能が保たれている人と,急速に悪化してしまう人が存在するのはなぜか・・・この問いは,これまでのバイオマーカー研究では十分に説明されてきませんでした.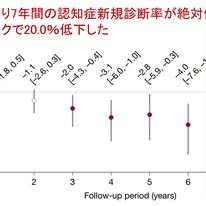 帯状疱疹の原因ウイルスである水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)をはじめとするヘルペスウイルスが,認知症の発症に関与している可能性が指摘されています(当科.森らの総説を参照;https://www.jstage.jst.go.jp/…/65_cn-002047/_pdf/-char/ja).これに関連して,ワクチンが認知症の発症リスクを抑えるのではないかという議論が活発になっています.そうした中,スタンフォード大学の研究チームは,Nature誌に注目すべき論文を発表しました.
帯状疱疹の原因ウイルスである水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)をはじめとするヘルペスウイルスが,認知症の発症に関与している可能性が指摘されています(当科.森らの総説を参照;https://www.jstage.jst.go.jp/…/65_cn-002047/_pdf/-char/ja).これに関連して,ワクチンが認知症の発症リスクを抑えるのではないかという議論が活発になっています.そうした中,スタンフォード大学の研究チームは,Nature誌に注目すべき論文を発表しました.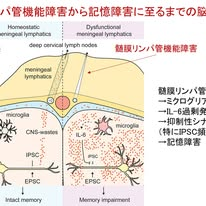 髄膜に「髄膜リンパ管」があることが最近,明らかになりました.脳脊髄液に含まれる老廃物を排出する重要な通路として作用しますが,この機能が低下すると何が起こるのか?Cell誌に掲載されたワシントン大学セントルイス校等の研究グループは,髄膜リンパ管はミクログリアと協調しながら,神経の興奮と抑制のバランス(E/Iバランス)を保ち,記憶機能に大きな影響を与えていることを明らかにしました.言い換えると,髄膜リンパ管の機能障害は大脳皮質のE/Iバランスを崩し,記憶障害を引き起こすことをマウスモデルで示しました.この変化はミクログリア活性化を介して,IL-6が過剰に発現することで生じるようです.
髄膜に「髄膜リンパ管」があることが最近,明らかになりました.脳脊髄液に含まれる老廃物を排出する重要な通路として作用しますが,この機能が低下すると何が起こるのか?Cell誌に掲載されたワシントン大学セントルイス校等の研究グループは,髄膜リンパ管はミクログリアと協調しながら,神経の興奮と抑制のバランス(E/Iバランス)を保ち,記憶機能に大きな影響を与えていることを明らかにしました.言い換えると,髄膜リンパ管の機能障害は大脳皮質のE/Iバランスを崩し,記憶障害を引き起こすことをマウスモデルで示しました.この変化はミクログリア活性化を介して,IL-6が過剰に発現することで生じるようです.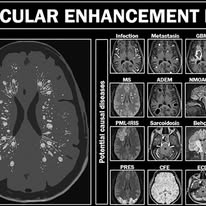 図1はJ Neuroradiol誌にフランスから発表された総説からのものです.近年注目されている血管周囲造影効果(perivascular enhancement: PVE)パターンについて豊富な画像とともに詳細に解説しています.まず図の中央には,T1強調造影MRIにおける典型的なPVEがイラスト化されています.大脳白質に多数の点状および線状の造影効果が広がっていますが,これらはPVS(血管周囲腔;図2)に沿って描出されているものです.つまりこの「点と線の造影」に着目したものがPVEです.
図1はJ Neuroradiol誌にフランスから発表された総説からのものです.近年注目されている血管周囲造影効果(perivascular enhancement: PVE)パターンについて豊富な画像とともに詳細に解説しています.まず図の中央には,T1強調造影MRIにおける典型的なPVEがイラスト化されています.大脳白質に多数の点状および線状の造影効果が広がっていますが,これらはPVS(血管周囲腔;図2)に沿って描出されているものです.つまりこの「点と線の造影」に着目したものがPVEです.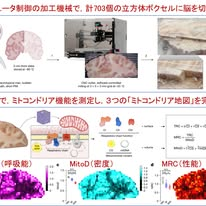 私たちの脳は膨大なエネルギーを消費しながら活動しています.このエネルギーは主にミトコンドリアによる酸化的リン酸化(OXPHOS)によって供給されています.このためミトコンドリアの機能は神経活動や神経疾患にも深く関わっています.今回,コロンビア大学などの国際共同研究グループから,ヒト脳のミトコンドリア機能の分布を初めて可視化した研究がNature誌に報告されました.
私たちの脳は膨大なエネルギーを消費しながら活動しています.このエネルギーは主にミトコンドリアによる酸化的リン酸化(OXPHOS)によって供給されています.このためミトコンドリアの機能は神経活動や神経疾患にも深く関わっています.今回,コロンビア大学などの国際共同研究グループから,ヒト脳のミトコンドリア機能の分布を初めて可視化した研究がNature誌に報告されました.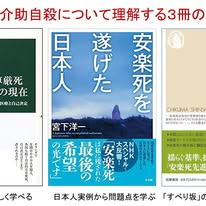 Neurological Sciences誌に,神経疾患患者における医師介助(幇助)自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)について,イタリア神経学会が包括的に論じたポジションペーパーが発表されました.非常に重要な論文だと思いました.
Neurological Sciences誌に,神経疾患患者における医師介助(幇助)自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)について,イタリア神経学会が包括的に論じたポジションペーパーが発表されました.非常に重要な論文だと思いました.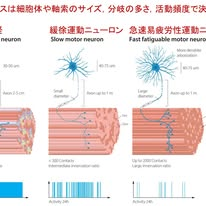 ALSにおけるCharcotの陰性4徴候のひとつに,眼球運動障害が生じにくいという点があります.これは多くの医学生も知っている基本的な知識であり,私もALSでは,病状がかなり進行するまで眼球運動が保たれると教えています.しかし,なぜこのような現象が生じるのかと問われると説明ができませんでした.ところが最近,Brain誌のオピニオン欄にミラノ大学等から報告された一本の論文に,その謎を考える大きな示唆を与えられ,思わずハッとさせられました.
ALSにおけるCharcotの陰性4徴候のひとつに,眼球運動障害が生じにくいという点があります.これは多くの医学生も知っている基本的な知識であり,私もALSでは,病状がかなり進行するまで眼球運動が保たれると教えています.しかし,なぜこのような現象が生じるのかと問われると説明ができませんでした.ところが最近,Brain誌のオピニオン欄にミラノ大学等から報告された一本の論文に,その謎を考える大きな示唆を与えられ,思わずハッとさせられました.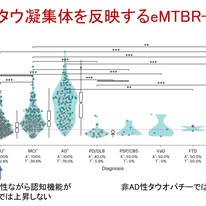 アルツハイマー病(AD)の診断や治療方針の決定に,脳内におけるアミロイドβおよびタウ蛋白の蓄積の評価が有用です.しかしその評価にはこれまでPET検査や脳脊髄液検査が必要であるため,日常診療への応用には限界がありました.しかしNature Medicine誌に相次いで掲載された2本の国際共同研究は,血液検査によりタウ蛋白の蓄積を高精度に評価できるというもので,今後の診療に大きなインパクトを及ぼすと予想されます.
アルツハイマー病(AD)の診断や治療方針の決定に,脳内におけるアミロイドβおよびタウ蛋白の蓄積の評価が有用です.しかしその評価にはこれまでPET検査や脳脊髄液検査が必要であるため,日常診療への応用には限界がありました.しかしNature Medicine誌に相次いで掲載された2本の国際共同研究は,血液検査によりタウ蛋白の蓄積を高精度に評価できるというもので,今後の診療に大きなインパクトを及ぼすと予想されます.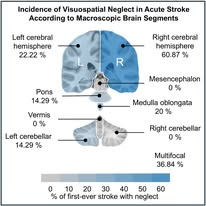 脳卒中後に生じる半側空間無視(hemispatial neglect もしくはvisuospatial neglect)は,日常生活への支障や予後不良と関連する重要な症候です.スイスの研究グループから,Stroke誌に半側空間無視の真の発生率を検討した前向きコホート研究が報告されました.この研究の特徴は,従来の紙ベースの検査(ベルテスト,線分二等分検査)に加え,より感度の高い評価法である自由視覚探索中のビデオ眼球運動計測(Free Visual Exploration with video oculography;FVE)というものを導入して,急性期脳卒中患者における半側空間無視の発生頻度を調べたことです.
脳卒中後に生じる半側空間無視(hemispatial neglect もしくはvisuospatial neglect)は,日常生活への支障や予後不良と関連する重要な症候です.スイスの研究グループから,Stroke誌に半側空間無視の真の発生率を検討した前向きコホート研究が報告されました.この研究の特徴は,従来の紙ベースの検査(ベルテスト,線分二等分検査)に加え,より感度の高い評価法である自由視覚探索中のビデオ眼球運動計測(Free Visual Exploration with video oculography;FVE)というものを導入して,急性期脳卒中患者における半側空間無視の発生頻度を調べたことです.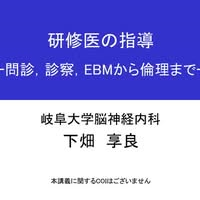 滋賀医科大学 総合内科学講座の杉本俊郎教授より貴重な機会を賜り,「研修医の指導」に関する講演をさせていただきました.医学教育の専門家という立場ではありませんが,現場で日々感じていることを踏まえ,これまで先輩の先生方から学んだことや,日々の診療の中で私自身が心がけていることを中心に,自分なりの視点でお話しさせていただきました.講演後には多くのご質問を頂戴し,大変刺激的で学びの多い時間となりました.改めまして,このような貴重な機会をいただきました杉本教授に,心より感謝申し上げます.
滋賀医科大学 総合内科学講座の杉本俊郎教授より貴重な機会を賜り,「研修医の指導」に関する講演をさせていただきました.医学教育の専門家という立場ではありませんが,現場で日々感じていることを踏まえ,これまで先輩の先生方から学んだことや,日々の診療の中で私自身が心がけていることを中心に,自分なりの視点でお話しさせていただきました.講演後には多くのご質問を頂戴し,大変刺激的で学びの多い時間となりました.改めまして,このような貴重な機会をいただきました杉本教授に,心より感謝申し上げます.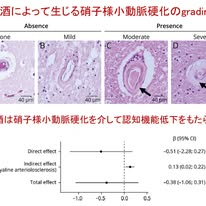 愛酒家の私にとって見て見ぬふりをすればよい論文でしたが,飲酒による認知機能低下の機序が示され,衝撃的でしたのでじっくり読みました.ブラジルのサンパウロ大学からの,飲酒に伴う脳の病理学的変化を検討した研究で,Neurology誌に掲載されました.この研究はバイオバンクに登録された1,781名の剖検データを用いて行っています.対象の平均年齢は74.9歳,平均教育歴は4.8年,女性は49.6%,白人は64.1%でした.
愛酒家の私にとって見て見ぬふりをすればよい論文でしたが,飲酒による認知機能低下の機序が示され,衝撃的でしたのでじっくり読みました.ブラジルのサンパウロ大学からの,飲酒に伴う脳の病理学的変化を検討した研究で,Neurology誌に掲載されました.この研究はバイオバンクに登録された1,781名の剖検データを用いて行っています.対象の平均年齢は74.9歳,平均教育歴は4.8年,女性は49.6%,白人は64.1%でした.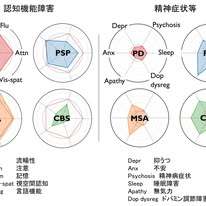 進行性核上性麻痺(PSP),大脳皮質基底核症候群(CBS),多系統萎縮症(MSA),パーキンソン病(PD)における認知機能と精神症状の違いを,英国の研究グループが詳細に解析し,Brain誌に報告しました.この研究では,2つの大規模コホートの計1138名のデータを統合し,各疾患を比較しています.診断は臨床診断に基づいて行い,診断基準としては,PSPはNINDS-SPSP→MDS PSP criteria,CBSはArmstrong基準,MSAはGilman改訂基準,PDはQueen Square Brain Bank基準を使用しています.
進行性核上性麻痺(PSP),大脳皮質基底核症候群(CBS),多系統萎縮症(MSA),パーキンソン病(PD)における認知機能と精神症状の違いを,英国の研究グループが詳細に解析し,Brain誌に報告しました.この研究では,2つの大規模コホートの計1138名のデータを統合し,各疾患を比較しています.診断は臨床診断に基づいて行い,診断基準としては,PSPはNINDS-SPSP→MDS PSP criteria,CBSはArmstrong基準,MSAはGilman改訂基準,PDはQueen Square Brain Bank基準を使用しています.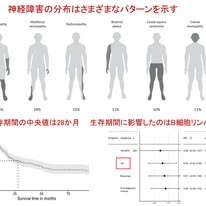 原発性神経リンパ腫症(primary neurolymphomatosis;PNL)は血液悪性腫瘍,主にB細胞リンパ腫が末梢神経系に直接浸潤する稀な疾患です.診断時には神経症状のみを呈することが多く,かつ他の神経疾患との鑑別が非常に難しい疾患です.これまでsystematic reviewは存在しませんでしたが,Eur Journal of Neurol誌の最新号に,フランスから自験例2例を含めた301例の検討が報告されています.結果は以下のとおりです.
原発性神経リンパ腫症(primary neurolymphomatosis;PNL)は血液悪性腫瘍,主にB細胞リンパ腫が末梢神経系に直接浸潤する稀な疾患です.診断時には神経症状のみを呈することが多く,かつ他の神経疾患との鑑別が非常に難しい疾患です.これまでsystematic reviewは存在しませんでしたが,Eur Journal of Neurol誌の最新号に,フランスから自験例2例を含めた301例の検討が報告されています.結果は以下のとおりです.