ポールウォーキングは、上肢・体幹・下肢を連動させる全身運動なので脳の運動中枢にとっても良い刺激となり、リハビリにも取り入れられますが、脳のトポロジーは変化させるのでしょうか?
脳のトポロジーにおける4つの重要な転換点(9歳:子ども期から思春期への移行、32歳:成人期の始まり、66歳:初期老化期の始まり、83歳:後期老化期の始まり)を明らかにした論文、定期的な運動のがん抑制メカニズムを明らかにした論文、岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報等を、お届けします。
1.2025年12月の活動状況
・長谷川 弘道さんの投稿
 ohana ポールウォーキング in モリコロパーク
ohana ポールウォーキング in モリコロパーク
・遠藤 恵子さんの投稿
 真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡
真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡
・スマイルチームさんの投稿
 ポールウォーキング
ポールウォーキング
・田村 芙美子さんの投稿
 午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。
午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。
・中村 理さんの投稿
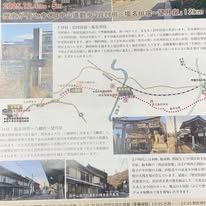 一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww
一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww
・校條 諭さんの投稿
 屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。
屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩
【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩
・スマイルチームさんの投稿
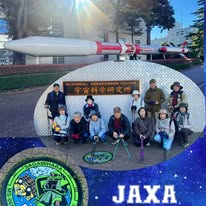 2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①
2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①
・中村 理さんの投稿
 佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。
佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。
・田村 芙美子さんの投稿
 神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)
神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)
・北陸ポールウオーキング倶楽部の中嶋 佳奈恵さんの投稿
 今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川
今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川
・長岡智津子さんの投稿
 どっ鯉ポールウォーキング
どっ鯉ポールウォーキング
・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿
 新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。
【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。
・田村 芙美子さんの投稿
 【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。
【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。
・校條 諭さんの投稿
 紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。
紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
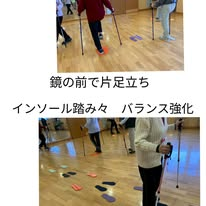 【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜
【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜
・田村 芙美子さんの投稿
 鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。
鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。
・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿
 台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。
【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。
・田村 芙美子さんの投稿
 きのこ頭の愉快な集まり
きのこ頭の愉快な集まり
・片山昇さんの投稿
 大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。
大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。
・中村 理さんの投稿
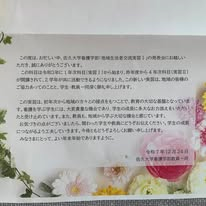 佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。
佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。
・大内 克泰さんの投稿
 クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌
クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌
・田村 芙美子さんの投稿
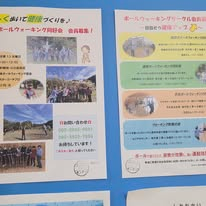 鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。
鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。
・佐藤 ヒロ子さんの投稿
 【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。
【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。
来月以降の開催
・みんなの元気学校さんの投稿
 志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木
志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木
・みんなの元気学校さんの投稿
 2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年
2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年
2.PW関連学術ニュース
2-1)脳は0歳から90歳までの間に4つの劇的な変化期を経験する
ヒトの脳内ネットワークの発達・変化についての大変興味深い論文がNature誌に掲載されたので、紹介します。
原論文:Nature Article (Open access)
公開日:Published: 25 November 2025
表題:Topological turning points across the human lifespan
(和訳:人間の生涯にわたる位相的転換点)
著者:Alexa Mousley, Richard A. I. Bethlehem, Fang-Cheng Yeh & Duncan E. Astle
掲載誌:Nature Communications volume 16, Article number: 10055 (2025)
要旨
構造的トポロジーは生涯を通じて非線形に発達し、認知軌跡と強く関連している。我々は、0歳から90歳までの集合的な年齢範囲のデータ・セット(N = 4,216)から拡散イメージングを収集した。我々は、組織化の12のグラフ理論メトリクスが加齢とともにどのように変化するかを分析し、均一多様体射影および近似を用いてこれらのデータを多様体空間に射影した。これらの多様体を用いて、我々は生涯を通じて4つの主要なトポロジー転換点(9歳、32歳、66歳、83歳頃)を特定した。これらの年齢は、それぞれが明確に加齢に伴うトポロジーの変化を伴った、トポロジー発達の5つの主要なエポックを定義した。これらの生涯エポックはそれぞれ、明確に異なる位相発達の方向と、年齢とトポロジーの関係を推進する組織特性の特定の変化を伴っている。本研究は、多変量、生涯、集団レベルの視点でのみ明らかにすることができる、トポロジー成熟の独特な段階を伴う、人間の発達の複雑で非線形な性質を強調している。
図 1: データセットの人口統計、方法の概略、およびネットワーク接続。
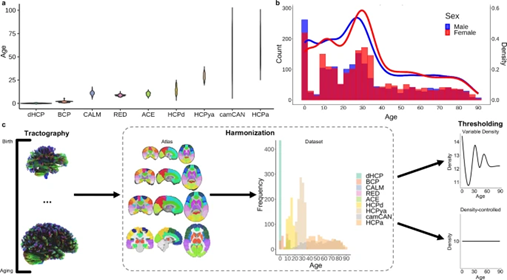 a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。
a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。
関連情報
1)同論文の紹介記事(Nature誌)です。
表題:Your brain undergoes four dramatic periods of change from age 0 to 90
Our brain wiring seems to undergo four major turning points at ages 9, 32, 66 and 83, which could influence our capacity to learn and our risk of certain conditions
(和訳:脳は0歳から90歳までの間に4つの劇的な変化期を経験する
私たちの脳の配線は、9歳、32歳、66歳、83歳で4つの大きな転換期を迎えるようで、それが学習能力や特定の病気のリスクに影響を与える可能性がある。)
著者:Carissa Won
掲載日:25 November 2025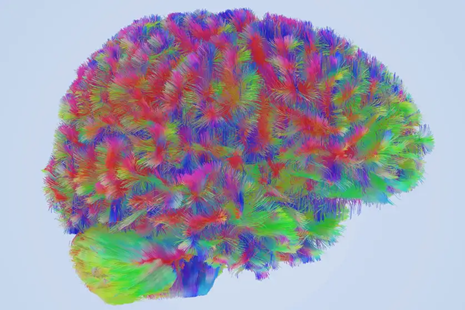 私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する
私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する
アレクサ・マウズリー、ケンブリッジ大学
**以下は、解説記事の冒頭部分の和訳です**
私たちの脳機能は生涯を通じて決して静止した状態ではありません。学習能力や認知機能低下のリスクは、新生児から90代まで変化することが既に知られています。そして今、科学者たちは、なぜこのような変化が起こるのか、その潜在的な理由を明らかにしたかもしれません。それは、脳の神経回路が9歳、32歳、66歳、そして83歳という4つの大きな転換期を迎えるからなのです。
2)同論文について、Copilotと会話してみました(2025年12月3日)。
Q1:次の論文の要旨を教えてください。
A1:この論文「Topological turning points across the human lifespan」は、人間の脳の構造的トポロジー(神経接続のパターン)が人生を通じてどのように変化するかを調べた研究です[1]。
研究チームは0歳から90歳までの4,000人以上の拡散MRIデータを用いて、脳ネットワークの12のグラフ理論指標を分析しました。その結果、脳のトポロジーにおける4つの重要な転換点が明らかになりました:
• 9歳:子ども期から思春期への移行
• 32歳:成人期の始まり
• 66歳:初期老化期の始まり
• 83歳:後期老化期の始まり
これらの転換点により、人生を5つの「トポロジー的時代」に分けることができ、それぞれの時代で脳のネットワーク構造が異なる方向に変化していることが示されました[2]。
この研究は、脳の発達と老化が単純な直線的変化ではなく、非線形で段階的な再構成を伴うことを示しており、認知機能や精神的健康との関連性を理解するうえで重要な知見を提供しています[3]。
もしご希望であれば、各時代の特徴や使われた指標の詳細もお伝えできますよ。
Q2:お願いします。
A2:お待たせしました!この研究では、人生を通じて脳のネットワーク構造がどのように変化するかを、12のグラフ理論指標(例:効率性、モジュラリティ、ハブ中心性など)を用いて解析しています[1]。その結果、脳のトポロジー的発達は5つの「時代(エポック)」に分かれることが明らかになりました。それぞれの時代には、特徴的な構造変化と機能的意味があるんです。
🧠 脳の5つのトポロジー的時代と特徴
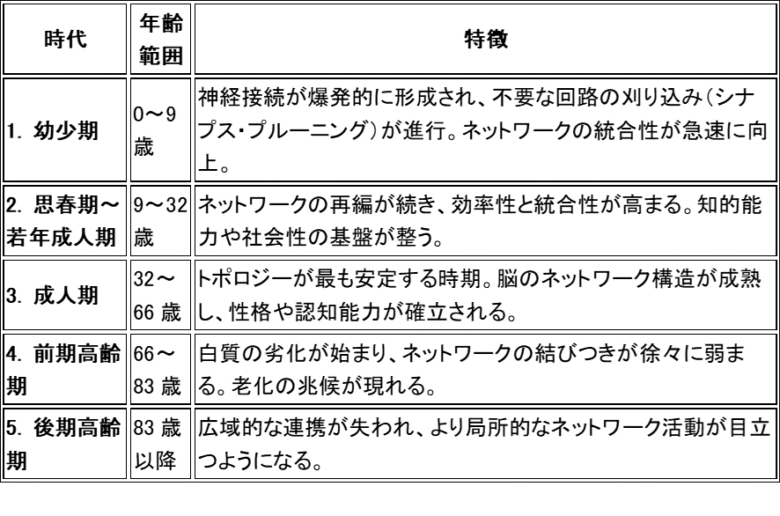 この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?
この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?
Q3:各指標がどのように変化しているのですか?教えてください。
A3:お待たせしました!この研究では、12種類のグラフ理論指標を用いて、脳のネットワーク構造が年齢とともにどのように変化するかを詳細に解析しています[1][2]。以下に、各指標の分類とその変化の傾向をまとめてみました:
🧠 使用されたグラフ理論指標とその変化
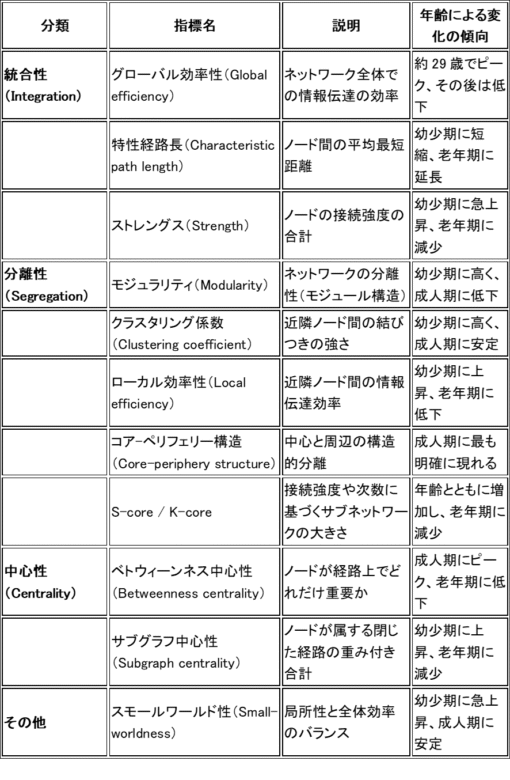 これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。
これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。
このような知見は、発達障害や認知症の早期発見、教育・介入の最適化、さらには高齢期の資産設計や生活支援のタイミングを考えるうえでも非常に有用です。
もっと深掘りして、特定の指標と認知機能や精神疾患との関連を見てみますか?それとも、これらの知見をどう応用できるかを一緒に考えてみましょうか?🍄
[1]: Nature Communications 論文PDF [2]: News-Medical.net 解説記事
Q4:まずは、認知機能との関連、次に、教育・介入の最適化との関連について解説して下さい。
A4:ではまず、認知機能との関連から見ていきましょう。
🧠 脳のトポロジーと認知機能の関連
この研究では、脳のネットワーク構造(トポロジー)と認知機能・行動・精神的健康との関連が明確に示されています[1][2]。特に以下のような関係が注目されています:
• 幼少期(〜9歳):この時期は「ネットワーク統合性」が急速に高まる時期で、言語、注意、記憶の基盤が形成されます。トポロジーの変化が学習能力や発達障害のリスクと密接に関係しています。
• 思春期〜若年成人期(9〜32歳):脳の効率性と統合性がピークに達する時期で、抽象的思考、自己制御、社会的判断力が発達します。精神疾患(例:統合失調症、うつ病)の発症リスクもこの時期に集中するため、トポロジーの変化が予測因子となる可能性があります[3]。
• 成人期(32〜66歳):脳の構造が最も安定し、認知的柔軟性や意思決定能力が成熟します。個人差が大きく、トポロジーの違いが知的能力や創造性の個人差と関連していると考えられています。
• 高齢期(66歳以降):ネットワークの統合性が低下し、記憶力や処理速度の低下が見られます。特に83歳以降は、認知症や軽度認知障害(MCI)との関連が強まるとされています。
🎓 教育・介入の最適化との関連
この研究のもう一つの大きな意義は、教育や医療的介入のタイミングを科学的に導く手がかりになることです:
• 9歳前後の転換点:この時期は学習支援や発達支援の「ゴールデンタイム」。ネットワークの再構成が始まるため、読み書きや社会性の介入が最も効果的とされます。
• 思春期(10代後半〜20代):精神的ストレスや社会的プレッシャーが増す時期。メンタルヘルス教育やレジリエンス強化の介入が、脳のトポロジー的安定性を高める可能性があります。
• 30代前半(32歳):脳の効率性がピークを迎える時期。成人教育やキャリア形成支援が、脳の構造的成熟と一致するため、学び直しやスキル習得に適した時期といえます。
• 66歳以降の高齢期:ネットワークの統合性が低下し始めるため、認知トレーニングや社会的活動の維持が、老化の進行を緩やかにする可能性があります。
このように、脳のトポロジー的転換点を軸にしたライフステージ別の介入設計は、教育政策や医療戦略に新たな視点を提供してくれます。
次は、これらの知見をどう資産設計や家族戦略に応用できるか、一緒に考えてみましょうか?それとも、特定の時期に焦点を当ててさらに深掘りしてみますか?🍄
[1]: Nature Communications 論文PDF [2]: Cambridge University 解説記事 [3]: News-Medical.net 解説記事
2-2)がんの予防と治療に関する最新の話題2つ:大阪大学宮坂先生のFB投稿より
2-2-1)定期的な運動が、がん細胞の増殖を抑制し、がんの予後を改善するメカニズム
**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年12月4日のFB投稿です**
 われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。
われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。
この研究では、マウスを回転するホイールの上を自発的に走らせるという「ホイールランニング」をさせています。すると、自発的な運動によって、からだの組織でグルコースの取り込みと酸化(=グルコースをエネルギーとして利用するのに必要な過程)が高まる一方、がん組織ではグルコースの取り込みと酸化が逆に減っていて、これとともにがん細胞の増え方が抑えられていました。そして、運動をしたマウスのがんでは、mTORという特定のシグナル経路(=細胞の増殖、成長、代謝を制御する経路)の働きが抑えられていました。
面白いのは、肥満マウスに運動をさせると、からだでのグルコース代謝が高まり、脂肪組織以外の体重はあまり変わらないものの脂肪は減少し、その後に腫瘍を移植した時には、非運動マウスに比べて、腫瘍細胞増殖が明らかに抑えられていて、たとえまだがんが出来ていない状態であっても運動をすれば、がん細胞が増えにくくなる状態が生まれてくることが観察されています、つまり、運動をがん治療後のリハビリテーションとして使うだけでなく、がん治療前のプレハビリテーション(=手術前や化学療法前に、前もって運動や栄養サポート、精神的ケアを行い、心身のコンディションを整えること;貯金ならぬ貯筋というプロセスがこれに相当)としても使える可能性が示されています。
以上、少なくともマウスにおいては、有酸素運動によって正常組織とがん細胞の間でグルコースの一種の代謝拮抗が見られ、そのためにがん細胞のエネルギー消費が抑えられ、増殖が抑えられる、というシナリオがはっきりとしてきました。しかも、運動ががんのリハビリテーションとしてだけでなく、プレハビリテーション(上記参照)としても有効である可能性が示されています。
ヒトでも「運動ががんの予後を改善する」と言われてきましたが、今回の話はなるほど、と思います。「ヒトでも実験によって確認しないと…」という(正論を)言う人が居るかもしれませんが、我こそは実験に参加したいという奇特なボランティアが出てこない限り、それはちょっと難しいでしょうね。
関連情報
原論文
表題:Precancer exercise capacity and metabolism during tumor development coordinate the skeletal muscle–tumor metabolic competition
(和訳:腫瘍発達中の前癌運動能力と代謝は骨格筋と腫瘍の代謝競合を調整する)
著者:Brooks P. Leitner, Andin E. Fosam, Won D. Lee, +7 , and Rachel J. Perry
掲載誌:PNAS December 1, 2025
doi:https://doi.org/10.1073/pnas.2508707122
要旨
運動能力の向上と定期的な運動トレーニングは、がんのあらゆるステージにおいて予後を改善する。しかし、腫瘍と宿主の相互作用を媒介する有酸素運動トレーニングに対する代謝適応については十分に解明されていない。本研究では、マウスにおいて、自発的なホイールランニングが腫瘍の成長を抑制し、ブドウ糖の取り込みと酸化を骨格筋と心筋に再分配し、乳がんおよび悪性黒色腫の腫瘍から遠ざけることを実証する。さらに、プレハビリテーションは肥満マウスにおいてブドウ糖代謝の再分配を誘導する。骨格筋と心筋におけるブドウ糖の取り込みと酸化は促進され、腫瘍におけるブドウ糖代謝は減少する。これらの筋肉におけるブドウ糖代謝の増加と腫瘍におけるブドウ糖代謝の減少は、腫瘍の進行遅延と相関している。[U- 13 C 6 ]ブドウ糖注入を用いて、運動は筋肉における酸化代謝へのブドウ糖の寄与を増加させる一方で、腫瘍における寄与を減少させることを示した。これは、有酸素運動が全身のブドウ糖代謝を腫瘍微小環境から代謝活性組織へと移行させることを示唆している。転写解析により、運動マウスの腫瘍におけるmTORシグナル伝達のダウンレギュレーションが明らかになった。これらの知見を総合すると、自発的な運動は宿主組織のグルコース酸化を促進し、腫瘍におけるグルコースの利用可能性を制限することで腫瘍の進行を抑制する可能性が示唆され、運動誘発性の代謝競合が腫瘍のエネルギー動態を抑制するというモデルを支持するものとなった。
2-2-2)大腸がんに対する新しい治療法開発の試み
**大阪大学の宮坂先生の2025年12月2日のFB投稿です**
大腸がんに対する新しい治療法開発の試みに関するお話です。ちょっと複雑な話です。DNAとか、遺伝子変異とか、がんのネオ抗原とかについてある程度の知識をお持ちの方々向けに書いています。
大腸がんには、最近はやりの免疫チェックポイント療法(免疫細胞のブレーキを外してがんを攻撃させる治療法)が良く効くものと、そうでないものがあります。良く効くものは、最初の図に示すように、マイクロサテライト不安定性の腫瘍、あまり効かないのはマイクロサテライト安定性の腫瘍、ということがわかっています。
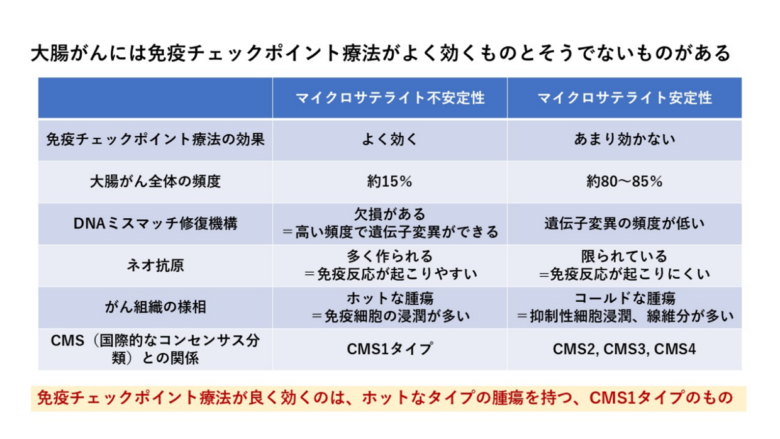 マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。
マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。
一方、免疫チェックポイント療法が効かないのは、いわゆるコールドな腫瘍で、がん組織の中に免疫細胞が非常に少ないタイプのものです。
最近、大腸がんの分類法として国際的コンセンサス分類(CMS分類)が用いられています。それを示したのが2枚目の図です。CMS分類の中でも、CMS1サブタイプが上記のマイクロサテライト不安定でホットな腫瘍を作るタイプのものに相当し、免疫チェックポイント療法が非常に良く効きます。一方、CMS2はコールドな腫瘍ですが、標準的な化学療法や分子標的薬が良く効き、幸い、予後が良いがんです。CMS3, 4はいずれもコールドな腫瘍で、特にCMS4は免疫細胞排除型ともよばれ、がん組織の中に免疫細胞を入れないようにしているように見えるタイプのもので、予後が悪く、免疫チェックポイント療法があまり効きません。
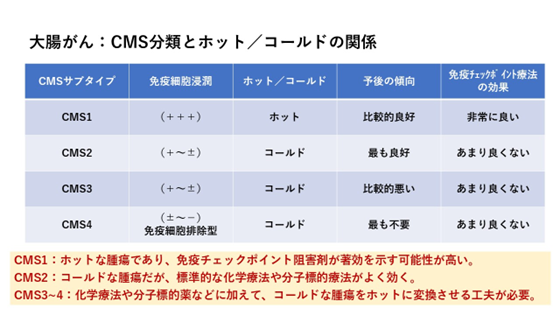 前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。
前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。
彼らは、CMS4タイプの大腸がんでは、がん組織のすぐ外側までキラーT細胞が来ているものの組織の中に入れないためにがん細胞が攻撃できないのかもしれないと考えました。そこで、このタイプのがんでは免疫細胞をがん組織の中に入れないようにしている仕組みがあると考え、がん組織に存在する線維芽細胞に注目して調べたところ、トロンボスポンジン-2(THBS2)という分子が沢山発現していることを見つけました。
THBS2は以前から発現が高いと予後が悪いことがわかっている分子で、彼らはこの分子が免疫細胞のがん組織への侵入を妨げていると考えました。そこで、マウスの実験モデルでTHBS2の発現を止めると、免疫チェックポイント療法が途端に良く効くようになり、キラーT細胞ががんの組織内に浸潤して、がん細胞の破壊が始まり、さらに、キラーT細胞を惹きつけるケモカインであるCXCL9/10ががん組織の中で強く発現するようになり、そのためにキラーT細胞がさらにがん組織に入りやすくなり、がんの治療効果が高まるようになりました。
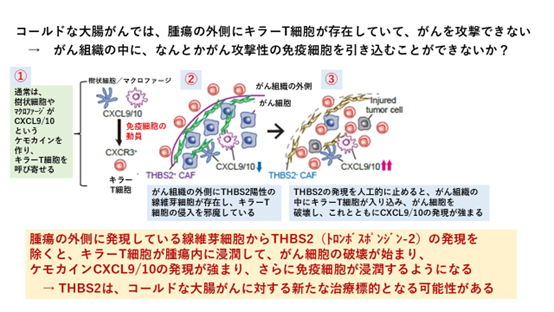 すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。
すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。
出来てしまったがん細胞を免疫の力で排除するというのが、がん免疫療法です。その際にTHBS2という分子の働きをうまく止められると、特定のタイプのがんでは、免疫療法の効果がぐんと高まるのかもしれません。医学は日進月歩の世界です。さらなる研究の発展が期待されます。
関連情報
原論文
掲載誌:Nature Communications Article(Open access)
公開日:Published: 23 November 2025
表題:Targeting fibroblast derived thrombospondin 2 disrupts an immune-exclusionary environment at the tumor front in colorectal cancer
(和訳:線維芽細胞由来トロンボスポンジン2を標的とすることで、大腸癌の腫瘍前線における免疫排除環境を破壊する)
著者:Kosuke Iwane, Yuki Nakanishi, Yu Muta, Jiayu Chen, Kento Yasumura, Mayuki Omatsu, Naoki Aoyama, Munehiro Ikeda, Yoko Masui, Liyang Cai, Go Yamakawa, Kensuke Hamada, Kenta Mizukoshi, Munenori Kawai, Kei Iimori, Shinnosuke Nakayama, Nobukazu Agatsuma, Takahiro Utsumi, Munemasa Nagao, Takahisa Maruno, Yukiko Hiramatsu, Nobuyuki Kakiuchi, Masahiro M. Nakagawa, Yasuhiro Fukui, …Hiroshi Seno Show authors
要約
線維性大腸癌(CRC)は、マイクロサテライト安定性が大部分を占め、免疫浸潤が乏しい線維形成性間質を呈する。本研究では、線維性CRCにおける免疫排除性表現型の重要な制御因子としてトロンボスポンジン2(THBS2)を同定した。THBS2は、腫瘍先端部のマトリックス癌関連線維芽細胞で高度に発現している。線維形成性腫瘍オルガノイドを用いた同所性モデルにおいて、Thbs2の全体的または線維芽細胞特異的な欠失は、排除バリアを破壊し、腫瘍内CD8 T細胞を増加させる。機構的には、THBS2は樹状細胞およびマクロファージ由来のCXCL9/10を抑制することでCXCR3 + CD8 T細胞の動員を制限する。これらの骨髄細胞の枯渇、またはCXCL9/10-CXCR3シグナル伝達の阻害は、増強されたCD8 T細胞流入と抗腫瘍効果を無効にする。空間プロファイリングにより、THBS2の欠損はCD8 T細胞と骨髄細胞の近接を誘導し、ケモカインの発現を上昇させることが示された。浸潤が増加するにもかかわらず、CD8 T細胞は疲弊状態を示し、腫瘍は免疫チェックポイント阻害に対する感受性が非常に高くなる。したがって、THBS2は線維性大腸癌における免疫排除を克服するための、CAF特異的な標的として扱いやすいと考えられる。
2-3)岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報(2025年12月)
・患者数 倍増のパーキンソン病を予防する25の提案!―話題の書『The Parkinson’s Plan』より―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月3日のFB投稿です**
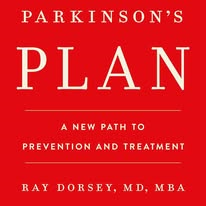 2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.
2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.
この本では,PDを増加させる「環境毒」として以下のものを紹介しています.これらは急性中毒ではなく,微量の長期蓄積がドパミン神経に負担を与えます.
◆農薬:パラコート,クロルピリホス,有機塩素系,ピレスロイド
◆工業用溶剤:TCE(トリクロロエチレン),PCE(パークロロエチレン)
◆大気汚染:PM2.5・交通・工場由来排気ガス
◆地下水や食品を介する化学物質
◆除草剤が散布される校庭・公園・ゴルフ場 など
本書は「完璧ではなくていいから,できることを少しずつ行っていこう」という姿勢で,生活の中で実践できる25の行動(Parkinson’s 25) を紹介しています.25項目を領域ごとに並び替えたものを以下に示します.
【食事・食材・農薬】
1.野菜・果物は有機でも必ずよく洗う(残留農薬を洗い流す)
2.和食ベース+野菜・魚中心の食生活(動物性脂肪は控えめに)
3.においが強いクリーニング工場が近いスーパーは避ける(ドライクリーニングでパークロロエチレンが使用されるため)
4.お酒は飲むなら少量,可能なら農薬の少ないものを選ぶ(ワインのぶどうの農薬残留が少ないもの)
5.糖尿病をつくらない・悪化させない(食事・体重管理・運動)
【生活習慣・からだの健康】
6.コーヒーやお茶を適量楽しむ(カフェインを摂取できる人)
21.週に150分以上の有酸素運動(散歩・自転車・体操など)
22.睡眠の質を高める(睡眠リズム・いびき・レム睡眠行動障害にも注意)
23.頭部外傷を防ぐ(シートベルト・ヘルメット・転倒予防)
【農作業・園芸】
7.農薬を使うときは防護具(手袋・マスク・ゴーグル)を使用する
17.園芸では素手で薬剤に触れず,必要最小限の散布にする
18.ゴルフ場では散布直後のプレーを避ける
19.学校・運動場での除草剤・農薬について確認してみる
【水と空気の安全】
8.井戸水を飲む地域では定期検査を行う
9.浄水器を使う場合はフィルター交換を守る
10.空気清浄機(HEPA+活性炭)を寝室・居間に設置する
16.渋滞・トンネルでは窓を閉じて「内気循環」(車の外気を取り込まず,車内の空気を循環させる設定にすることで,大気汚染物質の吸入を減らす)
【室内環境】
11.家庭用殺虫剤は必要最小限・換気を徹底する
12.住む地域の土壌・工場跡地情報も参考にする(過去に化学物質で汚染されていないか調べる)
13.クリーニング品はビニールを外して風通しの良い場所で保管する
14.集合住宅の1階がクリーニング店の場合は注意する
15.保育園・学童の近くにドライクリーニング工場がないか確認する
【職業と化学物質】
20.農業・造園・清掃・工場作業などでは防護具を使用する
25.軍務経験者・化学物質曝露歴がある方は相談先を確認(社会として支援する)
【コミュニティ】
24.公園・道路・学校などで農薬使用量を減らす活動に参加する
大変な時代になってきました.環境毒はPDのみならず,アルツハイマー病などの認知症,神経変性疾患にも関わる可能性があります.この本では取り上げられていませんが,ヒトの疫学研究はまだであるものの,基礎研究で報告され始めたものがマイクロ・ナノプラスチックです(Sci Adv. 2023 Nov 15;9(46):eadi8716. doi.org/10.1126/sciadv.adi8716). これもαシヌクレインを凝集させ,伝播を促進し,かつリソソーム機能を抑制します.マイクロ・ナノプラスチックと神経疾患については,明日の日本臨床麻酔学会第45回大会の招請講演で発表いたしますし,1月10日発売の「医学のあゆみ」誌でも特集「全身疾患の新たな危険因子としてのマイクロ・ナノプラスチック」を企画させていただきました.このような環境に対する取り組みや政策が疾患予防に重要となることを多くの人に啓発していく必要があります.
Dorsey R, Okun MS. The Parkinson’s Plan: A New Path to Prevention and Treatment. New York: PublicAffairs; 2025. https://amzn.to/4iyOBnF
・アルツハイマー病「ApoE4でも救える」可能性が見えてきた:酸化リン脂質とフェロトーシスを標的とした次世代治療戦略
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月4日のFB投稿です**
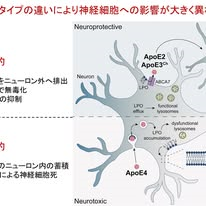 アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.
アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.
本研究で重要となるのが,脂質過酸化(lipid peroxidation;LPO)と酸化リン脂質の蓄積です.LPOとは,細胞膜の多価不飽和脂肪酸が酸化される現象で,その結果生じる酸化リン脂質は強い毒性を持ちます.ApoE2とApoE3Chは,ABCA7トランスポーターを介して酸化リン脂質をニューロン外へ排出することができ,排出された酸化リン脂質はグリア細胞内で脂肪滴として蓄えられ無害化されます(図上).こうして酸化リン脂質の蓄積とLPOの連鎖が抑えられることで,リソソーム機能が維持され,膜脂質のさらなる過酸化を防ぎ,フェロトーシスを回避できます.ちなみにフェロトーシスとは,細胞膜の脂質が過剰に酸化されることで起こる特殊な細胞死です.鉄(フェロ=Fe)が関与するためこの名前がついています.
対照的にApoE4では,酸化リン脂質排出が阻害されることでLPOが継続的に進行し,ニューロン内に酸化リン脂質が蓄積します.これによりリソソームが障害され,膜脂質の過酸化がさらに進み,最終的にフェロトーシスに至ります(図下).この模式図の対比は,ApoEの違いが神経保護的か神経毒性的かを分ける根幹に脂質代謝があることを示しており,非常に印象的です.
さらに研究チームは,ApoE4を発現させたヒトiPSC由来ニューロンを用いたin vitro実験で,グルタミン酸刺激により興奮毒性ストレスを与えて神経活動を低下させた後に,ApoE2またはApoE3Chタンパク質をリン脂質と組み合わせて人工的にHDLのような粒子にしたものを培地に加えると,ニューロンに蓄積していた酸化リン脂質は有意に減少し,リソソームのpHと分解活性は回復し,カルシウムイメージングおよび多電極アレイによって評価された神経活動も改善しました.すなわち,ApoE2/ApoE3Chはダメージ前の予防因子にとどまらず,ダメージ後の介入によっても神経機能を救済できる可能性を持つということが示されました.言い換えるとこの結果は,ApoE4による神経毒性が不可逆的,決定的なものではなく,脂質排出の経路を操作することで回復可能であることを意味しており,ApoE4キャリアに対する新たな治療戦略の可能性を示しています.
アミロイドβやタウが長らく研究の中心を占めてきましたが,そう単純なものではないのだと思います.「酸化リン脂質を外に出せるニューロンは生き残り,出せないニューロンは死に向かう」という明確な結論は,従来のアルツハイマー病観に,脂質代謝とフェロトーシスという新たな視点を加えるものと言えます.
Ralhan I, et al.Protective ApoE variants support neuronal function by effluxing oxidized phospholipids.Neuron.Article Online now December 02,2025.doi.org/10.1016/j.neuron.2025.10.040.
・見えない毒性因子―マイクロ・ナノプラスチックがもたらす脳・血管への脅威―@日本臨床麻酔学会第45回大会
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月5日のFB投稿です**
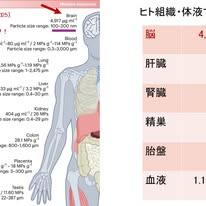 昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.
昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.
マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は,飲料水や食品包装だけでなく医療機器を介しても体内に侵入し,血液脳関門を通過して脳に蓄積します.臓器別では脳に最も多く蓄積することが示されており,なんとクレヨン1本分の重さ(10 g)になります.さらに頸動脈プラークや脳梗塞の血栓からも検出され,心血管イベントや脳卒中の重症度と関連することが報告されています.認知症患者の脳や脳脊髄液でも濃度上昇が確認され,神経炎症や神経変性を助長する可能性が指摘されています.加えて,αシヌクレインやアミロイドβがMNPsの存在下で凝集しやすくなり,毒性が増し,パーキンソン病や認知症の病態につながるという報告も今年相次いでいます.
麻酔科領域でも,手術室という特異な環境にも目を向ける必要があります.手術室は最もプラスチック密度の高い空間の一つであり,輸液ラインや麻酔回路などから発生したMNPsが血中に直接入り得ます.POCD(術後認知機能障害)は多因子的な病態ですが,プラスチック曝露がその一因となり得る可能性があり,今後の検証が必要です.
欧州や米国では対策が先行している一方,日本ではまだ認識が十分とは言えません.生活から完全にプラスチックを排除することは困難ですが,プラスチックが神経機能に影響しうるという知識を共有し,できるところから減らす意識を持つことは,個人レベルでも社会レベルでも意味があると感じています.以下よりスライドをダウンロードいただけます.
https://www.docswell.com/…/800…/5DW1JG-2025-12-05-104421
【内容】
1.マイクロ・ナノプラスチック総論(定義・発生源・検出技術)
2.曝露経路と体内動態・臓器蓄積(とくに脳への高蓄積と細胞毒性)
3.脳血管・心血管系への影響(頸動脈プラーク,血栓,脳卒中リスク)
4.認知機能障害と神経変性疾患への関与
― 認知症・アルツハイマー病・パーキンソン病・プラスタミネーション
5.大気汚染PM2.5と神経変性:MNPsとの共通機序と相乗効果の可能性
6.手術室環境と術後認知機能障害(POCD)におけるマイクロ・ナノプラスチック曝露
7.欧州と日本の対策状況の比較と,個人・社会レベルでの曝露低減策
8.今後の研究課題と海外で始まりつつある治療的アプローチ
関連情報
マイクロプラスチックについては、2025年6月のニュース、2025年3月のニュース、2025年2月のニュース、2024年4月のニュースでも取り上げています。
・特発性正常圧水頭症は「脳が硬いスポンジ」のようになり流れが滞るが,治療で再び動き出す
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月8日のFB投稿です**
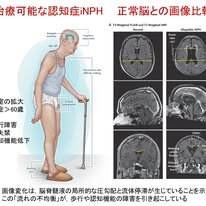 特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.
特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.
本論文が強調しているのは,脳血流・脳脊髄液・代謝老廃物のクリアランスを含む循環ネットワークが破綻しているということです.頭蓋内圧の波形解析では,1拍ごとの脈動に伴う圧変動が増大しており,脳のコンプライアンス(容積変化に対する柔らかさ)が低下していることが示唆されます.すなわちスポンジが固くなったような状況です.このため,心拍に同期した微小な圧力波が脳実質内に伝わりにくくなり,血管周囲の流体運動が滞ることを意味します.さらに,大脳白質では微小虚血を思わせるT2高信号がみられ,慢性的な血流低下や血管反応性の障害が報告されています.血管の拍動が脳脊髄液の流れを駆動していることを考えると,この血管反応性の低下は,脳脊髄液循環の低下と密接に関係しています.
また,神経活動のネットワークレベルでの異常も指摘されています.iNPH患者では,前頭葉と皮質下構造の機能的結合が低下し,これが歩行障害や注意機能の低下に関係していることが,fMRIや脳波研究から示されています.脳脊髄液除去後に一部のネットワーク結合が回復することから,脳内圧・流体環境の変化が神経活動に可逆的な影響を及ぼしていると考えられます.
さらに注目されるのが,グリンファティック経路の障害です.この経路は,脳脊髄液が動脈周囲から脳実質に入り,老廃物を洗い流しながら静脈周囲へと流れる排出システムであり,脳のリンパ系に相当します.iNPHではこの流れが遅延し,老廃物が除去されにくくなっていることが動物モデルやMRI研究で報告されています.血管周囲やくも膜下腔での脳脊髄液循環の停滞は,アミロイドβやリン酸化タウなどの蓄積を促進する可能性があり,iNPHが加齢性変化と神経変性疾患をつなぐ病態であるという仮説も浮上しています.しばしば併存が認められるPSPとの関連も関心があるところです.
図右では,iNPH患者のMRI画像として,Evans比の上昇と側脳室拡大に加えて,脳梁角の減少,頂部脳溝の圧排,Sylvian裂の拡大といった典型的なDESH(disproportionately enlarged subarachnoid-space hydrocephalus)所見が描かれています.これらの画像は,脳脊髄液が頭頂部のくも膜下腔から排出されにくくなり,側頭部に再分布することで局所的な圧勾配と流体停滞が生じていることを示唆しています.すなわち,脳全体の「流れの不均衡」が,歩行や認知に関わる領域の機能障害を引き起こしているものと考えられます.
著者らは,このような流体循環異常の背景に遺伝的素因も存在すると指摘しています.線毛の運動に関与するCFAP43遺伝子や,GPIアンカー型タンパク質の修飾に関わるCWH43遺伝子の変異が,家族性iNPHの原因として報告されており,線毛の異常が脳脊髄液流動障害をもたらすことが動物モデルで確認されています.これらの発見は,iNPHが単なる「老化の結果」ではなく,分子レベルの機能異常を基盤とする疾患であることを裏付けています.
では,なぜ脳脊髄液をシャントすると症状が改善するのでしょうか.iNPHでは,脳のコンプライアンス(柔らかさ)が低下して圧力波が広がりにくくなり,血流や髄液の循環,老廃物の排出が滞っています.シャントで脳脊髄液を逃がすと,コンプライアンスが回復し,血管の脈動に合わせて脳脊髄液が再びスムーズに流れるようになり,グリンファティック系による老廃物排出も改善します.その結果,歩行や認知機能が回復するため,脳室が縮まらなくても症状が改善すると考えれば良いようです.
つまりiNPHは脳循環ネットワークの可逆的破綻によって発症する疾患であり,その病態の解明がより早期の精度の高い診断と最適な治療法開発につながるものと期待されます.
Johnson MD, Williams MA. Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus. N Engl J Med. 2025;393:2243–2253. doi.org/10.1056/NEJMra2306506.
・ロバート・ワルテンベルグ ──医の倫理の岐路に立ったセミオロジストの光と影@Brain Nerve誌12月号
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月9日のFB投稿です**
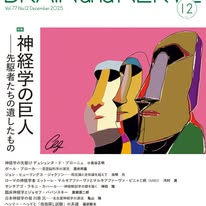 Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.
Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.
さて本書では以下に示すように「神経学の巨人」と呼ぶにふさわしい人物が,錚々たる執筆者により幅広く紹介されています.私はロバート・ワルテンベルグ(1887–1956)について執筆しました(図2).彼の名を冠した反射は神経症候学を学んだことのある方なら知らない人はいないと思います(https://www.med.gifu-u.ac.jp/…/observation/20220310.html).私も彼の執筆した本をいまもときどき参照します(図3).彼は神経診察を精緻化し,多数の徴候を体系化したセミオロジストであり,鋭い観察力と教育への情熱によって神経学の発展に大きな足跡を残しました.ドイツからの亡命後はUCSFで神経症候学を確立し,米国神経学会(AAN)の設立や『Neurology』誌の創刊にも助言するなど,中核的役割を果たしました.
一方で,1953年の国際学会においてナチス協力者であったユリウス・ハラーフォルデン(現在のPKAN;パントテン酸キナーゼ関連神経変性症の発見者)の登壇を擁護したことで強い倫理的批判を受けました.「科学的功績と政治的行為を切り離すべき」とする彼の判断は,冷戦期の政治背景も絡んで現在まで議論の対象となっています(いわゆるハラーフォルデン事件).AAN年次総会で最も権威あるセッションである「ロバート・ワルテンベルグ記念講演」も,2024年に発表されたこの倫理的問題を再検証するZeidmanの論文を契機として名称変更が発表されました.科学と倫理のあり方を深く考えさせられる事件でした.歴史を知ることは,過去を追体験するだけでなく,未来の神経学を形づくるための羅針盤になる──そのことを改めて感じさせてくれる特集号だと思います.
追伸:佐伯千寿先生による素晴らしい表紙のイラストは今回が最終回になりました.毎号とても楽しみにしておりましたが,毎号の制作は大変だったと思います.お疲れさまでした!
Amazonで予約が始まりました(https://amzn.to/4s1PPwj).
【目次と著者】
◆神経学の先駆け デュシェンヌ・ド・ブローニュ 小長谷正明
◆ポール・ブローカ ──言語脳科学の源流 酒井邦嘉
◆ジョン・ヒューリングス・ジャクソン ──局在論と全体論を超えて 虫明 元
◆ローマの神経学者 エットーレ・マルキアファーヴァとマルキアファーヴァ・ビニャミ病(MBD) 河村 満
◆サンチアゴ・ラモニ・カハール ──神経解剖学の礎を描く 神田 隆
◆臨床神経学とジョセフ・ババンスキー 廣瀬源二郎
◆日本神経学の祖 川原 汎 ──名古屋神経学の源流 亀山 隆
◆ヘンリー・ヘッドと「母指探し試験」の系譜 福武敏夫
◆神経病理学の父 ジョセフ・ゴッドウィン・グリーンフィールド 髙尾昌樹
◆ロバート・ワルテンベルグ ──医の倫理の岐路に立ったセミオロジストの光と影 下畑享良
◆ワイルダー・ペンフィールド ──ホムンクルスの構築とモントリオール手術法の開発 渡辺英寿
◆アレクサンドル・ルリヤの失語分類 ──その理論的背景 鹿島晴雄
◆オリヴァー・サックス ──神経学と文学の融合 山脇健盛
・フランス医学史学会誌に三浦・シャルコー研究論文が紹介されました!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月10日のFB投稿です**
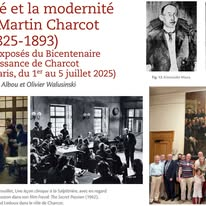 フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては
フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては
4–19頁 シャルコーの生涯と業績の総説(Olivier Walusinski)
20–42頁 「シャルコーの現代的意義と遺産」41演題の総括
43–46頁 生誕200周年記念イベントの写真アーカイブ
という構成になっています.
このなかで,私が発表した「Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A Master-Disciple Legacy in Modern Japanese Neurology」についても以下のように紹介していただきました.
三浦謹之助(1864–1950)はシャルコーの弟子であり,日本近代神経学の草創期を支えた人物です.わずか8ヶ月という短いサルペトリエール滞在であったにもかかわらず,三浦は生涯にわたりシャルコーを精神的師として敬愛し,回想録には「患者を細部まで観察し,観察を非常に重視するが,まったく尊大ではない人物であった」という証言が残されています.また,三浦はシャルコーに2通の手紙を送り,2通目(1893年初頭)では「東京大学に神経疾患の専門部門を作りたい」という志を記していました.この構想が実現するのは,実に70年後の1964年であったことが指摘されています.
下図のように三浦謹之助先生の肖像がに加え,三浦の弟子の佐藤恒丸先生の訳された「火曜講義」に掲載されたヒステリー発作の図版も収録されています.さらに拙著Shimohata T & Iwata M : Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A master–disciple legacy in modern Japanese neurology, Journal of the History of the Neurosciences, 2025(doi.org/10.1080/0964704X.2025.2581565)も引用して紹介していただきました.
この歴史的イベントの記録に加えていただけたことは大変光栄なことでした.PDFはフランス語になりますが,無料公開されていますので,ご興味のある方はぜひご覧ください.
https://walusinski.com/data/charcot_esfhm.pdf
・COVID-19は他の呼吸器感染症よりも「機能性神経障害」を新たに発症させる強い誘因となる!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月14日のFB投稿です**
機能性神経障害(FND)は歴史的にヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.私がこの疾患に取り組んだきっかけはCOVID-19後遺症やワクチン副反応として紹介されてきた患者のなかに多くのFNDが含まれていたことでした.また私がシャルコー先生について勉強したのも,COVID-19と同様に大きな精神的ストレスとなった普仏戦争後に増加したヒステリー患者への彼の取り組みが参考になると考えたためです.つまりCOVID-19後のFND増加は実感としては理解していたのですが,客観的データがありませんでした.
今回,国際的大規模電子カルテデータベースを用いて,COVID-19後のFND発症リスクを体系的に検討した研究が報告されました.この研究ではTriNetXという国際電子カルテネットワークを用い,約274万人のCOVID-19患者を解析対象としています.COVID-19罹患後2週から6か月の間に新たにFNDと診断された症例は1846例であり,その頻度を他の呼吸器感染症後のFND発症と比較しました.その結果,COVID-19後のFND発症率は,他の呼吸器感染症後より一貫して高いことが示されました(図). COVID-19患者全体では,他の呼吸器感染症と比べてFND発症のオッズ比は1.3〜1.6と有意に高く,COVID-19がFNDの誘因となりやすいことが示されています.
さらにCOVID-19の重症度との関係も示されています.入院を要したCOVID-19患者では,外来患者と比べてFND発症のオッズ比が約2.2と高く,救急外来(Accident & Emergency;A&E)を受診した外来患者でもオッズ比は約1.4に上昇していました.つまり,COVID-19の重症度が高いほどFNDを発症しやすい傾向があり,単なる偶然ではなく量反応関係を示唆する結果といえます.一方で,入院を要さない比較的軽症のCOVID-19症例に限定しても,他の呼吸器感染症よりFNDリスクが高いことが示されており,重症度だけでは説明できないおそらく個人の背景要因の存在も示唆されました.
また,パンデミック初期(2020–2021年)と後期(2022–2023年)を比較した解析も行われています.社会的混乱や不安が強かった初期にのみFNDが増えたのであれば,社会心理的要因が主因と考えられますが,図が示すように,時期を分けて厳密に調整した解析ではFND発症リスクに大きな差はありませんでした.この結果は,COVID-19後のFND増加が,一過性の社会不安だけでは説明できず,感染症そのものと個人の背景要因が重要であることを示しています.
さらに著者らは,COVID-19後に新たにFNDと診断された患者と,新たに片頭痛と診断された患者を比較しています.その結果,FND患者では,てんかんや運動障害などの神経疾患,気分障害や不安障害などの精神疾患,さらには心血管疾患や代謝疾患といった身体合併症が有意に多いことが明らかになりました.このことから,FNDは「誰にでも突然起こる」わけではなく,もともと神経学的・精神医学的・身体的な脆弱性を抱えた人に,COVID-19という強い身体的・心理的ストレスが加わることで発症しやすいと考えられました.個人の経験からも非常に納得のいく解釈です.
以上より,COVID-19は他の呼吸器感染症と比べて,FNDを新たに発症させる「強い誘因」となりうることが初めて明確に示されました.COVID-19は今後も続く感染症ですので,罹患後に出現する多彩な神経症状の原因の1つとしてFNDを想起し,早期に診断の説明と介入につなげることが重要と思われます.
★図がすぐに理解しにくいので,私のサマリーとともにGeminiに読み込ませたらあっという間に下図になりました.驚きですね!
Berlot R, et al. Functional Neurological Disorder Following COVID-19: Results From a Large International Electronic Health Record Database. Eur J Neurol. 2025 Dec;32(12):e70459. doi.org/10.1111/ene.70459.
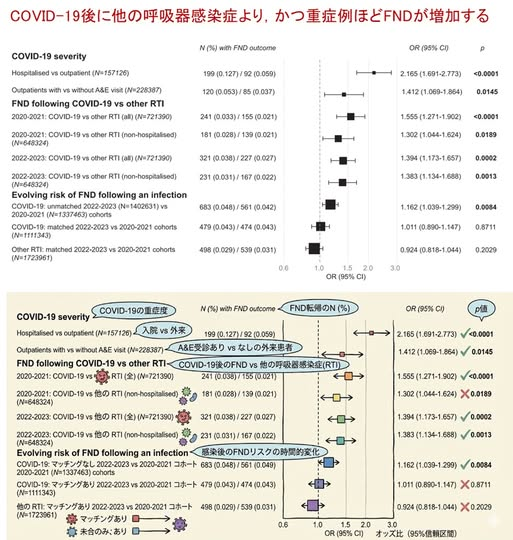
・アルツハイマー病はひとつの疾患ではなく,少なくとも「タウ主導型」と「血管主導型」に分かれる!!
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月16日のFB投稿です**
 アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.
アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.
対象は軽度認知障害およびAD患者116例と健常者85例の計201例で,アミロイドPET,タウPET,MRIを組み合わせ,約2年間の縦断的追跡を行いました.さて結果ですが,脳微小出血を認めない群では,ベースラインのタウPET蓄積が,その後の認知機能低下および皮質萎縮の進行と強く関連していました.これはタウ蓄積がADの認知機能に重要であるという近年の考え方に合致します.一方,脳微小出血を有する群では,認知機能低下や皮質萎縮自体は,脳微小出血なし群よりより,広範かつ顕著に進行しているにもかかわらず,それらがタウPETの蓄積量とはほとんど相関しませんでした(図).
図の見方ですが,緑色の部分はタウ蓄積と脳萎縮の関連が強い部位です.脳微小出血を認めない群では,タウ蓄積が高いほど側頭葉,前頭葉,頭頂葉に広範な皮質菲薄化が進行し緑色の部分が多いですが,脳微小出血を認める群では,皮質萎縮は進行しているにもかかわらず,タウ蓄積との関連は限定的で,ほとんど緑色の部分がありません.すなわち,脳微小出血が存在すると,認知症の進行は「タウ主導」では説明できなくなることが明確に示されたわけです.
この結果は,アミロイドβの役割を再考させます.脳実質に沈着するアミロイドβは,長い時間を要しますが恐らくタウ病理を誘導し,典型的なADの進行に関与します.一方,脳血管壁に沈着するアミロイドβ,すなわち脳アミロイド血管症では,血管の脆弱化,慢性虚血,微小出血や微小梗塞を介して,タウとは独立した経路で認知機能低下を進行させます.脳微小出血は,この血管型アミロイドβ病理が前景化していることを示すサインと考えられます.
では,アミロイドβ抗体療法をどのように考えるべきでしょうか.アミロイドβ抗体は,主に脳実質に沈着したアミロイドβを除去し,その結果としてタウ病理の進行を抑制することを目的とした治療です.したがって,脳微小出血を伴わず,タウ病理が病態の中心にある症例では,理論的にも臨床的にも一定の妥当性があります.しかし,脳微小出血や脳アミロイド血管症が前景に立つ症例では,認知機能低下の主因は血管障害であり,タウ病理の寄与は相対的に小さくなります.このような症例では,アミロイドβ抗体による臨床効果は限定的である可能性が高く,むしろ血圧管理のような血管性認知症の対策が有効と考えられます.つまりアミロイドβ抗体療法の是非は「アミロイドβがあるかどうか」ではなく,「どこに沈着し,どの病態経路が主導しているか」で判断すべきだということです.
以上のようにADは一つの疾患ではなく,少なくとも「タウ主導型」と「血管主導型」という異なる進行様式を含んでいそうです.ADの脳血管病としての側面を意識する必要があります.
★先日,ご紹介したこちらの記事もご参照ください(アルツハイマー病は「脳血管病」の性質をもつ:血液脳関門破綻,低灌流,血小板から見える新しい姿)https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/11/22/065353
Jung YH, et al. Impact of Cerebral Microbleeds on Tau-Associated Cognitive and Structural Decline. Neurology. 2026 Jan 13;106(1):e214453. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214453.
・整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患(整形・災害外科 12月号)
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月17日のFB投稿です**
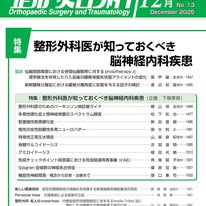 腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.
腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.
具体的な疾患としては,パーキンソン病,ALS,多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害(MS・NMOSD),慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー(CIDP)に加え,近年,注目の疾患として特発性正常圧水頭症,アミロイドーシス,免疫チェックポイント阻害薬による神経系免疫関連有害事象(irAE)や機能性神経障害など,整形外科との境界で問題となりやすい疾患を取り上げています.第一線で活躍するエキスパートが,最新の知見を踏まえて実践的に解説してくださいました.整形外科と脳神経内科の連携を深め,日常診療に役立つ現場志向の特集だと思います.最後に素晴らしい原稿をご執筆くださった先生方に感謝申し上げます.
Amazonページ https://amzn.to/3MK8mgc
ホームページ https://www.kanehara-shuppan.co.jp/magazines/detail.html…
【項目】
整形外科医のためのパーキンソン病診療ガイド;梶山 裕太,三原 雅史
多発性硬化症と視神経脊髄炎スペクトラム障害;松下 拓也
筋萎縮性側索硬化症;熱田 直樹
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー;国分 則人
特発性正常圧水頭症;山原 直紀,下畑 享良
脊髄サルコイドーシス;古賀 道明
アミロイドーシス;植田 光晴
免疫チェックポイント阻害薬における免疫関連有害事象(irAE);角南 陽子,鈴木 重明
Sjogren症候群の神経系合併症;桑原 宏哉
機能性神経障害―概念から診断・治療まで;関口 兼司
・血液タウで診断したアルツハイマー病は加齢で激増するが,症状の程度はタウだけでは決まらない――tau-clinical mismatchという新しい考え方
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月20日のFB投稿です**
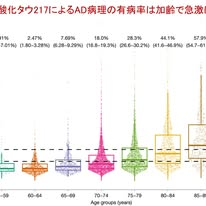 アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.
アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.
まず,Nature誌に掲載されたノルウェーの大規模地域住民研究であるHUNT研究を基盤とした論文では,血液中リン酸化タウ217(pTau217)を用いて,アルツハイマー病(AD)病理が地域社会にどの程度存在するのかが検討されています.本研究は,58歳以上の一般住民11,486人を対象とした大規模研究です.重要なのは図1です.年齢階級ごとにAD病理陽性(pTau217 ≥0.63 pg/mL)と推定される割合が示されています.その結果,58~69歳ではAD病理陽性者は8%未満にとどまる一方,70~74歳では約18%,75~79歳では約28%,80~84歳では約44%,85~89歳では約58%と,年齢とともに段階的に増加し,90歳以上では65.2%に達していました.すなわち,AD病理は高齢になるほど急速に頻度が増し,超高齢期には「例外的な病態」ではなく,「一般的な現象」に近づくことが,人口レベルで明確に示されたわけです.
さらに重要なのは,このAD病理の広がりが,必ずしも臨床症状と一致しない点です.70歳以上の集団を対象とした解析では,AD病理は認知症患者の60.0%に認められましたが,軽度認知障害(MCI)でも32.6%,認知機能が保たれている集団においても23.5%に存在していました.言い換えれば,70歳以上では,認知症でなくても約4人に1人がAD病理を有していることになります.これらの結果が示しているのは,タウを中心とするAD病理は「症状出現前に,すでに相当数の人に存在し得るもの」であるという事実です.
しかし,ここで次の疑問が生じます.もしタウ病理がすでに存在している場合,症状の出方や進行速度に個人差がないのだろうかということです.この問いに取り組んだのが,米国ペンシルベニア大学等からのJAMA Neurology誌に掲載された研究です.ADNIなどの縦断データを用い,アミロイドβ陽性例におけるタウ病理と臨床症状の関係を詳細に解析しました.図2では,タウPETあるいは血漿pTau217と,CDR-SBの関係が散布図として示されています.全体としてはタウ量と症状重症度に正の相関が認められるものの,同じタウ量であっても症状が軽い例と重い例が明確に存在しています.著者らはこの乖離を「tau-clinical mismatch」と名付けました.そして回帰モデルからの残差として定量化し,タウ量と症状が概ね一致するcanonical群,タウ量の割に症状が軽いresilient群,タウ量の割に症状が重いvulnerable群という3群に分類しました.そしてvulnerable群ではCDR-SBの上昇やMMSE低下が有意に速く,次の臨床ステージへの移行リスクも高いことが示されました.一方,resilient群ではその逆で,同じタウ病理を持ちながら全く異なる臨床経過をたどることも明らかになりました.
では,このtau-clinical mismatchは何によって生じるのでしょうか.本研究で最も説得力をもって示されたのは,vulnerable群ではTDP-43関連MRI指標の異常やαシヌクレインseed amplification assay陽性率が高く,共存病理の存在が臨床的脆弱性を規定しているという点です.一方,resilient群では共存病理が少ないだけでは説明しきれず,認知予備能やレジリエンスといった防御的要因の関与が考えられます.教育歴や知的活動,遺伝因子,免疫反応,血管因子などが,症状発現を抑制している可能性があります.
この2つの研究を合わせて考えると,AD病理を有する人は加齢で激増するが,タウ単独では決まらず,共存病理による加速と,レジリエンスによる防御という2方向の力のバランスによって規定されているということのようです.防御には恐らくグリンファティックシステムなどが関わるものと考えられます.結論として血液バイオマーカー時代のADは,「タウの有無」を問う段階から,「タウ × 共存病理× レジリエンス要因 × クリアランス(グリンファティック)」というものになっていきそうです.アミロイドβを脳脊髄液やPETで評価している現在とはかなり違ったものになりそうです.
Aarsland D, Sunde AL, Tovar-Rios DA, et al. Prevalence of Alzheimer’s disease pathology in the community. Nature. 2025. doi.org/10.1038/s41586-025-09841-y
Brown CA, Mundada NS, Cousins KAQ, et al. Copathology and clinical trajectories in individuals with tau-clinical mismatch. JAMA Neurology. 2025. doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.4974
・知っていただきたい「機能性神経障害」 ―診療に潜む倫理的課題と私たちができること―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月25日のFB投稿です**
 機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.
機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.
本総説では,2015年以降の文献を検討し,FNDをめぐる臨床倫理的問題を四つの領域に整理しました.それは「スティグマ」「誤診と医原性の害」「患者と医療者の病態理解の乖離と患者体験の軽視」,そして「ジェンダーと歴史的偏見」です.とくにスティグマは,患者さんが「症状を作っている」「怠けている」と疑われ,信じてもらえない経験を重ねることから生じます.このような経験は患者さんの尊厳を損ない,生活の質を低下させ,医療への信頼を失わせます.また,一度FNDと診断されるとその後に生じた新たな器質疾患が見逃されやすくなる「診断の影の効果」もあり,誤診や過剰治療,不必要な侵襲的処置が医原性の害として患者さんを苦しめる場合があります.
さらに,医療者と患者さんの間には,症状の随意性や意味づけに関する理解の乖離があります.医療者は「随意とも不随意とも解釈できる」と捉えがちですが,患者さんは「自分の意思ではどうにもならない」と感じています.このずれが診断の受容を妨げ,信頼関係の構築を困難にします.またFNDは歴史的に「ヒステリー」として女性に帰属されてきた経緯があり,ジェンダーバイアスや社会的偏見が現在の診療にも影を落としています.虐待や暴力といったライフイベントが発症や持続に関与する場合も少なくありませんが,これらへの配慮は十分とは言えません.
本総説の提案は,これらの問題を「臨床倫理の四原則」という枠組みで整理し,日常診療の具体的な行動に結びつけることでした.表(英語)では,自律尊重,善行,無危害,公正の四原則ごとに,現状の課題と望ましい対応を対比的に示しています.①自律尊重の観点からは,陽性徴候を示して疾患の実在性を保証し,患者さんの語りに耳を傾けることの重要性を示しました.②善行の観点からは,スティグマを軽減する医療者教育と心理社会的支援の充実を挙げました.③無危害の観点からは,除外診断ではなく陽性診断を行い,不必要な検査や治療を避ける姿勢の必要性を示しました.④公正の観点からは,ジェンダーや社会的弱者に対する不公平を是正し,公平な医療アクセスと資源配分を確保する必要性を示しました.
FNDでは,患者さんをどう理解し,どう関わるかという姿勢そのものが治療の一部になります.患者さんを信じて尊重し,害を最小化し,公平性を確保するという原則を意識的に実践し教育していくことが重要であると考えます.
下畑享良.機能性神経障害における臨床倫理的問題―患者尊重と医療者教育の必要性―.臨床神経(早期公開)https://doi.org/10.5692/clinicalneurol.cn-002182
無料でダウンロードできます.またスライドを以下からご覧いただけます.
https://www.docswell.com/…/800…/KG2PW4-2025-11-09-070636
・予防神経学がひらくこれからの健康社会 ― 脳神経内科医の新しい役割―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月28日のFB投稿です**
Neurology誌の総説「An Ounce of Prevention: The Growing Need for Preventive Neurologists」を興味深く読みました.米国神経学会ポッドキャストでも取り上げられた注目の論文です.脳神経内科医の役割を「発症後の治療」から「発症前の予防」へと転換する必要性を論じています.医療の進歩によってがんなどによる死亡が減少し,多くの人が脳卒中や認知症などの神経疾患とともに長く生きる時代になり,その結果,神経疾患は世界最大の障害負荷の原因となっています.2021年には世界人口の約43%にあたる34億人が何らかの神経疾患を有していたとされ,神経疾患は障害調整生命年の最大の原因であり,死亡原因としても第2位を占めています.とくに認知症は2050年までに3倍に増加すると予測され,医療費と介護負担の爆発的増加が懸念されています.
この論文のメッセージは,神経疾患の多くは「避けられない運命」ではなく,相当部分が予防可能であるという点です. INTERSTROKE研究では,高血圧,喫煙,腹部肥満,運動不足,不適切な食事,糖尿病,過剰飲酒,心理社会的ストレスやうつ,心疾患,脂質異常症という10の修正可能な危険因子で,脳卒中リスクの約90%が説明可能であることが示されています.そして生活習慣と危険因子管理により最大80%の脳卒中が予防可能とされています.
またLancet委員会は,教育歴,難聴,高血圧,喫煙,肥満,うつ,運動不足,糖尿病,社会的孤立,過剰飲酒,頭部外傷,大気汚染,視力障害,高LDLコレステロールという14因子を通じて,認知症の40%以上が予防または発症遅延可能であると報告しています.さらにFINGER試験やSPRINT-MIND試験といった前向き介入研究により,実際に介入することで認知機能低下を抑えうることも示されています.具体的にはFINGER試験は,認知症リスクを有する高齢者を対象に,食事指導,運動療法,認知トレーニング,血管危険因子管理を組み合わせた多領域介入を2年間行い,介入群では記憶や実行機能などの認知機能が有意に改善しました.SPRINT-MIND試験は,高血圧患者を対象に,収縮期血圧120mmHg未満を目標とする厳格な降圧治療が,軽度認知障害の発症および軽度認知障害または認知症の複合エンドポイントを有意に減少させることを示しました.これらの研究は,認知症は不可避な老化現象ではなく,危険因子への介入によってその進行を遅らせたり,発症を防いだりできる可能性があることを実証するものです.
論文の中で最も印象的なのが下図で,脳神経内科医の役割をピラミッドで示しています.最下層には個々の患者の診療があり,その上に家族への教育,医療チーム内での専門的助言,研修医・学生への教育が積み重なり,さらに上層では地域への啓発活動や社会・政策への提言が位置づけられています.これは,脳神経内科医は診療室の中だけで完結する存在ではなく,個人,家族,医療システム,社会という複数のレベルで脳の健康を支える「脳の健康推進者(brain health advocate)」として機能すべきであるという著者のビジョンを視覚的に表現したものです.予防神経学とは,個人医療と公衆衛生を橋渡しする新しい専門性であるとも言えます.この考え方は非常に納得できるものです.
論文タイトルに使われている「An Ounce of Prevention」は,英語の格言「An ounce of prevention is worth a pound of cure(わずかな予防は大きな治療にまさる)」に由来しています.つまり「ほんの少しの予防的努力が,将来の膨大な治療や苦痛を防ぐ」という意味が込められています.脳神経内科医は,病気を治す専門家であると同時に,病気を生まない社会をつくる専門家であるべきだというメッセージがこの一語に凝縮されています.
Sabayan B, Boden-Albala B, Rost NS. An Ounce of Prevention: The Growing Need for Preventive Neurologists. Neurology. 2025;105:e213785. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000213785
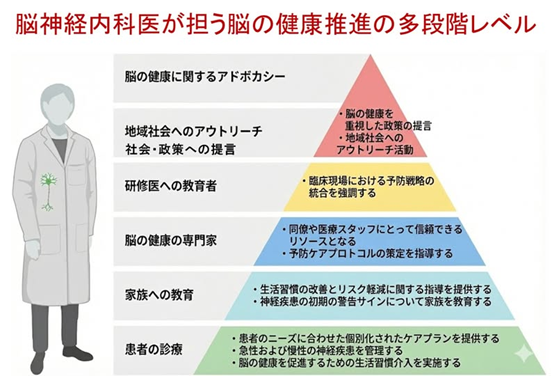
・抗ウイルス薬はアルツハイマー病に効くのか?VALAD試験が示した予想外の結論
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月29日のFB投稿です**
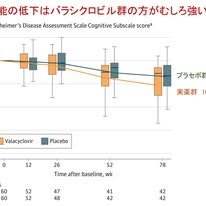 近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.
近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.
対象は,早期症候性ADまたはADバイオマーカー陽性の軽度認知障害(MCI)で,かつ血清HSV抗体陽性の成人120名で,平均年齢は71.4歳,女性66名でした.被験者は無作為にバラシクロビル群60名とプラセボ群60名に割り付けられ,バラシクロビルは2 g/日から開始して4週間で4 g/日まで漸増され,その後78週間まで維持されました.主要評価項目はADAS-Cog 11項目版の変化量でした.
結果はなんと仮説と逆でした.78週時点でのADAS-Cogの変化量は,バラシクロビル群で10.86点悪化し,プラセボ群では6.92点の悪化にとどまり,群間差は3.93点で統計学的にも有意でした.この差は臨床的に意味のある最小差である3点を上回っており,認知機能の低下はバラシクロビル群の方がむしろ強いことが示されました!!(図1)経時的にも,時間とともに両群の曲線が離れ,バラシクロビル群が一貫してより大きな悪化を示していく様子が分かります.
一方で,副次評価項目である日常生活動作スケール,アミロイドPET,タウPET,MRIによる海馬萎縮や皮質菲薄化などの指標では,いずれも群間差は認められませんでした.すなわち,バラシクロビルは認知機能のみならず,AD病理や神経変性にも影響を与えなかったことになります.安全性の面では,重篤な有害事象は両群で大きな差はありませんでしたが,バラシクロビル群では血清クレアチニン上昇や下痢,悪心,混乱などの軽度副作用がやや多く認められました.著者らは,高用量かつ長期のバラシクロビル投与が,軽微な神経毒性を通じて認知機能悪化として検出された可能性も否定できないと議論しています.
本研究の結論は明確であり,バラシクロビルは早期症候性ADに対して有効ではなく,むしろ認知機能悪化と関連した可能性があるため,治療として推奨されないということです.ただし,この結果は感染症仮説そのものや発症前予防の可能性を否定するものではありません.ADの病理は臨床症状の10年以上前から始まることが知られており,もしウイルス感染やその再活性化が初期トリガーとして関与しているのであれば,発症後の治療ではなく,発症前の段階での介入こそが意味を持つ可能性があります.実際に,帯状疱疹ワクチン接種と認知症リスク低下との関連を示す疫学研究も報告されており,免疫環境の長期的修飾という観点からは,抗ウイルス薬よりもワクチンや予防的介入の方が理論的に適している可能性も考えられます.本試験は,発症後治療の限界を示すと同時に,予防という視点の重要性をあらためて浮き彫りにした研究であるともいえます.
Devanand DP, et al.Valacyclovir Treatment of Early Symptomatic Alzheimer Disease.The VALAD Randomized Clinical Trial.JAMA.Published online December 17, 2025. PMID: 41405855
★FBの規則改訂で,1ヶ月のリンク付き投稿数が制限されるようになってしまいました(2個まで).このためMeta認証に有料加入したのですが,それでも月4個までなので,リンクを貼らず,PMIDを記載することにしました.
・アルツハイマー病病理はウイルスに対する2段階の防御反応?タウはリン酸化されて初めて抗ウイルス蛋白として機能し,伝播は感染防御のための準備反応である
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月30日のFB投稿です**
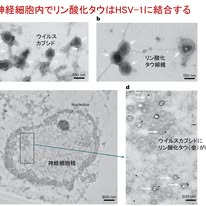 近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.
近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.
ADの代表的な病理所見である神経原線維変化は,リン酸化されたタウ蛋白の凝集によって形成されます.このリン酸化タウは長らく神経細胞にとって有害な異常産物とみなされてきましたが,今回,Nature Neuroscience誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院のWilliam A. Eimer博士らの論文は,この常識に根本的な再考を迫る内容です.この研究の最大の発見は,リン酸化タウがヒト神経細胞においてHSV-1に対して抗ウイルス活性を示したという点です.培養神経細胞にリン酸化タウを前処理すると,ウイルスに感染する細胞の数が減少し,形成されるウイルスプラークの数や大きさも有意に低下しました.一方で,リン酸化されていない通常のタウではこの効果は認められませんでした.すなわちタウはリン酸化されて初めて抗ウイルス蛋白として機能することが示されました.
とくに印象的なのが電子顕微鏡で示された所見です(図1).精製したHSV-1カプシドとリン酸化タウを共培養すると,リン酸化タウがウイルス粒子の表面に直接結合し,そこを足場として自己凝集し,線維状構造を形成していく様子が観察されました.aおよびbでは,ウイルスカプシド(矢印)の表面からリン酸化タウの線維が伸び,不定形の凝集体(矢頭)や線維状構造(★)が形成され,複数のウイルス粒子を絡め取っている様子が示されています.これはウイルス粒子がタウ凝集の核となり,防御構造としての線維形成が誘導されていることを意味します.さらにcおよびdでは,HSV-1に感染した三次元培養神経細胞の超薄切片において,抗リン酸化タウ抗体に金ナノ粒子を結合させた標識により,神経細胞核内のウイルスカプシド表面にリン酸化タウが実際に結合している様子が確認されています.すなわちこの現象は試験管内だけでなく,感染した神経細胞内でも実際に起きていることが示されたのです.
またウイルス感染により神経細胞内でリン酸化タウが増加し,それが細胞外にも放出されて周囲の未感染細胞に影響を及ぼすことが示されました.図2では,感染細胞と未感染細胞を細い通路でのみ連結した特殊な培養装置を用いることで,ウイルスそのものは移動できないが,タンパク質などの情報は伝わる状況が作られています.その条件下で,感染していない細胞の中にもリン酸化タウが増えている様子が観察されました.これはリン酸化タウが感染した細胞だけでなく,周囲の細胞を事前に守る役割も担っていることを示唆しています.いわゆるタウの伝播は,感染防御のための準備反応であるということになります.
さらにリン酸化タウとウイルスの複合体はミクログリアに貪食されることも示され,免疫細胞による病原体除去にも関与している可能性が示唆されました.これらの結果を総合すると,アミロイドβが細胞外でウイルスを捕捉するという既存の防御仮説(これはNHKタモリさんの番組でもご紹介しました)に加えて,本研究はリン酸化タウが細胞内でウイルスの輸送や増殖を妨げる役割を担う可能性を示し,脳内に2段階の自然免疫機構が存在するという新しい統合モデルを提示しています.
つまり,ADの主要な病理とされるアミロイドβ沈着,リン酸化タウ沈着,神経炎症はいずれも,感染防御と深く関係する生体反応であり,それらが慢性的に持続あるいは過剰化することで病理として現れている可能性を示しています.神経変性はこの防御機構が過剰化あるいは慢性化した結果であるかもしれません.アミロイドβに加え,タウも単なる「悪者」として排除するのではなく,なぜそれが生じたのかという進化的,免疫学的文脈の中で再評価する必要があることを,本研究は強く示唆しているように思われます.
Eimer WA, et al.Phosphorylated tau exhibits antimicrobial activity capable of neutralizing herpes simplex virus 1 infectivity in human neurons. Nature Neuroscience.2025. PMID: 41408481.
・アリと人間のパズル対決から学ぶ大切なこと ― チームの質は「対話の質」で決まる―
**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月31日のFB投稿です**
 1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.
1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.
結果は意外でした.アリは集団になるほど成績が良くなりました.壁に沿って動き続けるなどの行動が自然に生じ,結果として効率よく正解に到達します.個体にはない「集合的な記憶」が生まれていると解釈されています.逆に人間は,1人のときが最も効率的でした.話せるグループは1人と同程度の成績でしたが,話せないグループは,なんと1人よりも成績が悪くなりました.出口に対して遠回りすべき場面でも,直感的で誤った方向を選びやすい傾向が見られました.これは心理学でいう groupthink(集団浅慮)に近い現象です.「みんなと同じでいること」が目的になりすぎて,「正しく考えること」をやめてしまう集団心理です.つまり,アリは単純な個体ですが,集まると賢くなる.それに対して人間は,賢い個体であっても,話し合えない集団では賢さを失う・・・その対照的な特徴が浮かび上がりました.
この論文の教訓は極めてシンプルです.人間のチームの質は,個々のメンバーの賢さではなく,ひとえに「対話の質」によって決まる.バラバラな考えをつなぎ合わせ,一つの方向へと導くための最も大切な手段こそが対話なのだと,この研究は教えてくれます.当たり前のようでいて,これほど重要なことはありません.来年も教室やカンファレンスで,よく話し合っていきたいと思います.そして,この対話の力を社会や世界があらためて認識し,争いのない平和な未来へとつながることを,心から願っています.
本年も1年,ありがとうございました.どうぞ良いお年をお迎えください.
Dreyer T, et al. Comparing cooperative geometric puzzle solving in ants versus humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 Jan 7;122(1):e2414274121. PMID: 39715438(動画はフリーでDL可)
(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)
 今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。
今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます
#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます 佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。
佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。 前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。
前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。 【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動
【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動 🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶
🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶 20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106
20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106 今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。
今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。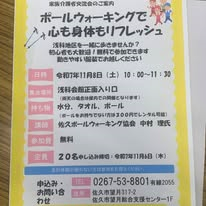 佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️
佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️ 地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。
地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。 【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク
【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。
この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。 2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走
2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走 それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね
それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね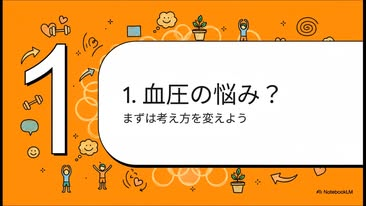 先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM
先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM 2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。
2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。 本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました
本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました 朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。
朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。 【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング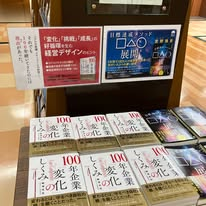 書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ
書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ 本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!
本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください! 大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。
大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。 鎌倉広町緑地でポール歩き
鎌倉広町緑地でポール歩き 【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。
【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。 MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌
MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌 第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。
第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。 11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊
11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊 【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ
【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ 20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘
20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘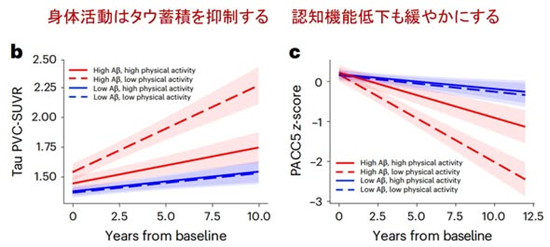
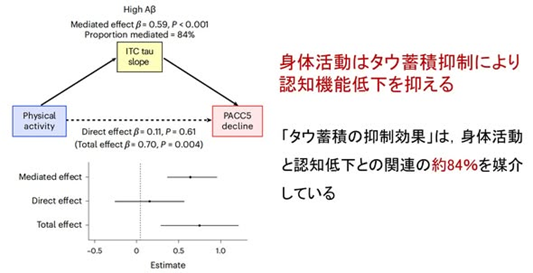 アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.
アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.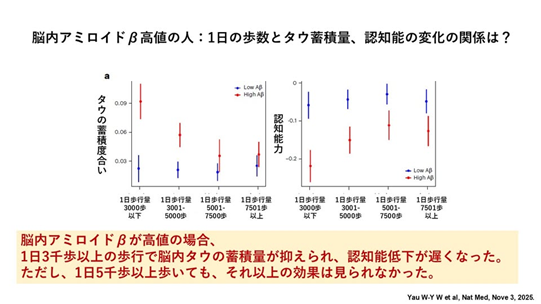 かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。
かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。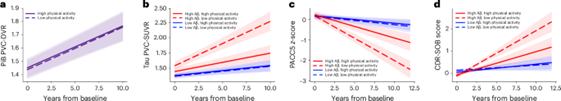 a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。
a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。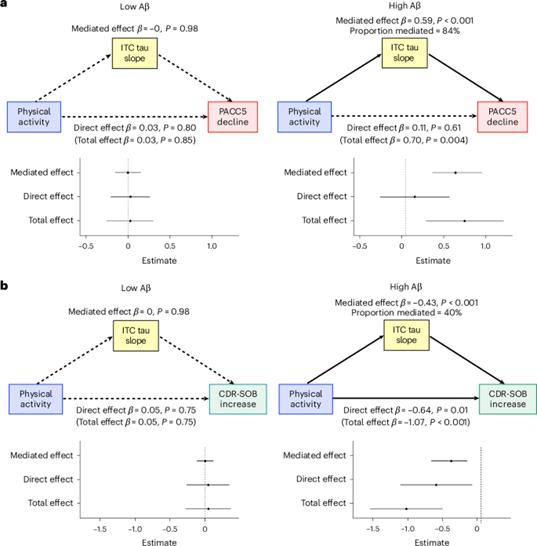 a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。
a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。 a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。
a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。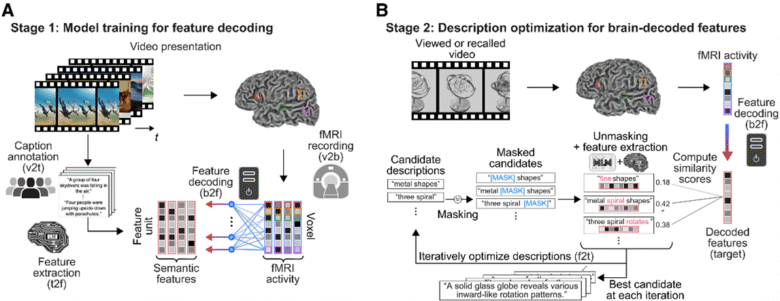 私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。
 機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL
機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL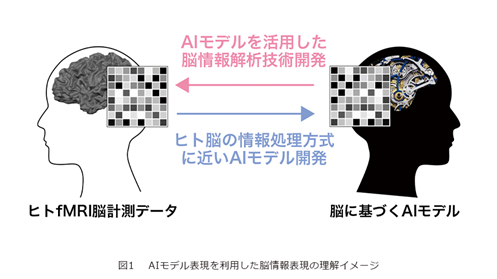
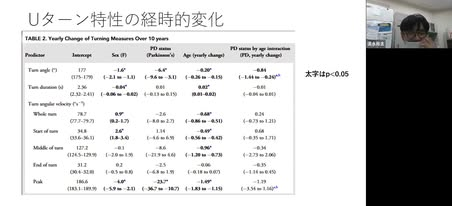 今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.
今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です. 疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.
疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.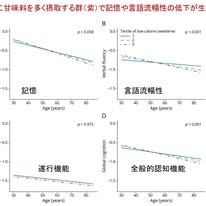 人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.
人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです. 昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.
昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました. ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.
ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.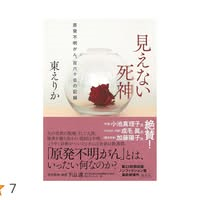 話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.
話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.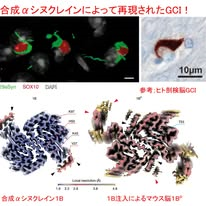 多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.
多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます. 片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.
片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.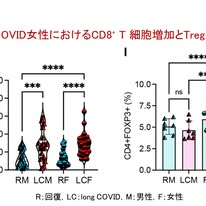 今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.
今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.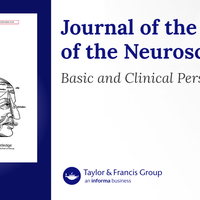 日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.
日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました. 6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.
6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした. 2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).
2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1). 第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.
第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.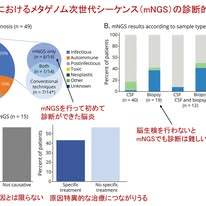 脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.
脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.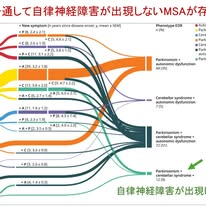 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.
多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.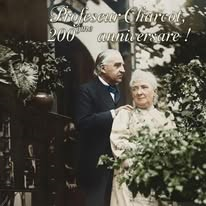 本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.
本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています. 第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。
第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。 【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩
【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩 秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨
秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨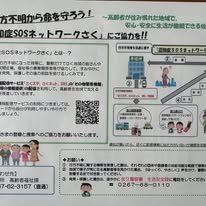 認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。
認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。 ㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。
㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。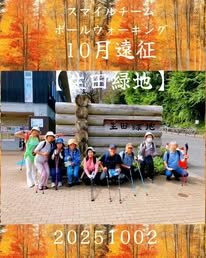 スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館
スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館 今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍
今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍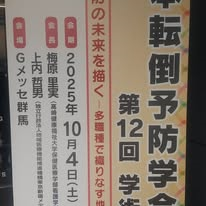 日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️
日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️ 【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会
【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会 佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww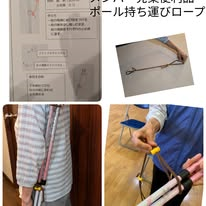 【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ
【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ 清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました
清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット
しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット 2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名
2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名 📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣
📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣 八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く
八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く 今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。
今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。 桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫
桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫ 【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動
【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動 午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡
午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡 佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww 三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。
三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。 10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。
10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。 2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける!
2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける! 一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気!
一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気! 【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング
【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング 秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル
秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル 今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。
今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。 本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝
本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝 2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部
2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部 第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC
第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC 10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊
10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊 月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。
月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。 地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。
地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。 昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭
昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭 今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス
今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス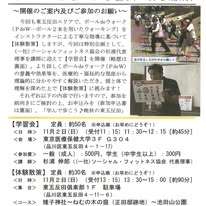 11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。
11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。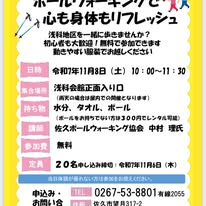 佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。
佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。 🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨
🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨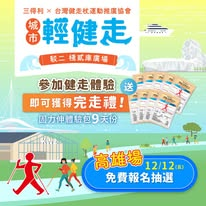 wellness.suntory.com.tw
wellness.suntory.com.tw Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。
Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。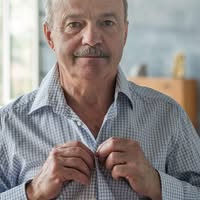 これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。
これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。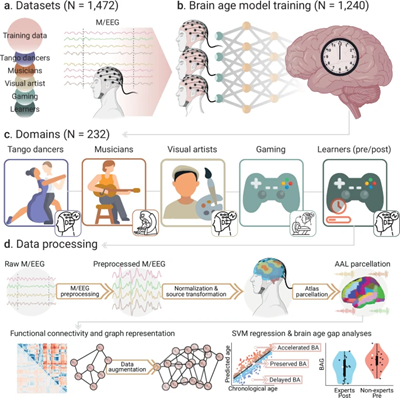 a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。
a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。 タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty
タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty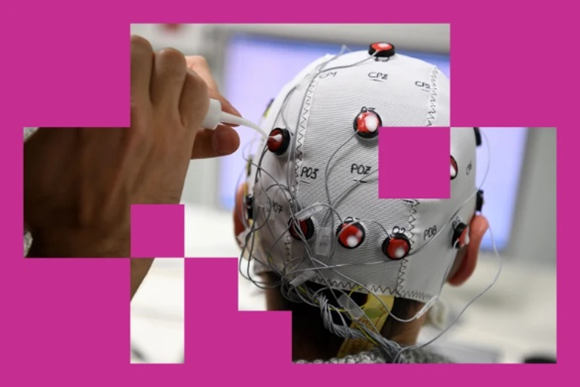 研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty
研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty 英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ
英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ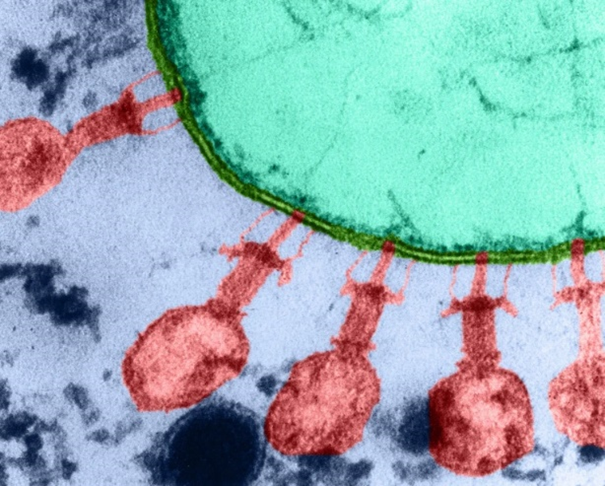 T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。
T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。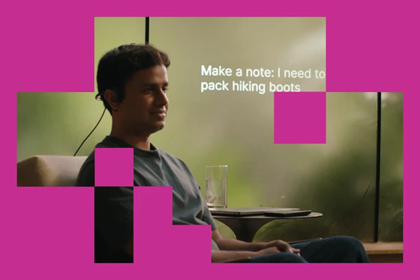 アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ
アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ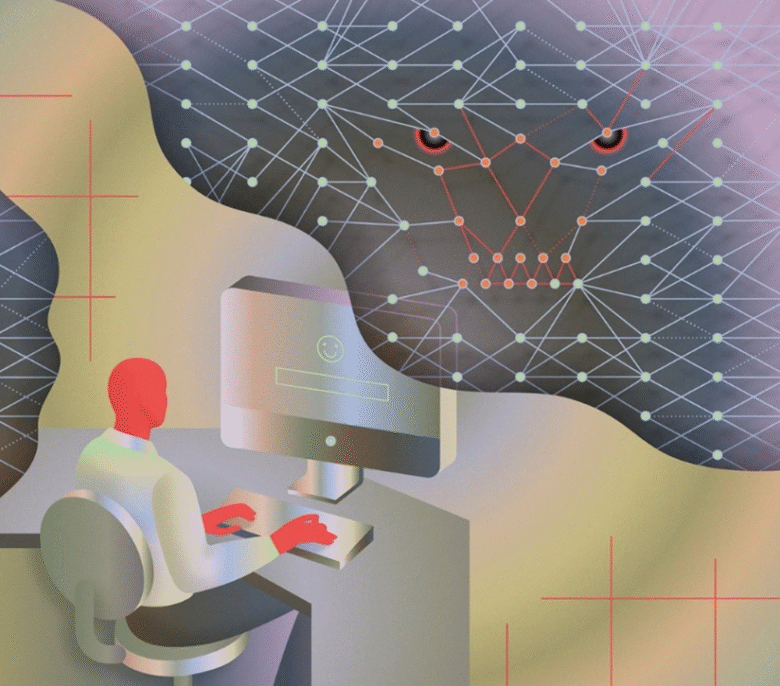 イラスト: アナ・コヴァ
イラスト: アナ・コヴァ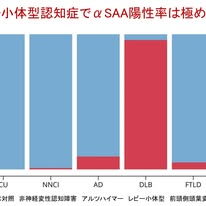 脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.
脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.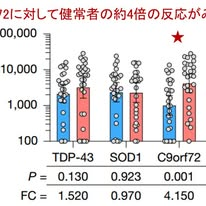 筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.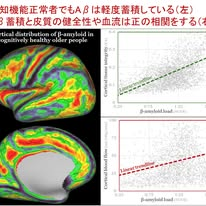 先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.
先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.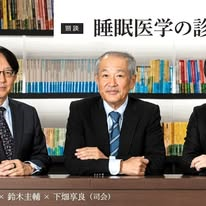 特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました.
特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました. ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.
ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.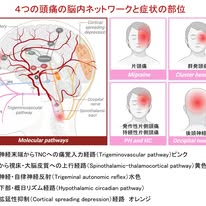 頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.
頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.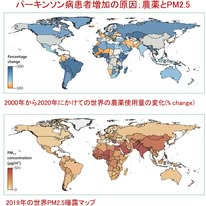 パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.
パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.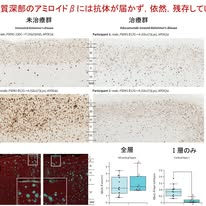 アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.
アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.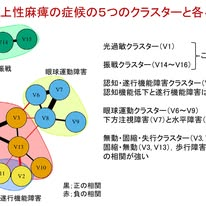 進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.
進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.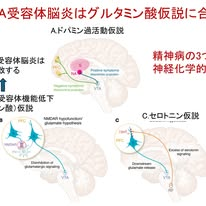 Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.
Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.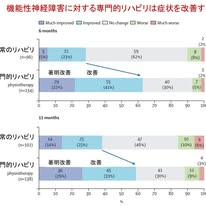 先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.
先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.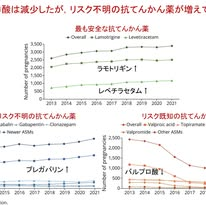 抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました.
抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました. 8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!
8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!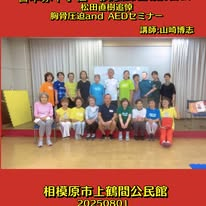 スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801
スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801 佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww
佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww 8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。
8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。 鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!
鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool! 8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。
8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。 スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩
スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩 真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。
真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。 🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!
🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來! 昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。
昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。 佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️
佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️ 8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。
8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。 8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!
8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話! 介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸
介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸 8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。
8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。 本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県
本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県 8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊
8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊 8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。
8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。 昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!
昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!! 8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!
8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話! 8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。
8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。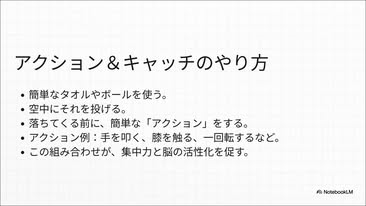 皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。
皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。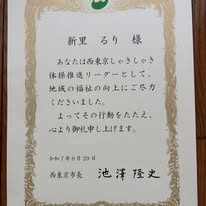 体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。
体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。 写真1件
写真1件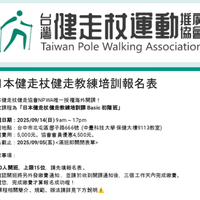 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表 📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!
📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活! 2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部
2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部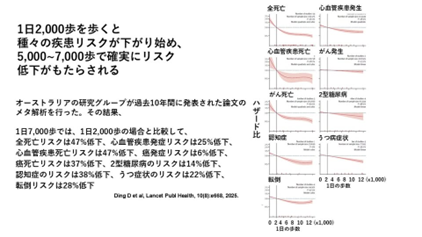 論文
論文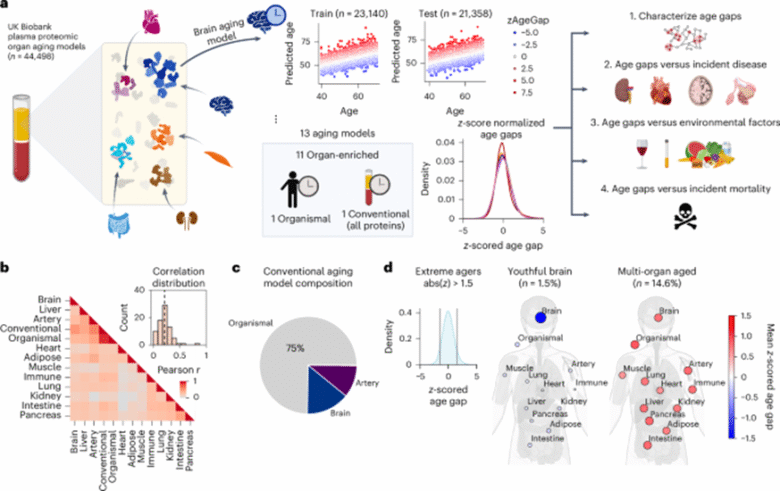 最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。
最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。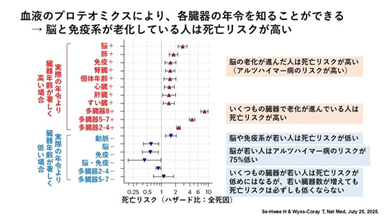 さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。
さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。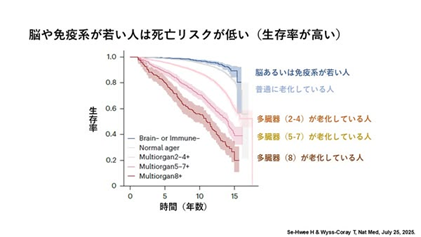 以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。
以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。 先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。
先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。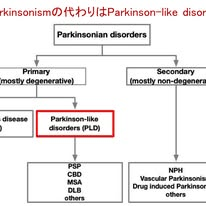 「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.
「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.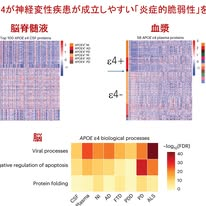 APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.
APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.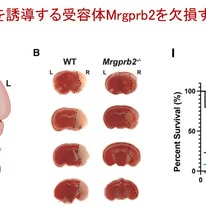 私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.
私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.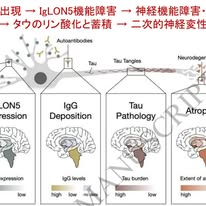 希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.
希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.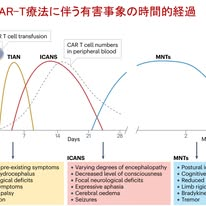 日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.
日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.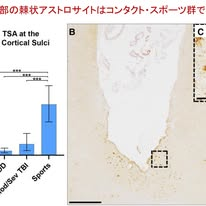 「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.
「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.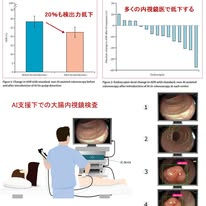 近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.
近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.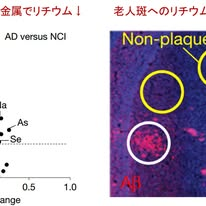 アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.
アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.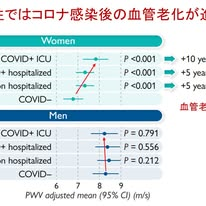 COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.
COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました. 昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.
昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです. アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).
アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります). 標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.
標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.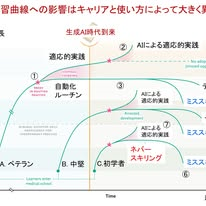 ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.
ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました. 7/1 いよいよ文月です。午後の強烈な雷雨のあとは、涼しくなったように感じました。今朝の火曜サークルは外歩きを変更して室内でポールストレッチ、筋トレのあとは、ステップエクササイズに励みました。少しずつ高さを上げて太股をしっかり上げて1-2、1-2! 徐々に回数も増やし夏休み中の自宅で出来る中強度運動に。 酷暑のため9月まで休暇に皆さん異議なし! 我が家は笹に襲われ中🎋 七夕飾りの枝 たくさんあります。
7/1 いよいよ文月です。午後の強烈な雷雨のあとは、涼しくなったように感じました。今朝の火曜サークルは外歩きを変更して室内でポールストレッチ、筋トレのあとは、ステップエクササイズに励みました。少しずつ高さを上げて太股をしっかり上げて1-2、1-2! 徐々に回数も増やし夏休み中の自宅で出来る中強度運動に。 酷暑のため9月まで休暇に皆さん異議なし! 我が家は笹に襲われ中🎋 七夕飾りの枝 たくさんあります。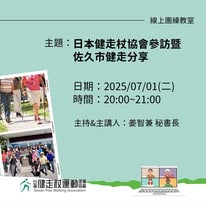 台灣健走杖運動推廣協會邀請指導員、教練們一起線上交流~ 【線上團練教室】 主持人及主講人:姜智兼 主題:日本健走杖協會參訪暨佐久市健走分享 教練分享: ⏰日期:2025/07/01(二) ⏰時間:20:00~21:00 🟩線上團練連結: https://meet.google.com/vuq-mujc-zyk (7:55pm開放入場) 非常歡迎教練們在發展健走杖推廣或教學上有任何想要更了解或交流的主題,請填寫表單,讓交流會安排更符合大家的需要。 https://forms.gle/FQoEDw2muJbjU2W28
台灣健走杖運動推廣協會邀請指導員、教練們一起線上交流~ 【線上團練教室】 主持人及主講人:姜智兼 主題:日本健走杖協會參訪暨佐久市健走分享 教練分享: ⏰日期:2025/07/01(二) ⏰時間:20:00~21:00 🟩線上團練連結: https://meet.google.com/vuq-mujc-zyk (7:55pm開放入場) 非常歡迎教練們在發展健走杖推廣或教學上有任何想要更了解或交流的主題,請填寫表單,讓交流會安排更符合大家的需要。 https://forms.gle/FQoEDw2muJbjU2W28 【暑さ薄れるウォーキング法】 2025/7/1 『#呼吸筋ストレッチ』と 『#呼吸筋活性化ウォーク』 この時期に意識を呼吸に移すと 体幹も心も整います #船橋ウォーキングソサイエティ #県立行田公園 #美姿勢ウォーキング
【暑さ薄れるウォーキング法】 2025/7/1 『#呼吸筋ストレッチ』と 『#呼吸筋活性化ウォーク』 この時期に意識を呼吸に移すと 体幹も心も整います #船橋ウォーキングソサイエティ #県立行田公園 #美姿勢ウォーキング 介護予防運動教室からの(╭☞•́⍛•̀)╭☞からの~ 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニングセッション!! ひまわり🌻いい感じに成長中🫶
介護予防運動教室からの(╭☞•́⍛•̀)╭☞からの~ 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニングセッション!! ひまわり🌻いい感じに成長中🫶 7/2 北鎌倉赤の洞門。 今日は介護予防教室を親子サークル(ネイルサロンも併設)の皆さんとスペース共有して 多世代交流会状態で 賑やかに楽しくエアーポールエクササイズ・チェア🪑筋トレ・脳トレゲームなど楽しめました。
7/2 北鎌倉赤の洞門。 今日は介護予防教室を親子サークル(ネイルサロンも併設)の皆さんとスペース共有して 多世代交流会状態で 賑やかに楽しくエアーポールエクササイズ・チェア🪑筋トレ・脳トレゲームなど楽しめました。 新幹線佐久平駅下りホームの看板を新しくしました。創業100年の看板を5年間も変えずに張っておりまして・・・。既に創業106年目、伝えたいことはいろいろありましたが、一点突破、思い切ってポールウォーキングに振り切りました。 ポールウォーキングをはじめよう!”健康と美” いかがでしょうか(^.^)?
新幹線佐久平駅下りホームの看板を新しくしました。創業100年の看板を5年間も変えずに張っておりまして・・・。既に創業106年目、伝えたいことはいろいろありましたが、一点突破、思い切ってポールウォーキングに振り切りました。 ポールウォーキングをはじめよう!”健康と美” いかがでしょうか(^.^)? 毎年この時期に担当させてもらっているヨガ教室ですが、今年が一番暑かった‥。どんなに暑くても参加率が高く、逆に元気をもらいました😌
毎年この時期に担当させてもらっているヨガ教室ですが、今年が一番暑かった‥。どんなに暑くても参加率が高く、逆に元気をもらいました😌 7/4 今日は渋谷区介護予防 PW教室2025年度2期初日。15名定員ですがお二人を除いて私より若いかたばかり。(私が高齢過ぎる?!)今日は計測日。教室休み明けの渋谷駅前のハチ公広場はハチ公の銅像を残して後ろの和風庭園などすっかりなくなっていました。34年度には新「ハチ公広場」となるそうです。
7/4 今日は渋谷区介護予防 PW教室2025年度2期初日。15名定員ですがお二人を除いて私より若いかたばかり。(私が高齢過ぎる?!)今日は計測日。教室休み明けの渋谷駅前のハチ公広場はハチ公の銅像を残して後ろの和風庭園などすっかりなくなっていました。34年度には新「ハチ公広場」となるそうです。 スキルアップ研修会IN佐久開催しました‼️ 安藤名誉会長にも参加いただきました。 坪井MCPRO,新地MCPROの正確な指導と参加者の真面目な受講姿勢に良好ですのお言葉いただきました‼️ 暑い中、皆さんお疲れ様でした‼️
スキルアップ研修会IN佐久開催しました‼️ 安藤名誉会長にも参加いただきました。 坪井MCPRO,新地MCPROの正確な指導と参加者の真面目な受講姿勢に良好ですのお言葉いただきました‼️ 暑い中、皆さんお疲れ様でした‼️ 佐久ポールウォーキング協会より 本日7月駒場PW例会でした。 佐久も朝から熱中症予防情報が出ている中、集まってくれた60名の参加者で公園〜牧場の木陰を選んでのポールウォーキングでした。 午後はNPWAコーチスキルアップセミナー(佐久会場)で 佐久の地元勿論、埼玉や千葉から#のコーチも集まってのお勉強会でした。 名誉会長/安藤先生も終始同席されPW考案者の立場より的確・明快な返答や指導を頂きました❗️
佐久ポールウォーキング協会より 本日7月駒場PW例会でした。 佐久も朝から熱中症予防情報が出ている中、集まってくれた60名の参加者で公園〜牧場の木陰を選んでのポールウォーキングでした。 午後はNPWAコーチスキルアップセミナー(佐久会場)で 佐久の地元勿論、埼玉や千葉から#のコーチも集まってのお勉強会でした。 名誉会長/安藤先生も終始同席されPW考案者の立場より的確・明快な返答や指導を頂きました❗️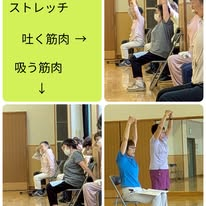 令和7年7月7日 シニアポールウォーキング 「この夏も元気に乗り切る」 そんな気迫みなぎる定例会 になりました #呼吸活性化ウォーキング #インターバルウォーク #ラダーとマットでコグニサイズ エアコンの効いた室内は 身体もしっかり動きます #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング
令和7年7月7日 シニアポールウォーキング 「この夏も元気に乗り切る」 そんな気迫みなぎる定例会 になりました #呼吸活性化ウォーキング #インターバルウォーク #ラダーとマットでコグニサイズ エアコンの効いた室内は 身体もしっかり動きます #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 7/8 今日の三浦ネットPWの活動は中止といたします。 ・・・・・・☀️・・・・・ 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されています。 本日は厳しい暑さが予想されます。 運動は原則中止し、外出はできるだけ控え、こまめに水分補給を行い、エアコン等を活用し、熱中症予防対策の徹底をお願いします。 また、炎天下の車内は大変危険です。わずかな時間であっても子どもを残したまま車から離れないようお願いします。 (市民健康課)
7/8 今日の三浦ネットPWの活動は中止といたします。 ・・・・・・☀️・・・・・ 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されています。 本日は厳しい暑さが予想されます。 運動は原則中止し、外出はできるだけ控え、こまめに水分補給を行い、エアコン等を活用し、熱中症予防対策の徹底をお願いします。 また、炎天下の車内は大変危険です。わずかな時間であっても子どもを残したまま車から離れないようお願いします。 (市民健康課) 写真1件
写真1件 柳澤 光宏さんの動画
柳澤 光宏さんの動画 今日から志木市の健康ポイント事業の計測会🦶多くの方がご参加されます! フットフレイル対策に加えて、オーラルフレイル対策がスタートします👄
今日から志木市の健康ポイント事業の計測会🦶多くの方がご参加されます! フットフレイル対策に加えて、オーラルフレイル対策がスタートします👄 ポケゴミスマイルの日。 #スマイルチーム #ポケゴミスマイル #ポールウォーキングしながらごみ拾い #日本財団海と日本プロジェクト #blueship #ブルーサンタ #記録 #20250710
ポケゴミスマイルの日。 #スマイルチーム #ポケゴミスマイル #ポールウォーキングしながらごみ拾い #日本財団海と日本プロジェクト #blueship #ブルーサンタ #記録 #20250710 7/10 猛暑日対策 「涼める場所あります」←市内に何ヵ所かありますね。今日のPW教室の会場のなごやかセンターには電動運動器具も沢山あり自由に利用できます。今日は欠席者が多くいつもの部屋が広々した感じ。他サークルのラダーをお借りしました。
7/10 猛暑日対策 「涼める場所あります」←市内に何ヵ所かありますね。今日のPW教室の会場のなごやかセンターには電動運動器具も沢山あり自由に利用できます。今日は欠席者が多くいつもの部屋が広々した感じ。他サークルのラダーをお借りしました。 2025.7.7〜11 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 19名 チェア体操 ☺︎令和7年度シニアサポートスタッフ養成研修(相模原市 高齢・障害者支援課) ☺︎親子ふれあい体操 15組 (10ヶ月〜32ヶ月.双子1組) ☺︎青少年指導委員ブロック研修 欠席 ☺︎上鶴間公民館青少年部部会 ☺︎8月日赤救急法短期講習会チラシ作成、申込受付開始 ☺︎ポケごみスマイルチーム 10名 ポールウォーキングdeゴミ拾い #BLUESANTA ☺︎ブルーシップ活動報告レポート提出 (SNSにてアップ) ☺︎相模原市文化協会会議 (9/14の文化協会祭について) ☺︎青空ポールウォーキング 11名 ☺︎スマイルチーム文化協会祭打合せ ☺︎文化協会祭ゲストチーム・ダブルダッチ Millennitm Collection 打合せ
2025.7.7〜11 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 19名 チェア体操 ☺︎令和7年度シニアサポートスタッフ養成研修(相模原市 高齢・障害者支援課) ☺︎親子ふれあい体操 15組 (10ヶ月〜32ヶ月.双子1組) ☺︎青少年指導委員ブロック研修 欠席 ☺︎上鶴間公民館青少年部部会 ☺︎8月日赤救急法短期講習会チラシ作成、申込受付開始 ☺︎ポケごみスマイルチーム 10名 ポールウォーキングdeゴミ拾い #BLUESANTA ☺︎ブルーシップ活動報告レポート提出 (SNSにてアップ) ☺︎相模原市文化協会会議 (9/14の文化協会祭について) ☺︎青空ポールウォーキング 11名 ☺︎スマイルチーム文化協会祭打合せ ☺︎文化協会祭ゲストチーム・ダブルダッチ Millennitm Collection 打合せ 【やるのは今でしょ! 私の番がきたのね】 町内では段々とご年配の方々が旅立ち、或は施設入居やデイサービスへ 在宅でも身体も思うようでは無さそう… 若い家族は赤ちゃんのお世話! 共働きと忙しいのがわかります ごみステーションのカラスよけネットもボロボロ 道路の草も時としてぼうぼうに! 町はちょっとの事を手出ししただけで気持良くすごせる! できる人ができる事をしなくては 【今が私の番】 2025/7/11
【やるのは今でしょ! 私の番がきたのね】 町内では段々とご年配の方々が旅立ち、或は施設入居やデイサービスへ 在宅でも身体も思うようでは無さそう… 若い家族は赤ちゃんのお世話! 共働きと忙しいのがわかります ごみステーションのカラスよけネットもボロボロ 道路の草も時としてぼうぼうに! 町はちょっとの事を手出ししただけで気持良くすごせる! できる人ができる事をしなくては 【今が私の番】 2025/7/11 2本のポールで西荻街歩き 夏場の気ままにポール歩き(気まポ)は、猛暑を考慮して「夕暮れウォーク」にしています。はじめはナイトウォークと呼んでいたのですが、7時頃まで明るいので呼び名を変更しました。 先日の雨のあと気温が下がって、当初の予想よりもずっと快適なウォーキングとなりました。合計12000歩。5km強のつもりだったけど、6kmくらいになったと思われます。 JR西荻窪駅南口に集合、まず仲通街を南下して駅方面にもどって、駅の北側の骨董屋などが並ぶ通りを経て、東京女子大、善福寺公園へ。池のまわりは人気少なく、暗くもなってきていたので、1人では怖そうだなんて言いながら。 帰りは、「はだしのオアシス公園」や「トトロの樹」と呼ぶ大ケヤキのある公園を通って駅近くのレストラン「バルタザール」へ。1階が有機野菜の八百屋で、その2階。3階は書店まで同じ経営です。 バルタザールでは、話題の映画「国宝」の話などで盛り上がりました。見た人3人から、ぜひとお勧め。月内に見るつもりです。 今回、会の常連北村さんが西荻に詳しいので、立ち寄りスポットや打ち上げの店の紹介などでお世話になりました。
2本のポールで西荻街歩き 夏場の気ままにポール歩き(気まポ)は、猛暑を考慮して「夕暮れウォーク」にしています。はじめはナイトウォークと呼んでいたのですが、7時頃まで明るいので呼び名を変更しました。 先日の雨のあと気温が下がって、当初の予想よりもずっと快適なウォーキングとなりました。合計12000歩。5km強のつもりだったけど、6kmくらいになったと思われます。 JR西荻窪駅南口に集合、まず仲通街を南下して駅方面にもどって、駅の北側の骨董屋などが並ぶ通りを経て、東京女子大、善福寺公園へ。池のまわりは人気少なく、暗くもなってきていたので、1人では怖そうだなんて言いながら。 帰りは、「はだしのオアシス公園」や「トトロの樹」と呼ぶ大ケヤキのある公園を通って駅近くのレストラン「バルタザール」へ。1階が有機野菜の八百屋で、その2階。3階は書店まで同じ経営です。 バルタザールでは、話題の映画「国宝」の話などで盛り上がりました。見た人3人から、ぜひとお勧め。月内に見るつもりです。 今回、会の常連北村さんが西荻に詳しいので、立ち寄りスポットや打ち上げの店の紹介などでお世話になりました。 雨天に悩まされた 1期の火曜日定例会でした 2025/7/15 本日も不安定な天気です 「しっかり運動したい」 声に応えて屋内ならではのメニュー #サーキットトレーニング #片足立ちバランスウォーキング #継足ウォーク #バックウォーキング #呼吸筋活性化ウォーキング #ペットボトルで体幹ウォーク #脳トレ 足の先から頭の中まで 動かしてみました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング
雨天に悩まされた 1期の火曜日定例会でした 2025/7/15 本日も不安定な天気です 「しっかり運動したい」 声に応えて屋内ならではのメニュー #サーキットトレーニング #片足立ちバランスウォーキング #継足ウォーク #バックウォーキング #呼吸筋活性化ウォーキング #ペットボトルで体幹ウォーク #脳トレ 足の先から頭の中まで 動かしてみました #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング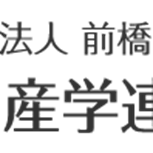 「ポールウォーキング 1日体験会」開催のお知らせ | 研究・産学連携推進本部
「ポールウォーキング 1日体験会」開催のお知らせ | 研究・産学連携推進本部 佐久ポールウォーキング協会より 梅雨明け〜 本日パラダPW散策でした。30℃越えの中、 参議院選挙投票を済ませた?60名越えの参加頂きました。 南パラダ/アスレチックコース〜セラピーロードと暑さを逃れての?癒しのPW〜❗️ マイナスイオンいっぱい〜 パラダ様より温泉券とキッズランド1日パス券の提供も有り皆さん堪能出来た散策となりました。
佐久ポールウォーキング協会より 梅雨明け〜 本日パラダPW散策でした。30℃越えの中、 参議院選挙投票を済ませた?60名越えの参加頂きました。 南パラダ/アスレチックコース〜セラピーロードと暑さを逃れての?癒しのPW〜❗️ マイナスイオンいっぱい〜 パラダ様より温泉券とキッズランド1日パス券の提供も有り皆さん堪能出来た散策となりました。 7/23 北鎌倉介護予防クラス 昨日楽動教室にも参加されたメンバーは連日出席!熱いのに偉いです。仲間と顔を合わせお喋りするのが楽しみかな。会場まで往復歩いて、認知症予防に有効ですね。チェア🪑オーラルエクササイズは嚥下予防です。70代2名のほかは80代の方々ですが皆さん回を重ねるごとに明るく笑顔で元気を増してタフです。毎週計測を続けていますが、暑い☀️連休明けにもかかわらず全員筋肉量アップしていて感心しました。
7/23 北鎌倉介護予防クラス 昨日楽動教室にも参加されたメンバーは連日出席!熱いのに偉いです。仲間と顔を合わせお喋りするのが楽しみかな。会場まで往復歩いて、認知症予防に有効ですね。チェア🪑オーラルエクササイズは嚥下予防です。70代2名のほかは80代の方々ですが皆さん回を重ねるごとに明るく笑顔で元気を増してタフです。毎週計測を続けていますが、暑い☀️連休明けにもかかわらず全員筋肉量アップしていて感心しました。 【令和7年度 佐久市1日有償仕事体験事業】参加学生を募集します!
【令和7年度 佐久市1日有償仕事体験事業】参加学生を募集します! 7/24 東京に比べると鎌倉は2~3℃低いようです。それでも暑いです。挨拶は皆共通「暑いね✨☀️✨」 腰越貯筋サークルでは包括さんの月イチ体測日。皆さん筋肉量upで素晴らしい🙌けれど握力が全体的に低いのはなぜでしょう。今日は1メンバーさんの発案 <行司スクワット>と7秒スクワットで汗を流しました。ローリング歩行はもうしっかりマスターです。次回はお盆休みなのでかき氷で暑気払いをしました。皆お元気で!
7/24 東京に比べると鎌倉は2~3℃低いようです。それでも暑いです。挨拶は皆共通「暑いね✨☀️✨」 腰越貯筋サークルでは包括さんの月イチ体測日。皆さん筋肉量upで素晴らしい🙌けれど握力が全体的に低いのはなぜでしょう。今日は1メンバーさんの発案 <行司スクワット>と7秒スクワットで汗を流しました。ローリング歩行はもうしっかりマスターです。次回はお盆休みなのでかき氷で暑気払いをしました。皆お元気で! 本日も覚悟の暑さです! 思い切ってお家を飛び出したメンバーでひとしきりの運動です #船橋ウォーキングソサイエティ 1期最後の定例会は #2本のポールを使うウォーキング ポールは今日は自宅でお留守番 クーラーの中で頭の中から爪先まで しっかり運動です! 2025/8/24 チェアエクササイズは #ふなばしシルバーリハビリ体操 その場でできる #サーキットトレーニング 狭い場所でも歩ける #バラエティウォーキング 認知症予防に #脳トレエクササイズ お口の体操は #夏休みの過ごし方 8月は夏休みです☀ 9月に元気に会うことを誓って 暑さと上手に付き合いながら お家トレーニングに励みましょう 💪🏝️🔥✨
本日も覚悟の暑さです! 思い切ってお家を飛び出したメンバーでひとしきりの運動です #船橋ウォーキングソサイエティ 1期最後の定例会は #2本のポールを使うウォーキング ポールは今日は自宅でお留守番 クーラーの中で頭の中から爪先まで しっかり運動です! 2025/8/24 チェアエクササイズは #ふなばしシルバーリハビリ体操 その場でできる #サーキットトレーニング 狭い場所でも歩ける #バラエティウォーキング 認知症予防に #脳トレエクササイズ お口の体操は #夏休みの過ごし方 8月は夏休みです☀ 9月に元気に会うことを誓って 暑さと上手に付き合いながら お家トレーニングに励みましょう 💪🏝️🔥✨ 7/25 連日熱中症警戒アラーム💥 消防署ではいつもの梯子の点検が行われていました。渋谷教室の会場 かんなみの杜はこのお隣です。包括支援センターや老人施設と同居なので共用部分はマスク着用😷です。室内はキンキンに冷えて寒いくらい。少し温度を上げて、今日はウォーキングの足の運び方!かかと接地(着地)↔ 後ろ足の踏み込み練習をびっしり練習しましたら全員歩幅が広くなり姿勢もきれいになって大喜び🎵😍🎵 ポールがあればみんな大股🚶♂️🚶♀️🚶 鎌倉から通ってる、っていうと皆びっくりですが湘南ライン1本で55分で楽勝です。車と違って眠れるし、何より楽しい🎶
7/25 連日熱中症警戒アラーム💥 消防署ではいつもの梯子の点検が行われていました。渋谷教室の会場 かんなみの杜はこのお隣です。包括支援センターや老人施設と同居なので共用部分はマスク着用😷です。室内はキンキンに冷えて寒いくらい。少し温度を上げて、今日はウォーキングの足の運び方!かかと接地(着地)↔ 後ろ足の踏み込み練習をびっしり練習しましたら全員歩幅が広くなり姿勢もきれいになって大喜び🎵😍🎵 ポールがあればみんな大股🚶♂️🚶♀️🚶 鎌倉から通ってる、っていうと皆びっくりですが湘南ライン1本で55分で楽勝です。車と違って眠れるし、何より楽しい🎶 20250725. スマイル星ヶ丘。 ポールウォーキング。リハビリポールウォーキング。ウォーキングポールでエクササイズ。 熱中症警戒アラート🥵発令中につき、外歩きはせずに室内でじっくりたっぷりエクササイズしました。 #ポールウォーキング #リハビリポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #
20250725. スマイル星ヶ丘。 ポールウォーキング。リハビリポールウォーキング。ウォーキングポールでエクササイズ。 熱中症警戒アラート🥵発令中につき、外歩きはせずに室内でじっくりたっぷりエクササイズしました。 #ポールウォーキング #リハビリポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ # #2025健走杖輕旅行
#2025健走杖輕旅行 福祉✖️スマイルチーム。 居宅介護支援事業所様からのご依頼を受け リズムダンス等,元気いっぱい体を動かす目的の活動がスタートしました。 ダウン症、自閉症,知的障害,発達障害、既往症、、、 若い世代の皆さん約30名とスタッフさんとで 約1時間半。 歌って踊って喋って、、、汗だく💦 そしてみなさんからたくさんの刺激をもらいました❣️ 次回も楽しみです😊 #福祉 #スマイルチーム #要介護1〜5 #居宅介護支援事業所 #相模原市 #sagamihara #20250725
福祉✖️スマイルチーム。 居宅介護支援事業所様からのご依頼を受け リズムダンス等,元気いっぱい体を動かす目的の活動がスタートしました。 ダウン症、自閉症,知的障害,発達障害、既往症、、、 若い世代の皆さん約30名とスタッフさんとで 約1時間半。 歌って踊って喋って、、、汗だく💦 そしてみなさんからたくさんの刺激をもらいました❣️ 次回も楽しみです😊 #福祉 #スマイルチーム #要介護1〜5 #居宅介護支援事業所 #相模原市 #sagamihara #20250725 7/27 時が経つのは本当に速い! もう7月最後の日曜日です。夕べ 7、8月の逗子PWは猛暑のため中止にすると連絡がありました。開始時間を繰り上げる予定でしたが連日の熱中症警戒アラームへの対処です。事故の心配なくなりひと安心です。時間が出来たので出掛けたいのですが こう暑くては・・・家でみちのくを味わいます。
7/27 時が経つのは本当に速い! もう7月最後の日曜日です。夕べ 7、8月の逗子PWは猛暑のため中止にすると連絡がありました。開始時間を繰り上げる予定でしたが連日の熱中症警戒アラームへの対処です。事故の心配なくなりひと安心です。時間が出来たので出掛けたいのですが こう暑くては・・・家でみちのくを味わいます。 7/31 おはようございます。今朝も心地よい風が吹いています。昨日は激動!?の1日でした。夏空の下、体操の後の月イチお楽しみ会を餌にうきうき🎵北鎌倉へ。カムチャッカの地震の影響で太平洋側へ押し寄せてくる津波注意報(→警報に変わったのを知らず)のサイレンを耳にしながら気にもせず、いつもと変わらずコアトレなど済ますと、お待ちかね!『食』の会をすっかり楽しんで帰宅路へ / <ここが境界> / 海岸方面を走る電車もバスもストップしていたのです(投稿済) 「健康のため」と自ら言い聞かせ炎天下を切通を抜けてPWで帰宅しました。前に進めば家🏚️に帰れる!と言い聞かせ、熱中症が怖くて最近は歩いてないなぁ~!と思いながら。 海の街に住むということ、今回は津波が来たときの対策を真剣に考える機会になりました。 必要なのはタフな心と身体。 今朝の団欒時の「あなたの刺激は何?」→ 「 ! 」
7/31 おはようございます。今朝も心地よい風が吹いています。昨日は激動!?の1日でした。夏空の下、体操の後の月イチお楽しみ会を餌にうきうき🎵北鎌倉へ。カムチャッカの地震の影響で太平洋側へ押し寄せてくる津波注意報(→警報に変わったのを知らず)のサイレンを耳にしながら気にもせず、いつもと変わらずコアトレなど済ますと、お待ちかね!『食』の会をすっかり楽しんで帰宅路へ / <ここが境界> / 海岸方面を走る電車もバスもストップしていたのです(投稿済) 「健康のため」と自ら言い聞かせ炎天下を切通を抜けてPWで帰宅しました。前に進めば家🏚️に帰れる!と言い聞かせ、熱中症が怖くて最近は歩いてないなぁ~!と思いながら。 海の街に住むということ、今回は津波が来たときの対策を真剣に考える機会になりました。 必要なのはタフな心と身体。 今朝の団欒時の「あなたの刺激は何?」→ 「 ! 」 今年も開催します。生プルーン食べ放題の佐久ぴんころウォーク(^^)皆さんのご参加お待ちしています!
今年も開催します。生プルーン食べ放題の佐久ぴんころウォーク(^^)皆さんのご参加お待ちしています!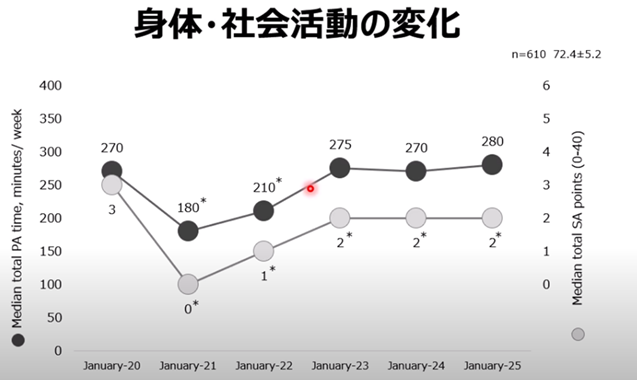 ・コロナ禍1年目で両活動は大きく制限され、
・コロナ禍1年目で両活動は大きく制限され、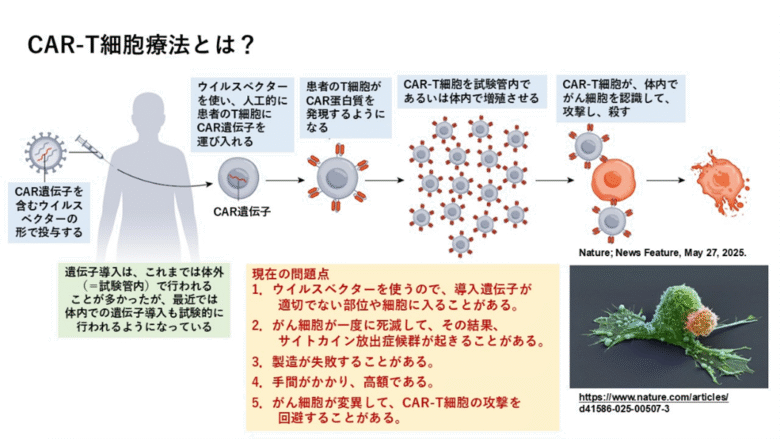 CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。ただし、患者自身のT細胞を集めて、がんを攻撃するように体外で遺伝子改変を施して同じ患者の体内に戻すという、非常に高度な個別化医療であるために、治療の実施には厳格な施設要件があり、日本では60ぐらいの施設でしか使えません。しかし、アメリカではすでにかなり広く使われるようになっていて、多くの医療機関や製薬会社が参画して、現時点でも1兆円以上の市場規模があるようです。
CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。ただし、患者自身のT細胞を集めて、がんを攻撃するように体外で遺伝子改変を施して同じ患者の体内に戻すという、非常に高度な個別化医療であるために、治療の実施には厳格な施設要件があり、日本では60ぐらいの施設でしか使えません。しかし、アメリカではすでにかなり広く使われるようになっていて、多くの医療機関や製薬会社が参画して、現時点でも1兆円以上の市場規模があるようです。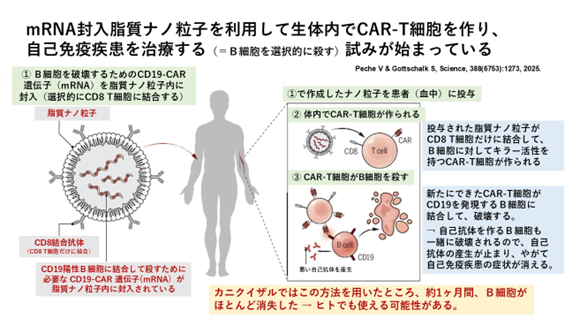 CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。
CAR-T細胞療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞を遺伝子導入によって新たに作り、それを増やして、がんを攻撃させるという新しい治療法です。CARというのはchimeric antigen receptor、すなわち、遺伝子導入によってT細胞に導入するキメラ抗原レセプター(人工的抗原レセプター)のことです。この治療法は、難治性の血液系の悪性腫瘍に対して大きな治療効果を示します。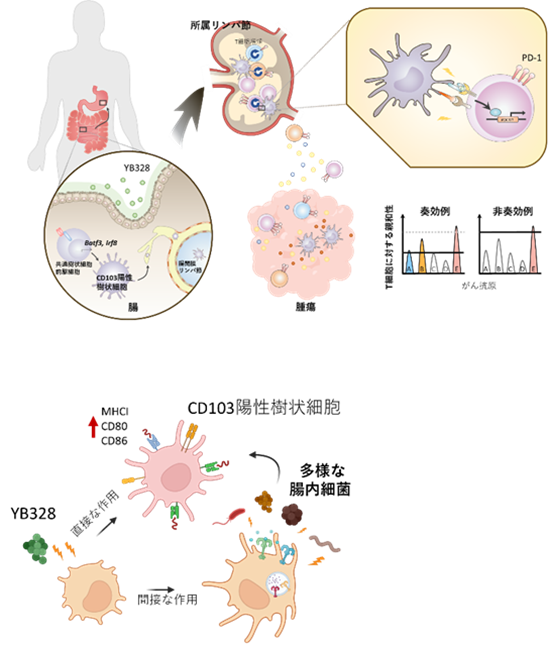
 パリでの学会(https://charcot2025.fr/)に参加する前に,週末を利用してアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れました.リベラルアーツ研究会で「夜と霧(https://amzn.to/46lteC8)」を取り上げた際に関連資料を読み漁ったため,知識としては理解していたつもりでしたが,実際にその場に立つと,まったく異なる感情がこみ上げてきました.毒ガス・チクロンBが投げ込まれたガス室,そして通路一面に貼られた被収容者の顔写真を前にしたとき,胸が押しつぶされるような苦しさを覚えました.戦争は人間をここまで残虐にするのかという思いが改めて浮かびました.
パリでの学会(https://charcot2025.fr/)に参加する前に,週末を利用してアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れました.リベラルアーツ研究会で「夜と霧(https://amzn.to/46lteC8)」を取り上げた際に関連資料を読み漁ったため,知識としては理解していたつもりでしたが,実際にその場に立つと,まったく異なる感情がこみ上げてきました.毒ガス・チクロンBが投げ込まれたガス室,そして通路一面に貼られた被収容者の顔写真を前にしたとき,胸が押しつぶされるような苦しさを覚えました.戦争は人間をここまで残虐にするのかという思いが改めて浮かびました. ジャン・マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot;1825–1893年)は,フランスの神経病学者であり,その名は多くの疾患や症候に残されています.彼の業績は医学にとどまらず,芸術や文学など広範な文化領域にまで影響を与えました.本年は,シャルコー生誕200年の節目に当たるため,第29回国際神経科学史学会(ISHN)は「シャルコー生誕200年記念式典」を兼ねて,パリのサルペトリエール病院内にあるICM Institute for Brain and Spinal Cordにて開催されています.
ジャン・マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot;1825–1893年)は,フランスの神経病学者であり,その名は多くの疾患や症候に残されています.彼の業績は医学にとどまらず,芸術や文学など広範な文化領域にまで影響を与えました.本年は,シャルコー生誕200年の節目に当たるため,第29回国際神経科学史学会(ISHN)は「シャルコー生誕200年記念式典」を兼ねて,パリのサルペトリエール病院内にあるICM Institute for Brain and Spinal Cordにて開催されています.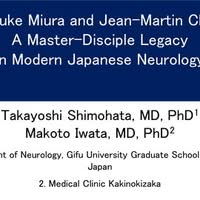 お蔭さまで,無事に講演を終了しました.終了後,多くの先生が集まって来られて,Congraturations!と言っていただき大変驚きました.これまで経験のないことで感激しました.三浦謹之助先生とシャルコー先生の師弟関係に心を動かされた先生が多かったのかなと思いました.
お蔭さまで,無事に講演を終了しました.終了後,多くの先生が集まって来られて,Congraturations!と言っていただき大変驚きました.これまで経験のないことで感激しました.三浦謹之助先生とシャルコー先生の師弟関係に心を動かされた先生が多かったのかなと思いました.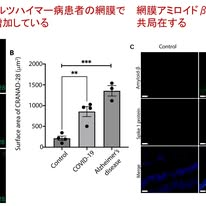 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染がアルツハイマー病発症のリスクを増加させるという複数の研究が報告されていますが,最新のScience Advances誌に報告された研究は,網膜においてアルツハイマー病様のアミロイドβ(Aβ)病理がCOVID-19によって誘導されることを示したもので注目されます.米国イェール大学眼科などの共同研究です.
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染がアルツハイマー病発症のリスクを増加させるという複数の研究が報告されていますが,最新のScience Advances誌に報告された研究は,網膜においてアルツハイマー病様のアミロイドβ(Aβ)病理がCOVID-19によって誘導されることを示したもので注目されます.米国イェール大学眼科などの共同研究です.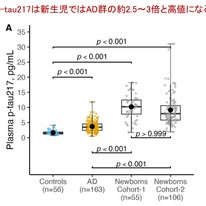 非常に驚いた報告です.スウェーデンを初めとするなど多数の研究機関が参加した国際共同研究です.チームは,「タウ蛋白のリン酸化が脳の発達と神経変性の両方に重要な役割を果たす」という仮説のもと,新生児を含む健常者とアルツハイマー病(AD)患者における血漿リン酸化タウ217(p-tau217)濃度を比較しました.
非常に驚いた報告です.スウェーデンを初めとするなど多数の研究機関が参加した国際共同研究です.チームは,「タウ蛋白のリン酸化が脳の発達と神経変性の両方に重要な役割を果たす」という仮説のもと,新生児を含む健常者とアルツハイマー病(AD)患者における血漿リン酸化タウ217(p-tau217)濃度を比較しました.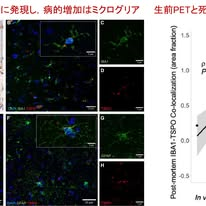 進行性核上性麻痺(PSP)は,中脳や大脳皮質にタウが蓄積し,運動障害や認知機能障害を引き起こすタウオパチーの代表的疾患です.これまで,神経炎症とタウの脳内伝播が病態進行に関与すると考えられてきましたが,その直接的証拠は限られていました.今回紹介する2つの研究は,TSPO PET画像と死後脳との対応づけ,およびタウのシナプス伝播機構の可視化というアプローチで,PSPの病態理解を大きく進めるものです.
進行性核上性麻痺(PSP)は,中脳や大脳皮質にタウが蓄積し,運動障害や認知機能障害を引き起こすタウオパチーの代表的疾患です.これまで,神経炎症とタウの脳内伝播が病態進行に関与すると考えられてきましたが,その直接的証拠は限られていました.今回紹介する2つの研究は,TSPO PET画像と死後脳との対応づけ,およびタウのシナプス伝播機構の可視化というアプローチで,PSPの病態理解を大きく進めるものです.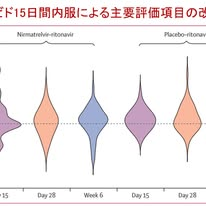 今回のキーワードは,long COVIDに対する抗ウイルス薬の単独使用では短期間での症状改善は見込めない,パーキンソン病患者ではCOVID-19罹患により長期的予後が悪化する,COVID-19後に現れる新たな片頭痛様頭痛―2年後も続く後遺症としての頭痛,Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群では共通する病態として「酸化ストレス」があり女性に顕著である,パンデミックにより感染しなくても脳の老化は進むが認知機能の低下は感染によってさらに深刻になる,です.
今回のキーワードは,long COVIDに対する抗ウイルス薬の単独使用では短期間での症状改善は見込めない,パーキンソン病患者ではCOVID-19罹患により長期的予後が悪化する,COVID-19後に現れる新たな片頭痛様頭痛―2年後も続く後遺症としての頭痛,Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群では共通する病態として「酸化ストレス」があり女性に顕著である,パンデミックにより感染しなくても脳の老化は進むが認知機能の低下は感染によってさらに深刻になる,です.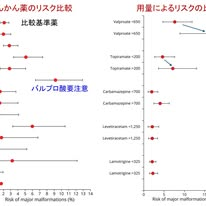 抗てんかん薬(Antiseizure Medication;ASM)は,妊娠中の使用に際して胎児への影響を十分に考慮する必要があります.2025年に発表された北米抗てんかん薬妊娠レジストリ(North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry)のデータから,妊娠初期に使用された薬剤ごとの主要な先天奇形のリスクが報告されました.図左に示されているように,主要奇形のリスクは以下の通りです:
抗てんかん薬(Antiseizure Medication;ASM)は,妊娠中の使用に際して胎児への影響を十分に考慮する必要があります.2025年に発表された北米抗てんかん薬妊娠レジストリ(North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry)のデータから,妊娠初期に使用された薬剤ごとの主要な先天奇形のリスクが報告されました.図左に示されているように,主要奇形のリスクは以下の通りです: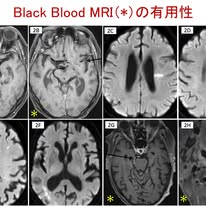 がん免疫療法に用いられる免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitor: ICI)は,進行がんの予後を大きく改善させる一方で,免疫関連有害事象(irAE)を引き起こすことが知られています.その中に中枢神経系に影響を及ぼす神経学的有害事象(nirAE)がありますが,とくに「免疫関連中枢神経血管炎(nirVasculitis)」は診断が難しく,重篤な転帰を取ることもあります.このnirVasculitisに関する最大規模のsystematic reviewが発表されています.自験例6例を含む計20症例が検討されています.
がん免疫療法に用いられる免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitor: ICI)は,進行がんの予後を大きく改善させる一方で,免疫関連有害事象(irAE)を引き起こすことが知られています.その中に中枢神経系に影響を及ぼす神経学的有害事象(nirAE)がありますが,とくに「免疫関連中枢神経血管炎(nirVasculitis)」は診断が難しく,重篤な転帰を取ることもあります.このnirVasculitisに関する最大規模のsystematic reviewが発表されています.自験例6例を含む計20症例が検討されています. 6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。
6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。 佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。
佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。 【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います!
【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います! 6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/
6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/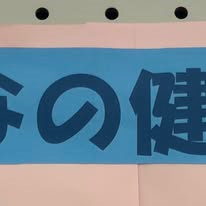 昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座
昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座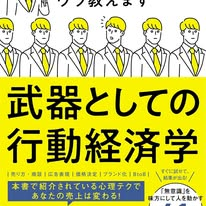 できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。
できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。 6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな?
6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな? Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング
Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング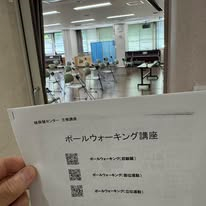 本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり
本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり 第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️
第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️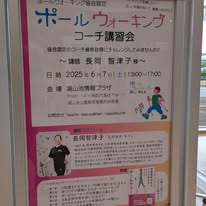 初上陸
初上陸 6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね)
6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね) #これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7
#これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7 佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️
佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️ 6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦
6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦 さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥
さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥 昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操
昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操 6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略
6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略 6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。
6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。 #船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。
#船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。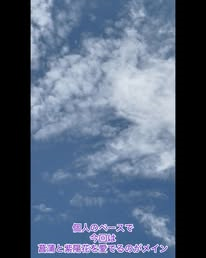

 緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。
緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。 6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。
6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。 いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。
いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。 6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。
6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。 猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり
猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり ㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇
㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇 6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。
6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。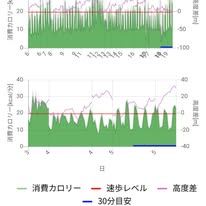 【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き
【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き #ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ
#ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ 【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体
【2023年6月ポールウォーキング体験イベント開催】の様子‼️ #ポールウォーキング #イベント #体験レッスン #芦屋町 #遠賀郡芦屋町 #夏井ヶ浜 #はまゆう公園 #恋人の聖地 #紫陽花 #2023年 #スポーツ推進委員会 #社会教育係 #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #福岡県 #町民 #自治体 先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。
先々週、ポールを持つ仲間十数人と秩父三峯神社と小鹿野町を旅しました。 何キロ歩くとか競争するとか何もなく仲間達と旅するのもまた楽しいものでした。 Facebookにいない方々が多く顔写真は無しで景色のみ。 まだ梅雨空で霧がかかった涼しい日でした。 写真は皆さんから頂いたものが殆どで順不同です🤳 しばらく休みなしだったのて頭の中がキリキリ舞いで 「もう計画するのやだー😭」と愚痴ってごめんなさい🙇♀️ 自己管理は自分の責任。汗 昨日今日と休んで落ち着きました。汗 皆さんが楽しい楽しいと喜んで下さり、 何と嬉しいことか。。。 ひと息ついた頃にはグチったのも忘れ、 「次はあそこ行って♨️あれしてこれして」などと また次の旅を妄想しているワタシなのでした。 6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。
6/22 青空に夏の太陽でしたがとても心地良い風に吹かれて逗子市ポールウォーキング会実施できました。自宅庭に入り込んだ青大将を集合の椿公園の奥に放した◎さん、洗濯物の籠に蜂が入っていて親指を刺され急遽欠席の○さん、思いがけないことが起きます。次回は30分繰り上げます。今日は休憩中にグループに別れて「土瓶・茶瓶」ゲームで脳を活性化しました(笑)沖縄の花デイゴと立派な合歓木が素晴らしい咲きっぷりでした。 海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl
海老川ノウゼンカツラトンネルを くぐり上流の木陰へ向いました。 風がぬける場所で ウォーミングアップは 新メニューで! 川面を渡る風を受け 爽やかに歩き終えました♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #ポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #mcl 「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています!
「タビランド」に行ってきました。東京都あきる野市。 タビランドというのは、医師兼作家(著書300点以上!)の 米山 公啓先生がDIYに凝りながら作ってきている、ドッグランとグランピング場を兼ねたような空間です。ですから、タビランドの主は愛犬の豆柴たたみちゃんです。 一行は、私が毎月やっている気まポ(気ままにポール歩き)のメンバー6人と近未来研究会メンバー石原さん、それにネパール出身の武田座奈久さんです。 米山先生と石原さん、私は近未来研の仲間です。武田さんは、以前浜田山でインド・ネパール料理店を経営していて、ポール歩きの会ではたびたびお世話になりましたし、近未来研の会場としても助けていただきました。 タビランドでさんざんごちそうになったあと、隣のログハウスに移ったのですが、居心地がよすぎて、合計4時間半くらい長居してしまいました。 米山先生との出会いは、もう10年以上前になると思います。先生がウォーキングを推奨する本を出しておられて、その中でノルディックウォーキングのことを紹介されていました。それで連絡をとって会っていただきました。 先生にはNPO法人みんなの元気学校の特別顧問でもあります。ノーギャラだし、もう忘れておられると思いますが(^^)。 医療の世界は曲がり角に来ていると言われています。医師兼作家の視野に加え反骨精神もある先生には、改めて社会的な発信を期待しています! 【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座
【足からコツコツ健康ライフ】 〜ポールウォーキング&セルフフットケア講座〜 先日のこと! 八幡大谷市民センターでの2回連続講座が無事終了しました! 八幡大谷市民センター館長にご依頼いただいて7年目にしてようやく実現しました✨️✨️✨️ しかも2講座ご依頼いただきまして ご縁に感謝です! とても嬉しく思いました! ✨1回目はポールウォーキングをみっちり2時間!! 参加者の皆さんの“学びたい熱”がすごくて部屋に入った瞬間ちょっと圧倒されてしまいました💦(笑) でもそれは本気の気迫🔥 「膝の痛みを改善したい」「ポールを活かしたい」など皆さんの目的や思いが真っ直ぐに伝わってきて私も全力で向き合いました🫡 ポールを持って歩くと姿勢もよくなるし歩くことに自信が持てることなる、すたすた歩けて気持ちいいと言っていただきました! みなさんの本気の気迫がすごくて 2時間じゃあたりなかったですねぇwww ✨2回目は前回の復習+セルフフットケア👣 ポールウォーキングの復習の前に ダイヤモンドカットボールを使いながら足骨格にアプローチ🦶 お天気よかったら外歩きをおこなう予定でしたが残念ながら土砂降り//☂// 足のケアははじめての方がほとんどで 足指の動きやバランスの変化、特に床を捉えて歩くという感覚は「目からウロコ!」の声が続々でした✨ 足はからだを支える土台👣 動けること、立てること、歩けること、 そのすべてを支えているのは「足」 私自身の実体験からも、足のケアの大切さを強く感じています。 年齢を重ねるほどに、足元からのケアが未来のからだづくりにつながります✨ そして…なんと!今回、とても嬉しいことがもうひとつありました!!(ひとつめは7年越しの実現) 以前、取材でお世話になった某役場の広報担当の方にも2講座ご参加いただいて数年ぶりのリアル再会に感激😭 【足からコツコツ健康ライフ】講座にご参加くださった皆さんにとって有意義な時間になっていたら嬉しいですが… 実は、私自身にとってもとても有意義で、学びの多い時間でした✨ これからも地域の皆様の 「健康ライフ」をサポートしていけたらと思います!! 【ポールウォーキング】と【セルフフットケア】のコラボは最強🔥💪 【ポールウォーキング】 【セルフフットケア】単発でも、もちろんOK👌 講座のリクエストお待ちしてます🌟 #ポールウォーキング #セルフフットケア #健康づくり #足から健康 #ダイヤモンドカットボール #ボディケア #地域のつながり #再会に感謝 #八幡大谷市民センター #ゲンキクリエイターケイコ #フットセラピスト #市民講座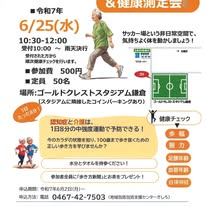 梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。
梅雨の晴れ間を楽しみながら 暑熱順化。 地元鎌倉インターナショナルFCのピッチを頻繁に休憩を挟みながら気持ちよく歩きました。フレイル予防、お出かけ促進、多世代交流と、従来活動の標準化モデルがカタチになってきました。 6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。
6/25 大船・北鎌倉地域中心の「生き生きウォーク&健康測定会」開催。なんとなんとなんと!悪天候のはずの朝から、雨が降ったのはピタリ始まる直前までと終了後。皆さん濡れずにゴールドクレストスタジアムの芝生を闊歩できました。骨量・歩幅等々チェックしたあとは 認知症・介護予防の歩き方教室。速歩を、慌て急ぎ足ではなく 肩を下げ、前を見て、しっかり歩きで1日5000歩(その中に8分のしっかり中強度歩き:2分×4も可)を体験しました。 6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。
6/26 6月最後の教室はなごやかセンターで貯筋クラスでした。暑い中参加されたメンバーで7-8月の予定を決めました。8月のお盆の14日だけお休みに。暑さなど何のその、皆さんやる気満々です。今日の計測で筋肉率が脂肪率をオーバーする男性が!目を閉じて足踏み→前に進む人、後ろに下がる人 ぶつかって大笑い。骨盤の傾きがわかります。 2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025/6/26 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ
【介護予防運動教室でポールウォーキング🚶♀️✨】 本日の介護予防運動教室では ポールウォーキングやってみたぁーーーー!!というリクエストにお応えしてポールウォーキングにチャレンジしていただきました🥳 最初はちょっと戸惑いながらも、みなさん一歩一歩前へ👏 「ものすごく脳を使った~!」 「自然に歩幅が広がるのね、すごい!」 そんな嬉しい声も😊 はじめての刺激が、心と体に心地よいスパイスとなりました💫 #ポールウォーキング #室内 #脳を鍛える #姿勢改善 #歩行能力 #歩行運動 #転倒予防 #介護予防運動 #歩くこと #歩けるからだ #動けるからだ #北九州 #ゲンキクリエイターケイコ #福岡県 #ポールウォーキングマスターコーチプロ 6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや
6/29 友あり 遠方より来る また楽しからずや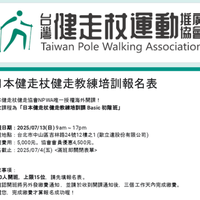 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表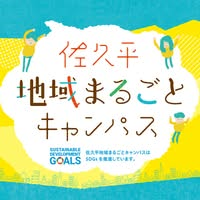 佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス!
佐久平地域まるごとキャンパス | 地域に見つけよう 君のキャンパス! 〇目 的
〇目 的 図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪
図1 オーラルフレイルへの対応はキュアとケアの両輪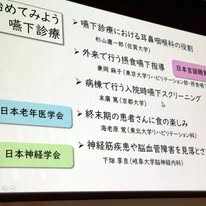 第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.
第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会・学術講演会において開催された標題のシンポジウムにて,「神経筋疾患や脳血管障害を見落とさないために」という講演の機会を頂戴しました.本シンポジウムは,多学会の連携によって嚥下障害への理解と対策を広める日本医学会TEAMS事業の一環として開催されたものです.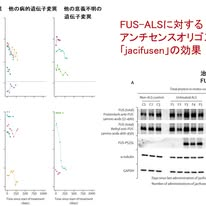 難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.
難攻不落とされてきた神経難病,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療の実現は,私たち脳神経内科医にとって,まさに長年の悲願と呼ぶべきものです.近年,治療法開発に向けて目覚ましい進展が見られるなかでも,とくにSOD1遺伝子変異を有する家族性ALSに対しては,その遺伝子発現を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤「トフェルセン(tofersen)」が臨床応用され,治療の手が届く時代が到来しつつあります.同様に,FUS遺伝子変異によって発症する家族性ALS(FUS-ALS)も注目すべき疾患の一つです.これは若年で発症し,極めて急速に進行することが多いため,これまで非常に予後不良なタイプとして知られてきました.このたび,Columbia大学を中心とする多施設共同研究グループは,FUS pre-mRNAを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド「jacifusen」の効果と安全性を検討したケースシリーズの結果を報告しました.アメリカとスイスの5つの医療機関で実施された成果をまとめたもので,Lancet誌に報告されました.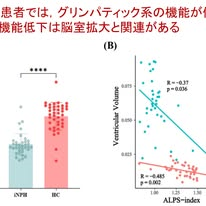 特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.
特発性正常圧水頭症(idiopathic normal pressure hydrocephalus:iNPH)は,歩行障害,認知機能障害,尿失禁を3徴とし,脳室シャント術が有効とされている疾患です.しかし,シャント術の治療効果のメカニズムについては,いまだ解明されていません.今回,中国の研究グループより,iNPHにおけるグリンパティック系の機能障害と,シャント術によるその回復についての研究がEur J Neurol誌に報告されました.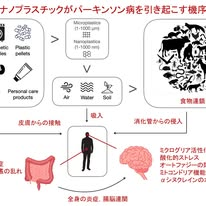 Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024).
Movement Disorders誌の最新号に,イタリア・サレルノ大学のRoberto Erro先生らによって執筆された総説です.食品や水,大気などから体内に取り込まれるマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)と心血管障害,認知症の関連が話題ですが,今度はパーキンソン病(PD)の発症や進行に深く関与する可能性が指摘されています.論文タイトルの「プラスタミネーション(plastamination)」は,昨年提唱された新語で,「plastic(プラスチック)」と「contamination(汚染)」を組み合わせたものです(Santoro et al., Curr Neuropharmacol 2024). 驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.
驚くべき論文がNature誌に掲載されました.脳脊髄液(CSF)は,脳内の老廃物や異常タンパク質を除去し,中枢神経系の恒常性を保つうえで重要な役割を果たしています(グリンファティック・システム).そのCSFの排出経路の一つとして,近年,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目を集めています.今回,韓国KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)などのグループは,このCSF排出経路を促進する物理的刺激法を開発し,マウスとカニクイザルにおいて有効性を確認しました.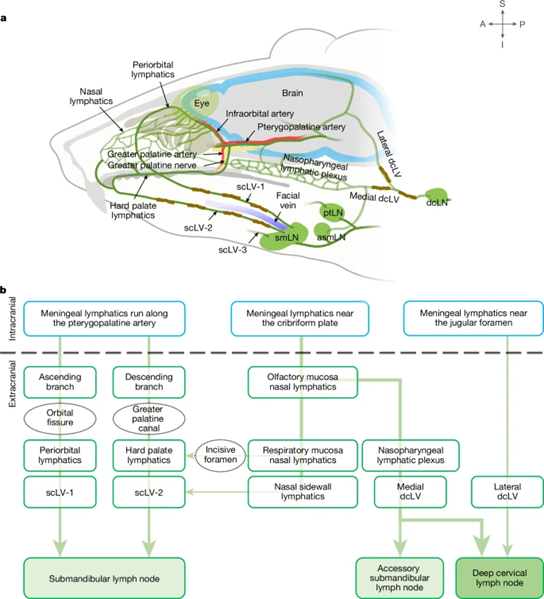 a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。
a、b図 ( a ) とフローチャート ( b ) は、髄膜リンパ管から複数のリンパ経路を通って浅頸部リンパ節と深頸部リンパ節に髄液が排出される複雑なリンパ系を示しています。 (1) 翼口蓋動脈と眼窩下動脈に沿って走る髄膜リンパ管は眼窩裂を横断して眼窩周囲リンパ管に結合し、scLV-1 を介して髄液を顎下リンパ節 (smLN) に運びます。 (2) 翼口蓋動脈、大口蓋動脈、大口蓋神経に沿って走る髄膜リンパ管の一部は大口蓋管を横断し、硬口蓋リンパ叢に結合して scLV-2 に至り、髄液を smLN に排出します。 (3) 嗅球近傍の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻粘膜および鼻側壁のリンパ管と合流して脳脊髄液をscLV-2へ輸送し、smLNへと導く。あるいは、鼻リンパ管は切歯孔を横断して硬口蓋リンパ叢と合流し、scLV-2およびsmLNへと導く。(4) 嗅球近傍の他の髄膜リンパ管は篩骨板を横断し、鼻咽頭リンパ叢につながる鼻リンパ管と合流して脳脊髄液を内側dcLVへ輸送し、副顎下リンパ節(asmLN)または深頸リンパ節(dcLN)へと導く。 (5) 頭蓋底の髄膜リンパ管は頸静脈孔を横切り、dcLNに向かう途中で外側dcLVに合流する。(6) 耳下腺リンパ節(ptLN)は髄液の排出を受けない。解剖学上の位置は右上に示されている。A:前方、I:下方、P:後方、S:上方。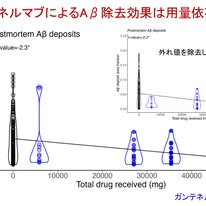 Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.
Acta Neuropathologica誌にインパクトのある論文が掲載されています.アミロイドβ抗体であるガンテネルマブの効果を複数の剖検脳で直接検討した報告であり,ワシントン大学を中心とするグループによって行われました.この研究は,常染色体顕性遺伝性アルツハイマー病(DIAD)を対象とした臨床試験「DIAN-TU-001」によるものです.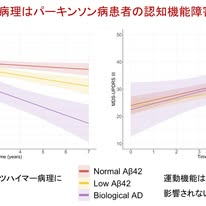 パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.
パーキンソン病(PD)における認知機能障害は,生活の質に大きな影響を与える非運動症状の一つです.また検査による客観的な認知機能障害が認められないにもかかわらず,患者本人が「もの忘れ」などの認知低下を訴える状態はParkinson’s Disease – Subjective Cognitive Decline(PD-SCD)と呼ばれ,将来的な認知機能障害の前駆状態である可能性が指摘されています.スペインから,このPD-SCD患者において,脳脊髄液中のアルツハイマー病(AD)関連バイオマーカー(Aβ42およびp-tau181)と,その後の認知機能低下との関連を明らかにすることを目的とした研究が報告されました.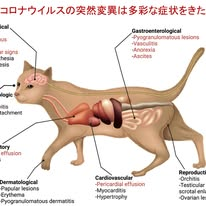 臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).
臨床実習中の学生から相談を受けました.「保護猫施設でボランティアをしているが,眼振やふらつき歩行の猫を少なからず見かける」というのです.猫の話題なので私が関心を持たないはずはなく,以前ひそかに購入した獣医向け教科書「犬と猫の神経病学(https://amzn.to/45wjhS5)」を取り出し,付録のDVDをいっしょに見て,猫の眼振の診察法を確認しました.方向から水平眼振,垂直眼振,回転眼振,眼球が左右(上下)に動くスピードにより急速相と緩徐相,そして左右(上下)の揺れのスピードに差がないものを振子眼振,と確認して,まず責任病変を探ろうということで猫の臨床実習開始です(笑).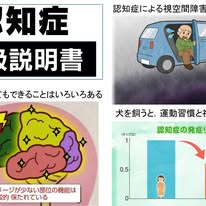 認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした.
認知症をテーマにした特集が,6月19日にNHK「あしたが変わるトリセツショー」で放送されました.「認知症=能力が失われ,何もできなくなる」という多くの人が抱く思い込みに対し,「できること」に注目した新しい視点が紹介されました.「認知症になっても,できること・やりたいことがあり,自分らしく生きることができる」という考えは「新しい認知症観」と呼ばれています.番組ではその具体的な例として,認知症のある「先輩」方の声や,生活の中での工夫,社会的孤立を防ぐために周囲との関係性を大切にする取り組みが丁寧に描かれており,非常に見ごたえのある45分でした.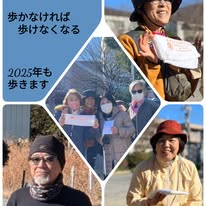 #2025年初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ 新年明けて4日目で もう活動開始です スッキリ&ニッコリ 今年も宜しくお願い致します #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜日コース #松の内の定例会 #サーキットトレーニング #お正月太りは早めに解消 #お年賀タオル
#2025年初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ 新年明けて4日目で もう活動開始です スッキリ&ニッコリ 今年も宜しくお願い致します #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜日コース #松の内の定例会 #サーキットトレーニング #お正月太りは早めに解消 #お年賀タオル #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 2025/1/6 「おめでとうございます」 と行き交う初顔合わせ 静かなやる気(長続きのコツ❤️) のメンバーに 新入会員2名が加わりました #コグニサイズ #体幹バランス 頭の中から足先まで 今日もしっかり動かしました〜 #転倒予防 #認知症予防 #姿勢改善 #チェアエクササイズ #ストレッチ #筋トレ #ポールエクササイズ
#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 2025/1/6 「おめでとうございます」 と行き交う初顔合わせ 静かなやる気(長続きのコツ❤️) のメンバーに 新入会員2名が加わりました #コグニサイズ #体幹バランス 頭の中から足先まで 今日もしっかり動かしました〜 #転倒予防 #認知症予防 #姿勢改善 #チェアエクササイズ #ストレッチ #筋トレ #ポールエクササイズ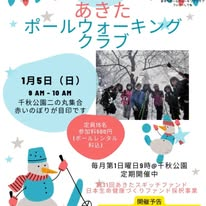 1/06 飛翔 羽を拡げて少し遠くに翔びませんか。今年は秋田の佐々木奈々子さんのPW活動をサポートします。 肩甲骨から羽を拡げます。力まずそして少しずつ羽ばたいて~!🪽❤🛫 去年後半からの雑務を整理して自粛生活を少しずつ解禁。皆さんのパワーをください。
1/06 飛翔 羽を拡げて少し遠くに翔びませんか。今年は秋田の佐々木奈々子さんのPW活動をサポートします。 肩甲骨から羽を拡げます。力まずそして少しずつ羽ばたいて~!🪽❤🛫 去年後半からの雑務を整理して自粛生活を少しずつ解禁。皆さんのパワーをください。 【チーム対抗じゃんけんゲーム】 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 2025/1/7 まだ松の内で長閑に 新年のご挨拶が交わされます #サーキットトレーニングはこの時期の定番メニューです きっちりと励みました(笑) 火曜日は年賀タオルお渡しも ゲームに取り込んで渡すので 盛り上がります⤴ チーム対抗じゃんけん大会 何と優勝は私達のチーム 勝って笑顔 負けても笑顔 毎回 大笑いです
【チーム対抗じゃんけんゲーム】 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 2025/1/7 まだ松の内で長閑に 新年のご挨拶が交わされます #サーキットトレーニングはこの時期の定番メニューです きっちりと励みました(笑) 火曜日は年賀タオルお渡しも ゲームに取り込んで渡すので 盛り上がります⤴ チーム対抗じゃんけん大会 何と優勝は私達のチーム 勝って笑顔 負けても笑顔 毎回 大笑いです #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コース お正月気分もすっかり 抜けての集合 90分あっという間終わりました
#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コース お正月気分もすっかり 抜けての集合 90分あっという間終わりました 1/11 午後からは 大田区ポールdeウォーク体験会(@御園神社)のあと、皆さんと健康安心講座に参加(@カムカム新蒲田)・・・ 喪中のため鳥居の脇からお邪魔し、境内でポール体操で身体を温め、脳トレで頭も準備運動をした後 意識して横断歩道の白帯は踏まず、歩幅を広げて講演会場までPWしました。 ・おしゃもじ社の謂れは? ・「後見人制度」は知っていましたが、「家族信託」は初めて知る制度でした。有意義な講演会に参加でき感謝です。
1/11 午後からは 大田区ポールdeウォーク体験会(@御園神社)のあと、皆さんと健康安心講座に参加(@カムカム新蒲田)・・・ 喪中のため鳥居の脇からお邪魔し、境内でポール体操で身体を温め、脳トレで頭も準備運動をした後 意識して横断歩道の白帯は踏まず、歩幅を広げて講演会場までPWしました。 ・おしゃもじ社の謂れは? ・「後見人制度」は知っていましたが、「家族信託」は初めて知る制度でした。有意義な講演会に参加でき感謝です。 高円寺・阿佐ヶ谷南部の寺社をポール歩き 新年初の「気ままにポール歩き=気まポ」 集合場所はJR高円寺駅南口の広場。 神社は氷川神社・気象神社(同じ空間にあり)、馬橋稲荷神社、神明宮、 寺は高円寺、長善寺、松応寺、西照寺 に寄りました。 松の内が明けるタイミングでもあり、寺はどこも閑散、神社は神明宮が正月らしい賑わいでした。 気象神社は氷川神社の域内にあるこぢんまりとした社ですが、ほかにはないユニークな神社なので訪れる人も多いようです。 たまたま毎月11日にご開帳という長善寺の「伎芸天」を拝むことができました。諸芸上達を願う人が訪れるとのことで、有名芸能人の写真などが飾ってありました。住職が親切に説明してくださいました。 実は、年が明けてから私は片足を少々痛めておりまして、いつもの後方に推すスポーツスタイルの歩き方(ノルディックウォーキング、4点駆動原理)を今回控えて、前方着地スタイル(ポールウォーキング、4点支持原理)で歩きました。全行程約5kmをスムーズに歩けて、ポールのありがたさを実感しました。 阿佐ヶ谷駅前の中華料理屋翠海(すいかい)で乾杯して新年会ランチを味わいました。
高円寺・阿佐ヶ谷南部の寺社をポール歩き 新年初の「気ままにポール歩き=気まポ」 集合場所はJR高円寺駅南口の広場。 神社は氷川神社・気象神社(同じ空間にあり)、馬橋稲荷神社、神明宮、 寺は高円寺、長善寺、松応寺、西照寺 に寄りました。 松の内が明けるタイミングでもあり、寺はどこも閑散、神社は神明宮が正月らしい賑わいでした。 気象神社は氷川神社の域内にあるこぢんまりとした社ですが、ほかにはないユニークな神社なので訪れる人も多いようです。 たまたま毎月11日にご開帳という長善寺の「伎芸天」を拝むことができました。諸芸上達を願う人が訪れるとのことで、有名芸能人の写真などが飾ってありました。住職が親切に説明してくださいました。 実は、年が明けてから私は片足を少々痛めておりまして、いつもの後方に推すスポーツスタイルの歩き方(ノルディックウォーキング、4点駆動原理)を今回控えて、前方着地スタイル(ポールウォーキング、4点支持原理)で歩きました。全行程約5kmをスムーズに歩けて、ポールのありがたさを実感しました。 阿佐ヶ谷駅前の中華料理屋翠海(すいかい)で乾杯して新年会ランチを味わいました。 写真1件
写真1件 1/14 今日は腰越グループ例会。新年第一回は 広町緑地から抜け出して鎌倉駅西口集合。源氏山健脚コース(扇が谷裏道階段利用)と海蔵寺ゆるゆるコースにわかれました。15/20名参加でした。
1/14 今日は腰越グループ例会。新年第一回は 広町緑地から抜け出して鎌倉駅西口集合。源氏山健脚コース(扇が谷裏道階段利用)と海蔵寺ゆるゆるコースにわかれました。15/20名参加でした。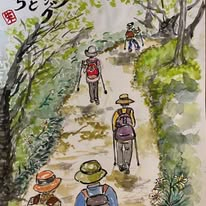 1/15 午前は今年初のDOJO 1人ずつ年末年始の一言を言いながらストレッチ。 午後は教養センター1期生(数年前の)PWグループの検定会でした。
1/15 午前は今年初のDOJO 1人ずつ年末年始の一言を言いながらストレッチ。 午後は教養センター1期生(数年前の)PWグループの検定会でした。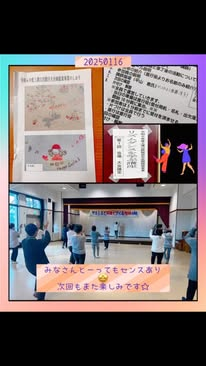 スマイルチーム上溝。 午前はスマイル活動。 午後は公民館自主企画案事業の講師アシスタントのお仕事。 #スマイルチーム #健康普及活動 #リズムダンス講座 #シニアダンス #リハビリダンス #脳トレダンス #昭和歌謡ダンス #懐メロダンス #上溝公民館 #上溝公民館まつり #相模原市中央区 #記録 #20250116
スマイルチーム上溝。 午前はスマイル活動。 午後は公民館自主企画案事業の講師アシスタントのお仕事。 #スマイルチーム #健康普及活動 #リズムダンス講座 #シニアダンス #リハビリダンス #脳トレダンス #昭和歌謡ダンス #懐メロダンス #上溝公民館 #上溝公民館まつり #相模原市中央区 #記録 #20250116 1/17 今日は3本立て 渋谷教室ではポールウォーキングはじめの一歩。肘引きしながらお互いに触れた肩甲骨の動きに皆さん声を上げて感動!「すごーい!動いてる~」 そして久々の我が古巣 駒沢公園ポール&ノルディックウォーキングクラスに顔を出しました。若い方々がしっかり引き継いで下さって感謝です。お任せしてもう2年以上になります。 その後税理士さんグループに参加。長い1日でした。
1/17 今日は3本立て 渋谷教室ではポールウォーキングはじめの一歩。肘引きしながらお互いに触れた肩甲骨の動きに皆さん声を上げて感動!「すごーい!動いてる~」 そして久々の我が古巣 駒沢公園ポール&ノルディックウォーキングクラスに顔を出しました。若い方々がしっかり引き継いで下さって感謝です。お任せしてもう2年以上になります。 その後税理士さんグループに参加。長い1日でした。 2025研修はポールウォークコーチ認定から無事キックオフしました。 JR輸送サービス組合の皆さんが東日本各地より参加くださり、寒空にも関わらずとても明るい双方向の学びの場となりました。次回は志木市NWPW全国大会で再会しましょう!お疲れ様でした。
2025研修はポールウォークコーチ認定から無事キックオフしました。 JR輸送サービス組合の皆さんが東日本各地より参加くださり、寒空にも関わらずとても明るい双方向の学びの場となりました。次回は志木市NWPW全国大会で再会しましょう!お疲れ様でした。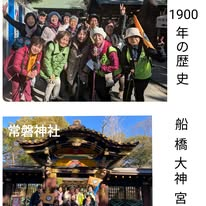 【又 来年も皆と来たいです】 混雑を避け遅めの初詣で 聞かれた声です 2025/1/18 いつもさり気なく繰り返えして いる初詣に 幸せを語ってくれるメンバーの 嬉しい一言です 1900年の歴史ある船橋大神宮 スタッフの名(迷?)ガイドは 大好評でした #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #船橋大神宮初詣
【又 来年も皆と来たいです】 混雑を避け遅めの初詣で 聞かれた声です 2025/1/18 いつもさり気なく繰り返えして いる初詣に 幸せを語ってくれるメンバーの 嬉しい一言です 1900年の歴史ある船橋大神宮 スタッフの名(迷?)ガイドは 大好評でした #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #船橋大神宮初詣 2025年、初ポールウォーキングでした。金町〜江戸川土手〜寅さん記念館〜山本邸〜帝釈天。のコースを歩きました。 インフルエンザ流行中の中、11名で元気に歩きました。 次は3月、ミステリーツアー。
2025年、初ポールウォーキングでした。金町〜江戸川土手〜寅さん記念館〜山本邸〜帝釈天。のコースを歩きました。 インフルエンザ流行中の中、11名で元気に歩きました。 次は3月、ミステリーツアー。 1/21 今年初の広町緑地PW。朝の日陰はひんやり、日向はぽかぽか上衣いらず。途中でロングコースとショートに分かれながら 元気に山道を歩き 再び広場で合流しCOOLDOWN。市の声掛けで6回の体験会を経て10年前に発足したこのサークルですが 最初から参加の最年長の女性はもう90歳!若々しくてとてもそのお年には見えません。始めるのに遅すぎる!ということはありません。継続こそ力なり。
1/21 今年初の広町緑地PW。朝の日陰はひんやり、日向はぽかぽか上衣いらず。途中でロングコースとショートに分かれながら 元気に山道を歩き 再び広場で合流しCOOLDOWN。市の声掛けで6回の体験会を経て10年前に発足したこのサークルですが 最初から参加の最年長の女性はもう90歳!若々しくてとてもそのお年には見えません。始めるのに遅すぎる!ということはありません。継続こそ力なり。 【スカンポって】 2025/1/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日定例会 グループで しりとりしながら 追い抜きウォーキング グループから 「知らない言葉が出たの」 聞くと すから始まる言葉で出たのが 「スカンポ」 メンバー半数以上が知らなかった💦 ゲーム後もググったり お口の体操に 勤しみました😅😀😉 それがいいんだな〜 #美姿勢ウォーキング #コグニサイズ
【スカンポって】 2025/1/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日定例会 グループで しりとりしながら 追い抜きウォーキング グループから 「知らない言葉が出たの」 聞くと すから始まる言葉で出たのが 「スカンポ」 メンバー半数以上が知らなかった💦 ゲーム後もググったり お口の体操に 勤しみました😅😀😉 それがいいんだな〜 #美姿勢ウォーキング #コグニサイズ 1/23 教会の駐車場をいつもお借りできて助かっています。曜日時間指定の許可証をフロントガラスの前に置きます。 不織布で覆った花壇にオレンジや白の花が咲き始めているのが見えました。ほっこり。 蝋梅、水仙、万両、山茶花、椿、早咲き梅、河津桜も蕾を脹らませ「春近し」。 PW貯筋クラブに片瀬山と七里ヶ浜から2名入会されたので改めて皆さんで自己紹介をしました(なんと!皆 初めての自己紹介)。少しずつ輪が広がります。 初参加の方が、結構キツイですね。との感想。マイペースで構いません。10%の顎の筋肉だけフル稼働の人もいますから。
1/23 教会の駐車場をいつもお借りできて助かっています。曜日時間指定の許可証をフロントガラスの前に置きます。 不織布で覆った花壇にオレンジや白の花が咲き始めているのが見えました。ほっこり。 蝋梅、水仙、万両、山茶花、椿、早咲き梅、河津桜も蕾を脹らませ「春近し」。 PW貯筋クラブに片瀬山と七里ヶ浜から2名入会されたので改めて皆さんで自己紹介をしました(なんと!皆 初めての自己紹介)。少しずつ輪が広がります。 初参加の方が、結構キツイですね。との感想。マイペースで構いません。10%の顎の筋肉だけフル稼働の人もいますから。 【面白かった〜】 2025/1/23 #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園木曜日コース #2本のポールを使うウォーキング ポールの力を借りて 美しく(?)身体を整える #ポールdeエクササイズ #ポールは魔法の杖 #歩くだけから進化して バレリーナみたいに 白鳥にもなれるかな〜 締めはポール脳トレ! 歩くを入れて #コグニサイズ 身体、頭 お口 良い運動になりました〜
【面白かった〜】 2025/1/23 #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園木曜日コース #2本のポールを使うウォーキング ポールの力を借りて 美しく(?)身体を整える #ポールdeエクササイズ #ポールは魔法の杖 #歩くだけから進化して バレリーナみたいに 白鳥にもなれるかな〜 締めはポール脳トレ! 歩くを入れて #コグニサイズ 身体、頭 お口 良い運動になりました〜 1/24 1泊明けの朝、30年来の犬友の散歩帰りにバッタリ!どちらも飼い犬の代が次々変わり当方はもう居ないのと鎌倉に移ったので中々会えないというのに。朝からWANに触れて幸せでした💕🍀 ウキウキ気分で渋谷へ🎶 今日は鏡ポールウォーキングにトライ。鏡の中の自分の歩容をチェックします。今日のクラスでも思ったよりキツイですね、と男性にいわれ次回から少し緩くしようと見直し。今日も暖かい1日でした。
1/24 1泊明けの朝、30年来の犬友の散歩帰りにバッタリ!どちらも飼い犬の代が次々変わり当方はもう居ないのと鎌倉に移ったので中々会えないというのに。朝からWANに触れて幸せでした💕🍀 ウキウキ気分で渋谷へ🎶 今日は鏡ポールウォーキングにトライ。鏡の中の自分の歩容をチェックします。今日のクラスでも思ったよりキツイですね、と男性にいわれ次回から少し緩くしようと見直し。今日も暖かい1日でした。 1/26日 お天気は良いのですが冷たい風に寒い寒いを連発🌁🌁。今日は逗子PWでラフターヨガやフラを参加20名で楽しみました。 最後は、笑顔で「やったーやったー!イェーイ!」 山茶花が今一番綺麗です🌺 (葉山の🥑ファームは欠席しました。今日は苗植えつけ用の大穴堀りの予定)
1/26日 お天気は良いのですが冷たい風に寒い寒いを連発🌁🌁。今日は逗子PWでラフターヨガやフラを参加20名で楽しみました。 最後は、笑顔で「やったーやったー!イェーイ!」 山茶花が今一番綺麗です🌺 (葉山の🥑ファームは欠席しました。今日は苗植えつけ用の大穴堀りの予定) www.city.yokohama.lg.jp
www.city.yokohama.lg.jp 東京フェスタ‼️ 強風の1日でした‼️ テントも5台破損‼️ スズカケの木の下で一息‼️ お疲れ様でした‼️
東京フェスタ‼️ 強風の1日でした‼️ テントも5台破損‼️ スズカケの木の下で一息‼️ お疲れ様でした‼️ 1/29 午前中は北鎌倉DOJOで詐欺被害回避の為の脳と運動神経の連動、危機回避のトレーニング。 頭ではわかっていても高齢者の詐欺被害が多い理由を納得www 午後は前々からお約束の十二所にあるブックマルシェ「みちくさ本棚」をやっと訪問出来ました。オーナー伊藤さんとお店担当の Fさんと閉店時間オーバーしてお喋り。古書・寄贈の本を無料・有料・回覧などで本のSDGs。本だけではなく手作りのものも扱っています。 当店の在庫グッズを仲間にいれて貰おうか、ポール歩きのステーションにも・・・と話しは尽きず。 https://www.facebook.com/share/p/19scxLddKe/
1/29 午前中は北鎌倉DOJOで詐欺被害回避の為の脳と運動神経の連動、危機回避のトレーニング。 頭ではわかっていても高齢者の詐欺被害が多い理由を納得www 午後は前々からお約束の十二所にあるブックマルシェ「みちくさ本棚」をやっと訪問出来ました。オーナー伊藤さんとお店担当の Fさんと閉店時間オーバーしてお喋り。古書・寄贈の本を無料・有料・回覧などで本のSDGs。本だけではなく手作りのものも扱っています。 当店の在庫グッズを仲間にいれて貰おうか、ポール歩きのステーションにも・・・と話しは尽きず。 https://www.facebook.com/share/p/19scxLddKe/ [6年度3期の(最後)講座です] 「認知症予防 計画力育成講座」でウォーキングを担当しています。 認知症予防としては色々ありますね…ウォーキングも効果あるんですよ。 そんな話と「健康を考えて」の歩きかたを話させていただいています。 1時間45分中の、先週、先々週は30分。今日は40分もらって3回が終了。 高齢者と言われる方々ですが、とっても意欲的でお元気🩷 後2回(担当のウォーキング)を「楽しかった🎵」と思ってもらいたい。 ╰(*´︶`*)╯♡ 主の講座、計画力は後5回…街歩きの計画を話し合います。
[6年度3期の(最後)講座です] 「認知症予防 計画力育成講座」でウォーキングを担当しています。 認知症予防としては色々ありますね…ウォーキングも効果あるんですよ。 そんな話と「健康を考えて」の歩きかたを話させていただいています。 1時間45分中の、先週、先々週は30分。今日は40分もらって3回が終了。 高齢者と言われる方々ですが、とっても意欲的でお元気🩷 後2回(担当のウォーキング)を「楽しかった🎵」と思ってもらいたい。 ╰(*´︶`*)╯♡ 主の講座、計画力は後5回…街歩きの計画を話し合います。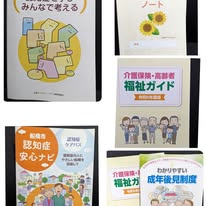 【深まったご縁】 #船橋ウォーキングソサイエティ 第2回スペシャル企画 「#認知症サポーター養成講座」 「#ウォーキング講座」に呼ばれた のがきっかけで実現しました。 知りたい事が分かって 短時間でも濃い内容で 資料も充実したのを頂きました。 会員からの質疑も活発で 有意義な時間を共有できました。 #自助共助公助 #知って安心認知症 #ウォーキング中に遭遇したらどうする #認知症安心ナビ #認知症を学び皆で考える #地域包括支援センター
【深まったご縁】 #船橋ウォーキングソサイエティ 第2回スペシャル企画 「#認知症サポーター養成講座」 「#ウォーキング講座」に呼ばれた のがきっかけで実現しました。 知りたい事が分かって 短時間でも濃い内容で 資料も充実したのを頂きました。 会員からの質疑も活発で 有意義な時間を共有できました。 #自助共助公助 #知って安心認知症 #ウォーキング中に遭遇したらどうする #認知症安心ナビ #認知症を学び皆で考える #地域包括支援センター 2025.1.30 スペシャル企画『認知サポーター養成講座』 於:塚田公民館 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ
2025.1.30 スペシャル企画『認知サポーター養成講座』 於:塚田公民館 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ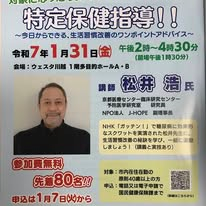 今日は、ウェスタでウェストの話しです。
今日は、ウェスタでウェストの話しです。 写真1件
写真1件 2025/2/22 第一屆第三次會員大會 (報名表單)
2025/2/22 第一屆第三次會員大會 (報名表單)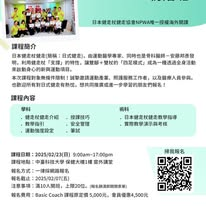 【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/2/23(日) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台中 中臺科技大學保健大樓1樓 窗外講堂 ⚠️滿10人開班,上限20位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️https://forms.gle/bDXy76JZVteDeK7L6 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~
【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/2/23(日) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台中 中臺科技大學保健大樓1樓 窗外講堂 ⚠️滿10人開班,上限20位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️https://forms.gle/bDXy76JZVteDeK7L6 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~ GWは「美の国あきた」へ! 5/4 「ポールを持って歩く会~秋田大会」が開催されます。 清々しい美の国の青空の下、ポールを持って一緒に歩きませんか(秋田県総合保健センター発)。 主宰のあきたPWクラブの佐々木コーチや秋田大の小玉コーチにもリアルでお会いして、地域活動や研究状況をお伺いでき、皆さまと交流できますこと、今からとっても楽しみです。
GWは「美の国あきた」へ! 5/4 「ポールを持って歩く会~秋田大会」が開催されます。 清々しい美の国の青空の下、ポールを持って一緒に歩きませんか(秋田県総合保健センター発)。 主宰のあきたPWクラブの佐々木コーチや秋田大の小玉コーチにもリアルでお会いして、地域活動や研究状況をお伺いでき、皆さまと交流できますこと、今からとっても楽しみです。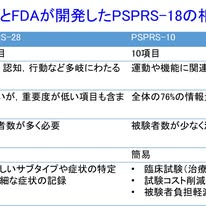 進行性核上性麻痺(PSP)は,運動障害,認知機能障害,行動変化など多彩な症候を呈する神経変性疾患です.このため臨床評価尺度も多彩な項目を要します.現在,使用されているProgressive Supranuclear Palsy Rating Scale(PSPRS)は28項目から構成されます.なんと米国食品医薬品局FDAがPSPRSを改訂し,10項目から構成されるPSPRS-10という評価尺度を作成したようです.その有用性を検証した論文がスウェーデンからMov Disord誌に報告されています(文献1).
進行性核上性麻痺(PSP)は,運動障害,認知機能障害,行動変化など多彩な症候を呈する神経変性疾患です.このため臨床評価尺度も多彩な項目を要します.現在,使用されているProgressive Supranuclear Palsy Rating Scale(PSPRS)は28項目から構成されます.なんと米国食品医薬品局FDAがPSPRSを改訂し,10項目から構成されるPSPRS-10という評価尺度を作成したようです.その有用性を検証した論文がスウェーデンからMov Disord誌に報告されています(文献1).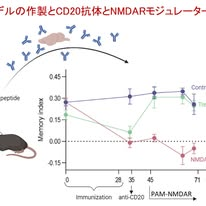 明けましておめでとうございます.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.自分にできること,行うべきことを地道に頑張っていきたいと思います.
明けましておめでとうございます.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.自分にできること,行うべきことを地道に頑張っていきたいと思います. 図はNeurology誌のClinical reasoning(臨床推論)のものです.症例はインドの16歳女子で,早期発症運動失調(early-onset ataxia, EOA)です.10歳頃から不安定歩行となり,14歳で感音性難聴が出現,また無月経で,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症と診断されました.画像検査で小脳萎縮を認め,また末梢神経障害を合併し,生検では髄鞘形成障害性神経障害が示唆されました.小脳性運動失調,感音性難聴,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症からPerrault(ペロー)症候群が疑われ,次世代シークエンサーによるエクソーム解析にて,HSD17B4遺伝子のホモ接合性変異が確認されました.
図はNeurology誌のClinical reasoning(臨床推論)のものです.症例はインドの16歳女子で,早期発症運動失調(early-onset ataxia, EOA)です.10歳頃から不安定歩行となり,14歳で感音性難聴が出現,また無月経で,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症と診断されました.画像検査で小脳萎縮を認め,また末梢神経障害を合併し,生検では髄鞘形成障害性神経障害が示唆されました.小脳性運動失調,感音性難聴,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症からPerrault(ペロー)症候群が疑われ,次世代シークエンサーによるエクソーム解析にて,HSD17B4遺伝子のホモ接合性変異が確認されました.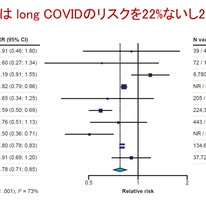 さて今回のキーワードは,ブースター接種は初回接種のみと比較してlong COVIDを23%低下させる,小児や思春期でもワクチン接種がlong COVIDのリスクを軽減する,感染時の腸内細菌叢の組成からlong COVIDを予測できる,COVID-19は神経細胞の機能障害と神経炎症をもたらすことで神経変性疾患の発症や進行を促進する可能性がある,Long COVIDに対し認知行動療法や身体・精神リハビリテーションが有効である,です.
さて今回のキーワードは,ブースター接種は初回接種のみと比較してlong COVIDを23%低下させる,小児や思春期でもワクチン接種がlong COVIDのリスクを軽減する,感染時の腸内細菌叢の組成からlong COVIDを予測できる,COVID-19は神経細胞の機能障害と神経炎症をもたらすことで神経変性疾患の発症や進行を促進する可能性がある,Long COVIDに対し認知行動療法や身体・精神リハビリテーションが有効である,です.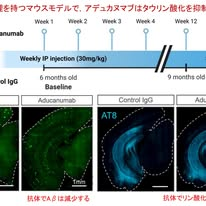 アルツハイマー病(AD)に対し,近年,アミロイドβ(Aβ)を標的とした抗体療法が臨床応用されました.しかし抗体療法がタウ病理や神経変性に及ぼす影響については十分明らかにされていません.これは過去の動物モデルを用いた研究の多くは,Aβ病理に特化した動物モデル(APP/PS1や5xFADなど)を使用し,タウ病理を持たないモデルが中心であったためです.
アルツハイマー病(AD)に対し,近年,アミロイドβ(Aβ)を標的とした抗体療法が臨床応用されました.しかし抗体療法がタウ病理や神経変性に及ぼす影響については十分明らかにされていません.これは過去の動物モデルを用いた研究の多くは,Aβ病理に特化した動物モデル(APP/PS1や5xFADなど)を使用し,タウ病理を持たないモデルが中心であったためです. 朝のカンファレンスで,味覚性発汗(gustatory sweating)とFrey症候群について議論しました.まず味覚性発汗とは味覚刺激により顔面に発汗が生じる現象で,一部の健常者には生理的味覚性発汗が認められますが,耳介側頭症候群(Frey 症候群)や交感神経切除後に生じる味覚性発汗など病的なものもあります.
朝のカンファレンスで,味覚性発汗(gustatory sweating)とFrey症候群について議論しました.まず味覚性発汗とは味覚刺激により顔面に発汗が生じる現象で,一部の健常者には生理的味覚性発汗が認められますが,耳介側頭症候群(Frey 症候群)や交感神経切除後に生じる味覚性発汗など病的なものもあります.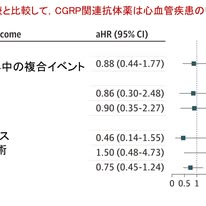 片頭痛治療において非常に重要な論文が報告されました.片頭痛は女性に多い疾患で,世界中で15%もの人が罹患していると言われています.近年,片頭痛特異的な予防薬として,CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)またはその受容体を標的とするモノクローナル抗体が臨床応用され,非常に大きなインパクトを与えています.一方で,CGRPは心血管系における保護的な役割があるとされており,CGRPを阻害するこれらの薬剤が心血管疾患のリスクを増加させる可能性について懸念がありました.
片頭痛治療において非常に重要な論文が報告されました.片頭痛は女性に多い疾患で,世界中で15%もの人が罹患していると言われています.近年,片頭痛特異的な予防薬として,CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)またはその受容体を標的とするモノクローナル抗体が臨床応用され,非常に大きなインパクトを与えています.一方で,CGRPは心血管系における保護的な役割があるとされており,CGRPを阻害するこれらの薬剤が心血管疾患のリスクを増加させる可能性について懸念がありました.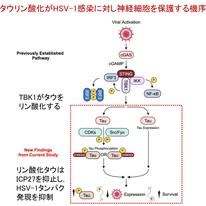 アルツハイマー病(AD)の病態にアミロイドβやリン酸化タウ(p-tau)が関与します.しかしこれらを脳に蓄積させる要因はよく分かっていません.しかし近年,ADとウイルス感染の関連が注目されており,そのなかにはヘルペスウイルス1型(HSV-1),帯状疱疹ウイルス,新型コロナウイルスなどが含まれます.今回,Cell Reports誌に掲載されたイスラエルと米国からの研究では,HSV-1とタウリン酸化の驚くような関係が示されています.
アルツハイマー病(AD)の病態にアミロイドβやリン酸化タウ(p-tau)が関与します.しかしこれらを脳に蓄積させる要因はよく分かっていません.しかし近年,ADとウイルス感染の関連が注目されており,そのなかにはヘルペスウイルス1型(HSV-1),帯状疱疹ウイルス,新型コロナウイルスなどが含まれます.今回,Cell Reports誌に掲載されたイスラエルと米国からの研究では,HSV-1とタウリン酸化の驚くような関係が示されています.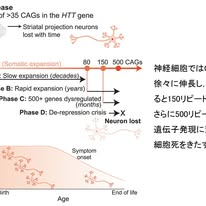 ハンチントン病(HD)は,常染色体顕性遺伝を呈する神経変性疾患で,原因は huntingtin(HTT)遺伝子内のCAGリピートの異常伸長です.HD患者は36回以上(ほとんどの場合40~49回)になります.未解明な点が多く,代表的なものとしては以下が挙げられます.
ハンチントン病(HD)は,常染色体顕性遺伝を呈する神経変性疾患で,原因は huntingtin(HTT)遺伝子内のCAGリピートの異常伸長です.HD患者は36回以上(ほとんどの場合40~49回)になります.未解明な点が多く,代表的なものとしては以下が挙げられます.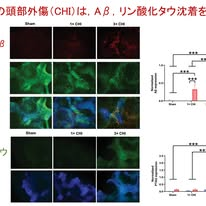 頭部外傷はアルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが知られています.また慢性外傷性脳症(CTE)というボクサーやアメフト選手などにみられる認知症も知られています.一方,単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)は,およそ8割の人が60歳までに感染しますが,高齢者の脳に潜伏し,APOE遺伝子e4アリル保因者においてADのリスクを高めることも知られていました.米国タフツ大学と英国オックスフォード大学のチームは「頭部外傷がHSV-1を再活性化し,ADに関連する表現型を引き起こす」という仮説を立てて検証実験を行い,その結果をScience Signaling誌に報告しました.
頭部外傷はアルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが知られています.また慢性外傷性脳症(CTE)というボクサーやアメフト選手などにみられる認知症も知られています.一方,単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)は,およそ8割の人が60歳までに感染しますが,高齢者の脳に潜伏し,APOE遺伝子e4アリル保因者においてADのリスクを高めることも知られていました.米国タフツ大学と英国オックスフォード大学のチームは「頭部外傷がHSV-1を再活性化し,ADに関連する表現型を引き起こす」という仮説を立てて検証実験を行い,その結果をScience Signaling誌に報告しました.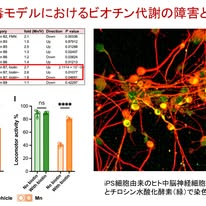 マンガン(Mn)中毒に伴う神経毒性が,パーキニズムを引き起こすメカニズムを解明し,それに対するビオチン(ビタミンB7)の保護的効果を明らかにした米国コロンビア大学などのチームによる研究が,Science Signaling誌に報告されています.ビオチンは細胞のエネルギー代謝に不可欠な補酵素として働き,特にミトコンドリアの呼吸やドパミン生成に関与しています.
マンガン(Mn)中毒に伴う神経毒性が,パーキニズムを引き起こすメカニズムを解明し,それに対するビオチン(ビタミンB7)の保護的効果を明らかにした米国コロンビア大学などのチームによる研究が,Science Signaling誌に報告されています.ビオチンは細胞のエネルギー代謝に不可欠な補酵素として働き,特にミトコンドリアの呼吸やドパミン生成に関与しています.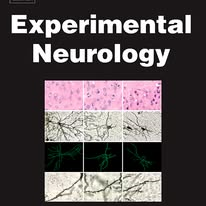 このたび,海外医学ジャーナル Experimental Neurology 誌の特集号でGuest Editorを務めさせていただきました!特集号にはアクセプトした6本の論文が掲載されておりますので,ぜひご覧いただければ幸いです.
このたび,海外医学ジャーナル Experimental Neurology 誌の特集号でGuest Editorを務めさせていただきました!特集号にはアクセプトした6本の論文が掲載されておりますので,ぜひご覧いただければ幸いです. 12/1 池上本門寺① 本蒲田1丁目から池上本門寺まで大田区の楽校の皆さんと数年振りにPWを楽しみました。昔の教え子さんたちは校長先生になられたりご立派に成長されたのに私はただ歳を重ねただけ。 本門寺で富士山を仰いで解散後ナマ友・FBFの事務局長さんに境内を案内して頂きました。鎌倉とも縁の深い日蓮宗のお寺は江戸時代の立派な珍しい墓地がたくさんあります。歴史上の方々始め有名人のお墓を巡らせて頂き、境内が広すぎて足が棒。
12/1 池上本門寺① 本蒲田1丁目から池上本門寺まで大田区の楽校の皆さんと数年振りにPWを楽しみました。昔の教え子さんたちは校長先生になられたりご立派に成長されたのに私はただ歳を重ねただけ。 本門寺で富士山を仰いで解散後ナマ友・FBFの事務局長さんに境内を案内して頂きました。鎌倉とも縁の深い日蓮宗のお寺は江戸時代の立派な珍しい墓地がたくさんあります。歴史上の方々始め有名人のお墓を巡らせて頂き、境内が広すぎて足が棒。 蒲田PW行進曲 今日は蒲田でPWイベント。 長く続けていたお陰で 懐かしい方々に再会できました。池上本門寺ご案内下さったYさんありがとうございました。北鎌倉を歩きませんか。
蒲田PW行進曲 今日は蒲田でPWイベント。 長く続けていたお陰で 懐かしい方々に再会できました。池上本門寺ご案内下さったYさんありがとうございました。北鎌倉を歩きませんか。 12/2 鎌倉ミステリーNo.10-① 鎌倉🍁のメッカ獅子舞から鎌倉アルプスの大平山~覚園寺を歩きました。イチョウの💛絨毯を踏みしめながら、始まったばかりの紅葉の🍁燃える色を見上げながらニコニコ元気に完歩。8日の②は後半のコースを変えます。 ご参加ありがとうございましたm(_ _)m
12/2 鎌倉ミステリーNo.10-① 鎌倉🍁のメッカ獅子舞から鎌倉アルプスの大平山~覚園寺を歩きました。イチョウの💛絨毯を踏みしめながら、始まったばかりの紅葉の🍁燃える色を見上げながらニコニコ元気に完歩。8日の②は後半のコースを変えます。 ご参加ありがとうございましたm(_ _)m 2024.11.29〜12.2 活動記録 ☺︎スマイルエクササイズ 13名 和室で出来るコンディショニングも とりいれました ☺︎上鶴間PW教室 14名 3回コース無事修理 半数の方がポール購入 自主サークル化決定 ☺︎上溝公民館自主企画事業打合せ 5回コースでのリズムエクササイズ 体験と発表 女性学級で1講座やらせて頂き好評 につき、自主企画事業として行う事 になりました ☺︎スマイル光が丘 20名 ラストに言葉遊びチェア体操で沢山 笑いました ☺︎公民館利用団体施設予約 5団体分
2024.11.29〜12.2 活動記録 ☺︎スマイルエクササイズ 13名 和室で出来るコンディショニングも とりいれました ☺︎上鶴間PW教室 14名 3回コース無事修理 半数の方がポール購入 自主サークル化決定 ☺︎上溝公民館自主企画事業打合せ 5回コースでのリズムエクササイズ 体験と発表 女性学級で1講座やらせて頂き好評 につき、自主企画事業として行う事 になりました ☺︎スマイル光が丘 20名 ラストに言葉遊びチェア体操で沢山 笑いました ☺︎公民館利用団体施設予約 5団体分 【楽しい街歩き】 船橋にこんな所があったの! そんな驚きの声が聞かれます #火曜日美姿勢コース #路地に佇む社寺を訪ねる街歩き 天気良し 案内の解説良し 聞くマナー良し 歩くマナー良し 皆がHAPPYで 良かったな〜💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #船橋寺町巡り #日本一小さい東照宮 #因果地蔵尊 #飯盛り大仏 #お女郎地蔵 #桜桃忌 #太宰治
【楽しい街歩き】 船橋にこんな所があったの! そんな驚きの声が聞かれます #火曜日美姿勢コース #路地に佇む社寺を訪ねる街歩き 天気良し 案内の解説良し 聞くマナー良し 歩くマナー良し 皆がHAPPYで 良かったな〜💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #船橋寺町巡り #日本一小さい東照宮 #因果地蔵尊 #飯盛り大仏 #お女郎地蔵 #桜桃忌 #太宰治 12/3 広町緑地公園で黄葉ポールウォーキング 昨日の天園の写真と紛らわしい こちらは泥濘がありませんが坂道階段は頻繁にあります。12/22は公園主催の紅葉散策(自由参加)イベントがあります。全体が色づくのはまだまだ先なんですね。 富士山も目の前に!
12/3 広町緑地公園で黄葉ポールウォーキング 昨日の天園の写真と紛らわしい こちらは泥濘がありませんが坂道階段は頻繁にあります。12/22は公園主催の紅葉散策(自由参加)イベントがあります。全体が色づくのはまだまだ先なんですね。 富士山も目の前に! 12/4 北鎌倉 爽やかで暖かな小春日和 テラススタジオでNewプログラム 鎌倉まで色づく秋を楽しみながらのんびり歩いて帰りました 円覚寺~東慶寺~途中 鉢の木でランチ~~~
12/4 北鎌倉 爽やかで暖かな小春日和 テラススタジオでNewプログラム 鎌倉まで色づく秋を楽しみながらのんびり歩いて帰りました 円覚寺~東慶寺~途中 鉢の木でランチ~~~ 2024【日式健走 Advance Coach 進階教練培訓課】 課程圓滿結束!🎉 為期2天的進階教練培訓課程在滿滿的收穫中劃下句點!👏💪 在專業講師的悉心指導下, 學員們不僅深入學習了健走杖運動的進階技巧, 更強化了教學能力與團隊帶領能力, 為推廣健康運動邁出了關鍵一步!🌟🚶♂️🚶♀️ 這是一場充滿挑戰與成長的旅程, 學員們在理論與實作中不斷突破自我, 展現了對健走運動的熱忱與專注🔥。 每一步都走得穩健,每一次學習都收穫滿滿!📚✨ 感謝所有參與的學員與教練們, 因為你們的投入與努力, 讓這次課程充滿活力與意義💖! 接下來, 讓我們一起期待未來更多的健走推廣計畫, #共同邁向更健康更精彩的生活!🌏💪 #日式健走AdvanceCoach進階教練培訓課
2024【日式健走 Advance Coach 進階教練培訓課】 課程圓滿結束!🎉 為期2天的進階教練培訓課程在滿滿的收穫中劃下句點!👏💪 在專業講師的悉心指導下, 學員們不僅深入學習了健走杖運動的進階技巧, 更強化了教學能力與團隊帶領能力, 為推廣健康運動邁出了關鍵一步!🌟🚶♂️🚶♀️ 這是一場充滿挑戰與成長的旅程, 學員們在理論與實作中不斷突破自我, 展現了對健走運動的熱忱與專注🔥。 每一步都走得穩健,每一次學習都收穫滿滿!📚✨ 感謝所有參與的學員與教練們, 因為你們的投入與努力, 讓這次課程充滿活力與意義💖! 接下來, 讓我們一起期待未來更多的健走推廣計畫, #共同邁向更健康更精彩的生活!🌏💪 #日式健走AdvanceCoach進階教練培訓課 #スマイルチーム#四季彩の杜#薬師池 #ポールウォーキング#紅葉#お弁当 #プラントベースのお弁当 ポールウォーキング12月は大人の遠足ポカポカ陽氣で氣もち良く楽しい遠足でした〜😘
#スマイルチーム#四季彩の杜#薬師池 #ポールウォーキング#紅葉#お弁当 #プラントベースのお弁当 ポールウォーキング12月は大人の遠足ポカポカ陽氣で氣もち良く楽しい遠足でした〜😘 12/6 渋谷PW教室3学期最終日 計測・ポールゲーム・お一人ずつモデルウォークでシメマシタ。全員の歩幅が、広がったのは素晴らしいです。 渋谷の街は少し寂しげ、クリスマス🎄🎅🎁✨の華やかさはショップのウィンドウのみ。夜になるとイルミネーションが綺麗なんでしょうね。あの幻想的な青の洞窟🟦とか。
12/6 渋谷PW教室3学期最終日 計測・ポールゲーム・お一人ずつモデルウォークでシメマシタ。全員の歩幅が、広がったのは素晴らしいです。 渋谷の街は少し寂しげ、クリスマス🎄🎅🎁✨の華やかさはショップのウィンドウのみ。夜になるとイルミネーションが綺麗なんでしょうね。あの幻想的な青の洞窟🟦とか。 2024.12.7 活動記録 活き活き中屋敷ライフ ポールウォーキング 10名 中屋敷中央公園集合 準備体操をして、境川沿いにウォーキング🐾本郷公園まで周りの景色を楽しみながら、今日の先導は89歳のゴローさん、しっかりしたウォーキングで交差点や横断歩道での確認、誘導までを行って下さいました。 公園ではみんなでおしゃべりタイム、自治会長から色々な情報もいただきました。帰路は親生会会長が先導、ゴローさんはしんがりで皆様を見守りながらのウォーキング。 帰路では珍しい青パパイヤの木にパパイヤもなっているし可愛らしいお花も咲いているのを見る事ができました。 中央公園にもどり整理体操と次回の連絡等、締めはゴローさんの『みなさん良いお年をね』で解散。 お天氣良く、氣温もウォーキングにちょうど良く、大変氣もちの良いウォーキングが出来ました😄 #ポールウォーキング #スマイルチーム #活き活き中屋敷ライフ
2024.12.7 活動記録 活き活き中屋敷ライフ ポールウォーキング 10名 中屋敷中央公園集合 準備体操をして、境川沿いにウォーキング🐾本郷公園まで周りの景色を楽しみながら、今日の先導は89歳のゴローさん、しっかりしたウォーキングで交差点や横断歩道での確認、誘導までを行って下さいました。 公園ではみんなでおしゃべりタイム、自治会長から色々な情報もいただきました。帰路は親生会会長が先導、ゴローさんはしんがりで皆様を見守りながらのウォーキング。 帰路では珍しい青パパイヤの木にパパイヤもなっているし可愛らしいお花も咲いているのを見る事ができました。 中央公園にもどり整理体操と次回の連絡等、締めはゴローさんの『みなさん良いお年をね』で解散。 お天氣良く、氣温もウォーキングにちょうど良く、大変氣もちの良いウォーキングが出来ました😄 #ポールウォーキング #スマイルチーム #活き活き中屋敷ライフ 【急がば回れ】 基本振り返りからの インターバルへ 2024/12 /7 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜日海老川ロード #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #インターバルウォーキング #トレーニング3原理5原則
【急がば回れ】 基本振り返りからの インターバルへ 2024/12 /7 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜日海老川ロード #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #インターバルウォーキング #トレーニング3原理5原則 感動~
感動~ 12月7日にスキルアップ研修会福岡会場を開催しました。 福岡の藤崎MCプロをメイン講師に、アットホームな感じのセミナーでした。 長崎の平山MCプロも参加して下さり、充実した内容になりました。 参加者同士の情報交換もでき、有意義なセミナーとなりました。
12月7日にスキルアップ研修会福岡会場を開催しました。 福岡の藤崎MCプロをメイン講師に、アットホームな感じのセミナーでした。 長崎の平山MCプロも参加して下さり、充実した内容になりました。 参加者同士の情報交換もでき、有意義なセミナーとなりました。 鎌倉ミステリーウォーキングvol.10 今回はアクティブ獅子舞谷コース。 12月2日(18名)と8日(25名) 2回の開催で鎌倉の紅葉🍁を楽しみながらたくさんの方に参加していただきました。 泥濘や丸太の橋を恐々と渡ったり… 銀杏の葉で黄色に染まった道を登りながら見上げると紅葉のグラデーション🍁とても綺麗でした。 そして楽しかったです。 ありがとうございました😊
鎌倉ミステリーウォーキングvol.10 今回はアクティブ獅子舞谷コース。 12月2日(18名)と8日(25名) 2回の開催で鎌倉の紅葉🍁を楽しみながらたくさんの方に参加していただきました。 泥濘や丸太の橋を恐々と渡ったり… 銀杏の葉で黄色に染まった道を登りながら見上げると紅葉のグラデーション🍁とても綺麗でした。 そして楽しかったです。 ありがとうございました😊 12/12 お昼前、一瞬でしたが小町通を歩いていたら 霙(みぞれ)のような粒が降りました。寒い筈ですね。 高齢者センターもクリスマスの飾りつけがされています。そしてどのPWサークルも忘年会の話で盛り上がっていますが、コロナや帯状疱疹にも気を付けなければ。
12/12 お昼前、一瞬でしたが小町通を歩いていたら 霙(みぞれ)のような粒が降りました。寒い筈ですね。 高齢者センターもクリスマスの飾りつけがされています。そしてどのPWサークルも忘年会の話で盛り上がっていますが、コロナや帯状疱疹にも気を付けなければ。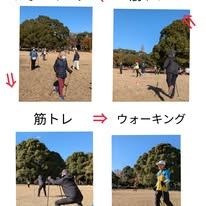 【寒さは何処に〜】 2024/12/12 ウォーキングとウォーキング の間に 色んな筋トレが次から次へと 入ります これが楽しい〜♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 #サーキットトレーニング #脂肪燃焼 #持久力UP #筋力UP
【寒さは何処に〜】 2024/12/12 ウォーキングとウォーキング の間に 色んな筋トレが次から次へと 入ります これが楽しい〜♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 #サーキットトレーニング #脂肪燃焼 #持久力UP #筋力UP 2024.12.13 活動記録 青空ポールウォーキング 9名 昨年包括支援センターでの事業で教室を行い、その後自主化し今年の1月から活動開始しました 私がコーチで一緒に行う日と、集まった仲間で自主練をする日の月2回の活動です 今日は私とアシスタントのMちゃんを除くと平均年齢80歳超えのハイシニアチームでした😆 楽しいが1番 集まって体操しておしゃべりして歩いて、お天気は少しどんよりでしたが 良く笑って皆さん明るい笑顔で帰っていかれました 楽しいと続けたくなるよね〜♡ #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #スマイルチーム #みかん狩り #地域包括支援センター
2024.12.13 活動記録 青空ポールウォーキング 9名 昨年包括支援センターでの事業で教室を行い、その後自主化し今年の1月から活動開始しました 私がコーチで一緒に行う日と、集まった仲間で自主練をする日の月2回の活動です 今日は私とアシスタントのMちゃんを除くと平均年齢80歳超えのハイシニアチームでした😆 楽しいが1番 集まって体操しておしゃべりして歩いて、お天気は少しどんよりでしたが 良く笑って皆さん明るい笑顔で帰っていかれました 楽しいと続けたくなるよね〜♡ #ポールエクササイズ #ポールウォーキング #スマイルチーム #みかん狩り #地域包括支援センター 紅葉・黄葉ラストチャンス 12月の「気ままにポール歩き」は、地元コースでした。 善福寺川緑地・和田堀公園、大宮八幡宮、おおぞら公園、神田川遊歩道、塚山公園、柏の宮(かしのみや)公園 予報では昼頃でも気温12度で、おまけに風が強いということでしたが、快晴のひざしに当たりながら快適なウォーキングでした。 ウォーキングのあとは、おなじみ浜田山駅前のネパール料理店「まいた」でランチ忘年会を楽しみました。
紅葉・黄葉ラストチャンス 12月の「気ままにポール歩き」は、地元コースでした。 善福寺川緑地・和田堀公園、大宮八幡宮、おおぞら公園、神田川遊歩道、塚山公園、柏の宮(かしのみや)公園 予報では昼頃でも気温12度で、おまけに風が強いということでしたが、快晴のひざしに当たりながら快適なウォーキングでした。 ウォーキングのあとは、おなじみ浜田山駅前のネパール料理店「まいた」でランチ忘年会を楽しみました。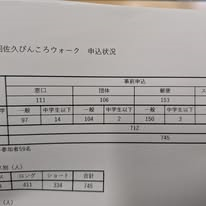 先週「ぴんころウォーク」の実行委員会が開かれ、9月実施の最終的な報告があった。参加人数745名(市内309名、市外201名、県外から235名)。多くの方に参加いただきました。ありがとうございました。「健康」×「観光」が融合したよい大会になってきたと思います。特にプルーン食べ放題が大きなフックになっています。 しかし大幅に人数が増えたことで課題も浮き彫りに。アンケートでは駐車場の問題、農道など細い道や草の問題、開会式のマイクが後ろまで聞こえていなかったなど。概ね好評でまた来たいという内容が大多数だが、実行委員長としてこれらの問題をできるだけ解決し、次回さらによい大会にしたいと思います。あとは収支の問題も大きい。これまでは元気づくり支援金を活用し収支がトントンの事業だったが、次回以降は支援金なしでしっかり黒字にしないといけない。とはいえ700名以上集まる「ぴんころウォーク」なので、まずはそこに魅力を感じてくれる地元企業から協賛を募っていきたい。これを見た経営者の皆さん宜しくお願い致します。応援してください(^.^)
先週「ぴんころウォーク」の実行委員会が開かれ、9月実施の最終的な報告があった。参加人数745名(市内309名、市外201名、県外から235名)。多くの方に参加いただきました。ありがとうございました。「健康」×「観光」が融合したよい大会になってきたと思います。特にプルーン食べ放題が大きなフックになっています。 しかし大幅に人数が増えたことで課題も浮き彫りに。アンケートでは駐車場の問題、農道など細い道や草の問題、開会式のマイクが後ろまで聞こえていなかったなど。概ね好評でまた来たいという内容が大多数だが、実行委員長としてこれらの問題をできるだけ解決し、次回さらによい大会にしたいと思います。あとは収支の問題も大きい。これまでは元気づくり支援金を活用し収支がトントンの事業だったが、次回以降は支援金なしでしっかり黒字にしないといけない。とはいえ700名以上集まる「ぴんころウォーク」なので、まずはそこに魅力を感じてくれる地元企業から協賛を募っていきたい。これを見た経営者の皆さん宜しくお願い致します。応援してください(^.^) #シニアポールウォーキング 2024/12/16 社会性は満点のメンバーです #転倒 #認知症予防 その二つに絞って 講堂内をフル活用 最期に一言スピーチ テーマは 「今年の自分を褒めてあげましょう」 皆さん、ニコニコしながら話します メンバーは今年も 充実した生活だったようです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #法典公民館
#シニアポールウォーキング 2024/12/16 社会性は満点のメンバーです #転倒 #認知症予防 その二つに絞って 講堂内をフル活用 最期に一言スピーチ テーマは 「今年の自分を褒めてあげましょう」 皆さん、ニコニコしながら話します メンバーは今年も 充実した生活だったようです #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #法典公民館 12/16 本日は渋谷。 友達とブツの受け渡し+お茶 そして、渋谷区役所で年に1度の渋谷介護事業の横繋がりの MTGがありました。社協、包括支援、健康はつらつ事業、元気すこやか事業その他充実したフレイル予防等プログラムの各担当など合同のミィーティングで大変有意義な意見交換会でした。大田区もポール事業では1歩大きく進展していますが、文系・運動系両方をここまで進めているのは都内で唯一の充実活動だと思います。渋谷区民は幸せです☘️ これからzoomです。(スマホばかり使ってPCを放置していたので動かなくなってしまいました😢 仕方なくスマホで参加)
12/16 本日は渋谷。 友達とブツの受け渡し+お茶 そして、渋谷区役所で年に1度の渋谷介護事業の横繋がりの MTGがありました。社協、包括支援、健康はつらつ事業、元気すこやか事業その他充実したフレイル予防等プログラムの各担当など合同のミィーティングで大変有意義な意見交換会でした。大田区もポール事業では1歩大きく進展していますが、文系・運動系両方をここまで進めているのは都内で唯一の充実活動だと思います。渋谷区民は幸せです☘️ これからzoomです。(スマホばかり使ってPCを放置していたので動かなくなってしまいました😢 仕方なくスマホで参加) 2024年、年忘れウォーキング。
2024年、年忘れウォーキング。 12/17 青い空 風もなく暖かい冬の朝 広町緑地で輪になってストレッチ・筋トレを済ませ、今日は忘年会✨🍹🎶 at homeな腰越サークルはもう何年目になりますか。継続のコツは「楽しい」こと。お花見🌸会や忘年会も交流を深めます。20名のメンバーのうちスマホを使わないお一人(電話連絡)以外はLINEで繋がりました。
12/17 青い空 風もなく暖かい冬の朝 広町緑地で輪になってストレッチ・筋トレを済ませ、今日は忘年会✨🍹🎶 at homeな腰越サークルはもう何年目になりますか。継続のコツは「楽しい」こと。お花見🌸会や忘年会も交流を深めます。20名のメンバーのうちスマホを使わないお一人(電話連絡)以外はLINEで繋がりました。 昨日の様子です #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング 2024/12/17 #行田公園イベント広場で #サーキットトレーニング 程よい高さの石垣で #腕立て伏せ #ボート漕ぎで腹筋 バラエティに富んだ筋トレが 出来ます 全天候型舗装になったので ウォーキングも思い切り 歩けるようになりました〜 目線は前に 中々良い調子です がっちりトレーニング 程々トレーニング 皆、自分の良い加減でね ♫
昨日の様子です #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング 2024/12/17 #行田公園イベント広場で #サーキットトレーニング 程よい高さの石垣で #腕立て伏せ #ボート漕ぎで腹筋 バラエティに富んだ筋トレが 出来ます 全天候型舗装になったので ウォーキングも思い切り 歩けるようになりました〜 目線は前に 中々良い調子です がっちりトレーニング 程々トレーニング 皆、自分の良い加減でね ♫ ポールウォーキングを始める動機は人それぞれ。同級会で同い年の歩きを見て、年寄りくさくて驚いたというFさんの変化ご覧ください。 #ポールウォーキング #ウォーキング #笠間市 #地域交流センターともべ
ポールウォーキングを始める動機は人それぞれ。同級会で同い年の歩きを見て、年寄りくさくて驚いたというFさんの変化ご覧ください。 #ポールウォーキング #ウォーキング #笠間市 #地域交流センターともべ 【根気よく身体に覚え込ませる】 2824/12/21 しっくり落ちるのは どの表現 ポールを使って歩くウォーキング 本日も感覚を身体に染み込ませます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク
【根気よく身体に覚え込ませる】 2824/12/21 しっくり落ちるのは どの表現 ポールを使って歩くウォーキング 本日も感覚を身体に染み込ませます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク みなとみらいわくわくポールウォーキング ステッキ工房の店長さんのご紹介で変形性膝関節症の方、腰痛の方が初めて体験にいらしてくれました。 歩き始めは痛そうで心配しましたがポールに慣れてくると、 「ポールがあると楽に歩けます」 「腰痛が楽になりました」と。 ポールの効果はお2人を笑顔にしてくれました♪良かった! 今年始めたM Mわくわくポールウォーキングはシナノ ステッキ工房さんのご協力もあり多くの方に参加いただきました。 また来年、楽しく歩きましょう。 次回は1月10日(金)です😊 #みなとみらい #ステッキ工房 #わくわくポールウォーキング #楽しい仲間たち #アメリカンポーク試食会
みなとみらいわくわくポールウォーキング ステッキ工房の店長さんのご紹介で変形性膝関節症の方、腰痛の方が初めて体験にいらしてくれました。 歩き始めは痛そうで心配しましたがポールに慣れてくると、 「ポールがあると楽に歩けます」 「腰痛が楽になりました」と。 ポールの効果はお2人を笑顔にしてくれました♪良かった! 今年始めたM Mわくわくポールウォーキングはシナノ ステッキ工房さんのご協力もあり多くの方に参加いただきました。 また来年、楽しく歩きましょう。 次回は1月10日(金)です😊 #みなとみらい #ステッキ工房 #わくわくポールウォーキング #楽しい仲間たち #アメリカンポーク試食会 夕暮れ時の八丁堀~隅田川畔~小網町~人形町あたりの雰囲気を満喫 杉並ポール歩きの会(2023年休止)で講師としてお世話になってきた藤井直子さん(ポルク主宰)が企画された“ポール遠足”に参加しました。(2024/12/21) 江戸情緒の残る界隈をキョロキョロしながらノルディックウォーキング。クールダウンのあとは、人形町の名前から想像しなかった「生ハムとワインの店」で忘年会でした。 年のしめくくりのハッピーウォーキング。藤井さんと忘年会企画でお世話になった木村研一さんに感謝です。 ※当初、藤井さんのお立場を間違って書いていたので修正しました。(12/23)
夕暮れ時の八丁堀~隅田川畔~小網町~人形町あたりの雰囲気を満喫 杉並ポール歩きの会(2023年休止)で講師としてお世話になってきた藤井直子さん(ポルク主宰)が企画された“ポール遠足”に参加しました。(2024/12/21) 江戸情緒の残る界隈をキョロキョロしながらノルディックウォーキング。クールダウンのあとは、人形町の名前から想像しなかった「生ハムとワインの店」で忘年会でした。 年のしめくくりのハッピーウォーキング。藤井さんと忘年会企画でお世話になった木村研一さんに感謝です。 ※当初、藤井さんのお立場を間違って書いていたので修正しました。(12/23) 12/22 午前中は逗子で PW教室(年内歩き納め)① 午後は葉山の🥑ファームで冬支度。
12/22 午前中は逗子で PW教室(年内歩き納め)① 午後は葉山の🥑ファームで冬支度。 【2024健走杖輕旅行 宜蘭冬山站】活動圓滿結束! 🌿🚶♂️🚶♀️ 在宜蘭的冬山美景中, 一場健康活力的健走杖輕旅行順利完成!🌞💪 夥伴們在清新空氣與自然美景的陪伴下, 一邊健走,一邊享受身心舒暢的美好時光。🍃🏞️ 感謝所有參與的朋友們熱情投入, 讓活動增添了滿滿的活力與歡笑聲!😄👏 還有協會教練們的專業帶領, 讓大家體驗到了健走杖運動的多重益處,既健康又有趣!✨🎯 期待下次的健走旅程,與大家再次相見, 共同走出健康新里程!🚶♀️🚶♂️🌟 #雷公農園 #健走杖輕旅行宜蘭冬山站 #台灣健走杖運動推廣協會
【2024健走杖輕旅行 宜蘭冬山站】活動圓滿結束! 🌿🚶♂️🚶♀️ 在宜蘭的冬山美景中, 一場健康活力的健走杖輕旅行順利完成!🌞💪 夥伴們在清新空氣與自然美景的陪伴下, 一邊健走,一邊享受身心舒暢的美好時光。🍃🏞️ 感謝所有參與的朋友們熱情投入, 讓活動增添了滿滿的活力與歡笑聲!😄👏 還有協會教練們的專業帶領, 讓大家體驗到了健走杖運動的多重益處,既健康又有趣!✨🎯 期待下次的健走旅程,與大家再次相見, 共同走出健康新里程!🚶♀️🚶♂️🌟 #雷公農園 #健走杖輕旅行宜蘭冬山站 #台灣健走杖運動推廣協會 佐久ポールウォーキング協会より 〜eveの日〜❗️ 佐久大学看護学部/1年生のPW実習報告会がありました。 毎年1年生がポールウォーキングをし参加者とふれあい佐久地域と皆さんの健康的な生き方の調査?が目的です。 コロナ時に始まり4年目で、その時体験した4年生も参加し新旧入り混じった和やかな報告会でした。 生徒の皆さん〜 同席したコーチの皆んな〜 お疲れ様でした。 〜Have a fun eve〜❣️
佐久ポールウォーキング協会より 〜eveの日〜❗️ 佐久大学看護学部/1年生のPW実習報告会がありました。 毎年1年生がポールウォーキングをし参加者とふれあい佐久地域と皆さんの健康的な生き方の調査?が目的です。 コロナ時に始まり4年目で、その時体験した4年生も参加し新旧入り混じった和やかな報告会でした。 生徒の皆さん〜 同席したコーチの皆んな〜 お疲れ様でした。 〜Have a fun eve〜❣️ #2024年歩き納め #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 暖かで軽やかに2024年を締めくくり 皆で集まるから元気になっちゃうね〜 そんなこんなの1年間 小さな元気の積み重ねが嬉しいね みんな今年も ありがとう〜
#2024年歩き納め #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園 暖かで軽やかに2024年を締めくくり 皆で集まるから元気になっちゃうね〜 そんなこんなの1年間 小さな元気の積み重ねが嬉しいね みんな今年も ありがとう〜 志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会(埼玉県 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所グランドテラス)
志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会(埼玉県 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所グランドテラス) 家の中や家の周りで、つまずいたり滑ったりして転びそうになったことはありませんか。年を重ねるにつれて転びやすくなり、骨折などのけがをしやすくなります。特に65歳以上の高齢者は要注意です。骨折がきっかけで寝たきりになってしまうことも。転倒事故が起こりやすい家の中や周囲の危険な箇所をチェックしながら、事故を防ぐための注意点を紹介します。
家の中や家の周りで、つまずいたり滑ったりして転びそうになったことはありませんか。年を重ねるにつれて転びやすくなり、骨折などのけがをしやすくなります。特に65歳以上の高齢者は要注意です。骨折がきっかけで寝たきりになってしまうことも。転倒事故が起こりやすい家の中や周囲の危険な箇所をチェックしながら、事故を防ぐための注意点を紹介します。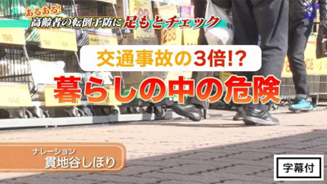 年齢と共に増える、暮らしの中の危険。簡単にできる「足もとチェック」で転倒事故を防ぎましょう。【字幕付】ナレーション:貫地谷しほり
年齢と共に増える、暮らしの中の危険。簡単にできる「足もとチェック」で転倒事故を防ぎましょう。【字幕付】ナレーション:貫地谷しほり 加齢に伴い身体機能が徐々に低下し、筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰え、とっさの反射的防御動作が、素早く力強く行えなくなります。また、自分自身の予測・期待する動作と現実の動作との間に齟齬が生まれて転倒を引き起こすことがあります。
加齢に伴い身体機能が徐々に低下し、筋力、バランス能力、瞬発力、持久力、柔軟性が衰え、とっさの反射的防御動作が、素早く力強く行えなくなります。また、自分自身の予測・期待する動作と現実の動作との間に齟齬が生まれて転倒を引き起こすことがあります。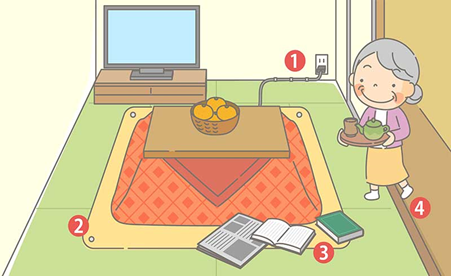 1. コードの配線は歩く動線を避ける。壁をはわせるか、部屋の奥にまとめる
1. コードの配線は歩く動線を避ける。壁をはわせるか、部屋の奥にまとめる 1. 手すりをつける
1. 手すりをつける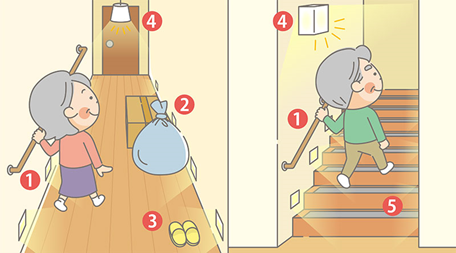 1. 手すりをつける
1. 手すりをつける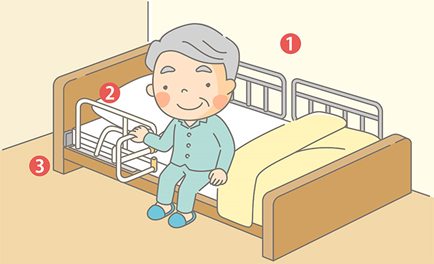 1. ベッドを壁に面するように配置し片方からの転落リスクをなくす
1. ベッドを壁に面するように配置し片方からの転落リスクをなくす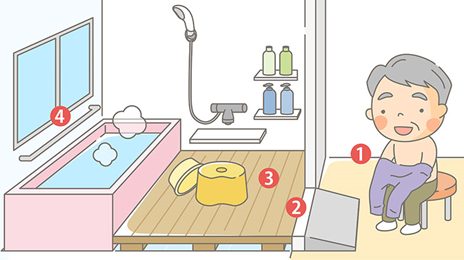 1. 椅子に座って着替える
1. 椅子に座って着替える • 床の水濡れで転倒(雨やケースからの水たれ)
• 床の水濡れで転倒(雨やケースからの水たれ)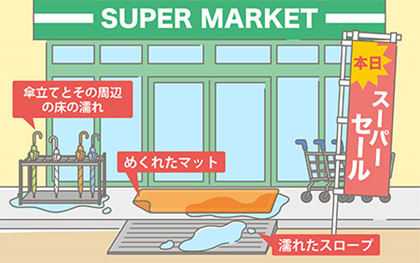 • 床の水濡れで転倒(雨など)
• 床の水濡れで転倒(雨など)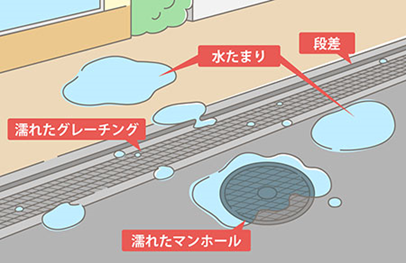 • 濡れた道路(雨など)で転倒
• 濡れた道路(雨など)で転倒 • 車止めにつまずく
• 車止めにつまずく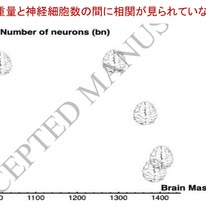 ヒトの脳のニューロン(神経細胞)数は「860億」と広く知られています(図3).しかしこの数値が科学的にどれほど正確なのか疑問を投げかける興味深いエッセイがBrain誌に発表されました.このエッセイの著者はオックスフォード大学の数学者Alain Goriely教授です.Goriely教授は,科学におけるデータの扱い方に厳密さを求める立場から,この「860億」という数字の根拠を詳細に検討しています.
ヒトの脳のニューロン(神経細胞)数は「860億」と広く知られています(図3).しかしこの数値が科学的にどれほど正確なのか疑問を投げかける興味深いエッセイがBrain誌に発表されました.このエッセイの著者はオックスフォード大学の数学者Alain Goriely教授です.Goriely教授は,科学におけるデータの扱い方に厳密さを求める立場から,この「860億」という数字の根拠を詳細に検討しています.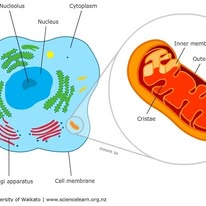 ミトコンドリアはパーキンソン病,脳卒中,認知症や老化など様々な病態において重要な役割を果たしています.動画はコロンビア大学のMartin Picard先生(@MitoPsychoBio)がSNSに投稿した,1つの細胞内のミトコンドリアを示したものです(オリジナルは@chillinwithpfn1).何百もの曲がりくねった細胞内小器官がエネルギーと情報を感知し,処理し,信号を送っています.初めてミトコンドリアの真の姿を示した動画を見たときには感動しましたし,教科書とのあまりの違いに驚きました.科学にはこういうことがまだまだたくさんあるのだろうと思います.
ミトコンドリアはパーキンソン病,脳卒中,認知症や老化など様々な病態において重要な役割を果たしています.動画はコロンビア大学のMartin Picard先生(@MitoPsychoBio)がSNSに投稿した,1つの細胞内のミトコンドリアを示したものです(オリジナルは@chillinwithpfn1).何百もの曲がりくねった細胞内小器官がエネルギーと情報を感知し,処理し,信号を送っています.初めてミトコンドリアの真の姿を示した動画を見たときには感動しましたし,教科書とのあまりの違いに驚きました.科学にはこういうことがまだまだたくさんあるのだろうと思います.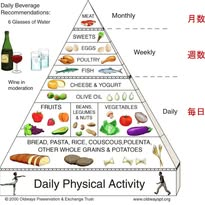 アメリカのハーバード大学を中心とする研究チームによる大規模なコホート研究が,JAMA Network Open誌に掲載されています.この研究では,認知症予防に有効らしいとされてきた地中海式食事(野菜や果物,全粒雑穀類,豆類,オリーブオイル,適量のワイン等;図1)のなかでオリーブオイルに着目し,米国成人において認知症予防に有効かを検討しています.具体的にはオリーブオイル摂取量が,認知症関連の死亡リスクを減少させるかを調べています.またマーガリンやマヨネーズ,バター,植物油といった他の脂質をオリーブオイルに置き換えることで,死亡リスクに変化が生じるかも評価しています.
アメリカのハーバード大学を中心とする研究チームによる大規模なコホート研究が,JAMA Network Open誌に掲載されています.この研究では,認知症予防に有効らしいとされてきた地中海式食事(野菜や果物,全粒雑穀類,豆類,オリーブオイル,適量のワイン等;図1)のなかでオリーブオイルに着目し,米国成人において認知症予防に有効かを検討しています.具体的にはオリーブオイル摂取量が,認知症関連の死亡リスクを減少させるかを調べています.またマーガリンやマヨネーズ,バター,植物油といった他の脂質をオリーブオイルに置き換えることで,死亡リスクに変化が生じるかも評価しています.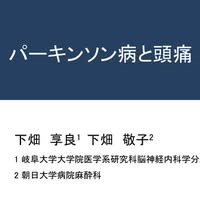 第52回頭痛学会総会(大会長 永田栄一郎先生)において,シンポジウム「片頭痛と神経疾患」のなかで,「パーキンソン病と頭痛」という講演をさせていただきました.8年前の頭痛学会で,同じテーマでシンポジストを担当し,歯が立たなかった内容ですが,今回,再挑戦の機会をいただきました.①片頭痛患者さんがパーキンソン病を発症すると片頭痛が改善する理由,②ドパミン作動薬が一部のパーキンソン病患者の片頭痛を改善する理由.③片頭痛がパーキンソン病の危険因子である理由,について考察しました.スライドは以下よりご覧いただけます.座長の立花久大先生,松浦徹先生,どうもありがとうございました.
第52回頭痛学会総会(大会長 永田栄一郎先生)において,シンポジウム「片頭痛と神経疾患」のなかで,「パーキンソン病と頭痛」という講演をさせていただきました.8年前の頭痛学会で,同じテーマでシンポジストを担当し,歯が立たなかった内容ですが,今回,再挑戦の機会をいただきました.①片頭痛患者さんがパーキンソン病を発症すると片頭痛が改善する理由,②ドパミン作動薬が一部のパーキンソン病患者の片頭痛を改善する理由.③片頭痛がパーキンソン病の危険因子である理由,について考察しました.スライドは以下よりご覧いただけます.座長の立花久大先生,松浦徹先生,どうもありがとうございました. 取材をいただき,新型コロナ感染症による神経後遺症について,最新の知見を分かりやすく記事にしていただきました.ワクチン接種についてはいろいろな考え方があって良いと思いますが,まず判明している科学的な事実を知って頂くことが大切だと思います.
取材をいただき,新型コロナ感染症による神経後遺症について,最新の知見を分かりやすく記事にしていただきました.ワクチン接種についてはいろいろな考え方があって良いと思いますが,まず判明している科学的な事実を知って頂くことが大切だと思います.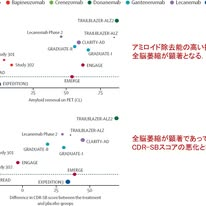 アルツハイマー病では,脳の萎縮(=体積の減少)が病態の進行を示す重要な指標とされてきました.しかし,アミロイドβを除去するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブなど)の臨床試験では,治療群において脳体積が対照群よりも速く減少するという「矛盾した」結果が報告されています.過去のブログでも紹介しました(https://tinyurl.com/2bzfv7wq).
アルツハイマー病では,脳の萎縮(=体積の減少)が病態の進行を示す重要な指標とされてきました.しかし,アミロイドβを除去するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブなど)の臨床試験では,治療群において脳体積が対照群よりも速く減少するという「矛盾した」結果が報告されています.過去のブログでも紹介しました(https://tinyurl.com/2bzfv7wq).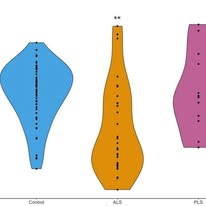 筋萎縮性側索硬化症(ALS)と原発性側索硬化症(PLS)におけるglymphatic systemの機能を縦断的に評価した研究が,カナダ・カルガリー大学等からBrain誌に報告されました.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)と原発性側索硬化症(PLS)におけるglymphatic systemの機能を縦断的に評価した研究が,カナダ・カルガリー大学等からBrain誌に報告されました.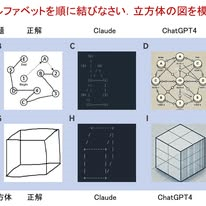 世界五大医学誌の一つBMJ誌は,毎年,クリスマスの時期になるとイグノーベル賞を凌駕するような面白論文の特集号を公開します.今年の原著論文は4つで,変形性手関節症患者の手指機能に対する電気加熱ミトンの効果を調べた論文や,タクシー運転手と救急車運転手におけるアルツハイマー病による死亡率を分析した論文などが報告されていますが,個人的に面白かったのは,今年急速に広まった大規模言語モデルであるChatGPT(OpenAI開発),Claude(Anthropic開発),そしてGemini(Alphabet開発)の「認知機能」を人間と同じようにテストした研究です.エルサレムにあるハダサ医療センターの脳神経内科チームが中心に行ったものです.
世界五大医学誌の一つBMJ誌は,毎年,クリスマスの時期になるとイグノーベル賞を凌駕するような面白論文の特集号を公開します.今年の原著論文は4つで,変形性手関節症患者の手指機能に対する電気加熱ミトンの効果を調べた論文や,タクシー運転手と救急車運転手におけるアルツハイマー病による死亡率を分析した論文などが報告されていますが,個人的に面白かったのは,今年急速に広まった大規模言語モデルであるChatGPT(OpenAI開発),Claude(Anthropic開発),そしてGemini(Alphabet開発)の「認知機能」を人間と同じようにテストした研究です.エルサレムにあるハダサ医療センターの脳神経内科チームが中心に行ったものです.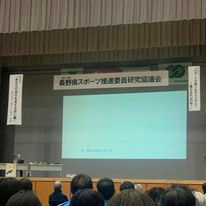 佐久ポールウォーキング協会より 長野県スポーツ推進委員研究協議会in佐久〜 基本講演(講師:佐久大学 坂江千鶴子 学長)後の分科会で県下のスポーツ推進委員の方々にポールウォーキングを体験して貰いました。 ホームの駒場公園〜茨城牧場のひとまわり3.5kmのPW散策でしたが皆さん良い汗かいたと述べてくれました〜❗️ お疲れ様でした。
佐久ポールウォーキング協会より 長野県スポーツ推進委員研究協議会in佐久〜 基本講演(講師:佐久大学 坂江千鶴子 学長)後の分科会で県下のスポーツ推進委員の方々にポールウォーキングを体験して貰いました。 ホームの駒場公園〜茨城牧場のひとまわり3.5kmのPW散策でしたが皆さん良い汗かいたと述べてくれました〜❗️ お疲れ様でした。 茨城県県立水郷県民の森にて。 ポールウォーキング。 気持ち良く、空気の美味しい1日でした。
茨城県県立水郷県民の森にて。 ポールウォーキング。 気持ち良く、空気の美味しい1日でした。 11/5 鎌倉市 健康診査 腰越PWサークル 今日は緑地公園を歩かずセンターで測量会。 市民健康課といつもお世話になっている包括支援センターテレジア1 & 2 の共催で令和5年の健康チェックが行われました。その後30分はポールを使って貯筋体操で汗を流し それぞれの計測結果にざわざわお喋り。 40cm台からの片足立ち上がりが難しかったようです。 次回も今日の結果より下がっていませんように。
11/5 鎌倉市 健康診査 腰越PWサークル 今日は緑地公園を歩かずセンターで測量会。 市民健康課といつもお世話になっている包括支援センターテレジア1 & 2 の共催で令和5年の健康チェックが行われました。その後30分はポールを使って貯筋体操で汗を流し それぞれの計測結果にざわざわお喋り。 40cm台からの片足立ち上がりが難しかったようです。 次回も今日の結果より下がっていませんように。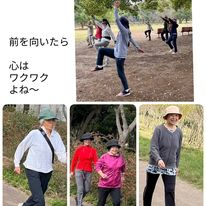 【徐々に 徐々に】 インターバルは 少しだけ負荷をかけながら それがとっても気持いい 2024/11/5 #船橋ウォーミングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #行田公園 #継続は力なり #インターバルウォーキング #ストレッチ筋トレ #健康ウォーキング指導士
【徐々に 徐々に】 インターバルは 少しだけ負荷をかけながら それがとっても気持いい 2024/11/5 #船橋ウォーミングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #行田公園 #継続は力なり #インターバルウォーキング #ストレッチ筋トレ #健康ウォーキング指導士 11/6 朝は北鎌倉テラススタジオで青空を仰ぎながらストレッチ。外のマット運動は風や木々の揺らぎのなかでこの上なく気持ちが良い。午後は西鎌倉サークルに移動。PWですてきな洋館を見ながら藤沢方面に歩きました。
11/6 朝は北鎌倉テラススタジオで青空を仰ぎながらストレッチ。外のマット運動は風や木々の揺らぎのなかでこの上なく気持ちが良い。午後は西鎌倉サークルに移動。PWですてきな洋館を見ながら藤沢方面に歩きました。 2024.11.5〜7 活動記録 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名 ☺︎スマイルエクササイズ.チラシ作成 ☺︎健康体操サークル 12名 ☺︎スマイルポールウォーキング 6名 ☺︎高齢者健康づくり支援士資格更新教育単位証明書発行手続き
2024.11.5〜7 活動記録 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名 ☺︎スマイルエクササイズ.チラシ作成 ☺︎健康体操サークル 12名 ☺︎スマイルポールウォーキング 6名 ☺︎高齢者健康づくり支援士資格更新教育単位証明書発行手続き 11/8 早朝から三本立てで夜まで働き(?)ました。 朝のPW教室は会館の非常用内階段を借りてSTEP昇降練習。 ポールがあると楽々ですね、と感激の声。でも気をつけて、油断しないでくださいね。お昼から特別パーソナルNWクラスを駒沢オリンピック公園で。腕振りに苦労した甲斐あって2キロ目は上手に捌いて初心者には見えませんでした。PWとの違いをはっきりさせて。後ろで衝くと思いがけず前へ進める!とこちらも感激の声。 夕方は二子玉途中下車で分倍河原まで足を伸ばし今帰路です。街はキラキラXmasです。
11/8 早朝から三本立てで夜まで働き(?)ました。 朝のPW教室は会館の非常用内階段を借りてSTEP昇降練習。 ポールがあると楽々ですね、と感激の声。でも気をつけて、油断しないでくださいね。お昼から特別パーソナルNWクラスを駒沢オリンピック公園で。腕振りに苦労した甲斐あって2キロ目は上手に捌いて初心者には見えませんでした。PWとの違いをはっきりさせて。後ろで衝くと思いがけず前へ進める!とこちらも感激の声。 夕方は二子玉途中下車で分倍河原まで足を伸ばし今帰路です。街はキラキラXmasです。 つかの間の?秋を満喫、「気まポ」(気ままにポール歩き)は中野南コース JR東中野駅前に集まって、映画館ポレポレ東中野前から、神田川沿いにしばらく歩き、桃園川緑道(暗渠)をたどって中野駅まで進みました。コース計約5km。 途中寄ったのが氷川神社。参加者のうち2人が幼い頃縁があった神社です。ひとりは小1の頃、よく遊んだところで、お祭りや飯ごう炊さんの思い出があるそうです。もうひとりは、自分では当然覚えてないけどお宮参りの場所だったとか。 もう1箇所、緑道からはずれて紅葉山公園に寄りました。林の中の起伏のある散歩道を気持ちよく散策しましたなかのZERO(ホール)や区立中央図書館もあります。 ついこの前までは暑かったのに、朝晩は冷え込む昨今ですが、ウォーキングには最高でした。 写真は、私と運営仲間の田村和史君撮影です。
つかの間の?秋を満喫、「気まポ」(気ままにポール歩き)は中野南コース JR東中野駅前に集まって、映画館ポレポレ東中野前から、神田川沿いにしばらく歩き、桃園川緑道(暗渠)をたどって中野駅まで進みました。コース計約5km。 途中寄ったのが氷川神社。参加者のうち2人が幼い頃縁があった神社です。ひとりは小1の頃、よく遊んだところで、お祭りや飯ごう炊さんの思い出があるそうです。もうひとりは、自分では当然覚えてないけどお宮参りの場所だったとか。 もう1箇所、緑道からはずれて紅葉山公園に寄りました。林の中の起伏のある散歩道を気持ちよく散策しましたなかのZERO(ホール)や区立中央図書館もあります。 ついこの前までは暑かったのに、朝晩は冷え込む昨今ですが、ウォーキングには最高でした。 写真は、私と運営仲間の田村和史君撮影です。 佐久ポールウォーキング協会より 本日は11月PW駒場例会でした。 朝6時の気温0℃〜初氷まだ不成! 元気シニア(若い?50代もチラホラ〜)が集まり、歩き出し10時前後には10℃に上がり太陽が眩しく温かい公園〜牧場のひとまわり散策でした。 外歩きは12月例会で終了です。1月2月は室内/総合体育館での〜室内ポールウォーク〜となります。 11月残りのイベントは、 来週11/17(日)健康講演会+PWは佐久大学で9時開始です❗️ 大学へ聴講においで下さい❗️
佐久ポールウォーキング協会より 本日は11月PW駒場例会でした。 朝6時の気温0℃〜初氷まだ不成! 元気シニア(若い?50代もチラホラ〜)が集まり、歩き出し10時前後には10℃に上がり太陽が眩しく温かい公園〜牧場のひとまわり散策でした。 外歩きは12月例会で終了です。1月2月は室内/総合体育館での〜室内ポールウォーク〜となります。 11月残りのイベントは、 来週11/17(日)健康講演会+PWは佐久大学で9時開始です❗️ 大学へ聴講においで下さい❗️ 2024.11.8〜10 活動記録 ☺︎青空PW 7名 ☺︎中屋敷親生会 20名 チェアエクササイズ ☺︎神奈川県青少年指導員大会
2024.11.8〜10 活動記録 ☺︎青空PW 7名 ☺︎中屋敷親生会 20名 チェアエクササイズ ☺︎神奈川県青少年指導員大会 【犀川ポールウォーキング大会 秋編】 11月10日日曜日 エコチーム犀川主催 犀川ポールウォーキング大会が開催されました。 大桑ぐるぐる公園発着 秋晴れの良い日に歩く事ができました。 ありがとうございました! また来春に犀川歩きましょう。 今年度のポールウォーキングイベントは終了になります。 来年度もよろしくお願いします。 担当 澤田MCpro・小高AC
【犀川ポールウォーキング大会 秋編】 11月10日日曜日 エコチーム犀川主催 犀川ポールウォーキング大会が開催されました。 大桑ぐるぐる公園発着 秋晴れの良い日に歩く事ができました。 ありがとうございました! また来春に犀川歩きましょう。 今年度のポールウォーキングイベントは終了になります。 来年度もよろしくお願いします。 担当 澤田MCpro・小高AC 📢 2024健走杖健康活力輕旅行 11/10(日)福隆站活動圓滿結束!🎉 福隆站活動在細小的雨🌧️及清新的海風🌬️吹拂下順利完成🌊🚶♂️🚶♀️, 感謝每一位參加的朋友們, 尤其要感謝站長的細心帶領, 讓整個活動進行得如此順利! 感謝 @護老長照 團隊帶領長者們一同參加, 讓大家感受到滿滿的溫暖與支持💙。 看到大家享受健走的樂趣, 並且在福隆美麗的景色中揮灑汗水, 真的讓人覺得無比動容與欣慰🌞💪。 期待我們未來的站點有更多朋友一起參與, 共同享受健走杖的活力與健康! #2024健走杖健康活力輕旅行
📢 2024健走杖健康活力輕旅行 11/10(日)福隆站活動圓滿結束!🎉 福隆站活動在細小的雨🌧️及清新的海風🌬️吹拂下順利完成🌊🚶♂️🚶♀️, 感謝每一位參加的朋友們, 尤其要感謝站長的細心帶領, 讓整個活動進行得如此順利! 感謝 @護老長照 團隊帶領長者們一同參加, 讓大家感受到滿滿的溫暖與支持💙。 看到大家享受健走的樂趣, 並且在福隆美麗的景色中揮灑汗水, 真的讓人覺得無比動容與欣慰🌞💪。 期待我們未來的站點有更多朋友一起參與, 共同享受健走杖的活力與健康! #2024健走杖健康活力輕旅行 2024年11月11日(月) 「郡山市制施行100周年記念事業」 11 月11日 ポールウォーキングツアー 安積開拓「一本の水路」の物語 郡山市長、郡山駅長、久留米観光ガイド会長、久留米ふるさと大使等を招いてポールウォーキングで開成山公園をガイド 勿論、リーダーは日本ポールウォーキング協会長岡智津子MCPROだ。 取り急ぎ、全体集合写真をメインにスタート前準備から打上げまでの様子を紹介しておこう(^O^☆♪
2024年11月11日(月) 「郡山市制施行100周年記念事業」 11 月11日 ポールウォーキングツアー 安積開拓「一本の水路」の物語 郡山市長、郡山駅長、久留米観光ガイド会長、久留米ふるさと大使等を招いてポールウォーキングで開成山公園をガイド 勿論、リーダーは日本ポールウォーキング協会長岡智津子MCPROだ。 取り急ぎ、全体集合写真をメインにスタート前準備から打上げまでの様子を紹介しておこう(^O^☆♪ 秋の木曽路 中山道馬籠 夜明け前ウォーキング2024 落合宿からの石畳を登り馬籠宿から馬籠峠まで 木曽路の秋を堪能しました。 恒例の馬籠黎明太鼓に後押しされ坂道を攻略しました。
秋の木曽路 中山道馬籠 夜明け前ウォーキング2024 落合宿からの石畳を登り馬籠宿から馬籠峠まで 木曽路の秋を堪能しました。 恒例の馬籠黎明太鼓に後押しされ坂道を攻略しました。 [報告会] 先月行われたアルツハイマーデーイベント「オレンジフェスタ」の報告会でした。 先ず各グループで作業しながら振り返りをし、それを元に発表を。昨年は芋煮のメンバーとしてハッスルしました。今年は、企画会で「ボッチャをやりたい」と提案。「スポーツ縁日」と題してボッチャの他、けん玉(支援学校卒業後介護施設に就職してるセミプロが演技し子達は大喜びだったそうです) 輪投げ、駒回し、ストラックアウトを行ったのですが… 区長がボッチャ体験をしたり、お子達に人気で行列が…と、評判良く「このメンバーでまたやろう」の声が出てちょっと嬉しい🎵 今年の豚汁も美味しかったらしい…商店街を巻き込んでクイズ解きながらのウォーキングは、高齢者や認知症カフェ利用者とスタッフも参加したとか。このグループも区内の商店街(100以上ある)を来年以後も次々回るとか。八潮をスタートしてマラソンとか… 聞く話は随分外は盛り上がっていたらしいです。体育館のボッチャに掛かり切り3時間半、行列は途切れなく(大袈裟かな?)おおよそ250人が体験してくれたらしいです。 片付けて18時過ぎ… オレンジのキャンドルの元くるみちゃんとパチリ📸してもらった写真も…(今年もキャンドル作りが賑わっていたらしくたくさんの暖かい灯りが素敵でした
[報告会] 先月行われたアルツハイマーデーイベント「オレンジフェスタ」の報告会でした。 先ず各グループで作業しながら振り返りをし、それを元に発表を。昨年は芋煮のメンバーとしてハッスルしました。今年は、企画会で「ボッチャをやりたい」と提案。「スポーツ縁日」と題してボッチャの他、けん玉(支援学校卒業後介護施設に就職してるセミプロが演技し子達は大喜びだったそうです) 輪投げ、駒回し、ストラックアウトを行ったのですが… 区長がボッチャ体験をしたり、お子達に人気で行列が…と、評判良く「このメンバーでまたやろう」の声が出てちょっと嬉しい🎵 今年の豚汁も美味しかったらしい…商店街を巻き込んでクイズ解きながらのウォーキングは、高齢者や認知症カフェ利用者とスタッフも参加したとか。このグループも区内の商店街(100以上ある)を来年以後も次々回るとか。八潮をスタートしてマラソンとか… 聞く話は随分外は盛り上がっていたらしいです。体育館のボッチャに掛かり切り3時間半、行列は途切れなく(大袈裟かな?)おおよそ250人が体験してくれたらしいです。 片付けて18時過ぎ… オレンジのキャンドルの元くるみちゃんとパチリ📸してもらった写真も…(今年もキャンドル作りが賑わっていたらしくたくさんの暖かい灯りが素敵でした 11/14 午後の貯筋クラスでは筋肉貯金残高チェック。 静的・動的バランス、下肢筋力、敏捷性等々8つの項目をチェック。大股でどのくらい歩き続けるかも試してみました。そして包括支援センターからスタッフさんが配布の住宅防火チェックシートも✅ 火災警報器の取り付けは消防職員さんがお手伝いしてくださるとのこと(要事前予約) 今日のおやつは浪花家の鯛焼き1匹。
11/14 午後の貯筋クラスでは筋肉貯金残高チェック。 静的・動的バランス、下肢筋力、敏捷性等々8つの項目をチェック。大股でどのくらい歩き続けるかも試してみました。そして包括支援センターからスタッフさんが配布の住宅防火チェックシートも✅ 火災警報器の取り付けは消防職員さんがお手伝いしてくださるとのこと(要事前予約) 今日のおやつは浪花家の鯛焼き1匹。 【小春日和のいい日です】 2024/11/14 インターバルで普段より 少しだけ頑張りました 定例会は おしゃべりができる良い場所 みたいです💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #インターバルウォーキング #一人より皆がいいね
【小春日和のいい日です】 2024/11/14 インターバルで普段より 少しだけ頑張りました 定例会は おしゃべりができる良い場所 みたいです💞 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #インターバルウォーキング #一人より皆がいいね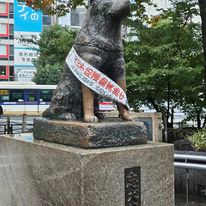 11/15 渋谷は大雨とtvで聞いて大きな傘を持って出掛けたのですが 着いた時は小雨🌂で助かりました。今日は自己紹介(今頃!)ゲームをしてご近所さんを確認。初台の方が一番多かったです。今期ももう6回目になり、皆さん中強度歩きが様になって来て嬉しいです。次期の会員募集が始まったそう(区報掲載)。
11/15 渋谷は大雨とtvで聞いて大きな傘を持って出掛けたのですが 着いた時は小雨🌂で助かりました。今日は自己紹介(今頃!)ゲームをしてご近所さんを確認。初台の方が一番多かったです。今期ももう6回目になり、皆さん中強度歩きが様になって来て嬉しいです。次期の会員募集が始まったそう(区報掲載)。 【ゴールはお祭りよ】 2024/11/16 船橋港親水公園で インターナショナルフェステバル 楽しい事が大好きメンバー しっかり歩いて 食べて 観て 遊んで 笑って 大忙しで〜す #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #海老川土曜日コース
【ゴールはお祭りよ】 2024/11/16 船橋港親水公園で インターナショナルフェステバル 楽しい事が大好きメンバー しっかり歩いて 食べて 観て 遊んで 笑って 大忙しで〜す #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #海老川土曜日コース ⼀般社団法⼈UDe-スポーツ協会が開発・販売を⾏う年齢や障がいの有無 にかかわらず、誰でもが行うことができるeスポーツ『UDe-Sports(ユーディイースポーツ)🄬』の無料体験を開始します。◎昨今のe-スポーツの広がりを受け、誰でもが楽しめるe-スポーツを⼿軽に、より簡単に⾼齢者や未就学児にもゲームを楽しんでもらえる。同協会の販売代理店また、UDe-スポーツ認定指導員としてUDe-Sportsを普及いたします。オリジナルゲームや、ゲーム以外の機能として簡易的な注意⼒、動体視⼒、判断⼒、記憶⼒などの認知機能をチェックするモードもあります。
⼀般社団法⼈UDe-スポーツ協会が開発・販売を⾏う年齢や障がいの有無 にかかわらず、誰でもが行うことができるeスポーツ『UDe-Sports(ユーディイースポーツ)🄬』の無料体験を開始します。◎昨今のe-スポーツの広がりを受け、誰でもが楽しめるe-スポーツを⼿軽に、より簡単に⾼齢者や未就学児にもゲームを楽しんでもらえる。同協会の販売代理店また、UDe-スポーツ認定指導員としてUDe-Sportsを普及いたします。オリジナルゲームや、ゲーム以外の機能として簡易的な注意⼒、動体視⼒、判断⼒、記憶⼒などの認知機能をチェックするモードもあります。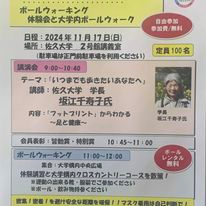 佐久ポールウォーキング協会より 秋恒例の健康講演会+PW体験・散策が、今年は佐久大学を会場に学長/坂江千寿子氏の講演会(フットプリントからわかる足と健康)とポールウォーキングでの大学構内〜クロスカントリーコース散策でした。 会員表彰の皆勤賞と頑張ったde賞で新米の贈呈も有りの本年の最大イベントも無事終わりに〜^_^ 参加者 スタッフの皆さん〜お疲れ様でした❗️
佐久ポールウォーキング協会より 秋恒例の健康講演会+PW体験・散策が、今年は佐久大学を会場に学長/坂江千寿子氏の講演会(フットプリントからわかる足と健康)とポールウォーキングでの大学構内〜クロスカントリーコース散策でした。 会員表彰の皆勤賞と頑張ったde賞で新米の贈呈も有りの本年の最大イベントも無事終わりに〜^_^ 参加者 スタッフの皆さん〜お疲れ様でした❗️ 2024.11.14〜17 活動記録 ☺︎スマイルチーム上溝 22名 ☺︎子育て広場 親子たいそう ☺︎ポールウォーキング講座 ☺︎公民館1月抽選申し込み 5団体分 ☺︎スマイル備品ガレージ整理 ☺︎ポールウォーキング講座資料作成 メンバーさんより菊芋、柿をいただきました😋 ☺︎メンバーさんより寄付していただいた毛布などを茨城県動物指導センターへ送りました
2024.11.14〜17 活動記録 ☺︎スマイルチーム上溝 22名 ☺︎子育て広場 親子たいそう ☺︎ポールウォーキング講座 ☺︎公民館1月抽選申し込み 5団体分 ☺︎スマイル備品ガレージ整理 ☺︎ポールウォーキング講座資料作成 メンバーさんより菊芋、柿をいただきました😋 ☺︎メンバーさんより寄付していただいた毛布などを茨城県動物指導センターへ送りました 【更新講習会】 本日11月17日日曜日 能美市物見山体育館会議室にて 日本ポールウォーキング協会更新講習会でした。1名のアドバンスコーチの方が、受講しました。 雨が降る前に、階段の登り方や降り方からギアチェンジの歩き方や、椅子に座りながら筋トレもしました。 お疲れ様でした‼️
【更新講習会】 本日11月17日日曜日 能美市物見山体育館会議室にて 日本ポールウォーキング協会更新講習会でした。1名のアドバンスコーチの方が、受講しました。 雨が降る前に、階段の登り方や降り方からギアチェンジの歩き方や、椅子に座りながら筋トレもしました。 お疲れ様でした‼️ 【58cmってどれくらいなの?】 #認知症予防・#転倒予防・ #社会参加 #介護予防 今日も皆で実践中 女性58cm以下は認知症リスク が高くなる! 歩幅58cmって実際は どのくらい? 10mだと何歩なの…? #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング
【58cmってどれくらいなの?】 #認知症予防・#転倒予防・ #社会参加 #介護予防 今日も皆で実践中 女性58cm以下は認知症リスク が高くなる! 歩幅58cmって実際は どのくらい? 10mだと何歩なの…? #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング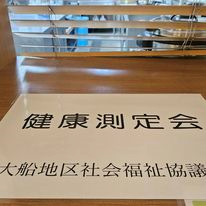 今日は大船地区社協主催、包括支援センターきしろ・ふれあいの泉協力のいきいき健康測定と杉浦コーチによるフレイル・認知症予防のお話と体操でした。 今日時点での骨密度・血管年齢測定。握力・歩幅テスト、バランス能力等々計測し運動・栄養の話に耳を傾けました。サプリメントのお話もためになりました。
今日は大船地区社協主催、包括支援センターきしろ・ふれあいの泉協力のいきいき健康測定と杉浦コーチによるフレイル・認知症予防のお話と体操でした。 今日時点での骨密度・血管年齢測定。握力・歩幅テスト、バランス能力等々計測し運動・栄養の話に耳を傾けました。サプリメントのお話もためになりました。 【気持ちいい〜】 2024/11/19 蒼空 インターバル頑張ったよ〜 バッチリね HAPPY〜 ♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバルウォーキング #県立行田公園
【気持ちいい〜】 2024/11/19 蒼空 インターバル頑張ったよ〜 バッチリね HAPPY〜 ♫ #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバルウォーキング #県立行田公園 11/19 昨日まで江ノ島の予定でしたが強い風と気温急降下の予報で急遽広町緑地に変更。木枯らし木枯らし寒い道~を大榎や石切場方面にPWで歩きました。広場でカタサゲ・ヒジヒキの練習をしたのですがお喋りに夢中になると・・・腕は動かなくなって~~😢
11/19 昨日まで江ノ島の予定でしたが強い風と気温急降下の予報で急遽広町緑地に変更。木枯らし木枯らし寒い道~を大榎や石切場方面にPWで歩きました。広場でカタサゲ・ヒジヒキの練習をしたのですがお喋りに夢中になると・・・腕は動かなくなって~~😢 11/20 真冬の寒さに冷たい雨。気温の差は老体に響きます。暖房を入れた会場で筋トレ・筋トレ・筋トレで暖かくなりました。筋肉マーチを唄いながらの足鍵盤🎹運動は新しいメニューでした。うちの前のソヨゴはいま真っ赤な実をつけています。谷川俊太郎氏に続いて火野正平さんの訃報。寒さがより厳しく感じます。
11/20 真冬の寒さに冷たい雨。気温の差は老体に響きます。暖房を入れた会場で筋トレ・筋トレ・筋トレで暖かくなりました。筋肉マーチを唄いながらの足鍵盤🎹運動は新しいメニューでした。うちの前のソヨゴはいま真っ赤な実をつけています。谷川俊太郎氏に続いて火野正平さんの訃報。寒さがより厳しく感じます。 【日式健走AC(進階)課程】兩天課程圓滿結束!🎉 經過兩天充實又緊湊的學習, 我們的日式健走AC(進階)課程在熱情與努力中完美落幕!👏💪 學員們在專業講師的指導下, 不僅加強了健走技術, 還深入了解了更多進階帶隊與教學的技巧, 為未來的健走推廣邁出更堅實的一步!🚶♂️🚶♀️ 這兩天的課程不僅是技術的升級, 更是一場與志同道合的健走夥伴們共同成長的旅程💖。 透過理論與實作的結合, 大家都收穫滿滿,熱情高漲, 展現出對推廣健走運動的無限信心與期待!🌟 再次感謝所有參與的學員和教練們的付出與努力, 讓這次課程充滿活力與收穫✨! 期待未來的大家, #將健走杖運動推向更高峰!⛰️🌍 #台灣健走杖運動推廣協會 #日式健走
【日式健走AC(進階)課程】兩天課程圓滿結束!🎉 經過兩天充實又緊湊的學習, 我們的日式健走AC(進階)課程在熱情與努力中完美落幕!👏💪 學員們在專業講師的指導下, 不僅加強了健走技術, 還深入了解了更多進階帶隊與教學的技巧, 為未來的健走推廣邁出更堅實的一步!🚶♂️🚶♀️ 這兩天的課程不僅是技術的升級, 更是一場與志同道合的健走夥伴們共同成長的旅程💖。 透過理論與實作的結合, 大家都收穫滿滿,熱情高漲, 展現出對推廣健走運動的無限信心與期待!🌟 再次感謝所有參與的學員和教練們的付出與努力, 讓這次課程充滿活力與收穫✨! 期待未來的大家, #將健走杖運動推向更高峰!⛰️🌍 #台灣健走杖運動推廣協會 #日式健走 11/22 今日は渋谷は総集編。盛り沢山のメニューのPW教室。3期7回目のこのクラスも和気藹々で皆笑顔です😁 午後からはパーソナルNW2回目 シニア同級生お二人に超特訓の充実2時間でした。10 STEPの後半はかなり運動量もありPWよりハードですが歩く楽しさは倍以上? PWは先チップが丸いので安定したポールエクササイズが豊富でバランスがとれ転倒予防に最適です。
11/22 今日は渋谷は総集編。盛り沢山のメニューのPW教室。3期7回目のこのクラスも和気藹々で皆笑顔です😁 午後からはパーソナルNW2回目 シニア同級生お二人に超特訓の充実2時間でした。10 STEPの後半はかなり運動量もありPWよりハードですが歩く楽しさは倍以上? PWは先チップが丸いので安定したポールエクササイズが豊富でバランスがとれ転倒予防に最適です。 2024.11.22〜23 活動記録 ☺︎スマイル星が丘PW 7名 ☺︎ポールウォーキング講座 10名 上鶴間地域包括支援センター主催 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会 ☺︎公民館まつり部門別会議 ☺︎スマイルチームメンバーカルテ整理
2024.11.22〜23 活動記録 ☺︎スマイル星が丘PW 7名 ☺︎ポールウォーキング講座 10名 上鶴間地域包括支援センター主催 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会 ☺︎公民館まつり部門別会議 ☺︎スマイルチームメンバーカルテ整理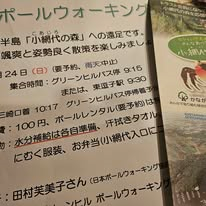 11/24 ①逗子市ポールウォーキングクラブの遠足 小網代の森を歩いてきました。遠足日和☀ 風もなく青空の下 小鳥の囀りを聴きながら木道~山道を歩きました。アカテガニは冬眠の時期でした。 事務局代表の簡潔なお話から ここは森林、湿地、干潟及び海までが連続して残されている、関東地方で唯一の自然環境だと知って鼻高々。
11/24 ①逗子市ポールウォーキングクラブの遠足 小網代の森を歩いてきました。遠足日和☀ 風もなく青空の下 小鳥の囀りを聴きながら木道~山道を歩きました。アカテガニは冬眠の時期でした。 事務局代表の簡潔なお話から ここは森林、湿地、干潟及び海までが連続して残されている、関東地方で唯一の自然環境だと知って鼻高々。 😘Bésame mucho in 台湾🇹🇼 3日👀 2024年11月24日 6:30の早朝ポールウォーキングから23:00ホテル到着までてんこ盛り!何万歩歩いたろう?ハードなスケジュールだったがロマンチックでもあったかな? ジオパークで女王への抱擁と接吻の試み、そして九份では‘ゆばば’と肩を組み「千と千尋」の世界に浸り、十分で天燈(ランタン)を美熟女達と夜空に想いを馳せて上げた🌌 大安森林公園ポールウォーキング→バスチャーターで台北近郊観光地へ ジオパーク・十分(滝とランタン揚げ)・陰陽海(海が2色)・九份散策・ディナー 今晩もお腹満杯で眠りに陥いる💤
😘Bésame mucho in 台湾🇹🇼 3日👀 2024年11月24日 6:30の早朝ポールウォーキングから23:00ホテル到着までてんこ盛り!何万歩歩いたろう?ハードなスケジュールだったがロマンチックでもあったかな? ジオパークで女王への抱擁と接吻の試み、そして九份では‘ゆばば’と肩を組み「千と千尋」の世界に浸り、十分で天燈(ランタン)を美熟女達と夜空に想いを馳せて上げた🌌 大安森林公園ポールウォーキング→バスチャーターで台北近郊観光地へ ジオパーク・十分(滝とランタン揚げ)・陰陽海(海が2色)・九份散策・ディナー 今晩もお腹満杯で眠りに陥いる💤 11/26 🟡 💛 🟨 三浦ネットポールウォーキンググループ 季節の「黄色を訪ねて」・・男子4、女子1で先日の鎌倉検定の問題を解説して頂きながら歩きました。難問が一杯! 安国論寺も長勝寺も門前~境内の銀杏が漸く八分は色づいていてきれいです。 ここから材木座の辻付近,元八幡、辻薬師堂、本興寺をたずね歩いてみました。 三浦道 朱塗りの魚橋を渡り、大町四つ角から水道路の辻町歩き。海の方から山へ向かって流れる逆川は地形の影響で面白い。のんびり歩くと片隅の道祖神や小さな花に気づきます。石碑を一字一句読む方に感心しながら。
11/26 🟡 💛 🟨 三浦ネットポールウォーキンググループ 季節の「黄色を訪ねて」・・男子4、女子1で先日の鎌倉検定の問題を解説して頂きながら歩きました。難問が一杯! 安国論寺も長勝寺も門前~境内の銀杏が漸く八分は色づいていてきれいです。 ここから材木座の辻付近,元八幡、辻薬師堂、本興寺をたずね歩いてみました。 三浦道 朱塗りの魚橋を渡り、大町四つ角から水道路の辻町歩き。海の方から山へ向かって流れる逆川は地形の影響で面白い。のんびり歩くと片隅の道祖神や小さな花に気づきます。石碑を一字一句読む方に感心しながら。 歩いて笑って 元気いばらき (笠間市芸術の森公園 笠間市笠間2345) 今日は小学2年生も一緒に歩きました! 外の空気をたっぷり吸いながら(ちょうど良い息の上がり方とも言う😁)ポールを使ってしっかり歩きの1時間半「この日は夜よく眠れました」との感想をいただきました。睡眠大事ですよね。 効果が感じられて良かった👍
歩いて笑って 元気いばらき (笠間市芸術の森公園 笠間市笠間2345) 今日は小学2年生も一緒に歩きました! 外の空気をたっぷり吸いながら(ちょうど良い息の上がり方とも言う😁)ポールを使ってしっかり歩きの1時間半「この日は夜よく眠れました」との感想をいただきました。睡眠大事ですよね。 効果が感じられて良かった👍 11/28 気温は高いけれど風が強かったですね。貯筋クラスは室内でぬくぬく姿勢チェック、右肩下がり気味多いです。昨日のクラスに続いて歩容もチェック。ポールあり無し共 きれいに歩けました。 肩下げ肘引き素晴らしいです。次回はもう師走。センターの図書室は飲食可とのことで忘年会の開催企画進行中。
11/28 気温は高いけれど風が強かったですね。貯筋クラスは室内でぬくぬく姿勢チェック、右肩下がり気味多いです。昨日のクラスに続いて歩容もチェック。ポールあり無し共 きれいに歩けました。 肩下げ肘引き素晴らしいです。次回はもう師走。センターの図書室は飲食可とのことで忘年会の開催企画進行中。 【いい事がいっぱいの日】 2024/11/28 小春日和の穏やかな日は 何気に特別な日になります インターバルで身体スッキリ 東から西公園の日本庭園へ 皆で揃って移動 ゆったりノンビリ それがいいと思えた 日です #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #インターバルウォーキング
【いい事がいっぱいの日】 2024/11/28 小春日和の穏やかな日は 何気に特別な日になります インターバルで身体スッキリ 東から西公園の日本庭園へ 皆で揃って移動 ゆったりノンビリ それがいいと思えた 日です #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #インターバルウォーキング 【2024健走杖輕旅行 苗栗通霄站 】 台日交流🇹🇼🇯🇵活動圓滿結束! 在美麗的苗栗通霄🌳, 我們迎來了一場精彩的台日交流健走活動! 來自台灣與日本的健走愛好者齊聚一堂, 以健走杖為媒介,不僅促進了文化交流, 更拉近了彼此的距離🌏🤝。 伴隨著清新的空氣與迷人的自然景色🌿, 大家一同健走, 現場充滿了笑聲與活力!🚶♂️🚶♀️ 感謝日本友人的熱情加入💖, 讓這次的苗栗通霄站活動更加豐富圓滿! 期待未來的健走旅程, 我們可以再次攜手, 一起走出健康,走向世界!🌟💪 #2024健走杖健康活力輕旅行
【2024健走杖輕旅行 苗栗通霄站 】 台日交流🇹🇼🇯🇵活動圓滿結束! 在美麗的苗栗通霄🌳, 我們迎來了一場精彩的台日交流健走活動! 來自台灣與日本的健走愛好者齊聚一堂, 以健走杖為媒介,不僅促進了文化交流, 更拉近了彼此的距離🌏🤝。 伴隨著清新的空氣與迷人的自然景色🌿, 大家一同健走, 現場充滿了笑聲與活力!🚶♂️🚶♀️ 感謝日本友人的熱情加入💖, 讓這次的苗栗通霄站活動更加豐富圓滿! 期待未來的健走旅程, 我們可以再次攜手, 一起走出健康,走向世界!🌟💪 #2024健走杖健康活力輕旅行 11/29 二階堂へ紅葉を求めてポールウォーキング♪ 来週は3~4回訪ねることになります。🍁🍁🍁🍁🍁
11/29 二階堂へ紅葉を求めてポールウォーキング♪ 来週は3~4回訪ねることになります。🍁🍁🍁🍁🍁 🍁鎌倉ミステリーvol.10🍁 9回祇園山には遠くからも沢山ご参加いただきありがとうございました。次回は紅葉狩り🍁で獅子舞へ参りたいと思います。 鎌倉の紅葉は毎年遅く、今年は夏日が続きましたのでこの日程で美しく燃えてくれるかは「ミステリー」です。, 〔日時〕 ①12月2日(月曜日) 🍂 ②又は同月8日(日曜🍂 どちらもおなじコースです。ご都合の良い方にご参加ください 〔集合時間・場所〕 ①②とも ✳ 金沢八景からバスのかた 大塔宮鳥居⛩️前 10時半 ✳ 鎌倉駅からのかたは東口みどりの窓口前 9時50分 (10時発のバスに乗ります) 〔保険〕 各自でご手配ください。 〔解散・食事〕 お昼前大塔宮バス停(鎌倉駅行き)で解散 ランチは各自で 〔参加費・持物〕 1000円 NW・PWポールどちらでも。 飲み物、飴玉🍬など。 体温調節の出来る服装。リュック。歩きやすい靴👟 帽子🧢 雨具🌂 山道を歩きます。前回の祇園山コースより凸凹少ないですが、滑りやすい箇所あり。 〔主催・企画」 日本ポールウォーキング協会マスターコーチプロ 酒井尚美(P&P)& 田村芙美子(鎌ポ) 〔雨天時〕 ①② 各々前夜19時 雨予報の場合は中止 〔申し込み・問合せ〕 酒井or田村まで 対面、メッセージ、LINE、メールで。 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂
🍁鎌倉ミステリーvol.10🍁 9回祇園山には遠くからも沢山ご参加いただきありがとうございました。次回は紅葉狩り🍁で獅子舞へ参りたいと思います。 鎌倉の紅葉は毎年遅く、今年は夏日が続きましたのでこの日程で美しく燃えてくれるかは「ミステリー」です。, 〔日時〕 ①12月2日(月曜日) 🍂 ②又は同月8日(日曜🍂 どちらもおなじコースです。ご都合の良い方にご参加ください 〔集合時間・場所〕 ①②とも ✳ 金沢八景からバスのかた 大塔宮鳥居⛩️前 10時半 ✳ 鎌倉駅からのかたは東口みどりの窓口前 9時50分 (10時発のバスに乗ります) 〔保険〕 各自でご手配ください。 〔解散・食事〕 お昼前大塔宮バス停(鎌倉駅行き)で解散 ランチは各自で 〔参加費・持物〕 1000円 NW・PWポールどちらでも。 飲み物、飴玉🍬など。 体温調節の出来る服装。リュック。歩きやすい靴👟 帽子🧢 雨具🌂 山道を歩きます。前回の祇園山コースより凸凹少ないですが、滑りやすい箇所あり。 〔主催・企画」 日本ポールウォーキング協会マスターコーチプロ 酒井尚美(P&P)& 田村芙美子(鎌ポ) 〔雨天時〕 ①② 各々前夜19時 雨予報の場合は中止 〔申し込み・問合せ〕 酒井or田村まで 対面、メッセージ、LINE、メールで。 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂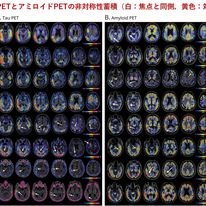 アルツハイマー病(AD)は,健康な高齢者に比べててんかん発症のリスクが2〜3倍高く,特に焦点発作(部分発作)の発症はADの進行と関連している可能性が指摘されています.しかし,ADにおける焦点発作とタウ・アミロイドβの蓄積との関連についてはよく分かっていませんでした.Neurology誌にマサチューセッツ総合病院(MGH)から,焦点発作を認めたAD患者(AD-Ep)において,焦点とタウ・アミロイドβの蓄積,および脳の萎縮の関連を検討した研究が報告されました.
アルツハイマー病(AD)は,健康な高齢者に比べててんかん発症のリスクが2〜3倍高く,特に焦点発作(部分発作)の発症はADの進行と関連している可能性が指摘されています.しかし,ADにおける焦点発作とタウ・アミロイドβの蓄積との関連についてはよく分かっていませんでした.Neurology誌にマサチューセッツ総合病院(MGH)から,焦点発作を認めたAD患者(AD-Ep)において,焦点とタウ・アミロイドβの蓄積,および脳の萎縮の関連を検討した研究が報告されました.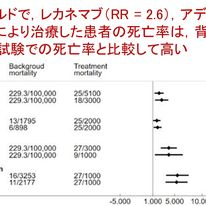 アルツハイマー病(AD)の病態修飾薬であるアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,アデュカヌマブ)に関する新たな報告がプレプリント(未査読)論文として発表されました.シンシナチ大学のEspay教授らによる報告です.この研究は,アメリカのFDA(食品医薬品局)の副作用報告システム(FAERS)のデータに基づき,これらの抗体薬を使用したAD患者の死亡率が,一般的なAD患者,もしくはこれらの抗体薬の臨床試験の患者と比較してどの程度異なるかを評価したものです.つまり,これらの抗体薬のリアルワールド(日常の臨床現場)での死亡率が,臨床試験およびFAERSで報告された年齢範囲(75~84歳)の一般的なAD患者の死亡率(背景死亡率)を上回るかどうかを評価しています.背景死亡率は2020年の75〜84歳のAD患者の死亡率である100,000人あたり229.3人を基準にしています.
アルツハイマー病(AD)の病態修飾薬であるアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,アデュカヌマブ)に関する新たな報告がプレプリント(未査読)論文として発表されました.シンシナチ大学のEspay教授らによる報告です.この研究は,アメリカのFDA(食品医薬品局)の副作用報告システム(FAERS)のデータに基づき,これらの抗体薬を使用したAD患者の死亡率が,一般的なAD患者,もしくはこれらの抗体薬の臨床試験の患者と比較してどの程度異なるかを評価したものです.つまり,これらの抗体薬のリアルワールド(日常の臨床現場)での死亡率が,臨床試験およびFAERSで報告された年齢範囲(75~84歳)の一般的なAD患者の死亡率(背景死亡率)を上回るかどうかを評価しています.背景死亡率は2020年の75〜84歳のAD患者の死亡率である100,000人あたり229.3人を基準にしています. 第12回難病医療ネットワーク学会@弘前のなかでもっとも印象に残った講演は,荻野美恵子先生(国際医療福祉大学)による標題の教育講演でした.取ったメモを教室メンバーに送り,自身のアドバンス ケア プラニング(ACP)のあり方を考えてもらいました.以下,そのなかの要点を5つ書き出しました(私の解釈も含まれているかもしれませんが,ご容赦ください).
第12回難病医療ネットワーク学会@弘前のなかでもっとも印象に残った講演は,荻野美恵子先生(国際医療福祉大学)による標題の教育講演でした.取ったメモを教室メンバーに送り,自身のアドバンス ケア プラニング(ACP)のあり方を考えてもらいました.以下,そのなかの要点を5つ書き出しました(私の解釈も含まれているかもしれませんが,ご容赦ください).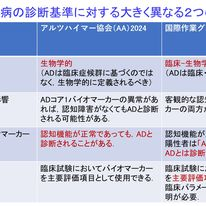 JAMA Neurologyの最新号にアルツハイマー病(AD)の診断と定義に関する重要な議論が掲載されています.著者の国際作業グループ(IWG)は多くの大学や医療機関に所属する専門家たちで構成されたものですが,アルツハイマー協会(AA)により提唱された最新のAD診断基準について見直しを求めています.
JAMA Neurologyの最新号にアルツハイマー病(AD)の診断と定義に関する重要な議論が掲載されています.著者の国際作業グループ(IWG)は多くの大学や医療機関に所属する専門家たちで構成されたものですが,アルツハイマー協会(AA)により提唱された最新のAD診断基準について見直しを求めています.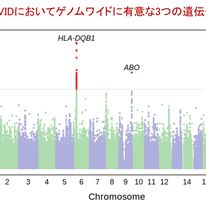 今回のキーワードは,long COVIDの3つの遺伝的要因(免疫,ウイルス応答,血液型)が同定された,小児において肥満がlong COVIDのリスク因子として重要である,被殻の縮小は,long COVIDの症状負荷と遂行機能の低下と関連する,下部延髄網様体や縫線核がlong COVIDに関与している,急性期におけるニルマトレルビル・リトナビルはlong COVIDを減少させる,です.
今回のキーワードは,long COVIDの3つの遺伝的要因(免疫,ウイルス応答,血液型)が同定された,小児において肥満がlong COVIDのリスク因子として重要である,被殻の縮小は,long COVIDの症状負荷と遂行機能の低下と関連する,下部延髄網様体や縫線核がlong COVIDに関与している,急性期におけるニルマトレルビル・リトナビルはlong COVIDを減少させる,です.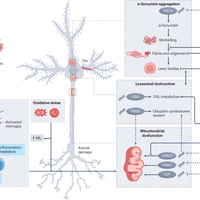 最新号のNat Rev Neurol誌に分かりやすい図がありました.最新情報を含む,今後の講義にも使える良い図だと思いました.神経細胞のどの部位にどのような変化が生じているか,また治療の標的が何なのかがよく分かります.アルツハイマー病病理のタウやアミロイドβも書かれて,おやっと思われるかもしれませんが,いわゆる混合病理が病態にも関わっているという立場を取られています.
最新号のNat Rev Neurol誌に分かりやすい図がありました.最新情報を含む,今後の講義にも使える良い図だと思いました.神経細胞のどの部位にどのような変化が生じているか,また治療の標的が何なのかがよく分かります.アルツハイマー病病理のタウやアミロイドβも書かれて,おやっと思われるかもしれませんが,いわゆる混合病理が病態にも関わっているという立場を取られています. Brain Nerve誌の11月号は筋萎縮性側索硬化症(ALS)の特集です(図2).診断と告知,新しい診断基準,緩和ケア,核酸医薬,治療薬開発の現状と,非常に勉強になる内容でした.そのなかでも福武敏夫先生×荻野美恵子先生×神田隆先生による鼎談「ALSの今日と明日」は勉強になりました.そのなかで,「難病患者さんにおける安楽死をどう考えるか?」についても議論がなされました.私はその感想をあとがきに書かせていただきました.編集部より許可をいただきましたので下記に掲載します.
Brain Nerve誌の11月号は筋萎縮性側索硬化症(ALS)の特集です(図2).診断と告知,新しい診断基準,緩和ケア,核酸医薬,治療薬開発の現状と,非常に勉強になる内容でした.そのなかでも福武敏夫先生×荻野美恵子先生×神田隆先生による鼎談「ALSの今日と明日」は勉強になりました.そのなかで,「難病患者さんにおける安楽死をどう考えるか?」についても議論がなされました.私はその感想をあとがきに書かせていただきました.編集部より許可をいただきましたので下記に掲載します.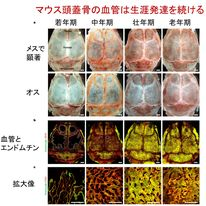 先日,日本神経学会のresidentホームページに「近未来の脳神経内科は頭蓋骨から診断し治療する!」というエッセイを執筆しました(https://resident.neurology-jp.org/…/future/future_15.html).またCOVID-19のSARS-CoV-2ウイルスが脳に侵入する経路として,頭蓋骨の骨髄ニッチが注目されていることも過去にブログでご紹介しました(https://tinyurl.com/25dqmh6j).頭蓋骨の骨髄は現在,脳との関連でとても注目を集めています.
先日,日本神経学会のresidentホームページに「近未来の脳神経内科は頭蓋骨から診断し治療する!」というエッセイを執筆しました(https://resident.neurology-jp.org/…/future/future_15.html).またCOVID-19のSARS-CoV-2ウイルスが脳に侵入する経路として,頭蓋骨の骨髄ニッチが注目されていることも過去にブログでご紹介しました(https://tinyurl.com/25dqmh6j).頭蓋骨の骨髄は現在,脳との関連でとても注目を集めています. 【おかえりなさい &ようこそ いらっしゃい】 #船橋ウォーキングサソイエティ #シニアポールウォーキング 2期スタートしました いろんな「おかえりなさい」が あった日 感慨深いです ◯闘病を経て4年のお休みからの復帰 ◯ご主人様の介護の合間に都合をつけ駆けつけて出席 《糸は繋がっていました》 暑く苦しかった夏を越えて 多くの人メンバーが元気に戻ってきました 去年の夏よりも元気そうです (≧▽≦) 体験者2名 新入会者1名を迎えました 同期がいる事は強運です 2期も楽しく〜 歩きましょう〜
【おかえりなさい &ようこそ いらっしゃい】 #船橋ウォーキングサソイエティ #シニアポールウォーキング 2期スタートしました いろんな「おかえりなさい」が あった日 感慨深いです ◯闘病を経て4年のお休みからの復帰 ◯ご主人様の介護の合間に都合をつけ駆けつけて出席 《糸は繋がっていました》 暑く苦しかった夏を越えて 多くの人メンバーが元気に戻ってきました 去年の夏よりも元気そうです (≧▽≦) 体験者2名 新入会者1名を迎えました 同期がいる事は強運です 2期も楽しく〜 歩きましょう〜 ピラティスエクササイズ 【シングルレッグキック】 下腹薄くし、胸椎伸転させ、ハムストリングで鍛えていきます。 さあ!レッツピラティス❣️
ピラティスエクササイズ 【シングルレッグキック】 下腹薄くし、胸椎伸転させ、ハムストリングで鍛えていきます。 さあ!レッツピラティス❣️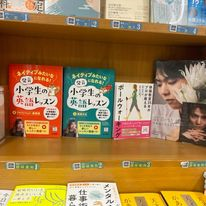 嬉しい😊
嬉しい😊 【暑さ対策の効果あり! みんな元気に夏を越えたね】 2024/9/3 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング 雨天予報で塚田公民館で開催 室内でも出来ます ウォーキング マットをつかってコグニサイズ たのしい〜♫ 夏やすみ明け ここのメンバーも元気です
【暑さ対策の効果あり! みんな元気に夏を越えたね】 2024/9/3 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング 雨天予報で塚田公民館で開催 室内でも出来ます ウォーキング マットをつかってコグニサイズ たのしい〜♫ 夏やすみ明け ここのメンバーも元気です 酷暑の夏がほぼ終わりを迎え 秋風と虫の声のテラススタジオ 蝉も負けじとミ~ンミン♬ あっ!赤トンボ! 久しぶりに空の下で身体を思いっきり伸ばし気持ち良~い!解放感に浸りました。
酷暑の夏がほぼ終わりを迎え 秋風と虫の声のテラススタジオ 蝉も負けじとミ~ンミン♬ あっ!赤トンボ! 久しぶりに空の下で身体を思いっきり伸ばし気持ち良~い!解放感に浸りました。 本日は海老原ダンススクールにてボールウォーキングの講習会を開催致しました!😊 講師は先日のサマーパーティーでも大変お世話になっております我孫子の社交ダンススクールオーナーの長岡智津子先生!🎶 とても分かりやすい解説で普段のウォーキングより20%筋力を使う歩き方やポールを使ってのストレッチ法等を教えて下さいました!👨🦯 有難う御座いました!🤲
本日は海老原ダンススクールにてボールウォーキングの講習会を開催致しました!😊 講師は先日のサマーパーティーでも大変お世話になっております我孫子の社交ダンススクールオーナーの長岡智津子先生!🎶 とても分かりやすい解説で普段のウォーキングより20%筋力を使う歩き方やポールを使ってのストレッチ法等を教えて下さいました!👨🦯 有難う御座いました!🤲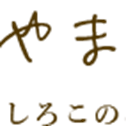 一本の水路でつながるマルシェを開成山公園で開催します – 郡山市公式ホームページ
一本の水路でつながるマルシェを開成山公園で開催します – 郡山市公式ホームページ 午前中はテレジア包括支援センターによるPW体験会の二回目。朝は秋を思わせる涼しい風のなか医療系大学の研修生3人も参加してくれました。両膝の人工関節のかた以外不具合のあるかたはいらっしゃらなくて皆さん初めてポールを持ったとは思えないしっかり大股歩きができました。でもポールを強く握りすぎ手の平が真っ赤になった方も。初めての時は力を脱くのは難しいですね。 無事会を終え、そのまま東京世田谷に参りました。久々の駒沢オリンピック公園。後輩が指導の明日のPW NWの活動は気温が高いので中止だそうです。私の渋谷教室はあります。
午前中はテレジア包括支援センターによるPW体験会の二回目。朝は秋を思わせる涼しい風のなか医療系大学の研修生3人も参加してくれました。両膝の人工関節のかた以外不具合のあるかたはいらっしゃらなくて皆さん初めてポールを持ったとは思えないしっかり大股歩きができました。でもポールを強く握りすぎ手の平が真っ赤になった方も。初めての時は力を脱くのは難しいですね。 無事会を終え、そのまま東京世田谷に参りました。久々の駒沢オリンピック公園。後輩が指導の明日のPW NWの活動は気温が高いので中止だそうです。私の渋谷教室はあります。 今日は東京目黒から渋谷へ。渋谷区包括支援センターのあるかんなみの杜は消防署のお隣にあります。この前の道は「ファイヤー通り」と言います。 今日はPWクラス2学期ラストデイ。恒例の計測から始まりました。3学期の募集はもう締め切ったとのことで嘆いていらっしゃる男性がた。4学期(1月~)に申し込んでみてください。午後は野暮用で三軒茶屋へ。
今日は東京目黒から渋谷へ。渋谷区包括支援センターのあるかんなみの杜は消防署のお隣にあります。この前の道は「ファイヤー通り」と言います。 今日はPWクラス2学期ラストデイ。恒例の計測から始まりました。3学期の募集はもう締め切ったとのことで嘆いていらっしゃる男性がた。4学期(1月~)に申し込んでみてください。午後は野暮用で三軒茶屋へ。 今朝は月に一度の津島市でのポールウォーキング教室でした😊 むかしお嬢様⁉️😅ばかりの皆様と毎月第一土曜日に、暑い日も、寒い日も続けてきております❗️ メンバーの中には津島市の日比市長とその奥様のみどりさんがいらっしゃいまして、場を盛り上げていただいております‼️ 元々は、みどりさんのお声がけがあってこの教室が誕生しました❣️😊 もう10年経ちますかね。。。 毎回、みどりさんが最後ご挨拶されるのですが、今日のお話の中で、「満足」という漢字を話題に取り上げられました。 「満足」、よく見ると、『足」あが『満たされる』と書くんですよね! そうなんですよ! 『足』が充実していることが『満足』なんですよね❗️😲 で、満足の逆の『不足』は『足』が不十分な状態を示すわけですよね! 漢字はいろいろなことを教えてくれますね‼️ 改めて、『足』の大切さがわかります❣️ みどりさん、素敵なお話、ありがとうございました😊 みなさん、ずっと座っていませんか⁉️ 1時間くらい座っていたら、まずはその場に立ち上がってみて下さい❗️ それだけでも良いです‼️ 足、腰をこまめに使うことが大切‼️ 二足歩行できることが人間の証でもありますからね❣️
今朝は月に一度の津島市でのポールウォーキング教室でした😊 むかしお嬢様⁉️😅ばかりの皆様と毎月第一土曜日に、暑い日も、寒い日も続けてきております❗️ メンバーの中には津島市の日比市長とその奥様のみどりさんがいらっしゃいまして、場を盛り上げていただいております‼️ 元々は、みどりさんのお声がけがあってこの教室が誕生しました❣️😊 もう10年経ちますかね。。。 毎回、みどりさんが最後ご挨拶されるのですが、今日のお話の中で、「満足」という漢字を話題に取り上げられました。 「満足」、よく見ると、『足」あが『満たされる』と書くんですよね! そうなんですよ! 『足』が充実していることが『満足』なんですよね❗️😲 で、満足の逆の『不足』は『足』が不十分な状態を示すわけですよね! 漢字はいろいろなことを教えてくれますね‼️ 改めて、『足』の大切さがわかります❣️ みどりさん、素敵なお話、ありがとうございました😊 みなさん、ずっと座っていませんか⁉️ 1時間くらい座っていたら、まずはその場に立ち上がってみて下さい❗️ それだけでも良いです‼️ 足、腰をこまめに使うことが大切‼️ 二足歩行できることが人間の証でもありますからね❣️ 【ポールを使うウォーキング でもでもポール無しよ】 2024/9/7(土曜) やっぱり暑かった‼️ 公民館を手配し涼しい場所で 「ウォーキングの基本」 持って来いのチャンスです ♫ ♫ ♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ウォーキングの基本 #早朝ウォーキング #ふなばしシルバーリハビリ体操初級指導士 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #パワーウォーキング
【ポールを使うウォーキング でもでもポール無しよ】 2024/9/7(土曜) やっぱり暑かった‼️ 公民館を手配し涼しい場所で 「ウォーキングの基本」 持って来いのチャンスです ♫ ♫ ♬ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ウォーキングの基本 #早朝ウォーキング #ふなばしシルバーリハビリ体操初級指導士 #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #パワーウォーキング 本日は自宅ミニスタジオで PWパーソナルレッスン。昨年末 股関節術後の女性。平日は施設でお仕事で土・日をご希望でしたので お電話いただいてすぐの方が良いかと 来客の約束を午後に伸ばし、午前中実施。ポールは新品トレッキングポールをご持参でしたのでこれを使用。半年自己流で歩いていらしたら痛みが出てきたそうで 「はじめの一歩」「右手~左足」 からじっくり始めました。たくさん歩きすぎて疲れるより筋トレで筋肉をつけるようにお話ししました。 午後からの訪問客とは 話の流れで縄跳びをする約束をしてしまいました。
本日は自宅ミニスタジオで PWパーソナルレッスン。昨年末 股関節術後の女性。平日は施設でお仕事で土・日をご希望でしたので お電話いただいてすぐの方が良いかと 来客の約束を午後に伸ばし、午前中実施。ポールは新品トレッキングポールをご持参でしたのでこれを使用。半年自己流で歩いていらしたら痛みが出てきたそうで 「はじめの一歩」「右手~左足」 からじっくり始めました。たくさん歩きすぎて疲れるより筋トレで筋肉をつけるようにお話ししました。 午後からの訪問客とは 話の流れで縄跳びをする約束をしてしまいました。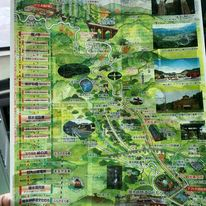 佐久ポールウォーキング協会より 9/8碓氷峠を歩こう〜❗️/アプトの道PW散策。埼玉県深谷市や志木市からの参加者を迎えバスチャーターイベント〜。90歳まじかの80代から小学5年(10歳男子)の参加者で 眼鏡橋から横川迄の約5kmの下り坂路をポールウォーキング〜‼️ 途中 碓氷湖/坂本ダムや峠の湯、丸山変電所跡や鉄道村を経由し横川/おぎのやがフィニッシュでした。 ランチは勿論〜峠の釜飯〜で皆さん舌鼓を〜ww 無事解散後のクールダウンは〜かき氷🍧〜でした‼️
佐久ポールウォーキング協会より 9/8碓氷峠を歩こう〜❗️/アプトの道PW散策。埼玉県深谷市や志木市からの参加者を迎えバスチャーターイベント〜。90歳まじかの80代から小学5年(10歳男子)の参加者で 眼鏡橋から横川迄の約5kmの下り坂路をポールウォーキング〜‼️ 途中 碓氷湖/坂本ダムや峠の湯、丸山変電所跡や鉄道村を経由し横川/おぎのやがフィニッシュでした。 ランチは勿論〜峠の釜飯〜で皆さん舌鼓を〜ww 無事解散後のクールダウンは〜かき氷🍧〜でした‼️ [大事なもの…] 昨日は地域で依頼受けてボッチャ体験会。そしてESC 定例キンボール活動。 今日は此処で…見学に来た場にユニホームを着て立てるとは。 そしてポールウォーキングスキルアップ、講師更新講習会。 動き過ぎと言われる歳になりましたが、どれももう少し続けたい、欲張りです。 キンボールスポーツを知って26年。 『いつまで走れるか?』考え始めた時知ったパワーウォーキングで18年。 その流れでポールウォーキングが15年。 地域健康づくりをパラスポーツ指導員で知ったボッチャで活動始めて6年。 今年に入り、レクでなく競技生をと学び始めて新たな出会いに喜びを持てています。 親の介護、見送り、子が独立した今、地域の健康づくりが主になりました。 上記の活動はそれに役立ってると思う事が自身の生きがい…言い過ぎかな(笑) で、日々のうるさい投稿になってます。 なので秀でたものがありません。でもどれも大事❣️もう暫く生存確認の意味でお付き合いください(*’▽’*)
[大事なもの…] 昨日は地域で依頼受けてボッチャ体験会。そしてESC 定例キンボール活動。 今日は此処で…見学に来た場にユニホームを着て立てるとは。 そしてポールウォーキングスキルアップ、講師更新講習会。 動き過ぎと言われる歳になりましたが、どれももう少し続けたい、欲張りです。 キンボールスポーツを知って26年。 『いつまで走れるか?』考え始めた時知ったパワーウォーキングで18年。 その流れでポールウォーキングが15年。 地域健康づくりをパラスポーツ指導員で知ったボッチャで活動始めて6年。 今年に入り、レクでなく競技生をと学び始めて新たな出会いに喜びを持てています。 親の介護、見送り、子が独立した今、地域の健康づくりが主になりました。 上記の活動はそれに役立ってると思う事が自身の生きがい…言い過ぎかな(笑) で、日々のうるさい投稿になってます。 なので秀でたものがありません。でもどれも大事❣️もう暫く生存確認の意味でお付き合いください(*’▽’*)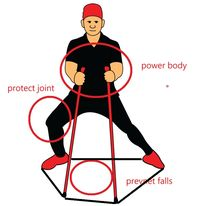 台湾の郭先生のわかりやすい説明です。 翻訳してみてください😊 ポールを持つことによる利点や安全面など 良いことがいっぱい書いてあります!
台湾の郭先生のわかりやすい説明です。 翻訳してみてください😊 ポールを持つことによる利点や安全面など 良いことがいっぱい書いてあります! 9月8日にスキルアップ研修東京会場を実施しました。 参加者数は23名で多くの方が参加されました。 次回は12月7日(土) 福岡です。九州地区初開催となります。 多くのコーチの参加をお待ちしております❗️
9月8日にスキルアップ研修東京会場を実施しました。 参加者数は23名で多くの方が参加されました。 次回は12月7日(土) 福岡です。九州地区初開催となります。 多くのコーチの参加をお待ちしております❗️ 📢 2024健走杖健康活力輕旅行 「第一站 烏來內洞森林遊樂區🌲」活動圓滿結束! 🎉 感謝大家的熱情參與, 這次活動不僅讓我們擁抱了大自然的美景, 更在健走中感受了健康活力的正能量!🚶♂️🌿 📍自然美景相伴:內洞森林遊樂區的清新空氣與壯麗景致,讓大家在享受健走的同時,與大自然進行了一場身心靈的對話。 📍專業教練帶領:由專業教練全程指導,學員們運用健走杖,走出了平穩與自信,充分發揮健走杖的支撐與推進力量,讓全身筋骨都動起來!💪 📍身心靈的放鬆:在這片靜謐的森林中,大家不僅鍛煉了身體,還讓緊繃的心靈得到了放鬆與釋放,呼吸間盡是清新與舒適🍃。 我們期待著與大家一起繼續這趟健康活力的健走之旅, 預告下一站,歡迎大家盡快報名!🚶♀️🌈 ✨第二站 時間:10/13(日) 上午 地點:嘉義公園+樹木園健走 站長:龔鈴智 🔥「2024健走杖.健康活力輕旅行」報名請填:https://reurl.cc/zDr9XQ 歡迎喜愛健走杖運動的好朋友們,跟著站長來一趟森療健走~ 敬請持續追蹤粉專跟line@公告📣 今年結合健康科技的joiisport app, 加入📱打卡記錄、蒐集獎章🎖️增加活動趣味性 揪起來蒐集獎章去! 打卡活動:https://reurl.cc/ReOGRn #2024健走杖健康活力輕旅行 #第一站烏來內洞森林遊樂區
📢 2024健走杖健康活力輕旅行 「第一站 烏來內洞森林遊樂區🌲」活動圓滿結束! 🎉 感謝大家的熱情參與, 這次活動不僅讓我們擁抱了大自然的美景, 更在健走中感受了健康活力的正能量!🚶♂️🌿 📍自然美景相伴:內洞森林遊樂區的清新空氣與壯麗景致,讓大家在享受健走的同時,與大自然進行了一場身心靈的對話。 📍專業教練帶領:由專業教練全程指導,學員們運用健走杖,走出了平穩與自信,充分發揮健走杖的支撐與推進力量,讓全身筋骨都動起來!💪 📍身心靈的放鬆:在這片靜謐的森林中,大家不僅鍛煉了身體,還讓緊繃的心靈得到了放鬆與釋放,呼吸間盡是清新與舒適🍃。 我們期待著與大家一起繼續這趟健康活力的健走之旅, 預告下一站,歡迎大家盡快報名!🚶♀️🌈 ✨第二站 時間:10/13(日) 上午 地點:嘉義公園+樹木園健走 站長:龔鈴智 🔥「2024健走杖.健康活力輕旅行」報名請填:https://reurl.cc/zDr9XQ 歡迎喜愛健走杖運動的好朋友們,跟著站長來一趟森療健走~ 敬請持續追蹤粉專跟line@公告📣 今年結合健康科技的joiisport app, 加入📱打卡記錄、蒐集獎章🎖️增加活動趣味性 揪起來蒐集獎章去! 打卡活動:https://reurl.cc/ReOGRn #2024健走杖健康活力輕旅行 #第一站烏來內洞森林遊樂區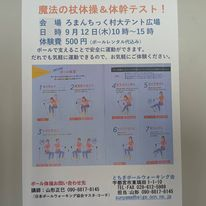 魔法の杖体操&体幹テスト
魔法の杖体操&体幹テスト 写真1件
写真1件 【出席しただけでも 100点満点】 月曜日・火曜日・土曜日 そして今日の木曜日コース 全コースとも2期がスタートしました 夏休み明けのこの暑さでも 参加者に勢いがあります ホッとしました #船橋ウォーキングソサイエティ 2期も頑張ります
【出席しただけでも 100点満点】 月曜日・火曜日・土曜日 そして今日の木曜日コース 全コースとも2期がスタートしました 夏休み明けのこの暑さでも 参加者に勢いがあります ホッとしました #船橋ウォーキングソサイエティ 2期も頑張ります 佐久ポールウォーキング協会より 佐久市教育委員会/佐久市スポーツ協会主催の「ポールを使ったウォーキング教室」第2日で、ブランドのお米処/五郎兵衛新田をPW〜❗️ 収穫前の一面黄金色の中を闊歩して来ました。9月中には収穫され無事皆さんの食卓に新米が届くモノと〜! 〜米騒動?もひと安心〜‼️ 散策後は来月散策予定の「女神湖」へ脚を伸ばし世話人さんとの下見MTGでした。
佐久ポールウォーキング協会より 佐久市教育委員会/佐久市スポーツ協会主催の「ポールを使ったウォーキング教室」第2日で、ブランドのお米処/五郎兵衛新田をPW〜❗️ 収穫前の一面黄金色の中を闊歩して来ました。9月中には収穫され無事皆さんの食卓に新米が届くモノと〜! 〜米騒動?もひと安心〜‼️ 散策後は来月散策予定の「女神湖」へ脚を伸ばし世話人さんとの下見MTGでした。 9月も気まポ(気ままにポール歩き)は夕暮れ歩き この日(14日、土曜)も最高気温35度になりましたが、夕方5時の井の頭公園は木陰も多く快適でした。池のまわりを一周して、神田川沿いに井の頭線三鷹台駅まで行き、左折して西荻窪駅に向かいました。だんだん日も暮れて、夜の住宅街を抜けて賑やかな駅前に。歩いた距離は5キロ弱。 8月は、室内企画でボウリングにしたので2ヶ月ぶりの外歩きでした。ボウリングも楽しかったけど、やっぱり歩くのがいいなあ。 今回、夕暮れ歩きなのでランチタイムにやってない店に行くことができました。西荻窪駅近くにあるiitoco です。コロナ前に何回か来て以来数年ぶりでした。おいしいものをたくさん作ってくれて大満足でした。 ※写真は一部田村和史さんからいただきました。
9月も気まポ(気ままにポール歩き)は夕暮れ歩き この日(14日、土曜)も最高気温35度になりましたが、夕方5時の井の頭公園は木陰も多く快適でした。池のまわりを一周して、神田川沿いに井の頭線三鷹台駅まで行き、左折して西荻窪駅に向かいました。だんだん日も暮れて、夜の住宅街を抜けて賑やかな駅前に。歩いた距離は5キロ弱。 8月は、室内企画でボウリングにしたので2ヶ月ぶりの外歩きでした。ボウリングも楽しかったけど、やっぱり歩くのがいいなあ。 今回、夕暮れ歩きなのでランチタイムにやってない店に行くことができました。西荻窪駅近くにあるiitoco です。コロナ前に何回か来て以来数年ぶりでした。おいしいものをたくさん作ってくれて大満足でした。 ※写真は一部田村和史さんからいただきました。 みなとみらい地区を歩こう わくわくポールウォーキング🎵 真っ青な空。 朝晩は秋の気配が。しかしまだまだ暑い〜💦 楽しい仲間たちと木陰を選びながら歩きました。 終了後は全員参加のランチタイム🎵中華街へ行き円卓で飲茶コース&🍺 みんなで旅の話で盛り上がりました。 次回の ☆みなとみらい 10月4日(金) 桜木町北口 コレットマーレ前 10:00集合 ☆鎌倉ミステリー 10月26日(土) 鎌倉 10:00集合 ご参加お待ちしております♪ #みなとみらい #ポールウォーキング #鎌倉ミステリー
みなとみらい地区を歩こう わくわくポールウォーキング🎵 真っ青な空。 朝晩は秋の気配が。しかしまだまだ暑い〜💦 楽しい仲間たちと木陰を選びながら歩きました。 終了後は全員参加のランチタイム🎵中華街へ行き円卓で飲茶コース&🍺 みんなで旅の話で盛り上がりました。 次回の ☆みなとみらい 10月4日(金) 桜木町北口 コレットマーレ前 10:00集合 ☆鎌倉ミステリー 10月26日(土) 鎌倉 10:00集合 ご参加お待ちしております♪ #みなとみらい #ポールウォーキング #鎌倉ミステリー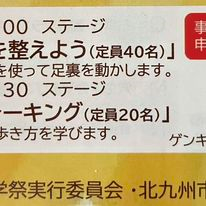 【穴生学舎大学祭&穴生ドームフェスタ】開催のお知らせ!! ・9月19日20日(土日) ・会場:穴生学舎、穴生ドーム 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5-1 この度ご縁をいただきましてゲンキクリエイターケイコは穴生ドームフェスタで2講座担当させていただくことになりました!! ◆10月19日(土) ★12:00~13:00 ステージ 「足裏筋膜を整えよう(定員40名)」 スーパーボールを使って足表を動かします。 ★13:30~14:30 ステージ 「ボールウォーキング(定員20名)」 ボールを使って歩き方を学びます。 ★一般の方もご参加いただけます! なお事前申込みが必要となります! ぜひ、この機会に皆様のご参加お待ちしておりますᥫᩣ ̖́- ※定員になり次第締切。 お申し込みお問い合わせ先 ↓↓↓ TEL 093-645-6688(穴生学) 平日9:00~17:00 #穴生ドームフェスタ #穴生学舎大学祭 #講師 #イベント #フェスタ #フットセラピー #セルフフット #ポールウォーキング #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #ソーシャルフィットネスコーチ #エアロビクスインストラクター #ボビナムボニャックインストラクター #加圧インストラクター #フィットネス指導者 #フットセラピスト #運動指導者 #JAFA #福岡県 #北九州 #北九州市
【穴生学舎大学祭&穴生ドームフェスタ】開催のお知らせ!! ・9月19日20日(土日) ・会場:穴生学舎、穴生ドーム 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目5-1 この度ご縁をいただきましてゲンキクリエイターケイコは穴生ドームフェスタで2講座担当させていただくことになりました!! ◆10月19日(土) ★12:00~13:00 ステージ 「足裏筋膜を整えよう(定員40名)」 スーパーボールを使って足表を動かします。 ★13:30~14:30 ステージ 「ボールウォーキング(定員20名)」 ボールを使って歩き方を学びます。 ★一般の方もご参加いただけます! なお事前申込みが必要となります! ぜひ、この機会に皆様のご参加お待ちしておりますᥫᩣ ̖́- ※定員になり次第締切。 お申し込みお問い合わせ先 ↓↓↓ TEL 093-645-6688(穴生学) 平日9:00~17:00 #穴生ドームフェスタ #穴生学舎大学祭 #講師 #イベント #フェスタ #フットセラピー #セルフフット #ポールウォーキング #ゲンキクリエイターケイコ #ポールウォーキングマスターコーチプロ #ソーシャルフィットネスコーチ #エアロビクスインストラクター #ボビナムボニャックインストラクター #加圧インストラクター #フィットネス指導者 #フットセラピスト #運動指導者 #JAFA #福岡県 #北九州 #北九州市 中秋の名月 十五夜 熱帯夜のお月見 明るくて大きいですね まん丸お盆のような月🌕 今日は熱中症を避け里山から室内に変更し、昇降台運動をしました。ステップ台から床にジャンプして降り骨強化。そしてリズムを刻んでベーシック、ニーアップなどSTEPエクササイズで太もも付け根が痛くなったかな。
中秋の名月 十五夜 熱帯夜のお月見 明るくて大きいですね まん丸お盆のような月🌕 今日は熱中症を避け里山から室内に変更し、昇降台運動をしました。ステップ台から床にジャンプして降り骨強化。そしてリズムを刻んでベーシック、ニーアップなどSTEPエクササイズで太もも付け根が痛くなったかな。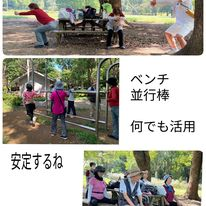 【止めない工夫】 暑さ指数が危険な時 コロナ禍の時 どうしたら定例会を 休まずにできるかな〜 小回りきくのが #船橋ウォーキングソサイエティ の良い所です 色んな事にチャレンジしました \(^o^)/ 暑さも少し収まりやっと 本拠地の行田公園に戻っ きました ♫ 公園の用具を使って 今日も楽しくトレーニング #美姿勢ウォーキング #ストレッチと筋トレ #県立行田公園
【止めない工夫】 暑さ指数が危険な時 コロナ禍の時 どうしたら定例会を 休まずにできるかな〜 小回りきくのが #船橋ウォーキングソサイエティ の良い所です 色んな事にチャレンジしました \(^o^)/ 暑さも少し収まりやっと 本拠地の行田公園に戻っ きました ♫ 公園の用具を使って 今日も楽しくトレーニング #美姿勢ウォーキング #ストレッチと筋トレ #県立行田公園 経験したことのない暑さにさらされながら畑に伸びて実をつけた蕎麦。今月末にご近所さんで刈り取ります。 最初にあげた写真を見て「え?これしか実がついてないの?不作か?」と言われ、慌てて「いえいえ、ほらこんなについてますよ」と付け足した一枚💦
経験したことのない暑さにさらされながら畑に伸びて実をつけた蕎麦。今月末にご近所さんで刈り取ります。 最初にあげた写真を見て「え?これしか実がついてないの?不作か?」と言われ、慌てて「いえいえ、ほらこんなについてますよ」と付け足した一枚💦 Taiwan Pole Walking Associationの皆様がご来社!明日のぴんころウォークにも参加していただきます。使用しているポールがどのように作られているのか、興味深く見ていました。 明日もよろしくお願いします(^.^)
Taiwan Pole Walking Associationの皆様がご来社!明日のぴんころウォークにも参加していただきます。使用しているポールがどのように作られているのか、興味深く見ていました。 明日もよろしくお願いします(^.^) 【太陽が隠れてホッ】 風もある〜 嬉しいね 海老川上流に向かいます いつまでも続く暑さに 疲弊した身体を包む川風 ゆったりメニューで 心と身体がリラックス 2024/9/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース
【太陽が隠れてホッ】 風もある〜 嬉しいね 海老川上流に向かいます いつまでも続く暑さに 疲弊した身体を包む川風 ゆったりメニューで 心と身体がリラックス 2024/9/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース 「ガイドと歩こう休日の鎌倉散歩」北条時行伝説① 家の事情で遠出を控え 地元でポールで山歩き。 この夏は熱中症警戒アラー ムが頻繁に発令され外歩きができませんでした。 今日は漸く風が涼しくなり、絶好のウォーキング日和となりました。
「ガイドと歩こう休日の鎌倉散歩」北条時行伝説① 家の事情で遠出を控え 地元でポールで山歩き。 この夏は熱中症警戒アラー ムが頻繁に発令され外歩きができませんでした。 今日は漸く風が涼しくなり、絶好のウォーキング日和となりました。 佐久ポールウォーキング協会より 〜佐久ぴんころwalk/12回〜 730名の参加者の皆さんを協会コーチ総出でのお迎えでした。 〜歩いて〜食べて〜健康に〜の元 遠くは兵庫県〜市外から約400名も来て頂き残暑の佐久路を満喫して頂いた様でご参加誠にありがとうございました。 今回は障害お持ちの学舎のグループや車椅子参加の家族、ペット同伴家族やら多方面の皆さんの参加も増え楽しいイベントとなった事にも感謝です。 ありがとうございました。 わざわざ台湾からお越しのPW協会の面々/総勢22名〜本当にお疲れ様でした。〜再見〜
佐久ポールウォーキング協会より 〜佐久ぴんころwalk/12回〜 730名の参加者の皆さんを協会コーチ総出でのお迎えでした。 〜歩いて〜食べて〜健康に〜の元 遠くは兵庫県〜市外から約400名も来て頂き残暑の佐久路を満喫して頂いた様でご参加誠にありがとうございました。 今回は障害お持ちの学舎のグループや車椅子参加の家族、ペット同伴家族やら多方面の皆さんの参加も増え楽しいイベントとなった事にも感謝です。 ありがとうございました。 わざわざ台湾からお越しのPW協会の面々/総勢22名〜本当にお疲れ様でした。〜再見〜 ぴんころウォーク700名を超える参加者です‼️ 台湾、静岡県、埼玉県他から沢山の皆さんに参加していただきました。来年もお待ちしております‼️
ぴんころウォーク700名を超える参加者です‼️ 台湾、静岡県、埼玉県他から沢山の皆さんに参加していただきました。来年もお待ちしております‼️ 第12回ぴんころウォークに参加しました。志木のノルディックウォーキング•ポールウォーキング全国大会でもお世話になっているシナノの柳澤社長が実行委員長‼️ 全国から、海外から700人を超える方々が集まり、食べ放題のプルーンや、酒蔵の甘酒や、仕込みの水の試飲、商工会女性部のおにぎりも配布され、とても賑わっていました。 志木市からの参加者の方とも交流。 自然に触れ、あたたかいおもてなしに感動❣️とっても参考になりました。 皆様,お疲れ様でした♪ #第12回ぴんころウォーク #佐久観光協会 #佐久市
第12回ぴんころウォークに参加しました。志木のノルディックウォーキング•ポールウォーキング全国大会でもお世話になっているシナノの柳澤社長が実行委員長‼️ 全国から、海外から700人を超える方々が集まり、食べ放題のプルーンや、酒蔵の甘酒や、仕込みの水の試飲、商工会女性部のおにぎりも配布され、とても賑わっていました。 志木市からの参加者の方とも交流。 自然に触れ、あたたかいおもてなしに感動❣️とっても参考になりました。 皆様,お疲れ様でした♪ #第12回ぴんころウォーク #佐久観光協会 #佐久市 ポールウォーキングベーシックコーチの指導員資格の認定を頂きました!🎖️ 先日の長岡智津子先生のポールウォーキング講習会を受講してポールを使う事でのウォーキングがより楽しく、よりバリエーションに富んだものになり、楽しく受講させて頂きました!🎶 西千葉でもポールウォーキングを広めたいと思っております!✨ 智津子先生、有難う御座いました!これからも宜しくお願い致します!🤗 #ポールウォーキング #指導員資格 #ポールウォーキング講習会 #大人の習い事 #大人の趣味 #千葉県千葉市中央区 #西千葉 #千葉 #千葉で1番居心地の良いスタジオを目指して #海老原ダンススクール #海老原晴美 #海老原正志
ポールウォーキングベーシックコーチの指導員資格の認定を頂きました!🎖️ 先日の長岡智津子先生のポールウォーキング講習会を受講してポールを使う事でのウォーキングがより楽しく、よりバリエーションに富んだものになり、楽しく受講させて頂きました!🎶 西千葉でもポールウォーキングを広めたいと思っております!✨ 智津子先生、有難う御座いました!これからも宜しくお願い致します!🤗 #ポールウォーキング #指導員資格 #ポールウォーキング講習会 #大人の習い事 #大人の趣味 #千葉県千葉市中央区 #西千葉 #千葉 #千葉で1番居心地の良いスタジオを目指して #海老原ダンススクール #海老原晴美 #海老原正志 熱中症警戒アラート発令で2ヶ月も休みになった逗子のPWサークルは今日の怪しい天気予報にめげず開催することになったのですが、ギリギリまで話し合った末 やはり中止となり 引き返しました。大雨の石川県の災害を思うと贅沢な悩みだと思いました。
熱中症警戒アラート発令で2ヶ月も休みになった逗子のPWサークルは今日の怪しい天気予報にめげず開催することになったのですが、ギリギリまで話し合った末 やはり中止となり 引き返しました。大雨の石川県の災害を思うと贅沢な悩みだと思いました。 長野 佐久ぴんころウォーク 台湾からコーチ陣達を含め20名程が来日。一緒にぴんころウォークに参加しました。 再会は最高に嬉しい❣️ プレゼントされたポロシャツを着て私も台湾PWチームに混じって歩きました😃 プルーンも甘酒もポップコーンも手づくりおにぎり🍙もとても美味しくて実に楽しいイベントでした。 ポールウォーキング協会の方々、イベントスタッフの皆さんどうもありがとうございました。 プルーン食べ放題に魅力を感じて一緒に参加してくれた友とは長野プルーン&♨️旅を満喫しています。 #佐久ぴんころウォーク #ポールウォーキング協会 #台湾ポールウォーキング協会 #あいとぴあ臼田 #長野プルーン #
長野 佐久ぴんころウォーク 台湾からコーチ陣達を含め20名程が来日。一緒にぴんころウォークに参加しました。 再会は最高に嬉しい❣️ プレゼントされたポロシャツを着て私も台湾PWチームに混じって歩きました😃 プルーンも甘酒もポップコーンも手づくりおにぎり🍙もとても美味しくて実に楽しいイベントでした。 ポールウォーキング協会の方々、イベントスタッフの皆さんどうもありがとうございました。 プルーン食べ放題に魅力を感じて一緒に参加してくれた友とは長野プルーン&♨️旅を満喫しています。 #佐久ぴんころウォーク #ポールウォーキング協会 #台湾ポールウォーキング協会 #あいとぴあ臼田 #長野プルーン # 21日開催の佐久ぴんころウォークの様子。実行委員長としてバタバタしていて写真を撮る余裕もなく、朝5時に起きてから怒涛の1日が過ぎました(^^)700名を超える方々に生プルーンの美味しさを味わってもらえました。食べ放題ですからね!県外から250名、台湾からも21名参加いただきました。ありがとうございます。5年ぶりの開催なので、来年に向けての課題も見つかりました。どうやら冒頭の実行委員長として挨拶はマイクの音量が小さく後ろまで声が届かなかったようです(TT) さて今日は仕事で東京。終電1本前に間に合ってよかった。寝過ごさないように頑張ります(^^)そして明日は早朝からゴルフ!体力持つかしら>.<
21日開催の佐久ぴんころウォークの様子。実行委員長としてバタバタしていて写真を撮る余裕もなく、朝5時に起きてから怒涛の1日が過ぎました(^^)700名を超える方々に生プルーンの美味しさを味わってもらえました。食べ放題ですからね!県外から250名、台湾からも21名参加いただきました。ありがとうございます。5年ぶりの開催なので、来年に向けての課題も見つかりました。どうやら冒頭の実行委員長として挨拶はマイクの音量が小さく後ろまで声が届かなかったようです(TT) さて今日は仕事で東京。終電1本前に間に合ってよかった。寝過ごさないように頑張ります(^^)そして明日は早朝からゴルフ!体力持つかしら>.< 2024.9.23 スマイル.ルネPW 軽いエクササイズ&ウォーキング&お喋り を90分 7.8月は酷暑の為お休みにしていたので お喋りタイムが長くなり大満足 氣候も良くて氣持ち良くエクササイズ出来ました☺️ #ポールウォーキング #花壇 #ハイシニアチーム
2024.9.23 スマイル.ルネPW 軽いエクササイズ&ウォーキング&お喋り を90分 7.8月は酷暑の為お休みにしていたので お喋りタイムが長くなり大満足 氣候も良くて氣持ち良くエクササイズ出来ました☺️ #ポールウォーキング #花壇 #ハイシニアチーム 今日は、一関市室根市民センター主催のウォーキング教室へ!久々の秋晴れ! 地元の名所を訪れて歴史を学んだり、栗拾いで盛り上がったり、田園風景に癒されたり‥。 さぁ、涼しくなってきたので、ウォーキングシーズン到来です😊
今日は、一関市室根市民センター主催のウォーキング教室へ!久々の秋晴れ! 地元の名所を訪れて歴史を学んだり、栗拾いで盛り上がったり、田園風景に癒されたり‥。 さぁ、涼しくなってきたので、ウォーキングシーズン到来です😊 ハロウィン前の軽井沢散策〜ww 1週間前の暑さは何処へ〜❓ 20℃ 心地良い(日陰は寒さが〜^_^)避暑地/軽井沢をポールwalker仲間と闊歩❗️ 大賀ホール〜万平ホテル〜諏訪神社・ユニオンチャーチ⛪️〜テニスコート〜室生犀星記念館〜ショー記念礼拝堂〜聖パウロ教会⛪️〜旧道別荘界〜お水端(雲場池)〜野菜のおいしいカレー🍛で締め‼️/6km越えのPW散策でした。
ハロウィン前の軽井沢散策〜ww 1週間前の暑さは何処へ〜❓ 20℃ 心地良い(日陰は寒さが〜^_^)避暑地/軽井沢をポールwalker仲間と闊歩❗️ 大賀ホール〜万平ホテル〜諏訪神社・ユニオンチャーチ⛪️〜テニスコート〜室生犀星記念館〜ショー記念礼拝堂〜聖パウロ教会⛪️〜旧道別荘界〜お水端(雲場池)〜野菜のおいしいカレー🍛で締め‼️/6km越えのPW散策でした。 【秋の1歩 自分の歩きはこうなのね】 2024/9/26 夏の疲れが残っても 身体を動かしたら 飛んでいきました〜 帰り道は 身体が軽くなる ウォーキングっていいね〜 そうよ 元気が出るのよ ウォーキングはやる気も出るのよ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング木曜日コース
【秋の1歩 自分の歩きはこうなのね】 2024/9/26 夏の疲れが残っても 身体を動かしたら 飛んでいきました〜 帰り道は 身体が軽くなる ウォーキングっていいね〜 そうよ 元気が出るのよ ウォーキングはやる気も出るのよ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング木曜日コース 今日は、食生活改善推進員養成講座を担当。 前半は、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」について解説しました。 筋トレの重要性、座りすぎのリスク、高齢者の多要素な運動の効果、などなど。 後半は、家でもできる筋トレやウォーキングフォームの実技。日々の健康づくりに役立ててもらえると嬉しいです😊
今日は、食生活改善推進員養成講座を担当。 前半は、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」について解説しました。 筋トレの重要性、座りすぎのリスク、高齢者の多要素な運動の効果、などなど。 後半は、家でもできる筋トレやウォーキングフォームの実技。日々の健康づくりに役立ててもらえると嬉しいです😊 本日は、大口町保健センターで、『粋々健幸ライフ講座』の二回目を開催。 今回は、アロマセラピストの塩屋紹子先生をお招きして、アロマの効果やその使い方、そして実技としてハンドマッサージをご指導いただきました。 参加者は30歳代が70歳代で、女性が多かったですが、男性も2名のご参加をいただき、合計で30名ほどの皆さんにご参加いただきました。 塩屋先生はイギリスで勉強され資格を取られました。 そのイギリスでは、医療として成り立つアロマですが、日本では大変残念ながら医療分野ではなかなか認められませんね。。。 西洋においては、今のような薬がない時代はこのアロマが薬として利用されていたとのこと。 例えば、ラベンダーは傷や火傷にも効果があるとのこと。 あるいは子供の風邪などは、足湯にアロマを入れて治してしまうような効能もあるとのこと。 今の日本は、何でもかんでもすぐに病院に行ってしまいますが、本来は自然治癒力によって病気、怪我を治していくもので、その治癒力をアップさせるのがこのアロマになるのだと思います。 使って酔いはわあい、ダメな場合もありますので、香りを楽しむレベルなら良いですが、薬的な使い方については専門家のアドバイスが必要になることは押さえておかないといけませんね。 実技ではペアーになってハンドマッサージを学びました。 みなさん、どんどん打ち解けていって、笑顔中で講習が進みました。 やはり、スキンシップは大切ですね❣️ 塩屋先生はベビーマッサージも幼稚園などで指導されているそうですが、こうきた親子のふれあいも良いですね‼️ 興味がある方は、写真に塩屋先生の案内チラシを貼り付けておきましたので、ご連絡いただければと思います。 また、本も出されていらっしゃいますので、本屋さんなどでご覧になってみてください。 #大口町保健センター #塩屋紹子 #アロマハンドケア #アロマテラピー
本日は、大口町保健センターで、『粋々健幸ライフ講座』の二回目を開催。 今回は、アロマセラピストの塩屋紹子先生をお招きして、アロマの効果やその使い方、そして実技としてハンドマッサージをご指導いただきました。 参加者は30歳代が70歳代で、女性が多かったですが、男性も2名のご参加をいただき、合計で30名ほどの皆さんにご参加いただきました。 塩屋先生はイギリスで勉強され資格を取られました。 そのイギリスでは、医療として成り立つアロマですが、日本では大変残念ながら医療分野ではなかなか認められませんね。。。 西洋においては、今のような薬がない時代はこのアロマが薬として利用されていたとのこと。 例えば、ラベンダーは傷や火傷にも効果があるとのこと。 あるいは子供の風邪などは、足湯にアロマを入れて治してしまうような効能もあるとのこと。 今の日本は、何でもかんでもすぐに病院に行ってしまいますが、本来は自然治癒力によって病気、怪我を治していくもので、その治癒力をアップさせるのがこのアロマになるのだと思います。 使って酔いはわあい、ダメな場合もありますので、香りを楽しむレベルなら良いですが、薬的な使い方については専門家のアドバイスが必要になることは押さえておかないといけませんね。 実技ではペアーになってハンドマッサージを学びました。 みなさん、どんどん打ち解けていって、笑顔中で講習が進みました。 やはり、スキンシップは大切ですね❣️ 塩屋先生はベビーマッサージも幼稚園などで指導されているそうですが、こうきた親子のふれあいも良いですね‼️ 興味がある方は、写真に塩屋先生の案内チラシを貼り付けておきましたので、ご連絡いただければと思います。 また、本も出されていらっしゃいますので、本屋さんなどでご覧になってみてください。 #大口町保健センター #塩屋紹子 #アロマハンドケア #アロマテラピー 佐久ポールウォーキング協会より 佐久市教育委員会/佐久市スポーツ協会さんとのコラボ企画〜 「スポーツ教室/ポールウォーキングde〜」3日目❗️ ぴんころ地蔵尊〜佐久の古刹/貞祥寺往復約6km(寄り道付)をポールwalk。 お米の収穫も無事済んだ田圃見ながら、ぴんころ地蔵尊も貞祥寺も初めてとの参加者も居て楽しめた散策でした。
佐久ポールウォーキング協会より 佐久市教育委員会/佐久市スポーツ協会さんとのコラボ企画〜 「スポーツ教室/ポールウォーキングde〜」3日目❗️ ぴんころ地蔵尊〜佐久の古刹/貞祥寺往復約6km(寄り道付)をポールwalk。 お米の収穫も無事済んだ田圃見ながら、ぴんころ地蔵尊も貞祥寺も初めてとの参加者も居て楽しめた散策でした。 2024.9.29ひるがの高原パノラマウォーク 今年は新コースで開催しました。 初秋のひるがの高原を歩くまくりました。
2024.9.29ひるがの高原パノラマウォーク 今年は新コースで開催しました。 初秋のひるがの高原を歩くまくりました。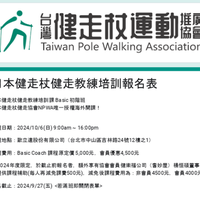 日本健走杖健走教練培訓報名表
日本健走杖健走教練培訓報名表 写真1件
写真1件 📢鎌倉ミステリーvol.9📢 猛暑のこの夏はお休みしておりましたが、待ちに待った涼しい秋風が吹きはじめましたので 再開いたします。 〔日時〕 ☀🌤️🌥️10月26日(土曜日) 予備日11月2日(土曜日) 〔集合場所〕 鎌倉駅東口みどりの窓口前にトイレを済ませて10時集合。 〔保険〕 各自でご手配ください。 〔解散・食事〕 鶴岡八幡宮三の鳥居⛩️付近 凡そ12時迄。ランチは各自自由。八幡宮参詣は解散後ご自由に。 〔参加費・持物〕 1000円 他に拝観料300円ご負担願います。 ポール有無どちらでも。 飲み物、飴玉🍬など。 体温調節の出来る服装。リュック。歩きやすい靴👟 帽子🧢 雨具🌂 〔主催・企画」 酒井尚美(P&P)& 田村芙美子(鎌ポ) 〔雨天時〕 前夜19時 雨予報の場合は中止・11/2に順延といたします。 〔申し込み・問合せ〕 酒井or田村まで メッセージ、LINE、メールで。 ・・・・・・・ 山道を歩きますが、距離は短いのでゆるゆる歩きます。
📢鎌倉ミステリーvol.9📢 猛暑のこの夏はお休みしておりましたが、待ちに待った涼しい秋風が吹きはじめましたので 再開いたします。 〔日時〕 ☀🌤️🌥️10月26日(土曜日) 予備日11月2日(土曜日) 〔集合場所〕 鎌倉駅東口みどりの窓口前にトイレを済ませて10時集合。 〔保険〕 各自でご手配ください。 〔解散・食事〕 鶴岡八幡宮三の鳥居⛩️付近 凡そ12時迄。ランチは各自自由。八幡宮参詣は解散後ご自由に。 〔参加費・持物〕 1000円 他に拝観料300円ご負担願います。 ポール有無どちらでも。 飲み物、飴玉🍬など。 体温調節の出来る服装。リュック。歩きやすい靴👟 帽子🧢 雨具🌂 〔主催・企画」 酒井尚美(P&P)& 田村芙美子(鎌ポ) 〔雨天時〕 前夜19時 雨予報の場合は中止・11/2に順延といたします。 〔申し込み・問合せ〕 酒井or田村まで メッセージ、LINE、メールで。 ・・・・・・・ 山道を歩きますが、距離は短いのでゆるゆる歩きます。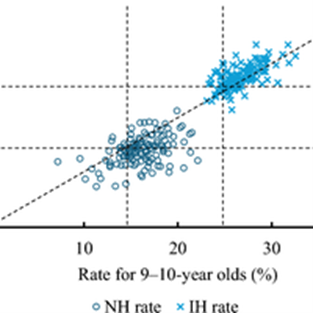 Predictors of flatfoot in 11–12-year olds: a longitudinal cohort study – BioMedical Engineering OnLine
Predictors of flatfoot in 11–12-year olds: a longitudinal cohort study – BioMedical Engineering OnLine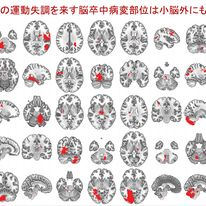 脳卒中後に認められる運動失調は,一般に小脳が損傷されたために生じます.しかし小脳が直接損傷を受けていない場合でも,四肢の運動失調が生じることがあります.フィンランドからそのメカニズムを検討した興味深い研究が,最新号のNeurology誌に報告されました.
脳卒中後に認められる運動失調は,一般に小脳が損傷されたために生じます.しかし小脳が直接損傷を受けていない場合でも,四肢の運動失調が生じることがあります.フィンランドからそのメカニズムを検討した興味深い研究が,最新号のNeurology誌に報告されました.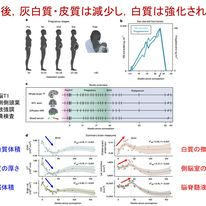 妊娠中は性ホルモンに大きな変化が生じます.しかしその過程で,脳にどのような変化が生じるかはほとんど分かっていませんでした.米国からの研究で,38歳の健康な初産婦1名に対し,妊娠前から出産後2年までにわたり,計26回の精密なMRI検査を行い,脳内で生じる変化を明らかにした研究がNature Neuroscience誌に報告されました.
妊娠中は性ホルモンに大きな変化が生じます.しかしその過程で,脳にどのような変化が生じるかはほとんど分かっていませんでした.米国からの研究で,38歳の健康な初産婦1名に対し,妊娠前から出産後2年までにわたり,計26回の精密なMRI検査を行い,脳内で生じる変化を明らかにした研究がNature Neuroscience誌に報告されました.